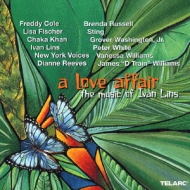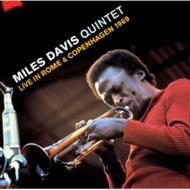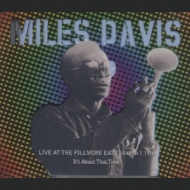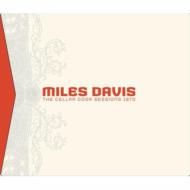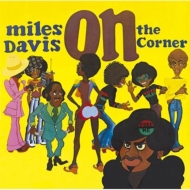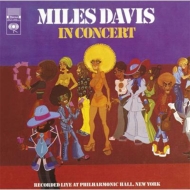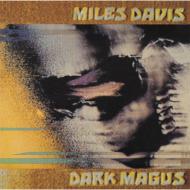�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v ���R�N������ɐu�� �q3�r
2010�N7��29�� (��)

- ---�@�u1972-1975�v�ɂ����ă}�C���X�́A�u�ō����H�v �u�ň����H�v�Ƃ������ɂ̓������ɔ����i�����n�i����Ӑ}�I�ɖژ_��ł����̂ł��傤���H
�@�ǂ���������ł��傤�ˁE�E�E�wBitches Brew�x�܂ł́A�}�C���X�̓��̒��Ƃ����̂͂�����x�t�H���[�ł��邵�A�����镔���������ł���ˁB����́A�������������悤�Ƀ}�C���X���g��������Ɠ��̒��Ŋy�Ȃ�g�ݗ��ĂĂ��邩��ł����āA���̕�������������������������������A�������t�Z�ł͂���܂����A�����ł���B
�@�����A�wOn The Corner�x�ȍ~�A�wAgharta�x�A�wPangaea�x�ɂȂ��Ă���ƁA���ꂪ�F�ڌ����Ă��Ȃ��B �Ђ���Ƃ�����A�����g�K�`���K�`���h��肽�����������Ȃ̂��ȁH �ƍl���Ă��݂���i�j�B�P���� �h�T�E���h�̉��y�h�Ƃ������̂����邶��Ȃ��ł����H ����̓}�C���X�������܂ł���Ă��Ȃ���������Ȃ�ł���B�������A����܂łɂ��i���j�g�j�[�E�E�B���A���X�̃h�������o�V���[���Ɠ���Ƃ��i�j�A�u�ԏu�Ԃł����������Ƃ͂������킯�ł����A����������ƑS�̂�ʂ��Ă� �h���Ղ芴�o�g�������Ƃ������E�E�E���ʓ_��T��Ƃ���A�i���j�T���E���[�̐��E�ł���ˁi�j�B
�@���邢�́A�i���j�W�F�C���X�E�u���E������ł���ˁB�h�T������̏j�ՓI�ȋ�ԁB�������A���̎��Ԃ�������Β����قǖ���������A�I���͎̂₵���Ȃ��A�Ƃ������o�i�j�B����ɁA���̍Ղ�̒����Ɏ�������������ƁA���̂Ƃ��������̂̒ɂ݂��Y����邩���A�Ƃ������҂�����܂���ˁB- ---�@�wOn The Corner�x�Ȃǂł� �g�K�`���K�`�����h �́A�T���E���[�AJB���y������s���Ă��܂���ˁB
�@���ǁA���E��y�_����������āA�����̉���ς��Ă��܂����Ƃ����̂́A�g�Q���ӎ��h�ɂ����̂������Ǝv����ł���B�g�����y�b�g���ƃo���h�̉��ɓ���߂Ȃ��g�悻�ҁh���ƁB���ہA�g�����y�b�g�̃X�g���[�g�ȉ��́A���̓����̉��ɍ���Ȃ���ł���B���邢�͂܂������t�ɁA�W�~�E�w���h���b�N�X�̃��E�E�M�^�[�ɐG������āA�Ƃɂ������E�E�y�_�����g�����������ƁB�����ă��E���������g�����y�b�g�̉��ɍł����������T�E���h��T���������ʁA�wOn The Corner�x�̂悤�ɂȂ����Ƃ��B������A�i���j���j�[�E���X�g���E�X�~�X���wOn The Corner�x���\��ɃN�r�ɂ����̂́A�L�[�{�[�h�������ƃ��E�̌��ʂ������ł��Ȃ��A�Ƃ�����C�t�������炩������Ȃ���ł��ˁB�܂�A�X�e�[�W�̏�ł݂�ȂŐ���オ�肽���A�������w�����ɂȂ������ɐZ��Ȃ���i�j�A�Ƃ������ƂȂ�ł��傤�ˁB
�@����܂ł́A�����̃\�����I���ƁA���̃����o�[�̃\�����I���܂ŕ��䗠��Ɉ�������ł����킯�ł���B�����ǁA�wAgharta�x�̍��ɂȂ�Ƃ����ƃX�e�[�W�ɂ���B�����̃p�[�g�ȊO�ł��A�w�����Ƃ��Ă����ł��ˁB�}�C���X�̒��ł���͍��܂łɂȂ��X�^�C���ł�������A�������Ă��傤���Ȃ�������Ȃ��ł��傤���ˁi�j�B- ---�@�o���h������o�[�Ƃ̉��y�̋��L���ŗD�悷���ł��邽�߁A���O����u�[�C���O�����ł��Ă��ӂɉ�Ȃ��i�j�B
�@����Ӗ��A�g�����h�ł���A�g�����h�ł���ˁi�j�B�������������ŃT���E���[�Ɠ����Ȃ�ł���B�����āA���Ȃ����l�������Ƃ͎v���܂����A���̋�ԂƂ����̂́A�܂��Ɂg�`���[�`�i����j�h�ł���ˁB����̓W�F�C���X�E�u���E��������Ă��邱�Ƃł�����B���ǃ}�C���X���x���Ă����̂́A����ȍ��l�ӎ��ł�����A�s�������Ƃ���̓W�F�C���X�E�u���E���ƌ��\�߂��Ƃ���Ȃ�Ȃ����ȂƎv����ł���ˁB
- ---�@���̈���ł́A���l�̎�ґw���X�i�[�ւ̃Z�[���X���C�ɂ����Ă�����ł���ˁH
�@�����������l�̃G���^�[�e�C�i�[�������������Y�݂ł������ł����A���ǎ������x���Ă���͔̂��l�ł���Ƃ����W�����}�ł���ˁB���ꂪ���ŁA�`�����e�B�����ɑ����Ă��܂��悤�Ȑl�����܂����ǁi�j�A����͎����ɑ���߂̈ӎ��݂����Ȃ悤�Ȃ��̂ł�����B
- ---�@����ł͍Ō�̎���ɂȂ�̂ł����A2010�N���݁A�}�C���X��84�Ό����o���o���Ŋ������Ă���Ɖ��肵�āA�ǂ̂悤�ȃT�E���h�����߂Ē��Ă���Ǝv���܂����H
�@���`��E�E�E����ł���ˁi�j�B
- ---�@�N���u�E�~���[�W�b�N�̂悤�ȋߑ�T�E���h������ɓ���Ă���\���A���邢�͋t�ɁA�g�o�b�N�E�g�D�E���[�c�h�ȃA�R�[�X�e�B�b�N�E�T�E���h�ɗ����Ԃ��Ă���\���A�F�X�Ƒz���Ɍ��E���Ȃ��ƌ����܂����E�E�E
�@���ꂱ���A�l�I�ɂ̓V���v���ȕ����ɍs���Ă����Ƃ͎v����ł����A�g�����y�b�g�𐁂��Ă��邩�����Ă��Ȃ����ŁA�l������������ƕς���Ă���Ǝv����ł��ˁB�}�C���X�́A�g�����y�b�g�𐁂��Ȃ��Ă������̉��y�������ŁA�Ђ���Ƃ�����M���E�G���@���X�݂����Ȃ��ƂɂȂ��Ă����̂��ȂƁi�j�B
- ---�@�i�j�A�����W���[�I�ȗ���ŗl�X�ȕ�����s�������Ă���悤�ȁB
�@�܂��A91�N�Ɏ���ł��Ȃ���A���R�Ō�ɂ��������肳��悤�Ƃ��Ă����v���W�F�N�g�ɂ��ẮA���̂܂܈��������s���Ă����Ǝv����ł���ˁB����́A�i���j�C���@���E�����X�Ƃ̋������܂߂��u���W��������������A���邢�́A�i���j�}�[�J�X�E�~���[�Ƃ̍ċ�����������ł�����A���̉�������ɂ�����̂��낤�ȂƂ����z���͂ł��܂���ˁB
�@�Ƃ����̂��A65�Ŏ���ŁA���������Ă����痈�N��85�B����20�N�ԂƂ����̂́A�}�C���X�̂���܂ł̉��y�ϑJ�����ԕʂɌ���ƁA���4���炢�̃e�[�}�ɒ��肷��\�����傫����ł���B�܂�5�N�����ŁB��������ƁA���������u���W�����̂��܂߂��v���W�F�N�g���ł���ˁB- ---�@�����ɂ��Ă��A���ɉ����n�߂邩�H ���ɋ��������̂��H �Ƃ����̂��ł��ǂ݂ɂ��������̂ł��傤�ˁB
�@����ɍ��́A���j�I�Ȑi���_�����͂�ʗp���Ȃ�����ɂȂ��Ă���킯�ł�����A���̌�ǂ��Ȃ����̂��H �Ƃ����̂͂Ȃ��Ȃ��������ɂ����B�l��͂ǂ����Ă��A�I��������̂ɑ��Ă̘��Ղ������������ł��܂��ǁA�Ⴆ�A�P���ɁwBitches Brew�x������������A�wAgharta�x������Ƃ����킯�ł��Ȃ��悤�ȋC�������ł���ˁB
�@�W���Y�̗��j���̂��̂������悤�Ȃ��Ƃ��������ł����A�ЂƂ̗��ꂪ�����āA�Ⴆ�r�E�o�b�v�������ăn�[�h�E�o�b�v������Ƃ�������B����́A67�N�܂ł͐������Ǝv����ł���B���̔N�̏ے��I�Ȃ��Ƃ������A�}�C���X�́wNefertiti�x�A�����ăW�����E�R���g���[���̎��B����ɂ���Ď}�����ꂵ���Ǝv����ł���B�܂�A����܂ł̂悤�Ɂu�r�E�o�b�v�Ɏ���đ����ăn�[�h�E�o�b�v���o�Ă����v�Ƃ������j�̐ςݏd�˂ł͂Ȃ��āA�n�[�h�E�o�b�v�̓n�[�h�E�o�b�v�Ƃ��Ă��钆�ōו������Ă����B�����10�N���炢�o�ƁA�܂���������}�����ꂵ�Ă����B
 1967�N�̃}�C���X
1967�N�̃}�C���X
�@�}�C���X�́wNefertiti�x�Ƃ����̂́A67�N�����ŁA�A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y�̍ō��Ǝv����ł���B�����܂ł́A�n�[�h�E�o�b�v�̗���ő����邱�Ƃ��ł���B�Ƃ��낪�A���������A�wMiles In The Sky�x�ɂȂ�ƁA�ꕔ�̊y�Ȃ������āA���̐���ɂ͓���Ȃ��Ȃ��Ă����ł���B�����āA�ǂ�ǂ��E���Ă����B���̈�E���Ă��������̂��W���Y�̗��j�̒��ɖ������������ŁA�n�[�h�E�o�b�v�Ɏ���đ�����̂Ƃ��Ă���̂��A�܂茻�݂̗��j�ςȂ�ł��B������A�����������ł���B�n�[�h�E�o�b�v�ƁA�G���N�g���b�N�E�t���[�W�����A�u���R���Ƃł́A������O�ł����A�S�R�Ⴂ�܂�����ˁB
�@���ǁA���܂ł́A�������������ȏ����������Ă��������߂ɁA�}�C�P���E�w���_�[�\����G���g�D�[���Ȃ��ǂ����痈���̂��Ƃ������ƂɐG��邱�Ƃ��ł��Ȃ�������ł���B�o�����W���Y�Ȃ킯�ł͂Ȃ��ł�����B������ˑR�W���Y�j�ɓ����Ă���B�ł����ہA�ނ炪�����̂̓W���Y�j�ł͂Ȃ��A�Ƃ����Ƃ���Ȃ�ł���ˁB����̖{�ł͂��������������ł��邾���r�����Ă��������Ǝv���āB������A�W���Y�E�t�@�����ǂ�`���v���J���v���ȕ�����������������Ȃ���ł���i�j�B���������A�L�[�X�E�W�����b�g���i���j�W���b�N�E�f�W���l�b�g�̖��O���o�Ă��邮�炢�ł�����B- ---�@�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v�������ɑ����̐l���Ǝ��R�ȊW�������Ă������Ƃ������Ԃ��ł���ˁB
�@���������Ӗ��ł́A���̖{���̂��u�ō����H�v�u�ň����H�v�Ƒ�����W���Y�E�t�@�������Ȃ肢��Ǝv���܂���i�j�B
 |
|
�}�C���X�E�f�C���B�X�E�e���e�b�g 1973�N4�����̃X�e�[�W
|
 |
|
�}�C���X�E�f�C���B�X�E�Z�v�e�b�g 1973�N6�������X�e�[�W
|
|
�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v��20��
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
�y�~���u�K�z ��}�C���X ��Ղ̃��X�g�E�C���[�Y� ���R�N������ɐu��
-
��}�C���X�E�f�C���B�X ��Ղ̃��X�g�E�C���[�Y� ���R�N������ɐu��
��Ղ̃J���o�b�N���ʂ������鉤����������Ȃ�r��B�u�d���}�C���X�v�u�K�Ɉ��������A���R�N����������}�����Ă�����u�}�C���X�̉ؗ�Ȃ郉�X�g�E�C���[�Y�v�ɂ��Ă̂��b�E�E�E
���̑��̊֘A�L��
-
�y���W�z �}�C���X�E�f�C���B�X �wTUTU�x �i2011�N5���j
�}�C���X�E�f�C���B�X��1986�N���[�i�[�ڐБ�1�e��i�wTUTU�x���A�{�҃��}�X�^�[�ɓ��N7���̃j�[�X����������lj�����2���g���ؔՂɂēo��B��������̎���}�[�J�X�́uTUTU�lj����C���v�������E�E�E�E�E�E
-
�y���W�z �d���鉤�w�� �u�r�b�`�F�Y�v�ɂ��� �i2010�N7���j
�wBitches Brew�x 40���N�L�O�������K�V�[�Ղ������B�����\���C������CD�A�����\���C��DVD����lj��������S���Y����̂䂾���������B�d���鉤�w�ƁwBitches Brew�x�ɂ��ĐF�X�ƁE�E�E
-
�e�n���E �����O�E�C���^�r���[ �i2008�N6���j
2008�N6���ɍs��ꂽ�e�n���E���C���^�r���[�̑S7�S�ŁB�_�u�E�Z�N�X�e�b�g�A�}�C���X�A�t�@�b�V�����A���̌q�����������x�l�@���Ă݂�ƁE�E�E�E�E�E
���~�E�� �I�����C�� �u�V���Ƃȑ����v�ŘA�ڒ��� �u�W���Y��Փ���v
|

-
���R�N�� �i�Ȃ���� �₷���j
�@1952�N���{�o�g�B���y�]�_�ƁB�W���Y�G���u�X�C���O�W���[�i���v�ҕҏW���߂���A���M�����ɓ���B����Ɂw�}�C���X�E�f�B���B�X �̎���x�A�w�}�C���X vs �R���g���[���x�A�w�}�C���X�̉āA1969�x�A�w�}�C���X���I�x�������B�Ɂw�}�C���X�E�f�B���B�X�����`�x������B�܂��A���b�N�ɂ����w���[���A�w�r�[�g���Y�ƃ{�u�E�f�B�����x�A�w���ƗE�C�̃��b�N50�x�A�w�f�B������!!�x��������B
- �֘A�T�C�g�i�O���T�C�g�j
- �֘A���W�iHMV�T�C�g���j
�{�����ɓo�ꂷ���v�l���ɂ��� |
 |
Tony Williams �i�g�j�[�E�E�B���A���X�j 1962�N�ɃW���b�L�[�E�}�N���[���̃O���[�v�ɎQ�����邽�߁A�̋��V�J�S����j���[���[�N�Ɉڂ�B��63�N�ɂ͎㊥17�Ń}�C���X�̏����u�����̃N�C���e�b�g�v�̃����o�[�ɔ��F����A69�N�܂ōݐЂ���B��Ƀe���|�┏�q��ς��A���C�h�E�V���o���̃��Y�����L�[�v���X�l�A�E�h�����ō����̃|�����Y����@���o���e�N�j�b�N�B�܂��A������4�r�[�g�����ӂƂ��Ă���A�ނ̉����ȍ~�̃}�C���X�E�O���[�v�ł͓����Ȃɂ����Ă��N��ǂ����ƂɃe���|�������Ȃ��Ă����̂��悭�킩��B�Ȍ�A���b�N�ւ̌X�|����W�����E�}�N���t�����A�����[�E�����O�A�A�����E�z�[���Y���[�X�A�W���b�N�E�u���[�X����}�����g�̃O���[�v�A���C�t�^�C�������������ق��A�n�[�r�[�E�n���R�b�N�Ƃ̃v���W�F�N�g�uV.S.O.P.�N�C���e�b�g�v�ɎQ�����Ă���B |
 | Sun Ra �i�T���E���[�j �u�y���������ė����v�ƂȂɂ���ʊ�Ō�������s�A�j�X�g�^�R���|�[�U�[�^�o���h�E���[�_�[�A�T���E���[�́A40�N��̃V�J�S�ŃL�����A���X�^�[�g�����A�t���b�`���[�E�w���_�[�\���y�c�ł̊������o�Ď��Ȃ̃r�b�O�E�o���h�A�T���E���[�E�A�[�P�X�g���������B���X�̐_���`���R���Z�v�g�ɔ����I�ɓn��1993�N5���Ɏ�������܂Ŋ����𑱂����^�j��ȏW�c�B60�N�ォ��́A���Ȃ肽�Ă�悤�ȃI���K���ƃV���Z�T�C�U�[�A���A�t���J�̃��Y���A�����y�̕��@�_�A�t���[�L�[�ȃ\���E�v���C�A�r�b�O�E�o���h�̃_�C�i�~�b�N���A�X�E�B���O���郁���f�B�A�Ƃ��ɂ́A�o���h�̃����o�[�B���}�C�N�����A�A�t���J��A��F���ɂ��Ẵv���[�`�ƁA�l�X�ȉ��y�i���邢�͉����I�ȁj�v�f��S�Ď�荞�݁A����ɂ���500���ɂ��y�ԃA���o�������吧�삵���C�����Ō��胊���[�X���Ă����B |
 |
James Brown �i�W�F�C���X�E�u���E���j ���킸�ƒm�ꂽ�u�S�b�h�t�@�[�U�[�E�I�u�E�t�@���N / �\�E���v�AJB���ƃW�F�C���X�E�u���E���B60�N��ȍ~�A���n�[�h�ȃT�E���h���w�����A63�N���색�C���E�A���o���wLive At The Apollo�x�A65�N�wPapa's Got A Brand New Bag�x�A�V���O���uI Got You�iI Feel Good�j�v�̑S�ăq�b�g�Ŕ��l�w�̐l�C���l�����Ȃ���A���݂Ɏ���h�t�@���N�E�~���[�W�b�N�h�̊�b�������グ���B69�N�ɂ̓L���b�g�t�B�b�V���E�R�����Y�ig�j�A�u�[�c�B�E�R�����Y�ib�j���o���h�E�����o�[�ɉ����B�ނ�͂��炭����ƃp�[�������g�ƃt�@���J�f���b�N���������邽�߂Ƀo���h�𗣂ꂽ���A70�N��ɓ����JB�Y�𗦂��Ċ��������B60�N��㔼����70�N�㒆���ɂ����ẴW�F�C���X�E�u���E���y��JB�Y�̉��i���͂����܂����A���̎������u�{���̃t�@���N�̉������v�ƌĂԉ��y�t�@���͑����B���̌�̃f�B�X�R�E�u�[���ɂ���킷���80�N��ɓ���ƁA�ނ����X�y�N�g����q�b�v�z�b�v�E�A�[�e�B�X�g�����Ƃ̊����������A86�N�ɂ̓A�t���J�E�o���o�[�^�Ƃ̃R���{���[�V�������b��ƂȂ����B |
 |
Lonnie Liston Smith �i���j�[�E���X�g���E�X�~�X�j 1972�N����73�N5���܂łƂ����킸��1�N���炸�̎Q���ƂȂ������A�wOn The Corner�x�ɂ�����L�[�{�[�h�̃V���v���ȃR�[�h�������A���o���̃T�E���h���x�z���Ă���͖̂��m���B�o���h�E�ތ�́ARCA�̃t���C���O�E�_�b�`�}���ƌ_�A1973�N�Ƀ��j�[�E���X�g���E�X�~�X���U�E�R�Y�~�b�N�E�G�R�[�Y���������A���N�Ƀt�@�[�X�g�E�A���o���wAstral Traveling�x�\�B���̌�A�Ǝ��̃X�s���`���A���ȃt���[�W�����E�T�E���h���\�����Ă������ƂɂȂ�B |
 |
Ivan Lins �i�C���@���E�����X�j �uLove Dance�v�A�uThe Island�v���͂��߂Ƃ��鐔�����̖��Ȃu���W�����ւ�V�˃����f�B�E���C�J�[�A�C���@���E�����X�B1960�N�ォ�烊�I�E�f�E�W���l�C���𒆐S�ɑn�슈�����͂��߁A�G���X�E���W�[�i�ɒ����uMadalena�v���q�b�g�B80�N��ɓ���Ɖ��Ăł����Ȑl�C���l�����A�}�C���X���͂��߁A�N�C���V�[�E�W���[���Y�A�W���[�W�E�x���\����������A�[�e�B�X�g�𖣗����Ȃ���A�u���W�����y�E���w�̃V���K�[�E�\���O���C�^�[�Ƃ��Ă̒n�ʂ��m�������B���O�}�C���X���C���@���E�����X�̊y�Ȃɍ��ꂱ��ł����̂͗L���ŁA�����X�ɕ�����A���o������낤�Ƃ��Ă�������1991�N�Ƀ}�C���X�͑��E�B���̈�u���p�����W�F�C�\���E�}�C���X�i�ȑO�Ƀ}�C���X��}�[�J�X�̍�i���v���f���[�X�^�A�����W���Ă����j���A�}�[�J�X�E�~���[�A�X�e�B���O�A�`���J�E�J�[����������Đ��삵���̂��C���@���E�����X�E�g���r���[�g�E�A���o���wA Love Affair�x�ł���B |
 |
Marcus Miller �i�}�[�J�X�E�~���[�j �W���Y�^�t���[�W�����݂̂łȂ��AR&B�A�t�@���N�Ƃ������C�f�B�I����p���Ȃ���A�X���b�v�A�^�b�s���O�t�@�Ȃǂ���g���ĕ\���͖L���ȃT�E���h��e���o������ō��̃x�[�V�X�g�ɂ��āA�v���f���[�T�[�A��ȁE�ҋȉƂƂ��Ă���}�ȍ˔\���݂���}�[�J�X�E�~���[�́A1981�N�㊥20�̂Ƃ��ɁA�}�C���X�̕��A��ƂȂ�wThe Man With The Horn�x�Ƀx�[�V�X�g�Ƃ��Ĕ��F�����B���̌�́wTutu�x�ɂ����Ă��A�x�[�X�͂��Ƃ��}�C���X�̃g�����y�b�g�ȊO�̊y����قƂ�ǒS���A����ɂ͊y�Ȓ���v���f���[�X�Ɏ���܂ŁA�ӔN�̒鉤�̊����̓}�[�J�X�Ȃ��ł͍l�����Ȃ��قǑS���̐M�������Ă����B |
 |
Jack Dejohnette �i�W���b�N�E�f�W���l�b�g�j �n���V�J�SAACM�ɎQ��������ɃT���E���[�A�W���b�L�[�E�}�N���[���A���[�E���[�K���A�`���[���Y�E���C�h�E�J���e�b�g�A����ɂ́A�r���E�G���@���X�̃s�A�m�g���I�Ȃǂւ̎Q���ŃL�����A�����h���}�[�A�W���b�N�E�f�W���l�b�g�́A1968�N�Ƀg�j�[�E�E�B���A���X�̌�C�Ƃ��ă}�C���X�E�O���[�v�ɓ��c�B�wBitches Brew�x�A�wA Tribute To Jack Johnson�x�A�wOn The Corner�x�Ƃ������d�v��i�ɎQ���B�܂��A�t�B�����A��C�g���t�F�X�e�B���@���ł̉��t�ɂ��A���l���b�N�E�t�@���`�q�b�s�[�����ɂ�����Ȉ�ۂ��c�����ƌ����Ă���B�}�C���X�E�O���[�v����71�N�ɂ́A�{�u�[���[�[�X�ids,vo�j��Ə��̎��ȃO���[�v�A�R���|�X�g�������BColumbia����2���̃A���o�����c�����U��AECM���R�[�h�ɂăf�C���E�z�����h�ƂƂ��Ƀ`�b�N�E�R���A�̃��R�[�f�C���O�ɎQ���B���̑��A�V���Ȏ��ȃO���[�v�ƂȂ�f�B���N�V�����Y�A�j���[�E�f�B���N�V�����Y��2�̃O���[�v�Ŋ������A�܂��A�Q�C���[�E�s�[�R�b�N�Ƌ��ɃL�[�X�E�W�����b�g�Ƃ̃X�^���_�[�Y�E�g���I�ł̊������s�Ȃ��Ă���B |