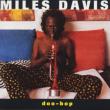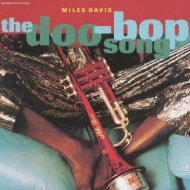��}�C���X ���X�g�E�C���[�Y� ���R�N������ɐu��
2010�N12��21�� (��)

�@�W���Y�E�́u�鉤�v���ƃ}�C���X�E�f�C���B�X�́A1975�N�ˑR���y�V�[������p���������B��ɕ�܂ꂽ�B�ِ�������6�N�A��Ղ̃J���o�b�N���ʂ������}�C���X�́A�Ⴂ����̃����o�[���W�߁A����ɐV�������y��Nj�����B�����čŔӔN�A�}�C���X�͍��܂Ŏ���ɋւ��Ă����u�ߋ��̍ĉ��v���s�����E�E�E�B
�@1975�N9��6�����畜���̐��ꕑ��ƂȂ���1981�N7��5���Ɏ���܂ŁA�鉤�͕��d���������̋ɓ��d���l���ɁA��ċz���ꂽ�B���̈�ċz�́A�����n���l�̃t���b�g�Ȏ��Ԏ��ɂ��Ċ�6�N�B����������A�Z��������[�d�i�`���[���E�A�b�v�j���Ԃ��o�ăV�[���ɃJ���o�b�N�����鉤�́A���͂�ߋ��̃}�C���X���Ɨe�ՂɌ��ѕt���邱�Ƃ��ł��Ȃ��^�V�����������Ȃ��Ă����B�}�[�J�X�E�~���[���v�����X���C�[�W�[�E���[�E�r�[���N�C���V�[�E�W���[���Y���A���ׂĂ����̃��K�}�}�ł����ڂȒ����̂��甭������}�W�b�N�ɖ������A�ۂݍ��܂�Ă����B
�@�O���w�G���N�g���b�N�E�}�C���X 1972-1975 �q�W���Y�̒鉤�r���t�ł��h���ƏI���̐^���x�Ɉ��������A�u�}�C���X�V���V���[�Y�v�̊����҂ƂȂ�ŐV�����w�}�C���X�E�f�C���B�X ��Ղ̃��X�g�E�C���[�Y�x�����ꂽ���{�ɂ�����}�C���X�E�f�C���B�X�����̑��l�ҁE���R�N������ɂ��b�����f�����Ȃ���A�}�C���X�Ō��16�N�Ƃ����Y���B�肵�āAHMV�v���[���c �u�}�C���X ���X�g�E�C���[�Y �~���u�K�v�B
�C���^�r���[�^�\���F ���l���� |
-
---�@����́A��Ղ̃J���o�b�N���ʂ�����1981�N����ӔN�Ɏ���܂ł̎����ɏœ_�Ă��A���R�N������̍ŐV�����w�}�C���X�E�f�C���B�X ��Ղ̃��X�g�E�C���[�Y�x��ǂ݉����Ȃ���A�O�l�A�}�C���X�E�f�C���B�X�̉��y��l�����Ȃǂɂ���ɐ[���G��Ă�����Ǝv���Ă���܂��B
�@�@
�@�O��̃e�L�X�g�ƂȂ����w�G���N�g���b�N�E�}�C���X 1972-1975 �q�W���Y�̒鉤�r���t�ł��h���ƏI���̐^���x�ł́A������u���فv�O��1975�N�܂ł̊����̗��ꂪ�傽��e�[�}�Ƃ��Ĉ����Ă��܂����B�����āA����̂������ɂ�����e�[�}�́A6�N�̒��ي����܂߂��Ō��15�N�ԂƂȂ�܂��B �}�C���X�ӔN��55�`65�Ƃ����̂́A���R�����ۂɃ}�C���X�ƌ𗬂�������Ă��������ł������āA���Ƃ����ł́u�{���������ɂ�����l�I�Ȏv���o��ł��������ƂɘJ�͂�v�����v�Ƃ������Ƃ�������Ă��܂����ˁB �@���ǂ��̃V���[�Y�Ƃ����̂́A�u�l�v�Ƃ����l�Ԃ������Č��ɂ������Ă���Ƃ������ƂȂ̂ŁA���R�u�l�v�Ƃ�����ς�����ƁA�����̍�ƂɂƂ��Ă̓W���}�ɂȂ��Ă���킯�ł��B�������Ȃ���A�v���o�Ƃ����̂͂���킯�ŁB���ׂĂ��������ɁA�ߋ���U��Ԃ��Ă��������Ƀ}�C���X�̎������o�Ă���B����͏����l�^�ɂȂ����Ƃ��Ă��A�����܂ł̃X�g�[���[�ƏƂ炵���킹�Ă݂�Ƃ���ς�W���}�ɂȂ��Ă��܂���ł��ˁB�ςȋ�ł͂����ł����ǁi�j�B
�@�v���o������Ƌq�ϐ���������B���������̎����ɕt���������������̂͊m���B�Ƃ����Ƃ���ł̂����̊����݂����Ȃ��͓̂��R����܂����B�������A����܂ł̃}�C���X�̐V���̃V���[�Y�Ƃ܂��傫���Ⴄ�Ƃ���ł��B- ---�@1975�`81�N�ɂ�����u���ي��v�B���́u���فv���A���ǂ͌���t�����Ƃ������A�g�}�C���X���ꂪ���̐_�b�Ƃ��ăO���[�h�A�b�v�����h�ƌ����������͂��ʓI�ɂ͑����̂ł��傤���H
�@���Ȃ��Ƃ��l�͂������Ă��܂��B
- ---�@����̓A�����J�ł����{�ł������Ȃ̂ł��傤���H
�@�����ł��ˁB�A�����J�ŁA�}�C���X���J���o�b�N�����Ƃ��Ƀ��b�Ɛ���オ�����̂������������Ƃ����A���{�����l�ɐ���オ�����B������A�u���فv��������Β����قǁA���̂܂�����ꍇ������ɂ���A���������ɓ]�Ƃ��͌��ʂ����{�ɂ��Ȃ�Ƃ������Ƃł���ˁB�}�C���X���i���j�u���C�A���E�E�B���\���Ȃ́A��������ĉߋ��̓`����h��ւ��Ă������ƌ������Ȃ��ł��傤���B
�@�����u�`���̗́v�݂����Ȃ��̂�����Ƃ�����A���[�����O�E�X�g�[���Y�݂����ɂ����Ƃ�葱���Ă�����́A���́u���x���x�ށv�Ƃ����s�ׂɂ���āA���������̊��Ԃ�������Β����قǁA���Ȍ��ʂ����������̂ł͂Ȃ����ƁB

�i���j�u���C�A���E�E�B���\���́u���ي��v�E�E�E�����m�r�[�`�E�{�[�C�Y�̌����[�_�[�B1966�N�́wPet Sounds�x�ł��̗ދH�Ȃ鉹�y�I�˔\�𐢂ɒm�炵�߂����A�h���b�O�ˑ��ɉ����āA����wSmile�x�̐���ڍ������������Ɏ���ɐ��_�Ɉُ���������悤�ɂȂ�A���̌�͎���Ɉ����U�肪���ɂȂ����B�h���b�O�A���A�ߐH�ɂ��ڂꂽ�����Ȑ����ɐZ��A20�N�߂��u���ي��v�Ƃ����������̈�r��H��B88�N�ɏ��̃\���E�A���o���wBrian Wilson�x�Ŋ��S�������ʂ����A���܂Ƀr�[�`�E�{�[�C�Y�ɎQ�������\����̂Ŋ����𑱂��A��J�[�������1999�N�ȍ~�͊��S�Ƀo���h���Ԃ�Ђ��A���g�̖����������o���h�𗦂��Đ��͓I�Ƀ��C�����s�Ȃ��Ă���B - ---�@�������A�}�C���X�͂�������O�Ɍv�Z���ĉB�������킯�ł͂Ȃ��ł���ˁH
�@�����A�������B�����A���ɂ���Ȃ��Ƃ��v�Z���Ă��v�Z���Ȃ��Ă��A�J���o�b�N�����Ƃ��̉��y���_����������A����ς�_���Ȃ�ł���ˁB�`���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���R�Ȃ���A�ŏI�I�ɂ͉��y�̗͂Ȃ�ł���ˁB
- ---�@���̒��ي��ɁA�����炭�}�C���X�͎���Ń��R�[�h�A�e���r�A���W�I�Ȃ�ŁA�F�X�ȉ��y�����ɂ��Ă������Ǝv���̂ł����A�������ɂ́A�i���j���[�Y�E���C�X�uLove Don't Live Here Anymore�v�̃J���@�[�E�A�C�f�A����������A�Ƃ������悤�Ȃ��Ȃ��̓I�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂����B�ߏ��ɏZ��ł����Ƃ����`���J�E�J�[���Ƃ̌𗬂��܂߂āA���������\�E���E�~���[�W�b�N�ւ̓��ʂȓ��ۂ⎷���Ƃ������̂��A���̎������ɋ��������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H
�@���ʂ��������X�������������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�Ⴆ�A���R�[�h�E�V���b�v�Ȃɍs���ƁA�}�C���X�̃��R�[�h�Ƃ��̕ӂ�̃u���b�N�E�~���[�W�b�N�̃��R�[�h�Ƃ����͖̂��m�ɕ�����Ă��邶��Ȃ��ł����B�t���A���R�[�i�[���S���B�������A�}�C���X�A���邢�́A�i���j�`���J�E�J�[�����i���j���o�[�^�E�t���b�N�̂悤�ȃA�[�e�B�X�g�Ƃ����̂́A���̕ӂ�̉��y��S���ꏏ�̂��Ƃ��Ē����Ă����ł���ˁB������A���ꂼ��̑��݉e���݂����Ȃ��̂������Ăނ��듖�R�����A�l�炪�v���Ă���ȏ�ɁA���邢�͑z���̕t���Ȃ��͈͂Ŗ��ڂȊW������킯�Ȃ�ł��B
�@���o�[�^�E�t���b�N�ɂ��Ă��`���J�E�J�[���ɂ��Ă��A���̉��y�̃o�b�N�g���b�N�������Ă���ƁA�ʂɃ}�C���X���g���Ă������悤�Ȃ��̂������ς������ł���B���p�������悤�Ȃ��̂��B�ŏI�I�ɂ����ɏ��������̂��A�`���J�E�J�[���̐����}�C���X�̃g�����y�b�g���A�݂����ȂƂ���ŃW�������������ł��Ă��܂��Ƃ������Ƃł����āA�o�b�N�g���b�N������Ă��鎟���ɂ����ẮA���ۂɋ��ʂ̃~���[�W�V���������܂����A���@�_���Ⴄ�Ƃ͌����A���G��͂قڈꏏ���Ǝv���܂����A�W�������I�ɂ����������͂Ȃ��Ǝv����ł���ˁB
- ---�@�����������Ƃ��ӂ܂��āA���̎����̃}�C���X�ɑ���]���Ɋւ��ẮA�W���Y�̐��E�ł́u�k���v�A�W���Y�ȊO�̐��E�ł́u�g��v�ƁA������ɂƂ��Ă͂���ɋɒ[�Ɏ^�ۂ�������Ă��������ł��ˁB
�@�����Ȃ�ł���B���������Ӗ��ł͗����̐��E�œ����ɐ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ���ł���ˁA���Ԃ�B
- ---�@�ӔN�Ɏ���܂ŁA���̓�ɂ̕]���Ƃ����͕̂t���܂Ƃ��Ă����܂��B
�@�������A���̓����}�C���X���̂͑��݂��Ă���B���R�A���O�̓}�C���X���S�Ɍ���킯�ł�����A���̉��y�ɑ���u�W�������_�v�𐢊E���l����]�T�͂Ȃ������Ǝv���܂��B������A����Ɏ��Ԃ��o�߂��Ă���F��Ȃ��Ƃ����߂Čn�����Ă邱�Ƃ��ł����ƁB������Ԃ��o���Ă���̌������������Ƃ͌���Ȃ���ł����A�}�C���X�����ۂɑ��݂��Ă�������Ƃ͈Ⴄ���������������Ƃ͊m�����Ǝv����ł���ˁB
�@�}�C���X�Ɍ��炸�A�i���j�W�����E���m���Ȃɂ��Ă������ł����A�Ⴆ���������Ă��Ȃ��Ă��A���̐l���u���݂���v�Ƃ������ƂƁA�{���ɂ��̐����炢�Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł́A�Ӗ����������Ȃ�Ⴄ�̂��ȂƁB������A�̐l�ɂȂ��Ă��܂��ƁA���ƌ������E�E�E��X�Ɂu�X�L��^����v�݂����Ȃ��ƂɂȂ��Ă��āi�j�A�F��Ȃ��Ƃ��l����������B�����Ȃ�Ɩϑz�������ς������Ă��Ă��܂��B�������A�{�l���������́A�����ْ̋���������킯�ł���ˁB�u������������邩������Ȃ��v�݂����ȁB���̈Ⴂ�͂��Ȃ�傫���Ǝv���܂��B- ---�@�Ƃ������Ƃ́A���R�����ۃ}�C���X�Ƃ��t�������̂����������ƁA���̌�ł͌��������Ȃ�قȂ��Ă����Ƃ������Ƃł�����킯�ł���ˁH
�@��͂�S�R�Ⴂ�܂���ˁB���������{���������ƂɂȂ�Ƃ͎v���Ă����Ȃ������Ƃ������Ƃ�����܂����A�Ⴆ�A�i���j�M���E�G���@���X�Ɖ�����Ƃ��ɁA�M���͂��̓������Ȃ�N��������ł����A�ł��{�l���ڂ̑O�ɂ������́A�u���̐l�̐l���͒Z������A���F�X�Ɛu���Ă����Ȃ��Ɓv���Ȃ�Ďv��Ȃ��킯�ł���i�j�B���Ȃ��Ȃ��Ă���A���[�����[���ɂȂ�킯�Łi�j�B����̓}�C���X�ɂ��Ă������B�������̎��ɂǂꂾ�����₵�s�����Ă����Ƃ��Ă��c��A������邢�͗~�����Ǝv����ł���ˁB�wSketches of Spain�x���wThe Man With The Horn�x�̘b�������Ɛu���Ă����悩�����A�Ƃ��B����Ȃ��Ƃ͌���Ȃ�����킯�ŁA����͂���ł����d�����Ȃ��Ƃ������ƂȂ�ł��傤�ˁB
�@�{�l�������Ă���Ƃ��ْ̋����Ƃ����̂͊m���ɂ���܂��B����䂦�A�{�l���O�Ɍ������Ă���ȏ�́A�����ɂ�����Ƃ��Ă͓����������Ƃ����C�����������Ƌ����Ȃ�B������A���̏�ɂ�����wSketches of Spain�x�Ȃ̂��Ƃ����܂�v���o���Ȃ��B����́A�܂����Ǝv���Ă��邩��ł�����Ǝv���܂��B�}�C���X�Ɍ��炸�N�ɑ��Ă��B10���ڎ����p�ӂ�������8�����u���Ȃ������B�����ǁA����2�͂܂����x�ł������A�݂����ȃm���Ȃ�ł���ˁB �@- ---�@�Ⴆ�A�u1979�N�ɁA�i���j�|�[���E�o�b�N�}�X�^�[�ƃM���E�G���@���X�ɋ�����Ȃ��w�����Ă����v�Ƃ����悤�Șb�̗��t���Ȃ�ڃ}�C���X�ɐu�����Ƃ��Ȃ�������ł��ˁB
�@�}�C���X�ɂƂ��Ă͏I���������̂��Ƃł�����A���Ӗ��Ȃ�ł���B���ɉ��y�̐��E�ł͂�����������b�݂����Ȃ��̂������B�������ēZ�܂����{��ǂނƁA�ЂƂЂƂ���������Ă��܂����A���A���^�C���ɖ��������݂��ߋ����������Ă���Ƃ��A�܂�{�l�����݂���Ƃ��ɂ́A�Ⴆ�u1979�N�ɂ��Ȃ��̓|�[���E�o�b�N�}�X�^�[�ɉ�܂����ˁv�݂����Ȏ���͐��܂�悤���Ȃ���ł��B�������Ă��b�̌��ʁA���݂����F��������łȂ��ƁA������������͏o�Ă��Ȃ����A�ނ������������Ȃ���ł���ˁB���ꂾ���ׂ������ƂȂ�ł���A�����Ă����́B�l���{�ɏ������ȏ�̂��Ƃ���������������Ȃ����A�����ɏ����ꂽ���Ƃ��S�Ă������̂�������Ȃ��B
�@�}�C���X�́A���R�[�h��ГI�ȃX�P�W���[���̎��Ԏ��œ����Ă���킯�ł͂Ȃ��āA���������y�̒��Ő����Ă���悤�ȃ^�C�v�̐l�ł�����A�����ɂ̓|�[���E�o�b�N�}�X�^�[�����łȂ��A�M���E�G���@���X���i���j�s�[�g�E�R�[�W�[���������낤���A�Ƃ��ׂĒn�����Ȃ�ł���ˁB���Ƃ��{�l�ɂ��̂��Ƃ�u�����Ƃ��Ă��A����́u10�N�O�̉��������̗[�H�ɉ���H�ׂ܂������H�v�Ƃ����悤�Ȏ���Ɠ����悤�Ȃ��̂Łi�j�A�����悤���Ȃ��B���ɁA����ɑ��ē�����ꂽ�Ƃ��Ă��A���̓����̗��t���͎��Ȃ��B�ł܂��A�{�l�������Ă��邱�Ƃ�����M�p�ł��邩�Ƃ��������ł��A����͕ʖ��ł�����ˁB
�@�{�l���S���Ȃ��Ă��珑����{�ƁA�������W�Ȃ�������{�ƐF�X�^�C�v������Ǝv���܂��B���̎�̃h�L�������g�́A����ς�ǂ����Ō������t�����l����Ȃ��Ɩ����Ȃ�ł���ˁA���Ȃ��Ƃ��l�ɂƂ��ẮB- ---�@1981�N���wThe Man With The Horn�x�ŕ��A�����}�C���X�́A�X�e�[�W�Ń��C�����X�E�}�C�N��p���āA�u���O�Ɍ�肩����v�Ƃ����p�t�H�[�}���X�����܂���ˁB���̂��Ƃɂ��ẮA�ǂ̂悤�ɑ����Ă�������Ⴂ�܂����H
�@�����O�̃I�[�v���Ȑ��i�Ƀv���X���āA�a�C���������ƂȂ���������āA������Ɗۂ��Ȃ�����ł����ˁB
- ---�@��͂�u�ۂ��Ȃ����v�Ƒ�����̂����R�H
�@���͖l�͂����v���ĂȂ���ł����ǁA��ʓI�ɂ͂���������Ǝv���܂���B�l�́A�}�C���X�͒��O��M���Ă����A���̃}�C���X�Ȃ�̊���\���������Ǝv���܂��B
- ---�@�������́A�ЂƂ́u���o�v�Ƃ��āA�������Ă����H
�@��{�I�ɂ́u�f�v�ł��傤�ˁB����Ȃɂ��܂���ɉ��Z�ł���l�ł͂Ȃ��ł�����B������A�}�C���X�̈ӎ��̒��ł́A�������ڐ��������ē����Ȃ��Ɓu����邾�����v�Ƃ����s�����͂������Ǝv����ł���B���ꂱ���u�X�g���[�g���o�̌��@�v�݂����ȁB����͗Ⴆ�A�������L���ȃX�^�[��Twitter�����悤�Ȃ��̂Łi�j�A���o��������Ȃ�����ǁA�ǂ����Ő��ԂƂȂ�������������Ƃ����v���B��������ɂ́A�����������Ȃ��ƁA�Ƃ������Ƃł���ˁB
- ---�@����ŁA����Ƒ�O�����߂�u�|�b�v�E�X�^�[�v�Ƃ��ĐU�������Ƃɂ������������Ă����Ƃ����B
�@�I�V�����̉����Ȃ�ł���B�V���������āA���āA���ꂪ�����h���̂���ꏊ�͂ǂ����A�݂����ȂƂ��납�炢���ƁA���R�W���Y�E�N���u�ł͂Ȃ��킯�ł���ˁH �������A�t�@�b�V������s�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA�F�X�ȗv�f���Ђ�����߂Ă��̈ʒu�ɂ܂ōs�����Ǝv����ł����B�����������o�ŁA�I�����݂����Ȃ��̂��F�X�Ƃ�������ł��傤�ˁB
- ---�@���ɁA���́w���X�g�E�C���[�Y�x�ɂ����Ă͂��̊��o����w�����Ȃ��Ă����B
�@�����ł��ˁB�����A����ȏ㑼�̉��҂��ɂȂ�K�v�͂Ȃ��킯�ł�����B
- ---�@���̕��A����ڂƂȂ����wThe Man With The Horn�x�Ɋւ��ẮA�u���܂��m�ł���]�����^�����Ă��Ȃ��v�Ə�����Ă�������Ⴂ�܂���ˁB
�@�wThe Man With The Horn�x�݂̂Ȃ炸�A�Ǝv����ł����A���A��̃}�C���X�͂���ς葨���������Ǝv���܂��B�}�C���X�͍Ō���wDoo-Bop�x�Ńq�b�v�z�b�v��������킯�ł����A���������̊����`�������ɖS���Ȃ��Ă���B������A�ǂ��܂ł��}�C���X�̍�i���Ƃ�������������ɂ���A�u�q�b�v�z�b�v�v�Ɓu�W���Y�v�Ƃ������́A�����𑨂��邱�Ƃ��ł��Ȃ���A���̎���̃}�C���X�𗝉����邱�Ƃ͕s�\�Ȃ�ł���B�Ƃ��낪�A�W���Y�̐l�̓q�b�v�z�b�v���Ȃ��B�q�b�v�z�b�v�̐l�̓W���Y���Ȃ��ƁB�Ƃ������Ƃ́A�w�����킹�Ƃ������E�E�E���܂Ōo���Ă��}�C���X����낤�Ƃ��Ă������Ƃ����̂͌����Ă��Ȃ���ł���B
- ---�@�����A�}�C���X�́u�X�g���[�g��A�v�Ƃ��������ł́A��ʓI�ɂ��̋c�_�̖��悪�wDoo-Bop�x ��_�ɏW�����Ă�X��������܂���ˁB
�@�悤����ɍŏ�����X�g���[�g�u���Ȃ�ł���B���ꂪ�u�V�������Ɓv�Ƃ������ƂȂ�ł���ˁB�wKind of Blue�x�ł��A��ʂɂ͔�������Ă��܂��A�V���O���Ղ������ς����ăW���[�N�{�b�N�X�ɓ��ꂽ�肾�Ƃ��A�Ƃɂ��������������X�g���[�g�ɐg��u���Ⴂ�w�ɒ����Ă��炢�����Ƃ������Ƃ͏�ɂ���܂�������ˁB�����炭����̓}�C���X��������Ȃ��Ǝv����ł����B������A���̂��Ƃ���ʎ�����K�v���Ȃ����A�������ߏ��]������K�v���Ȃ��B�����A�l��{���̎v�������������Ă����̂��}�C���X�������Ƃ������Ƃł���ˁB
�@�Ⴆ�A�r�[�g���Y���V���O���Ղŏo�������̂�LP�ɂ͓���Ȃ��Ƃ����p���Ƃ������ŁA�����������Ă��Ȃ��Ă�������Ⴂ�w�ɏ�Ɏ��_��u���Ă����ƁB�}�C���X�̂悤�Ɉ̑�ȑ��݂ɂȂ��Ă���ƁA�����������w�Ƃ̘������o�Ă���̂ŁA�]�v�Ɏ������g���������邱�Ƃ������]��Ŕ������Ȃ��ƁA�����̒��ł́u�i�E�v�Ƃ������o���Ȃ��Ȃ��āi�j�A�����Ƃ����ԂɁu�����فv�Ƃ������u��䏊�v�Ƃ������A���������s�{�ӂȈ���������Ă��܂��B���������A���ɂ����Ȃ��Ă��A�����������Ƃ���Ɏ����Ă�����Ă��܂�����ɂ���l�ł�����ˁB- ---�@�q�b�v�z�b�v���V�������l�̉��y�����Ƃ��đ䓪�����������ł����B
�@�������A���ꂪ�t�@�b�V�����ɂ܂ŋy�B���ۂƂ��ẮA���S�Ƀr�o�b�v�̏Ă������Ȃ�ł���ˁB�r�o�b�v�̎���ɂ̓W�����v�E�X�|�c�����s���āA���ꂪ�q�b�v�z�b�v�ł̓i�C�L�ȂɂȂ����Ƃ��������̘b�ŁB�����ɐe�a���Ƃ������̂������ł���B�}�C���X�ɂ���N�ɂ���A���l�ӎ�������������قǁA�����I�ȃ��b�Z�[�W��������A������������Ō���Ă��邱�Ƃɕq���ɂȂ�킯�ł���ˁB�ŁA�����Ɋ��H�����o�����B
�@�r�o�b�v����A���b�v�A�q�b�v�z�b�v�ƍs���āA�Ō���wDoo-Bop�x�Ƃ�����͂̂悤�ȗ��ꂪ�ЂƂł���悤�ȋC�����Ă����ł���ˁB�������A���݂́A�q�b�v�z�b�v�A���b�v�A�N���u�E�W���Y�A���~�b�N�X��T���v�����O�E�~���[�W�b�N���S���ꏏ�����̃C���[�W�̒��ő������Ă���悤�ȋC�����Ă��āA�܂��Ă�A���̃C���[�W�̒��̗D�揇�ʂƂ��ď�ʂɃW���Y�͂Ȃ��B������A������܂��������āA���炪�������������B�u�R���ƃR���͎��͂Ȃ����Ȃ����H�v�Ƃ��u�Ȃ����Ă���Ǝv���Ă������ǁA��������������Ȃ����H�v�Ƃ��B��������������������ŁA�i���j�p�u���b�N�E�G�l�~�[���Ƃ��ے��I�ȃq�b�v�z�b�v�E�A�[�e�B�X�g�������Ȃ���𖾂��Ă����A�ŏI�I�Ƀ}�C���X���wDoo-Bop�x�܂Ŏ����Ă����Ƃ������@���c����Ă���Ǝv���B�܂�A�}�C���X�����������ƁA�}�C���X�Ɍ��関���Ƃ����\�}�ł��ˁB
�@�q�b�v�z�b�v�j�Ŗ{���ɏd�v�Ȃ��Ƃ́A�wDoo-Bop�x�ȍ~�ɋN�����Ă���킯�ł�����ˁB����͂����炭�A�}�C���X�̎���ɂ����Ă�����傫�ȃ��[�������g���Ǝv����ł���B- ---�@�wDoo-Bop�x�ȍ~�A�q�b�v�z�b�v�͕����E�Y�Ƃǂ���̖ʂɂ����Ă������܂����}�������݂��܂���ˁB
�@�����܂Ń}�C���X�����������Ă�����A���̉e�����̃h�^�ɂ�����Ȃ����ȂƂ����C�͂����ł���B���͂��̕����ł̃h���}�͂܂��I����Ă��Ȃ��Ƃ������B�t�ɁA�q�b�v�z�b�v�̃v���W�F�N�g�����S�ɏI���O�ɍŌ���}���Ă��܂������Ƃ��h���}�`�b�N�ł͂����ł����ǂˁi�j�B
- ---�@�h�~�X�e���[�h����������c���i�j�E�E�E
�@���������A���̃A���o����1�Ȗڂ͂��������^�C�g�����������i�j�B���͖l���l�I�ɍ��ЂƂ��M�����ĂȂ������������āA����͗Ⴆ�q�b�v�z�b�v�̒��́u���b�v�v�B���ꂪ�܂��u���t�̃T�E���h�v�ł���Ƃ������ƂŁA����ς肿����Ɨ������y�Ȃ�����������킯�Ȃ�ł���ˁB�����ЂƂ́A���l�̕����Ƃ͌����A�A�����J�ɌÂ����炠���i���j�u�|�G�g���[�E���[�f�B���O�v�̂悤�Ȑ��E�̓`������������ŊJ�Ԃ��Ă���悤�Ɏv����Ƃ������ƁB�����Ȃ�ƁA�����܂ŗ��j�������̂ڂ鎩�M���܂��Ȃ���ł���B
- ---�@�i���j�M���E�X�R�b�g���w�������i���j���X�g�E�|�G�b�c������ɂ����̂ڂ����ꍇ�A�ƁB
�@��������1969�A70�N�̃��X�g�E�|�G�b�c�����肩��l���n�߂āA�Ƃ����̂��ʗႩ������܂��E�E�E�{���͂����ƈȑO�ɂ������������E�͂���킯�ł�����A�����ŋ���Ă����̂��Ƃ����ڕ��ʂ��v�肫��Ȃ���ł���ˁB���̂����������ɍl����ƁA���X�g�E�|�G�b�c����A�N�C���V�[�E�W���[���Y�́wMellow Madness�x�ɂ��Q�������i���j���b�c�E�v���t�F�b�c�A���邢�̓p�u���b�N�E�G�l�~�[�̐���A�������i���j�C�[�W�[�E���[�E�r�[�ƁA���������������̓_������ł��������Ȃ���ł���A���܂̂Ƃ���́B������g����Ƃ܂��L�����Ȃ��ł�����ˁB

�i���j�|�G�g���[�E���[�f�B���O�E�E�E���l������̎���N�ǂ���A�[�g�`�Ԃ��ĂсA��ʓI�ɂ́A�E�B���A���E�o���E�Y�A�W���b�N�E�P���A�b�N�炪���S�ƂȂ���1950�N��̃r�[�g�j�N�������w�����Ƃ������B����ŁA�A�t���E�A�����J���`���e�B�[�m���y�j�ɂ�����|�G�g���[�E���[�f�B���O�̗��j�Ƃ��ẮA���̍Ŏn�_���m�F���邱�Ƃ͓�����A60�`70�N��̃��X�g�E�|�G�b�c�A���b�c�E�v���t�F�b�c�A�M���E�X�R�b�g���w�����炪�A���NY�̃n�[���������_�Ɋ������Ȃ���A�p�[�J�b�V�����Ȃǂ��o�b�N�ɐ����I�ȃA�W�e�[�V�����荞���e�̍�i�𑽂����\���Ă������Ƃɂ܂��͑�\����邾�낤�B���̓`���́A�̂��̃q�b�v�z�b�v����ɂ��p����A���݂ł̓|�G�g���[�E���[�f�B���O������ɐi���������u�X�|�[�N���E���[�h�v�Ƃ������悤�Ȍ`�Ԃ����܂�Ă���B�������A����͑S�l�ނɋ��ʂ��������p�����A�[�g�E�t�H�[���ł���A���{�ɂ����Ă��A���Ƃ��������������S�ƂȂ��čs�Ȃ�ꂽ�`�����e�B�[�E���C�u�w�~�����}�[�R�������ɍR�c����|�G�g���[�E���[�f�B���O�x���ŋ߂ł͗L����������Ȃ��B�ʐ^�́A���X�g�E�|�G�b�c�i��i�j�A���b�c�E�v���t�F�b�c�i���j�A�M���E�X�R�b�g���w�����i�E�j�B
�@�����̂��Ƃ͎���ȍ~�̖{�̃e�[�}�Ƃ��ĂЂƂl���Ă���Ƃ���ł������ł���B�u�q�b�v�z�b�v�ƃ}�C���X�̗��j�v�݂����ȂƂ���ŁB������������ŁA���ۂɂ����������Ƃ�������̂̓}�C���X�����ł͂Ȃ���ł����A�}�C���X�̂�����������Ղ�������ł���ˁB�Ƃ͌����A�K��������肭�������Ƃ͎v���Ȃ���ł����B����́A���̃q�b�v�z�b�v�E�v���W�F�N�g���r���ŏI���������Ȃ̂�������Ȃ���ł����A������Ō�ɗ��铚���Ƃ��ẮA���̃A���o����������V���v���ŁA�S�i�������Ă���B���̊ԂɁA�i���j�n�[�r�[�E�n���R�b�N�́wFuture Shock�x���i���j�r���E���Y�E�F���̎����I�ȍ�i�Ȃ���������������ł����A����ς肻���͈�ߐ��̂��̂ɂ����Ȃ������̂��ȂƁB
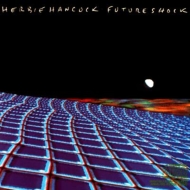
�i���j�n�[�r�[�E�n���R�b�N�wFuture Shock�x�E�E�E�x�[�V�X�g���v���f���[�T�[�̃r���E���Y�E�F���̎����I�ȉ��y�A�C�f�A�����ɐ��삳�ꂽ1983�N�̍�i�B�O�����h�~�L�T�[DST��DJ�X�N���b�`���_�Ƀt�B�[�`���[�����uRockit�v�i��26��O���~�[�܁u�x�X�g�ER&B�E�C���X�g�D�������^���E�p�t�H�[�}���X�v��܁j��J�[�e�B�X�E���C�t�B�[���h���Ȃ̍Ő�[�G���N�g���j�N�X���߂�M���ɁA�}�C���X�����āu�d�����i�I�^�N�v�ƌ��킵�߂��n���R�b�N�̃G���N�g���E���r�h�[�S�J�̃T�E���h���y��B�}�C�P���E�o�C���z�[���A�_�j�G���E�{���X�A�s�[�g�E�R�[�W�[�A�X���C�E�_���o�[�炪�Q���B

�i���j�n�[�r�[�E�n���R�b�N�wSound System�x�E�E�E��f�O��ɑ����A��27��O���~�[�܁u�x�X�g�ER&B�E�C���X�g�D�������^���E�p�t�H�[�}���X�܁v����܂���1984�N��i�B�r���E���Y�E�F���̘A���v���f���[�X�ɂ���āA�t�F�A���C�gCMI�A���}�nDX7���͂��߂Ƃ��铖���Ő�[�̃f�W�^���@�ނ�ԗ������e�N�m���W�J���E�G���N�g���b�N�E�n���R�b�N�̐��E�͂ЂƂ̒��_���ɂ߂��BCD���ɍۂ��A�uMetal Beat�v�̒��ڃo�[�W���������^���Ă���B - ---�@����ɁA�n���R�b�N�A���Y�E�F���ɂ���A�W���Y���q�b�v�z�b�v�̂��Ƃǂ��炩�ɕ��Ă��銴��������܂���ˁB
�@�܂����̕ӂ�ɂ��Ă͖l�̒��ł܂������ł������āB���́A���̃e�[�}�Ƃ��ď������Ǝv���Ă��邱�Ƃ��A�����ЂƂ���܂��āB�V���̃V���[�Y�́A���́w�}�C���X�E�f�C���B�X ��Ղ̃��X�g�E�C���[�Y�x�ň�U�I���Ȃ�ł��B����Ŏ��͒P�s�{�ł��B������A�����e�[�}�������ƃ}�j�A�b�N�ɂȂ�킯�Ȃ�ł��ˁB����Ӗ��ł����ƃh�L�������g����тт��������ȂƁB����ɁA�e�[�}�ݒ��N��ł͂Ȃ��āA����ɍׂ����Ƃ���ɏœ_�ĂāA���Ȃ�i���Ă����B���グ��͈͍͂L����ɂ���A������͋������̂ɂ������ȂƁB
 |
|
1978�N3��2�� N.Y. �R�����r�A�E�X�^�W�I�ɉ�����Z�b�V��������B�O����F�����[�E�R���G���A�G���A�i�E�X�^�C���o�[�O�E�e�B�[�E�R�u�A�}�C���X�A�A���E�t�H�X�^�[�A�e�I�E�}�Z���@�����F�����s�ځA�e�n��́AT.M.�X�e�B�[�����X�A�W���[�W�E�p�����X
|
 |
|
�uDoo-Bop Song EP�v�̃W���P�b�g���
|
�@�����炵�āA�wDoo-Bop�x�͓ˑR�ψٓI�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��āA�Ⴆ����ȑO���wSun City�x�ł���Ƃ��A�wThe Man With The Horn�x�̂��镔���ł���Ƃ��A���ƍׁX�Ƃł͂����ł����A���ʉ��ł͂Ȃ����Ă��鐢�E�ł͂����ł���ˁB�q�b�v�z�b�v�̕����I�ȖʂƐ̂̃r�o�b�v�Ƃ̐e�a���B������ŏ��Ɍ��������̂��A�}�C���X���i���j�}�b�N�X�E���[�`�Ƃ����r�o�b�v�̐���̃~���[�W�V�����Ȃ�ł���B�}�b�N�X�E���[�`�́u������i���j�`���[���[�E�p�[�J�[�̓��b�v���猻��邾�낤�v�݂����Ȍ��t���c���Ă��܂����ǁA�܂肻�̕ӂ̓������������x�������Ă����Ȃ��ƁA�u���b�N�E�~���[�W�b�N�Ƃ��ẴW���Y���A�܂��Ă�q�b�v�z�b�v�������ł��Ȃ����A���ɗ����ł����Ƃ��Ă��A�����炭�}�C���X�܂ł��ǂ蒅���Ȃ��ŁA�����͈̔͂ɂƂǂ܂�Ǝv����ł���B
�@�����ɒ��ڂ����̂��i���j�N�C���V�[�E�W���[���Y�ŁA�i���j�wBack On The Block�x�Ƃ����A���o���Ńr�o�b�v����ƃ��b�p�[���ꏏ�ɂ����B���ꂪ�ЂƂ̉��Ǝv����ł���ˁB�u���b�N�E�~���[�W�b�N�Ƃ��ẴW���Y�̐�s���⋥�\���A������ߌ��ȕ����Ƃ����̂͑S���A���̎����q�b�v�z�b�v�ɗ��ߎ��ꂽ��ł���A�l�̏����ł́B
|
�u���X�g�E�C���[�Y�v��20��
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
�y�Ċ��u�K�z �u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v ���R�N������ɐu��
-
�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v ���R�N������ɐu��
�s��ȃX�P�[���Ɩ��x�́u�鉤�E���d���G���v�B���̓�������������w�G���N�g���b�N�E�}�C���X 1972-1975�x�����ꂽ�}�C���X�����̑��l�ҁA���R�N������ɂ��b���f���܂����E�E�E
���̑��̊֘A�L��
-
�y���W�z �}�C���X�E�f�C���B�X �wTUTU�x �i2011�N5���j
�}�C���X�E�f�C���B�X��1986�N���[�i�[�ڐБ�1�e��i�wTUTU�x���A�{�҃��}�X�^�[�ɓ��N7���̃j�[�X����������lj�����2���g���ؔՂɂēo��B��������̎���}�[�J�X�́uTUTU�lj����C���v�������E�E�E�E�E�E
-
�y���W�z �d���鉤�w�� �u�r�b�`�F�Y�v�ɂ��� �i2010�N7���j
�wBitches Brew�x 40���N�L�O�������K�V�[�Ղ������B�����\���C������CD�A�����\���C��DVD����lj��������S���Y����̂䂾���������B�d���鉤�w�ƁwBitches Brew�x�ɂ��ĐF�X�ƁE�E�E
-
�e�n���E �����O�E�C���^�r���[ �i2008�N6���j
2008�N6���ɍs��ꂽ�e�n���E���C���^�r���[�̑S7�S�ŁB�_�u�E�Z�N�X�e�b�g�A�}�C���X�A�t�@�b�V�����A���̌q�����������x�l�@���Ă݂�ƁE�E�E�E�E�E
���~�E�� �I�����C�� �u�V���Ƃȑ����v�ŘA�ڒ��� �u�W���Y��Փ���v
|

-
���R�N�� �i�Ȃ���� �₷���j
�@1952�N���{�o�g�B���y�]�_�ƁB�W���Y�G���u�X�C���O�W���[�i���v�ҕҏW���߂���A���M�����ɓ���B����Ɂw�}�C���X�E�f�B���B�X �̎���x�A�w�}�C���X vs �R���g���[���x�A�w�}�C���X�̉āA1969�x�A�w�}�C���X���I�x�������B�Ɂw�}�C���X�E�f�B���B�X�����`�x������B�܂��A���b�N�ɂ����w���[���A�w�r�[�g���Y�ƃ{�u�E�f�B�����x�A�w���ƗE�C�̃��b�N50�x�A�w�f�B������!!�x��������B
- �֘A�T�C�g�i�O���T�C�g�j
- �֘A���W�iHMV�T�C�g���j
�{�����ɓo�ꂷ���v�l���ɂ��� |
 |
Chaka Khan �i�`���J�E�J�[���j �����`���J�E�J�[����1988�N�̃A���o���wCK�x�Ɏ��^����Ă���A�v�����X���v���f���[�X�A��ȁA���t�Q�������uSticky Wicked�v�ɔӔN�̃}�C���X���Q���B�I�[���@�[�E�_�r���O�̃~���[�g�E�g�����y�b�g�����łȂ��h���h�i�ȍŌ�̂��Ƃ�j�ł̋q�����ʂ����Ă���A�v�����X�Ƃ̗B��̌������������Ƃ��č������d����Ă���B���Ȃ݂ɖ{�Ȃ́A�}�C���X���ӔN�i1986�`90�N�j�ɑ��̃A�[�e�B�X�g�̍�i��f��̃T���g���ɃQ�X�g�Q�������������R���p�C�������wSpecial Guest is...Miles�x�i�p�Ձj�Ƃ������Ղɂ����^����Ă����B�܂��A1979�N�����A�j���[���[�N�̃}�C���X��̋ߏ��ɏZ��ł������Ƃ�����A���ي��̓��@��̑�|�����}�C���X�̎o�h���V�[�A���J�m�A�V�V���[�E�^�C�\���Ǝ�`�������Ƃ��{���ɏ����L����Ă���B |
 |
Roberta Flack �i���o�[�^�E�t���b�N�j 1973�N�́uKilling Me Softly with His Song�i�₳�����̂��āj�v�̃q�b�g��_�j�[�E�n�U�E�F�C�Ƃ̃f���G�b�g�ȁuThe Closer I Get To You�i���̋C�����j�v�Ȃǂōł��m����ł��낤���l�V���K�[�E�\���O���C�^�[�B���X�E�}�b�L�����Ɍ��o����A1969�N��Atlantic ���R�[�h����wFirst Take�x�Ńf�r���[�B�W���Y�A�\�E���A���Y���E�A���h�E�u���[�X�A�t�H�[�N�̃G�b�Z���X���U��߂�����Ȃ₻�̃T�E���h�ɂ́A�t���I�ɂǂ��ɂ������Ȃ��B�ꖳ��̐��E���������낵�A�\�E���⍕�l���y�E�����ɂƂǂ܂�Ȃ��A�܂��Ɂh�X�P�[���̑傫�ȏ����̎�h�Ƃ����`�e���s�^���Ƃ��Ă͂܂�B���o�[�^�̐e���Ԃ�͗L���ŁA1984�N�̏������ȍ~���R���X�^���g�ɓ��{��K��A���N10���ɂ́A���E���E�~�h���A���䌘�Ƃ̓��{�����كW���C���g�E���C�����s�Ȃ��Ă���B�}�C���X�̒��ْ��ɂ́A���g�̃o���h�ɁA���� �h��l�������Ă����h �G���g�D�[���ƃ��W�[�E���[�J�X�����������Ă���B���̗��҂̋���Ő��܂ꂽ�̂��uThe Closer I Get To You�v���Ƃ������Ƃ͈ӊO�ƒm���Ă��Ȃ�������������Ȃ��B |
 |
Gil Evans �i�M���E�G���@���X�j �s�A�j�X�g�E�ҋȎ҂Ƃ��ăA�����J�̃W���Y�E�r�b�O�o���h�E�Ɋv���������炵���l���Ƃ��Ē����ȃM���E�G���@���X�B1948�N�ɁA�}�C���X�A�W�F���[�E�}���K����ƃm�l�b�g�i��d�t�Ȋy�c�j���������A�`���[���[�E�p�[�J�[�̃r�o�b�v�Ƃ͑ΏƓI�ȉ��y�����u�����A49�N����50�N�ɂ����ẴZ�b�V�����́A�̂��ɁwThe Birth Of Cool�i�N�[���̒a���j�x�Ƃ��Ĕ��\����Ă���B���̌�A�ҋȉƂƂ��Ă̊�������s���Ȃ���A�Ăу}�C���X�Ƒg�݁A�wMiles Ahead�x(1957�N)�A�wPorgy �� Bess�x(1958�N)�A�wSketches of Spain�x(1960�N)�A�wQuiet Nights�x(1962�N)�\�B���̌�ɂ����Ă��A�N���W�b�g��������Ă��Ȃ����̂́A�X�^�W�I���ŃA�h�o�C�X��������A�y���̃������������t�҂ɓn������ƁA�}�C���X�̍�i�ɂ͗l�X�Ȍ`�ł�����葱���A�u�}�C���X�̒m�b�܁v�Ƃ��Ă�Ă����B |
 |
Paul Buckmaster �i�|�[���E�o�b�N�}�X�^�[�j ���Ƃ��Ɨc���̍�����}�C���X�̃��R�[�h���D��Œ����Ă����A�`�F���t�ҁ^��E�ҋȉƂ̃|�[���E�o�b�N�}�X�^�[�ƃ}�C���X�́A1969�N11���Ƀ����h���ŏo�����B�o�b�N�}�X�^�[�̍�i�ɂ����鉹�y���_�ɋ����������͂��߂Ă����}�C���X�́A�wOn The Corner�x�̃Z�b�V�����ɓ��钼�O��72�N�Ɂu�j���[���[�N�ōs���V�����A���o���̃��R�[�f�B���O�ɋ��͂��Ă���v�Ƃ����|�̓d�b����ꂽ�B�����h���������Ă����o�b�N�}�X�^�[�����Q���Ă����h�C�c�̑O�q��ȉƃJ�[���n�C���c�E�V���g�b�N�n�E�[���̃��R�[�h�w�O���b�y���x�A�w�~�N�X�g�D�[���x�ɁA�}�C���X�͖����ɂȂ����Ƃ����B�wOn The Corner�x�ɋy�ڂ����V���g�b�N�n�E�[���̃��R�[�h�̉e���͕͂s���Ȃ���A�Z�b�V��������}�C���X�͔M�S�ɂ��̃��R�[�h�������Ă����B�܂��A�wOn The Corner�x�Z�b�V�����́A�o�b�N�}�X�^�[�̈ӂ̂܂܂ɍs���邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ������Ƃ�{�l���獐�����Ă���B |
 |
Pete Cosey �i�s�[�g�E�R�[�W�[�j �V�J�S�o�g�ŁA���X�́A�`�F�X�E���R�[�h�̃X�^�W�I�E�~���[�W�V�����Ƃ��ă}�f�B�E�E�H�[�^�[�Y�A�n�E�����E�E���t�Ȃǂ̃o�b�N�ŃM�^�[��e���Ă����s�[�g�E�R�[�W�[�B72�N�����A���[���X�E�z���C�g��ƌ��������O���[�v�i�̂��ɃA�[�X�E�E�C���h���t�@�C�A�ɔ��W�j�Ŋ������Ă����R�[�W�[�́A���N9���̃t�F�X�e�B���@���o�����̊y���ɂ��܂��܋����킹�����W�[�E���[�J�X��G���g�D�[����ƃW�����E�Z�b�V�������s���A�G���g�D�[������Ă��̌�73�N�̃c�A�[����}�C���X�E�o���h�ɉ����i���̎��_�Ńo���h�́h�e���e�b�g�h�ɂ܂Ŋg�債���j���邱�ƂƂȂ����B�h�u���b�N�x�A�[�h�i���Ђ��j�h�Ə̂��ꂽ���̗e�p�ŁA�I�R�ƈ֎q�ɍ���Ȃ���c�݂܂����������Ń��X�|�[���������炷���̗l�́A�ɉ��ɂ܂�Ȃ��B�܂��A�M�^�[�̂ق��Ɋe��p�[�J�b�V�����A�L�[�{�[�h�Ȃǃ}���`�E�C���X�g�t�҂Ƃ��Ă̑��ʂȍ˔\�ŁA�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v�̃T�E���h���x���Ă����B |
 |
Max Roach �i�}�b�N�X�E���[�`�j �㊥18�˂Ńf���[�N�E�G�����g���E�I�[�P�X�g���ɎQ��������A�`���[���[�E�p�[�J�[�A�o�h�E�p�E�G���A�N���t�H�[�h�E�u���E����Ƃ̊����A���ł��V�˃g�����y�b�^�[�̃N���t�H�[�h�E�u���E���Ƒg��1954�N�̃��[�`���u���E���E�N�C���e�b�g�ňꎞ���z�����A�r�o�b�v�����犈�閼�h���}�[�B�P�j�[�E�N���[�N���J�����_���E�h���~���O�����������A�܂��A�|�����Y�������߂ăW���Y�ɂ������p�C�I�j�A�ł�����B���l�ł��邱�Ƃ������ӎ����Ă������[�`�́A��ɕv�l�ƂȂ�A�r�[�E�����J�[���ivo�j�Əo�����A�v�z�I�ȋ�������B���l����^���̓��m�Ƃ������ꂩ��l�퍷�ʓP�p�^���ɂ��ϋɓI�ɎQ������悤�ɂȂ�A60�N���\�̃A���o���wWe Insist�I�x�ł́A��̓I�Ȑ����ւ̃��b�Z�[�W�͍��߂��Ă��Ȃ����A�������^���E����^���ɂ����郍�[�`�̎p�����������f����Ă���B�W���[�W�E���b�Z����1959�N�̃��[�_�[��wNew York N.Y.�x�ɂ́A���[�`�̒@���ό����݂̃��Y���ɃW�����E�w���h���b�N�X�̌y���ȃi���[�V���������uManhattan�v�Ƃ����Ȃ����邪�A���łɃ��[�`�͂��̎��_�Łh���b�v�E�~���[�W�b�N�h�̌����ɖڂ�t���Ă����̂�������Ȃ��B�@�@ |
 |
Charlie Parker �i�`���[���[�E�p�[�J�[�j 1944�N�A����18�̃}�C���X�́A�n���Z���g���C�X�ŋ��R�ɂ��`���[���[�E�p�[�J�[�A�f�B�W�[�E�K���X�s�[�Ɠ����X�e�[�W�ɗ����Ƃ��ł����B�p�[�J�[���A�C�h���Ƃ���}�C���X�́A���̓����ŐV�̃W���Y�̃��[�������g�u�r�E�o�b�v�v�����߁A�����Ȃ�u�o�[�h�ɉ���߁v�ɁA���N9���j���[���[�N�֍s�����Ƃ����ӁB�㋞�̂��߂́h�����h�Ƃ�������W�����A�[�h���y�@���w��A���͊w�Z�A��̓p�[�J�[�A�f�B�Y�Ƃ̃Z�b�V�����Ƃ����߂܂��邵�����Z���ȓ��X�𑗂�悤�ɂȂ�B�����āA1945�N�H�A�f�B�Y�̌㊘�Ƃ��ă}�C���X�͐���ăp�[�J�[�y�c�̃g�����y�b�^�[�ɔ��F����A���N11���A�}�C���X���߂ẴX�^�W�I�E���R�[�f�B���O���s�����ƂƂȂ����B���̌��1947�N�ɂ́A�p�[�J�[��}�b�N�X�E���[�`��̃T�|�[�g�āA�u�}�C���X�E�f�C���B�X�E�I�[���X�^�[�Y�v�Ƃ������`�ŏ��̃��[�_�[�E�Z�b�V������Savoy�ōs���Ă���B |
 |
Quincy Jones �i�N�C���V�[�E�W���[���Y�j 1950�N�ォ������Ŋ���𑱂��A�O���~�[�܂��͂��߂Ƃ��鉹�y�܂𑽐���܂��Ă���A�u���b�N�E�~���[�W�b�N�E�݂̂Ȃ炸�|�s�����[���y�E�̈̑�Ȃ鉹�y�v���f���[�T�[�A��ȉƁB���X�g�����y�b�^�[�������N�C���V�[�́A���C�I�l���E�n���v�g���y�c�ł̊�����p���ɓn��A���X�̃r�b�O�E�o���h�𗦂��Đ��������߂��B60�N�ォ��̓v���f���[�T�[�Ƃɂ�����B1963�N�Ƀ��X���[�E�S�[�A�́u�܂̃o�[�X�f�C�E�p�[�e�B�[�v�̃q�b�g����ɁA�}�C���X�E�f�C���B�X�A�t�����N�E�V�i�g���Ȃǂ̃v���f���[�X���肪�����B���g�̍�i�ł����X�̖�����c���A1981�N�́u���̃R���[�_�v�̂悤�ȃ|�b�v�E�t�B�[���h�ł̃����X�^�[�E�q�b�g�����B�ł����������߂��d���́A1982�N�ɔ��\���ꂽ�}�C�P���E�W���N�\���̃A���o���wThriller�x�ł���A�j������Ƃ����ꂽ�A���o���ƂȂ�A�܂��A���́uWe Are The World�v�̑��w��������ȂǁA�L�����A�̐Ⓒ���ɂ߂�B�}�C���X�ƃM���E�G���@���X�̋�����̍Č�����������������1991�N7��8���X�C�X�E�����g���[�ɂ�����u�ĉ�Z�b�V�����v�ł́A�u�ߋ���U��Ԃ�Ȃ��v�}�C���X���N�C���V�[�͎��ۂɂǂ̂悤�Ɍ��������Ƃ����̂��낤���H |
 |
Public Enemy �i�p�u���b�N�E�G�l�~�[�j MC�̃`���b�N�ED�A�t���C���@�[�E�t���C���A�v���t�F�b�T�[�E�O���t�ADJ�̃^�[�~�l�[�^�[X��𒆐S�Ƀj���[���[�N�̃����O�A�C�����h�Ō������ꂽ�q�b�v�z�b�v�E�O���[�v�B1987�N�A�wYo! Bum Rush The Show�x��Def Jam����f�r���[�B�퓬�I�ȃu���b�N�p���[�^����S1W�iSecurity of the First World�j�ƘA�g���Ă��邱�Ƃł��L���ŁA�����I�E�Љ�I���邢�͕����I�Ȉӎ����A�I�݂Ŏ��I�ȃ��C���ɂ̂��邱�Ƃɂ���ă��b�v�̐��E��ϊv�����B�T�E���h�ʂɂ����Ă��A�v���f���[�T�[�E�`�[���̃{���E�X�N���b�h��ʂ��ăt���[�E�W���Y��n�[�h�E�t�@���N�A����ɂ̓~���W�[�N�E�R���N���[�g�̗v�f��������荞�݁A�O��̂Ȃ��悤�Ȃ�������Ƃ������\�ȃT�E���h�����グ���B����ɂ́A�wDoo-Bop�x�͓���2���g�Ő��삳��A���̈ꕔ�ɂ̓`���b�N�ED�ƃt���C���@�[�E�t���C���Ƃ̃Z�b�V�������\�肳��Ă����Ƃ����B |
 |
Easy Mo Bee �C�[�W�[�E���[�E�r�[ 80�N�ォ��D�ꂽ�g���b�N���J��o���Ă���q�r�v���f���[�T�[�̂ЂƂ�B�L�����A�����́A�W���[�X�E�N���[�ALL�N�[��J�̍�i�ɑ�\����A���ł��r�b�O�E�_�f�B�E�P�C���wIt's a Big Daddy Thing�x�́A�_�f�B�E�P�C���̃u���C�N�X���[��Ƃ��Ă����ł��]���������B�ق��A�E�[�^���E�N�����ł̃f�r���[�O��GZA�i�W�[�j�A�X�j�̃f�r���[��wWords From the Genius�x�⓯�����E�[�^���O���RZA�i�v�����X�E���L�[���j�̃f�r���[�E�V���O���uOoh I Love You Rakeem�v����|�������Ƃł��̖����V�[���ɒm�炵�߂��B���̌�́A�p�t�E�_�f�B�i���f�B�f�B�j��Bad Boy �G���^�[�e�C�������g�ɓ��t���ʂ����A�m�[�g���A�XB.I.G�̃f�r���[�E�V���O���uParty and Bullshit�v��f�r���[�E�A���o���wReady To Die�x�A�N���C�O�E�}�b�N�wProject: Funk da World�x�A���̂ق��A2�p�b�N�A���X�g�E�{�[�C�Y�A�_�X�E�G�t�F�b�N�X��̏d�v�y�Ȃ̃v���f���[�X����|�����B�}�C���X�ƃC�[�W�[�E���[�E�r�[�̃p�[�g�i�[�E�V�b�v�́A�}�C���X�����[�E�r�[�ɓˑR�d�b�����������Ƃ���n�܂����Ƃ����B������}�C���X�̎w�肷��Z���ɍs���A�������̃��Y���E�p�^�[�������A�}�C���X���C�ɓ������ȁi�uThe Doo-Bop Song�v�A�uTrue Fresh MC�v�Ȃǁj���珇�ɐ���Ɏ��|�����Ă������Ƃ������E�E�E�}�C���X���\�z���Ă����q�b�v�z�b�v�E�A���o���A���̐���Ӑ}�Ȃ�ɑ��Ă̖{�l�̖��m�Ȕ����͎c����Ă��炸�A�i���̓�ƂȂ��Ă���E�E�E |
 |
Herbie Hancock �i�n�[�r�[�E�n���R�b�N�j �uWatermelon Man�v�̑�q�b�g��͉�����������ʃu���[�m�[�g�V�嗬�h�̒��S�A�[�e�B�X�g�ɂ̂��オ�����n���R�b�N�́A�����m1963�`68�N�ɂ̓}�C���X�E�f�C�r�X�E�N�C���e�b�g�̃����o�[�Ƃ��Ċ���B70�N��ȍ~���W���Y�E�t�@���N�E�O���[�v�̃w�b�h�E�n���^�[�Y�A�����̓}�C���X���V�[���ɌĂі߂���݂Ƃ������Ă����A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y�E�O���[�v�AV.S.O.P.�N�C���e�b�g�i�}�C���X�����̃N�C���e�b�g�Ăс��E�F�C���E�V���[�^�[�A�g�j�[�E�E�B���A���X�A�����E�J�[�^�[�j�̏���A�W���Y�ƃq�b�v�z�b�v�̊_�������S�Ɏ�蕥�����uRockit�v�̃q�b�g�wFuture Shock�x�ȂǁA�W���Y�̐V����������b���\���Ă����B�ŐV�A���o���́A2010�N6���Ƀ����[�X���ꂽ�wThe Imagine Project�x�B�V�[���A�s���N�A�W�����E���W�F���h�A�W�F�t�E�x�b�N�A�f�C���E�}�V���[�Y�A�f���b�N�E�g���b�N�X�A�`���J�E�J�[���A�`�[�t�^���Y�A���X�E���{�X�A�W�F�C���X�E�����\���A�R�m�mNo.1�A�A�k�[�V���J�E�V�����J�[���A�e�B�i���E�F���A�C���f�B�A�E�A���[�A�t�A�l�X�A�E�F�C���E�V���[�^�[�A�}�[�J�X�E�~���[�A���I�[�l���E���G�P�Ƃ��������~���[�W�V�������Q�����A�u���a�ƒn���K�͂̐ӔC�v���R���Z�v�g�Ɍf���������ʂ�̃v���W�F�N�g�E�A���o���B |
 |
Bill Laswell �i�r���E���Y�E�F���j �܂��ɋS�˂Ƃ������ɑ��������x�[�V�X�g�A���y�v���f���[�T�[�A�r���E���Y�E�F���̃L�����A�́A70�N��j���[���[�N�̎������y�V�[���ɐG������A�W�����W�I�E�S�����X�L�[�̃��t�g�ɎQ���������Ƃ���X�^�[�g����B�T�E���h�E�G���W�j�A�̃}�[�e�B���E�r�V�Ƃ̋����o�c�̎��僌�[�x�����Z�����C�h�E���R�[�h�𗧂��グ�A�����O�̃A���@���M�����h���y�̃A���o���̔z�����s���B70�N��㔼�́A�S���O�̃f���B�b�h�E�A�����ƌ��������u�j���[���[�N�E�S���O�v�A�}�C�P���E�o�C���z�[���A�t���b�h�E�}�[��ƌ������������I�t�@���N�E�o���h�u�}�e���A���v�A�A�[�g�E�����[�C�A�A���g���E�t�B�A�A�t���b�h�E�t���X��Ƃ́u�S�[���f���E�p���~�m�X�v�ȂǂŊ����B�_�E���^�E���́u�m�[�E�E�F�C���v�V�[���Ő�ΓI�ȑ��݂Ƃ��ČN�Ղ���悤�ɂȂ�B80�N�㏉���ɂ́A�t�@�u�E�t�@�C�u�E�t���f�B�uChange The Beat�v�A�A�t���J�E�o���o�[�^�uTime Zone�v��12�C���`���Z�����C�h���烊���[�X���A�q�b�v�z�b�v�E�V�[���Ƃ̋��������k�߁A83�N�ɂ̓n�[�r�[�E�n���R�b�N�wFuture Shock�x���v���f���[�X���A����̒����ȁuRockit�v�̃q�b�g�ݏo���B84�N�ɂ́A���̃��[�_�[�E�A���o���wBaselines�x�\���A���̌��PIL�wAlbum�x�A��{����wNeo Geo�x�A�~�b�N�E�W���K�[�wShe's The Boss�x�A�I�m�E���[�R�wStarpeace�x�Ȃǎ����I�ȐF�����̍�i�𐔑������삵�Ă���B86�N�Ƀ��X�g�E�C�O�W�b�g�̊������J�n���A�O���C���h�E�R�A�A�m�C�Y�̃T�E���h�E�v���f���[�X�ւƎ��������݂�B90�N��ȍ~�̓A�C�����h�E���R�[�h����AXIOM ���[�x���𗧂��グ�āA�d�q���y��f�g���C�g�E�e�N�m�ւ̊S�����߃t���[�E�W���Y��_�u�Ɨ��߂Ă����A91�N�ɂ́A�W�����E�]�[���A�~�b�N�E�n���X�Ƌ��Ɍ��������y�C���L���[�A�o�P�b�g�w�b�h�A�u���C���AP�t�@���N�̃u�[�c�B�[�E�R�����Y�A�o�[�j�[�E�E�H�[������ƌ��������v���N�V�X�Ƃ������O���[�v�̊������J�n���Ă���B2000�N��ɓ���Ɨ����A���_�[�O���E���h�A�j���X�E�y�b�^�[�E�������F����V����̃A�[�e�B�X�g�̃��~�b�N�X���肪���A�C���h���y�ƃ_�u��Z���������^�u���E�r�[�g�E�T�C�G���X���n�������Ă���B�}�C���X�ƃ��Y�E�F���̒��ړI�ȋ�������͎������Ȃ��������A�G���N�g���b�N�E�}�C���X���c�����}�e���A�������Y�E�F�������~�b�N�X����1999�N�̕ҏW�ՁwPanthalassa�x�́A�wIn A Silent Way�x�����ՂŃJ�b�g����Ă����W�����E�}�N���t�����̃M�^�[�E�\�������@����Ă�����A�}�j�A���X�炸�ɂ͂����Ȃ��_���������R���X�g���N�V�����Ԃ肪�������ꂽ�B |