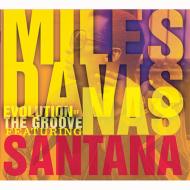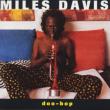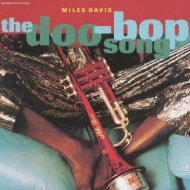��}�C���X ���X�g�E�C���[�Y� ���R�N������ɐu�� �q3�r
Monday, December 13th 2010

- ---�@1985�N���i���j�u���o�[�E�o���h�E�Z�b�V�����v�ɂ����āA�}�C���X�͒��X���i���j�W���[�W�E�f���[�N���O���[�v�ɗU���Ă��܂����A�����ł܂����Ă���ʓI�Ȏ��Ԃ̊��o�z�����G�s�\�[�h�����炩�ɂ���Ă��܂����B1971�N�Ɂu���̃o���h�ɓ���B�܂���œd�b����v�Ɠ`�����܂܉������Ȃ��̏�Ԃ������A���ۂɂ�14�N���1985�N�ɍĂу}�C���X�̓W���[�W�E�f���[�N�Ɋ��U�̓d�b�����Ă��܂��B
�@������A���ي���6�N�ɂ��Ă��l��̎��Ԃ̊��o�Ƃ͈Ⴄ�Ǝv���܂���B
�i���j�u���o�[�E�o���h�E�Z�b�V�����v�E�E�E1985�N10��17������s�Ȃ�ꂽ�Z�b�V�����̒ʏ́B�����f�B�E�z�[���ig,key,vo�j�𒆐S�I�ȃR���{���C�^�[�ɋN�p���A�O�����E�u���X�isax�j�A�[�C���E�M���X�ig,key�j�A�A�_���E�z���c�}���isynth�j�A�j�[���E���[�Z���ikey�j�A���B���X�E�E�B���o�[���ids�j�A�E�F�C���E�����[�C�ikey�j�A�X�e�B�[���E���[�h�iper�j�A�}�C�N�E�X�^�[���ig 10��17���̂݁j�Ƃ����z�w�ōs�Ȃ�ꂽ�ŏ��̃Z�b�V�����ŁuRubberband�v�Ƃ����y�Ȃ��������܂�A���̖����t�����B���B�c�A�[�̂��߂����̒��f�����݁A85�N11���ɃZ�b�V�����͍ĊJ�B���̎��_�Ń����f�B�E�z�[�����Z�b�V�����E�����o�[����O����A�u���o�[�E�o���h�E�Z�b�V�����v�͎�����̏I���B��86�N1���A�}�C���X�́A14�N�O��1971�N�Ɉ�x�O���[�v�Q���������������W���[�W�E�f���[�N�ɍĂѓd�b�����A�V�Ȃƃf���E�e�[�v�̒�o�����߂��B�}�C���X����Q�l�ɑ����Ă����Ƃ����C���P���̃e�[�v���A�����グ��1�Ȃ��uBackyard Ritual�v�ł������B�܂��A���N�����\�ƂȂ��Ă����uRubberband�v�́A�悲�냊���[�X���ꂽ�鉤�̃��[�i�[���̃A���\���W�[�ՁwPerfect Way -The Miles Davis Anthology�x�Ɏ��^����Ă���B - ---�@�����Ƃ����Ԃ������̂ł��傤���H
�@�ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁH�E�E�E�Ƃɂ����A�A�[�e�B�X�g�ł���Ƃ����Ƃ���Ȃ�ł���A�̂́B�Ⴆ�A�f��ḗA�f��������ŎB�e���Ă��Ȃ��Ă��f��ēȂ�ł���ˁB�����Ŏ��ۂɊG��`���Ă��Ȃ��Ă���Ƃł���ƁB�e���r�E�^�����g�݂����ɖ����̂悤�Ƀe���r�ɏo�����ς�Ƃ������o�ł͂Ȃ��킯�ŁE�E�E���ƌ������A�ʂɍ�i�\���Ȃ��Ă��A�[�e�B�X�g�̓A�[�e�B�X�g�ł���Ƃ����B���̒��ŁA���ߐ肾������A���������Ȃ��Ⴂ���Ȃ��݂����Ȏ��Ԃ̍S���Ƃ����̂́A�}�C���X���炢�ɂȂ�Ɨ]���̌_���ɂȂ�����͂Ȃ��Ǝv����ł���B���A���A�邮�炢�̊��o�����ŁB�l��ɂ́A�ǂ����`���N�`����������Ă��邶��Ȃ��ł����i�j�H ���ꂪ�����ǂ����łȂ��Ȃ�Ǝv����ł���B������z�����Ƃ���łȂ���A�l�炪����ł��Ȃ����E�ɐ��܂Ȃ��ƁA���z�̕����ȂŁA������������i�͍��Ȃ��ł��傤�ˁB�N�X���ɗ����Ă����Ƃ���͂������ɂ���B�l�炪����ȂƂ���֍s������o�J�ɂȂ邾���ł��傤���ǁi�j�A�{���ɍ˔\�̂���l�ԂƂ����̂́E�E�E
- ---�@�قځA�\�i�@�ŕ����𑨂��Ă��Ȃ��Ƃ����E�E�E
�@������A�}�C���X�ɉ���Ă��A�u�v���Ԃ�ł��ˁv�u�����͂����V�C�ł��ˁv�̂悤�ȓ���̈��A���b�Ȃ͐��܂�Ȃ��i�j�B�O������b���܂������A�̂̂��Ƃ����X�ɉ����Ă����肵�āA���̂��Ǝ��̂��Ⴄ���v�������Ă����ł���ˁB����͌��ǁA���y�̒��ɐ����Ă���Ƃ������Ƃ�����Ȃ�ł����˂��E�E�E�B�l��̂悤��18���Ɏd�����I���A���Ԃ���ւ���āA���ꂪ�ς���āA�݂����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��āA�����ƃ}�C���X�E�f�C���B�X�Ȃ킯�ł�����B
- ---�@�܂����R�A���y������Ă��邱�Ǝ��̂ɁA�u�d���v�Ƃ����ӎ��͂��قNj����Ȃ��̂ł��傤�ˁB
�@�����Ƃ����ł��傤�ˁB���������Ӗ��ł́A�K�v�̂Ȃ��Ƃ��ɉ����o���Ȃ������B���ꂪ���܂���6�N�߂��ɂȂ����Ƃ������Ƃ�������Ȃ��ł���ˁB�}�C���X�ɂƂ��Ă̕\���̂�����i�Ƃ��Ă̒��قƂ������܂����A���̋t�ɁA�����P���ɋx�݂�����������x��ŁA���ꕜ�A�������������畜�A�����Ƃ������܂����ˁi�j�B
- ---�@���ł̓U���ɂ���Ǝv���܂����A70�N�ォ��80�N�㏉�������A�W���Y�ɂ��Ă��|�b�v��b�N�̃A�[�e�B�X�g�ɂ��Ă��A5�N�ȏ�̃C���^�[�o�����č�i�\����Ƃ����̂́A���Ȃ蒿�������Ƃł���ˁH
�@�悤����ɁA�����Ȃ�6�N�o�����킯�ł͂Ȃ���ł���B�������P�ʂŁu�V���܂��Ȃ̂��ȁH�v�݂����Șb��������ł���B���̊ԂɕҏW�ՂȂ��o����ł����A�����������ςݏd�˂Ƃ��āA�U��Ԃ��Ă݂���2�N�o���A3�N�o���ƁB���S������A�ǂ����ɈڏZ�����݂����ȃj���[�X�����Ȃ��킯�ł�����A������Ƃ��Ă͑҂����Ȃ��Ƃ������B���������N����Ȃ���Ԃ������������A�����������E�E�E������6�N���Ă���Ȃɒ��������Ƃ����̂������ł���ˁB
�@�����l�݂����ȔM�S�ȃ}�C���X�҂́A�u�܂��o�Ȃ��́H�v�Ɠ��X�v���āA�u���N���o�Ȃ������E�E�E���N�͂ǂ��Ȃ낤�H�v�ƂȂ��Ă����킯�ł���B�s���Ɗ��҂Ŗ��N���߂����Ă�����ł��ˁB����͂���ł��̂���������ł����i�j�B�������A���̂Ƃ��͂܂���6�N���Ƃ͎v��Ȃ�����䖝�ł����ł���B�����炠�������1������Č���ꂽ�炳�����ɖ����ł���ˁB- ---�@���̓C���^�[�l�b�g�Ȃł���Ȃ�̏����d����A���Ƃ̂�т�҂��\���邱�Ƃ��ł��܂���ˁB
�@����ƁA�����ƍ��Ƃł́A�}�C���X���܂߂ăX�^�[�̓`����������������ł���B�W�����E���m�����ɏo���Ɣ���₷����ł����A�i���j�W�����E���m�������N�ԉ������Ă��Ȃ��������������B���̊ԁA���x�������┠���ɗ��Ă����肷���ł���B�ł��A�N�������łȂ��B�l�̗F�l�ł��u�����A�����ʂ�ŃW�����E���m���ɉ������v�u���s�w�ł���������v�Ȃ�Ă悭�����Ă������炢�ł�����A�z���g�ɂ��̒��x�B�W�����E���m���������ɑ؍݂��Ă���Ƃ������Ƃ��݂�Ȓm���Ă��Ă��A�T�C����Ⴂ�ɂ��Ƃ��A����������킴�킴�s���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������ł�����ˁB

�i���j�W�����E���m�������N�ԉ������Ă��Ȃ��������������E�E�E������W�����E���m���́u�n�E�X�E�n�Y�o���h�i��Ǝ�v�j�v����B�uStand By Me�v�̃q�b�g��1975�N�̃J���@�[�E�A���o���w���b�N���E���[���x���\���1976�N�A�O�N�ɒa���������j�E�V���[���̗{��ɐ�O�ɂ��邽�߉��y�������x�~�����B���̌�A�ق�5�N�ԃW�����̓n�E�X�E�n�Y�o���h�Ƃɐ�O���Ă������A���̊Ԃ�����ō�Ȋ����͑����Ă���A�ɂ������Ă̓e�[�v�ɘ^�����Ă����B���̎����ɍ��ꂽ�y�Ȃ̃f���E�e�[�v�̐��X��98�N�́w�W�����E���m���E�A���\���W�[�x�̒��Ŕ��\����Ă���B���̊Ԃ�77�N����79�N�ɂ́A���[�R�A�V���[���Ɩ��N�������A�����⋞�s�A����Ƃ̕ʑ�������y���ʼnĂ��߂����Ă����Ƃ����B�����h�����Ă����y���̖����z�e����A��Ƃ������̂悤�ɒʂ��Ă����t�����X�E�x�[�J���[�A�i���X�A���R�[�Ȃǂ䂩��̏ꏊ�́A���ł͊ό������ɂȂ��Ă���B - ---�@�}�X�R�~�����ʌQ���邱�Ƃ��Ȃ��B
�@�S�R���Ȃ������B������Ȃ��ƂɂȂ������ςȑ����i�j�B������A���傫���Ȃ��Ă����ł���A�X�^�[���₻�̓`���݂����Ȃ��̂��B����Ȃ��̂��Ǝv���Ă����O���[�v��~���[�W�V�������`���ɂȂ�B�Ⴆ�A�N�C�[����X���C�E�X�g�[�������̊Ԃɂ���ȂɃf�J�����݂ɂȂ��Ă����A�Ƃ����b�Ɠ����ŁB�܂��ă}�C���X��W�����E���m���̃f�J���Ȃ�悤�Ƃ����̂͂������킯�ł���B���������������͖��m�ɂ͔���܂��B
- ---�@����̗���Ƌ��ɐ_�i������Ă�����ł��ˁB
�@������A���ȂȂ��ƃ_�����Ă����Ƃ��������̂�������܂��ǁi�j�B�����A��قǂ̘b�ɖ߂�ƁA�W�����E���m���Ō����A�wRock 'n' Roll�x���o����̒��قɂ����ẮA�u���N���o�Ȃ������E�E�E�v�Ǝv���Ă����l��������������܂��A��ʓI�ɂ͂��قNjC�ɂ͂���Ă��Ȃ������ł���B�i���j�wDouble Fantasy�x���̂�����Ղ͂���ȂɃv���X����Ă��Ȃ������͂��ł���B�����炭����o�ז����͐����ł��傤�B���ꂪ�A����3�T�Ԍ�Ɏ���ł��琢�E�I�Ƀq�b�g�����킯�ł���ˁB�܂�A�W�����E���m���ł��瓖���͂��̒��x�̑傫���������肷���ł���B
�@�}�C���X��6�N�Ԃ��A�W�����E���m����5�N�Ԃ��A������Ƃ��̂��������ƂɂȂ��Ă����ł����A���A���^�C���ł͂ǂ������ʓI�ɂ́u�����Ă���̂��ȁH�v�Ƃ������x�B���ꂾ�����ɂ���āA�܂��Ɋg�傳��Ă�����Ȃ����ȂƁB�����������ۂƂ����̂́A���ׂĂɌ�����Ǝv���܂����ǂˁB�i���j�r�[�`�E�{�[�C�Y�́wPet Sounds�x�����̊Ԃɂ���Ȃɒ������悤�ɂȂ����A�Ƃ��B

�i���j�r�[�`�E�{�[�C�Y�uPet Sounds�v�E�E�E1966�N�Ƀ����[�X���ꂽ�r�[�`�E�{�[�C�Y�̒ʎZ12���ڂ̃A���o���B���݂ł������b�N�j��Ɏc�閼�ՂƂ��Ĉ����Ă�����̂́A���������͍��܂ł̃r�[�`�E�{�[�C�Y�ɂ������u�T�[�t�B���v�A�u�z�b�g�E���b�h�v�Ƃ��������t���S���o�ꂹ���A�u���C�A���E�E�B���\���̐S���f�I�����悤�ȓ��ȓI�ŕ��G�ȓ��e����A���܂������Ȃ������B���ہA���R�[�h��Б�������s�����F�����Ȃ��̂����āA�����Ƀx�X�g�E�A���o���̃����[�X�ɓ��ݐ��Ă���B�Ȃ��A�r�[�g���Y�̃A���o���wRubber Soul�x����e�����Ė{�A���o����������ƁA��Ƀu���C�A���͖������Ă���B - ---�@����35�̖l�Ȃ����S�������ɂ́A�����O�̏o���A���o���ɂ͂��łɁu���Ձv�̃n���R����������Ɖ�����Ă��܂�������ˁB
�@�����������Ƃ��A�Ђ���Ƃ�������j���d�˂�Ƃ������ƂȂ̂����m��܂��ǂˁB�ǂ������͕ʂɂ��āA�ǂ����Ńv���f���[�T�[��T�C�h�������C�ɂ���悤�ȕ����ɂȂ��Ă����킯�ł���B�����̊Ԃ܂ŒN������Ȃ��ƋC�ɂ��Ă��Ȃ������̂ɁB���ꂪ���y�����̂��ݕ����g�����Ƃ�������̂ł��傤���A�ǂ������̌�Ⴄ�����ɍs���Ă���悤�ȋC�������ł���E�E�E���̌��ʂ̂ЂƂƂ��āACD������Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ȁi�j�B
- ---�@�i�j�u�����ĐX�������v�̂悤�ȂƂ���͑������邩������܂���B�ł��A�̂͂����܂Ńv���f���[�T�[��Q���~���[�W�V�������C�ɂ��Ă��Ȃ�������ł��ˁB
�@�W�Ȃ�������ł���ˁB�r�[�g���Y�̍�i�ł���A�W�����ƃ|�[���ǂ���������Ă���̂��Ȃ�Ęb�ɂ͂Ȃ�Ȃ��i�j�B�ӂ���ō���Ă���Ǝv������ł��܂�������B�W���[�W�E�}�[�e�B���Ƃ����v���f���[�T�[�����邾�Ƃ��A�t�B���E�X�y�N�^�[�Ƃ����l�����邾�Ȃ�āA�����̊Ԃ̘b�ł���B�̂̊���炷��ƁA����ȍׂ������Ƃɍ\���Ă�����قǃq�}�ł͂Ȃ������B���A���^�C���ɂǂ�ǂ�h���I�ȍ�i���o�Ă���킯�ł�����B
�@�W�����E���m���̃X�^�[����`���Ƃ������̂����ɑ傫���Ȃ����̂́A�������Ă���������ł����āA�����ɋy�Ȃ����̂́A�}�C���X�������悤�ɒ��ي��Ƃ������̂�������������傫�����݂ƂȂ����B���A���ʂ������Ƃ��́A�}�C���X�̐g���͕ς��Ȃ���ł����A���Ԃ��猩���g�����ς���Ă����ł���ˁi�j�B�g����3�{���炢�L�тĂ�i�j�B- ---�@����Ƀ}�C���X�́A1991�N�̎���ɂ��A�wOn The Corner�x���w�A�K���^�x�Ȃ��܂��ʂ̐���̐l�����ɂ���čĕ]������͂��߂܂���ˁB
�@�}�C���X�ƃW�����E���m���̍ĕ]���E�Ĕ����ɂ͈Ⴂ������Ǝv���܂��B�}�C���X�̓|�C���g�A�|�C���g�ōĕ]������Ă���B�N���u�n�ƌĂ��悤�Ȑl�������wOn The Corner�x���ĕ]����������������A���̎��̐��オ�܂��Ⴄ�A���o�����ĕ]������B�܂�����Ƃ���ł��wThe Birth of Cool�x�������ƌ����Ă�����A�����ƍ�i���o���o���Ȃ�ł���ˁB���ꂪ�ЂƂɂȂ�ƍĕ]�����[�������g�Ƃ��đ傫���Ȃ��ł����A���܂��o���o���̂܂܂Ȃ̂����Ǝv����ł���B
�@������A�A�R�[�X�e�B�b�N�̃}�C���X�ƃG���N�g���b�N�E�}�C���X���r�ׂ�̂Ƃ��Ȃ莗���悤�Ȃ��̂ŁA��ɕ��f����āA����ɍו�������Ă����ł��ˁB�����A�R�[�X�e�B�b�N��i�ł��wNefertiti�x�A�wThe Birth Of Cool�x�A�wSketches of Spain�x�A�wQuiet Nights�x��������ƁA�Ƃɂ�������������ׂ�����ł���B- ---�@���ꂪ�����}�C���X�̉��y�̖��͂ƌ����܂����B
�@������ו������������قǁA���������猩��Ƒ傫���l���ȂƁB
- ---�@���Ȃ݂ɁA���̒��ٌ���wThe Man With The Horn�x�����悢��o�邼�Ƃ����Ƃ��̐��Ԃ̔����Ƃ����̂́H
�@��������܂�����B����قǐؖ]����Ă����V����Ȃ������ł��傤���A����ł͋������̌������݂����ȂƂ��������܂������ˁi�j�B���}�C���X�I�Ȑl�������炷��ƁA�u�ǂ��܂ŗ����Ԃ�Ă��邩���̖ڂŊm���߂Ă��v�݂����ȂƂ��낪�������ł��傤���A���Ȗʂ��܂߂��l�Ԃ̐F�X�Ȋ��Ҋ����W��Ă����Ǝv����ł���B
- ---�@���ۂɂ��������悤�ȉ����͂�����Ƃ́H
�@�v���Ă��Ȃ������ł��傤�ˁB�l���v���Ă��܂���ł������A���ƌ����ċ�̓I�ɃC���[�W���Ă��������Ȃ������ł����B�܂�A�}�C���X�̎��̉����ǂ߂Ȃ������̂́A���ʓI�Ɍ��J����Ă��A�����ɃN���W�b�g����Ă��郁���o�[�����̓����قƂ�ǒm��Ȃ��킯�Ȃ�ł���B�u�i���j�A���E�t�H�X�^�[�͔��邯�ǁA�i���j�r���E�G���@���X���ĉ��Ȃ́H�v���āi�j�B���ꂪ���Ȃ��݂̊�Ԃꂾ������A����Ȃ�ɓǂ߂���������ł����A�����Ȃ�ƒ����Ă݂Ȃ��Ɣ���Ȃ��Ƃ����̂����ۂ̂Ƃ���ŁA���������Ӗ��Ŋ��Ҋ����ۂ����ɂ����܂�Ƃ����̂͂���܂�����ˁB
�@������A�ŏ��Ɋ�Ԃ�ł���ς�}�C���X�͂������ȂƎv�킹�܂�����ˁB�i���j�}�[�J�X�E�~���[���܂߂ē����܂��S�������̃~���[�W�V�����𑽂��N�p���Ă��܂�����B- ---�@�����̃~���[�W�V�������N�p�������ŁA�wStar People�x�Ńe�I�E�}�Z���ƁA�wDecoy�x�ŃM���E�G���@���X�ƁA����܂Ŗ��Q�d�ƌĂ�Ă����v���f���[�T�[���Ԃ��킯�ł����A�}�C���X�͂����ɑ����̕s���v�f�Ȃǂ������Ȃ������̂ł��傤���H
�@���U�\���E�A�[�e�B�X�g�Ƃ������ƂȂƎv���܂��B�A�[�e�B�X�g�͗₽���Ƃ������{�ł�����B�F��≷��͂���Ȃ�ɂ���ɂ���A�����Ŕނ���S�O�Ȃ���邷�����Ƃ������̂������ł���ˁB
- ---�@����͑O�b�ɂ����������q�̃h���}�[�A���B���X�E�E�B���o�[�����S�O�����ƂȂ��N�r�ɂ����ꌏ�ɂ������ł����ˁB
�@���X�N��w�������Ƃ�����܂����A�ŏI�I�ɂ͂��̕����V�����Ƃ���ɍs���₷����ł��傤�ˁB�l�炪������ׂ�₷���̂��A�v���f���[�T�[�Ƃ������݂ɑ��Ă̕]������Ɉ�Ƃ����Ƃ���Ȃ�ł���B�܂�u�ߑ�]���v���u�ߏ��]���v�����Ȃ��B���傤�ǂ悢�����ł͌���Ȃ���ł���B�r�[�g���Y�ƃW���[�W�E�}�[�e�B���̊W�ɂ������Ă��������A�}�C���X�ƃe�I�ɂ��Ă������B�����������̂Ȃ�ł���A�v���f���[�T�[�Ƃ������݂́B
- ---�@�h���I�ɕ]�����^����ɕ�����鑶�݁B
�@�u�e�I�E�}�Z���͈̑�ȃv���f���[�T�[�ł��v�Ƃ����͓̂��R�����Ȃ�ł����A����ň̑�Ƃ͌ĂׂȂ��A�}�C���X�ȊO�̍�i�������ς�����Ă����ł���B�W���[�W�E�}�[�e�B���������ł��B�����Ȃ��Ă���ƁA�ǂ��܂ł��v���f���[�T�[�{�l�̍˔\�Ȃ̂��A�ƂȂ��Ă���B������A�u�ߑ�v���u�ߏ��v���ł����]���ł��Ȃ���ł���B�~���[�W�V�����ɂ���Ă͂��̃v���f���[�T�[��]������l������A�N�ł��悩�����ƌ����l�������ł���ˁB
- ---�@�X�|�[�c�Ȃǂɂ�����ē�R�[�`�ɑ���]���̓���ƈꏏ�ł���ˁB
�@�i���j���厡����Ă��r��R�[�`�A�݂����Ȃ��̂Łi�j�B�l��ɂ͖��m�ȕ]�������Ȃ���ł���B������A�u�����ꂩ���ďグ�Ă������ȁv�ƂȂ邩�A�u���Ȃ���A�N���R�[�`�ł��L�т����낤�v�ƂȂ邩�i�j�B

�i���j���厡����Ă��r��R�[�`�E�E�E���{�v���싅�E�ō���́u��l�O�r�v�X�g�[���[�Ƃ����A��͂�ǔ����l�R�̉��厡�ƍr�씎�i���v�j�́u��{���Ŗ@�v�����グ���t��W���낤�B���N����̉��̑f�������o���ĕ�Z�̑���c���ƍ��Z�ւ̐i�w��E�߁A���N���ēɐ���ꋐ�l�̑Ō��R�[�`�ɏA�C���A�u�r�쓹��v�ƌĂ�錵�����w���ň�{���Ŗ@�ݏo�����B���c�����͖���̋���ʂ��ɖ�������ӂ��҂������Ƃ��������������A1961�N�̃V�[�Y���E�I�t�A�r��̓��������ɂ����K�̒��ɁB���A�����A����f���A��ԗ��K�ł͍r��̎���ŁA�o�b�g�̑���ɓ��{�����\���A���̑���V�䂩��邵�����������P�̓��X�B��62�N�A38�{�ۑł��L�^���A�u���E�̃z�[���������v�ւ̑����ݏo�����B
�@�b��߂��܂����A�}�C���X�ɂƂ��ăe�I�E�}�Z���́A�]���ł���j������ꏏ�ɂ���Ă��Ă��������ǁA�ŏI�I�ɂ͎����̗͂ō�����Ƃ����v���������R�Ȃ��킯�ł�����A�����Ă��������炢�̑��݂�������ł��傤�ˁA�����ƁB����ƃ}�C���X�́A�Z���t�E�v���f���[�X�݂����Ȃ��Ƃ���肽���Ȃ�����ł��傤�ˁB���邢�͊��S�ɈႤ�l�Ƃ�肽���Ȃ����Ƃ��B����͂���Ӗ��ŗ��l��ւ���悤�Ȃ��ƂƓ����ł�����A�V��������Ɏh�������߂�Ƃ����Ƃ���ł͂������R�Ȃ��Ƃ�������ł͂Ȃ��ł��傤���B- ---�@���������A�ł��邾�������悤�Ɏg���ēs���̂����Ƃ���ŁA�|�C�ƁB
�@�e�I�E�}�Z���A�W���[�W�E�}�[�e�B���A���邢�̓r���E���Y�E�F���ɂ��Ă��A���ꂾ���̑f�ނ��p�ӂ��ꂽ��A�ǂ��ҏW�������Ă����ǂ����̂����ł��Ȃ����낤���Ďv���܂���i�j�B�i���j�uIn A Silent Way�v�Ȃɂ��Ă��A�悭DJ�̐l���������~�b�N�X�������A�T���v�����O�E�\�[�X�Ɏg��������Ă��邶��Ȃ��ł����B���R����Ȃ�ɂ������悭�Ȃ�킯�Ȃ�ł���A�f�ނ��f�ނł�����B
- ---�@�����ŃX�x������A�ނ���厖���i�j�B
�@�i�j�X�x��悤���Ȃ����炢�̑f�ނ�����킯�ł�����A���������ꂪ�v���Ɩ��̕t���v���f���[�T�[�ł���A���̂��炢�͍���ē��R���낤�Ǝv���܂����ˁB���ꂪ�Ђ���Ƃ���Ɓu�ߏ��]���v�Ȃ̂�������Ȃ���ł����B
�@�l��͍ŏ��Ƀe�I�E�}�Z���̎肪�������wIn A Silent Way�x���Ă��邩��A���ꂪ�x�X�g���Ǝv����ł����A������Ƃł��Ⴄ�ҏW�̂��̂��ŏ��ɒ����Ă�����A���������I���W�i���Ƃ��Ă������Ǝv���̂�������Ȃ����E�E�E������A���̕ӂ�Ɋւ��Ă͉i���ɓ�ł��ˁB
�i���j �uIn A Silent Way�v �̊e�탊�~�b�N�X
�@���������Ӗ��ŁA�}�C���X���e�I�E�}�Z����������Ƃ�^���Ɍ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv����ł���B�A�����J�l���悭�]�E���J��Ԃ��Ă���A���̒��x�̕��i���Ǝv���Ă��������Ȃ��ł��傤���ˁi�j�B- ---�@�}�C���X�ɂƂ��ẮA����Ȃ�̕]���ɒl����l�����Ƃ͎v���Ă�������ǁA��l�O�r�ō�i������Ă���悤�Ȉӎ��͂قƂ�ǂȂ������Ƃ������Ƃł���ˁB
�@�Ⴆ�A�s�J�\���u���́A����揤�Ɠ�l�O�r�ł���Ă��܂����v�Ɛ�Ɍ���Ȃ��̂Ɠ����ŁA�A�[�e�B�X�g�̈ӎ��Ƃ��Ă͂܂����肦�Ȃ��ł��傤�ˁB�W�����ƃ��[�R���炢�ł���i�j�B����͂Ȃ��Ȃ��ُ킾�Ǝv���܂����ǁB
�@�ЂƂd�v�Ȃ��Ƃ������A�Ⴆ�A�i���j�I�[�l�b�g�E�R�[���}�����������i���j�A�[�`�[�E�V�F�b�v��������A������60�N��Ƀt���[�E�W���Y�Ə̂���Ă�����i�����ܒ����ƁA���ƕ��ʂ̃W���Y�ɉ߂��Ȃ������肷��Ƃ������Ƃ�����B����́A�l�炪�g�ގ����i�h�����ɂ���@���������A�����������m�C�W�[�ȉ��Ɋ��ꂽ����Ƃ������Ƃł������ł����A�܂�́A�o�N�ω��̒��ŕ��ʂɒ�������悤�ɂȂ��Ă������Ƃ������Ƃł���ˁB
�@���̋t�ɁA�G���N�g���b�N�E�}�C���X�͎����ǂ����ƂɑO�q�ɂȂ��Ă����ł���B�����Ă�Ă����t���[�E�W���Y�Ǝ嗬�h�̍\�}���A�[���N��ȍ~180�x�Ђ�����Ԃ��Ă���ƁA�l�͌��Ă��܂��B������A�wOn The Corner�x�ɂ����w�A�K���^�x�ɂ���A���̕ӂ̍�i�͂��ׂč��̑O�q�Ȃ�ł���B���̎���̉��������Ȃ�����A���̎������Ȃ������ŁA�Ⴆ�A�i���j1973�N11��1���̃x�����������̉��Ȃ́A���炩�ɑO�q�W���Y�Ȃ�ł���B���邢�́A�~�j�}���E�A�[�g�Ƃ������������ނ̂��̂ɋ߂��B���オ���������āA�}�C���X�̉��y�����߂đO�q�ɂȂ��Ă��܂�����ł��B

�i���j1973�N11��1���̃x�����������E�E�E�`���̃W���p���E�c�A�[����5�����A����ɃJ�I�e�B�b�N�ȓd�����i�ރ}�C���X�E�O���[�v�͂��悢��W���Y�O�l�����̋��n�u�A�K�p���v�o���h�ւƐi���𐋂��悤�Ƃ���B1973�N11��1���A�`���̃x�������E�t�B���n�[���j�[�����B�s�[�g�E�R�[�W�[�̃L�����Ղ��M���ɁA�o���h�S�̂ɕY���E�C�ƃq���q���Ƃ����O���[���́uIfe�v�ŃG�N�X�^�V�[���}����B�G���N�g���b�N���ɂ�����}�C���X�E�o���h�̍ō��̃p�t�H�[�}���X�Ɩ������B
�@�����āA�O�q�ɂȂ������䂦�ɁA�A�R�[�X�e�B�b�N���Ƃ��G���N�g���b�N���Ƃ��̋��ڂ��Ȃ��Ȃ�����ł���B�������A������Ă��鑽���̃~���[�W�V�����̃A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y�����wNefertiti�x�̕����O�q�B������G���N�g���b�N�̃m�C�W�[�ȉ��y�����w�p���Q�A�x���wDark Magus�x�̕����͂邩�ɑO�q�Ȃ�ł���ˁB������ׂĂł͂Ȃ���ł����A���̉��y�V�[�����������Ă���Ƃ���́u�ߋ��̃}�C���X�̉��y�v�Ƃ����̂��l�̈ʒu�Â��Ȃ�ł��B�݂�Ȃ��ڎw���Ă�����̂́A�ߋ��ɍ��ꂽ���̂ł���ƁB���邢�̓}�C���X�́A�ߋ��ɖ����̉���n�������ƁB- ---�@���䂦�ɁA���܂��Ƀ}�C���X�͑O�q�ƁB
�@�Ƃ͌����A�u����ł����y�͉i�����v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�}�C���X�̉��y�����X�����Ă����������̗v�f�̒��ŁA����ɂ���Ăǂ�ǂ�\�ʉ����镔���������Ă����B���ł͂��镔���̑S�e�͂قڌ����Ă��āA�wOn The Corner�x�����ʂɒ������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��O�q���Ƃ������ƂȂ�ł���B����́A60�N��ɃI�[�l�b�g�E�R�[���}�����i���j�W�����E�R���g���[�����O�q�ƌĂ�Ă������Ƃ����O�q�ȂƎv���B
�@���y�I�ɑO�q�ł���Ɠ����ɁA�wNefertiti�x���wSketches of Spain�x�Ȃ́A���@�_�Ƃ��Ă��O�q���Ǝv����ł���ˁB����������������܂��A�}�C���X�̉��y�̑N�x�͎���ƂƂ��ɑ����Ă��銴���������ł��B���ꂪ�B�ꖳ��ł���ؖ����ȂƁB�O�q�Ƃ������t�̈Ӗ����̂��F�X���邩�Ǝv���܂����A�����Ƃ��Ă͂����������������܂��B- ---�@�N��ǂ����ƂɑN�x�������Ă���Ƃ����̂́A�o�N�ω��̒��ł͂Ȃ��Ȃ����肦�Ȃ����Ƃł���ˁB
�@�J��Ԃ��������Ƃɂ���ă}�C���X�̉��y�ł��������ɂƂ��Ă͕��ʂɒ������Ă����ł����A���̉��y�V�[���Ƃ����Ƃ���Ř��ՓI�Ɍ����ꍇ�A�wOn The Corner�x�̂悤�ȃT�E���h�Ƃ����̂͑��ɂȂ��͂��Ȃ�ł���B�ꎞ�I�ɗ��s��������������܂������A�����܂ň����̈���o�Ă��Ȃ������B�q�b�v�z�b�v�ł������ł����A����オ�肪��x�����������Ƃ��Ɏc�������͉̂����Ƃ����ƁA���ǂ͂�����������ꂽ����Ƃ���ȑO���炠���wOn The Corner�x�̂悤�ȍ�i�Ȃ�ł���ˁB�I���W�i���Ƃ��Ă̋��x�Ƒϐk�\�������Ȃ�����i�Ƃ������Ƃł��B
�@���A���^�C���Œ����Ċ������V�����ƁA50�N�o���Ă��璮���Ċ������V�����Ƃł́A�ǂ������V�������H �ƂȂ����͊ԈႢ�Ȃ���҂��Ǝv����ł���ˁB�����V�������Ă����i�j�B- ---�@��ɐV�������X�V����Ă����A���̂������ł���ˁB
�@�܂��A����𑼂Ƃ̍˔\�̈Ⴂ�ƌ����Ă��܂��A�g���W���Ȃ���ł��傤����ǁA�����b�A�����������Ƃł���ˁi�j�B�i���j�}�n���B�V���k�E�I�[�P�X�g����E�F�U�[�E���|�[�g�݂����ȁu�}�C���X�E�t�@�~���[�v�ƍ������r�ׂĂ݂Ă��A�t�@�~���[�̍�i�͂���ς菬�����Ⴍ��������B���̍��ł���ˁB�}�C���X�̉��y����h���������̂́A�}�C���X�قǂł͂Ȃ��ɂ���A�����ɔ䌨���邮�炢�̂��̂Ƃ��đ����Ă���Ƃ����̂������Ƃ��Ă͂���ׂ��Ȃ�ł����A�ǂ����Œu������ɂ���Ă���B�����̍�i���������ɂ́A�������ߋ��Ƀ��Z�b�g���Ȃ��ƔM���ł��Ȃ���ł���B���A2010�N�̐�����Ԃ̒��Œ������y�Ƃ��āA�}�C���X�ɂ͔����ł��܂����A�E�F�U�[�E���|�[�g��^�[���E�g�D�E�t�H�[�G���@�[�Ȃ͖��炩�Ɏ���x��ł�����i�j�B
- ---�@�ǂ�ȍ�i�ɂ���A�����i�����̑N�x���L�[�v���邱�Ǝ��̂Ȃ��Ȃ�����Ǝv���܂��B
�@���ǁA�N���u�E�W���Y���}�C���X�h�����ЂɊ����Ȃ�����ŏI�I�Ɏ�荞�߂Ȃ������̂͂����ȂƎv���܂��B�R���g���[���܂ł͂������ł���B�}�C���X���݂̃g���r���[�g��������T���v�����O�������̂������肪���Ƃ��Ƃ������ɑς��Ȃ����R�Ƃ����̂��A����ς肻���ɂ���Ǝv����ł���B�܂�A���p�ł��Ȃ����y�Ƃ������E�E�E
- ---�@��ɉ��߂��X�V����Ă����Ƃ������Ƃ������āA�N���u�E�W���Y�I�ȕ����̒��́u�ÓT�v�Ƃ��Ă܂�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��H
�@���邢�́A�T���v�����O�̂悤�Ȗ����̋Z�p������}�C���X�͎�����Ă��������߂ɁA���e��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂�������܂����ˁB���オ�����܂ł��āA�l������͂̉��y���Ŏ������炳��āA���̉��y�I�ɂ���@�I�ɂ��V�����Ƃ������Ƃ��悤�₭�I�ɂȂ����킯�ł�����B��������������������t�͂Ȃ�������ł����A�v�f�Ƃ��Ă͂܂������wOn The Corner�x�̓T���v�����O��~���[�W�b�N�ł���A�wIn A Silent Way�x�̓A���r�G���g�B��قnj������u�ڎw���Ă������͉̂ߋ��ɂ���v�Ƃ����ЂƂ̍D�Ⴞ�Ǝv����ł���B�l�炪�u���̐悱��ȉ��y�����������v�u���������T�E���h���o�Ă���v�Ǝv���Ă��邷�ׂĂ��}�C���X�̍�i�̒��ɂ����āA�C�t���Ă��Ȃ����������Ŏ��͂��łɒʂ�߂��Ă����\��������܂���ˁi�j�B
�@�}�C���X�̉��y���Ă��ĖO���Ȃ��̂́A���������Ƃ���Ȃ�ł��B����ɁA�}�C���X�Ƒ��̃~���[�W�V�����̈Ⴂ�Ƃ����̂��܂��ɂ����Ȃ̂��ȂƎv����ł���B����ɂ��Ă���ׂ����ׂ�قǔ��R�Ƃ����\�������o�Ă��Ȃ���ł����i�j�A�����ĂЂƂ��ƂŌ����u�n���͂̈Ⴂ�v�ƂȂ��ł��傤�ˁB
�@���ǁA�}�C���X�ɂ��Ď����Ă������������ŏ����Ă��A�����ǂ�ł���ɓ䂪�[�܂�P�[�X�������킯�Łi�j�B- ---�@�l���܂��ɂ��̃^�C�v�ł��i�j�B
�@���ꂪ�}�C���X�Ȃ�ł���ˁB�V�������Ă�ꂽ�Ƃ��Ă��A����ɂ���ė������[�܂邱�Ƃ͂Ȃ��i�j�B
- ---�@�i�j���j�I�Ȏ����͔����Ă��A���ꂪ���ړ���𖾂��錮�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��B
�@�����Ɖ��y�Ƃ̋����ł���ˁB�𖾂��悤�Ƃ��邱�Ǝ��̊Ԉ���Ă���̂�������Ȃ���ł����i�j�B
- ---�@�������Ȃ���A���ꂱ�����}�C���X�Ƃ́u�Y��v�Ƃ������Ƃł���ˁB�ӔN�ɂ����ẮA���Ƀt�����X�Ɠ��{���悭�}�C���X�Ɓu�Y��āv�����Ƃ������Ƃł����B
�@�t�����X�͂���ς�M�͂ł��傤�ˁA���̏ے��Ƃ��ẮB����Ɓu�ĉ�Z�b�V�����v�̕���ɂȂ����Ƃ������ƁB���ꂩ��}�C���X���g�A�t�����X���D���������Ƃ������Ƃł��傤�B
- ---�@���{�͂܂��قȂ�u�Y��v���Ƃ������A�������A�t�����X�Ƃ͐����̕t�������Ƃ����������ł��ˁB
�@�i���j�����ł���ˁB�����x�̈Ⴂ�Ƃ��������̈Ⴂ�Ƃ������E�E�E�}�C���X�����ł͂Ȃ��āA�����������̂������ۂ̓y��̈Ⴂ�ł���ˁB
 �鉤�A�����̊ԂɁB�}�C���X�̊e����CM�ƍL���B�����莞�v���ɁA�O�y�Ē��uVAN�v�ATDK�J�Z�b�g�e�[�v�uSR60�v�A�A�[�X�g���E�{���[�W���i�L���j�AHonda�X�N�[�^�[
�鉤�A�����̊ԂɁB�}�C���X�̊e����CM�ƍL���B�����莞�v���ɁA�O�y�Ē��uVAN�v�ATDK�J�Z�b�g�e�[�v�uSR60�v�A�A�[�X�g���E�{���[�W���i�L���j�AHonda�X�N�[�^�[
�@�܂��ǂ���ɂ���A���������u�Y��v���܂߂āA�����ƃ}�C���X�ƈꏏ�ɐl�������̂��߂�킯�Ȃ�ł���i�j�B���̂��̂��݂������Ƒ傫������ɂ́A����ς�m�邱�ƂȂ킯�ŁB���y�Ɋւ��Č����A�Ƃɂ����������Ƃł���ˁB�A�[�e�B�X�g�ɂ���Ă͂���ŐF��ꍇ�������ł����A�Ƃ��낪�z�����m�́A���Ƀ}�C���X�̏ꍇ�͒m��Βm��قǑ傫���Ȃ�B���̑傫���Ȃ��Ă��������ɂ͓�����邵�A���̂ЂƖ{�l�ɂ͒������Ă��Ȃ��T�E���h�����邵�B�C�t���Ȃ������ɂǂ�ǂ�]���Ƃ����������������Ă�����ł���ˁB
�@������A�Ō��10�N�A15�N��������Ƃ����͓̂��ɓ䂪������ł���B�܂��]������Ă��Ȃ��킯�ł�����B�����̕]���͂���Ă��Ă��A���ꂪ�蒅���Ă��Ȃ��B�]�����Ă���l�Ɂu�{���ɂ����v���Ă�H�v���Đu���Ă��A�ǂ������M�Ȃ����ȕ]���Łi�j�B- ---�@���̐���]�����蒅���邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��l���ɂ����悤�ȁE�E�E
�@���ǂ́A�l�l�̃}�C���X�̂��̂��ݕ�����ȂƎv���܂��B�l�݂����Ȑl������A������̎��ゾ���������Ƃ��̂��ސl������B�Ђ���Ƃ����炻��͓����Ȃ��ƂȂ̂�������܂��B�}�C���X�̉��y�ɂ���A�s�J�\�̊G�ɂ���A�t�F���[�j�̉f��ɂ���A�ŏI�I�ɂ͎�̓��̒��ɕ`�������̂ł����Ȃ���ł���B�����������ɓ��̒��ɑ傫���`����悤�ȕ���������o���Ă����l�ɑ��āA�l��͂���������A���Ԃ��₵���肷��킯�ŁA���܂菬�������̂ōׁX���߂�K�v���Ȃ��悤�ȋC�������ł���i�j�B���̂��Ƃ������Ă���Ă���̂��A�}�C���X�̉��y�ł͂Ȃ����ȂƁB
- ---�@�Ȃɂ��A����������ɉ��X�Ƌc�_�ł���Ƃ��낪�}�C���X�̂������Ȃ̂ł͂Ȃ����ȂƁi�j�B
�@��̂��ƂȂ�2���Ԉȏ���M�S�ɂ���ׂ��Ă���킯�ł�����ˁi�j�B���Ƃ́A�����Â������Ȃ��Ƃ����_�B�r�W���A���ɂ����Ă��B70�N��̃G���N�g���b�N���ɒ��Ă��镞�͂Ƃ��Ɋ��V�����肷���ł����i�j�A�܂������Â����������Ȃ��̂́A����ς肷�������݊����ȂƁB����ȑO�̃X�[�c���ɂ��Ă����l�Ɏ�������������Ȃ���ł���B
- ---�@�ǂ̎������l�Ƀq�b�v�Ȋ���������܂���ˁB
�@�}�C���X�E�f�C���B�X�Ƃ������݂𒆐S�ɂ��āA���̎���Ɏ��オ���邩�̂悤�ŁB�ނ���A�p�u���b�N�E�G�l�~�[�̕����Â�����������Ƃ����i�j�B
 70�N��}�C���X�̃t�@�b�V�����B������A75�N�g���o�h�[���A75�N���c��`�A73�N�R�y���n�[�Q��
70�N��}�C���X�̃t�@�b�V�����B������A75�N�g���o�h�[���A75�N���c��`�A73�N�R�y���n�[�Q��
�@�悭�����邱�Ƃł����A�u�}�C���X�E�f�C���B�X�v�Ƃ����W������������Ƃ������Ƃł���ˁB���y�I�ɂ��r�W���A���I�ɂ��B����͖{�l�̐����ɊW�Ȃ����R�Ƃ����ł���B�������������ł͍���̖{�����n�_�������Ă����킯�ł͂Ȃ��A����́u�̏d��40�L����������Ă����Ƃ����v�Ƃ����I�����ɂ����炩�Ȃ킯�ŁB�u�}�C���X������ł����y�͉i���ł���v�݂����ȃV���ł��Ȃ�ł��������Ƃ͂ł�����ł����A�ǂ��I��点�邩��������ł���ˁB����ɋ�J���܂����B- ---�@���̒��O�ɂ��i���j�N���[�N�E�e���[�ɂ��u�Ō�̉�b�v�i���ۂɂ͎o�h���V�[����Ă̓d�b�`���j�̏q����������Ă��܂����B
�@����ǂ��A�l�ɂ̓N���[�N�E�e���[���N�̂��Ƃ�b���Ă���̂��s���Ƃ��Ȃ�������ł���B�܂�A�}�C���X�E�f�C���B�X���l�Ԃł͂Ȃ����o������܂��B�ɒ[�Ɍ������{�b�g�݂����ȁB����̓}�C�P���E�W���N�\���ɂ������邱�ƂŁA�}�C�P�����S���Ȃ����Ƃ��ɂ݂�Ȃ��߂��݂ɕ����ł����A����͂������Ⴊ��ꂽ�Ƃ��̂悤�Ȕ߂��ݕ��ɖl�͌�������ł��ˁB���̐l���S���Ȃ����Ƃ����߂��݂͂����ƌォ������Ƃ��ĕ����Ă���Ƃ͎v����ł����E�E�E�܂����ꂪ�A�C�h���A�A�C�R���̎��Ƃ������̂Ȃ�ł��傤���ǁB������A�N���[�N�E�e���[�̍Ō�̉�b�̃G�s�\�[�h�ɂ��Ă��A�}�C���X�����łɎ��������Ƃ͈قȂ��Ԃɑ��݂�����̂Ƃ��Ċ����Ă��܂�����ł���ˁB�܂������ʂ̎����̐����̂Ƃ������B������A�}�C���X���S���Ȃ����Ƃ��ɂ��قǔ߂����Ȃ������̂́A�����������ƂȂ̂��ȂƁB
- ---�@����̒��̃q�[���[�����𐋂����Ƃ������o�ł��傤���H
�@���̂��Ă��Ȃ����Ƃ������E�E�E���ƌ����āA�J��Ԃ��܂����A�u����ł����y�͉i�����v�Ȃ�Ă������Ƃ͎v���Ă��Ȃ���ł���B�����̐^���ł͂���Ǝv���܂����B���̓I�Ȓɂ݂�߂��݂Ƃ����l�ԓI�Ȋ����Ȃ����Ƃ������A�Ⴆ�Β����v���~�܂����悤�Ȋ����E�E�E������A�܂������o���Ă��s���R�ł͂Ȃ��悤�ȁA�������������ł���������ł���ˁB
- ---�@����ł́A�Ō�Ƀ}�C���X�E�f�C���B�X�̑��]���E�E�E�Ƃ��������Ƃ���Ȃ̂ł����A���R����̂�������ʂ��Č����Ă��������͑��X����Ȃ�����A��͂�}�C���X�͉��y���A�l�Ԑ����ׂĂ��Ђ�����߂āA�����l�̒��ł͂܂��܂����R�Ƃ������l�Ƃ����C���[�W���@���܂���i�j�B
�@���y���ė�����[�߂�B���������{��ǂ�ł܂�������[�߂�B�l���g�͂���ɐ^���ɔ��肽���Ƃ��v���ŁA���������{�������Ă����ł����A�����������Ƃ������قǓ䂪������ꍇ���������ł́A�t�ɉ����Ȃ��l������̂͊m���ł��B�������āA�䂪����ĂԂƂ������A�c��ޕ���������B�}�C���X�͂��������̂肵�낪���̂������傫����ł���B�������A���ꂪ�傫�����ǂ����́A������̃C�}�W�l�C�V�����ɋ���Ƃ���ȂƎv���܂��B
�@���ǁA�}�C���X�̉��y�Ƃ����̂͒����������Ӗ��őI�ԁB���m�Ɍ����ƁA������ɑz���́A�܂��͑n���͂����߂�B�ْ�������ɗ^�������𓊂�������A�Ƃ����̂��}�C���X�̉��y�Ȃ�ł���ˁB�c�����A���o����10�����x�ł���Θb�͊ȒP�Ȃ�ł����A�Ȃɂ����̐��͑����ł�����B��l�ɃW���Y�E�~���[�W�V�����̃A���o���Ƃ����̂͑������̂Ȃ�ł����A�}�C���X�̂悤�ɂقڃA���o�����ɑ傫���ω������Ă���~���[�W�V�����Ƃ����̂͑��ɂ��Ȃ��B������A������Ƃ��đ̌�����ΐقǁA�]�v�ɂ��炪���Ă��܂���ł���ˁB�e�[�}�p�[�N�̂���ɂ��̒��ɂ�����H�ɓ������悤�Ȃ��̂ŁA���ɂ�������E�o�����Ƃ��Ă��܂��Ⴄ�g���b�N���҂��Ă���A�݂����Ȃ��Ƃ�����킯�Ȃ�ł���i�j�B
�@�}�C���X���ė�����[�߂�Ƃ������Ƃ́A���ۂɗ����͐[�܂��Ă����ł����A���ꂪ�ǂ��Ɍ������Ă��āA�ǂ̒��x�͈̗̔͂����Ȃ̂��Ƃ������Ƃ͎����ł͔���Ȃ���ł��ˁB�ŁA�������܂��N���d�˂Ă����B�����A���o���ł��A������J��Ԃ��������Ƃɂ���ď�����������悤�ɒ���������A�����Ă���i�F���ς�����肷��킯�ł���ˁB�܂肻�ꂪ�A�}�C���X�̉��y���O���Ȃ��Ƃ������Ȃ��Ǝv����ł���B
 |
|
1971�N�A�R�����r�A�E�X�^�W�I�O�ɂāB�e�I�E�}�Z���ƃ}�C���X
|
|
�u���X�g�E�C���[�Y�v��20��
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
�y�Ċ��u�K�z �u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v ���R�N������ɐu��
-
�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v ���R�N������ɐu��
�s��ȃX�P�[���Ɩ��x�́u�鉤�E���d���G���v�B���̓�������������w�G���N�g���b�N�E�}�C���X 1972-1975�x�����ꂽ�}�C���X�����̑��l�ҁA���R�N������ɂ��b���f���܂����E�E�E
���̑��̊֘A�L��
-
�y���W�z �}�C���X�E�f�C���B�X �wTUTU�x �i2011�N5���j
�}�C���X�E�f�C���B�X��1986�N���[�i�[�ڐБ�1�e��i�wTUTU�x���A�{�҃��}�X�^�[�ɓ��N7���̃j�[�X����������lj�����2���g���ؔՂɂēo��B��������̎���}�[�J�X�́uTUTU�lj����C���v�������E�E�E�E�E�E
-
�y���W�z �d���鉤�w�� �u�r�b�`�F�Y�v�ɂ��� �i2010�N7���j
�wBitches Brew�x 40���N�L�O�������K�V�[�Ղ������B�����\���C������CD�A�����\���C��DVD����lj��������S���Y����̂䂾���������B�d���鉤�w�ƁwBitches Brew�x�ɂ��ĐF�X�ƁE�E�E
-
�e�n���E �����O�E�C���^�r���[ �i2008�N6���j
2008�N6���ɍs��ꂽ�e�n���E���C���^�r���[�̑S7�S�ŁB�_�u�E�Z�N�X�e�b�g�A�}�C���X�A�t�@�b�V�����A���̌q�����������x�l�@���Ă݂�ƁE�E�E�E�E�E
���~�E�� �I�����C�� �u�V���Ƃȑ����v�ŘA�ڒ��� �u�W���Y��Փ���v
|

-
���R�N�� �i�Ȃ���� �₷���j
�@1952�N���{�o�g�B���y�]�_�ƁB�W���Y�G���u�X�C���O�W���[�i���v�ҕҏW���߂���A���M�����ɓ���B����Ɂw�}�C���X�E�f�B���B�X �̎���x�A�w�}�C���X vs �R���g���[���x�A�w�}�C���X�̉āA1969�x�A�w�}�C���X���I�x�������B�Ɂw�}�C���X�E�f�B���B�X�����`�x������B�܂��A���b�N�ɂ����w���[���A�w�r�[�g���Y�ƃ{�u�E�f�B�����x�A�w���ƗE�C�̃��b�N50�x�A�w�f�B������!!�x��������B
- �֘A�T�C�g�i�O���T�C�g�j
- �֘A���W�iHMV�T�C�g���j
�{�����ɓo�ꂷ���v�l���ɂ��� |
 |
George Duke �i�W���[�W�E�f���[�N�j �W���[�W�E�f���[�N�ɂƂ��ăn�C�X�N�[�����ォ�瓲��̑��݂������}�C���X�B����ȃA�C�h�����璼�X�Ɂu�I���̃o���h�ɓ���v�Ƃ����O���[�v�����̓d�b���������̂�1971�N�B���g�́A�L���m���{�[���E�A�_���C�A�N�C���V�[�E�W���[���Y�A�t�����N�E�U�b�p�A�r���[�E�R�u�n����̃O���[�v�ɎQ�����A�܂��A�wSolus �iThe Inner Source�j�x�A�wThe Inner Source�x�Ƃ���2���̃��[�_�[�E�A���o����MPS���甭�\���A�܂��ɃL�����A���O���ɏ��A�S�Z�̂Ƃ��ɐL�ѐ���ɂ����������B�����������A�鉤�́u���Ƃœd�b����v�ƌ���������14�N�̍Ό��͔��ɂ����ꂽ�B�Ƃ͌������̊ԁA77�N��Epic/CBS�ɈڐЂ��āwFrom Me To You�x�A�wReach For It�x�A79�N�ɂ́wBrazilian Love Affair�x�Ƃ����������O�̃t�@���L�[�ȃv���C���܂���̃f�B�X�R�^AOR�u�[���ƌ����ɃV���N���������샊�[�_�[�E�A���o�������X�ɔ��\���邱�ƂŁA�W���[�W�E�f���[�N���g�̃L�����A�͐Ⓒ�����}�����ƌ����Ă悢���낤�B���̌���Â�����̖��F�ł���X�^�����[�E�N���[�N�Ƃ̃��j�b�g���N���[�N�E�f���[�N�E�v���W�F�N�g�ȂǂŃR���X�^���g�ɃA���o���\���Ă���Ƃ���ցA�܂����Ă����̑O�Ԃ���Ȃ��}�C���X����A�����B86�N�́uTutu�v�Z�b�V�����p�ɐV�Ȃƃf���E�e�[�v�̒�o�����߂���B���ǂ́A���v3�Ȃ��������낵�A���̂�����1�ȁuBackyard Ritual�v���̗p���ꂽ�B |
 |
Al Foster �i�A���E�t�H�X�^�[�j 1972�N����}�C���X�E�O���[�v�ɎQ�������h�����t�҃A���E�t�H�X�^�[�B�wOn The Corner�x�̐��E�����C���Ŏ��������悤�Ƃ����wMiles Davis In Concert�x�ȍ~�A�wAgharta�x�A�wPangaea�x�Ɏ���܂ł̃X�e�[�W�ŁA�B�ꖳ��̃n�C�n�b�g�A�ŁA�V���o���J�����݂����B1981�N�A�}�C���X�̕��A�Ƌ��Ƀt�H�X�^�[���J���o�b�N�B���N�̓��{�����ɂ����s���A���̌�ӔN�ɋy�Ԃ܂Ń}�C���X��i�̃��Y���ݏo�����B�����炭�}�C���X���A�Z�p�ʂɂ����Ă��l�ԓI�Ȗʂɂ����Ă��ł��M�����Ă����~���[�W�V�����̂ЂƂ肾���ƌ����邾�낤�B |
 | Bill Evans �i�r���E�G���@���X�j �wThe Man With The Horn�x�A�N�������̃N���W�b�g�����āu�N����!?�v�ƃc�b�R�~����ꂽ�͂����낤�B�������uWaltz For Debby�v�̂��̃s�A�j�X�g�Ƃ͓��������̕ʐl�ŁA�����W���Ȃ��B������̃r���E�G���@���X�́A�C���m�C�B�o�g�̃e�i�[�^�\�v���m�E�T�b�N�X�t�ҁB���̃r���E�G���@���X������A�}�[�J�X�E�~���[�A�}�C�N�E�X�^�[���Ƃ��������̓����قږ��������������N�p�����}�C���X�����������A�鉤�Ɉޏk���邱�ƂȂ���炢�t���Ă������ނ�̃K�b�c���������B�u�Ⴂ�Ƃ������Ƃ͂��ꂾ���ŕ���Ȃ̂��v�Ƃ͒�����ȏ�Ƀ}�C���X���������������Ƃ������̂�������Ȃ��B�܂��A�r���́A82�N�ɃW�����E�}�N���t�����̃}�n���B�V���k�E�I�[�P�X�g���ɎQ�����A�˔\�������]�����ꂽ��ށB1989�N�ɏ����[�_�[��wSummertime�x�\���Ĉȍ~�A�����ɃA���o���𐧍삵�A90�N��̃t���[�W�����E���������鑶�݂ƂȂ����B |
 |
Marcus Miller �i�}�[�J�X�E�~���[�j �W���Y�^�t���[�W�����݂̂łȂ��AR&B�A�t�@���N�Ƃ������C�f�B�I����p���Ȃ���A�X���b�v�A�^�b�s���O�t�@�Ȃǂ���g���ĕ\���͖L���ȃT�E���h��e���o������ō��̃x�[�V�X�g�ɂ��āA�v���f���[�T�[�A��ȁE�ҋȉƂƂ��Ă���}�ȍ˔\���݂���}�[�J�X�E�~���[�́A1981�N�㊥20�̂Ƃ��ɁA�}�C���X�̕��A��ƂȂ�wThe Man With The Horn�x�Ƀx�[�V�X�g�Ƃ��Ĕ��F�����B���̌�́wTutu�x�ɂ����Ă��A�x�[�X�͂��Ƃ��}�C���X�̃g�����y�b�g�ȊO�̊y����قƂ�ǒS���A����ɂ͊y�Ȓ���v���f���[�X�Ɏ���܂ŁA�ӔN�̒鉤�̊����̓}�[�J�X�Ȃ��ł͍l�����Ȃ��قǑS���̐M�������Ă����B |
 |
Vince Wilburn �i���B���X�E�E�B���o�[���j 1985�N�ɔ��\���ꂽ�wYou're Under Arrest�x�̘^���i84�N12���j���Ō�Ƀo���h�𗣂ꂽ�A���E�t�H�X�^�[�̌�C�Ƃ��āA�}�C���X�̉��ł����郔�B���X�E�E�B���o�[�����V�C�h���}�[�Ƃ��ēo�p���ꂽ�BCBS����Ō�̐���A���o���ƂȂ����wAura�x�i84�N�^���j�ł́A�f���}�[�N�ɕ����A�W�����E�}�N���t�����ig�j�A�_�����E�W���[���Y�ib�j�ɉ����A�j�[���X�E�y�f���Z���ib�j�猻�n�̋����~���[�W�V�����������ẴZ�b�V�������s�����B�{�C���^�r���[���ɂ�����悤�ɁA�u���Y�����x���v�Ƃ������R�ʼn��ق������n���ꂽ���B���X�̕�e�A�܂�}�C���X�̎o���}�C���X�Ɂu�N�r�ɂ���Ȃ�A���߂Ēn���̃V�J�S�������I���Ă���ɂ��Ăق����v�ƍ��肵������������Ă��炦�Ȃ������Ƃ����B���ꂾ���}�C���X�́A�h���}�[�ɋ������������݂��Ă����B |
 |
Ornette Coleman �i�I�[�l�b�g�E�R�[���}���j 1959�N�AAtlantic ���R�[�h�ɈڐЂ��A�w�W���Y����ׂ����́x�A�w�t���[�E�W���Y�x�Ƃ������A�����̃r�[�o�b�v�ɂ�����n�[���j�[�̃��[����j�������I�ȏG��\�B�I�[�l�b�g�E�R�[���}�������ݏo�����V�������y�́A��Ɏ^�ۗ��_�̓I�ƂȂ�A�~���[�W�V�����̊Ԃł��A���_���E�W���Y�E�J���e�b�g�̃����o�[�������獂���]����������A�}�C���X��}�b�N�X�E���[�`����͔ᔻ���ꂽ�B�������A�I�[�l�b�g�̐�i���͂Ƃǂ܂邱�ƂȂ��A�u�t���[�E�W���Y�v�Ƃ����V���ȗ���ݏo���Ă������B1960�N��ɂ́A�g�����y�b�g�⃔�@�C�I�������}�X�^�[���A���g�̃��[�_�[�E�A���o���Ő��ʂ��I�B65�N�ɂ�Blue Note����w�S�[���f���E�T�[�N���̃I�[�l�b�g�E�R�[���}���x�\�B�I�[�l�b�g�̑��ʐ��Ɛ�捂ȃt���[�̐��_�������Ɍ�����������i�Ƃ��čō�����ɋ�����t�@���������B70�N��㔼����́A�G���N�g���b�N�E�W���Y�̗̈�ɂ������߁A�n�[���j�[�ƃ����f�B�̗Z�����߂������u�n�[�����f�B�N�X���_�v�i����j�Ƃ����Ǝ��̗��_���l�āB88�N�ɂ́A�I�[�l�b�g������v���C���E�^�C���ɂ��A�M�^�[2�{�A�x�[�X2�{�A�h����2�Z�b�g�̃_�u���E���Y���E�Z�N�V�������J��o�������E�wVirgin Beauty�x�����\����A������A���@���M�����h���_���|�b�v�Ŕ\�V�C�ȃ����f�B�ɂ�180�x�Ђ�����Ԃ����B |
 |
Archie Shepp �i�A�[�`�[�E�V�F�b�v�j ���͓I�ȃA�t���J���E�A�����J�������ƂƂ��Ă����̖����Ƃǂ납�����e�i�[�E�T�b�N�X�t�҃A�[�`�[�E�V�F�b�v�́A��ȉƁA���l�A����ƂƂ��đ����ʂɓn��˔\�������B�ނ̍�i�͂�������A���l�ł��邱�Ƃ̃t���X�g���[�V������{���X��悤�ȃu���E�ŃX�g���[�g�ɕ\�����A�u60�N��̓��m�v�u�{���Ⴋ�e�i�[�v�Ə̂���邱�Ƃ������B1965�N�O��ɂ́AImpulse!���瓖���̃t���[�E�W���Y�E���[�������g�Ɍĉ������wFour For Trane�x�i�W�����E�R���g���[���̃v���f���[�X�j�A�wFire Music�x�A�wMama Too Tight�x�Ƃ������A���o���A����ɂ́A71�N���e���̉��P�����߂ĖI�N�������l���l�ɑ��A���l�B�����e�ɂ������A43�l�̎��҂��o�����u�A�b�e�B�J�Y�����\���v�ɐG�����ꐧ�삳�ꂽ�wAttica Blues�x����\��Ƃ��ċ������邾�낤�B�܂��A�`���I�ȃu���[�X��A�t���J��A�v�z�ɍ���������i�wBlase�x�A�wYasmina, A Black Woman�x�Ȃǂ���BYG���甭�\���Ă���B�ߔN�́AVenus ���R�[�h����A���g�̃��H�[�J�����������Ì��ȃo���[�h�E�A���o���������������[�X���Ă���B |
 |
John Coltrane �i�W�����E�R���g���[���j 1955�N�Ƀ}�C���X�E�f�C���B�X�̃O���[�v�ɓ��c�B����܂łقƂ�ǖ������������A��������������ɂ��̖��O���m����悤�ɂȂ�A�}�C���X�E�O���[�v�ȊO�ɂ����郌�R�[�f�B���O�̋@��������Ȃ����B���Ȃ݂ɗ��҂Ƃ���1926�N���܂�ł���B1957�N�Ɉ�U�}�C���X�E�O���[�v��ޒc���A�Z���j�A�X�E�����N�̃O���[�v�ɉ����B���̌�u���[�m�[�g�ɏ����̑�\��wBlue Trane�x�𐁂����݁A���N�}�C���X�E�O���[�v�ɍĉ����B�}�C���X�͂��̎����A�R���g���[�����\�j�[�E�������Y�ƕ���2��e�i�[�t�҂Ƃ��č����]�����Ă����Ƃ����B1959�N�ɂ́A�}�C���X�́wKind Of Blue�x�̎��^�ɎQ���B�܂��A�A�g�����e�B�b�N�ɈڐЂ��A��\��wGiant Steps�x�\�B1960�N�t�A�ӂ����у}�C���X�E�O���[�v��E�ށB�}�b�R�C�E�^�C�i�[�A�G�����B���E�W���[���Y�𒆐S�Ɏ��g�̃��M�����[�E�o���h���������A���N10���ɂ͎��g�ŏ��̃q�b�g�ȂƂȂ����uMy Favorite Things�v�𐁂�����ł���B |
 |
Mahavishnu Orchestra �i�}�n���B�V���k�E�I�[�P�X�g���j �W���Y�A���b�N�����x�ȃA���T���u���ŗZ�����A�C���h���y�̃G�b�Z���X�������A���@�C�I���������[�h�y��Ƃ��Ď������A70�N�㓖���̃W���Y�E���b�N���̒��ł��ٍʂ�����Ă����}�n���B�V���k�E�I�[�P�X�g���́A1970�N�ɃW�����E�}�N���t�����̎哱�̉��Ō������ꂽ�B�}�N���t�����ig�j�ȉ��A�}�C���X�E�o���h�̖��F�ł��������r���[�E�R�u�n���ids�j�A���b�N�E���A�[�h�ib�j�A�����E�n�}�[�ikey�j�A�W�F���[�E�O�b�h�}���ivl�j�Ƃ����������o�[�ŁA��71�N�ɁwThe Inner Mounting Flame�i���ɔ�߂����j�x�ŏՌ��I�ȃf�r���[����A2��ڂ́wBirds of Fire�i�̒��j�x���W���Y�E���b�N�̃A���o���Ƃ��Ă͈ٗ�̑S��15�ʂ��L�^�B����l�C�O���[�v�̒��ԓ�����ʂ������B�o���h�������Ƀ}�N���t�����́A�q���h�D�[���̓��t�V�����E�`�����C�ɏ@���I�Ɏt�����āu�}�n���B�V���k�v�Ƃ������O��^�����Ă������߁A���̖��O���t�����B�}�N���t�����́A�g���[�h�}�[�N�ƂȂ����_�u���l�b�N�̃G���L�E�M�^�[�A�����E�n�}�[�����[�O�E�V���Z�T�C�U�[������ȂǁA���ꂼ���i��I���A�O���b�V�u�Ɏ����̗��z�Ƃ��鉹��Nj������B����ɂ���Đ��܂ꂽ�}�n���B�V���k�̉��y�́A�W�~�E�w���h���b�N�X���v�킹��f�B�X�g�[�V�����E�T�E���h�̃M�^�[���苿�����A�C���h���y��t�@���N�A�W���Y�Ȃǂ̑������t��A�N���V�b�N���y�̘a���@�܂ł����G���Ɏ������ꂽ�Ɠ��Ȃ��̂ƂȂ�A�����v���O���b�V�u�E���b�N�̎��_�Ō���鎖���������B�}�n���B�V���k��76�N�ň�U���U���邪�A84�N�Ƀr���E�G���@���X�isax�j����}���Č�������A2���̃A���o���\�����B |
 |
Clark Terry �i�N���[�N�E�e���[�j �~�Y�[���B�Z���g���C�X�o�g�A�܂�̓}�C���X�Ɠ����ƂȂ�g�����y�b�g�^�t�����[�Q���E�z�����t�҃N���[�N�E�e���[�B�}�C���X���6�N��̃g�����y�b�^�[�ł��������N���[�N�́A1940�N��ɂȂ�ƒn���̃N���u�ʼn��t���A���̌�47�N����́A�`���[���[�E�o�[�l�b�g�A�J�E���g�E�x�C�V�[�A50�N�ォ��̓f���[�N�E�G�����g���A60�N�ォ��̓N�C���V�[�E�W���[���Y�Ȃǂ̊e�r�b�O�E�o���h�ɍݐЂ����B���̊Ԃ̉��t�X�^�C���A���Ƀ~���[�g�����������z�[���̓}�C���X�ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ����B�̐S��ꂽ�y���ȃA�h���u�E�\���A������x����m���ȉ��t�Z�p�A�y�c���ЂƂɂ܂Ƃ߂铝���́A�ǂ���Ƃ��Ă��}�C���X�̎t�A�A�C�h���A�����Z�M���Ƃ��Đ\�����Ȃ����݂������B�{���̃��X�g�ł́A�ŔӔN�̃}�C���X�̕a���փN���[�N�E�e���[�������̂悤�ɓd�b�������Ă����Ƃ����G�s�\�[�h���Ԃ��Ă���B |