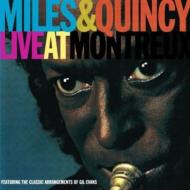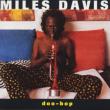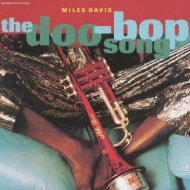��}�C���X ���X�g�E�C���[�Y� ���R�N������ɐu�� �q2�r
Monday, December 13th 2010

�@�����݁A����e�ł͂Ȃ���ł����A���̖{�̃^�C�g���Ƃ��āA�ЂƂ́u�A�K���^�ƃp���Q�A�̕���v�B���邢�́A�u�A�K���^�ƃp���Q�A�ɂ܂�镨��v�݂����Ȃ��̂��l���Ă��܂��i���F12����{���݁A4�����܂Ŏ��M���i�s���Ă���B�c���8�������H�j�B
- ---�@����́A�u���{�ƃ}�C���X�v�Ƃ����悤�ȃe�[�}�ݒ�Ȃ̂ł��傤���H
�@�����A�����ł��Ȃ��āE�E�E���͂����ЂƂ́u�A�K���^���i���j���[�^�X�̓`���v�Ƃ����^�C�g�����l���Ă��܂��āB
- ---�@�}�C���X�ƃT���^�i!?
�@�����B�l���������������ЂƂ̃e�[�}�Ƃ����̂́A�i���j�K�{�[���E�U�{����͂��܂��āA�i���j�T���^�i�ƃ}�C���X�����Ԑ��B
�@�s�s�Ō����ƁA�j���[���[�N�A���傱���ƃC���h�A���ꂩ�烁�L�V�R�A�T���E�t�����V�X�R�A�Ō�ɑ��̖�݂����Ȋ����ŁB����́A�ǂ��܂Ŋg���邩�����Ă݂Ȃ��Ɣ���Ȃ���ł����E�E�E�����炵��ׂ邱�ƂƎ��ۂ̖{�̓��e���قȂ�\��������Ƃ������Ƃ�O��ɂ��b�����܂����i�j�A�w�A�K���^�x���w�p���Q�A�x�����I�Ƃ������^���I�Ȃ̂́A���܂��܁A���ي��O�̍Ō�̍�i�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������Ƃł���ˁB���� �h���܂��܁h �ɌŎ���������ł���ˁB
 �T���^�i �w���[�^�X�̓`���x�E�E�E���I���E�g�[�}�X�A�g���E�R�X�^�[�A���`���[�h�E�J�[���[�h�A�_�O�E���[�`�A�}�C�P���E�V�����[���A�z�Z�E�`�F�s�[�g�E�A���A�X�A�A���}���h�E�y���[�U��i�����j���[�E�T���^�i�E�o���h��1974�N�ɔ��\�������C���E�A���o���B�O�N7��3�A4���ɍs��ꂽ�������N����ٌ������̖͗l�����^�B�T���^�i��i�̓��{�ɂ����锭����������CBS�\�j�[�̎哱�Ő��삳�ꂽ�B�I���W�i��LP��3���g�ŁACD�ł�2���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���A2006�N�ɔ������ꂽ���W���P�b�g�̍Ĕ�CD�ł́A�I���W�i���Ɠ���3���g�d�l�ƂȂ��Ă���B�W���P�b�g�́A22�ʂƂ����傪����Ȃ��̂ŁA�f�U�C���͉����������S���B2006�N�ɂ͐��E�ő��LP�W���P�b�g�Ƃ��ăM�l�X�L�^�ɂ��F�肳��Ă���B�Ⓒ���̃T���^�i�̋����Ɗ��\�̃��C���̐�����]���Ƃ���Ȃ����߂��A70�N��̈�A�́u���C���E�C���E�W���p���v���̂��\����1���B�uGipsy Queen�v�݂̂Ȃ炸�uBreezin�v�̈�߂��J��o���ȂǁA�T���^�i�̃K�{�[���E�U�{�ւ̌X�|�Ԃ�͐����Ɍ����B���p�͂��̑��A�R���g���[���A�A���E�o���[�]�Ȃǂ̖��t���[�Y���������ƎU��߂��Ă���B�����ʐ^�̑ѕt��LP�́A���I���ꂽ10�Ȃ����^�����R���p�N�g�ҏW�ՁB
�T���^�i �w���[�^�X�̓`���x�E�E�E���I���E�g�[�}�X�A�g���E�R�X�^�[�A���`���[�h�E�J�[���[�h�A�_�O�E���[�`�A�}�C�P���E�V�����[���A�z�Z�E�`�F�s�[�g�E�A���A�X�A�A���}���h�E�y���[�U��i�����j���[�E�T���^�i�E�o���h��1974�N�ɔ��\�������C���E�A���o���B�O�N7��3�A4���ɍs��ꂽ�������N����ٌ������̖͗l�����^�B�T���^�i��i�̓��{�ɂ����锭����������CBS�\�j�[�̎哱�Ő��삳�ꂽ�B�I���W�i��LP��3���g�ŁACD�ł�2���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���A2006�N�ɔ������ꂽ���W���P�b�g�̍Ĕ�CD�ł́A�I���W�i���Ɠ���3���g�d�l�ƂȂ��Ă���B�W���P�b�g�́A22�ʂƂ����傪����Ȃ��̂ŁA�f�U�C���͉����������S���B2006�N�ɂ͐��E�ő��LP�W���P�b�g�Ƃ��ăM�l�X�L�^�ɂ��F�肳��Ă���B�Ⓒ���̃T���^�i�̋����Ɗ��\�̃��C���̐�����]���Ƃ���Ȃ����߂��A70�N��̈�A�́u���C���E�C���E�W���p���v���̂��\����1���B�uGipsy Queen�v�݂̂Ȃ炸�uBreezin�v�̈�߂��J��o���ȂǁA�T���^�i�̃K�{�[���E�U�{�ւ̌X�|�Ԃ�͐����Ɍ����B���p�͂��̑��A�R���g���[���A�A���E�o���[�]�Ȃǂ̖��t���[�Y���������ƎU��߂��Ă���B�����ʐ^�̑ѕt��LP�́A���I���ꂽ10�Ȃ����^�����R���p�N�g�ҏW�ՁB
�@�ǂ�������{��CBS�\�j�[�����R�[�f�B���O�������̂ł����A��������������Ȃ����R�[�f�B���O�����̂��H �Ƃ����Ƃ��납������Ă��������B��������ƁA����ȑO�A�i���j�V�J�S�́w���C�u�E�C���E�W���p���x�Ƃ��A���Ђł����i���j�f�B�[�v�E�p�[�v���w���C�u�E�C���E�W���p���x�Ƃ��A���ꂱ���w���[�^�X�̓`���x�Ƃ��A�O��A�����������Ⴊ����������킯�Ȃ�ł���ˁB1973�N�Ƀ}�C���X�����������ۂɂ͌��������ǒf���āA�������A1975�N�ɂ���͎�������B����́u���C�u�E�C���E�W���p���v�̈�A�̐����̗���Ő������ł��邱�ƂȂ�ł����A���l�������v���Ă��݂Ȃ��������ƁA�Ⴆ�u���ꂪ�Ō�ɂȂ�v�Ƃ������悤�Ȃ��ƁB�����������Ƃ͘��Ղ��Č���Ƃ����Ƃ���悤�ȋC�������ł���B
�i���j �u���C�u�E�C���E�W���p���v �e��A���o��
�@CBS�\�j�[���s���J�ɎЉ����\�����Ƃ��ɁA�T�C�������K�[�t�@���N���́w���Ɓx����q�b�g���ĉ�Ђ������B���{�R�����r�A���瓯����S��G�̃��R�[�h�͏o�Ă������ǃq�b�g���Ă��Ȃ������B����A�j���[���[�N�ł��i���j�e�I�E�}�Z�����w���Ɓx�̃T�E���h�g���b�N����|���Ă������Ƃ������āA���ꂪ�����I�ɔ���āA�}�C���X�̓X�^�W�I�����R�Ɏg����悤�ɂȂ����A�Ƃ��B���̃G�s�\�[�h���w�}�C���X�̉āA1969�x�ŏ����܂�������ǁB�Ƃ�����A���镔���͋����ł����A���镔���͂��ڂ낰�Ȃ���ɂ����ʍ�����������B�ق��ɂ��A�w���[�^�X�̓`���x���w�A�K���^�x�͂ǂ�����������ŁA����ɗ��҂����Ԃ̂��i���j���������ł�������ƁB�����A�����͂��ׂČ��ۖʂł̋��ʐ��B���������ł͂Ȃ��āA���ړI�ȉe�����ǂ����͕ʂƂ��āA�K�{�[���E�U�{�ɂ͂��܂鐳�̕s���̗���݂����Ȃ��̂�����܂���ˁH ���̕ӂ��˂��l�߂Ă��������Ƃ������E�E�E

���������E�E�E1936�N���Ɍ����܂�̔��p�ƁA�O���t�B�b�N�f�U�C�i�[�B�j���[���[�N�ߑ���p�فA�A���X�e���_�����p�فA�J���e�B�G������p���c�ȂǓ��O�ŌW���J�ÁB�����|�p�܁A�����J�́A���{�����f�U�C����܂Ȃǎ�ܑ����B70�N��ȍ~�A�y���I�������A�����I�Ń|�b�v�E�A�[�g���ȃR���[�W���ɍ\�������앗����A�q���h�D�[���I�w�}�`��h���̐����}�G�Ȃǂ����`�[�t�Ƃ������k�i�������j�ȍ앗�ւƈڍs�������A81�N����͉�ƂƂ��Ă̊������J�n���A�j���[�E�y�C���e�B���O���̍앗��W�J�B��\��Ɂw��������x�A�w��6�����۔ʼn�r�G���i�[���W�|�X�^�[�x�A�w�N���A�[���C�g�x�ȂǁB �܂��A�����O�̉��yLP�W���P�b�g��|�X�^�[�̃A�[�g���[�N����|���邱�Ƃ������B�T���^�i�A�}�C���X�A���L�Q�ƍ�i�̂ق��A��CD����i�̒��ɂ́A���q���u���q���f���b�N�X�v�A�����q�u�ꉲ�O���k�v�A������u������S���v�A�n�v�j���O�X�E�t�H�[�u���Ȃ����~�����vEP�Ȃǂ�����B�A�[�e�B�X�g�E�|�X�^�[����ł́A�r�[�g���Y�A73�N�̃��[�����O�E�X�g�[���Y���̓��{�����ٌ������L���B
- ---�@���[�K�Ƃ������A�C���h���ۂ����͋C�̓��̂̒m��Ȃ��͋��ʂ��Ă���܂���ˁB
�@���[�h�Ȃ�ł����A�C���h�������Ă���B����ɁA�T���^�i������ȑO�ɁA�i���j�����[�E�R���G�����K�{�[���E�U�{�́uGipsy Queen�v���J���@�[���Ă�����Ƃ��B���������W���Ƃ����̂́A�}�C���X�����ɖڔz�����Ă���ƁA����ς蔲�������Ă��܂���ł��B���̐V���̎��_���璭�߂�ƁA���܂�ɂ������Ƃ���ɂ��܂�����ˁB�����͂��Ă��Ȃ���������ǁA���ۂ̋����҈ȏ�ɉe����^�������W�Ƃ����̂͂���Ǝv����ł���B���Ă��i���j�W�~�E�w���h���b�N�X�R��A�i���j�v�����X�R��B
�@�T���^�i�̓K�{�[���E�U�{���Ă����B�}�C���X�̓T���^�i���Ă����B�ŁA���̃}�C���X�ɕ������Ă����̂́A���́u�}�C���X�E�t�@�~���[�v�Ə̂����~���[�W�V������O���[�v�����T���^�i�Ȃ�ł���ˁB- ---�@�T���^�i�́A�}�C���X�̊y���ɂ��K��Ă��������ł��ˁB
�@��������イ�ł��B���̎����A�wIn A Silent Way�x�A�wBitches Brew�x�Ƃ��������̒��_�ɂ������T�E���h�ɂ��߂������o���Ă����̂��T���^�i�Ȃ�ł���ˁB�i���j�E�F�U�[�E���|�[�g�ł͂Ȃ���ł���B���Ԉ�ʂł͂��������Ă��܂����B���܂��܋����҂���ɃE�F�U�[�E���|�[�g���i���j���^�[���E�g�D�E�t�H�[�G���@�[���������āA�u�}�C���X�E�t�@�~���[�v�ƌĂ�Ă��邾���ł����āA�}�C���X�ɂ�����߂������ŕ������āA����ߎ��l�������T�E���h���o���Ă����̂́A���̓T���^�i�B�uIn A Silent Way�v�̃J���@�[�Ȃ�����܂������ˁB
�@�T���^�i�͈���ŁA�i���j�W�����E�}�N���t�����A�i���j�A���X�E�R���g���[���Ȃƈꏏ�ɉ���A�C���h���ʂ������������Ƃ��Ă����B�����܂ł̓����Ƃ����̂́A�}�C���X�Ƃ҂����蕄�������ł���B����͂ǂ������ǂ����Ƃ����b�ł͂Ȃ��āA�o���ɏh���I�Ȃ��̂������������ł���ˁB���ꂪ���ʂƂ��āw���[�^�X�̓`���x�ɂȂ�����A�w�A�K���^�x�ɂȂ����肵�āA���ꂪ �h���܂��܁h ���{�Ř^��ꂽ�Ƃ������ƂȂ�ł��B- ---�@���́A�g���܂��܁h�Ƃ������ƂȂ�ł��ˁB
�@�����Ȃ�ł��B������A�w�A�K���^�x���w�p���Q�A�x�̕���ł͂����ł����A���Ԃ́A�w�A�K���^�x�Ƃ܂��ʂ̉����̕���ł�����B���ꂪ�w���[�^�X�̓`���x�Ȃ̂��A�����ƈႤ���̂Ȃ̂��͒肩�ł͂Ȃ���ł����E�E�E���܂��ɂ��̕ӂ���\�z���悤�Ƃ��Ă���Œ��Ȃ�ł��B
- ---�@�����[���e�[�}�ł���̂͂������ł����A���Ȃ�˂����A�������ƂĂ��Ȃ��a�V�Ȋp�x����̌��ł��ˁi�j�B
�@��قǂ̎����Ȃ�����A�K�{�[���E�U�{�͐�Ώo�Ă��Ȃ��ł�����ˁi�j�B��قǂ̃}�C���X�ƃq�b�v�z�b�v�̘b�������ł����A�����������_�ɗ����Ȃ��ƁA�܂Ƃ߂���Ȃ���ł���B�l���u�}�C���X�͏����Ă������Ă��s���Ȃ��v�ƌ����̂͂����������Ƃł������āB
�@�wDoo-Bop�x�ɂ��Ă��wThe Man With The Horn�x�ɂ��Ă��A���̕]���Ƃ����̂͂����Ė����悤�Ȃ��̂Ȃ�ł���B�wYou're Under Arrest�x�������B�ЂƂ��ƂŌ����u�|�b�v�ȃ}�C���X�v�Ƃ������ƂȂ�ł����A���̈Ӗ�������̂��l�����Ă��Ȃ��Ƃ����̂�����ł��傤�B�wDoo-Bop�x�ɂ��Ă��u�X�g���[�g���o���ق��������v�u�Ⴂ���c��Ɍ����ẮE�E�E�v�݂����ȑ��ʂł�������Ă��Ȃ��B����͎����ł����Ĕے肷����̂ł͂Ȃ���ł����A����ς�����ƌ����ׂ��ʂ̑��ʁA�܂艽������̈Ӗ�������Ǝv����ł���B�����A�����₢���������߂̎��ۓI�ȍޗ������܂�ɂ����Ȃ������ł��ˁB���̍ޗ��̂ЂƂƂ��āA�q�b�v�z�b�v�Ƃ̊֘A�����ǂ����邩�Ƃ������_������B����͑傫�ȍޗ��B
�@�u�}�C���X�̓W���Y�̐l�ł���B�q�b�v�z�b�v�͌������̐��E�̂��̂ł���B�����Ń}�C���X�́A����Ă���q�b�v�z�b�v�𗘗p�����v�Ƃ��������́A�ߋ��Ɂu���b�N�𗘗p�����wBitches Brew�x��������v�Ƃ��邱�ƂƓ����Q�ނ��Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��킯�ŁB�܂�A��Ƃ��Ă͏��Ă��܂����炢�������Ă��Ȃ��Ƃ����i�j�B
�@���ۂ��wBitches Brew�x�͓������������Ă��܂������A���X�ɂ��̈Ӗ������炩�ɂȂ��Ă���킯�ł���ˁB������O�̂悤�Ɏv�������Ƃ������̂ɁA���̂Ƃ��C�t���Ȃ��������Ƃ����ƂȂ��ォ������͂������n�߂�B�q�b�v�z�b�v���wDoo-Bop�x�̊W�ɂ��Ă��A�������������Ȃ邩�ȂƁB- ---�@�q�b�v�z�b�v������Ȃ�̗��j�ƂȂ�A�ނ���A�Ђƒi�����������݂��A��Âɂ��̈Ӗ������������������@��Ȃ̂�������܂���ˁB
�@������A�q�b�v�z�b�v���܂������������A�܂������Q���ɂ������Ƃ��ɂ́A�����������_�͂Ȃ��Ȃ����ĂȂ�������ł���B�����ǁA���܌��݂ɂ����Ă��A�����������_�����܂�ɂ��Ȃ��������ł���ˁB�Ⴆ�A�}�C���X���������������y��������Ӗ����Ƃ��A�i���j�E�B���g���E�}���T���X�̈Ӗ����Ƃ��A�l�������Ă��ޗ����Ȃ��Ɠ��R���������ɐi�߂Ȃ��킯�ł�����B���Ƀu���b�N�E�~���[�W�b�N�̐��E�͂��������Ӗ��ŁA�����������Ȃ��䂪������ł���A���܂����āB
- ---�@���j�̌��݂Ȃǂ��ӂ܂��Ă����ƁE�E�E
�@�E�B���g���E�}���T���X���Ȃ��������������������Ă���̂��A�Ƃ����̂���ɔ���Ȃ������Ȃ�ł���B�l�ɋ��������艮�ł�������A�`����`�҂ł�������Ƃ��������͂�������ł����A����ȏ�̂��ƂƂȂ�ƂȂ��Ȃ��E�E�E
�@�E�B���g���́A1981�N���i���j�uLive Under The Sky�v�Ƃ����W���Y�E�t�F�X�e�B�o���ŁA�n�[�r�[�E�n���R�b�N�̃T�C�h�����Ƃ��ē��{�ɏ��߂ė�����ł��ˁB�܂��c���R���V�A���ŊJ�Â���Ă������ŁA���傤�ǃ}�C���X���wThe Man With The Horn�x���o���Ƃ��B�����i���j�X�C���O�E�W���[�i������Łu4�̈ӌ��v�Ƃ����A1���̃A���o���ɂ��Ċe�E��4�l����ӌ���u���Ƃ����R�[�i�[����������ł��B�]�_�ƁA�~���[�W�V�����A�o�D�A�f�U�C�i�[�݂����ɂł��邾���قȂ镪��̐l��4�l�W�߂āB�����l���S�����Ă����̂ŁA�wThe Man With The Horn�x�̊��z��u�����Ǝv���A�E�B���g���̏h����̃v�����X�E�z�e���ɍs������ł���B

�i���j�X�C���O�E�W���[�i�����u4�̈ӌ��v�E�E�E�u�b��̐V��4�̈ӌ��v�Ƃ��āA���̌��Ɏ��グ���V���A���o���ɑ��āA�~���[�W�V�����A�]�_�ƂɌ��炸�A�����ƁA�f�U�C�i�[�A�o�D�ȂǁA�W���Y�ɑ��w�̂���e�E�̗l�X�Ȑl����������̂Ȃ��ӌ������߂��A�X�C���O�E�W���[�i�����̖����N���X�E���r���[�E�R�[�i�[�B
�@����������E�E�E�{�������Ɍ����킯�ł���ˁi�j�B����͂��̂܂܋L���ɂȂ�����ł����A�悤����Ƀ}�C���X������Ȃ��Ƃ�����Ă���̂��u�Q���킵���v�ƁB�u�}�C���X�̓R�}�[�V�����Ȑ��E�ɍ������B���ׂ��������������Ȃv�Ƃ������Ԃ�Ȃ�ł���B�܂��A����͂���ł�����ł����A���̂Ƃ��E�B���g���������Ă����̂́A�u���̎Ⴂ���l�͔E�ϗ͂��Ȃ��Ȃ��Ă���B������W���Y�Ȃ����Ȃ��v�Ƃ������ƂȂ�ł���ˁB�u���������Ȃ�����A3�����z���鉹�y��A���͒����Ȃ��v�ƁB���ɁA���W�J�Z�������ő傫������炵�ĊX����������l�ɂ��������肵�Ă�����ł��B�����E�B���g���Ɠ�����A���邢�͂����ƎႢ���ゾ�����肷���ł����A�Ƃɂ����匙����������ł��ˁi�j�B�u���l�������ł����Ă̓_���Ȃv�Ǝv���Ă��āA����Ɂu�{�N�̓W���Y���L�߂����B���������A���ɂ��������������v�ƌ����Ă��āA���ۂ������E�B���g���̌��_���Ǝv����ł���B�t�Ƀ}�C���X�́A�������̐��E�ɍs�����������B���W�J�Z�̒��Ŗ炵�Ăق���������ł��B�uShout�v�Ƃ����ȂȂ͂܂��ɂ��̐��E��ڎw���Ă���B������A�E�B���g���̓}�C���X�ɉ�����킯�Ȃ�ł���ˁB
�@�Ƃ������Ƃ́A�E�B���g���͒N�Ɠ����Ă���̂��H �Ƃ����ƁA�悤����Ƀq�b�v�z�b�v�Ȃ킯�ł��B���ɘ_��������܂��B�܂�A�q�b�v�z�b�v�����l�ɂƂ��Ė����ł��Ȃ������������B�ނ���E�B���g���ɂƂ��Ă͋��ЂƂ��ĉf������ł���B�����肩�炵�āA�u���b�N�E�~���[�W�b�N�Ƃ��ẴW���Y�̂������������A�����S�������Ă����ꂽ�悤�Ȋ�@�����E�B���g���͎@�m�����Ǝv����ł���B�������}�C���X�A�~���K�X�A�G�����g���ɂ��тꂽ�悤�ȁA����Ɠ����悤�Ȃ��т���������Ⴂ����̓q�b�v�z�b�v�Ɋ����Ă���B������A�`���b�N�ED�i�p�u���b�N�E�G�l�~�[�j���i���j�h�N�^�[�E�h���[���G�����g���ɂȂ��Ă��܂�����ł���ˁB- ---�@����͗��j�ςƂ��Ă͂���Ӗ��Ő����������A�������ł�����܂���ˁB
�@���̚��ĂɃ}�C���X���s�����Ƃ����B���ۂɍs���Ă��܂��܂������B���W�J�Z��ь�������E�B���g���ƁA���W�J�Z�ŗ�����邱�Ƃ����߂��}�C���X�B�x�N�g�����^�t�ł�����i�j�A���R�G������B�����������Ƃ������āA��قnj������u�q�b�v�z�b�v�ƃ}�C���X�v�̕���̎�l���́A�ЂƂ�̓E�B���g���ł������ł���B�E�B���g���̐���ɂ���ăq�b�v�z�b�v���ǂꂾ���������̂��A�W���Y�E�~���[�W�V�����ɂ��ՁX�Ɨ����ł��Ă��܂����Ƃ����B
�@�}�C���X�́A���l�܂�u�����A�����J�v�Ɠ����Ă����B����A�E�B���g���́u�����������Ă��鍕�l�v�Ɠ����Ă���悤�ȋC�����܂��B�����炭�E�B���g���ɂ́A���l�Ɠ����ȑO�ɓ��E�Ƃ̓������������ƁB���̔��[�́A�g���N���h�̃q�b�v�z�b�v�ɂ���Ăł����f�w�ɂ����̂��Ǝv���Ă����ł��B��̓I�ɂ��̎����A���̍�i�Ƃ����͔̂���Ȃ���ł����B����̓q�b�v�z�b�v�����̍����łɓ��퐶���ɂ���������ȂƎv����ł���ˁB- ---�@ �W���Y���Ǝゾ�����Ƃ������������ł������ł��傤���H
�@���`��E�E�E�W���Y�͌��݊e���Ő���ł͂���܂����A�u���b�N�E�~���[�W�b�N�Ƃ��ẴW���Y���Ǝ�Ȃ�ł���B���ꂪ���̍��A���̐l��ɗ]�T��^���Ă����ł��ˁB�X�L�������Ă���Ƃ������B�܂�F�X�Ȑl���o������]�n�B���܂Őς܂�Ă����d��������Ƃ���Č��������āA�������瑽���Ђ̐l���ǂ�ǂ�o�čs���悤�Ȋ����������ł���ˁB
�@������A�wBitches Brew�x�̃��K�V�[�E�G�f�B�V�����ɓ����Ă����i���j1970�N�̃^���O���E�b�h�ł̃��C�����������Ă݂�ȃu�b��Ԃ̂́A�u�{���͂���Ȃɂ����������v�Ǝv�����炢�Ј��I�Ȕ��͂����������炾�Ǝv����ł����E�E�E���ꂪ���܌��݂̃u���b�N�E�~���[�W�b�N��W���Y�ɂ͂Ȃ�����]�v�Ƀr�b�N������Ƃ������Ƃɂ��Ȃ����Ă���킯�Łi�j�B

�i���j1970�N8��18���̃^���O���E�b�h�����E�E�E���̂��сA�wBitches Brew�x�̃��K�V�[�E�G�f�B�V�����ՂɂĐ��K���o��ƂȂ����A1970�N8��18���}�T�`���[�Z�b�c�B�{�X�g���x�O�̃^���O���E�b�h�A�o�[�N�V���[�E�~���[�W�b�N�E�Z���^�[�ɂ����郉�C�������B�n�����o�s��ł́u�^���O���E�b�h�̗��v�Ƃ��Ē��炭�L�������A�����ʂ�r�ꋶ�����̂��Ƃ��̃Z�v�e�b�g�ɂ�鋥�C�̉��t�́A�o���h���E���O�ƂȂ�`�b�N�E�R���A�ƁA�L�[�X�E�W�����b�g�́u�v�L�[�{�[�h�v�̂Ԃ��荇���Ɉ���Ƃ��낪�傫�����낤�B
�@�Ⴆ�A���炩�̃R�s�[�̂悤�Ȃ��̂��Ė������Ă���悤�Ȑl���A�����I���W�i���ɏo�������Ƃ�����A���̂Ƃ��̏Ռ��͓�d�̈Ӗ��ő傫���Ǝv����ł��ˁB�u���܂Ŏ����̓R�s�[���Ă����̂��E�E�E�v�Ƃ����V���b�N���܂��ЂƂi�j�B�����ăI���W�i���̂������Ƃ����̂͂���ς蕁�ՁB���́A���y�s�ꂪ�������������I���W�i���ɂȂ��Ȃ��o�����Ȃ��悤�ȃV�X�e���ɂȂ��Ă��邱�ƂȂ�ł��B- ---�@�I���W�i����H�邨�����낳�ɖ��ڒ��ȃV�X�e���E�E�E
�@�R�s�[�����m��Ȃ��l�́A���ꂪ���̐l�ɂƂ��ẴI���W�i���Ȃ킯�ł�����A�l�����������悤�ȊT�O����Ӗ��̂Ȃ����ƂȂ�ł���ˁB���܂��������̂��������Ń}�C���X���~���K�X����m�����Ƃ��ɂǂ��Ȃ邩�H �Ƃ������ƂȂ�ł���ˁB
- ---�@���l�ς�180�x���邩������Ȃ��l������B
�@ ���ꂪ���y�����̂��݂ł������ł����ǂˁB���ƁA���́A�����wBitches Brew�x�̃��K�V�[�E�G�f�B�V�����ɂ���A�i���j���̊Ԃ̃��[�����O�E�X�g�[���Y�ɂ���A��ԍ����ȃ{�b�N�X�E�Z�b�g�̂悤�Ȃ��̂���������M�����[�Ղ܂ŁA����ނ���x�ɏo�鎞�ザ��Ȃ��ł����B�����������Ƃ�����Ă��邩�琷��オ��Ȃ���ł���i�j�B

�i���j���̊Ԃ̃��[�����O�E�X�g�[���Y�E�E�E����A5���Ƀ����[�X���ꂽ�w���C�� �X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̃X�[�p�[�E�f���b�N�X�E�G�f�B�V�����B���j���[�A���E�{�[�i�X�E�T�C�h���������{��2����SHM-CD�i���{�Ղ̂݁j��2LP�A����ɂ́A�w�Ȃ炸�ҁx�̃��C�L���O�A1972�N�̖k�ăc�A�[�𑨂����R���T�[�g�f��w���f�B�[�X���W�F���g�������x����̔����A�u���h�L�������^���[�v�Ƃ������ׂ��w�R�b�N�T�b�J�[�E�u���[�X�x����̔��������^����DVD��t�����������Z�b�g�B - ---�@�u���v�u�|�v�u�~�v�ƁA���i�ɂ�鍷�ʂ����ƘI���ł���ˁi�j�B
�@�����������������Ȃ��悤�ȃZ�b�g�����݂���킯�ł����B�{���͒l�i�ł͂Ȃ��āA�݂�Ȃ��������̂���ɂ��āA�����Řb������L����Ƃ������Ƃɂ��Ȃ��Ɛ���オ��Ȃ���ł���B������A���܂݂͂�Ȃ��Ⴄ���Ƃɂ��Ă���ׂ��Ă���i�j�B���������̍��������B��Ԉ����Z�b�g�����l�́A��ԍ����Z�b�g�����l�ɑ��ė��������܂�Ȃ��i�j�B����͐���オ��Ȃ��Ɍ��܂��Ă܂���B
- ---�@�i���Љ��y�����ł����炳�܂ɂȂ�Ƃ����߂����E�E�E�i�j
�@�������A�����Z�b�g�ɂ͕K������Ȃ�̃v���X�E�A���t�@������B���ꂪ�����\�\�[�X�Ȃ̏ꍇ�A�N�����Đl�Ԃł�����A�o���ꂽ�����ς蒮�������킯�ł���B���̎�݂ɂ�����Łi�j�E�E�E�����A�o���ꂽ�璮���������ǁA�o����Ȃ�������N������̂��Ƃ������ƁA���邢�́A������ǂꂾ���̐l�����������̂��A�Ƃ������Ƃł���ˁB�^���O���E�b�h�̃��C����������A���ꂾ����P�̂ŏo���ׂ��Ȃ�ł���B��������A�������������I���W�i���ɂ��͂��Ȃ��悤�Ȑl�����ɂ��A���͂��₷���Ȃ�B
- ---�@�ނ���A��������}�C���X�ɓ���l�����Ă���ł��傤���B
�@�����ł��B�����Ⴆ�A1���~�߂��o���Ă��ǂ蒅���Ƃ����͖̂����Șb�Ȃ�ł���B�wBitches Brew�x�ɂ������ǂ蒅���Ă��Ȃ��l�������ς�����̂ɁA����ɂ��̉����~�ɂ��邢���関���\�����Ƀ^�b�`����͓̂���s�\�B�t�ɁA�P�̂ŏo������������������ł���悤�ȋC�������ł��B���ł��u�������̂����킹��v�Ƃ����悤�Ȑ������X����܂����i�j�A�����������s����������Ȃ��ʼn�������킹�邱�Ƃ��ł���悤�ȋC�����܂��B�����A���������g�����h��ɉ��o���Ȃ�������̂��炢��ł���ˁi�j�B��x�Ƀh�J�b�Əo����Ă��u�����Ȃ������v�ƁE�E�E�܂��A�b�͏�������Ă��܂��܂�������ǁi�j�B
- ---�@�����\�Ȃƌ����A���́u���X�g�E�C���[�Y�v�ł́A��͂�v�����X�Ƃ̋����Ȃ��ڋʂł�����܂���ˁB�wDoo-Bop�x����r���̃h�C�c�����ł͋������s�Ȃ��Ă��������ŁE�E�E
�@����A�����ł͂Ȃ��āA�v�����X�̏������V�Ȃ����C����4�A5�Ȃ���Ă����ł��B����ŁA���̂Ƃ��X�^�W�I�ł����n�[�T�����x���Ǝv����ł����A�v�����X�̋Ȃ������R�[�f�B���O����Ă����ł��ˁB���S�Ȃ��̂Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂����B�����Œ��ڂ��ׂ��Ȃ̂́A�O���ɍs���Ă܂ł��v�����X�̐V�Ȃ�^�������������Ƃ����A���̈ӗ~�ł��傤�ˁB���������ɒ��ڂ��Ă�������Ȃ����ȂƎv���Ă��܂��B
- ---�@�����Ȃ��i���j�uCan I Play With U �H�v�́A���ǒ��O���wTutu�x�ւ̎��^���������܂����B�v�����X����̃{�c��Ăł������A�}�C���X�͂���Ȃ�ɋC�ɓ����Ă����̂ł��傤���H
�@�܂��A�ǂ����ł��悩������ł���i�j�B�܂�A�ЂƂ̃~���[�W�V�����E�V�b�v�̃J�^�`�Ƃ��āA�v�����X����������̂ɑ��Ă͂����ɏ]���Ƃ������Ƃł���ˁB�������ނ������ƌ����A�����Ɏ^�����Ă����͂��ł��傤���B������A�O����b�������Ƃ��Ǝv���܂����A���̕ӂ̃~���[�W�V�����E�V�b�v�ɂ����Ă͎��Ƀt�F�A�ł���ˁA�}�C���X�́B
�@�������}�C���X�́A�Ⴆ�v�����X�̋Ȃ����悤���A�}�C�P���E�W���N�\���̋Ȃ���낤���A����Ȃ��ƂŔ���锄��Ȃ���}���Ă͂��Ȃ����A������������ȉ��l�ς������Ă��Ȃ���ł���B

�i���j�}�C���X�~�v�����X�uCan I Play With U�v�E�E�E85�N6���Ƀ��[�i�[�E�u���U�[�Y�ƌ_�����������}�C���X�B����ă��[�x���E���C�g�ƂȂ����v�����X�ƃ}�C���X�͓��N12��7���ɋ��R���T���[���X��`�ŏo��A��20���ԃ}�C���X�̑��}�Ԃɏ�荞��ʼn�b�����킵���Ƃ����B���̂킸��20����A�v�����X�͔M�S�ȃ}�C���X�M�҂ł��������߂̃T�b�N�X�t�҃G���b�N�E���[�Y�ƃ}�C���X�̂��߂̃f���E�e�[�v����ɓ���A12��29���A�}�C���X�̃}���u�̕ʑ��ɁuCan I Play With U�H�v�Ƒ肳�ꂽ�A�h�炵���S�J�h�̃t�@���N�y�Ȃ��͂���ꂽ�B��86�N�ɂ̓}�C���X�̃g�����y�b�g�̃I�[�o�[�_�u���I���A�ŐV�A���o���wTutu�x�̃��X�g�ɁA�uFull Nelson�v�����t�i�v�����X�̖{���h�v�����X�E���W���[�Y�E�l���\���h�ւ̐���҃}�[�J�X�E�~���[�ɂ����̃g���r���[�g�j�ɂ��Ď��^�����͂����������A�y�d��Ńv�����X�ɂ��u�҂����v�������肨������ƂȂ��Ă���B�u�A���o���Ƀt�B�b�g���Ȃ��v�Ƃ����̂��匳�̗��R�����������A������`�҂̉��q�ɂƂ��ẮA�y�Ȏ��̂̃N�I���e�B����ђ鉤�̃\���E�e�C�N�ɂ͂܂��܂��C���̗]�n���������Ƃ������Ƃ��낤�B�ʐ^�́A���Y�Ȃ����^�����L���u�[�g�wCrucial�x�B - ---�@�P���ɋC�ɓ������Ȃ����t���邾���Ƃ����B
�@ ������A�Ō���i���j�u�ĉ�Z�b�V�����v�ɂ��Ă��A��ʓI�ɂ́u�����̂��߁v�ƌ����Ă��܂����A�����������l�ςɊ�Â������̂ł͂Ȃ���ł���B���ۂ����̂��߂ł������疈�N����Ă���킯�Łi�j�A�����������Ƒ�����������B
�@�}�C���X�̂悤�ȃA�[�e�B�X�g��l��̂悤�Ȉ�ʓI�Ȋ��o�ő�����̂͂��܂�E�E�E�l��ł�������u�����̂��߁v�Ƃ����͓̂���I�ɑ傢�ɂ��肦�邱�Ɓi�j�B�����������܂ł̐l�ɂȂ�ƁA��������͗~�����Ɍ��܂��Ă�ł��傤���A���ꂾ���œ����킯�͂Ȃ���ȂƁB�u�����͗p�ӂ��܂����B�X�������肢���܂��v�Ƃ����b�ł͂Ȃ��B������A����ۂǏ��X�̃^�C�~���O�����܂��͂܂�Ȃ��ƁA�u�ĉ�Z�b�V�����v�̂悤�ȃC�x���g�Ƃ����̂͂ł��Ȃ��悤�ȋC�������ł���ˁB�ŏI�I�ɂ͎����Ō��߂邱�Ƃł͂����ł����A���̒i�K�ɍs�������ł����͂ɂƂ��Ă͑�ςȘJ�͂�v����Ǝv����ł���B- ---�@�Ƃ��܂��ƁA���́u�ĉ�Z�b�V�����v�ɏo�����邱�Ƃ��ŏI�I�Ɍ��߂��}�C���X��˂������������̂Ƃ����̂́E�E�E
�@ �{�ɂ����������ƂȂ�ł����A����ς艹�y����肽���Ƃ����C�����ЂƂł���ˁB������A�u�ĉ�Z�b�V�����v�ł����Ă��Ȃ��Ă����y�͂���Ă����A���̒��x�̑I�ʁB�܂�ǂ����I������ɂ���A�ǂ̓����y����邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��Ƃ������Ƃ������Ǝv���܂��B���ꂪ�uHuman Nature�v�ƁuSummertime�v�̈Ⴂ�Ȃ����ł����āA�{���͕ς��Ȃ��B�����A���@�⎞����I�ԂƂ������ƂŁA���܂łɂ͓��R�Y�Ƃ͎v���܂�����A�����̓N�C���V�[�E�W���[���Y��������̐s�͂������ɂ�������Ȃ��ł��傤���ˁB
- ---�@���̑O��Ɂu���͈��ނ���v�i1991�N6���A���E�����h����j�ƃ}�C���X�͔������Ă��܂����A���̈ӎu�̂悤�Ȃ��̂��O��ɂ�������ł́u�ĉ�Z�b�V�����v�o���̑I���Ƃ����߂ł������ł����B
�@�������A����͎c���ꂽ�҂��z���ŗV�ԃ��x���̗v�f�ł����Ȃ���ł���B�u�}�C���X�͎��ʂ��Ƃ�m���Ă����v�Ǝv���Ē��������������I�ɒ�������l�A����͂���Ő����ȂƎv���i�j�B��������Ȃ������Ƃ����ӌ������R���邵�A���N���ނ��邩�炨�ʂ�̈Ӗ������߂ăX�e�[�W�ɏオ�����Ƃ����ӂ��ɑ����Ă��ʂɕs���R�ł͂Ȃ��ł�����B����N����߂��āA�̂������Ȃ����x���x�������𑱂��Ă���l�Ɋւ��ẮA���������悤�Ȃقڂ��ׂĂ̗v�f�����Ă͂܂�悤�Ɏv���܂��B�܂艽���N���Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��ƁB
�@���ꂪ�Ⴆ�A�wBitches Brew�x�̎��Ɂu�ĉ�Z�b�V�����v����������낪����Ȃ��i�j�B���R�܂��Ⴂ����B��������90�N��Ƃ��Ȃ�ƁA��ʓI�ɂ͔N���Ƃ͌ĂׂȂ���������܂��A�̂̂��������ɃK�^�����Ė��g�n�w�ȏ�ԂȂ킯�ł�����ˁB- ---�@�����A���̎����͕��s�����wDoo-Bop�x�̐���ɂ��Ȃ�O�����Ɏ��g��ł��܂�����A�u����������Ă����v���邢�́u���N���ނ��邩��v�Ƃ����������ɂ͏����s���R�Ȋ������E�E�E
�@�����Ȃ�ł��B������A���������l�X�ȉ��߂ɂ͂��ׂăc�b�R�~�ǂ��떞�ڂȂ�ł���i�j�B�u���N���ނ��邩��v�ƂȂ�Ɓu���Ⴀ�wDoo-Bop�x�͂ǂ��Ȃ�H�v�ƂȂ�܂�����ˁB�ЂƂЂ�����Ԃ�Ƃ���܂ł̃J�[�h�����ׂė��Ԃ��Ă����悤�ȁA���̒��x�̐����͂��������Ȃ��z���ł����Ȃ���ł���B�������}�C���X�̍Ō�̕���̖ʔ����Ƃ���Ȃ�ł���ˁB
�@�wDoo-Bop�x�ɌŎ����āA�}�C���X�͍Ō�܂ŐV�������Ƃ���낤�Ƃ��Ă����Ƃ����z���B����͓��R�����Ȃ�ł���B�}�C���X�̂悤�ȃ~���[�W�V�����Ƃ������\���҂͖{�\�I�ɂ����������̂ł��傤����B���Ⴀ����ŁA�N�C���V�[�Ƃ́u�ĉ�Z�b�V�����v�ɂ͂Ȃ��o�������H �ƂȂ����Ƃ��ɂǂ��������t�ŕԂ����Ƃ����i�j�B
�@�����A�ЂƂ�����̂́A�wDoo-Bop�x�͉i�����̂���v���W�F�N�g�ł����A�N�C���V�[�Ƃ̃X�e�[�W�́u�����E�i�C�g�E�X�^���h�v�A�悤�̓C�`���ł�����ˁB�����͖��m�ɈႤ�Ƃ͎v����ł���B�ʂɃN�C���V�[�y�c�̕Ґ��Ńc�A�[�ɏo��킯�ł͂Ȃ������̂ŁB- ---�@�t�ɁA�C�[�W�[�E���[�E�r�[�Ƃ̓c�A�[�ɏo�悤�Ƃ��Ȃ�ӗ~�I�ɍl���Ă����悤�ł��ˁB
�@����͂������R�ȗ���ł���ˁB���̈قȂ闼����{�Ƃ��Ĉꏏ�����ɂ��Ă��܂��ƁA�ǂ��������ɂȂ�B�Ⴆ�A�i���j�n�[�r�[�E�n���R�b�N��V.S.O.P. �N�C���e�b�g�́A���ǂ͐��E�c�A�[�ɏo�čP�v�I�ȃO���[�v�ɂȂ����B�������������ƂƂ͂܂������Ⴄ��ł���ˁB����ɁA�u�ĉ�Z�b�V�����v�������������i���j�f�C���E�z�����h���i���j�`�b�N�E�R���A�ƃO���[�v��g��ł��悩��������ǁA��������Ȃ������B�����������Ƃ����ɂ߂���ōŌ�̌l�l�̑��������Ă����Ȃ��ƁA�����Ⴂ�����Ċr�ׂ��Ȃ���ł���B
�@�}�C���X�Ƃ��Ă͉��Ƃ��Ăł��wDoo-Bop�x�̘H�����x�[�X�ɂ��Ă��̐���������Ă����A�����l����̂����R�ł͂Ȃ��ł��傤���B�����̃O���[�v�ɃC�[�W�[�E���[�E�r�[���������肾�Ƃ��B���̕������̂������A��������������ł���ˁB������A�����Ɍ�����v����������A�����ւ̂Ȃ���݂����ȂƂ���ł́A�}�C���X�̖{���͂���ς��wDoo-Bop�x�ɂȂ�܂���ˁB�����������wDoo-Bop�x�́A�����ɏI��������炱���i���̖��������ꂽ�킯�ŁA�t�Ɂu�ĉ�Z�b�V�����v�͊�搫�Ƃ��Ă͏G��ł����A�������ʼn����o�����u�ԂɏI������B�`�������W�ł͂������ł��傤���A�}�C���X�ɂƂ��Ă͂���Ӗ��ł����ē���`�������W�ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B�wDoo-Bop�x�ŃC�[�W�[�E���[�E�r�[�ƃc�A�[�ɏo���������ۂǃn�[�h���̍����`�������W�������Ǝv���܂���B����܂ŁA�n���R�b�N������Ă����悤�Ƀ��C���Ń^�[���e�[�u���X�g���ق������ƂȂȂ������ł����ˁB- ---�@�wDoo-Bop�x�̃`�������W�ɂ͂�����N���N���Ă�����ł��傤�ˁB
�@�����ł��傤�ˁB�������u���͉ߋ���U��Ԃ�Ȃ��v�Ƃ����Ƃ��낾�Ǝv����ł��B
- ---�@�wDoo-Bop�x�́A����2���g�ɂȂ�\�肾���������ł��ˁB1���ڂɂ́A�p�u���b�N�E�G�l�~�[�̃`���b�N�ED���MC�Ńt�B�[�`���[�����q�b�v�z�b�v�E�T�C�h�ŁA2���ڂ͐̂̃Z�b�V������v�����X�Ƃ̋��������߂���ƁA�z�����������ł��̂�������i�ɂȂ�Ƃ����B
�@�wOn The Corner�x�ɂ����wBitches Brew�x�ɂ���A����Ȃ��Ȃ�ɍ�i�Ƃ��Ă͊������Ă���̂ŁA�����͔����ł���B�����Ȃ�ɂ��̍�i�ɑ��錈���͕t������B�Ƃ��낪�wDoo-Bop�x�́A�u�N�̍�i�ȂH�v�Ƃ����b��������Ă����ƁA�������}�C���X�Ȃ�ł����A�Ō�܂ł͊ւ���Ă��Ȃ���ł���ˁB�����Ȃ�ƁA�䂵���c��Ȃ��Ƃ������E�E�E���܂ł����V�����c�����܂܂��݂��ɕt�������Ă��������Ȃ��Ƃ����i�j�B
- ---�@�����炱���́u�i���̖����v�Ƃ����E�E�E
�@�u�I���O�ɏI���������A�I����Ă��Ȃ��v�Ƃ������g���b�N�ł���ˁB�W�����E���m���݂����Ɉ��Ƃ��Č��͂�����ŁA�Ƃ������ƂƂ͂���ς菟�肪�Ⴄ��ł���B
 |
|
1986�N�u���@���N�[���@�[�E�C���^�[�i�V���i���E�W���Y�E�t�F�X�e�B���@���v�ɂāB�E�B���g���E�}���T���X�ƒ鉤
|
 |
|
1991�N7��8���X�C�X�́u�����g���[�E�W���Y�E�t�F�X�e�B���@���v�ɂĎ������ꂽ�u�ĉ�Z�b�V�����v
|
�u���X�g�E�C���[�Y�v��20��
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
�y�Ċ��u�K�z �u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v ���R�N������ɐu��
-
�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v ���R�N������ɐu��
�s��ȃX�P�[���Ɩ��x�́u�鉤�E���d���G���v�B���̓�������������w�G���N�g���b�N�E�}�C���X 1972-1975�x�����ꂽ�}�C���X�����̑��l�ҁA���R�N������ɂ��b���f���܂����E�E�E
���̑��̊֘A�L��
-
�y���W�z �}�C���X�E�f�C���B�X �wTUTU�x �i2011�N5���j
�}�C���X�E�f�C���B�X��1986�N���[�i�[�ڐБ�1�e��i�wTUTU�x���A�{�҃��}�X�^�[�ɓ��N7���̃j�[�X����������lj�����2���g���ؔՂɂēo��B��������̎���}�[�J�X�́uTUTU�lj����C���v�������E�E�E�E�E�E
-
�y���W�z �d���鉤�w�� �u�r�b�`�F�Y�v�ɂ��� �i2010�N7���j
�wBitches Brew�x 40���N�L�O�������K�V�[�Ղ������B�����\���C������CD�A�����\���C��DVD����lj��������S���Y����̂䂾���������B�d���鉤�w�ƁwBitches Brew�x�ɂ��ĐF�X�ƁE�E�E
-
�e�n���E �����O�E�C���^�r���[ �i2008�N6���j
2008�N6���ɍs��ꂽ�e�n���E���C���^�r���[�̑S7�S�ŁB�_�u�E�Z�N�X�e�b�g�A�}�C���X�A�t�@�b�V�����A���̌q�����������x�l�@���Ă݂�ƁE�E�E�E�E�E

-
���R�N�� �i�Ȃ���� �₷���j
�@1952�N���{�o�g�B���y�]�_�ƁB�W���Y�G���u�X�C���O�W���[�i���v�ҕҏW���߂���A���M�����ɓ���B����Ɂw�}�C���X�E�f�B���B�X �̎���x�A�w�}�C���X vs �R���g���[���x�A�w�}�C���X�̉āA1969�x�A�w�}�C���X���I�x�������B�Ɂw�}�C���X�E�f�B���B�X�����`�x������B�܂��A���b�N�ɂ����w���[���A�w�r�[�g���Y�ƃ{�u�E�f�B�����x�A�w���ƗE�C�̃��b�N50�x�A�w�f�B������!!�x��������B
- �֘A�T�C�g�i�O���T�C�g�j
- �֘A���W�iHMV�T�C�g���j
�{�����ɓo�ꂷ���v�l���ɂ��� |
 |
Santana�iCarlos Santana�j �i�T���^�i / �J�����X�E�T���^�i�j 1966�N�ɃT���t�����V�X�R�Ō������ꂽ�T���^�i�E�u���[�X�E�o���h���O�g�B���̌�T���^�i�Ɖ������A1969�N�Ƀ��R�[�h�E�f�r���[�B�������ɃE�b�h�X�g�b�N�E�t�F�X�e�B�o���ɏo�����A�b��ƂȂ�B���N�̃Z�J���h�E�A���o���wAbraxas�i�V�̎��_�j�x�̓r���{�[�h���̃A���o���E�`���[�g��1�ʂ��l���B�W���Y�E���b�N�F�����߂�1972�N�̃A���o���wCaravanserai�x���\��A�啝�ȃ����o�[�E�`�F���W�����s�B73�N7���̑������̖͗l�́A���������f�U�C���̃W���P�b�g�ł��L���ȃ��C���Ձw���[�^�X�̓`���x�Ɏ��^���ꂽ�B76�N�́wAmigos�x���^�Ȃ́uEuropa�v�́A�J�����X�E�T���^�i���\���閼���Ƃ��Ēm���Ă���B���̌���R���X�^���g�Ɋ������p�����A1999�N�ɔ��\�����A���o���wSupernatural�x�́A�o���h�ɂƂ���28�N�Ԃ�̑S��1�ʊl�����ʂ����A�A�����J������1500�����A�S���E��2500�����ȏ��グ��Ƃ����啜���ƂȂ�A�O���~�[�j��ő���9�������܂����B�o���h�̒��S�l���ł���M�^���X�g�̃J�����X�E�T���^�i���}�C���X�����Ȃ�h�����Ă���A72�N�́w�T���^�i�V�x�ł́uIn A Silent Way�v���J���@�[���A����Ɂw���[�^�X�̓`���x�̕���ƂȂ���73�N�̓��{�����c�A�[�ł́A�܂��ɃG���N�g���b�N�E�}�C���X�̐��E���T���^�i���ɍ\�z�������̂悤�ȉ��t�����Ƃ��ł���B�܂��A���m�N�w�ɌX�|���Ă���A�V�����E�`�����C�ɋA�˂��Ă���73�N�ɂ́A�������V�����̐M��҂ł���W�����E�}�N���t�����Ƃ̘A���ŁwLove, Devotion and Surrender�i���̌Z�킽���j�x�Ƃ����A���o���\���Ă���B |
 | Gabor Szabo �i�K�{�[���E�U�{�j �n���K���[�A�u�_�y�X�g���܂�ŁA�n�Č��1958�N����60�N�ɂ����ăo�[�N���[���y�@�Ŋw�сA���̌�`�R�E�n�~���g���y�c�Ŋ������邱�ƂƂȂ����M�^���X�g�B�`�R�y�c�E�ތ�́AImpulse!���R�[�h�Ƃ̌_��āA�o���h�E���[�_�[�Ƃ��Ă������B65�N11���ɂ́wGypsy '66�x�A66�N5���ɂ́wSpellbinder�x�Ƃ���2���̑�\�I�ȃ��[�_�[�E�A���o����^���B��Ҏ��^�́uGypsy Queen�v�́A�����[�E�R���G���A����ɂ́A�T���^�i�̃A���o���w�V�̎��_�x�ŁA�t���[�g�E�b�h�E�}�b�N�́uBlack Magic Woman�v�Ƃ̃��h���[�Ƃ����`�ŃJ���@�[���ꂽ�B���̌�A�t�����[���[�������g�`�T�C�P�f���b�N�E�J���`���[�ɐG������Đ��삵���wJazz Raga�x��A�C���h���y����̉e����������A�V�^�[���t�҂��܂ޕҐ��Ń��R�[�f�B���O���ꂽ�wWind, Sky And Diamonds�x�ȂǁA�{�����ɂĒ��R�����u�T���^�i�ƃ}�C���X�����Ԑ���ɂ���v�Ǝw�E���Ă����d�v��i�\�B70�N�A�u���[�X�E���[�x����Blue Thumb ���R�[�h���甭�\���ꂽ�A���o���wHigh Contrast�x�ł́A�{�r�[�E�E�H�}�b�N�Ƌ����B����ŃE�H�}�b�N���K�{�[���̂��߂ɏ������낵���uBreezin'�v�́A76�N�ɃW���[�W�E�x���\���ɂ��J���@�[�E���@�[�W��������q�b�g�����B81�N�A�̋��u�_�y�X�g�̕a�@�Ŏ����B |
 |
Larry Coryell �i�����[�E�R���G���j �W���Y�ƃ��b�N�̗Z���ɑ���������g��ł����M�^���X�g�A�����[�E�R���G���́A1965�N�Ɍ��������W���Y�E���b�N�E�o���h�A�t���[�E�X�s���b�c�̃A���o���wOut Of Sight And Sound�x�ɂč����A�u�u���b�h�E�X�E�F�b�g�E�A���h�E�e�B�A�[�Y��}�C���X�E�f�C���B�X������������W���Y�ƃ��b�N�̒��a�����݂��o���h�v�Ƃ��ĕ]������Ă���B�܂��A�`�R�E�n�~���g���̃o���h�ɃK�{�[���E�U�{�ƂƂ��ɍݐЁB�䂦�ɁA�U�{�̃M�^�[�E�v���C���悭�������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B60�N��㔼�ɂ́A�W�~�E�w���h���b�N�X��N���[���̃G���b�N�E�N���v�g���̃M�^�[�E�v���C�ɑ傫�ȏՌ��Ɗ������A71�N�ɂ̓W�~�̃G���N�g���b�N�E���f�B�E�X�^�W�I�ŁA�t�B�[�h�o�b�N�t�@�Ǝa�V�ȃf�B�X�g�[�V�����E�M�^�[���y��wBarefoot Boy�x��^�����A�����ɂ�10�������́uGipsy Queen�v�̃J���@�[�����߂��Ă���B72�N����́A�����f�B�E�u���b�J�[��Ƌ��ɁA�C�������X�E�n�E�X�Ƃ����t���[�W�����E�o���h�Ƃ��Ċ������Ă������A75�N�ɂ́A�X�e�B�[���E�J�[���Ƌ��ɃA�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�����ɂ��c�A�[���s�Ȃ��A�Ȍ�1980�N�㒆���܂ŁA�A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�̉��t�����S�ƂȂ�A�W���Y�ƃN���V�b�N�̗Z�������݂�悤�ɂȂ����B�����̃}�C���X�́u����߂Đe�����K�[���t�����h�v�ł������G���A�i�E�X�^�C���o�[�O�E�e�B�[�E�R�u�i�̎�E�쎌�ƁE�v���f���[�T�[�E���l�j���F�l�̃W���[�i���X�g�A�W�����[�E�R���G���ɕv�ł��郉���[�E�R���G���̃Z�b�V�����ւ̎Q���𑊒k�B�u���ي��v�^�������ł�����78�N2���̃R�����r�A�E�Z�b�V�����Ƀ����[�͎p���������ƂɂȂ������A���ۂ́u�e��������v�Ƃ������R�ŁA�鉤�͂悭�Ȃ������炵���B |
 |
Teo Macero �i�e�I�E�}�Z���j �}�C���X��i�A1959�N�́wSketches of Spain�x����83�N�́wStar People�x�܂ł̊��Ԃ̐������̃A���o���E�v���f���[�X����|���Ă����R�����r�A�̖��v���f���[�T�[�A�e�I�E�}�Z���B�wSketches of Spain�x�A�wPorgy and Bess�x�A�wKind of Blue�x�̃v���f���[�X�̓e�I�̖��������m�ł�����̂ɂ������A����肻�̎�r���������̂�1968�N�ȍ~�̍�i�B���\�e�C�N�����Ԃɂ��y�Ԙ^���e�[�v���\�肵���k���ɂ��đ�_�ȉ��G�������グ�Ă����s�������́A�wIn A Silent Way�x�A�wBitches Brew�x�A�wJack Johnson�x�A�wOn The Corner�x�A�wGet Up With It�x�A�wLive Evil�x�Ȃǂł��������i���ҏW�}�W�b�N�j�ɍł������B�e�I�����Ȃ���A�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v�Ƃ������ׂƂ��������|�p�͐��܂�邱�Ƃ͂Ȃ��������낤�B�}�C���X�̂ق��ɂ��A�Z���j�A�X�E�����N�A�`���[���Y�E�~���K�X�A�f���[�N�E�G�����g���A�r���E�G���@���X�A�f�C���E�u���[�x�b�N�A�T�C�������K�[�t�@���N���w���Ɓx�A���E���W�E���U�[�Y�ȂǑ���W�������ɘj���i�𐔑������삵�Ă����B2008�N�����B |
 |
Jimi Hendrix �i�W�~�E�w���h���b�N�X�j �X���C�ƕ��сA70�N��̃}�C���X�̉��y���ɑ傫�ȉe���͂������炵���W�~�E�w���h���b�N�X�̃p�t�H�[�}���X�B�f��u�����^���[�E�|�b�v�E�t�F�X�e�B���@���v�� �h�����w���h���b�N�X�h���ςĂ����}�C�X�����A���߂Đ��Ńw���h���b�N�X�̃X�e�[�W��ڂ̓�����ɂ����̂��A1969�N��A������70�N���U�ɂ����čs��ꂽ�t�B�����A�E�C�[�X�g�B�r���[�E�R�b�N�X�ib�j�A�o�f�B�E�}�C���X�ids�j�𗦂����o���h�E�I�u�E�W�v�V�[�Y�̃��C���������B�o�f�B�E�}�C���X�̉�z�ɂ��ƁA����ȃA���v�̎R�A���X�̃��E�E�y�_���ɐS��D��ꂽ�}�C���X�́A���̖�̊y���Łu���x��������ɂȂɂ���낤���v�ƌ����c�������A�w���h���b�N�X��70�N9���̑��E�ɂ��A�ŏI�I�ɋ����͎������Ȃ������B�܂��A�w���h���b�N�X���}�C���X�ɏЉ�������̑O�ȃx�e�B�E�f�C���B�X���A�}�C���X�Ƃ̌����������w���h���b�N�X�Ƃ��Ȃ�e���ȊW�ɂ��������Ƃ�i�܂����v���Ă����Ƃ������Ƃ����炩�ɂ���Ă���B |
 |
Prince �i�v�����X�j �W�~�w���A�X���C�ƕ��ԁu�}�C���X�̑n���ւ̃J���t���܁v�ƂȂ��������ׂ��u���U�[�B1982�N����A�o�b�N�E�o���h���u�U�E�����H�����[�V�����v�Ɩ��t���A����܂ł̃v�����X�P�Ɩ��`����v�����X�E�A���h�E�U�E�����H�����[�V�����ɕύX���A�uLittle Red Corvette�v�A�uDelirious�v�A�u1999�v�Ƃ������S�ăq�b�g�E�V���O�������^�����w1999�x�ł��悢��u���C�N���ʂ����B84�N�A�����f��̃T�E���h�g���b�N�Ƃ��āwPurple Rain�x�����\����A�v�����X�̃R�}�[�V�����I�ȉ��l�͒��_�ɁB���\���T��100������グ�����̃A���o���́A�r���{�[�h�E�`���[�g�̃g�b�v��24�T��������Â��A�V���O���E�J�b�g���ꂽ�uWhen Doves Cry�v�A�uLet's Go Crazy�v��2�Ȃ��V���O���E�`���[�g��1�ʂƂȂ�A�v�����X�͑S�Ăł̃{�b�N�X�E�I�t�B�X�A�A���o���A�V���O���E�`���[�g�ł��ׂ�1�ʂ��l������Ƃ����̋Ƃ�B�������B�S�Ă�1300�����A�S���E��1500������グ���wPurple Rain�x�̎��v�œƎ����[�x���ł���y�C�Y���[�E�p�[�N�E���R�[�h��ݗ��B���N���̃��[�x������wAround The World In A Day�x�\���A��������S�ă`���[�g��1�ʂ��l���B�܂��Ɏ���̒����ƂȂ����u�a���v�ɒ鉤���ڂ�t���Ȃ��킯���Ȃ��B��86�N�Ƀ��[�i�[�ɈڐЂƂȂ����}�C���X�ƃv�����X�͂��̔N��12���ɋ��R���T���[���X��`�ŏ��߂ďo��A��20���ԃ}�C���X�̑��}�Ԃɏ�荞��ʼn�b�����킵���Ƃ����B���̂킸��������A�v�����X�͔M�S�ȃ}�C���X�M�҂ł��������߂̃T�b�N�X�t�҃G���b�N�E���[�Y�ƃ}�C���X�̂��߂̃f���E�e�[�v����ɓ���A12��29���A�}�C���X�̃}���u�̕ʑ��ɁuCan I Play With U�H�v�Ƒ肳�ꂽ�A�h�炵���S�J�h�̃t�@���N�y�Ȃ��͂���ꂽ�B��86�N�ɂ̓}�C���X�̃g�����y�b�g�̃I�[�o�[�_�u���I���A�ŐV�A���o���uTutu�v�̃��X�g�Ɏ��^�����͂����������A�y�d��Ńv�����X�ɂ��u�҂����v�������肨������ƂȂ��Ă���B�܂��A�������v�����X�͂���1�ȁuA Couple of Miles�v�Ƃ����Ȃ������グ�Ă����Ƃ����B���Ȃ݂ɁA�}�C���X���ӔN�Ƀ��C���ʼn��t�����uAre You Regal Yet�H�v�A�uPenetration�v�A�uA Girl and Her Puppy�v�A�uJailbait�v�Ƃ������v�����X��̐V�Ȃ́A�a���̃W���Y�v�f�̋����ʓ��C���X�g�E�t�@���N�E�o���h�A�}�b�h�n�E�X�̌���3��ڂɎ��^�����\�肾�����Ƃ����B���҂̋����A���o�������Ƃ͂����Ȃ��������A87�N�̑�A���Ƀ��C���ň�x�A����Ƀ`���J�E�J�[����88�N�^����wC.K.�x�ŋ������ʂ�����Ă���B |
 |
Weather Report �i�E�F�U�[�E���|�[�g�j �u�}�C���X�E�t�@�~���[�v�̒��j�V�Ƃ������邾�낤���A��2���N�C���e�b�g�ȍ~1970�N�܂Ń}�C���X�E�O���[�v�ɍݐЂ��Ă����E�F�C���E�V���[�^�[�ƁA�wIn A Silent Way�x���͂��ߏ����G���N�g���b�N�E�}�C���X�ւ̍v���x���傫���W���[�E�U���B�k����2�l�����S�ƂȂ�A�h���}�ɃA���t�H���X�E���[�]���A�p�[�J�b�V�����ɃA�C�A�[�g�E�����C���ƃh���E�E���E���}���A�x�[�V�X�g�Ƀ~���X���t�E���B�g�E�X���}����1971�N�Ɍ��������O���[�v�B���̏�����i�́A�}�C���X�́wBitches Brew�x�̉�������ɂ���A������\�Ɉӎ������T�E���h�ɂȂ��Ă������A3��ڂ́wSweet Nighter�x�̎�������A�t�@���N�E�O���[���̗v�f���̂�������悤�ɂȂ�A���B�g�E�X���A�R�[�X�e�B�b�N�ɉ����ăG���N�g���b�N�E�x�[�X��p�ɂɎg���悤�ɂȂ����B74�N�Ƀx�[�V�X�g�����B�g�E�X����A���t�H���\�E�W�����\���ւƌ��B�U���B�k���ɂ��V���Z�T�C�U�[���p������A���z�I�ŐV���ȃO���[���ƃT�E���h�������炳��鎖�ɂȂ����B75�N�́wBlack Market�x���쎞�ɂ̓W�����E�t�@���N�E�Z�b�V�������M��тсA���̔N���g�̃\���E�f�r���[�E�A���o���\��������̃W���R�E�p�X�g���A�X���A���o������㔼�ŎQ�����邱�ƂɂȂ����B �A���b�N�X�E�A�N�[�j���ids�j�A�}�m���E�o�h���i�iper�j���}������A76�N�̃����^���[�E�W���Y�E�t�F�X�e�B�o���ւ̏o���Ȃǂ��܂߂āA�E�F�U�[�E���|�[�g�̓O���[�v�Ƃ��Ē��_�Ɍ������͂��߂��B77�N�́wHeavy Weather�x�A79�N�̃L���[�o�u�n�o�i�E�W�����v�ւ̎Q���A80�N�A���o���wNight Passage�x���\�Ƃ܂��ɐl�C�Ⓒ��81�N�ɃW���R���E�ށB���̌�́u�t���[�W�����v�V�[�Y���̎����X��������O���[�v�͎����B86�N�ɉ��U���Ă���B |
 |
Return To Forever �i���^�[���E�g�D�E�t�H�[�G���@�[�j ������́u�}�C���X�E�t�@�~���[�v�̎��j�V�H �}�C���X�wIn A Silent Way�x�A�wBitches Brew�x�ŃL�[�{�[�h��e���A�G���N�g���b�N�E�W���Y���t������S�����`�b�N�E�R���A���A�����X�^���E�Q�b�c�̃o���h�ȂǂŊ������Ă����x�[�V�X�g�A�X�^�����[�E�N���[�N��U���A���̑���������}�C���X�E�O���[�v�̖��F�A�C�A�[�g�E�����C���ids�j�Ƃ��̉����t���[���E�v�����ivo,per�j�A�W���[�E�t�@�����isax,fl�j������1972�N�Ɍ����������^�[���E�g�D�E�t�H�[�G���@�[�B�`�b�N�E�R���A�̃\�����`�����A�����I�ɂ̓o���h�Ƃ��Ẵf�r���[��ƂȂ������NECM���甭�\���ꂽ�wReturn to Forever�x�A����ɂ́A��73�N�́wLight As a Feather�x�����̃C���g���Ƀz�A�L���E���h���[�S�u�A�����t�G�X���t�ȁv�̃����f�B��}�������uSpain�v�ň���S����ɁB�A�C�A�[�g���t���[���v�ȁA�W���[���E�ނ��A�r���E�R�i�[�Y�ig�j�A���j�[�E�z���C�g�ids�j�����������o�[�Ɍł܂�����2���ł̓��b�N�F�����܂�A�R�i�[�Y�E�ތ�A�A�[���E�N���[�ig�j�̈ꎞ�I�Q�����o�ăA���E�f�B�E���I���ig�j����������74�N�́w��͂̋P�f�x�ɂ����āA�������ƌĂ�郉�C���i�b�v�������B����75�N�́wNo Mystery�x�́A�O���~�[�܁u�x�X�g�E�W���Y�E�C���X�g�D�������^���E�p�t�H�[�}���X�i�O���[�v�j�v����܂����B76�N�ɃR�����r�A�ɈڐЂ����o���h�́w�Q���̋R�m�x�\����q�b�g��������A�f�B�E���I���A���j�[���E�ށB�W�F���[�E�u���E���ids�j�A�`�b�N�̍Ȃ̃Q�C���E�������ivo,key�j�A���������o�[�̃W���[�E�t�@�������}���A����Ƀz�[���E�Z�N�V�������������Ґ���77�N�ɁwMusicmagic�x�\��������N���U�����Ă���B82�N�Ƀf�B�E���I���ݐЎ��̃��C���i�b�v�ōČ������ʂ����A�����2008�N�ɂ͍āX�����������B���N5���̑S�ċy�щ��B�c�A�[�̖͗l��2���g�̃A���o���܂���DVD�wReturns�`Reuinon Live�x�Ƃ��Ĕ��\���ꂽ�B |
 |
John McLaughlin �i�W�����E�}�N���t�����j �C�M���X�A���[�N�V���[�E�h���J�X�^�[�o�g�̃M�^���X�g�A�W�����E�}�N���t�����́A1969�N�ɓn�āB�g�j�[�E�E�B���A���X�̃��C�t�^�C���ɎQ����A�}�C���X�E�O���[�v�ɓ��c�B�wIn A Silent Way�x�A�}�N���t�����̖����^�C�g���œ����Ă���i�������A�}�C���X�͕s�Q���j�wBitches Brew�x�A�wOn The Corner�x�A�����ă}�N���t�����̓����̐�D���Ԃ��@���Ɍ����wA Tribute to Jack Johnson�x�܂łɎQ�������B70�N�����̃}�C���X�E�T�E���h�̏ے��Ƃ�������}�N���t�����̃v���C���A�}�C���X���ufar in�i���[���j�v�ƕ\�������̂͗L���ŁA���Ȃ荂���]����^���Ă����B�}�C���X�E�o���h���E��́A1971�N�ɁA�C���h���y�ɌX�|���͂��߂�2��ڂ̃\���E���[�_�[��wMy Goal's Beyond�x�i���̌�q���h�D�[���ɉ��@�j�\�B����ɂ́A�����E�n�}�[�ikey�j�A�r���[�E�R�u�n���ids�j��e�N�����̐��s��Ǝ��ȃo���h�̃}�n���B�V���k�E�I�[�P�X�g���������B���N��1st�A���o���w���ɔ�߂����x�\���A70�N��̃W���Y�E���b�N�E�V�[�������������B |
 |
Alice Coltrane �i�A���X�E�R���g���[���j �̋��f�g���C�g�Ŏ��Ȃ̃g���I�⃔�B�u���t�H���t�҂̃e���[�E�|�[�����h�ƃf���I��g��Ńv���Ƃ��Ċ������n�߂��A���X�E�R���g���[���B1962�N����63�N�ɂ����ăe���[�E�M�u�X�̃J���e�b�g�ɂ��Q�����A���̊ԂɃW�����E�R���g���[���Əo��B65�N�Ƀ}�b�R�C�E�^�C�i�[�ɑ���A�W�����̃O���[�v�ɎQ���B���N�ɃW�����ƌ������邪�A67�N�ɃW�����͊̑����ׂ̈ɖS���Ȃ�B�ނƂ̊Ԃɂ́A�W�����E�W���j�A�i���j 1982�N�����j�A�T�b�N�X�t�҂̃����B�E�R���g���[���A�T�b�N�X�^�N�����l�b�g�t�҂̃I�����E�R���g���[��������B�n�[�v�݂̂����t���Ă���Ǝv��ꂪ�������A�s�A�m�A�I���K���A�V���Z�T�C�U�[�e�팮�Պy������t�B�S���v�̈�u���p���Ȃ�����Ǝ��̓��m�v�z�Ɋ�Â����V�㐢�E��z���グ��Impulse!����̑�\�I�ȃ��[�_�[�E�A���o���́A�ߔN��DJ�I���_����wA Monastic Trio�x�A�wPtah, the El Daoud�x�A�wWorld Galaxy�x�Ȃǂɒ��ڂ����тĂ���B2003�N�ɂ͌Ñ�Impulse!����26�N�Ԃ�ƂȂ�V��wTranslinear Light�x�\���b��ƂȂ����B2007�N�ċz�s�S�Ŏ����B |
 |
Wynton Marsalis �i�E�B���g���E�}���T���X�j �u�W���Y�E�A�b�g�E�����J�[���E�Z���^�[�v�̌|�p�ē߂�ȂǁA�E�B���g���E�}���T���X�́A�W���Y�E�p�t�H�[�}���X�ƍ�Ȃ̋Z�p�A�������ꂽ�X�^�C���A�W���Y�ƃW���Y�̗��j�Ɋւ���ڂ�������m���A�܂��N���V�b�N���y�̖����t�Ƃł��邱�Ƃɂ���āA����W���Y�̐��E�ōł����������Ă���~���[�W�V�����̂ЂƂ肾�낤�B�j���[�I�[�����Y�o�g�ŁA���̓s�A�j�X�g�̃G���X�E�}���T���X�A�Z�̓T�b�N�X�t�҂̃u�����t�H�[�h�E�}���T���X�Ƃ����R�����������y��ƂɈ�����E�B���g���́A1978�N�ɃW�����A�[�h���y�@�֓��w�B80�N�ɂ́A�킸��18�ŃA�[�g�E�u���C�L�[&�W���Y�E���b�Z���W���[�Y�ɉ������A�v���Ƃ��Ă̊������J�n�B81�N7���A�n�[�r�[�E�n���R�b�N�̃o���h�́uLive Under The Sky�v�i���c���R���V�A���j���s����Ƃ��ď��������ʂ����A���N�o���h�E���[�_�[�Ƃ��āwWynton Marsalis�x�Ńf�r���[�B�`���I�ȃA�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y���p�������^�V�l�Ƃ��Ęb��ƂȂ�A���̌�N���V�b�N���y�̑t�҂Ƃ��Ă��������J�n���Ă���B���̏��������ɁA���R���́A���������ă}�C���X�����A����Ƃ��ĕ������wThe Man With The Horn�x�̊��z��SJ���̊��̈�Ƃ��Đu���ɃE�B���g���̏h�ɂɑ����^���������A���̑��]�����U�X�ȁE�E�E |
 |
Dr. Dre �i�h�N�^�[�E�h���[�j ����܂Łu��������v�������S�Ẵq�b�v�z�b�v���͐}��h��ւ������C�݃q�b�v�z�b�v��G�t�@���N�E���[�������g�̊J�c�ɂ��āA���݂ɂ����Ă��ł��e���͂�����A�ł��������A�ł��L���ȃv���f���[�T�[�̂ЂƂ�ł���A�h�N�^�[�E�h���[�B80�N��̃��[���h�E�N���X�E���b�L���E�N���[�A90�N���N.W.A.�ł̊�����A91�N�ɃV���O�E�i�C�g�Ƌ���Death Row ���R�[�h��ݗ��B92�N�ɂ́A���̃\���E�V���O���uDeep Cover�v�A�\���E�f�r���[�E�A���o���wThe Chronic�x�\�B���ɁA�܂��f�r���[�O�̃X�k�[�v�E�h�M�[�E�h�b�O�i���X�k�[�v�E�h�b�O�j���X�I�Ƀt�B�[�`���[�B�A���o���́A�}���`�E�v���`�i�ƂȂ�A���j��ł����ꂽ�q�b�v�z�b�v�E�A���o���̂ЂƂƂȂ����B93�N�ɂ́A�X�k�[�v�̃f�r���[�E�A���o���wDoggystyle�x���v���f���[�X�B���A���o���́A���̃r���{�[�h�E�`���[�g1�ʃf�r���[�Ƃ������ٓI�ȃq�b�g���L�^�����B96�N�ɂ́A2�p�b�N�́uCalifornia Love�v���v���f���[�X���A������q�����邱�Ƃő�q�b�g�B����ɂ��A�f�X����E�A�����ăh���[���g�̉��y�ƊE�ł̗��ꂪ�m�ł�����̂ƂȂ������A���N����2�p�b�N�̏e�����ɒ[�������[�x�������̊�@���@�m���ADeath Row��E�ށB����̎��Aftermath Entertainment�𗧂��グ���B����������������Ă������̂́A98�N�Ƀf�g���C�g�̃��b�p�[�A�G�~�l���ƌ_�����ƂŃ��[�x���ɓ]�@���K�ꂽ�B�G�~�l���̃��W���[�E�f�r���[�E�A���o���wThe Slim Shady LP�x����2004�N�wEncore�x�Ɏ���܂łɐ���Ɋ֗^���A�����͂���Ȃ������X�^�[�E�q�b�g���L�^�����B2003�N�ɂ̓N�C�[���Y�̃��b�p�[�A50�Z���g�̃��W���[�E�f�r���[�E�A���o���wGet Rich Or Die Tryin'�x���G�~�l����ƃv���f���[�X����q�b�g�����Ă���B�h���[���g��2���ڂ̃A���o���w2001�x��99�N�ɔ��\����A�X�k�[�v���t�B�[�`���[�����uThe Next Episode�v����q�b�g�B���̒��Ő��̍����h�[�v�E�r�[�g�������u��E�F�b�T�C�E�u�[���v�̉Εt�����ƂȂ������Ƃ��ؖ������B�h���[���g�̍Ō�̃A���o���Ɖ\����Ă���wDetox�x�́A�ŏ��̃����[�X�E�A�i�E���X����6�N�Ƃ�������������Ă��܂������A2010�N���A���ɐ�����s�V���O���uKush�v�ifeat. �X�k�[�v�E�h�b�O���G�C�R���j���͂���ꂽ�B |
 |
Dave Holland �i�f�C���E�z�����h�j ���Ɍ����h���X�g�E�N�C���e�b�g�h�ɍݐЂ��Ă����C�M���X�̔��l�x�[�X�^�R���g���o�X�t�҃f�C���E�z�����h�B 1968�N���ď���߂���ƁA�傫���ϖe�����}�C���X�̉��y�Ƀ����E�J�[�^�[�̃x�[�X�͒ǂ������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B�w�L���}���W�����̖��x�ɂ�����uFrelon Brun�v�̎���͊��S�Ƀf�C���E�z�����h�̐��ݏo���t�@���L�[�E�O���[���ł���A���ڂ̃o���[�h�uMademoiselle Mabry�v�ɂ����Ă��D�L�����Y���E�A���h�E�u���[�X���̔S�肪�j�ƂȂ��Ă���B�x�[�X�������E�J�[�^�[����z�����h�ɑ��������_�ŁA�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v�̗��H�͎n�܂����ƌ���t�@���������̂ł͂Ȃ����낤���H �}�C�P���E�w���_�[�\���ɂ��̑������ꂽ�d���̂��������n�����70�N6�����܂ŁA�z�����h�́u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v�̃{�g�����u���v�u�d�C�v�̗����ł�������Ǝx���Ă����B�O���[�v�E�ތ�́A�`�b�N�E�R���A�A�o���[�E�A���g�V�����A�A���\�j�[�E�u���N�X�g����ƃT�[�N���Ƃ����O���[�v���������AECM����A���o���������[�X���Ă���B�ŐV���[�_�[��́A���r���E���[�o���N�X�itb�j�A�l�C�g�E�X�~�X�ids�j�狭�̓����o�[�𑵂����I�N�e�b�g�Ґ��^���́wPathways�x�B |
 |
Chick Corea �i�`�b�N�E�R���A�j 1968�N�̕�ꂩ��n�[�r�[�E�n���R�b�N�ɑւ��}�C���X�E�O���[�v�ɉ��������`�b�N�E�R���A�B�f�C���E�z�����h���l�w�L���}���W�����̖��x�ɂ�����uFrelon Brun�v�ƁuMademoiselle Mabry�v�̘^������Q���B�wIn a Silent Way�x�A�wBitches Brew�x�Ȃǂ̃A���o���ł́A�}�C���X�̎w���ŃG���N�g���b�N�E�s�A�m�i�t�F���_�[�E���[�Y�j��e���悤�ɂȂ�B�܂����t�ʂɂ����Ă��A�A�o���M�����h�ȃA�v���[�`��������悤�ɂȂ��Ă���A�u�t�B�����A�v�A�u�^���O���E�b�h�v�A�u���C�g���v�ɑ�\����邱�̎����̃}�C���X�E�O���[�v�̃��C���Œ������`�b�N�̃\���́A���Ȃ�t���[�̗v�f�������B70�N7���ɃO���[�v��E�ނ�����A�x�[�X�̃f�C���E�z�����h�A�h�����̃o���[�E�A���g�V�����ƃT�[�N���������B��ɃT�b�N�X�̃A���\�j�[�E�u���N�X�g���������t���[�E�W���Y���̉��t��W�J�B71�N�ɂ̓X�^�����[�E�N���[�N��U���ă��^�[���E�g�D�E�t�H�[�G���@�[���������A�v�V�I�ȉ��y���Ƒ�z�������t�Z�p�ɗ��ł����ꂽ���̃o���h�́A���X�̍�i�ݏo���A�g�b�v�E�A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă̒n�ʂ��m������i�ȉ��A���^�[���E�g�D�E�t�H�[�G���@�[�͎̏Q�Ɓj�B |