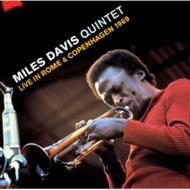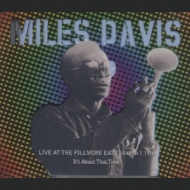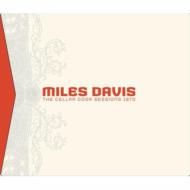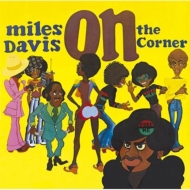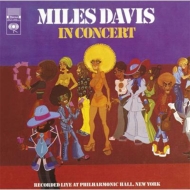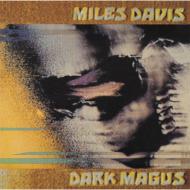�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v ���R�N������ɐu�� �q2�r
Thursday, July 29th 2010

- ---�@�X���C��W�~�w���Ƃ̊W�ɂ��b��߂����Ă��������܂��āA�}�C���X���C�ɓ����Ă����X���C�A�W�~�w���A���邢�́A�v�����X�̉��y�ɂ͖��m�ȉ́��̎��Ƃ������̂������āA���b�Z�[�W������₷���`���Ƃ��낪����Ǝv���̂ł����A����ŁA�}�C���X�̉��y�ɂ͈ꕔ�������āA�̎��A�̂Ƃ������̂����݂��܂���B�̎��܂��͉̎�ɂ��āA�}�C���X�͂ǂ������������������Ă����̂ł��傤���H
�@�肩�ł͂Ȃ���ł����E�E�E�Ⴆ�A1981�N�́wThe Man With The Horns�x�ɉ̎�����̊y�ȁi�uThe Man With The Horns�v�j������܂���ˁB ���̋ȂɊւ��ẮA�}�C���X���{���ɍD���ł����Ȃ����̂��ǂ����͎��۔���Ȃ���ł���B����̒��Ō��ʂ������������Ɏd�オ���������Ƃ������Ƃ����肦��̂ŁB
�@���������}�C���X�́A�������u�̎�v���Ǝv���Ă��܂�������ˁB�u���͉̂��g�����y�b�^�[���v�Ƃ�������������܂�������A�̎���t����Ƃ��A�̎���g���ĉ̂킹��Ƃ��A���̔��z�͂Ȃ������Ǝv����ł���B��������Ƃ����ɂ���Ă����͂��ł���ˁB
�@�����A�̂��肻�̂��͍̂D���Ȃ�ł���B�Ȗ��ɂ��Ȃ����i���j�E�B���[�E�l���\���A�i���j�t�����N�E�V�i�g���A�ӔN�ɂ��i���j�A���E�W�����E���Ƃ��B�ނ�̉̂��āA�t���[�W���O���w��A�����ꂽ��A�t�Ɂu�����͉��̉e�����Ă�ȁv�Ƃق����肵�Ă����Ǝv����ł���i�j�B
�@���ي��ɁA�j���[���[�N�Ńt�����N�E�V�i�g���̃R���T�[�g������ƕ������}�C���X�́A�}�l�[�W���[�ɘA��čs���Ă�����āA�V�i�g���Ɖ��ł���B�����ŁA�V�i�g���A���邢�̓V�i�g���̃v���f���[�T�[���N�����u�ꏏ�ɂ��܂��H�v�Ƌ��������������������Ȃ�ł��B����ƁA�u���̕K�v�͂Ȃ��v�ƃ}�C���X�͒f���ł���B�t�B�����A�ɏo�����Ă���70�N�ɂ��A���[���E�j�[���̃��R�[�f�B���O�ɌĂ���ł����A���[���̉̂��āA�u�����ɉ��͕K�v�Ȃ��v�Ɣ��f�����ł��B�W���j�E�~�b�`�F���̏ꍇ�ɂ��Ă������B- ---�@�u�ޏ������̐��E�ŏ\�����v�ƁB
�@�u�������t����������̂͂Ȃ��v�ƁB���������Ӗ��ł��A�~���[�W�V�����E�V�b�v�ɂ����Ĕ��Ƀt�F�A�Ȑl�������Ǝv����ł���ˁB����̗L�������A�N��A�L�����A�A�܂��Ă�W��������l��I�Ȃ��Ƃ͈�؊W�Ȃ��Ƃ���őn�����Ă����낤�ȂƎv����ł���B����̓~���[�W�V�����̗��z�ł������ł����A�Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ����Ƃł�����B�������������ŁA�����܂œO�ꂵ�Ă����l�Ƃ����̂́A�قƂ�ǂ��Ȃ�������Ȃ����ȂƎv���܂��B
- ---�@���Ɏ��~���[�W�V�����̍˔\���������͔͂��Q�ł���ˁB
�@�wThe Man With The Horns�x�ŋN�p�����p�[�J�V���j�X�g���i���j�T�~�[�E�t�B�K���A�́A���X�`���J�E�J�[���ƈꏏ�ɂ���Ă����l�Ȃ�ł��ˁB�}�C���X�̓`���J����D���ŁA�ޏ��̃f�r���[�E�A���o���w������`���J�x����������イ�����Ă����B���̃A���o����1�Ȃ����t�B�K���A���t�B�[�`���[����Ă��āA����1�Ȃ̂�����Ƃ����������āA�u�悵�A�������g�����v�ƂȂ����炵����ł���B���̎��͂������Ǝv���܂��B���̂��Ƃ܂��Ă��̋Ȃ��Ă݂Ă��A�����đ債�����Ƃ͂Ȃ���ł����A�}�C���X�ɂƂ��ẮA�����g�債���h���Ƃ���������ł���ˁB
�@���������Ӗ��ł��A�u�v���^�����Ă��A�����ɂ͂��ꂪ������Ƃ͌���Ȃ���ł���B- ---�@�Ȗ��Ɂu�i���j�W�����E�}�N���t�����v�A�u�G���g�D�[���v�A�u�E�B���[�E�l���\���v�A�u�i���j�r���[�E�v���X�g���v�Ɖ��̃q�l�����Ȃ����t���邠������A�����ȃ~���[�W�V�����E�V�b�v�̋������ꂩ�ȂƁB
�@���܂���ˁi�j�B���ʂ̊��o�ł����ƁA�Ȃ�Ń}�C���X���u�E�B���[�E�l���\���v�Ƃ����Ȗ���t����H �������Ă���̂��H �ƁA������Ǝא����Ă��܂�����Ȃ��ł����B�Ƃ��낪�܂����������ł͂Ȃ��āA���Ƀt���b�g�Ȃ�ł���i�j�B�t�ɁA���ɂ��l���Ă��Ȃ��Ƃ������i�j�B���y�ɑ��Ĕ��Ɏ����Ȃ�ł���ˁB
- ---�@�������A���̎���ȑO�Ɉ�x�u�������v�������āA�Ƃ������Ƃł�����ˁB
�@�����̗���A�����A���Y���Ƃ������ׂđ䖳���ɂ������Ȃ��Ƃ��������Ă���킯�ł���i�j�B����Ȃ��Ɣ����Ă��Ă�����Ă��܂��B���������̂��{���̃A�[�e�B�X�g���Ƃ͎v����ł����A���ʂ͂Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��ł���ˁB
- ---�@�̂����g���Ă܂ŁA�Ƃ����̂�����ɉ����āB
�@�����Ȃ�ł���B������A�R���T�[�g���ł��邾���L�����Z���͂������Ȃ��B����f���Ăł��X�e�[�W�ɗ��B���ɐ̋C���Ȃ�ł���ˁB�ł��A����Ă��鉹�y�͍Ő�[�Ȃ�ł���i�j�B�܂��Ƀr�E�o�b�v�ƃq�b�v�z�b�v�����������Ă���悤�Ȋ����ŁA�����͂ǂ�ǂ�c��݂]�����Ă����B�����65�N�̐��U�������Ǝv����ł���B������A�}�C���X�Ɏ����l�Ƃ����̂͂���ς肢�Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
- ---�@�\�w�I�Ɏ����T�E���h���o���Ă���l�Ƃ����̂́A�����̂����Ȃ肢��Ƃ͎v���̂ł����A�����܂Ń~���[�W�V�����E�V�b�v�ɒ����āA�Ȃ�����Ɋv�V�I�ȃT�E���h�����߂āA����ݏo�������Ă���Ƃ����l�͂Ȃ��Ȃ����Ȃ��ł���ˁB�����l����ƁA���ɂ��̎���̃}�C���X�́A�����̃}���`�E�J���`���[���ׂĂ����ݍ���ł����̂ł́H �Ƃ����C�������Ă��܂��B
�@����ɁA�l�ԓI�ɂ��������͓I�Ȃ�ł���ˁB�����`�Ȃ�ǂނƁA18���炢�Ńj���[���[�N�ɏo�Ă��āA�݂�ȂɍD����Ă���킯�Ȃ�ł���B�Ⴆ�A�u�i���j�Z���j�A�X�E�����N����A�}�b�`���ɃR�[�h�i�s�������ċ����Ă�������v�Ƃ��B ����Ȃ́g�J�}���h����A�Ƃ݂�Ȏv������Ȃ��ł����H�i�j �Ƃ��낪�A�}�C���X�Ɏ��ۉ�����l�Ɍ��킹��ƁA�����������b���S���{�����Ǝv����قǁA�u�C�C�l�v�Ȃ�ł���B�������A�ꗬ�̃A�[�e�B�X�g������A�����ɂ����ʂ�����Ƃ͎v����ł����A�������`���[�~���O�Ȑl�Ȃ�ł���ˁB
�@�l���}�C���X�Ɠ��ɐe�����Ȃ����̂́A55�`65�A�Ō��10�N�Ȃ�ł��B������A�Ⴂ���݂����ɐ���Ă���悤�Ȃ��Ƃ��قڂȂ���ł���B�l�����̓����̂��Ƃ����܂菑���Ȃ��̂́A�t�̈Ӗ��Ń}�C���X�̃C���[�W������Ă��܂��̂�����Ă��邩��Ȃ�ł���B- ---�@�}�C���X�ɑ��鍋���Ŗz���Ȑ��Ԃ̃C���[�W�����Ă��܂��B
�@�D�������āi�j�B���͂ƂĂ����V�Ȑl�Ȃ̂ŁA���ɑ��Ă����ӂ������ē����悤�Ƃ����ł��B�u�}�C���X�E�f�C���B�X�Ȃ̂ɁE�E�E�v�Ƃ��������v���Ă��܂��قǁB������A���̎����́A�u�}�C���X��^�v�I�Ȕ������Ȃ���ł���B�����A��ނʼn�ƁA�T�[�r�X���_�����Ȑl�Ȃ̂ŁA�L���b�`�E�R�s�[�I�Ȃ��Ƃ͌����Ă�����ł��ˁB�{�S���ǂ����͂��Ȃ�^��Ȃ�ł����ǂˁi�j�B
�@�܂��A���Ԉ�ʂł́A�u�C���^�r���[�����v���Ƃ������Ă��܂����A���������ꍇ�͑��A�����肪�}�C���X�̉��y�������ƒ����Ă��Ȃ���ł���B�}�C���X�͂���������������B��������Ɩق��ł���ˁB���邢�́A�uMy Funny Valentine�v��uSketch Of Spain�v�̍��̘b�������Ȃ��l�������ł���B���������Ƃ����}�C���X�́A�Ȃ�ƂȂ����݂����ɂȂ��ł��i�j�B
�@���{�ł������Ǝv����ł����ǁA�����肪�u�}�C���X�����킪�t�v�݂����ȃm���Řb�������ł���B��������ƁA�wBitches Brew�x�܂łȂ�܂������A�}�C���X�������ݎ��g��ł��鉹�y�̂��ƂɒN���G��Ă���Ȃ��B���̓����̍ŐV��Ƃ��B�u���̎��wCookin'�x���悭�����Ă��܂����v�Ƃ��A�u���̐l���ɂ��Ȃ��͂ǂ�قǂ̉e�����E�E�E�v�݂����Ȃ��Ƃ����茾���킯�ł���ˁi�j�B�����Ȃ�ƁA�}�C���X�͌��\�V�������ł���i�j�B�����Ń}�C���X���v���C�h�����邩��A�u������O����B���̓}�C���X�E�f�C���B�X�Ȃ��v�݂����ȑԓx���킴�Ǝ��Ƃ��������ł���i�j�B����͖T���猩�Ă���ƁA�`���[�~���O�ł͂����ł����ǂˁB�ł��Ⴆ�A�u���[�����O�E�X�g�[���v���̎Ⴂ�L�҂Ȃł��A�����ƍ�i���Ă�����A���邢�͉s���c�b�R�~����ꂽ�肷��ƁA�}�C���X�͂�������Ԃ�ł���i�j�B- ---�@�ӔN�Ƃ����̂́A��ɎႢ����̃~���[�W�V������A�V�������y�̘b�����Ă����̂ł����H
�@���������b�������Ȃ���ł���ˁB
- ---�@�ނ���G���N�g���b�N���ȍ~�A���ɂ͏�Ɏ������͂邩�ɎႢ�~���[�W�V������u���Ă����̂́A�����������R����Ȃ̂�������܂����ˁB
�@���ƁA�}�C���X�ɂƂ��ėB��̉Ƒ��́A���������o���h�̃����o�[��������Ȃ����ȂƎv����ł���ˁB������o�����Ȃ͂���킯�ł����ǁA�ނ��낻���̊W�͂��Ȃ�������̂ł͂ƁB�Ƃɂ����o���h�̃����o�[���������Ƃł���A��ɐM�����ł���B�Ⴆ�A�̒��������Ƃ��ɁA�����o�[�Ɂu���������I���Â͂悭��������A�ł����ق��������ł���v�Ȃ�Č�����ƁA�����s���B�u�������̃��C���͔��������v�ƂȂ�Ƃ��������i�j�B�u���̃T�b�N�X�͂����v�ƂȂ�Ƃ��������B�܂������^���]�n���Ȃ��B���ɂ́A�N�r�ɂ�����A�M�����ŝ��߂��肵�������o�[�Ȃ͂����Ǝv����ł����A�N�Ƃł���l�ɕt���������ł���ˁB
�@���ي��̃G�s�\�[�h�Ȃ�ł����A�}�C���X�̉��ɂ�����A��̃J���o�b�N���菕�����邱�Ƃɂ��Ȃ�h���}�[���i���j���B���X�E�E�B���o�[���̗F�l�ɁA�O�����E�u���X�Ƃ����T�b�N�X�t�҂�������ł��ˁB����Ƃ��A���B���X�Ƃ��̃O�������A�V�J�S����j���[���[�N�ɗV�тɗ�����ł��B���B���X�̓}�C���X�̉Ƃɔ��܂�A�O�����͂ǂ����ߏ�̈����z�e���ɔ��܂�B�������āA�O�����̓��B���X�Ƀ}�C���X���Љ�Ă��炢�A�ꏏ�ɃZ�b�V����������H�������肷��悤�ɂȂ��ł��ˁB�ŁA���B���X�͐�ɃV�J�S�ɋA��B������A�O��������}�C���X�Ɂu���̓x�͂����b�ɂȂ�܂����B�l���z�e���オ�Ȃ��Ȃ����̂ł��낻��V�J�S�ɋA��܂��v�Ƃ����d�b�������������Ȃ�ł���B����ƃ}�C���X���u�E�`�ɗ����v�A�u�D���Ȃ�������v�A�����āA�u�T�b�N�X�𐁂��v�ƌ����������Ȃ�ł���B�}�C���X�͂����������Ƃ��ł���l�Ȃ�ł���ˁB�������A�O���������M�����[�E�����o�[�ɋN�p���ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B������A���R�[�h�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��~���[�W�V�����𗬘^�݂����Ȃ��̂́A���̂��������L����ł���B- ---�@ �l����� �g�Ȃ��Ȃ��h �ɂ͂Ȃ�Ȃ���ł��ˁB
�@�������A�܂��Ƀ}�C���X�E�f�C���B�X�B�������������ł́A�u�ߋ���U��Ԃ�Ȃ��v�Ƃ����g��ɂ����ʂ��Ă���p�����Ǝv���܂����A�Ȃɂ��A���y�͓��ʂȗ̈�ɂ���ׂ����̂��Ƃ����l�������������莝���Ă�����Ȃ��ł��傤���B
�@���B���X��E�B���o�[�����}�C���X�ɔ��F����āA�悤�₭�n���V�J�S�ŗ��A���������������Ƃ������O�ɁA�}�C���X�̓��B���X���N�r�ɂ����ł��ˁB���B���X�̕�e�A�܂�}�C���X�̂��o����́A�u���߂č��x�̃V�J�S�����܂ł̓����o�[�ɂ������Ă����āB�F�B�������ς�����̂�v�ƃ}�C���X�ɋ����Ă��肢�����ł���i�j�B�ł��A�������Ȃɋ��ۂ���킯�ł�����ˁB
�@�����������b�ړI�ɂ��ԐړI�ɂ��������肷��ƁA���h�Ȑl���N�w���ȂƁB�P�Ȃ�W���Y��~���[�W�V�����ł��Ȃ����A�P�Ȃ�ϐl�ł��A���l�ł��Ȃ��i�j�B�����ǂ���̂Ȃ������́A���ꂪ�}�C���X�E�f�C���B�X�Ȃ�ł���ˁB- ---�@�������A�����ł��Ɛl�Ԃ������B
�@���̏�A�O���邱�Ƃ̂Ȃ����y�����ꂾ���c���Ă���B�l���A�r�[�g���Y�Ƃ��{�u�E�f�B�����Ƃ��A�F�X�ȃ~���[�W�V�����Ɣ�r���Ă݂��肷���ł����A����ς�ŏI�I�Ƀ}�C���X�������c���Ă䂭��ł���ˁB
�@���̖{�̍Ō�ɁA�}�[�N�E���X�o�E���Ƃ��������̃}�l�[�W���[�̔��������������p���čڂ��Ă����ł����A�g��Ȃ��������Ɂu�}�C���X���Ăǂ�Ȑl�H�v�Ǝ��₳��āA���X�o�E���������Ă�����̂������ł���B�u�N�����A�n����ɂ��邷�ׂĂ̐l�ԂƉ���Ƃ͂ł��Ȃ�����ǁA���ɉ�����Ƃ���Ń}�C���X�E�f�C���B�X�̂悤�Ȑl���́A�����}�C���X�ЂƂ肵�����Ȃ����낤�v�ƌ����킯�ł���B��Ԑg�߂ȃ}�l�[�W���[�������������炢�Ȃ�ŁA�������قȑ��݊�������Ă�����ł��傤�ˁB- ---�@�}�C���X�́A�u�u���b�N�E�q�[���[�v�Ƃ������������������������ł����A���L���𗬘^�̒��ł́A�����悤�Ȏ����������Ă����ƌ��������ȃ{�u�E�}�[���[�A�t�F���E�N�e�B�Ƃ������A���Q�G�A�A�t���E�~���[�W�b�N�̃A�C�R���ƐڐG���Ă����\���Ƃ����̂͂���̂ł��傤���H
�@ ���Q�G�ł͂Ȃ���ł����A�J�b�T�u�Ƃ����t�����`�E�J���r�A���̃o���h�̃��R�[�h�͍D��ł悭�����Ă��������Ȃ�ł���B�N���ɑE�߂��Ē����n�߂��Ǝv���܂����B
- ---�@�}�C���X�����ق��Ă���76�N���炢�ɂ́A�{�u�E�}�[���[�͂��ƕp�ɂɃj���[���[�N�̃A�|���E�V�A�^�[�Ń��C�����s���Ă��܂���ˁB�����ʼn�������̃R���^�N�g�͂������̂��ȁH �Ǝא����Ă��܂��̂ł����B
�@�������ςɍs���Ă���\���͂���܂���ˁB��������𗠕t����\���ȏ؋����Ȃ���ł���ˁB
�i���ҏW���j �wOn The Corner�x�̉��̊������݂����Ȃ��̂́A�����̃u���b�N�E�~���[�W�b�N�̒��ł������������^�C�v�̂��̂��Ǝv������ł����A���ɍł��߂��̂��ȁH �ƍl�����Ƃ��ɁA���Q�G�̃X�^�W�I�E�����Ȃ̃T�E���h�����������ɏ������Ă���̂��ȁH �ƁB�ǂ���������Ƃ肵�Ă��Ȃ��B
�@����I�ȕ������傫���̂�������܂����ˁB
 |
|
���[���E�j�[�� �w�C�[���C��13�Ԗڂ̜����x�̃u�b�N���b�g���
|
 |
|
�����ق荞�ޒ鉤�E�E�E�H
|
 |
|
1987�N�̃X�e�[�W�B������ �}�C���X(����61��)��~�m��V�l��(30��)��{�r�[��u���[��(26��)��P�j�[��M�����b�g(27��)
|
�u�G���N�g���b�N�E�}�C���X�v��20��
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
�y�~���u�K�z ��}�C���X ��Ղ̃��X�g�E�C���[�Y� ���R�N������ɐu��
-
��}�C���X�E�f�C���B�X ��Ղ̃��X�g�E�C���[�Y� ���R�N������ɐu��
��Ղ̃J���o�b�N���ʂ������鉤����������Ȃ�r��B�u�d���}�C���X�v�u�K�Ɉ��������A���R�N����������}�����Ă�����u�}�C���X�̉ؗ�Ȃ郉�X�g�E�C���[�Y�v�ɂ��Ă̂��b�E�E�E
���̑��̊֘A�L��
-
�y���W�z �}�C���X�E�f�C���B�X �wTUTU�x �i2011�N5���j
�}�C���X�E�f�C���B�X��1986�N���[�i�[�ڐБ�1�e��i�wTUTU�x���A�{�҃��}�X�^�[�ɓ��N7���̃j�[�X����������lj�����2���g���ؔՂɂēo��B��������̎���}�[�J�X�́uTUTU�lj����C���v�������E�E�E�E�E�E
-
�y���W�z �d���鉤�w�� �u�r�b�`�F�Y�v�ɂ��� �i2010�N7���j
�wBitches Brew�x 40���N�L�O�������K�V�[�Ղ������B�����\���C������CD�A�����\���C��DVD����lj��������S���Y����̂䂾���������B�d���鉤�w�ƁwBitches Brew�x�ɂ��ĐF�X�ƁE�E�E
-
�e�n���E �����O�E�C���^�r���[ �i2008�N6���j
2008�N6���ɍs��ꂽ�e�n���E���C���^�r���[�̑S7�S�ŁB�_�u�E�Z�N�X�e�b�g�A�}�C���X�A�t�@�b�V�����A���̌q�����������x�l�@���Ă݂�ƁE�E�E�E�E�E
���~�E�� �I�����C�� �u�V���Ƃȑ����v�ŘA�ڒ��� �u�W���Y��Փ���v
|

-
���R�N�� �i�Ȃ���� �₷���j
�@1952�N���{�o�g�B���y�]�_�ƁB�W���Y�G���u�X�C���O�W���[�i���v�ҕҏW���߂���A���M�����ɓ���B����Ɂw�}�C���X�E�f�B���B�X �̎���x�A�w�}�C���X vs �R���g���[���x�A�w�}�C���X�̉āA1969�x�A�w�}�C���X���I�x�������B�Ɂw�}�C���X�E�f�B���B�X�����`�x������B�܂��A���b�N�ɂ����w���[���A�w�r�[�g���Y�ƃ{�u�E�f�B�����x�A�w���ƗE�C�̃��b�N50�x�A�w�f�B������!!�x��������B
- �֘A�T�C�g�i�O���T�C�g�j
- �֘A���W�iHMV�T�C�g���j
�{�����ɓo�ꂷ���v�l���ɂ��� |
 |
Willie Nelson �i�E�B���[�E�l���\���j 2005�N�Ƀ����[�X���ꂽ5���g�{�b�N�X�Z�b�g�wThe Complete Jack Johnson Sessions�x�ɂ�����f�B�X�N1�̔����ȏ�ƂȂ�6�Ȃ��A�uWillie Nelson�v�Ƃ����^�C�g���̃e�C�N�Ⴂ�\�[�X�B�܂�A�A���R�[���Ђ��A�}���t�@�i��D���̃A�E�g���[�ȃJ���g���[�̎�A�E�B���[�E�l���\���̂��Ƃ��B�}�C���X�Ƃ̂Ȃ���Ƃ��ẮA70�N�㓖���̏������R�[�h��ЁiCBS�j�������ŁA����Ƀ}�l�[�W���[�����ʂ��Ă����_�B�܂��A�}�C���X�̎t�`���[���[�E�p�[�J�[����̃J���g���[�E�t�@���������Ƃ������Ƃ͂͂����ĊW���Ă����̂��낤���H |
 | Frank Sinatra �i�t�����N�E�V�i�g���j �}�C���X���h�����Ă����t�����N�E�V�i�g���́A�A�����J�̃X�^���_�[�h�Ȃ��̂킹����E�ɏo��҂͂��Ȃ��ō��̃|�s�����[�E�V���K�[�B�}�C���X�́A�}���\���E�Z�b�V�����Ő������uMy Funny Valentine�v�Ƃ������X�^���_�[�h�E�i���o�[�����t����ۂɂ́A�����V�i�g���̉��߂P���Ă����Ƃ����B |
 |
Al Jarreau �i�A���E�W�����E�j 1975�N�A���[�i�[�^���v���[�Y����wWe Got By�x�Ńf�r���[�����W���Y�E�V���K�[�A�A���E�W�����E�B78�N�ɁwLook to the Rainbow�x�A��79�N�ɁwAll Fy Home�x�����ꂼ��O���~�[�܍ŗD�G�W���Y�E�{�[�J���E�A���o���܂���܁B80�N��ɂ́A�W�F�C�E�O���C�h���A�i�C���E���W���[�X�A�i���_�E�}�C�P���E�E�H���f����̃v���f���[�X�̉��AAOR�^�u���b�N�E�R���e���|�����[�H���������i�߁A�|�b�v����ł̃q�b�g���������ݏo�����B2006�N�ɂ́A�W���[�W�E�x���\���Ƃ̋���A���o���wGivin' It Up�x�ŁA�}�C���X�́uFour�v�����グ�Ă���B |
 |
Sammy Figueroa �i�T�~�[�E�t�B�K���A�j �p�L�[�g�E�f���x�[���A�Z�C�X�E�f���E�\���[���A�~�V�F���E�J�~�[���Ȃǂ̃T�C�h�����Ƃ��Ē��N���Ă���p�[�J�b�V�����t�҃T�~�[�E�t�B�K���A�B1981�N�A�}�C���X�̕��A��wA Man With The Horn�x�ɓ˔@���F����A�}�C���X�y�Ȏj�㏉�̃��H�[�J������ȁuA Man With The Horn�v�ł̓p�[�J�b�V�����ɉ����A�����f�B�E�z�[���ivo�j�̃o�b�N�ŃR�[���X���Y���Ă���B |
 |
John McLaughlin �i�W�����E�}�N���t�����j �C�M���X�A���[�N�V���[�E�h���J�X�^�[�o�g�̃M�^���X�g�A�W�����E�}�N���t�����́A1969�N�ɓn�āB�g�j�[�E�E�B���A���X�̃��C�t�^�C���ɎQ����A�}�C���X�E�O���[�v�ɓ��c�B�wIn A Silent Way�x�A�}�N���t�����̖����^�C�g���œ����Ă���i�������A�}�C���X�͕s�Q���j�wBitches Brew�x�A�wOn The Corner�x�A�����ă}�N���t�����̓����̐�D���Ԃ��@���Ɍ����wA Tribute to Jack Johnson�x�܂łɎQ�������B70�N�����̃}�C���X�E�T�E���h�̏ے��Ƃ�������}�N���t�����̃v���C���A�}�C���X���ufar in�i���[���j�v�ƕ\�������̂͗L���ŁA���Ȃ荂���]����^���Ă����B�}�C���X�E�o���h���E��́A1971�N�ɁA�C���h���y�ɌX�|���͂��߂�2��ڂ̃\���E���[�_�[��wMy Goal's Beyond�x�i���̌�q���h�D�[���ɉ��@�j�\�B����ɂ́A�����E�n�}�[�ikey�j�A�r���[�E�R�u�n���ids�j��e�N�����̐��s��Ǝ��ȃo���h�̃}�n���B�V���k�E�I�[�P�X�g���������B���N��1st�A���o���w���ɔ�߂����x�\���A70�N��̃W���Y�E���b�N�E�V�[�������������B |
 |
Billy Preston �i�r���[�E�v���X�g���j �u5�Ԗڂ̃r�[�g���Y�v�Ƃ��Ă��m���錮�Ցt�҃r���[�E�v���X�g���́A1970�`71�N�ɍs��ꂽ�X���C�E�X�g�[���́w�\���x�Z�b�V�����ւ̎Q���i�N���W�b�g�͂Ȃ��j�����������ɁA�}�C���X�ƑΖʂ����\���������ƌ����Ă���B���ۗ��҂��Z�b�V�������s�����L�^�E�،��͎c���Ă��Ȃ��炵�����A74�N�i���{��75�N�j�Ƀ����[�X���ꂽ�wGet Up With It�x�ɂ́uBilly Preston�v�Ƃ����Ȃ����^���ꂽ�B72�N12���̃Z�b�V�����Ř^�����ꂽ���̃t�@���N�E�i���o�[�́A�}�C���X���w�\���x�̃Z�b�V�����Ŗڂ̓�����ɂ����r���[�̃v���C�ɋ��������������Ƃ������ł���B |
 |
Thelonious Monk �i�Z���j�A�X�E�����N�j 1954�N12��24���A�v���X�e�B�b�W�E���R�[�h����̗v���Ń}�C���X�̃��R�[�f�B���O�ɎQ�������Z���j�A�X�E�����N�B�A���o���wMiles Davis And The Modern Jazz Giants�x���^�́uThe Man I Love�iTake 2�j�v�ɂ����āA�u�I���������Ă���Ƃ��́A�s�A�m��e���ȁv�i�����̐��Ԃ̉��߂́A�����N���s�A�m�E�\����r���Ŏ~�߁A����ɑ��ē{�����}�C���X�������̏o�Ԃł��Ȃ��̂Ƀg�����y�b�g��炷�A�Ƃ������̂������j�ƃ}�C���X�����������ْ����̂������肪�^�����ꂽ�B���Ɍ����u���܃Z�b�V�����v�ŁA���̌�����{�I�ȉ��y���̈Ⴂ����A��������Ƀ��R�[�f�B���O�����邱�Ƃ͂Ȃ������i��55�N�̃j���[�|�[�g�E�W���Y�E�t�F�X�ɂċ����j���A�}�C���X�̓j���[���[�N�ɗ��ĊԂ��Ȃ����Ƀ����N�ɏo�����ȉe�����Ă��邱�Ƃ�����A�����N�̍�Ȕ\�͂�傢�ɔF�߂���ŁA�wRound About Midnight�x��wMilestones�x�Ń����N�̋Ȃ����グ���A�Ƃ���Ă���B |
 |
Vince Wilburn �i���B���X�E�E�B���o�[���j 1985�N�ɔ��\���ꂽ�wYou're Under Arrest�x�̘^���i84�N12���j���Ō�Ƀo���h�𗣂ꂽ�A���E�t�H�X�^�[�̌�C�Ƃ��āA�}�C���X�̉��ł����郔�B���X�E�E�B���o�[�����V�C�h���}�[�Ƃ��ēo�p���ꂽ�BCBS����Ō�̐���A���o���ƂȂ����wAura�x�i84�N�^���j�ł́A�f���}�[�N�ɕ����A�W�����E�}�N���t�����ig�j�A�_�����E�W���[���Y�ib�j�ɉ����A�j�[���X�E�y�f���Z���ib�j�猻�n�̋����~���[�W�V�����������ẴZ�b�V�������s�����B�{�C���^�r���[���ɂ�����悤�ɁA�u���Y�����x���v�Ƃ������R�ʼn��ق������n���ꂽ���B���X�̕�e�A�܂�}�C���X�̎o���}�C���X�Ɂu�N�r�ɂ���Ȃ�A���߂Ēn���̃V�J�S�������I���Ă���ɂ��Ăق����v�ƍ��肵������������Ă��炦�Ȃ������Ƃ����B���ꂾ���}�C���X�́A�h���}�[�ɋ������������݂��Ă����B |