【特集】 マイルス・デイヴィス”ロスト・クインテット”
2013年1月29日 (火)

帝王マイルス、幻の音源シリーズ第2弾登場!
昨年の生誕85周年および没後20年を記念してリリースされた「ブートレグ・シリーズVol.1」の続編が遂に登場! これぞまさに「帝王マイルス・デイヴィス・アーカイヴ」の決定盤! 「Vol.1」は、アコースティック・ジャズの最高峰にして臨界点、マイルス・デイヴィス黄金の第二期 クインテットによる1967年11月のヨーロッパ・ツアー音源だったが、今回は第三期、「ロスト・クインテット」と言われるクインテットによる音源である。
メンバーはウェイン・ショーター (sax)、チック・コリア(key)、デイヴ・ホランド(b)、ジャック・デジョネット(ds)。このユニットは 1968年から1970年まで存在したが、公式なアルバムは『1969マイルス』(1969年7月のライヴ録音)しかない。そのぶん、ブート音源は多数存在するわけであるが、伝統の破壊と再構築を極限まで推し進めたこのユニットのすさまじいパフォーマンスが、ついにここに公式に明らかとなる!
(メーカーインフォより)
 Miles Davis Quintet
Miles Davis Quintet
『Live In Europe 1969 The Bootleg Series Vol.2』
『Live In Europe 1969 The Bootleg Series Vol.2』
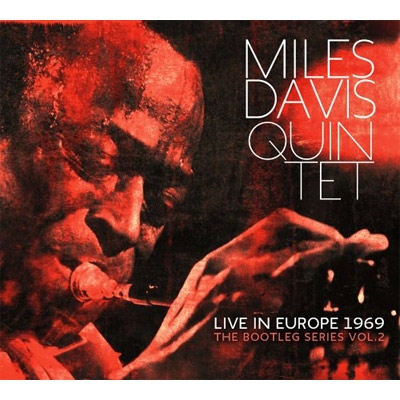 こちらは1月29日発売のUS盤となります。
こちらは1月29日発売のUS盤となります。
【CD1】 Recorded 7/25/69 at Festival Mondial du Jazz d’Antibes, La Pinede, Juan-les-Pins, France
1. Introduction by Andre Francis (0:27) / 2. Directions (6:06) / 3. Miles Runs The Voodoo Down (9:10) / 4. Milestones (13:53) / 5. Footprints (11:37) / 6. 'Round Midnight (8:59) / 7. It's About That Time (9:24) / 8. Sanctuary (4:15) / 9. The Theme (0:53)
【CD2】 Recorded 7/26/69 at Festival Mondial du Jazz d’Antibes, La Pinede, Juan-les-Pins, France
1. Introduction by Andre Francis (0:26) / 2. Directions (6:18) / 3. Spanish Key (10:37) / 4. I Fall In Love Too Easily (2:54) / 5. Masqualero (8:29) / 6. Miles Runs The Voodoo Down (8:46) / 7. No Blues (13:35) / 8. Nefertiti (8:50) / 9. Sanctuary (3:33) / 10. The Theme (0:48)
【CD3】 Recorded 11/5/69 at Folkets Hus, Stockholm
1. Introduction by George Wein (0:30) / 2. Bitches Brew (14:39) / 3. Paraphernalia (9:20) / 4. Nefertiti (10:03) / 5. Masqualero (incomplete) (7:58) / 6. This (6:18)
【DVD】 Recorded 11/7/69 at Berliner Jazztage in the Berlin Philharmonie
1. Introduction by John O’Brien-Docker (2:07) / 2. Directions (6:42) / 3. Bitches Brew (13:39) / 4. It's About That Time (14:09) / 5. I Fall In Love Too Easily (3:39) / 6. Sanctuary (3:55) / 7. The Theme (1:11)
 国内盤はBlu-spec CD 仕様
国内盤はBlu-spec CD 仕様
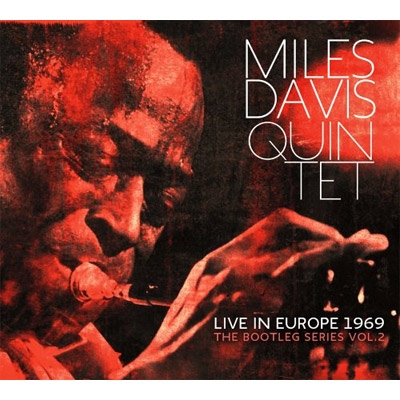 こちらは2月27日発売の国内盤です。
こちらは2月27日発売の国内盤です。
* 国内盤のみ 生産限定 Blu-Spec CD仕様。収録内容は上掲US盤と同じとなります。
* ブックレットには、1万字にも及ぶライナーノーツ(対訳)を掲載。
 COLUMBIA/LEGACYから限定コレクターズ・アイテムも
COLUMBIA/LEGACYから限定コレクターズ・アイテムも
 マイルス・デイヴィス限定コレクターズ・シングル。「Miles Runs The VooDoo Down」、「In A Silent Way」を収録した7インチ・シングルに、Tシャツ(XLサイズのみ)をパッケージ。
マイルス・デイヴィス限定コレクターズ・シングル。「Miles Runs The VooDoo Down」、「In A Silent Way」を収録した7インチ・シングルに、Tシャツ(XLサイズのみ)をパッケージ。
 TOUR DATES 1969
TOUR DATES 1969
1/25〜2/16 Club Baron, New York
3/5〜10 Cellar Door, Washington
3/11〜17 Duffy's Backstage, Rochester
4/25,26 Village Gate, New York
5/11 Spectrum,Philadelphia
5/23,24 Village Gate, New York
6/4〜14 Plugged Nickel Club, Chicago
6/21〜29 Blue Coronet Club, Brooklyn
6/22 Morgan State Jazz Festival, Baltimore
7/5 Newport Festival
7/7 Central Park, New York
7/25,26 Juan-les-Pins Festival, Antibes
7/27 Rutgers University Stadium, New Brunswick
7/29〜8/10 Village Gate, New York
7/31 Sheraton Park Hotel, French Lick (French Lick Jazz Festival)
8/15 The Spectrum, Philadelphia
8/16 Kiel Auditorium, St. Louis
8/22 Grant Park Theater, Chicago
8/23 Crosley Field, Cincinnati (Ohio Jazz Festival)
9/9〜21 Shelly's Manne-Hole, Los Angeles
:
10/26 Teatro Lirico, Milan
10/27 Teatro Sistina, Rome
10/31 Stadthalle, Vienna
11/1 Hammersmith Odeon, London
11/2 Ronnie Scott's Club, London
11/3 Salle Pleyel, Paris
11/4 Tivoli Konsertsal, Copenhagen
11/5 Folkets Hus, Stockholm
11/7 Philharmonie, Berlin
11/8 Sart Tilman, Liège
11/9 De Doelen, Rotterdam
 マイルス「ブートレグ・シリーズ」の第1弾はこちら!
マイルス「ブートレグ・シリーズ」の第1弾はこちら! アコースティック・ジャズの最高峰にして臨界点。マイルス・デイヴィス黄金の第二期クインテットによる1967年欧州ツアーの記録が、3CD+DVDのボックスセットにて遂に公式リリース!
 1969年、”失われたクインテット” 準電化のミクロコスモス
1969年、”失われたクインテット” 準電化のミクロコスモス
瓦解の連続にならわしが乱麻し、何かが木端微塵となって葬り去られていく、五里霧中の帝王エレクトリック大作戦。凄惨なるラウドマシーンと化したアガパン・シーズンをその先に見据え、「準電化/ハーフ電化」の男たちは今日も広漠荒れ野をいざ往かん。その本格的な嚆矢の現場となった1969年1月25日ニューヨーク「クラブ・バロン」におけるギグは、おそらく多くのスクエアなジャズ・セクトたちから誹謗中傷の声を浴びせられたに違いない。「ジャズの歴史に対する冒涜だ」と。五分刈りの大親分以下、ウェイン・ショーター(ts,ss)、チック・コリア(el-p)、デイヴ・ホランド(b)、ジャック・デジョネット(ds)による通称”ロスト・クインテット”は、そんなこともお構いなしにドンパチ、銃撃戦や組み討ちのようなジャズを白日の下にさらしていった。
時は流れに流れて、1993年。「衝撃の未発表ライヴ!」という興奮抑えきれぬ惹句をブラさげ、ソニーから本国を差し置き日本独占リリースされた『1969 Miles』。ご存知、1969年7月25,26日、当時のロスト・クインテットがフランス・アンティーブで開催されたジュアン・レ・パン・フェスティヴァルに大トリとして登場(音源は25日のみを収録)したときの記録だ。
20余年という月日の流れは、そこに経年劣化の余地すら与えず、ポストロック〜クラブ系若年層リスナーまでを巻き込みながら、尚かくしゃくとしたジャズ進歩史観のイデオロギーを当世に問うた。もちろんハードバップ〜モード期からのマイルス信者も手放しでこれを称賛。資料的価値の高さだけでなく、評価軸を根底から覆すという意味でのクーデター的発掘音源の登場に皆が溜飲を下げたのは確かだろう。
ときならぬ衝撃からさらに20年。その間、「ショーター遅刻によるロスト・カルテット編成」として有名な1969年7月5日のニューポート・ジャズ・フェスティヴァル出演時の音源が冒頭に収録された『Bitches Brew Live』、1969年11月4日のコペンハーゲン公演がDVDで格納された『Bitches Brew Legacy Edition』、あるいは、『Live In Rome And Copenhagen 1969』(69年10月27日ローマ/同年11月4日コペンハーゲン)、『Live In Berlin 1969』(69年11月7日ベルリン)、『Complete Live At The Blue Coronet 1969』(69年6月21〜29日NYCブルックリン)、はたまた半地下古典『Double Image』(69年10月27日ローマ)のアップグレイド盤といった、我々とロスト・クインテットとの距離をグッとつめる発掘ライヴ音源・映像などもオフィシャル、グレーひっくるめて玉石混淆色々とリリースされてはいたが、先の『1969 Miles』のような安心二重丸のオフィシャル完全盤に悠々とありつけなかったのがつまるところ現状。だからして、今回のロスト・クインテット ”正規” 解凍に只ならぬ慶びを憶えてしまう。
ロスト・クインテットはここでも聴ける
 『1969 Miles』 (1993)
『1969 Miles』 (1993)
 1990年にハーフ・オフィシャルとして世に出た『Double Image』が、それまで唯一のロスト・クインテット音源として重宝されていたが、こちらの本丸公式盤の登場によって、日本のハーフ電化マイルス・フリーク誰もがその真髄に喚起し、恍惚の表情を浮かべた。1969年7月25日のフランス・アンティーブ公演は、手探り状態の春を越えて、いよいよ本格的に伝統的なジャズの歴史からの逸脱を目指す五人の夏を捉え、親分の絶対的なタクトのもと凄まじいまでのエネルギー放射を「ヤメ!」と言われるまで死に物狂いで繰り返す。この音塊、体いっぱいで受け止めよう。
1990年にハーフ・オフィシャルとして世に出た『Double Image』が、それまで唯一のロスト・クインテット音源として重宝されていたが、こちらの本丸公式盤の登場によって、日本のハーフ電化マイルス・フリーク誰もがその真髄に喚起し、恍惚の表情を浮かべた。1969年7月25日のフランス・アンティーブ公演は、手探り状態の春を越えて、いよいよ本格的に伝統的なジャズの歴史からの逸脱を目指す五人の夏を捉え、親分の絶対的なタクトのもと凄まじいまでのエネルギー放射を「ヤメ!」と言われるまで死に物狂いで繰り返す。この音塊、体いっぱいで受け止めよう。
 『Bitches Brew Live』 (2011)
『Bitches Brew Live』 (2011)
 1969年7月5日、スライ、ツェッペリン、ジェフ・ベック、BS&Tなどロック〜ソウル勢大挙ブッキングで聴衆を熱狂させたニューポート・ジャズ・フェス出演時の音源から、「Miles Runs The Voodoo Down」、「Sanctuary」、「It's About That Time / The Theme」の3曲を前半に収録。ショーターの交通渋滞による遅刻で、所謂「ロスト・カルテット」と呼ばれている有名な音源。そのためか、音の厚みやカオス度に関してはアンティーブにやや譲るものがあるが、ロック・リスナーを相手にカッカしているようなマイルス怒りの一撃(?)や、相も変わらず凶暴なデジョネットのドラムなど、燃える要素には事欠かない。後半6曲は、こちらも有名な1970年8月29日ワイト島でのライヴ音源。
1969年7月5日、スライ、ツェッペリン、ジェフ・ベック、BS&Tなどロック〜ソウル勢大挙ブッキングで聴衆を熱狂させたニューポート・ジャズ・フェス出演時の音源から、「Miles Runs The Voodoo Down」、「Sanctuary」、「It's About That Time / The Theme」の3曲を前半に収録。ショーターの交通渋滞による遅刻で、所謂「ロスト・カルテット」と呼ばれている有名な音源。そのためか、音の厚みやカオス度に関してはアンティーブにやや譲るものがあるが、ロック・リスナーを相手にカッカしているようなマイルス怒りの一撃(?)や、相も変わらず凶暴なデジョネットのドラムなど、燃える要素には事欠かない。後半6曲は、こちらも有名な1970年8月29日ワイト島でのライヴ音源。
 『Bitches Brew - Legacy Edition』 (2010)
『Bitches Brew - Legacy Edition』 (2010)
 『The Complete Bitches Brew Seessions』で泣きを見た多くの電化マイルス・ファンに対する、せめての罪滅ぼしだったのだろう。1970年8月18日のボストン・タングルウッドでのライヴCDが一応の目玉ではあるが、あくまで本稿向けは、DVDサイドに収録の1969年11月4日のコペンハーゲン公演。ハーフ・オフィシャルの『Live In Copenhagen & Rome 1969』に収録されたものと同じ映像だが、「Directions」と「Miles Runs The Voodoo Down」が追加されている完全版、さらに当然ながら画質・音質も格段アップということで、ハーフ電化ファンは地下アイテムで所有済みだとしても改めて必見。
『The Complete Bitches Brew Seessions』で泣きを見た多くの電化マイルス・ファンに対する、せめての罪滅ぼしだったのだろう。1970年8月18日のボストン・タングルウッドでのライヴCDが一応の目玉ではあるが、あくまで本稿向けは、DVDサイドに収録の1969年11月4日のコペンハーゲン公演。ハーフ・オフィシャルの『Live In Copenhagen & Rome 1969』に収録されたものと同じ映像だが、「Directions」と「Miles Runs The Voodoo Down」が追加されている完全版、さらに当然ながら画質・音質も格段アップということで、ハーフ電化ファンは地下アイテムで所有済みだとしても改めて必見。
 『Complete Live At The Blue Coronet 1969』 (2010)
『Complete Live At The Blue Coronet 1969』 (2010)
 ハーフ・オフィシャルながら、ロスト・クインテットのツアー前半戦(ビッチェズ録音前まで)を捉えた貴重な記録として人気の高い、1969年6月6月21〜29日NYCブルックリンのクラブ「ブルー・コルネット」でのライヴを、1stショウ/2ndショウとで収録した2枚組。「No Blues」、「Gingerbread Boy」、さらには「Walkin'」が並ぶ、この時期ならではのレアなセットリストは、まさにハーフ電化マイルス進化の軌跡をたどるのに打ってつけの資料になるだろう。デジョネットのドラムはここでも凄い!
ハーフ・オフィシャルながら、ロスト・クインテットのツアー前半戦(ビッチェズ録音前まで)を捉えた貴重な記録として人気の高い、1969年6月6月21〜29日NYCブルックリンのクラブ「ブルー・コルネット」でのライヴを、1stショウ/2ndショウとで収録した2枚組。「No Blues」、「Gingerbread Boy」、さらには「Walkin'」が並ぶ、この時期ならではのレアなセットリストは、まさにハーフ電化マイルス進化の軌跡をたどるのに打ってつけの資料になるだろう。デジョネットのドラムはここでも凄い!
この度の『Live In Europe 1969 The Bootleg Series Vol.2』、その特筆すべきキラーコンテンツのひとつが、7月26日のフランス・アンティーブ音源になるだろうか。つまり『1969 Miles』の翌日のステージを収録した、地下盤ハンター諸氏には『Another Night』や『Second Night』でおなじみのアレだ。ビッチェズ吹き込み直前、すでに春先からお披露目されている「Spanish Key」、「Miles Runs The Voodoo Down」、「Sanctuary」、さらにジョー・ザビヌル作の「Directions」といったブリブリのニューサウンドも刺激的だが、前日の「Milestones」、「'Round About Midnight」などに取って替わりセットに加えられた「I Fall In Love Too Easily」、「Masqualero」、「No Blues」、「Nefertiti」がとにかく興味深い。
『Miles Smiles』から、『Sorcerer』、『Nefertiti』を経て、『Miles In The Sky』、『Filles De Kilimanjaro』にたどり着くまでの2年強、かの60年代第二期クインテットを率いてアコースティック・ジャズの頂に立つ一方で、 ”ジャズ村だけの脆弱な名誉” をかなぐり捨ててでも取り組みたい、どうにも抑えきれなかったグローバルな電化欲というものが次第に露になっていたマイルス。ゆえにいずれのアルバムにもウズウズとした前途への成算あるいは現状へのもどかしさを、断片的にでも感受することができるだろう。とまれ、1969年の曙を待たずして、大願の「電化推進プロジェクト」なるものは、逸る気持ちを抑えつつも事実上の実装着手をみることとなり、その大掛かりな電界テストの第一歩として、クインテットの一新、即ちロスト・クインテットの登場へとつながっていった。
 ことさら前述の4曲は、電化計画の初期段階において、過去との決別を図ったかのような形相と、そうではない名残惜しさとの両面を覗かせているようで俄然おもしろい。「No Blues」にしても、マイルスがいくら斬新なフレーズをブチ込もうと、その旧態然とした景色には、一向にヴィヴィッドなカラーが着色されない。厳密に言えば、マイルスのトランペットだけがドキッとするほど鮮かな発光色を放つパートカラーの世界。しかしそれが「Nefertiti」になだれ込むと、目下エレピ効能模索中のチック、暴れ太鼓はお手の物デジョネットのグッドな閃きも相俟って、突飛な世界のキッチュな美女の姿を映し出す。
ことさら前述の4曲は、電化計画の初期段階において、過去との決別を図ったかのような形相と、そうではない名残惜しさとの両面を覗かせているようで俄然おもしろい。「No Blues」にしても、マイルスがいくら斬新なフレーズをブチ込もうと、その旧態然とした景色には、一向にヴィヴィッドなカラーが着色されない。厳密に言えば、マイルスのトランペットだけがドキッとするほど鮮かな発光色を放つパートカラーの世界。しかしそれが「Nefertiti」になだれ込むと、目下エレピ効能模索中のチック、暴れ太鼓はお手の物デジョネットのグッドな閃きも相俟って、突飛な世界のキッチュな美女の姿を映し出す。
試行錯誤を繰り返す中でバケモノみたいに育つ曲もあれば、逆にサイズダウンしてしまい、やむなく置いていかなければならないような曲もあるだろう。二義的であれ三義的であれ、ビッチェズ録音前夜にそうした絞込み作業を目的に演奏されていたこれらの曲にこそ、1969年のマイルス・サウンドの独自性があるとも認識できそう。ジャズの壊れ損ないでもなければ、ロックの出来損ないでもない。図らずもか台本通りか、これは1969年製の完全なる、そしてスキのない未完成品の音楽だ。だからして不安定でアブナイ。
折りしも、ジミヘンやスライが自身の民族的アイデンティティを音楽的なイディオムやリズムそのものに練り込み、「ロック」や「ファンク」の共通コードで世界中を席巻していたシーズンだったが、そこに感化されたマイルスが、この時点でジャズから遥か遠くフリークアウトしていくことだけを望んでいたとは必ずしも言い切れない。現に「No Blues」は、同年11月2日のロンドン・ロニー・スコット・クラブ公演、11月5日のストックホルム公演(夜の部)、「Nefertiti」は、11月5日のストックホルム公演(昼の部)、「'Round About Midnight」は10月27日ローマ公演など、秋の欧州ツアーでもガンガン披露されている。アコースティック・マイルスの象徴にしてモード・ジャズの親玉のような「No Blues」が、然も重要レパートリーのごとき立ち居地に据えられていることがその証左に他ならないだろう。これは例えば老舗のロックバンドが、流れ完全無視でハイライトに往年のヒット曲を持ってくるといったサービス芸能にも近似することと言えるのだろうか?
双方メンタリティ的に通ずる部分や純粋なファンとしての目線はあったにせよ、マイルスの「ジャズだってビリビリと電気を帯びたいんだ」という思いの丈が、ジミヘンやスライの音楽フォーマットと短絡的にイコールで結ばれがちな時代にあっただけということで、「誰がロックを目指し、誰がジャズを目指した」というレベルの話では到底片付かないような気さえもしてきた。ただし、前述のロック、ソウル勢大挙出演で聴衆を鼓舞したニューポート・ジャズ・フェスで、マイルスがスライの大爆発ステージを目の当たりにして「畜生、オレだって・・・」と嫉妬の念に駆られたであろうことなどを含め、この時代特有のカオティックなつむじ風に巻かれれば巻かれるほど、謎は深まるばかりなのである。
革命児たちの1969
 ジミ・ヘンドリックス
ジミ・ヘンドリックス
『Message From Nine To The Universe』 (2006)
『Message From Nine To The Universe』 (2006)
 1980年にアラン・ダグラスの編集でLPリリースされていた「ジミがジャズに最も接近した」ときのセッション記録を、5曲のボーナスを加え、さらには未編集ヴァージョンを採用してCD再発したもの。但し、ソースの出所自体はオフィシャルとは言えない可能性も高い? 録音は、マイルスとのセッションが頓挫した翌年、つまり69年から70年にかけて断続的に行なわれたものと言われている。ビリー・コックス、バディ・マイルス、ミッチ・ミッチェルらに加え、”マイルス組”からはデイヴ・ホランド、ラリー・ヤングが参加。完成形からは程遠いのだろうが、「Nine To The Universe」、「Easy Blues」などで、「何かが起ころうとしているタダならぬ気配」を感じることができれば是幸い。
1980年にアラン・ダグラスの編集でLPリリースされていた「ジミがジャズに最も接近した」ときのセッション記録を、5曲のボーナスを加え、さらには未編集ヴァージョンを採用してCD再発したもの。但し、ソースの出所自体はオフィシャルとは言えない可能性も高い? 録音は、マイルスとのセッションが頓挫した翌年、つまり69年から70年にかけて断続的に行なわれたものと言われている。ビリー・コックス、バディ・マイルス、ミッチ・ミッチェルらに加え、”マイルス組”からはデイヴ・ホランド、ラリー・ヤングが参加。完成形からは程遠いのだろうが、「Nine To The Universe」、「Easy Blues」などで、「何かが起ころうとしているタダならぬ気配」を感じることができれば是幸い。
[こちらの商品は現在お取り扱いしておりません]
 スライ&ザ・ファミリー・ストーン
スライ&ザ・ファミリー・ストーン
『Woodstock Edition』 (2009)
『Woodstock Edition』 (2009)
 「ウッドストック40周年」となる2009年にリリースされた、1969年8月17日、スライ&ザ・ファミリー・ストーンの同フェス出演時の全貌を収録したアルバム。「とにかくスライにはビビった」という逸話も残るほど、マイルスのスライへの傾倒ぶりはもはや狂信にも近かったとか。音楽意匠としてのファンク・ミュージックの反復性・永続性に着目したこともそうだが、何よりニューポート・ジャズ祭でクラウドを焚き付け暴徒化させてしまうほどの扇動力や求心力に強く惹き込まれたのは言うまでもない。この当時はまだ『暴動』こそリリースされていないが、『スタンド!』収録曲のライヴでのテンションの高さや迫力もハンパじゃない。
「ウッドストック40周年」となる2009年にリリースされた、1969年8月17日、スライ&ザ・ファミリー・ストーンの同フェス出演時の全貌を収録したアルバム。「とにかくスライにはビビった」という逸話も残るほど、マイルスのスライへの傾倒ぶりはもはや狂信にも近かったとか。音楽意匠としてのファンク・ミュージックの反復性・永続性に着目したこともそうだが、何よりニューポート・ジャズ祭でクラウドを焚き付け暴徒化させてしまうほどの扇動力や求心力に強く惹き込まれたのは言うまでもない。この当時はまだ『暴動』こそリリースされていないが、『スタンド!』収録曲のライヴでのテンションの高さや迫力もハンパじゃない。

1969年8月19日から3日連続で行なわれた『Bitches Brew』のレコーディング・セッションには、クインテット・メンバーを核としながら、ジョー・ザビヌル(el-p)、ジョン・マクラフリン(g)、ラリー・ヤング(el-p)、ベニー・モウピン(bcl)、ハーヴィー・ブルックス(el-b)、レニー・ホワイト(ds)、ドン・アライアス(ds)、ジム・ライリー(per)というマイルスのお眼鏡にかなった布陣が召集され、そこに加わった。
ライヴの中で練り上げられ培養なり変体なりを繰り返してきた「Spanish Key」、「Miles Runs The Voodoo Down」、「Sanctuary」に関しても、一応の完成形が指示されたという捉え方をしてもよいだろうか。中でも「Sanctuary」の1年ぶりの再録は、ドラマティックで壮大なコスモスに仕立て上げられており、柔らかいショックの中で望外のカタルシスを得ることができる。これによりロスト・クインテットは、アルバム制作を一義的な目的として編まれたバンドではなく、あくまで最前線ともいえるライヴの現場でのみその真価を発揮することが許された、逆にいえば、純粋なクインテット編成で記録に残ることを概ね許されなかった ”哀しき” 特殊精鋭部隊だったことを明確に位置付けた。
このことは、前作にあたる2月録音の『In A Silent Way』を例に挙げても明白。すでに1月の段階でニューヨークの「クラブ・バロン」で初陣を飾っていたロスト・クインテットだったが、翌月当アルバムのレコーディングに入るやいなや、スタジオに顔を揃えたのは他でもない、ハービー・ハンコック(el-p)にトニー・ウィリアムス(ds)、黄金の第二期クインテットを形成した旧知の面々だった。さらにデジョネット(ds)不参加の中で、意中のザビヌルやら嘱目のマクラフリンやら初参加組も加わるというのだからややこしいというか、マイルスの脳内宇宙で組み立てられていた創造プラン、特に人事任免にまつわる企画イメージというものが、ある種のゲゼルシャフトに基づきながらいかに冷静沈着且つ複雑多岐であったかということを推して知ることができるだろう。
テオ・マセロによるマジカル・ポスト・プロダクションが加えられた『Bitches Brew』は翌70年の4月まで陽の目を見ることはなかったが、依然ロスト・クインテットは矢面に立って黙々と任務を遂行。結果的に、電化とアコースティックを共存させながら行なわれた瞠目すべきミニマムな肥大化は、アイアート・モレイラ(ds)が参加する70年1月まで継続されていった。
スタジオ・プロダクツ 1969
 『In A Silent Way』 (1969)
『In A Silent Way』 (1969)
 1969年2月18日録音。チック、ハンコックに加え、本作の実質的な音楽監督であるジョー・ザビヌルという3人の鍵盤奏者が、それぞれエレクトリック・ピアノとオルガンを自由に弾きながら、ジョン・マクラフリンのギターにまとわりついていく。ショーター、ホランドもいるが、デジョネットはいない。 ”呼び戻された”トニー・ウィリアムスのドラムは、その後テオ・マセロによって大胆に鋏を入れられるエディット作業によって不可思議な連続性と浮遊感を与えられ、創作物の中におけるひとつの機能を果たす。また、同年録音のビッチェズがこの延長線上にあったわけではないことは、編集前の音源を収めた『Complete In A Silent Way』の登場によりさらに明確となり、3、40年後、あわよくば100年後にあっても「最先端・最新鋭の嚆矢」としてほぼ永久的に崇められる可能性を秘めていることをも示唆した。
1969年2月18日録音。チック、ハンコックに加え、本作の実質的な音楽監督であるジョー・ザビヌルという3人の鍵盤奏者が、それぞれエレクトリック・ピアノとオルガンを自由に弾きながら、ジョン・マクラフリンのギターにまとわりついていく。ショーター、ホランドもいるが、デジョネットはいない。 ”呼び戻された”トニー・ウィリアムスのドラムは、その後テオ・マセロによって大胆に鋏を入れられるエディット作業によって不可思議な連続性と浮遊感を与えられ、創作物の中におけるひとつの機能を果たす。また、同年録音のビッチェズがこの延長線上にあったわけではないことは、編集前の音源を収めた『Complete In A Silent Way』の登場によりさらに明確となり、3、40年後、あわよくば100年後にあっても「最先端・最新鋭の嚆矢」としてほぼ永久的に崇められる可能性を秘めていることをも示唆した。
 『Bitches Brew』 (1970)
『Bitches Brew』 (1970)
 1969年8月19〜21日録音。当初このセッションは、テオ・マセロのプロデュースによって、ベティ・デイヴィスのメジャー・デビュー・アルバム用に行なわれたものだったという。ビリー・コックス(b)、ミッチ・ミッチェル(ds)に、トニー、ショーターと、まさにジミヘン・バンドとマイルス・バンドがくっついた夢の共演は、レコーディング途中に企画ごとお流れに。この夢のかけらを掻き集め、現実的なレベルで再構築したのが、他でもない当時の夫マイルス。クインテットほか、ザビヌル、マクラフリン、モウピンから、ラリー・ヤング、レニー・ホワイト、ハーヴィー・ブルックスまで、録音メンバーが複雑に入り組んだことで、純正クインテットは遅かれ早かれ「ロスト」となることを約束されたかのような様相を呈する。セクションごとにメロディやリフを延々とループ演奏させる中で、パーツとして「使えるもの」と「使えないもの」に二分。それがテオの編集素材となっていった。魔法のようなテープ・エディットとの融合を果たした、ザビヌル作の「Pharoah's Dance」はことさら圧巻だ。マイルス初のグラミー賞受賞作で、初のゴールド・ディスクとなった。
1969年8月19〜21日録音。当初このセッションは、テオ・マセロのプロデュースによって、ベティ・デイヴィスのメジャー・デビュー・アルバム用に行なわれたものだったという。ビリー・コックス(b)、ミッチ・ミッチェル(ds)に、トニー、ショーターと、まさにジミヘン・バンドとマイルス・バンドがくっついた夢の共演は、レコーディング途中に企画ごとお流れに。この夢のかけらを掻き集め、現実的なレベルで再構築したのが、他でもない当時の夫マイルス。クインテットほか、ザビヌル、マクラフリン、モウピンから、ラリー・ヤング、レニー・ホワイト、ハーヴィー・ブルックスまで、録音メンバーが複雑に入り組んだことで、純正クインテットは遅かれ早かれ「ロスト」となることを約束されたかのような様相を呈する。セクションごとにメロディやリフを延々とループ演奏させる中で、パーツとして「使えるもの」と「使えないもの」に二分。それがテオの編集素材となっていった。魔法のようなテープ・エディットとの融合を果たした、ザビヌル作の「Pharoah's Dance」はことさら圧巻だ。マイルス初のグラミー賞受賞作で、初のゴールド・ディスクとなった。
 10月下旬より次なる、そして最後の山場を迎える。イタリア・ミラノのリリコ劇場を皮切りにスタートしたヨーロッパ・ツアーで、 ロスト・クインテットが ”ロスト”であることを大局的に悔やまずにはいられないような名演を数多残すこととなった。『Bitches Brew』のレコーディングを超えて感度がさらに高くなったのは何もマイルスだけではない。ザビヌルとの邂逅の中でエレクトリック・ピアノの楽器としての特性を掴み始めていたチックは、その修練の成果を自らのリーダー録音(バックは、マイルスを除く同クインテットの残党)にまで封じ込め、ヨーロッパに乗り込む頃には、あたかも電子音楽類に覚醒したかのようなトリッピーでキワキワに歪む術を完全マスターしていた。
10月下旬より次なる、そして最後の山場を迎える。イタリア・ミラノのリリコ劇場を皮切りにスタートしたヨーロッパ・ツアーで、 ロスト・クインテットが ”ロスト”であることを大局的に悔やまずにはいられないような名演を数多残すこととなった。『Bitches Brew』のレコーディングを超えて感度がさらに高くなったのは何もマイルスだけではない。ザビヌルとの邂逅の中でエレクトリック・ピアノの楽器としての特性を掴み始めていたチックは、その修練の成果を自らのリーダー録音(バックは、マイルスを除く同クインテットの残党)にまで封じ込め、ヨーロッパに乗り込む頃には、あたかも電子音楽類に覚醒したかのようなトリッピーでキワキワに歪む術を完全マスターしていた。
覚醒という意味合いでは、ホランド=デジョネットのリズム・セクションもさらにタガの外れかかった、激しくキツいリズム&グルーヴの渦中にいた。電化を標榜する過程で、矛盾とも言うべきか ”あえて”のアコースティックで奮戦することを今だもって強いられていたホランドは、オスティナートやゴーストノートを多用しながら、フレットレスのエレキ・ベースでも操っているかのようなビリビリする音圧で、ファンクのスペースをあたかも前衛的に創出することに心を砕いている。
ロスト・クインテット、準電化の天王山その(1)、1969年11月5日のストックホルム、ニューポート・ジャズ・フェスティヴァル・イン・ヨーロッパ出演時の音源は、まさしく本盤2つ目のハイライト。エレピ不具合につき、アコースティック・ピアノで急場を凌いだ1stセット中心の編纂(チックの「This」のみ2ndセットから)に若干の物足りなさを感じるものの(資料的価値は高いが)、結成から間もなく1年を迎えようとしていたクインテットの総仕上げ的なパフォーマンスを堪能できることには間違いない。そこには至極当然ながら、後のセクステット〜セプテット、またはアガパン・バンドとも異なる特殊なアンサンブルが存在する。
「Paraphenalia」などで、 ”踏み外しのない”幾ばくかノスタルジックな時間が約束されていることも大きな違いだが、さて、正史から切り捨てられる運命にあった物の怪のアンサンブルからは、その怨念を晴らすべくドロドロの怪電波が放たれ続け、やがて来る超電化期以上の通電力を持つ、とするのはいささか大袈裟だろうか。だが、この日の彼らを評した、地下ではまことしやか有名な合言葉「スウェーデンに降り立った悪魔たち」はやはり言い得て妙で、彼らの演奏がすでに混沌極めるサタニックな領域に片足を突っ込んでいる状態にあったことは確か。さらに、それがアガパンの世界としっかり地続きとなっていることも再認識できるだろうか。チックのエレピにしても何かに憑かれていた・・・鎌首をもたげてこちらをやぶにらみの「Bitches Brew」。躁と自閉が入り組む地獄絵的なジャズのプロトがここに完成した。
それぞれの1969
 ウェイン・ショーター
ウェイン・ショーター
『Super Nova』 (1969)
『Super Nova』 (1969)
 ビッチェズ直後、1969年8月29日と9月2日に録音されたショーターの傑作リーダー・アルバム(プロデュースはデューク・ピアソン)。「それまでのジャズの概念を壊した規格外の」という意味では、その『Bitces Brew』と双璧を成すものの、音の質感そのものに関しては真逆と言っていいほど強烈なまでに相違する。その後のロスト・クインテット演奏時にもそのメロディがさりげなく導入される表題曲が不気味さも相俟り白眉。マイルス外伝『Water Babies』に収録されていた「Water Babies」、「Swee-Pea」、「Capricorn」にしても、その初録音の面持ちとは異なり、さらなる浮遊〜漂流感をまとった深淵なものへと仕立て上げられている。ブラジルのウォルター&マリア・ブッカーをフィーチャーした「Dindi」では、『Native Dancer』 世界への布石ともなるブラジル嗜好の手初めを見る。バックは、チック、デジョネット、マクラフリン、アイアート、ヴィトウスらおなじみのマイルス組に、ソニー・シャーロック(g)など。
ビッチェズ直後、1969年8月29日と9月2日に録音されたショーターの傑作リーダー・アルバム(プロデュースはデューク・ピアソン)。「それまでのジャズの概念を壊した規格外の」という意味では、その『Bitces Brew』と双璧を成すものの、音の質感そのものに関しては真逆と言っていいほど強烈なまでに相違する。その後のロスト・クインテット演奏時にもそのメロディがさりげなく導入される表題曲が不気味さも相俟り白眉。マイルス外伝『Water Babies』に収録されていた「Water Babies」、「Swee-Pea」、「Capricorn」にしても、その初録音の面持ちとは異なり、さらなる浮遊〜漂流感をまとった深淵なものへと仕立て上げられている。ブラジルのウォルター&マリア・ブッカーをフィーチャーした「Dindi」では、『Native Dancer』 世界への布石ともなるブラジル嗜好の手初めを見る。バックは、チック、デジョネット、マクラフリン、アイアート、ヴィトウスらおなじみのマイルス組に、ソニー・シャーロック(g)など。
 チック・コリア
チック・コリア
『Complete Is Sessions』 (1969)
『Complete Is Sessions』 (1969)
 既出の同一セッション、『Is』と『Sundance』をカップリングにてCD化。1969年5月、3日間に亘り吹き込まれたチックのマラソン・セッションの模様で、アコースティックはおろかエレクトリック・ピアノを駆使し、迷いながらも真摯に「ジャズ電化時代」と向き合う様子が克明に記録されている。当時27歳、まだまだエレピ演奏にも伸びしろがあることを感じさせるが、ロスト・クインテットからWキーボード時代、さらには自身のリターン・トゥ・フォーエヴァーに至るプロセスの中で徐々に完成されていく音作りのプロトタイプが、この3日間に集約されていたとしても決して大袈裟ではない。また、リズムセクションには、ホランド、デジョネットという盟友コンビが揃い、さらにはビッチェズ参加直前のモーピンまでが加わっているということで、ハーフ電化マイルス・サウンドの基礎作りの現場のようなものも散見できると言えるだろう。
既出の同一セッション、『Is』と『Sundance』をカップリングにてCD化。1969年5月、3日間に亘り吹き込まれたチックのマラソン・セッションの模様で、アコースティックはおろかエレクトリック・ピアノを駆使し、迷いながらも真摯に「ジャズ電化時代」と向き合う様子が克明に記録されている。当時27歳、まだまだエレピ演奏にも伸びしろがあることを感じさせるが、ロスト・クインテットからWキーボード時代、さらには自身のリターン・トゥ・フォーエヴァーに至るプロセスの中で徐々に完成されていく音作りのプロトタイプが、この3日間に集約されていたとしても決して大袈裟ではない。また、リズムセクションには、ホランド、デジョネットという盟友コンビが揃い、さらにはビッチェズ参加直前のモーピンまでが加わっているということで、ハーフ電化マイルス・サウンドの基礎作りの現場のようなものも散見できると言えるだろう。
 エリック・クロス
エリック・クロス
『To Hear Is To See / Eric Kloss & The Rhythm Section』 (1969)
『To Hear Is To See / Eric Kloss & The Rhythm Section』 (1969)
 盲目の白人アルト・サックス奏者エリック・クロスが、チック、ホランド、デジョネット、当時のロスト・クインテットのリズムセクションをそのまま起用し、1969年6月に吹き込んだ『To Hear Is to See!』と、パット・マルティーノ(el-g)を加えた1970年1月録音の「Consciousness!」をカップリング。軽快なジャズロック・ビートを創出するためにホランドはエレクトリック・ベースを併用し、この時期プラグド・インすることに全く二の足を踏んでいなかったことを窺わせる。後者では、ドノヴァンやジョニ・ミッチェルのカヴァーまでが披露され、自由気ままなセッションの様子が如実に伝わってくる。この二作を挟むかたちでビッチェズが吹き込まれ、さらにはロスト・クインテットが解体→膨張されようとしていた1970年の録音を含むことから、電化マイルス・ファンにも興味の尽きない一枚だろう。
盲目の白人アルト・サックス奏者エリック・クロスが、チック、ホランド、デジョネット、当時のロスト・クインテットのリズムセクションをそのまま起用し、1969年6月に吹き込んだ『To Hear Is to See!』と、パット・マルティーノ(el-g)を加えた1970年1月録音の「Consciousness!」をカップリング。軽快なジャズロック・ビートを創出するためにホランドはエレクトリック・ベースを併用し、この時期プラグド・インすることに全く二の足を踏んでいなかったことを窺わせる。後者では、ドノヴァンやジョニ・ミッチェルのカヴァーまでが披露され、自由気ままなセッションの様子が如実に伝わってくる。この二作を挟むかたちでビッチェズが吹き込まれ、さらにはロスト・クインテットが解体→膨張されようとしていた1970年の録音を含むことから、電化マイルス・ファンにも興味の尽きない一枚だろう。
[こちらの商品は現在お取り扱いしておりません]
 ジャック・デジョネット
ジャック・デジョネット
『The DeJohnette Complex』 (1969)
『The DeJohnette Complex』 (1969)
 ジャック・デジョネット 1968年12月26,27録音の初リーダー・アルバム。あの暴れ太鼓がイヤというほど味わえると思いきや、主役デジョネットのドラムは全8曲中わずか3曲でしか聴くことができない。残りは、ロイ・ヘインズによって叩かれている。本作はむしろ、メロディカやピアノもプレイするデジョネットの多芸ぶりに焦点を合わせたコンセプチャルな一枚となっている。ヘインズほか、スタンリー・カウエル(p)、エディ・ゴメス(b)、さらにはモーピンやヴィトウスらが参加。強引にこの時期のマイルス・サウンドとの最接近を見つけるならば、ヴィトウス&ゴメスのWベース(左右チャンネル)の上で、デジョネットがらしさ全開の8ビートを刻む「Mirror Image」あたりとするのが適当だろうか。
ジャック・デジョネット 1968年12月26,27録音の初リーダー・アルバム。あの暴れ太鼓がイヤというほど味わえると思いきや、主役デジョネットのドラムは全8曲中わずか3曲でしか聴くことができない。残りは、ロイ・ヘインズによって叩かれている。本作はむしろ、メロディカやピアノもプレイするデジョネットの多芸ぶりに焦点を合わせたコンセプチャルな一枚となっている。ヘインズほか、スタンリー・カウエル(p)、エディ・ゴメス(b)、さらにはモーピンやヴィトウスらが参加。強引にこの時期のマイルス・サウンドとの最接近を見つけるならば、ヴィトウス&ゴメスのWベース(左右チャンネル)の上で、デジョネットがらしさ全開の8ビートを刻む「Mirror Image」あたりとするのが適当だろうか。
天王山その(2)は2日後、11月7日のドイツはベルリン・フィルハーモニーにて訪れる。公式DVD化があまりにも待たれていた完璧な一夜。目で見て初めて分かるマイルスおよびロスト・クインテットのヒッピー・カルチャーへの露骨な傾倒ぶり。裕福な中産階級出身ならではの崩し・汚れの美学は、白人文化を嫌悪するマイルスさえも虜にした。歯医者のせがれという富裕層の代表格のような出自を持つマイルスにとっては極めて自然な流れだったのかもしれないが。それにしても、自慢のフェラーリよろしく真紅に染め上げられたスカーフがやけにまぶしい。このあたりには、 ”マドモアゼル・メイブリー” ことベティ・デイヴィスと価値観を共有しようといじらしいまでにイキったことも散見できる。
 ここでは『Bitches Brew』収録曲を惜しみなく繰り出す。「Directions」から ”古株” ショーターも大燃焼。「オレをジャズメンと呼ぶのはやめろ!」と折に触れ口にしていた絶対恐怖の親方の脇で、ビクビクしながらテナーをソプラノに持ち替えるその”古株”は、新主流派急先鋒としてアコースティック・ジャズのバブル期ド真ん中を知るがゆえ、「コルトレーン意識下のモーダリティ」などというような青春めいた甘酸っぱさを後ろめたくポケットの奥底に仕舞い込まなければ、保身という部分においてはニッチもサッチもいかなくなった・・・とまぁ、マイペースで彷徨える妖精のようなショーターに限っては、そこまで求心力のある抑圧された徒弟エピソードは見当たるはずもないのだろうが。
ここでは『Bitches Brew』収録曲を惜しみなく繰り出す。「Directions」から ”古株” ショーターも大燃焼。「オレをジャズメンと呼ぶのはやめろ!」と折に触れ口にしていた絶対恐怖の親方の脇で、ビクビクしながらテナーをソプラノに持ち替えるその”古株”は、新主流派急先鋒としてアコースティック・ジャズのバブル期ド真ん中を知るがゆえ、「コルトレーン意識下のモーダリティ」などというような青春めいた甘酸っぱさを後ろめたくポケットの奥底に仕舞い込まなければ、保身という部分においてはニッチもサッチもいかなくなった・・・とまぁ、マイペースで彷徨える妖精のようなショーターに限っては、そこまで求心力のある抑圧された徒弟エピソードは見当たるはずもないのだろうが。
ショーターには、親の目を盗んで制作した『Super Nova』にしろ、卒業後に旧知のザビヌルらと興したウェザー・リポートにしろ、トップダウンの指南と薫陶、「ハーフ電化、インプロ、ポリの三すくみによる、伝統の破壊・創造・発展」に独自の解釈でアプローチしていった産物というものが存在する。その後70年代を通じて、ブラジル音楽の陰と陽を、持ち前の魔性やSF趣味の中でジャズにアジャストさせていったりと、ある種の千里眼に裏打ちされた荒技をさみだれ式に披露。Blue Note LAシーズンの秀作『Moto Grosso Feio』や『Odyssey Of Iska』で全体を支配していた捉えどころのない呪術性にしても、アコースティックの、というよりは丸腰のジャズに“行き詰まり”を憶えていた親方との見つめるべく方向性の前一致を十全に感じさせる。吐き出し方の違いこそあれど、マイルスとショーターは64年のベルリン・フィルハーモニーから、神秘的でブラック・マジカルな禍々しさを創出するために、一心同体というか表裏一体というか、「言わずとも通ずる」 熟年おしどり夫婦のような絶対的な信頼関係をキープしていたのだと思われる。
「この時点で、ロスト・クインテットがこのまま歴史の闇に葬り去られるなど誰が予想していただろか?」ということ以前に、「ショーターにとってのロスト・クインテットとは何だったのか?」ということを考えたときに、あまつさえロスト・クインテットは、マイルス、そしてショーターという希代のインプロヴァイザーにして似た夢を追う二者による、時代に則し(または先駆け)たジャズのチュートリアル教育の現場であったことを、少なからず拡大解釈〜誇大妄想の中でイメージさせてしまう。翌70年3月7日のフィルモア東公演をもってグループを離れるが、大燃焼ギネスを記録したこの日の「Directions」や「It's About That Time」の鮮明でジェネリックな可視化によって、さらに興味深い何かが明るみになるのかもしれない。
ショーターはその後どうなったか
 ウェイン・ショーター
ウェイン・ショーター
『Moto Grosso Feio』 (1970)
『Moto Grosso Feio』 (1970)
 1970年3月7日のフィルモア・イースト公演を最後にマイルス・バンドを離れたショーター。それからわずか1ヶ月後の4月3日にブルーノートに録音された、『Super Nova』 共々この時期のショーターの抽象世界が余すところなく描き上げられたミステリアスな傑作。「南米のアマゾン」を意味するその表題もさることながら、前作「Dindi」からさらに深く突っ込んだ結果花開いた、ブラジル音楽を軸とした複合的なリズム・アプローチの数々。のちの『Native Dancer』や『Tales Spinnin'』ほど土着的ではないが、ミルトン・ナシメントのカヴァー「Vera Cruz」などでは、ブラジル音楽の美しく神秘的な側面が巧みに表現されている。またパーソネルが中々イビツで、ロスト・クインテット・メンバー+@が参加するものの、チックはドラム/パーカッション/マリンバ、ホランドはギター、マクラフリンは12弦ギター、さらにミシェリン・プレルなる弱冠19歳の”謎の”ベルギー人女性がドラムで数曲に参加と、まるで集団即興性と紙一重の混乱を意図的に招いているかのようだ。ラストの「Iska」は、ビッチェズの世界観をも凌ぐカオティック/ミスティックで圧倒的な音の渦。
1970年3月7日のフィルモア・イースト公演を最後にマイルス・バンドを離れたショーター。それからわずか1ヶ月後の4月3日にブルーノートに録音された、『Super Nova』 共々この時期のショーターの抽象世界が余すところなく描き上げられたミステリアスな傑作。「南米のアマゾン」を意味するその表題もさることながら、前作「Dindi」からさらに深く突っ込んだ結果花開いた、ブラジル音楽を軸とした複合的なリズム・アプローチの数々。のちの『Native Dancer』や『Tales Spinnin'』ほど土着的ではないが、ミルトン・ナシメントのカヴァー「Vera Cruz」などでは、ブラジル音楽の美しく神秘的な側面が巧みに表現されている。またパーソネルが中々イビツで、ロスト・クインテット・メンバー+@が参加するものの、チックはドラム/パーカッション/マリンバ、ホランドはギター、マクラフリンは12弦ギター、さらにミシェリン・プレルなる弱冠19歳の”謎の”ベルギー人女性がドラムで数曲に参加と、まるで集団即興性と紙一重の混乱を意図的に招いているかのようだ。ラストの「Iska」は、ビッチェズの世界観をも凌ぐカオティック/ミスティックで圧倒的な音の渦。
 ウェザー・リポート
ウェザー・リポート
『Weather Report』 (1971)
『Weather Report』 (1971)
 『In A Silent Way』、『Bitches Brew』のレコーディングをきっかけに再会を果たした、メイナード・ファーガソン・ビッグバンド時代の旧友ショーターとザビヌルが、アルフォンス・ムーゾン(ds)、アイアート・モレイラ(per)、ミロスラフ・ヴィトウス(b)を迎えて1971年に結成したグループ。同年2〜3月に録音されたこのデビュー・アルバムは、アコースティック・ジャズの可能性を実験的な角度から強く推し進める中で、結果その枠組みからはどんどんと乖離していったユニークな記録をも捉えている。まさしくジャズの飛翔とでも言うべき、真新しい70年代型集団即興の金字塔だ。初期においてイニシアチヴを握っていたヴィトウスが引っ張る「Umbrellas」や、ショーター、ザヴィヌル、ヴィトウスがガンガン ソロを回し、せめぎ合う「Seventh Arrow」など、序盤から電化マイルスとは種の異なるエキサイト・シーンの応酬。ただ作品のトーンは一定せず、『Big Fun』で明らかになった「Orange Lady」など、束の間牧歌的な時間も訪れる。終盤の「Tears」にしてもショーターの目線でじっくり練り上げられ、爽快な中にもどこか幻想的なムードが介在。密度の濃い電化マイルスとの関連性云々というよりは、のちのRTFなどでも顕著な「間の取り方」にこそこのグループの特徴があると思う。
『In A Silent Way』、『Bitches Brew』のレコーディングをきっかけに再会を果たした、メイナード・ファーガソン・ビッグバンド時代の旧友ショーターとザビヌルが、アルフォンス・ムーゾン(ds)、アイアート・モレイラ(per)、ミロスラフ・ヴィトウス(b)を迎えて1971年に結成したグループ。同年2〜3月に録音されたこのデビュー・アルバムは、アコースティック・ジャズの可能性を実験的な角度から強く推し進める中で、結果その枠組みからはどんどんと乖離していったユニークな記録をも捉えている。まさしくジャズの飛翔とでも言うべき、真新しい70年代型集団即興の金字塔だ。初期においてイニシアチヴを握っていたヴィトウスが引っ張る「Umbrellas」や、ショーター、ザヴィヌル、ヴィトウスがガンガン ソロを回し、せめぎ合う「Seventh Arrow」など、序盤から電化マイルスとは種の異なるエキサイト・シーンの応酬。ただ作品のトーンは一定せず、『Big Fun』で明らかになった「Orange Lady」など、束の間牧歌的な時間も訪れる。終盤の「Tears」にしてもショーターの目線でじっくり練り上げられ、爽快な中にもどこか幻想的なムードが介在。密度の濃い電化マイルスとの関連性云々というよりは、のちのRTFなどでも顕著な「間の取り方」にこそこのグループの特徴があると思う。
1969年がポピュラー音楽界、ことさらロック・フィールドにとって特別意味のある年だったとしても、ことライヴの現場においてマイルスは一気にアクセルを踏み込まず、結果「準電化」という一方で大きなジレンマと混乱を招きかねない虻蜂取らずのようなフォーマットを、丸一年ジャズ・クラブ興行の中で継続し熟成させていった。さらに、そのスジのアイコンたちと(表層的にでも)仲睦まじげにクリンチを繰り返したことも意に介さず、むしろこの時点ではそれが殆どなかったことのように、「長髪の白人のガキ共」を相手にした大規模コンサートに対する強烈なディスを吐き捨てた。関係者誰もが、マイルスにとっての「ロックの1969年」というのは、凡そその程度のことでしかなかったのだろうと高を括っていたが、実際ニューポート・ジャズ・フェスティヴァル出演〜ウッドストック閉幕後にスタジオ入りし制作された『Bitches Brew』には、「ロックの1969年」に静かに震えたマイルス自身の姿がしっかりと投影されていた。
いずれにせよ、テオ・マセロとの二人三脚による緻密なテープ・エディットがコロムビア・スタジオで音盤に記録される一方で、ただの一度として彼らロスト・クインテットの純粋な演奏が当時において陽の目を見なかったのは、いくら慎重で、のちの隠居前夜までパンパンに膨れ上がるアガパン・バンドへの単なる助走やブリッジでしかなかったということに例え固執したとしても、それはあまりにも片手落ちで雑駁すぎるというのが、90年代以降突如として多く現れたハイブロウな結論であり、したがって、『1969 Miles』はそのクレームにも似た指摘に対するひとつの回答としての役割をきっちり果たしたことになる。
が、それだけでは、永続的に行なわれているセッションの向こう側に、ロスト・クインテットの失われた総体を透かして見るのはあまりにも不可能であると。ロックの刹那とファンクの律動に彩られ、2曲で魔法の切り貼り加工が成された『Bitches Brew』という過去のジャズ史に類を見ない問題作を軸にした場合、やはり公に語られるべき、明らかにされるべきはロスト・クインテットのビッチェズ 8月録音前後の ”状態変化” とその ”経過観察”。つまり複数の公演記録を並べてこそのモノダネだったということである。
いくらか強引な結びかもしれないが、ロスト・クインテットは、「7月の顔」 「11月の顔」というビッチェズ時間軸に基づく進化/深化の過程を、いよいよ公式の場に露にする。
参考図書
 中山康樹
中山康樹
『マイルスの夏、1969』
『マイルスの夏、1969』
 世紀の傑作誕生の秘密に迫る、ジャズ評論の新しい挑戦! ジャズの帝王マイルス・デイヴィスの金字塔『ビッチェズ・ブリュー』。マイルス研究の第一人者が、このアルバム誕生の秘密に迫る。そのスリルは、まさに探偵小説さながら。
世紀の傑作誕生の秘密に迫る、ジャズ評論の新しい挑戦! ジャズの帝王マイルス・デイヴィスの金字塔『ビッチェズ・ブリュー』。マイルス研究の第一人者が、このアルバム誕生の秘密に迫る。そのスリルは、まさに探偵小説さながら。目次 :
第1章 魔女の季節 / 第2章 未遂の美学 / 第3章 夜を往く舟 / 第4章 家族の肖像、イギリスからの使者 / 第5章 おお、神のご加護を / 第6章 ミスター&ミセス・デイヴィスの冒険 / 第7章 マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥー・ダウン / 第8章 フェスティヴァルの終わり、ストリートの夏
 菊地成孔 / 大谷能生
菊地成孔 / 大谷能生
『M/D マイルス・デューイ・デイヴィス3世研究 (下)』
『M/D マイルス・デューイ・デイヴィス3世研究 (下)』
 下巻はエレクトリック期から沈黙の六年、そして晩年まで。『憂鬱と官能』コンビの東京大学講義録となる、当時没後二十年を迎えようとしていたマイルスに迫る名著の文庫版。
下巻はエレクトリック期から沈黙の六年、そして晩年まで。『憂鬱と官能』コンビの東京大学講義録となる、当時没後二十年を迎えようとしていたマイルスに迫る名著の文庫版。目次 :
第4章 電化、磁化、神格化― 1966−1976(アコースティックからエレクトリックへ / さらなる電化/磁化への道程 / エレクトリック・マイルスの構造分析 / 『オン・ザ・コーナー』から引退まで) / 第5章 帝王の帰還―復帰 ‐1991(帝王のいない六年 / 八〇年代の感傷的な速度 / 帝王の退場、二〇世紀の終わり
 『マイルス・デイビス 不滅の帝王』
『マイルス・デイビス 不滅の帝王』
(KAWADE夢ムック 増補新版)
(KAWADE夢ムック 増補新版)
 2011年に没後20年を迎えた巨星マイルスの魅力と可能性を豪華な顔ぶれで検証する決定版。中山康樹、後藤雅洋、村井康司、原雅明の座談、菊地成孔、大谷能生、中山康樹の討議を増補。さらに、「マイルス・ディスコグラフィ 2001〜2011」(杉田宏樹編:p218〜222)、「マイルス・デイビス年表&ディスコグラフィ」(杉田宏樹編:p223〜247)などを追加。
2011年に没後20年を迎えた巨星マイルスの魅力と可能性を豪華な顔ぶれで検証する決定版。中山康樹、後藤雅洋、村井康司、原雅明の座談、菊地成孔、大谷能生、中山康樹の討議を増補。さらに、「マイルス・ディスコグラフィ 2001〜2011」(杉田宏樹編:p218〜222)、「マイルス・デイビス年表&ディスコグラフィ」(杉田宏樹編:p223〜247)などを追加。
 『マイルス・デイヴィス・ディスクガイド』
『マイルス・デイヴィス・ディスクガイド』
(レコードコレクターズ増刊)
(レコードコレクターズ増刊)
 マイルスが残した厖大な数のオフィシャル・アルバムを、その歩みをたどりながらていねいに解説。セッション別のボックス・セットや特別編集盤もわかりやすく紹介しました。また、ジャズ史にその名を残す歴代共演者120人の“マイルス的”代表作をセレクト。さらにDVDや参加アルバムを含め、マイルスの作品の全体像とその周辺まで理解できる、これまでになかったディスク・ガイド。
マイルスが残した厖大な数のオフィシャル・アルバムを、その歩みをたどりながらていねいに解説。セッション別のボックス・セットや特別編集盤もわかりやすく紹介しました。また、ジャズ史にその名を残す歴代共演者120人の“マイルス的”代表作をセレクト。さらにDVDや参加アルバムを含め、マイルスの作品の全体像とその周辺まで理解できる、これまでになかったディスク・ガイド。
 21世紀に花咲いた エレクトリック・マイルスの種子
21世紀に花咲いた エレクトリック・マイルスの種子
 Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O.
Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O.『Son Of A Bitches Brew』 (2012)
マーズ・ヴォルタ、モグワイ、さらにはゴング、テリー・ライリーら海外の同志強兵からも絶大なプロップスを得ている、日本が世界に誇るトリップ・サイケの剛毅アシッド・マザーズ・テンプル(&ザ・メルティング・パライソ U.F.O.)。「我らビッチェズのせがれ也」と題された最新アルバムは、冒頭からビッチェズを軽く飛び越えて、一気にオン・ザ・コーナー〜アガパンのカオスへ。掬えども掬えども溢れ出る音・音・音。脳をかきむしられ、こねくり回され、トバされて・・・ それでもなお中毒症状を引き起こしそうなハイと酩酊を手に入れることができる。「John McLaughlin」ならぬ「Tabata Mitsuru」もキワどい。
 Fontanelle 『Vitamin F』
Fontanelle 『Vitamin F』(2012)
米シアトルのドゥームメタル/ドローン/ノイズ・バンド、サン O))) にサポート・ミュージシャンとして参加していたレックス・リターを中心に結成されたフォンタネルの1stアルバム。ギター・サウンドが幅を利かせてはいるものの、「ヘヴィロック〜ドローン〜ジャズ〜現代音楽をつなぐミッシングリンク」と称されるだけあって、一筋縄ではいかない多様な質感がゴッタ返し煮え立つ。「The ADJacent Possible」がビッチェズに流れる重く不穏な空気を匂わせれば、「Watermelon Hands」のジワジワと締め上げる感じは、まさにビッチェズ以降、フィルモアやライヴ・イーヴィルの世界を想起させる。プロデュース/ミックスは勿論 サン O))) のランドール・ダン。
 DCPRG
DCPRG『Second Report From Iron Mountain USA』
(2012)
Impulse! 移籍第2弾は、SIMI LAB 4MCズ、ジャズ・ドミュニスターズ、さらにはボーカロイド:兎眠りおんが揃い踏む、脅威のDCPRG流ヒップホップ・アルバムに。また、前作収録の「New York Girl」に続く注目の帝王カヴァーは、『The Complete Jack Johnson Sessions』に収録されていた「Duran」。帝王の閃きとマクラフリンのファズが音頭を取るJB〜ジミヘン式ファンク・ロック祭りに、リロイ・ジョーンズ(aka アミリ・バラカ)のアナウンステープをサンプリング&スクラッチ&ミックス。それはあたかも、昨今局地的ながら再燃する巷の”ヒップホップ×マイルス”議論にDCPRGが叩き付けたひとつの回答のよう。
 Animation 『Asiento』
Animation 『Asiento』(2011)
ブルーノート研究でもその名を知られるサックス奏者/プロデューサー、ボブ・ベルデン率いるアンダーグラウンド・ジャズ・バンド、アニメーションによるビッチェズ・カヴァー・アルバム(英RareNose Records)。バンドは、ベルデン以下、トライバル・テックのスコット・キンゼイ(key)、独ACTに『Future Miles』(02年)というリーダー作も残すティム・ハーゲン(tp)、ジミー・ギャリソンの息子マシュー・ギャリソン(b)、ビル・ラズウェルのメソッド・オブ・ディファイアンスにも在籍するガイ・リカタ(ds)、そしてジョン・スコフィールドやジョン・メデスキなど多くのジャズ・セッションに引っ張りだこのDJ ロジックという猛者揃いのセクステット。人力とは思えないドラムンベース系のファンク・サウンドで、現代においてビッチェズがダンス・ミュージックとしていかに機能的かという是非を問う。
 Mederic Collignon 『Shangri-Tunkashi-La』
Mederic Collignon 『Shangri-Tunkashi-La』(2010)
強烈な電化ハイトーン、からのウニョウニョ。フランスのトランペッター、メデリック・コリニョンは、別働エレクトリック・プロジェクト、コレクティーフ・スラングを率いて八面六臂の活躍をみせる、仏・新世代ジャズ・シーンの中心的存在。本作では、電化マイルスの世界をカルテットで再現。ビッチェズや「Shhh Peaceful / It's About Time」などの定番曲ほか、「Billy Preston」、「Ife」、さらにはザビヌル作「Early Minor」、エルメート・パスコアール作「Nem Um Talves」といった比較的珍しい楽曲をレパートリーに組み込んでいるのがミソか。ツェッペリン「Kashmir」はご愛嬌。
 Will Sessions 『Kindred EP』 [Analog]
Will Sessions 『Kindred EP』 [Analog](2010)
スラム・ヴィレッジやブラック・ミルクらとも親交が深く、また一昨年、エルザイ(スラム・ヴィレッジ)との共演で ナズ『Illmatic』の全編カヴァーアルバム『Elmatic』を発表し話題をさらったデトロイトのファンク・バンド、ウィル・セッションズ、その1st EP(現状アナログのみ)。同郷のサックス・レジェンド、ウェンデル・ハリソンを迎えた表題曲にしても、「Interlude」とテキサス・ファンクの合いの子のような「Polyester People」にしても、ほんのり漂う電化マイルス臭に思わずニヤリ。サン・ラ名曲のオマージュ「Omniverse」も収録。
 U.T. Gandhi Fearless Five 『Travellers』
U.T. Gandhi Fearless Five 『Travellers』(2008)
ドラマーのU.T. ガンディことウンベルト・トロンベッタ率いるイタリアン・クインテットによるマイルス・トリビュート。ザビヌル作の「Doctor Honoris Causa」、「Orange Lady」、「Early Minor」、ショーター作の「Pinocchio」、パスコアール作の「Nem Um Talves」、あるいは「Recollections」、「Take It Or Leave It」といった『Complete Bitches Brew Sessions』(または『Big Fun』のボーナストラック)収録楽曲が並んでおり、前述のメデリック・コリニョン盤同様 ”周囲” の人間にきっちりフォーカスしている選曲はファンには嬉しいところだろう。ちなみにガンディは、2010年にウェザー・リポートのトリビュート・アルバムも制作している。
[こちらの商品は現在お取り扱いしておりません]
 Cesare Dell'anna 『My Miles』
Cesare Dell'anna 『My Miles』(2007)
オパ・クパなど個性的なジプシー・ブラス系ミクスチャーバンドを率いて注目を集めるイタリアの鬼才トランペッター、チェザレ・デッランナの初ソロ・アルバムにして会心のエレクトリック・マイルス・トリビュート。ただし、80年代マイルス・バンドの屋台骨を支えたアダム・ホルツマン(key,synth)の参加(3曲)が功を奏してか、ビッチェズ〜アガパンの世界に限定したものではなく、晩年のヒップホップ期に至るまでの包括的なエレクトリック・マイルス・フィーリングを体感できる。打ち込みによるブレイクビーツ、四つ打ちトラックを多用するも決して無味乾燥になることなく、マイルス的ともまた違う独特のセクシーな妖気を生み出している。
 Yesterdays New Quintet 『Yesterday's Universe』
Yesterdays New Quintet 『Yesterday's Universe』(2007)
ラスト・エレクトロ・アコースティック・ジャズ&パーカッション・アンサンブルのタイトルがいくら『Miles Away』でも、やはりエレクトリック・マイルスと直接的に結び付けるのは気が引ける。というかほぼ不可能だ。マッドリブのサウンドは、例え抽象的な表現を用いたとしてもオマージュの対象がハッキリしている。となると、コレしかない。多重人格ジャズ事業計画 イエスタデイズ・ニュー・クインテットのどんずば ビッチェズ・カヴァー。ファズ・ベースが地を這い、ドープ・フルートが毒を撒き散らす。シンプルなれど確実にキテる。もしマイルスが存命だったら、「よぉ俺にトラックを作ってくれよ、マザーファッカー」と、この希代のビートメイカーにベタ惚れだったかもしれない。
 Eivind Aarset 『Sonic Codex』
Eivind Aarset 『Sonic Codex』(2007)
北欧では、マイルスでジャズに開眼し、「フューチャー・ジャズ」と呼ばれる新時代の音を生み出し続けるトランペッター、ニルス・ペッター・モルヴェルが、ポスト電化マイルス・サウンドの筆頭として有名だろう。そしてもうひとり、強引ながらもその文脈で語りたいパフォーマーがいる。ニルスのバンドなどで活躍するギタリスト、アイヴァン・オールセットだ。2010年のライヴ・アルバム『Live Extracts』や、N.Y. タイムズ紙で「近年ピカイチのポスト・マイルス的エレクトロニック・ジャズアルバム」と称賛された1stアルバム『Electronique Noire』も捨てがたいのだが、個人的には本盤収録の「The Return Of Black Noise And Murky Lamabada」が、他のどの曲よりも電化マイルスの世界に密にリンクしているように思えてならない。
 「エレクトリック・マイルス」 中山康樹さんに訊く
「エレクトリック・マイルス」 中山康樹さんに訊く 壮大なスケールと密度の「帝王・超電化絵巻」。その謎を解き明かす。最新著書『エレクトリック・マイルス 1972-1975』を発刊されたマイルス研究の第一人者、中山康樹さんにお話を伺いました。
 【特集】 電化帝王学と 「ビッチェズ」について
【特集】 電化帝王学と 「ビッチェズ」について マイルス・デイヴィス『Bitches Brew』 40周年記念国内レガシー盤が到着。未発表ライヴ音源CD、未発表ライヴDVD等を追加した完全生産限定のつゆだく特盛丼。
 【特集】 マイルス・デイヴィス『TUTU』
【特集】 マイルス・デイヴィス『TUTU』 マイルス・デイヴィスの1986年ワーナー移籍第1弾作品『TUTU』が、本編リマスター、さらには同年7月のニース公演音源を追加した2枚組豪華盤にて登場。マーカスの「TUTU追憶ライヴ」も同発!
 「マイルス ラスト・イヤーズ」 中山康樹さんに訊く
「マイルス ラスト・イヤーズ」 中山康樹さんに訊く 奇跡のカムバックを果たした帝王が往くさらなる荒野。前回の「電化マイルス」講習に引き続き、中山康樹さんをお迎えしておくる「マイルス 華麗なるラスト・イヤーズ」についてのお話。
 【インタビュー】 DCPRG 菊地成孔 × ヒップホップ (2012年)
【インタビュー】 DCPRG 菊地成孔 × ヒップホップ (2012年) DCPRG 新作は、SIMI LAB、ボカロ、大谷能生氏参戦の完全ヒップホップ仕様のアルバムに。その完成を記念して、主幹・菊地成孔氏にお話を伺ってまいりました。
 【インタビュー】 DCPRG 菊地成孔 (2011年)
【インタビュー】 DCPRG 菊地成孔 (2011年) アルバム『Alter War In Tokyo』がImpulse! から遂に到着。活動再開から1周年を迎えた新生デートコースのここまでとこれから。主幹・菊地成孔さんに色々と伺ってまいりました。
