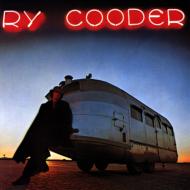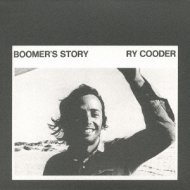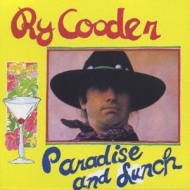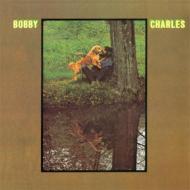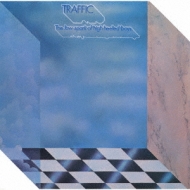Thursday, May 6th 2010

- --- この時期はミック・テイラーの加入もそうですが、とりわけサポート・メンバーとの協力体制がストーンズにとっては大きかったのではないでしょうか? ボビー・キーズ、ジム・プライス、ビリー・プレストン、ニキ・ホプキンズ・・・
ボビー・キーズとジム・プライスはレコーディング中ずっとネルコットにいましたよね。ニキ・ホプキンズもそう。ボビーはキースとまったく同じ日(1943年12月18日)に生まれているんですって。「ヤツは素晴らしいサックス・プレイヤーだけど、唯一の欠点はテキサス出身だっていうところ」って、『Stones In Exile』の中でもキースが冗談を言ってましたけど(笑)、そのぐらいツーカーの仲。
- --- ビリー・プレストンは、ストーンズとの交流以前にビートルズの「ゲット・バック・セッション」でロック・ファンに広く名前が知れていきました。
ビリー本人もあの時期にいくつかヒット曲があって、Appleから出した「That's The Way God Planned It」とか、A&Mから出した「Outa Space」とか「Will It Go Round In Circles」とか。元々はジョージ・ハリスンの手引きがあって、ビートルズやストーンズなどのセッションに招かれるようになりましたからね。
-
--- 『All Things Must Pass』や『Concert For Bangladesh』といったジョージ・ハリスンの当時の作風をふまえれば、ビリーがこの時期の南部志向のストーンズ作品に参加することになったのはごく自然なことだったんでしょうね。
あの時代はみんなアメリカ南部のサウンドにすごく影響を受けていましたね。エリック・クラプトンなんかは、(註)デレイニー&ボニーのトゥアー・メンバーになってしまうぐらいの衝撃を受けていたわけですから。ちょうど、(註)J.J.ケイルといった人たちも出てきますし、スワンプ・ロックではないけれど、(註)グラム・パーソンズ、(註)フライング・ブリートー・ブラザーズといったカントリー・ロックも盛り上がっている。
フライング・ブリートー・ブラザーズは、カントリーとソウルの両方の要素を持っているグループですよね。(註)レオン・ラセルなんかにしてもそうだし。- --- たしかにレオンは、『Hank Wilson's Back』というカントリー・アルバムを作っていたりもしますね。
そういうのもありましたし、元々の彼の歌い方がかなりカントリーっぽいし、その一方で(註)Dr.ジョンに近いものも持っているという感じなんですよね。ようするにアメリカ南部の音楽は、常に境界線がはっきりしないものだと思うんです。カントリーもあり、ブルーズもあり。リズム・アンド・ブルーズからソウルの時代に入っても、例えば同じ曲を黒人が歌えば「ソウル」になるし、白人が歌えば「カントリー」になるっていう、ちょっとした編曲の違いでどっちがどうっていう判別ができないものがいっぱいあるから。そういったことが70年代の初頭に全て一緒くたになったっていう感じだと思うんですよ。『メインストリートのならず者』はそのことを的確に言い表しているようなアルバムということもあって、当時判りにくかったのかなと思いますね。
(註) 文中に登場するアーティストの主なアルバム
- --- ストーンズの作品に限らず、この時期に作られたロックのアルバムには、そうしたアメリカ・ルーツ・ミュージックの“ごった煮”感がおしなべて強かったり、多少なりともルーツ回帰を意識しているものが多かったのでしょうか?
多かったとは思いますが、まだ当時は、今の様に捉えていなかったかもしれません。ほぼ40年経った今振り返ったときに、それぞれの相互関係が見えてくるんですけど、当時は僕らも興味があったレコードを全部買えるような経済状況でもなかったから(笑)、知らないものも多かった。だから、どうしても断片的にしか捉えられなかったんですね。
例えばグラム・パーソンズにしたって、当時イギリスではかなり“渋い存在”。(註)バーズの『ロデオの恋人』は、本当にごく一部のカントリーに興味があったような人たちしか買っていなかったアルバムだったと思います。
バーズは、ボブ・ディランのカヴァーをやったり、もっとフォーク・ロック色の強い時期のヒット曲が多かったから、かなりカントリー寄りの『ロデオの恋人』を友人に聴かせてもらったときはピンとこなかった。17歳ぐらいのときだったかな。今は好きですよ。その当時何が流行っていたかっていうと、ジミ・ヘンドリックスだったり、ブルーズ・ロック、サイケデリック・ロックだったりだから、僕も含めて『ロデオの恋人』を聴いてもピンとこなかった人は多かったんじゃないかな。
僕にとって、「あっ!違う方向があるんだ」ということを発見させてくれたレコードというのが、ザ・バンドの(註)『Music From The Big Pink』。このアルバムも『ロデオの恋人』とほぼ同時期に出たんだけど、ザ・バンドの方がなぜかしっくりくるレコードでしたね。

(註)ザ・バンド 『Music From The Big Pink』・・・サイケデリック革命真っ盛りの1968年にレコーディングされたザ・バンドの記念すべき1stアルバムは、ウッドストック・サウンドの道先案内人としてタクトを揮っていたジョン・サイモンのプロデュースも手伝い、母国のアーシーなルーツ・ミュージック探求旅行の奥深さと愉しさを窺わせてくれる。ロビー・ロバートソン、リック・ダンコ、リチャード・マニュエル、リヴォン・ヘルム、ガース・ハドソン。歌える3人に各種楽器をマルチに操ることができる2人、というバランスが洗練され過ぎずに最も有機的に機能した最高の見本。また、親方ボブ・ディランとの共作「Tears of Rage」、「I Shall Be Released」などでのリチャード・マニュエルの歌唱は永遠。アメリカン・トラッド、リズム・アンド・ブルーズ、ゴスペル、カントリー、ブルーズといった種々の音楽を十分に咀嚼した上で自らの音へと展開させる、そのセンスがズバ抜けてよい。ちなみにジャケ画はボブ・ディラン。 - --- 同じアメリカン・ルーツを辿ったレコードでも、“ピンとくるもの”と“こないもの”では感覚的にどのあたりに違いがあったのでしょうか?
『ロデオの恋人』はもろにカントリーのレコードでしたから、中にはSTAXのウィリアム・ベルのカヴァー曲があったりはしましたけど、ペダル・スティール・ギターを全面に取り入れていたり、ジャケットのイメージなんかにしてももろにカントリー。あの時代、カントリー・ミュージックは“ダサい”っていうイメージがあったんですよ。ブリートー・ブラザーズはあえて(註)ヌーディ・スーツを着ていたりしてたじゃないですか? だから、当時の若いロック・ファンの間では、「え? コレはちょっと違うんじゃない?」っていうところがありました(笑)。今となっては違う見方をするんですけど、若いときはファッションを気にしますよね? その分ちゃんと音楽的な部分を捉えることができなかったんですね。だから、当時『ロデオの恋人』やブリートー・ブラザーズの初期のアルバムが好きだったっていう人はよっぽど先見の明があったんだと思います。
ブリートー・ブラザーズを初めていいなと思ったのが、グラム・パーソンズがいなくなった後のライヴ・アルバム(『The Last Of Red Hot Burritos』)だから。あのアルバムでは、中盤にブルーグラス・コーナーが入っているんだけれど、ブルーグラスってまた別の魅力があるんですよね。でまた、ロック色も強いんですよ。初期のブリートー・ブラザーズを好きになったのはもっと後ですね。

(註)ヌーディ・スーツ・・・ハンク・スノウやファーリン・ハスキーといったカントリー・ミュージシャンに欠かせないステージ衣装「ヌーディ・スーツ」は、50〜60年代当時のハリウッド・スターご用達のテイラーとして人気だったヌーディ・コーン氏によってデザインされた”一張羅”のスーツ。ラインストーンをふんだんに散りばめてカラフルな生地に様々なモチーフを刺繍しているのが特徴で、「リッチ&ゴージャス」な装いを存分に醸し出す。カントリー界の大物たちに加え、あのエルビス・プレスリーも常連客だったそう。その後迎えた「カントリー・ロック」という70年代のリヴァイヴァル・ムーヴメントの中では、グラム・パーソンズや彼が率いたフライング・ブリートー・ブラザーズがヌーディ・スーツをオーダーメイドで愛着(左下写真はグラムとヌーディ氏)。グラム・パーソンズの再評価が高まった90年代後半以降にも、ウィルコのジェフ・トゥイーディやフーティー・アンド・ザ・ブロウフィッシュのダリアス・ラッカーなどがカントリー・ミュージック・カルチャーへの敬意を込めてヌーディ・スーツを愛着している。 - --- ブリートー・ブラザーズは1stアルバムの『Gilded Palace Of Sin』で「Wild Horses」を取り上げていますよね。
当時はおそらく(ブリートー・ブラザーズのヴァージョンは)聴いていないと思いますが、本家のストーンズがやるとまた違うんですよ。若いときに耳にする印象としては。
- --- ちなみにグラム・パーソンズとストーンズの交流というのは、68年のバーズのロンドン公演のホスト役をミックとキースが買って出たことに始まったらしいんですね。その後意気投合してすぐに「Country Honk」を録ることになったそうなんですよ。
でも、当時グラム・パーソンズという名前は、“ストーンズと関わりのある人物”としてときどき耳にするぐらいだったんですよ。だから、彼のソロ・アルバムも当時は全く聴いていなかった。
- --- グラムの再評価は90年代に入ってからというのもありますよね。98年に日本盤でCD化され初めてグラムのソロなどを聴いてから、あらためて「Sweet Virginia」などを聴くと、特にキースがグラムから受けた強い影響を窺い知れたり、といったような文脈で取り上げられたりもして。
なるほどね。あと、これは『Stones In Exile』の中でシェリル・クロウが言っていたんだけれど、アメリカでは「Sweet Virginia」が究極のジャム・ソングなんだってね。お互い知らないミュージシャン同士が集まってジャム・セッションをする時、とにかく「Sweet Virginia」を知らなければ、そういったセッションの場に参加できない。つまり、この曲ができれば誰とでもジャムができるっていうことを言っていましたね。それは面白いと思った。
- --- 「Sweet Virginia」は一大ジャム・アンセムだったんですね。ちなみに、「カントリー・ロック」という言葉自体は70年代初頭当時すでに存在していたのでしょうか?
71、2年ぐらいからなんとなく「カントリー・ロック」という言葉は使われ始めていたと思います。ブリートー・ブラザーズがそう呼ばれる最初だったかな。あと、(註)バファロー・スプリングフィールドもちょっとそういう感じがあったかもしれないけど、60年代にはまだなかった言葉。もう少し後になって、ジム・メシーナやラスティー・ヤングのやっていた(註)ポコなんかがまさしく「カントリー・ロック」と呼ばれていたんじゃないかな。(註)イーグルズのデビューもちょうどその後ぐらいになると思うしね。イーグルズのデビュー・アルバムはすごく新鮮でした。グリン・ジョンズがプロデュースしているんだけれど、彼はアクースティック・ギターの音を綺麗に録るエンジニア/プロデューサーとして当時評判だったんです。
ただ、「スワンプ・ロック」という括りは、『メインストリートのならず者』が出た当時にはなかったと思います。いつ頃からだろうね、そういう言葉が出てきたのは? 同時期に出たDr.ジョンの『Gumbo』にしても、スワンプ云々というよりも「ニューオーリンズにこんな音楽があったのか!?」っていう驚きのほうが僕には大きかったから。あとは、(註)ライ・クーダーなんかもちょうど72年の『Into The Purple Valley』から聴き始めて、J.J.ケイルの『Naturally』、(註)ボビー・チャールズの『Bobby Charles』、(註)ポール・バタフィールドの『Better Days』だとか、今考えればアメリカのルーツ・ミュージックの“はしり”みたいなアルバムが、この時期に集中して出てきていたことはたしかです。いわゆる“玄人好み”なものではあったけれど、僕はたまたまラジオで耳にして「いいなぁ」と思って買っていましたね。
(註) 文中に登場するカントリー・ロック、またはその前夜の主なアルバム+@
- --- そうしたアメリカン・ルーツ・ミュージックに根差したアルバムが、当時“玄人好み”だったことを考えれば、同じような流れを汲んでいると言えそうな『メインストリートのならず者』も、やはり当時は“玄人好み”な1枚としてみなされてしまった気もするのですが・・・
やっぱり当時は、ストーンズの中ではそんなに人気のあったレコードではなかった・・・と言われているんだけれど、ただ「Tumbling Dice」が大ヒットして毎日ラジオでかかっていたのは事実だから。実際の売り上げは判らないけど、それを考えるだけでもとてもヒットしていなかったと言われるアルバムとは思えないんですよね。
- --- この時期、こうしたアメリカのルーツ・ミュージックを探求したアルバムで、ストーンズ以外のイギリス勢の作品でお好きなものというのは?
70年代初頭に、純粋に僕がいちばん好きだったイギリスのバンドはトラフィックでしたね。(註)『John Barleycorn Must Die』がいちばん好きかな。あれは傑作だと思う。アメリカのルーツ・ミュージックの影響もあるけど、イギリスのフォークの影響もかなり色濃く出ていて、スティーヴ・ウィンウッドという人は昔からそうなんですよ。ブルーズやソウルも大好きなら、フォークやジャズも大好きだっていうぐらいで、本人の頭の中では全部が一体となっている感じで、特にそれらを区別しているわけではないそうなんですよね。そういうところが僕は好きでしたね。
(註) 70年代初期のトラフィックの主なアルバム
あとは、ロッド・スチュワート。フェイセズよりもロッドのソロのレコードが大好きでした。大学生当時に(註)『Gasoline Alley』のレコードを見つけたときは、狂ったように聴いていましたね(笑)。あれと(註)『Every Picture Tells A Story』の2枚は今でも好きで、ラジオでよくかけますね。あの頃のロッド・スチュワートがイギリスでいちばん輝いていた。『Atlantic Crossing』以降のロッドは全然おもしろくないんですけどね(笑)。結局、“スター街道”の誘惑みたいなものに負けちゃったんだと思う。
(註) 70年代初期のロッド・スチュワートの主なアルバム
とは言っても、このぐらいの時期にはほとんどアメリカの音楽を聴いていました。ブルーズは高1ぐらいで真剣に聴き始めて、ニューオリンズの音楽はDr.ジョンの『Gumbo』がきっかけとなって、そのすぐ後に(註)プロフェサー・ロングヘアの『New Orleans Piano』というアルバムを聴いてかなりハマるようになって。あとは、さっき言ったJ.J.ケイルやボビー・チャールズ、(註)オールマン・ブラザーズ・バンドなんかも好きでしたね。70年代に入るとオールマンや(註)Jガイルズ・バンドみたいなアメリカの白人ブルーズ・ロック・ブームみたいなものが始まって、またそれがすごいかっこよかったんですよね。それから、(註)リトル・フィート。73年の『Dixie Chicken』にハマって、そのままロウエル・ジョージが亡くなる79年ぐらいまで、狂ったようにリトル・フィートを聴いていましたね(笑)。だから、イギリスの音楽はほとんど聴いていなかったんですよ。
- --- 今回の『メインストリートのならず者』のスーパー・デラックス・エディションには、「Cocksucker Blues」の抜粋映像も付属されるということなのですが、一部でストーンズのオフ・ステージの破廉恥ぶりを余すことなく伝えているがゆえに、長らくお蔵入りとなっているいわくつきのフィルムですよね。
あれは昔からかなりブートレグが出回っていましたからね。ロバート・フランクが、あえてかなりゲリラ的にカメラを回していたもので、おもしろい部分もあれば、それほどでもない部分も個人的にはあるかなって思うんですが(笑)、でもまぁストーンズ・ファンがこの時期のひとつの記録として見る分には基本的には興味深いかなとは思います。
『Stones In Exile』の方はカンヌでも上映されるみたいで、これは本当におもしろい。完全なドキュメンタリー・フィルムなんですが、これこそファンならば観て全く損はない内容。1時間ほどの本編ドキュメンタリーに、特典映像として、ストーンズや当時のサポート・メンバーたちのインタヴューが入っていて。ボビー・キーズ、ジム・プライス、アンディ・ジョンズ、ジミー・ミラーなんかが出てきてたかな。アンディ・ジョンズは、これが初めてのエンジニア仕事で当時まだ21歳。すごく感動したということを語っていましたね。- --- 21歳、しかも初めての大仕事で、よくストーンズに付いていけたなという話ですよね(笑)。
彼はネルコットにも同行していましたからね。かなり大変だったと思う。ドン・ウォズの回想には、「このアルバムは、ドラッグの種類が変わったのも大きい」なんていうのもあったかな(笑)。つまり、“コカイン”がこのあたりでかなりで出てくるんじゃないかなと。それまではマリファナとLSDだから、まだかわいいものというか(笑)・・・ここからだんだんとヘヴィになってくる。
- --- 歌詞の部分でも“ヤクねた”をメタファーもしくは露骨に用いたりすることも多くなってきたのでしょうか?
『Sticky Fingers』には「Sister Morphine」なんて曲もあったけど、『メインストリートのならず者』に関してはもう歌詞がほとんど聴き取れないんだよね(笑)。
- --- たしかに当時の日本盤LPを見ると、何曲かで「歌詞聴取り不可能のため省略」となっていました(笑)。
今回の再発盤も歌詞については、日本側で聴き取ったものが採用されているので、是非原詞を読んでみたいんですよね。
『Stones In Exile』に話を戻せば、あとは、さっき言ったシェリル・クロウ、ジャック・ワイト、リズ・フェア、ウィル・アイ・アム(ブラック・アイド・ピーズ)、ドン・ウォズといった人たちのインタヴューも収めてあるんですよ。これを観ていると、けっこう『メインストリートのならず者』を後追いで聴いている人が多いんですよね。当時リアルタイムで聴いていたのは、ドン・ウォズぐらい。ウィル・アイ・アムなんかは、90年代に、入り浸ってた中古レコード屋で見つけて、「ストーンズのこのアルバムを持っているのは違いのわかるヤツだ」っていう意識で自分のレコード・バッグに入れていたそうなんですよね。- --- 僕もウィル・アイ・アムと同世代なので、完全に後追いになってしまう分、当然先にレビューなどの情報ありきで『メインストリートのならず者』を最初に聴いたパターンだったことはたしかですね。このアルバムに限った話ではありませんが。その分心の準備はできていたというか(笑)・・・リアルタイムで聴いた人たちに較べ困惑する感じはあまりなかったかと思います。
最初に聴いたストーンズのCDってちなみに何でした? リアルタイムで新しいもの?
- --- 廉価盤のベストでしたね。当時13か14の時で、87年ぐらいでした。
その当時はアルバム出してましたっけ?
- --- いえ、86年の『Dirty Work』から89年の『Steel Wheels』までのちょうど空白期で、キースがソロ・アルバムを出していたかなっていう時期でしたね。だから、世間一般的にはストーンズがどうこうといった感じもほとんどありませんでした。
来日もまだでしたからね。
- --- そうですね。初来日公演の大騒ぎでようやくローリング・ストーンズを、ある種リアルタイムなバンドとして受け止めることができるようになりましたね。90年の初来日公演には行かれたのですか?
行ってますね。その後も何回かは来日公演を観てるんですが・・・実は僕は、『Beggars Banquet』から『メインストリートのならず者』までの時期のストーンズは全部好きなんだけど、それ以降のアルバムに関しては、個人的に1枚もなくても困りはしない(笑)。ただ、こないだ『Love You Live』を久々に聴いたんだけれど、コレはかなり良かった。ちょっと見直しました。
昔から思っていたことなんですが、「世界一のロックンロール・バンド」と呼ばれるようになったのは、実際『Goat's Head Soup』や『It's Only Rock n' Roll』の後からなんですが、そういう風に言われるようになると、ある意味“おしまい”かなとも思ってて。本人たちがそのことをどこまで意識していたとかは判らないけれど、「あ、もうピーク過ぎたな」っていうのは当時から何となく感じていました。
『Goat's Head Soup』もそんなに好きじゃないし、「Angie」もラジオで聴きすぎたかなぁ(笑)・・・『It's Only Rock n' Roll』は、まぁ聴いてて楽しいんだけど、アルバムとしては決して傑作だとは思わない。『Black And Blue』も・・・どのアルバムもそれなりに聴ける曲があるんだけれど・・・『メインストリートのならず者』があまりにも出来が良すぎたから。ひとつのアルバム作品としての存在感があるのは、この時期までだって思ってしまうんですよね。もちろん 「いや、違う」って言う人もいっぱいいるんでしょうけど。
ただひとつ間違いなく言えることは、アメリカのルーツ・ミュージックが好きな僕のような人間にとっては、『メインストリートのならず者』はストーンズの最高傑作だっていうことでしょうね。
|
ローリング・ストーンズ その他の記事はこちら
 【スペシャル・インタビュー企画 第1回】 仲井戸 ”CHABO” 麗市
【スペシャル・インタビュー企画 第1回】 仲井戸 ”CHABO” 麗市
 【スペシャル・インタビュー企画 第3回】 寺田正典 (レコード・コレクターズ編集長)
【スペシャル・インタビュー企画 第3回】 寺田正典 (レコード・コレクターズ編集長)
 【スペシャル・インタビュー企画 第4回】 サエキけんぞう
【スペシャル・インタビュー企画 第4回】 サエキけんぞう
 【スペシャル・インタビュー企画 第5回】 中川敬 (ソウル・フラワー・ユニオン)
【スペシャル・インタビュー企画 第5回】 中川敬 (ソウル・フラワー・ユニオン)
 【スペシャル・インタビュー企画 最終回】 〈特別対談〉越谷政義 × 石坂敬一
【スペシャル・インタビュー企画 最終回】 〈特別対談〉越谷政義 × 石坂敬一
 『メインストリートのならず者』の真実
『メインストリートのならず者』の真実
 HMVオリ特決定! 『メインストリートのならず者』
HMVオリ特決定! 『メインストリートのならず者』
 【解剖】 『メインストリートのならず者』
【解剖】 『メインストリートのならず者』
 SHM-CD/紙ジャケ・ボックス第2弾
SHM-CD/紙ジャケ・ボックス第2弾
 ストーンズ 真夏のネブワーズ祭 1976
ストーンズ 真夏のネブワーズ祭 1976
ピーター・バラカン イベント&トークライヴ・スケジュール
Afro Blue Vol.2@Soul Bar Stone (新宿・大久保) *DJ 出演
会場:Soul Bar Stone(新宿・大久保)
日時:2010年5月22日(土)17:00-19:00(16:30開場)
料金:2500円(1ドリンク付き)
お問合せ:ウィンド
ピーター・バラカン×長田弘×野村恵子 トーク・ライヴ
[第一部] 〜魂のうた〜響きあう音楽と言葉とアート
パート1 写真スライドショー「Red Water」by 野村恵子
パート2 お話と詩の朗読「どんなものもみな言葉」by 長田弘
パート3 DJライヴ「Song for Tomorrow」by ピーター・バラカン
[第二部] ジョイント・トーク
生き難さを感じる日々に 〜with a little help〜
会場:武蔵野スイングホール(150名)JR中央線武蔵境駅北口から徒歩2分
日時:2010年6月13日(日)13時開場 13時30分開演
会費:2000円(自由席)
お問合せ・お申し込みはこちら
|
Exile On Main Street メインストリートのならず者 |
その他のバージョン
 国内盤
¥2,200 2010年05月19日
国内盤
¥2,200 2010年05月19日
 国内盤
¥2,800
国内盤
¥2,800限定盤 SHM-CD (紙ジャケ) 2010年06月30日

-
Peter Barakan (ピーター バラカン)
1951年ロンドン生まれ。ロンドン大学日本語学科を卒業後、1974年に音楽出版社の著作権業務に就くため来日。
現在フリーのブロードキャスターとして活動、「Barakan Morning」(インターFM)、「ウィークエンド・サンシャイン」(NHK-FM)、「CBS60ミニッツ」(CS ニュースバード)、「ビギン・ジャパノロジー」(NHK BS1)、「バラカン・ビート」(OTONaMazuインターネットラジオ)などを担当。
著書に『200CD ブラック・ミュージック』(学研)、『わが青春のサウンドトラック』(ミュージック・マガジン)、『猿はマンキ、お金はマニ』(NHK出版)、『魂(ソウル)のゆくえ』(アルテスパブリッシング)、『ロックの英詞を読む』(集英社インターナショナル)、『ぼくが愛するロック名盤240』(講談社+α文庫)などがある。
インタビュー中に登場する主要人物について |
 |
Andy Johns (アンディ・ジョンズ) ロンドンのオリンピック・スタジオを拠点に仕事をしていたイギリスの名エンジニア/プロデューサー、グリン・ジョンズを兄に持つアンディ・ジョンズ。60年代末から70年代初頭にかけては兄の関わる作品で共同エンジニアを務め、レッド・ツェッペリン、ブラインド・フェイスのアルバムに携わり、また、70年代初期のフリーの作品をプロデュースしていることでも知られている。ストーンズ作品では、『Sticky Fingers』から『It's Only Rock'n'Roll』までの4作品でエンジニアを務め、70年代黄金期のストーンズ・サウンドの確立に貢献している。70年代末にアメリカに移り、テレヴィジョン、ジョニ・ミッチェル、ロン・ウッドの作品に参加。80年代以降はヴァン・ヘイレンなどハード・ロックの名プロデューサーとして名を馳せている。 |
 | Billy Preston (ビリー・プレストン) カリフォルニアの出身と思われがちだが、実は生まれ故郷はテキサス州ヒューストン。10歳の頃から教会でゴスペルのオルガン奏者としてキャリアをスタートさせ、16歳の頃にはすでにリトル・リチャード、レイ・チャールズ、サム・クック、キング・カーティスといった大スターのバック・バンドの一員として活躍。ゴスペルを下地にした泥くさいサザンソウル・スピリッツ溢れる楽曲においてこそ真価が発揮されるビリーの黒くアーシーなタッチ。ビートルズの「ゲット・バック・セッション」に参加し、「Get Back」、「Let It Be」、「Something」でエレクトリック・ピアノを弾いたことを機に、ロック界隈でもその名が広く知られていくようになる。アップル・レコード移籍第1弾のソロ・アルバム『That's the Way God Planned It』には、プロデューサーを務めたジョージ・ハリスンをはじめ、キース・リチャーズ、エリック・クラプトンらも参加している。70年代に入り米南部指向を強めたストーンズのアルバムには、『Sticky Fingers』以降『Black And Blue』までの期間レコーディングに参加。1973年のストーンズのツアーには前座+サポート・メンバーとして、1975年〜76年のツアーではサポート・メンバーとして参加し、主役をバックに自身の曲「Nothing From Nothing」、「That's Life」を堂々披露している。 |
 |
Bobby Keys (ボビー・キーズ) 60年代末、レオン・ラセルを中心とする米南部スワンプ・ロック・サークルで活動していたボビー・キーズは、ジミー・ミラーを介してストーンズと出会うことになる、テキサス出身のサックス奏者。10代でバディ・ホリーのバック・バンドでの演奏を経験し、その後も様々なバンドでの演奏を経たのちにレオンの紹介でディレイニー&ボニーのツアー・バンドに参加。この大編成バンドには、エリック・クラプトンやデイヴ・メイソンらも参加していたということもあり、彼らからストーンズ作品参加へのアドバイスなどもされていたのだろう。『Let It Bleed』所収の「Live With Me」を皮切りに、『Sticky Fingers』の「Brown Sugar」など数々のストーンズ楽曲でブルース・フィーリング溢れるサックス・ソロを披露し、1970年以降はツアーのレギュラー・メンバーに着任(1975〜78年はゲスト扱い)している。ボビーに「キースのような人間に一生で5人会えればラッキーだよな」と言わしめたそのキースとは同じ生年月日(1943年12月18日)ということもあり、ソロやニュー・バーバリアンズなどストーンズ以外の活動でも度々共演しながら、現在もソウルメイトのような理想的な信頼関係を保ち続けている。 |
 |
Dr. John (ドクター・ジョン) おなじみニューオリンズ・スワンプの生き字引、Dr. ジョンことマック・レベナック。ニューオリンズ・ミュージックとスワンプ・ロックの素晴らしい交叉盤『Gumbo』をすぐ近くのサウンド・シティ・スタジオでレコーディングしていた時期でもあり、そちらのレコーディング・メンバーであったタミ・リン、シャーリー・グッドマンを引き連れ、ハリウッド・スタジオでの「Let It Loose」のコーラス録音に参加したというのがおおよその経緯。また、1970年に録音されたDr. ジョンのアルバム『The Sun、Moon & Herbs』には、ミック・ジャガーが6曲もバック・コーラスで参加しており、そのお礼に、といったところも多分に含んでいるのだろう。 |
 |
Gram Parsons (グラム・パーソンズ) インターナショナル・サブマリン・バンド、バーズ(『ロデオの恋人』時代)、フライング・ブリートー・ブラザーズを渡り歩き、カントリー、またはカントリー・ロックを追求し続けた男、グラム・パーソンズ。『Let It Bleed』の制作にとりかかった頃から、キースとグラムとの親交は始まったと言われている。「Love In Vain」、「Country Honk」、「Wild Horses」、「Dead Flowers」、また、キースとグラムが南カリフォルニアの公園にUFOを見に行った時にアイデアが浮かんだとも言われている「Moonlight Mile」など、グラムがストーンズ・サウンドに与えた影響というものは計り知れない。もちろん『Exile On Main Street』のレコーディングにおいても、仏ネルコート、最終ミックスが行われたLAハリウッド・スタジオにグラムは訪れていて、「Sweet Virginia」、「Torn & Frayed」といった楽曲でその親睦がのぞかれる。グラムは、1973年、2枚目のソロ・アルバム『Grievous Angel』を完成させた直後にアルコールとドラッグの過剰摂取により26歳という若さでこの世を去ったが、その後もストーンズは、「Far Away Eyes」、「Indian Girl」、「The Worst」、「Sweethearts Together」といった曲にカントリー・フレイヴァを吹き込むことによって、その友情を永遠のものとしている。 |
 |
Glyn Johns (グリン・ジョンズ) 上掲アンディ・ジョンズの実兄でもあるエンジニア/プロデューサー、グリン・ジョンズは、ザ・フー、フェイセズ、ハンブル・パイなどの所謂ブリティッシュ・ロックの名盤と呼ばれる作品を数多く手掛けていた名伯楽。ストーンズとは彼らのデビュー以前から交流があったそうだが、60年代後半(『Their Satanic Majesties Request』以降)から70年代初頭にかけてのストーンズのスタジオ・レコーディングのサウンド面において全面的なイニシアチヴをとっていた。ディレイニー&ボニー、レオン・ラセル、ジェシ・デイヴィス、リタ・クーリッジ、イーグルズ、ジョー・コッカーといったLA〜イギリス・スワンプの主流アーティストたちがこぞって惚れ込んだグリン特有の洗練されていないむきだしのサウンド・プロダクションは、当時ルーツ指向にあったストーンズにとってもベストのものであった。 |
 |
Ian Stewart (イアン・スチュワート) ”第6のストーンズ”の大本命というよりは、結成時からの正式メンバーとして活動していたものの当時のプロデューサー、アンドリュー・ルーグ・オールダムによる「やぼったいルックスがバンドに相応しくない」という理由だけでメンバーを外されたというイアン・スチュワート。その後もストーンズのローディーを任される一方で、セッション・ピアニストとしても活動し、スタジオ、ライヴを含むDECCA初期・中期ストーンズのピアノ・サウンドを一手に引き受けた。また、レッド・ツェッペリン「Rock And Roll」、「Boogie With Stu」などでの名演も語り草となっており、「ブルーズやブギウギ・ピアノを弾かせたらスチュの右に出る者はいない」とはニキ・ホプキンズの弁。60年代末以降様々な音楽スタイルを取り入れたストーンズには、そのニキやビリー・プレストン、イアン・マクレガンらが主にサポート・ピアニストとして同行していたが、ストーンズがいつでもブルース(=原点)に立ち返れるのは、やはりスチュの存在があったからと言われている。『Dirty Work』を最後の仕事に、85年心臓麻痺でこの世を去った。 |
 |
Jimmy Miller (ジミー・ミラー) 1968年、春の訪れとともに「ブルース」、「米国南部」というルーツ・ミュージックへの指針をしっかりと捉えたストーンズは、アイランド・レコーズ創設者クリス・ブラックウェルの肝煎りとしてスペンサー・デイヴィス・グループやトラフィックなどを手掛け注目を集めていた新進気鋭のジミー・ミラーをプロデューサーに抜擢。ちょうどその頃完成したばかりだったトラフィックの2ndアルバム『Traffic』のサウンドをミックがいたく気に入ってスカウトしたそう。ブルースを機軸とした手堅くアーシーなサウンド作りの中にも実験的な試みを次々と取り入れた『Beggars Banquet』でそれは吉と出て、以降『Goat's Head Soup』までにおいてジミー・ミラーはストーンズから全幅の信頼を得て、揺るぎない黄金期のサウンドを作り上げている。 |
 |
Jim Price (ジム・プライス) ボビー・キーズと同じくLAスワンプ・サークル諸作品やビートルズ作品などに参加していたテキサス出身のセッション系トランペット奏者ジム・プライス。ボビ・キーズの紹介によりストーンズ作品へ参加となったその初登場曲は、『Sticky Fingers』所収となる「Bitch」で1970年のオリンピック・スタジオにて。Stax系ジャンプ・ナンバーをストーンズ流に昇華したこの曲では、ジムとボビーによるパンチの効いたホーン・セクションが明らかにドライヴ感を与えている。この後1973年のウインター・ツアーまでバンドに同行し、70年代ストーンズの黄金期を支えた。 |
 |
Leon Russell (レオン・ラセル) グリン・ジョンズの紹介でストーンズと出会うこととなるレオン・ラセルは、まずは『Let It Bleed』の「Live With Me」にピアノで参加し持ち前のLA流スワンプ・サウンドの一片を名刺代わりに差し出す。しかし、レオンのストーンズへの最大の貢献は、その広い人脈を生かし米南部のミュージシャンズ・サークルを彼らストーンズと共有したという点にある。自身のシェルター・ピープル、ディレイニー&ボニー&フレンズ、ジョー・コッカーのマッド・ドッグス&イングリッシュメンといった共同体が誇る腕利きの人海を、当時南部ルーツ・サウンドに飢えていたストーンズの助力のために惜しげもなく送り込み、ブルース、ソウル、カントリー、ゴスペルの持つ泥くさく豊かなニュアンスを分かち合ったその功績は称えられてしかるべき。また、1969年初のソロ・アルバム『Leon Russell』の録音には、ビル・ワイマン、チャーリー・ワッツが参加している。 |
 |
Nicky Hopkins (ニキ・ホプキンズ) ジャック・ニッチェ、イアン・スチュワートに次いで登場し、”第6のストーンズ”となるレギュラー・ピアニストの座を1967年『Between The Button』録音時に射止めたニキ・ホプキンズは、『Tattoo You』までの間実に70曲以上の楽曲に参加。現在に至るまでの歴代全サポート・メンバーの中でも群を抜いて高い人気を誇っている。『Exile On Main Street』においても感性豊かなピアノ・ワークは冴えわたり、「Loving Cup」の流麗なタッチから「Turd On The Run」や「Rip This Joint」でのワイルドに転がるブギまで緩急自在。パーマネントな鍵盤奏者を置かないバンドにとって各時期の”6番目のストーンズ”というのは、まさにバンドが目指す方向性を左右する重要な存在であるということは疑いもないだろう。とりわけ、『Thier Satanic Majesties Request』から『It's Only Rock'n'Roll』まで、さらには1971〜73年絶頂期(&乱痴気)と評されるライヴを一任されていた。彼なくしては、ホンモノのストーンズ・サウンドを語ることはできない。ちなみに、1969年『Let It Bleed』録音時のアウトテイク・ジャム『Jamming With Edward』(CD廃盤)は、ニキにライ・クーダー、そして、キース抜きのストーンズがスタジオ・セッションした時の記録で、72年に正式リリースされている。 |
 |
Robert Frank (ロバート・フランク) 大方のロック・ファンにとっては『Exile On Main Street』のジャケット・アートワーク、そして、ドキュメンタリー・フィルム『Cocksucker Blues』という、ストーンズ史上屈指のいかがわしい芸術性を匂い立たせる2大プロダクツを手掛けた人物としてよく知られるロバート・フランク。1924年、スイスのチューリッヒで生まれ育ったフランクは、47年に移民としてニューヨークに出てきた後、50年代半ばには全米を放浪しながら、実にフィルム767本を使用しながら市民の現実の生活を写真に収め続けた。撮影イメージ約27、000点、ワークプリント約1000枚の中から83作品が写真集にまとめられ、58年5月に「Les Americains(アメリカ人)」として刊行されている。アレン・ギンズバーグやジャック・ケルアックといったビート詩人らと共鳴し合うことで「視覚的詩人」とも呼ばれていたフランク。「Les Americains(アメリカ人)」にも掲載されていた写真をコラージュしたアートワークは、ストーンズの楽曲イメージを肥大化させる一種の魔法や麻薬めいたパワーに満ちている気がしてならない。 |
 |
Ry Cooder (ライ・クーダー) 『Exile On Main Street』の録音に直接関わってはいないが、『Let It Bleed』以降のストーンズ、特にキースのギター・プレイに与えた影響を考えるとこのライ・クーダーを外すわけにはいかない。ジャック・ニッチェがオリンピック・スタジオに連れてきた当時まだ無名に等しいギタリストであったライは、表向きは「Love in Vain」にマンドリンでクレジットされるだけにとどまったが、「Honky Tonk Women」の有名なオープンGフレーズの発案者、ひいてはキースにオープンGチューニングのスタイルを取り入れさせることになった家元であると古くから言われている。そのあたりの真意を明かす手がかりとしては、この時のセッションを収録し公式音源化した『Jamming With Edward』(CD廃盤)が最も有効だろう。キース抜きによるストーンズとのジャム・セッションにも関わらず、フレーズ、リフのカッティングの端々にキースのそれとの類似性が聴いてとれ、まるでストーンズ本隊によるセッションと何ら遜色がない。さらに、唯一この時期に至るまでのストーンズらしくない点として、ライの米南部色豊かなサウンド・デザインが挙げられる、とまでくれば、後の『Sticky Fingers』(ライは「Sister Morphine」の再録に参加)、『Exile On Main Street』でキースがひたむきに追い求めるようになる米南部サウンドの旨味、その最も身近で良質なお手本がライのギター・プレイだったのかもしれないと言えるはずだ。 |