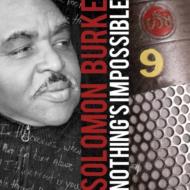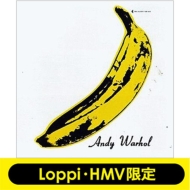Sunday, May 9th 2010

�@���[�����O�E�X�g�[���Y�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�f���b�N�X�E�G�f�B�V�����̔������L�O���Ă�����AHMV�X�y�V�����E�C���^�r���[���B�肵���u���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁA�������́A���[�����O�E�X�g�[���Y���͂Ă��Ȃ����[�ׁv�B
�@��2��ڂ̃Q�X�g�́A�e���r�A���W�I���͂��߂Ƃ���l�X�ȃ��f�B�A��ʂ��āA��������Ǝ��̉��y�Љ��W�J����Ă���u���[�h�L���X�^�[���s�[�^�[�E�o���J������B2009�N9���́u�r�[�g���Y�E���}�X�^�[�Ք������v�ɑ����܂��Ă̂��o��ł��B
�@1962�N�A�r�[�g���Y�̃Z���Z�[�V���i���ȃf�r���[��̊��������Ƃɂ��{�i�I�ɉ��y�̐��E�ɊJ��B�w������ɂ͂��łɁA�u���[�Y�A���Y���E�A���h�E�u���[�Y�A�j���[�I�[�����Y�Ƃ������A�����J�̃��[�c�E�~���[�W�b�N�ɖ������Ă����Ƃ����o���J������ɁA���́w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�͂ǂ̂悤�ɋ����Ă����̂ł��傤���H 60�N�㖖����70�N�㏉���̃C�M���X�̎Љ�w�i�Ȃǂ������Ȃ���A�����̃��[�����O�E�X�g�[���Y�A����ɂ̓o���J�������g�ƁA���f�̃A�����J���E���[�c�E�~���[�W�b�N�Ƃ́h�����h�����b���������܂����B
�C���^�r���[�^�\���F ���l����
�@
- ---�@�s�[�^�[�E�o���J������́A��N���u�r�[�g���Y�E���}�X�^�[�Ք������v�Ɉ��������܂��Ă̂��o��ƂȂ�܂��B�܂��́A�S11�Ȃ̖����\�T�C�h�iDisc-2�j���������ɂȂ��������z���炨�f���������̂ł����A�����ɂ������ł������H
�@����A�����������ł��ˁB���S�ȏ��o��ƌ�����悤�Ȃ��̂�5�A6�Ȃ��炢�ɂȂ�̂��ȁH �c��͂��łɖ{�҂ɂ���Ȃ̕ʃe�C�N��������A�uTumbling Dice�v�Ɋւ��ẮA�܂�����ߒ��̒i�K�� �g�A�[���[�E���@�[�W�����h ��������ƁB����͂قƂ�ǕʋȂ݂����Ȋ����ł����B�V���O���ɂȂ��Ă���uPlundered My Soul�v��uPass The Wine�v�������B���̕ӂ�́A���X�̃A���o���ɓ����Ă��Ă����������Ȃ����炢�����x�̍����Ȃ��Ǝv���܂��B�u�^�C�g�� 5�v�Ƃ����C���X�g�ȂȂɂ��Ă��A����܂ł̃X�g�[���Y�ɂȂ��^�C�v�̋Ȃ�����A�ƂĂ������[���ł��ˁB
- ---�@�����_�ŏڍׂȃN���W�b�g�Ȃǂ͔���Ȃ��̂ł����A�u�^�C�g�� 5�v�Ɋւ��ẮA�u���[�X�E�u���C�J�[�Y���ۂ���������������̂ŁA�Ђ���Ƃ�����~�b�N�E�e�C���[���傫���ւ���Ă���̂��ȂƁB
�@�~�b�N�E�e�C���[�F�������o�Ă��銴���͂��邩������܂���ˁB���̎����̃X�g�[���Y�̃����o�[�Ƀ~�b�N�E�e�C���[���������Ă��Ƃ́A���܂�d�v������Ă��Ȃ��C�������ł����E�E�E�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�ł́A���Ȃ肢�����킢���o���Ă��܂���ˁB ���ǂ́A�wLet It Bleed�x����wIt's Only Rock n' Roll�x�܂ł�5�N���炢�̊��Ԃ����ݐЂ��Ă��Ȃ������킯�����ǁB
- ---�@�~�b�N�E�e�C���[�͍�N�����������s���Ă��܂�����ˁB
�@���͓�Ă�������c�A�[�ʼn���Ă���݂����ł����ǂˁB
- ---�@���āA���̃~�b�N�E�e�C���[�͖{�҂́uVentilator Blues�v�ŁA�X�g�[���Y�ݐЎ��B��ƂȂ�g��ȃN���W�b�g�h����������Ă����܂��B�ł����A���̎����̃X�g�[���Y�̃��R�[�f�B���O��c�A�[�̃X�P�W���[���͑����Ƀ^�C�g�Ńn�[�h�������炵���A�o���h�ɂ̂߂荞��ł����㏞�Ƃ��ă~�b�N�E�e�C���[�̉ƒ�͕��O�������Ƃ����L�q�^�������ł���ˁE�E�E
�@�܂��A���̃A���o���Ɍ����ẮA�^���̂������ɂ߂ĈٗႾ�����Ƃ������Ƃ�����܂�����ˁB
�@�܂��w�i�Ƃ��ẮA�����̃C�M���X���J���}�����ŁA�����ł����̂������オ���Ă������ゾ������ł���B�X�g�[���Y�̂悤�ȉ҂������Ă���ƁA������������90%�ȏ��ŋ��Ŏ����Ă�����Ă��܂��B�X�g�[���Y�͎��������̊m��\��������ł���Ă���킯���Ȃ�����B�}�l�W�����g�E�T�C�h�ɂ������������Ƃ�S�ĔC���Ă������ǁA���鎞�C���t�����炫����Ɛŋ��̏���������Ă��Ȃ��āA����Ȃ�������Ȃ��ŋ����u�����Ȃ��v�Ɓi�j�B����ŁA�C�M���X�����ɂ͂���ꂸ�A���̃A���o���̃^�C�g���ɂ��Ȃ��Ă���Ƃ���A�uExile�v�A�܂�h�S���h���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ɂȂ��āA�d���Ȃ��t�����X�ɓn������ł��B
�@�t�����X�ɈڏZ���邱�Ƃɑ��ẮA�~�b�N��L�[�X�͂܂����ƐϋɓI�������炵����ł����A�`���[���[�E���b�c�Ȃ͍�������̃����h�����q�����t�����X����S���ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ������āA���Ȃ�a�X�������Ƃ���������������Ȃ�ł��B�ł��܂��A���ǂ̓����o�[�݂�Ȃœ�t�����X�ɍs���āA�i���j�l���R�b�g�Ƃ����L�[�X�̂ł����Ƃ����R�[�f�B���O��X�^�W�I�Ɏg���킯�Ȃ�ł���ˁB

�i���j���B���t�����V�����V���������[���̃��B�b���E�l���R�b�g�E�E�E��������N���[�W���O�Ȃǂł��L���ł������A��t�����X�̊C�ݒn��R�[�g�E�_�W���[���ɂ��鏬���ȍ`�����B���t�����V�����V���������[���B�j�[�X�A���i�R�A�J���k�Ƃ�������v�s�s�ɗאڂ���A������h�Z���u�w�h�Ɉ����ꑱ���Ă��鍂�����]�[�g�n�i�ۗ{�n�j�ł�����A��Ƃ̃W�����E�R�N�g�[�A�L���T�����E�}���X�t�B�[���h�AR��B�̎�̃e�B�i�E�^�[�i�[�炪���@���\���Ă����B�L�[�X��Ƃ̏Z�ރ��B�b���E�l���R�b�g�@����Ɉ��ʑ卋�@�ŁA�s�[�^�[�E�o���J������H�����X�̓C�M���X�C�R�̒�����L���Ă������̂��Ƃ����B�܂��A�h�L�������^���[�f��wStones In Exile�x�ł́A�~�b�N�ƃ`���[���[�������̂��Ƃ���z���邽�߂Ɍ��݂̃l���R�b�g��K��Ă���V�[��������̂ŁA�h�ڂ����n�����̊Ԏ��h�Ȃǂ͂�����ł��m�F���Ă���������Ǝv���B���Ȃ݂Ƀ~�b�N�́A��Ƃ̃p�u���E�s�J�\���ӔN���߂��������Ƃł��m���铯�����R�[�g�E�_�W���[���̃��[�W���A�r���E���C�}���́A���E�p�X�e�B�f�E�T���E�A���g���[�k�A�`���[���E���b�c�͌I�̓��Y�n�Ƃ��Ă��L���Ȓ������Z���F���k�̔_��A�~�b�N�E�e�C���[�͓쓌���̓s�s�O���[�X�ɂ��ꂼ��Z�����\���Ă����B - ---�@�L�[�X�̃l���R�b�g�@���������n��Ƃ����̂́A������x�T�w�̔����n�݂����ȂƂ��낾�����̂ł��傤���H
�@��t�����X�̂��̊C�ݎ��ӂɂ͑�@������ς������āA�̂���C�M���X�l���D��ŕʑ����\���Ă����肵�Ă���ł��B�L�[�X�̎肽�Ƃ́A���X�C�R�̒���Ȃ������Ă����Ƃ炵���ł����B����ŁA���̃����o�[���e�X�ɉƂ��肽����ǁA�������ăL�[�X�̉Ƃ���Ԃ�4�A5���Ԃ�����Ƃ���ɉƂ��肽�l����������A�����������܂������ԂɃ��R�[�f�B���O���Ă����킯����Ȃ��B�{���͂����Ƃ������R�[�f�B���O�E�X�^�W�I�ł�낤�Ƃ��Ă����炵����ł����A������t�����X�ɂ���Ƃ������X�^�W�I���Ȃ���������B�ł��A���傤�ǃX�g�[���Y���i���j���[�o�C���E���R�[�f�B���O����j�b�g�����L���Ă����̂ŁA���Ⴀ������L�[�X�̉ƂɎ�������Ń��R�[�f�B���O���悤�ƁB

�i���j���[�o�C���E���R�[�f�B���O����j�b�g�E�E�E�����o�[�������^���ꏊ�����R�ɑI�אV�N�ȋC�����Ń��R�[�f�B���O�ł���悤�ɁA��^�g���[���[�ɘ^���@�ނ������������ړ����̘^���X�^�W�I�B�X�^�W�I�����ɂ́A16�`�����l���E�}���`�g���b�N�E���R�[�_�[�A�^������̗l�q���f���r�f�I�E���j�^�[�Ȃǂ���������Ă���B�X�g�[���Y�́wSticky Fingers�x�A�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̐��쎞�ɂ��̃��j�b�g���g�p���Ă���B�܂��A���b�h�E�c�F�b�y�����w�V�x�A�w�W�x�A�f�B�[�v�E�p�[�v���wMachine Head�x�A�w���̏ё��x�A�wBurn�x�Ȃǂ̘^���ɂ��݂��o����g�p����Ă���B
�@�L�[�X�̉Ƃ̒n���͂������L��������ł����A�K�������^���ɓK���Ă����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���������镔�����A�~�b�N�̘^���u�[�X�A�L�[�X�̃u�[�X�A�{�r�[�ƃW���̃z�[�����̃u�[�X���Ƃ��ɐU�蕪���Ę^�����Ă����炵����ł��B�r���E���C�}�����x�[�X�����ۂɒe���Ă��镔���ƃx�[�X�E�A���v���u���Ă��镔�����ʂ�������Ƃ��i�j�A�G���W�j�A�̃A���f�B�E�W�����Y�̊炪�����Ȃ��Ƃ��A�������������̒��Ř^�����Ă����悤�Ȃ�ł����ǂˁi�j�B
�@�܂��L�[�X���g���Z��ł���Ƃł����邩��A�L�[�X���ϋl�܂�����C�������Ȃ������肵����A�����̃x�b�h����[������o�Ă��Ȃ����Ƃ����܂ɂ����āB���̃����o�[�������Ԃ����ăL�[�X�̉ƂɏW�܂��Ă���̂ɁA�L�[�X�{�l�̎p�͂Ȃ��Ƃ����i�j�B�@- ---�@�i�j�B�L�[�X�͑��q�̃}�[��������̎q��Ȃǂ������āA���R�[�f�B���O�̐Ȃ��O�����Ƃ����������������ł��ˁB���̊ԑ��̃����o�[�͖�̃j�[�X�̊X�ɌJ��o������Ƃ��A�����ԉH��L���Ă����炵���ł����ǁB
�@���������B������d���ɂȂ�Ȃ����Ƃ����Ȃ肠�����炵������A���ǔ��N���炢�l���R�b�g�� �h�������h �h���Ȃ�������h���J��Ԃ��Ă����炵����ł��ˁB
- ---�@�n�����́A�N�[���[���Ȃ������������������Ƃ����E�E�E
�@�����Ȃ����ˁB�^�����Ă���Ƃǂ�ǂ����㏸���āA���I���ǂ𗬂�邱�Ƃ������āi�j�A���Ȃ�L�c�������炵���ł��B
- ---�@���̏����������āA���̃A���o���ł̓M�^�[�̃`���[�j���O���Â��Ƃ������������̂ł����B
�@�ł��A�ނ�ɂƂ��Ă͂���Ȃɂ߂��炵�����Ƃ���Ȃ��ł���i�j�B�l�����w���̂Ƃ��ɏ��߂ăX�g�[���Y�̃��C�����ςĎv�����̂��A�u�M�^�[�̃`���[�j���O���Ȃ��ĂȂ��v���Ă��Ƃ���������i�j�B64�A5�N�̘b�ł��ˁB
- ---�@�������o���J������́A69�N���i���j�n�C�h�p�[�N�E�t���[�R���T�[�g�������ɂȂ��Ă����ł���ˁH
�@�����B�~�b�N�E�e�C���[�̏��o��B�z���g�ɓ������炢�̑傫���Łi�j�B����̓R���T�[�g���ς����Ă������́A���Ղ�ɎQ���������Ă��������ł��ˁB

�i���j�n�C�h�p�[�N�E�t���[�R���T�[�g�E�E�E���Ƃ̓u���C�A���E�W���[���Y�E�ތ�̌㊘�Ƃ��ăX�g�[���Y�ɓ������M�^���X�g�A�~�b�N�E�e�C���[�̂���I�ڃR���T�[�g�Ƃ��āA1969�N7��5���Ƀ����h���̃n�C�h�p�[�N�ŗ\�肳��Ă����t���[�R���T�[�g�B�J�Â�2���O�ƂȂ�7��3���Ƀu���C�A��������̃v�[���Ŏ��S���Ă���̂���������A�}篒Ǔ��R���T�[�g�Ƃ�������ł��A25���l�ȏ�̊ϋq���������B�`���A�~�b�N�E�W���K�[�̓C�M���X�̎��l�p�[�V�[�E�r�b�V���E�V�F���[�́uAdonais�v��N�ǁB�܂��A�u���C�A�����D���������Ƃ����W���j�[�E�E�B���^�[�́uI'm Yours And I'm Hers�v�����t���Ĕނ̍��ɕ������B��Ɂw���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�Ɏ��^����邱�ƂƂȂ�uLoving Cup�v�������ŏ���I����Ă���B���Ȃ݂ɑO���̓f�r���[���O�̃L���O�E�N�����]���B - ---�@���߂Ă����ɂȂ����X�g�[���Y�̃��C����64�A5�N�Ƃ���������Ă��܂������A��͂�r�[�g���Y���l �g���F�������h �ɉ��t������������Ă��܂������������̂ł��傤���H
�@�܂��E�E�E�����ł��ˁB�ł��A1�K�̑O�̕��̐ȂŃX�e�[�W���炩�Ȃ�߂������̂ŁA���t���̂͂悭����������ł���B����PA�ݔ��͂Ȃ��ł�����A�������A���v���璮�����邮�炢�̋����ł����ˁB
- ---�@���C���Ɋւ���Ƃ���ł́A��N�����[�X���ꂽ�wGet Yer Ya-Ya�fs Out�x�f���b�N�X��G�f�B�V������DVD�͂������ł������H �uProdigal Son�v�A�uYou Gotta Move�v���~�b�N�ƃL�[�X�ʼn��t����Ƃ������C���f�������^����Ă��܂����B
�@����ς�M�^�[�̃`���[�j���O��������Ƃˁi�j�B�ł��A�wGet Yer Ya-Ya�fs Out�x���̂͑f���炵���A���o�����Ǝv���܂��B69�N�����Ƃ��ẮA�����܂ł̃��C���E�A���o���͂����߂����ɂ͂Ȃ������B�܂����C���E�A���o��������Ȃɍ���Ă��Ȃ���������ł����邩��B�X�g�[���Y�͂����ƑO�ɁwGot Live If You Want It�I�x�Ƃ����A���o�����o���Ă͂��܂����ǁA����͋[�����C���݂����Ȃ��̂ł�����ˁB
- ---�@69�N�ӂ�́A���b�N�E�R���T�[�g�̋K�͎��̂��G���^�[�e�C�������g�Ƃ��Ăǂ�ǂ��剻���Ă����������ł���ˁB
�@�R���T�[�g�̌`�Ԃ����l�ɂȂ������ォ�ȁB�ŏ���2000�l�A3000�l�����e���錀��^�̃R���T�[�g���嗬���������ǁA60�N��̌㔼�����w�̍u���݂����ȂƂ���ŊJ�Â���悤�ɂ��Ȃ�����ł���B�����h�����i���j���E���h�n�E�X�Ȃ��L���B�������Ƃ���ł́A�p�u��2�K�ɂ��邿����Ƃ����z�[���ł������Ƃ��B���Ƃ́A�t�F�X�e�B�o����68�A9�N������n�܂�܂���ˁB�X�g�[���Y�Ō����A�n�C�h�p�[�N�����������A�E�b�h�X�g�b�N��4������ɍs�����I���^�����g�������B���������Ӗ��ł͂��������R�ɂȂ�������ł���ˁB

�i���j�����h���E���E���h�n�E�X�E�E�E���X�͓S���ԗ��̌�����ς���]�ԑ������������Ƃ���1846�N�Ƀ����h���Ɍ��݂���A��2�����O�܂ł͑q�ɂȂǂƂ��Ă��g���Ă������A60�N��ȍ~�A�A�[�g�A���y�A�������͂��߂Ƃ����l�X�ȗp�r�Ŏg���鑽�ړI�z�[���Ƃ��ĉ��z���ꂽ�B���b�N�E�A�[�e�B�X�g�̌����Ƃ��ẮA�Â��̓h�A�[�Y�A�W�~�E�w���h���b�N�X�A���[�����O�E�X�g�[���Y�A�W�F�t�E�x�b�N�A���b�h�E�c�F�b�y�����A�s���N�E�t���C�h�Ȃǂ̃p�t�H�[�}���X���L���B�ŋ߂ł̓{�u�E�f�B�����i2009�N�j�̌������s��ꂽ�B�@
- ---�@�ł́A�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�{�҂�72�N�̔��������ɒ������ŏ��̈�ۂƂ����̂͂������������̂ł��傤���H
�@�l�͍ŏ������D����������ł���B�������u�ԁA�X�g�[���Y�̒��ł�������D���ȃ��R�[�h�ɂȂ�܂����ˁB
�@���̍Ĕ��Ղ�CD�ɕ����āA�h�L�������^���[�f��wStones In Exile�x��DVD�����삳��Ă��܂��āA������ς��Ă�����������ł��B�X�g�[���Y�{�l�����̃C���^�����[�ɉ����āA�W���b�N�E���C�g�i���C�g�E�X�g���C�v�X�j��V�F�����E�N���E�A���ꂩ��ACD�̖����\�T�C�h�̋����v���f���[�T�[�߂��i���j�h���E�E�H�Y�Ƃ������l�����̃C���^�����[�������Ă����ł����A�F��Ȑl�����̏،����Ă�ƁA �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̔��������́A�݂�ȁu����Ȃ��v�Ƃ��u�Â��v�Ƃ��A���y�G���̃��R�[�h�]�����܂�悭�Ȃ������Ƃ��A���������b���ǂ�ǂ�o�Ă��邩��A�l�́u���I�H ���������������H�v���āA������ƕs�v�c�Ȋ�����������ł����E�E�E�Ƃɂ����l�͑�D����������ł���B

�i���j�h���E�E�H�Y�E�E�E�{���h�i���h�E�t�F�C�O�\���B80�N��ɂ́A���Ƃ��̃f���B�b�h�E�E�F�C�X�ƌ��������f�g���C�g�̃t�@���L�[�E�o���h�A�E�H�Y�E�m�b�g�E�E�H�Y�Ŏa�V�ŃJ���t���ȃ_���X�E�T�E���h�ݏo���ꐢ���r�����B���̃J���t���Ԃ�́A�E�F�C���E�N���[�}�[�iMC5�j�A�����E�g�[���A���i�[�h�E�R�[�G���A�~�b�`�E���C�_�[�A�I�W�[�E�I�Y�{�[���A�n�[�r�[�E�n���R�b�N�A�}�[���E�n�K�[�h�A�V�[���EE ��Ƃ̋������ɂ������B�u12�C���`�E���~�b�N�X�v�̐���ɐϋɓI�������_���X�E�p�C�I�j�A�I�ȑ��ʂ̈���ŁA�v���f���[�X��ł́A����̃J���[���d�邩�Ȃ�E�l�C���Ȗ����ɓO����B�{�j�[�E���C�b�g�wNick of Time�x�ɂ���A�{�u�E�f�B�����wUnder The Red Sky�x�ɂ���A�X�g�[���Y�wVoodoo Lounge�x�ɂ���A��������̃R���Z�v�g���\���������Ȃ���V���v���ŗ��ɂ��Ȃ������@�_�ŃT�|�[�g���A�S�̂��I���܂Ƃߏグ�Ă���B
�@�u����Ȃ��v�Ƃ����l�������Ƃ���A�A�����J�̐F��ȃ��[�c�E�~���[�W�b�N�̗v�f�������Ă��邩��Ȃ̂�������Ȃ��B�Ƃ����̂́A�X�g�[���Y�ɂ͌��X�u���[�Y��Y���E�A���h�E�u���[�Y�̗v�f�͂������ǁA���̃A���o���ł͂��ƃo�b�N����H�[�J���̎g�����ȂǂɃS�X�y���F�������o�Ă�����A���Ƃ́uSweet Virginia�v�A�uTorn And Frayed�v�ȂǂŃJ���g���[�̗v�f���܂�ł�����A�����Ă���炪�S���������Ă��銴���ɂȂ��Ă��āA������72�N�Ƃ����̂́A������A�����J�́u���[�c�E�~���[�W�b�N�v�Ƃ����Ăѕ��͂܂��Ȃ��������ゾ��������B�u���b�N�E�~���[�W�b�N���D���Ȑl�̓J���g���[�����܂蒮���Ȃ��A�Ƃ��B���̋t���R��ŁB�ǂ��炩�Ƃ����Ζl���A�u���[�Y��\�E�����D���ł��J���g���[�͂܂����܂�D������Ȃ��������ȁB�ł��A�X�g�[���Y�̂������ƁA�S����R�͂Ȃ��������A�ނ�͂��Ə�������h�J���g���[���ۂ�"�Ȃ����グ�邱�Ƃ�����������B�i���j���C�E�`���[���Y�̃��@�[�W���������~���ɂ��Ă͂�����ǁA�uI'm Moving On�v�Ƃ��ˁB���Ȃ��i���j�n���N�E�X�m�E�̃J���g���[�B
�@���ƁA�i���j�\�������E�o�[�N�̋ȂȂ������Ɏ��グ�Ă����ł����A�\�������E�o�[�N�����������J���g���[�̉e�����Ă���R&B�̎�Ȃ�ł���ˁB�X�g�[���Y�͂����������Ƃ���������ƒ����Ă���킯������A���̃A���o�����o�Ă�����Ȃɂт����肷��Ƃ������Ƃ͖l�̒��ɂ͂Ȃ�������ł���ˁB
�@�f��̒��Ńh���E�E�H�Y�́A���̃A���o���������Ă���h�댯�ȕ��͋C�h������Ă����ł���B�������ɂ��������s���ȋ�C�����X�Ŋ��������ł����E�E�E�����A�wBeggars Banquet�x�A�wLet It Bleed�x�A�wSticky Fingers�x�ƒ����Ă���ƁA�����Ȃ肻�̕ӂƂ͑S���ʂ̐��E�Ƃ������Ƃł͂Ȃ�����B
- ---�@����3���Ɗr�ׂĂ��A�h���E�E�H�Y�������悤�Ɂw���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx����͂ǂ�����Ȃ����肪���������Ă���ƁA�l���l�I�ɂ͊����Ă��܂��B
�@�܂��A���̒��ł��w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx���Ɠ��̕��͋C�������Ă���̂͂������ł��ˁB�^���̎d���ɂ��������W���Ă���ł��傤���A���Ɖ��ƌ����Ă�������т����肵���̂́A�A�[�g���[�N�ł���B
- ---�@�i���j���o�[�g�E�t�����N�ɂ��ʐ^���R���[�W�������W���P�b�g�ł��ˁB
�@�����̓��o�[�g�E�t�����N��m��Ȃ��������ǁA���܂��܋��N�A�wThe Americans�x�Ƃ����ނ̎ʐ^�W���v�X�ɍďo�ł���āA��������Ă����Ƃ��ɁA�Ⴆ�����i���j�W���[�N�{�b�N�X���Ă���l�̎ʐ^�i�C�i�[�X���[���j�Ȃ��ڂ��ĂāA�u�����A���ꂾ�����̂��v���āB���Ƃ́A�����������t���[�N�̎ʐ^����������ł������낢�B�wStones In Exile�x�ł́A���Y�E�t�F�A���u�X�g�[���Y�͎��������̂��Ƃ��t���[�N�Ɗ����Ă�����Ȃ����H�v���Č����Ă܂�����B�ޏ��̐��U�ł��D���ȃ��R�[�h���w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�炵����ł���ˁB

�i���j���o�[�g�E�t�����N�uThe Americans�v�E�E�E����ʐ^�̃��[�c�Ƃ��č����]������Ă��郍�o�[�g�E�t�����N�̎ʐ^�W�B1955�N����1956�N�ɂ����ăO�b�Q���n�C�����c�̏��w���ăA�����J�e�n��30�B�𗷍s�B���̂Ƃ��t�B����767�{���g�p���B�e���ꂽ�s���̌����̐��������^����Ă���B�B�e�C���[�W�͖�27,000�_�A���[�N�v�����g�͖�1000���v�����g����A�t�����N�͂��̕ҏW�A�Z���N�V�����A�z��ɖ�1�N�������A���̒���83��i���܂Ƃ߂��A�uLes Americans�v�Ƃ���1958�N�p���̃f���s���Ђ��犧�s���ꂽ�i�A�����J�͗��N�j�B�X�C�X�E�`���[���b�q����̈ږ��҂̖ڐ��ŁA����̂܂܂̌����̃A�����J���B�e������A�̃C���[�W�́A�u������50�N��v���������Ă����A�����J�l�������ꍑ�̃C���[�W�Ƃ�������Ă���A���\���́g���A�����J�I�h�ƍ��]���ꂽ�B�����t�H�g�E�W���[�i���X�g�I�ʐ^���嗬���������ŁA�l�̎�ϓI�Ȏ��_�ŕ\�������t�����N�̎ʐ^�͉���I�ł�����A���̌㑽���̎ʐ^�Ƃɑ傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ����B98�N�ɏ��߂čďo�ł��ꂽ���̂́A���J����1���Âz�u���ꂽ�ʐ^����80���A�ǎ҂̌������B�e�n�ʼne������Ȃ��悤�ɃL���v�V�����������ɂ܂Ƃ߂��Ă���B�����̓r�[�g�j�N��ƃW���b�N�E�P���A�b�N�ɂ����́B - ---�@���S���班�����ꂽ�Ƃ���ŁA��⎩�}�C���Ɏ����������g�t���[�N�h�Ƃ��ċq�ώ����Ă����������E�E�E
�@�t�ɖl�́A���̃W���P�b�g�̃t���[�N�����ƃ^�C�g���ƂړI�ɂ͌��ѕt���Ă��Ȃ������B�������A�ŋ��������Ȃ��ăt�����X�ɓn��Ƃ������Ƃ́A���y���̃g�b�v�ɍڂ��Ă����̂Œm���Ă��܂������A����ȏ�̂��ƂŃX�g�[���Y�������ǂ������ɒu����Ă����̂��͒m��Ȃ������ł�����B
- ---�@DECCA����A�wBeggars Banquet�x�����肩��A�X�g�[���Y�̓W���P�b�g�̃A�[�g���[�N�ɂ������咣�����ߎn�߂Ă����܂���ˁB
�@�wBeggars Banquet�x�́A�������̃W���P�b�g�Ń����[�X�ł��Ȃ������ł�����ˁB���̎���A�g�C�����ʂ����Ƃ͎Љ�I�Ƀ^�u�[����������B�����i���j�^�����ȃW���P�b�g�ɍ����ւ����āB�wLet It Bleed�x�́A�l�͍������܂�D���ł͂Ȃ���ł����i�j�A���Ȃ�ς�����A�[�g���[�N�ł͂���B�ŁA���̎��́wSticky Fingers�x���i���j�A���f�B�E�E�H�[�z���ł�����ˁB

�i���j�^�����ȃW���P�b�g�E�E�E�����A�wBeggars Banquet�x�̃W���P�b�g�͂��Ȃ��݂́u�g�C���̗������v�̃A�[�g���[�N���̗p�����͂����������ADECCA�ALONDON������1968�N8���̔������O�ɂ�������ہB�o���h�ƃ��R�[�h��ЂƂ̃W���P�b�g�E�A�[�g���[�N���߂���Η��͑������A���ǃo���h���͏��ҏ��^�����V���v���ȃf�U�C���ɂ����̂�12���̃����[�X�����߂��B���F�ʼn����ꂽ�A�C�{���[�E�z���C�g�̃J���o�X�ɁuRolling Stones Begger's Banquet�v�ƁA�������ɁuR.S.V.P.�v�i'Réponse s'il vous plait�����Ԏ��肢�܂��j�ƋL�����ꂽ�����̃f�U�C���́A�s�{�ӂȂ���r�[�g���Y�̃��C�g�E�A���o���Ƃ̍�������]�_�Ƃ����ɂ��ꂽ�B1986�N�̃��}�X�^�[���̍ۂɃI���W�i���E�W���P�b�g�����߂č̗p����邱�ƂƂȂ�A�ȍ~���݂Ɏ���قƂ�ǂ̖{��Ĕ��ՂŁu�g�C���E�W���P�v���̗p����Ă���B
- ---�@�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̃W���P�b�g�E�A�[�g���[�N�̖��͂Ɋւ��Č����A�z���͂��ǂ��܂ł��c��܂���͂������Ă���Ƃ����_�ɂ����Ă��A�h���E�E�H�Y�̊����� �g�댯�ȕ��͋C�h�͓I�Ă���悤�ȋC�����܂��B
�@�h���E�E�H�Y�Ƃ����A������wStones In Exile�x�̒��Ŕނ������\�����̐���o�܂Ƃ��Č���Ă������ƂȂ�ł����A�u���x��Exile On Main St.�����Ĕ�����ۂɁA����1�������\���W�߂�CD�������t���悤�Ǝv���Ă�����ǁA�v���f���[�X�����Ă��炦�Ȃ������H�v���ēˑR�~�b�N����A�������������Ȃ�ł��ˁB�h���E�E�H�Y�̓h�L�h�L���Ȃ���������炵����ł����i�j�A������̂������ʂ̃}�X�^�[��e�[�v���͂��������ł��B
�@�����ɂ͐F��Ȏ����̃}�X�^�[�������āA������Â����̂ŁuHonky Tonk Women�v�B���ꂪ9���炢�̃��@�[�W�������������悤�ŁA�ŏ����̃��@�[�W�����́uCountry Honk�v�B�������炾��ƃe�C�N���d�˂čŏI�I�ɍ����ɏo�Ă�����̂ɂȂ��ł����A�����C���g���ɂ́A�C�A���E�X�`�����[�g�̒e���z���L�[�g���N�E�s�A�m�������Ă��������ł��B�ŁA���̃s�A�m�̃t���[�Y�̍��ԂɃL�[�X���M�^�[�̃t���[�Y�����Ă���ƁB���̃��@�[�W�������������������ǁA�ǂ������łɌ����čŏI�I�ɂ̓s�A�m�𗎂Ƃ����������ł��ˁB
�@������A�uHonky Tonk Women�v�ł̃L�[�X�̂��̃M�^�[�̃C���g�����Ă����̂́A�Ɠ��̊ԂŒe����Ă����ł���ˁB���X�s�A�m�̂����Ԃɓ��ꂽ�t���[�Y������A�s�A�m���Ƃ����������ς�������Y���̃t���[�Y���c���āA��������ۓI�ȃC���g���ɂȂ�Ƃ����B����͏��߂Ēm�������Ƃŋ����܂����B�����������G�s�\�[�h�͂Ȃ��Ȃ��o�Ă��Ȃ����̂ł�����ˁB- ---�@ �������I�Ȃ�قǁA������������ł��ˁB���̃s�A�m����̃e�C�N�������͒����Ă݂����ł��ˁi�j�B
�@���ƁA�h���E�E�H�Y���d��������������ɁA�L�[�X����1����FAX���͂��āA�����ɂ́u���̖����\�f�ނ� �gExile�炵���h �܂Ƃ߂悤�Ƃ��Ȃ��ł���B���łɁgExile�h�ɂȂ��Ă��邩��v���ď����Ă����������ł��B�܂�A�����ɂ܂Ƃ߂悤�Ƃ��Ȃ��Ă��������A�ςɂ����ȁA�Ƃ����Ӗ����Ǝv����ł����A�h���E�E�H�Y�������ǂ�Łu�Ȃ�قǁv�Ǝv������ł����āB
- ---�@���X�̖{�҂��A�ςɂ܂Ƃ߂č�荞�����͂Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�@�S�R�Ȃ��B���́wStones In Exile�x�ŃC���^�����[���Ă����~���[�W�V�������������ʂ��āA�u���R�̂ȃA���o���v�Ɠ����Ă��܂�������ˁB�������݂�ȍD�������āB
�@�l�͊w������ɂ��̃A���o�����Ă��Ƃ��ɂ́A���ʂ������������Ƃ��l�����킯�ł͂Ȃ�����ǁA�����Ă݂�ƁA�u�������Ɏ��R�̂��ȁv���Ďv���B����ƁA�g�������h���Ă����A�g�������h����ǁA���������ȃ������ł͂Ȃ��āA�ƂĂ��������~�̃������B- ---�@�Ȃ̕��т����R���K�R���A����ȏ�Ȃ������Ƃ����܂����E�E�E
�@�ł��A����͋��R�ł͂Ȃ��炵����ł���B���̂��Ƃ��L�[�X������Ă�������ǁA�y�Ȃ����������Ȑ��o���オ���Ă������_�ŁA�܂�2���g�Ŕ������悤�ƌ��߂�B �ŁA�������̃A���o���𑨂����Ȃ������l�����ɂƂ��ẮA�܂����̂��Ƃ����f�������炵����ł��B2���g�ł��������Ƃ��B�i���j�r�[�g���Y�́g���C�g�E�A���o���h�A�i���j�N���[���wWheels Of Fire�x�A�i���j�W�~�E�w���h���b�N�X�wElectric Ladyland�x�A�i���j�{�u�E�f�B�����wBlonde On Blonde�x�A�i���j�O���C�g�t���E�f�b�h�A�i���j�t�����N�E�U�b�p�Ȃ͂��������ǁA�_�u���E�A���o�����Ă����̂́A�����z���g�ɐ����邮�炢�ł�������B�@����ɁA�L�[�X�͋Ȃ̕��ו��ɂ����������Ԃ��������݂����Ȃ�ł���ˁB
�@�^�����I�������Ƃ����̂́A�~�b�N���`���[���[���u�悵�A���������v���āA�ŏI�̃~�b�N�X�Ȃ��قڃv���f���[�T�[�C���ɂ��Ă��܂��ꍇ�������悤�ł��B���R�[�h���o������A�~�b�N�ɂ���`���[���[�ɂ��날�炽�߂Ē����Ԃ����Ă��Ƃ͂Ȃ��炵�����B���łɎ��̂��Ƃɖڂ������Ă���B�ł��L�[�X�́A�^������������̃e�[�v���ƂŌJ��Ԃ������āA�I�[���@�[�_�u��~�b�N�X���ǂ����邩���ꂱ��ƍl����^�C�v�B����ɁA���������A���o�������[���ƒ����Ă�����āB�ȑO���ɂ����b�ł́A�L�[�X�̓X�g�[���Y�̃u�[�g���O�Ŏ����Ă��Ȃ����̂͂Ȃ����炢�A�����̃o���h�̉����W�߂Ē����Ԃ��Ă���炵����ł���B������A���̕ӂ̎p���ɂ��ẮA���̃����o�[�Ƃ͈Ⴄ�݂����Ȃ�ł��ˁB
- ---�@�~�b�N�ƃL�[�X�Ƃł́A���ۂɂ͈�ʓI�ȃp�u���b�N�E�C���[�W�Ƌt�ł���ˁB
�@�L�[�X�͂������������������Ɍ����܂����ǁA���y�Ɋւ��Ă͂�������Ȃ��݂����ˁB
���[�����O�E�X�g�[���Y ���̑��̋L���͂�����
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��1��z ����� �hCHABO�h ��s
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��1��z ����� �hCHABO�h ��s
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��3��z ���c���T �i���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�ҏW���j
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��3��z ���c���T �i���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�ҏW���j
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��4��z �T�G�L����
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��4��z �T�G�L����
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��5��z ����h �i�\�E���E�t�����[�E���j�I���j
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��5��z ����h �i�\�E���E�t�����[�E���j�I���j
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� �ŏI��z �q���ʑΒk�r�z�J���` �~ ��h��
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� �ŏI��z �q���ʑΒk�r�z�J���` �~ ��h��
 �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̐^��
�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̐^��
 HMV�I��������I �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
HMV�I��������I �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
 �y��U�z �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
�y��U�z �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
 SHM-CD�^���W���P�E�{�b�N�X��2�e
SHM-CD�^���W���P�E�{�b�N�X��2�e
 �X�g�[���Y �^�Ẵl�u���[�Y�� 1976
�X�g�[���Y �^�Ẵl�u���[�Y�� 1976
�s�[�^�[�E�o���J�� �C�x���g���g�[�N���C���E�X�P�W���[��
Afro Blue Vol.2��Soul Bar Stone �i�V�h�E��v�ہj�@��DJ �o��
���FSoul Bar Stone�i�V�h�E��v�ہj
�����F2010�N5��22���i�y�j17:00-19:00�i16:30�J��j
�����F2500�~�i1�h�����N�t���j
���⍇���F�E�B���h
�s�[�^�[�E�o���J���~���c�O�~�쑺�b�q �g�[�N�E���C��
[��ꕔ]�@�`���̂����`�����������y�ƌ��t�ƃA�[�g
�@�@�p�[�g1�@�ʐ^�X���C�h�V���[�uRed Water�vby �쑺�b�q
�@�@�p�[�g2�@���b�Ǝ��̘N�ǁu�ǂ�Ȃ��̂��݂Ȍ��t�vby ���c�O
�@�@�p�[�g3�@DJ���C���uSong for Tomorrow�vby �s�[�^�[�E�o���J��
[���]�@�W���C���g�E�g�[�N
�@�@���������������X�� �`with a little help�`
���F������X�C���O�z�[���i150���jJR�������������w�k������k��2��
�����F2010�N6��13���i���j13���J��@13��30���J��
���F2000�~�i���R�ȁj
���⍇���E���\�����݂�������
|
Exile On Main Street ���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�� |
���̑��̃o�[�W����
 ������
��2,200 2010�N05��19��
������
��2,200 2010�N05��19��
 ������
��2,800
������
��2,800����� SHM-CD �i���W���P�j 2010�N06��30��

-
Peter Barakan �i�s�[�^�[ �o���J���j
�@1951�N�����h�����܂�B�����h����w���{��w�Ȃ𑲋ƌ�A1974�N�ɉ��y�o�ŎЂ̒��쌠�Ɩ��ɏA�����ߗ����B
���݃t���[�̃u���[�h�L���X�^�[�Ƃ��Ċ����A�uBarakan Morning�v�i�C���^�[FM�j�A�u�E�B�[�N�G���h�E�T���V���C���v�iNHK-FM�j�A�uCBS60�~�j�b�c�v�iCS �j���[�X�o�[�h�j�A�u�r�M���E�W���p�m���W�[�v�iNHK BS1�j�A�u�o���J���E�r�[�g�v�iOTONaMazu�C���^�[�l�b�g���W�I�j�Ȃǂ�S���B
�����Ɂw200CD�@�u���b�N�E�~���[�W�b�N�x�i�w���j�A�w�킪�t�̃T�E���h�g���b�N�x�i�~���[�W�b�N�E�}�K�W���j�A�w���̓}���L�A�����̓}�j�x�iNHK�o�Łj�A�w���i�\�E���j�̂䂭���x�i�A���e�X�p�u���b�V���O�j�A�w���b�N�̉p����ǂށx�i�W�p�ЃC���^�[�i�V���i���j�A�w�ڂ��������郍�b�N����240�x�i�u�k�Ё{�����Ɂj�Ȃǂ�����B
�C���^�r���[���ɓo�ꂷ���v�l���ɂ��� |
 |
Andy Johns �i�A���f�B�E�W�����Y�j �����h���̃I�����s�b�N�E�X�^�W�I�����_�Ɏd�������Ă����C�M���X�̖��G���W�j�A�^�v���f���[�T�[�A�O�����E�W�����Y���Z�Ɏ��A���f�B�E�W�����Y�B60�N�㖖����70�N�㏉���ɂ����Ă͌Z�̊ւ���i�ŋ����G���W�j�A�߁A���b�h�E�c�F�b�y�����A�u���C���h�E�t�F�C�X�̃A���o���Ɍg���A�܂��A70�N�㏉�����t���[�̍�i���v���f���[�X���Ă��邱�Ƃł��m���Ă���B�X�g�[���Y��i�ł́A�wSticky Fingers�x�����wIt's Only Rock'n'Roll�x�܂ł�4��i�ŃG���W�j�A�߁A70�N�㉩�����̃X�g�[���Y�E�T�E���h�̊m���ɍv�����Ă���B70�N�㖖�ɃA�����J�Ɉڂ�A�e�����B�W�����A�W���j�E�~�b�`�F���A�����E�E�b�h�̍�i�ɎQ���B80�N��ȍ~�����@���E�w�C�����Ȃǃn�[�h�E���b�N�̖��v���f���[�T�[�Ƃ��Ė���y���Ă���B |
 | Billy Preston �i�r���[�E�v���X�g���j �J���t�H���j�A�̏o�g�Ǝv��ꂪ�������A���͐��܂�̋��̓e�L�T�X�B�q���[�X�g���B10�̍����狳��ŃS�X�y���̃I���K���t�҂Ƃ��ăL�����A���X�^�[�g�����A16�̍��ɂ͂��ł����g���E���`���[�h�A���C�E�`���[���Y�A�T���E�N�b�N�A�L���O�E�J�[�e�B�X�Ƃ�������X�^�[�̃o�b�N�E�o���h�̈���Ƃ��Ċ���B�S�X�y�������n�ɂ����D�������T�U���\�E���E�X�s���b�c����y�Ȃɂ����Ă����^�������������r���[�̍����A�[�V�[�ȃ^�b�`�B�r�[�g���Y�́u�Q�b�g�E�o�b�N�E�Z�b�V�����v�ɎQ�����A�uGet Back�v�A�uLet It Be�v�A�uSomething�v�ŃG���N�g���b�N�E�s�A�m��e�������Ƃ��@�ɁA���b�N�E�G�ł����̖����L���m���Ă����悤�ɂȂ�B�A�b�v���E���R�[�h�ڐБ�1�e�̃\���E�A���o���wThat's the Way God Planned It�x�ɂ́A�v���f���[�T�[�߂��W���[�W�E�n���X�����͂��߁A�L�[�X�E���`���[�Y�A�G���b�N�E�N���v�g������Q�����Ă���B70�N��ɓ���ē암�w�������߂��X�g�[���Y�̃A���o���ɂ́A�wSticky Fingers�x�ȍ~�wBlack And Blue�x�܂ł̊��ԃ��R�[�f�B���O�ɎQ���B1973�N�̃X�g�[���Y�̃c�A�[�ɂ͑O���{�T�|�[�g�E�����o�[�Ƃ��āA1975�N�`76�N�̃c�A�[�ł̓T�|�[�g�E�����o�[�Ƃ��ĎQ�����A������o�b�N�Ɏ��g�̋ȁuNothing From Nothing�v�A�uThat's Life�v�X��I���Ă���B�@�@�@ |
 |
Bobby Keys �i�{�r�[�E�L�[�Y�j 60�N�㖖�A���I���E���Z���𒆐S�Ƃ���ē암�X�����v�E���b�N�E�T�[�N���Ŋ������Ă����{�r�[�E�L�[�Y�́A�W�~�[�E�~���[����ăX�g�[���Y�Əo����ƂɂȂ�A�e�L�T�X�o�g�̃T�b�N�X�t�ҁB10����o�f�B�E�z���[�̃o�b�N�E�o���h�ł̉��t���o�����A���̌���l�X�ȃo���h�ł̉��t���o���̂��Ƀ��I���̏Љ���f�B���C�j�[���{�j�[�̃c�A�[�E�o���h�ɎQ���B���̑�Ґ��o���h�ɂ́A�G���b�N�E�N���v�g�����f�C���E���C�\������Q�����Ă����Ƃ������Ƃ�����A�ނ炩��X�g�[���Y��i�Q���ւ̃A�h�o�C�X�Ȃǂ�����Ă����̂��낤�B�wLet It Bleed�x�������uLive With Me�v����ɁA�wSticky Fingers�x���uBrown Sugar�v�Ȃǐ��X�̃X�g�[���Y�y�ȂŃu���[�X�E�t�B�[�����O����T�b�N�X�E�\�����I���A1970�N�ȍ~�̓c�A�[�̃��M�����[�E�����o�[�ɒ��C�i1975�`78�N�̓Q�X�g�����j���Ă���B�{�r�[�Ɂu�L�[�X�̂悤�Ȑl�ԂɈꐶ��5�l�����b�L�[����ȁv�ƌ��킵�߂����̃L�[�X�Ƃ͓������N�����i1943�N12��18���j�Ƃ������Ƃ�����A�\�����j���[�E�o�[�o���A���Y�ȂǃX�g�[���Y�ȊO�̊����ł��x�X�������Ȃ���A���݂��\�E�����C�g�̂悤�ȗ��z�I�ȐM���W��ۂ������Ă���B |
 |
Dr. John �i�h�N�^�[�E�W�����j ���Ȃ��݃j���[�I�����Y�E�X�����v�̐��������ADr. �W�������ƃ}�b�N�E���x�i�b�N�B�j���[�I�����Y�E�~���[�W�b�N�ƃX�����v�E���b�N�̑f���炵���������wGumbo�x�������߂��̃T�E���h�E�V�e�B�E�X�^�W�I�Ń��R�[�f�B���O���Ă��������ł�����A������̃��R�[�f�B���O�E�����o�[�ł������^�~�E�����A�V���[���[�E�O�b�h�}���������A��A�n���E�b�h�E�X�^�W�I�ł��uLet It Loose�v�̃R�[���X�^���ɎQ�������Ƃ����̂������悻�̌o�܁B�܂��A1970�N�ɘ^�����ꂽDr. �W�����̃A���o���wThe Sun�AMoon & Herbs�x�ɂ́A�~�b�N�E�W���K�[��6�Ȃ��o�b�N�E�R�[���X�ŎQ�����Ă���A���̂���ɁA�Ƃ������Ƃ���������Ɋ܂�ł���̂��낤�B |
 |
Gram Parsons �i�O�����E�p�[�\���Y�j �C���^�[�i�V���i���E�T�u�}�����E�o���h�A�o�[�Y�i�w���f�I�̗��l�x����j�A�t���C���O�E�u���[�g�[�E�u���U�[�Y��n������A�J���g���[�A�܂��̓J���g���[�E���b�N��Nj����������j�A�O�����E�p�[�\���Y�B�wLet It Bleed�x�̐���ɂƂ肩������������A�L�[�X�ƃO�����Ƃ̐e���͎n�܂����ƌ����Ă���B�uLove In Vain�v�A�uCountry Honk�v�A�uWild Horses�v�A�uDead Flowers�v�A�܂��A�L�[�X�ƃO��������J���t�H���j�A�̌�����UFO�����ɍs�������ɃA�C�f�A�������Ƃ������Ă����uMoonlight Mile�v�ȂǁA�O�������X�g�[���Y�E�T�E���h�ɗ^�����e���Ƃ������̂͌v��m��Ȃ��B��������wExile On Main Street�x�̃��R�[�f�B���O�ɂ����Ă��A���l���R�[�g�A�ŏI�~�b�N�X���s��ꂽLA�n���E�b�h�E�X�^�W�I�ɃO�����͖K��Ă��āA�uSweet Virginia�v�A�uTorn & Frayed�v�Ƃ������y�Ȃł��̐e�r���̂������B�O�����́A1973�N�A2���ڂ̃\���E�A���o���wGrievous Angel�x����������������ɃA���R�[���ƃh���b�O�̉ߏ�ێ�ɂ��26�Ƃ����Ⴓ�ł��̐������������A���̌���X�g�[���Y�́A�uFar Away Eyes�v�A�uIndian Girl�v�A�uThe Worst�v�A�uSweethearts Together�v�Ƃ������ȂɃJ���g���[�E�t���C���@�𐁂����ނ��Ƃɂ���āA���̗F����i���̂��̂Ƃ��Ă���B |
 |
Glyn Johns �i�O�����E�W�����Y�j ��f�A���f�B�E�W�����Y�̎��Z�ł�����G���W�j�A�^�v���f���[�T�[�A�O�����E�W�����Y�́A�U�E�t�[�A�t�F�C�Z�Y�A�n���u���E�p�C�Ȃǂ̏����u���e�B�b�V���E���b�N�̖��ՂƌĂ���i�𐔑�����|���Ă��������y�B�X�g�[���Y�Ƃ͔ނ�̃f�r���[�ȑO����𗬂����������������A60�N��㔼�i�wTheir Satanic Majesties Request�x�ȍ~�j����70�N�㏉���ɂ����ẴX�g�[���Y�̃X�^�W�I�E���R�[�f�B���O�̃T�E���h�ʂɂ����đS�ʓI�ȃC�j�V�A�`�����Ƃ��Ă����B�f�B���C�j�[���{�j�[�A���I���E���Z���A�W�F�V�E�f�C���B�X�A���^�E�N�[���b�W�A�C�[�O���Y�A�W���[�E�R�b�J�[�Ƃ�����LA�`�C�M���X�E�X�����v�̎嗬�A�[�e�B�X�g�������������č��ꍞ�O�������L�̐�������Ă��Ȃ��ނ������̃T�E���h�E�v���_�N�V�����́A�������[�c�w���ɂ������X�g�[���Y�ɂƂ��Ă��x�X�g�̂��̂ł������B |
 |
Ian Stewart �i�C�A���E�X�`�����[�g�j �h��6�̃X�g�[���Y�h�̑�{���Ƃ������́A����������̐��������o�[�Ƃ��Ċ������Ă������̂̓����̃v���f���[�T�[�A�A���h�����[�E���[�O�E�I�[���_���ɂ��u��ڂ��������b�N�X���o���h�ɑ��������Ȃ��v�Ƃ������R�����Ń����o�[���O���ꂽ�Ƃ����C�A���E�X�`�����[�g�B���̌���X�g�[���Y�̃��[�f�B�[��C��������ŁA�Z�b�V�����E�s�A�j�X�g�Ƃ��Ă��������A�X�^�W�I�A���C�����܂�DECCA�����E�����X�g�[���Y�̃s�A�m�E�T�E���h�����Ɉ������B�܂��A���b�h�E�c�F�b�y�����uRock And Roll�v�A�uBoogie With Stu�v�Ȃǂł̖�������葐�ƂȂ��Ă���A�u�u���[�Y��u�M�E�M�E�s�A�m��e��������X�`���̉E�ɏo��҂͂��Ȃ��v�Ƃ̓j�L�E�z�v�L���Y�̕فB60�N�㖖�ȍ~�l�X�ȉ��y�X�^�C���������ꂽ�X�g�[���Y�ɂ́A���̃j�L��r���[�E�v���X�g���A�C�A���E�}�N���K���炪��ɃT�|�[�g�E�s�A�j�X�g�Ƃ��ē��s���Ă������A�X�g�[���Y�����ł��u���[�X�i�����_�j�ɗ����Ԃ��̂́A��͂�X�`���̑��݂�����������ƌ����Ă���B�wDirty Work�x���Ō�̎d���ɁA85�N�S����Ⴢł��̐����������B |
 |
Jimmy Miller �i�W�~�[�E�~���[�j 1968�N�A�t�̖K��ƂƂ��Ɂu�u���[�X�v�A�u�č��암�v�Ƃ������[�c�E�~���[�W�b�N�ւ̎w�j����������Ƒ������X�g�[���Y�́A�A�C�����h�E���R�[�Y�n�ݎ҃N���X�E�u���b�N�E�F���̊̐���Ƃ����X�y���T�[�E�f�C���B�X�E�O���[�v���g���t�B�b�N�Ȃǂ���|�����ڂ��W�߂Ă����V�i�C�s�̃W�~�[�E�~���[���v���f���[�T�[�ɔ��F�B���傤�ǂ��̍������������肾�����g���t�B�b�N��2nd�A���o���wTraffic�x�̃T�E���h���~�b�N���������C�ɓ����ăX�J�E�g���������B�u���[�X���@���Ƃ����茘���A�[�V�[�ȃT�E���h���̒��ɂ������I�Ȏ��݂����X�Ǝ����ꂽ�wBeggars Banquet�x�ł���͋g�Əo�āA�ȍ~�wGoat's Head Soup�x�܂łɂ����ăW�~�[�E�~���[�̓X�g�[���Y����S���̐M���āA�h�邬�Ȃ��������̃T�E���h�����グ�Ă���B |
 |
Jim Price �i�W���E�v���C�X�j �{�r�[�E�L�[�Y�Ɠ�����LA�X�����v�E�T�[�N������i���r�[�g���Y��i�ȂǂɎQ�����Ă����e�L�T�X�o�g�̃Z�b�V�����n�g�����y�b�g�t���W���E�v���C�X�B�{�r�E�L�[�Y�̏Љ�ɂ��X�g�[���Y��i�֎Q���ƂȂ������̏��o��Ȃ́A�wSticky Fingers�x�����ƂȂ��uBitch�v��1970�N�̃I�����s�b�N�E�X�^�W�I�ɂāBStax�n�W�����v�E�i���o�[���X�g�[���Y���ɏ��������̋Ȃł́A�W���ƃ{�r�[�ɂ��p���`�̌������z�[���E�Z�N�V���������炩�Ƀh���C������^���Ă���B���̌�1973�N�̃E�C���^�[�E�c�A�[�܂Ńo���h�ɓ��s���A70�N��X�g�[���Y�̉��������x�����B |
 |
Leon Russell �i���I���E���Z���j �O�����E�W�����Y�̏Љ�ŃX�g�[���Y�Əo����ƂƂȂ����I���E���Z���́A�܂����wLet It Bleed�x���uLive With Me�v�Ƀs�A�m�ŎQ���������O��LA���X�����v�E�T�E���h�̈�Ђ𖼎h����ɍ����o���B�������A���I���̃X�g�[���Y�ւ̍ő�̍v���́A���̍L���l�������ē암�̃~���[�W�V�����Y�E�T�[�N����ނ�X�g�[���Y�Ƌ��L�����Ƃ����_�ɂ���B���g�̃V�F���^�[�E�s�[�v���A�f�B���C�j�[���{�j�[���t�����Y�A�W���[�E�R�b�J�[�̃}�b�h�E�h�b�O�X���C���O���b�V�������Ƃ����������̂��ւ�r�����̐l�C���A�����암���[�c�E�T�E���h�ɋQ���Ă����X�g�[���Y�̏��͂̂��߂ɐɂ������Ȃ����荞�݁A�u���[�X�A�\�E���A�J���g���[�A�S�X�y���̎��D�������L���ȃj���A���X�������������̌��т͏̂����Ă�����ׂ��B�܂��A1969�N���̃\���E�A���o���wLeon Russell�x�̘^���ɂ́A�r���E���C�}���A�`���[���[�E���b�c���Q�����Ă���B |
 |
Nicky Hopkins �i�j�L�E�z�v�L���Y�j �W���b�N�E�j�b�`�F�A�C�A���E�X�`�����[�g�Ɏ����œo�ꂵ�A�h��6�̃X�g�[���Y�h�ƂȂ郌�M�����[�E�s�A�j�X�g�̍���1967�N�wBetween The Button�x�^�����Ɏˎ~�߂��j�L�E�z�v�L���Y�́A�wTattoo You�x�܂ł̊Ԏ���70�Ȉȏ�̊y�ȂɎQ���B���݂Ɏ���܂ł̗��S�T�|�[�g�E�����o�[�̒��ł��Q���č����l�C���ւ��Ă���B�wExile On Main Street�x�ɂ����Ă������L���ȃs�A�m�E���[�N�͍Ⴆ�킽��A�uLoving Cup�v�̗���ȃ^�b�`�����uTurd On The Run�v���uRip This Joint�v�ł̃��C���h�ɓ]����u�M�܂Ŋɋ}���݁B�p�[�}�l���g�Ȍ��Ցt�҂�u���Ȃ��o���h�ɂƂ��Ċe�����́h6�Ԗڂ̃X�g�[���Y�h�Ƃ����̂́A�܂��Ƀo���h���ڎw�������������E����d�v�ȑ��݂ł���Ƃ������Ƃ͋^�����Ȃ����낤�B�Ƃ�킯�A�wThier Satanic Majesties Request�x�����wIt's Only Rock'n'Roll�x�܂ŁA����ɂ�1971�`73�N�Ⓒ���i�����s�C�j�ƕ]����郉�C������C����Ă����B�ނȂ����ẮA�z�����m�̃X�g�[���Y�E�T�E���h����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ȃ݂ɁA1969�N�wLet It Bleed�x�^�����̃A�E�g�e�C�N�E�W�����wJamming With Edward�x�iCD�p�Ձj�́A�j�L�����C�E�N�[�_�[�A�����āA�L�[�X�����̃X�g�[���Y���X�^�W�I�E�Z�b�V�����������̋L�^�ŁA72�N�ɐ��������[�X����Ă���B |
 |
Robert Frank �i���o�[�g�E�t�����N�j ����̃��b�N�E�t�@���ɂƂ��Ă��wExile On Main Street�x�̃W���P�b�g�E�A�[�g���[�N�A�����āA�h�L�������^���[�E�t�B�����wCocksucker Blues�x�Ƃ����A�X�g�[���Y�j����w�̂������킵���|�p���������������2��v���_�N�c����|�����l���Ƃ��Ă悭�m���郍�o�[�g�E�t�����N�B1924�N�A�X�C�X�̃`���[���b�q�Ő��܂������t�����N�́A47�N�Ɉږ��Ƃ��ăj���[���[�N�ɏo�Ă�����A50�N�㔼�ɂ͑S�Ă���Q���Ȃ���A���Ƀt�B����767�{���g�p���Ȃ���s���̌����̐������ʐ^�Ɏ��ߑ������B�B�e�C���[�W��27�A000�_�A���[�N�v�����g��1000���̒�����83��i���ʐ^�W�ɂ܂Ƃ߂��A58�N5���ɁuLes Americains�i�A�����J�l�j�v�Ƃ��Ċ��s����Ă���B�A�����E�M���Y�o�[�O���W���b�N�E�P���A�b�N�Ƃ������r�[�g���l��Ƌ����������ƂŁu���o�I���l�v�Ƃ��Ă�Ă����t�����N�B�uLes Americains�i�A�����J�l�j�v�ɂ��f�ڂ���Ă����ʐ^���R���[�W�������A�[�g���[�N�́A�X�g�[���Y�̊y�ȃC���[�W���剻��������̖��@�▃��߂����p���[�ɖ����Ă���C�����ĂȂ�Ȃ��B |
 |
Ry Cooder �i���C�E�N�[�_�[�j �wExile On Main Street�x�̘^���ɒ��ڊւ���Ă͂��Ȃ����A�wLet It Bleed�x�ȍ~�̃X�g�[���Y�A���ɃL�[�X�̃M�^�[�E�v���C�ɗ^�����e�����l����Ƃ������C�E�N�[�_�[���O���킯�ɂ͂����Ȃ��B�W���b�N�E�j�b�`�F���I�����s�b�N�E�X�^�W�I�ɘA��Ă��������܂������ɓ������M�^���X�g�ł��������C�́A�\�����́uLove in Vain�v�Ƀ}���h�����ŃN���W�b�g����邾���ɂƂǂ܂������A�uHonky Tonk Women�v�̗L���ȃI�[�v��G�t���[�Y�̔��ĎҁA�Ђ��Ă̓L�[�X�ɃI�[�v��G�`���[�j���O�̃X�^�C���������ꂳ���邱�ƂɂȂ����ƌ��ł���ƌÂ����猾���Ă���B���̂�����̐^�ӂ𖾂����肪����Ƃ��ẮA���̎��̃Z�b�V���������^�����������������wJamming With Edward�x�iCD�p�Ձj���ł��L�����낤�B�L�[�X�����ɂ��X�g�[���Y�Ƃ̃W�����E�Z�b�V�����ɂ��ւ�炸�A�t���[�Y�A���t�̃J�b�e�B���O�̒[�X�ɃL�[�X�̂���Ƃ̗ގ����������ĂƂ�A�܂�ŃX�g�[���Y�{���ɂ��Z�b�V�����Ɖ��瑻�F���Ȃ��B����ɁA�B�ꂱ�̎����Ɏ���܂ł̃X�g�[���Y�炵���Ȃ��_�Ƃ��āA���C�̕ē암�F�L���ȃT�E���h�E�f�U�C������������A�Ƃ܂ł���A����wSticky Fingers�x�i���C���uSister Morphine�v�̍Ę^�ɎQ���j�A�wExile On Main Street�x�ŃL�[�X���Ђ��ނ��ɒǂ����߂�悤�ɂȂ�ē암�T�E���h�̎|���A���̍ł��g�߂ŗǎ��Ȃ���{�����C�̃M�^�[�E�v���C�������̂�������Ȃ��ƌ�����͂����B |