Monday, September 12th 2011

�@�A�t�����|�����Y���𐢋I������[���N��̓����̃N���u�V�[���ɔ��������A�����������t�@���N�o���h�A�f�[�g�R�[�X�E�y���^�S���E���C�����K�[�f���iDCPRG�j�B�|��BPM�ɂ��t�F�C�Y�̐[���A�}�C���X�E�f�C���B�X�̃G���N�g���b�N�E�t�@���N�Ƌe�n��̓}�i�[�ɂ��}�C���X���A�N���X���Y���̃A�t���J�I�Ȏ��H�ɂ���āA����Ȃ�i���𐢊E�ŗB����������B2007�N�Ɋ������x�~������A2010�N10��9���A�J�̓���J��O���y���ŐV�����o�[�ɂ��`���I�ȕ��A�𐋂���B
�@�����č��N6��6���̌b���LIQUIDROOM�B�uALTER WAR & POLYPHONIC PEACE�v�ƌf����ꂽ�M�O�ɂ́A�A�[�g�E�����[�C���Q�X�g�o���B�啝�ȁh���̓���ւ��h���s�Ȃ����V��DCPRG�́h�a��h�̂ЂƂƉ����āA�N���E�h�����g�������S�����A�͂Ă͐S�̃q�_��܂������Ƃ����̂����畷���̂ĂȂ�Ȃ��B����ɁA�`���̈��ƂȂ������̃M�O��CD���A���������̘V�ܖ���W���Y�E���[�x���uIMPULSE!�i�C���p���X�j�v���烊���[�X�����Ƃ������ƂŁA�}�C�P���E�w���_�[�\���E�G���N�g���b�N�E�}�C���X�E�����j�I���E�o���h�̓��{�����O���i���ǂ͂��ׂĂ��v��̂܂܃G���X�g�j�o���݂̂̕����v�悪�����܂Ŕ��W���c������Ƃ�...�����Ɗ��т��n�[�h�ŃR�X���|���ȃA�}���K���ƂȂ���DCPRG�}�̉����ʂ�����ɂ͂����B
�@���̖����wALTER WAR IN TOKYO�x�B�u�ʉ����ꂽ�푈�ɍR���镽�a�͑��^�d�w�I�łȂ���Ȃ炸�v�iPELISSE �e�n���L���j�B�u9.11�v�A�����āu3.11�v�ɑΛ�������X�̑R��ׂ� �h�ŐV�̐퓬���@�h�Ƃ������ƂŁBDCPRG�̑�O�V�[�Y���A�ꔭ�ڂ̑S����v���_�N�c�͕S�o�܂Ƃ܂�Ȃ�2011�N�j�b�|���̃��[�h���ق��~�ς��邩�̂��Ƃ��A�T�d�����|�����Ȃ��ԓx�̃N���X�^�[�Ń_���X�t���A�Ɏ��ɐ^�����ŃV���v���ȃ��u��ʎY����B�����āA�s�ς́A�]�肠��}�C���X�E���X�y�N�g�ƂƂ��ɁB


1. Catch22
2. �Ԋ�
3. �W�����O����N���[�Y�ɂ����Ă�
���̓�
4. Hard Core Peace
5. �t�H�b�N�X�E�g���b�g
|
|
 �@Musical From Chaos 3�F HOA-KY �@Musical From Chaos 3�F HOA-KY |
| �@P���@�C���@PVDV34�@ |
�@������芈�������ɂ��Ă����S�ˉf��ēE�Ėڌ����A�e�n���̓��ʂ���uDCPRG���ہv���č\�z����Ƃ����R���Z�v�g�̂��Ƃɐ��삳�ꂽDVD�B�������DCPRG�̍ő�̖��͂ł��郉�C�u�̖͗l�����^�B�V�Ȃ𒆐S�ɃZ���N�g����Ă���B
|
|
|
|
|

[disc 1]
1. �W�����O����N���[�Y�ɂ����Ă�
���̓�
2. �i�C�b�c�E�A�E�X���[���j���[���h�E
�~���[�W�b�N�X�E���[���h
3. �����i���o�[49�̋���
[disc 2]
1. ���V���g��DC
2. 1865�N �o�[�W�j�A�B ���b�`��
���h
3. �t�H�b�N�X�E�g���b�g
4. �Ԋ�
|
|
 �@Franz Kafka's America �@Franz Kafka's America |
| �@P���@�C���@PCD18514�@ |
�@�J�t�J�̒��ҏ����u�A�����J�v�����p�����^�C�g���ɒ��n���Ȃ���A�u�ϑz�̃A�����J�v��`��������2007�N���\��3rd�A���o���B�J�I�X�ɖ��������|�I�ȃO���[���́A����ɂ��̍��דx�𑝂��Ȃ���F���I�ȍL������݂���B�u�i�C�b�c�E�A�E�X���[���j���[���h�E�~���[�W�b�N�X�E���[���h�v�����āA�u�A�����J�R�̋f���Ƀ{�T�m���@���~�b�N�X���ꂽ�G���K���g�ɓ������A�쐶�̎v�l�ɂ�銮���ȃ}���A�[�W���v�i©�e�n���j�B
|
|
|
|

1. �\���T �i�����p�̍\���j
2. �\���U �i�����A�����J�̍\���j
3. �\���V �i��]�̂Ɣ��t�̍\���j
4. �\���W �i���@�ƓV���̍\���j
5. �\���X �i�`�p�Ɗ��y�X�̍\���j
6. �\���Y �i�V�����p�������̍\���j
|
|
 �@Musical From Chaos 2 �@Musical From Chaos 2 |
| �@�R�����r�A�@COCP50828�@ |
�@�wMusical From Chaos�x���e�ł́A2003�N��������2004�N��܂ł̃��C�u�f�ނ��猵�I�����x�X�g�e�C�N�ɂ���đ������B��p�I�łȂ��{�\�I�ȃ_���X�~���ɑi��������DCPRG�̃��C�u�����Ɖf�����S��iDVD�t�������DVD�͐��Y�I���j�B����ɋe�n���ɂ��Ύ��I�ȃJ�b�g�A�b�v���{���ADCPRG�̖������ɖ������p��N���ɕ����т����点�Ă���B
|
|
|
|
|

1. Stayin' Alive
2. Fame
3. Pan-american Beef
Stake Art Federation 2
4. �y�G���n���X�h�z structure I
�iLive Version�j
|
|
 �@Stain Alive / Fame / Pan-american Beef Stake Art Federation 2 �@Stain Alive / Fame / Pan-american Beef Stake Art Federation 2 |
| �@�R�����r�A�@COCP50817�@ |
�@2004�N�̃��W���[�ՁB��������M�]����Ă������C�u�ł��Ȃ��݂̃��p�[�g���[�ɏ������낵2�Ȃ��v���X�i1�Ȃ̓J���@�[�j�BDCPRG�̓���҂Ƃ��Ă��@�\������ׂ��A���ĂȂ��قǃ����f�B�b�N�ȃi���o�[���W���B���C�u�ő��Ԃ̃r�[�W�[�Y�uStain Alive�v�i�X�^�W�I�e�C�N�͏��j�A�f���B�b�h�E�{�E�C�̖��ȁuFame�v�̃t�@���L�[�E�J���@�[�ɁAROVO�Ƃ̃X�v���b�g�E�V���O���Ŕ��������uPan-American Beef Stake Art Federation�i�S�ăr�[�t�X�e�|�L�|�p�A���j�v�̑��҂����^�B
|
|
|
|

1. �\���T �i�����p�̍\���j
2. �\���U �i�����A�����J�̍\���j
3. �\���V �i��]�̂Ɣ��t�̍\���j
4. �\���W �i���@�ƓV���̍\���j
5. �\���X �i�`�p�Ɗ��y�X�̍\���j
6. �\���Y �i�V�����p�������̍\���j
|
|
 �@Structure Et Force �@Structure Et Force |
| �@P���@�C���@PCD18508�@ |
�@�^�C�g���͓��{��Łu�\���Ɨ́v�B1983�N�ɏo�ł��ꂽ��c�����̒������t����ꂽ2003�N��2nd�A���o���B�o���h�̎x���Ƃ��������F�ljp�̒E�ނ͂��������̂́A�u���X���������������ƂȂǂɂ��A����ɃA�����W���A�O���b�V�u�ɁB��C�T�|�[�g�E�M�^���X�g��PANIC SMILE����W�F�C�\���E�V�����g�����}���A�W���Y�A�t�@���N�A���b�N�A�N���u�E�~���[�W�b�N���ׂĂ����ݍ��J�I�e�B�b�N�̂ւƐi���𐋂����B
|
|
|
|
|

[disc 1]
1. Catch 22
2. Catch 22
3. Catch 22
4. Catch 22
5. Catch 22
[disc 2]
1. Playmate At Hanoi
2. Spanish Key
3. Stain Alive
4. Circle/Line�`Hard Core
Peace
5. S
6. �z�[�`�~���s�̃~���[�{�[��
|
|
 �@Musical From Chaos �@Musical From Chaos |
| �@P���@�C���@PCD18506�@ |
�@�l�͂őn��o�����ׂƎܔM�̉����B2002�N���̒E�ނ��Ռ��I��������F�ljp���ݐЂ����������E������t���E���C�u�ՁB�ߋ��̖c��ȃ��C�u�E�X�g�b�N��������x�X�g�e�C�N��I�肷����B�uCatch22�v�̃��@�[�W�����Ⴂ5�Ȃ����ō\�����ꂽ�f�B�X�N1�ɂ́A���ׂƂ����܂ܔ���������A�~�j�}���ɂȂ�����A���܂��ܕ\����܂�ŕʋȂ̂悤�ɒ�������DCPRG�̃��C�u�̖��͂������Ƀp�b�P�[�W�B
|
|
|
|

1. Catch 44.1 �iOe
Reconstraction�j
2. Bayaka
3. Play Mate at Hanoi -Inu
Ni Kirawareta- �iDJ
Quietstorm Mix�j
4. Play Mate at Hanoi
�iOlantunji Mix�j
5. Circle Line �iDJ Me DJ
You Mix�j
6. Catch 22 �iKazunao
Nagata Showa Dub Mix�j
7. Pan American Beef
Stake Art Federations
�iRei Harakami
Re-Arrange�j
|
|
 �@3rd General Representation Products Chain Drastism �i1CD�j �@3rd General Representation Products Chain Drastism �i1CD�j |
| �@P���@�C���@PCD24131�@ |
�@���C�n���J�~�A�u�L���v�e���t�@���N�v���ƃI�I�G�^�c���ADJ �N���C�G�b�g�X�g�[���ASUKIA��DJ ME DJ YOU�A����Ƀg�����\�j�b�N�̉i�c�꒼�A�����o�[�̑�F�ljp�Ƃ����A�ЂƃN�Z���ӂ��N�Z�����郁���c�ɂ�郊�~�b�N�X�ՁB���ꂭ�炢�N�Z�̂��郁���c�łȂ���DCPRG�̉����͗����ł��Ȃ��B
|
|
|
|
|
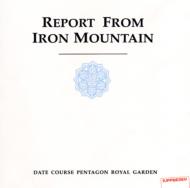
1. Catch22
2. Playmate At Hanoi
3. S
4. Circle/Line�`Hard Core
Peace
5. Hey Joe
6. Mirror Balls
|
|
 �@�A�C�A���}�E���e���� �@�A�C�A���}�E���e���� |
| �@P���@�C���@PCD18502�@ |
�@�e�n���E���劲�ɁA��F�ljp�A�،������A�F�_���m�A�I�������A�g�������A����M�Y�A��V�����A�Ï㌤���A����N���A��֍D�G�Ƃ������B�X���郁���o�[����Ȃ�u�f�[�g�R�[�X�E�y���^�S���E���C�����E�K�[�f���v�A2001�N�����[�X�̋L�O���ׂ�1st�t���E�A���o���B70�N��}�C���X�ւ̃��X�y�N�g���\���ɛs�݂A�u�펞���Ɋ��s���ꂽ�푈�Ɋւ���U���v������p���ꂽ�^�C�g���ȂǁA�����Ƀp�C�\���Y���Ȃ���̍��������d���܂�Ă���B
|
|
|
|

1. �V�m / ROVO
2. Pan-american Beef
Stake Art Federations
/ DCPRG
|
|
 �@�S�ăr�[�t�X�e�[�L�|�p�A�� �@�S�ăr�[�t�X�e�[�L�|�p�A�� |
| �@P���@�C���@PCD18501�@ |
�@�u�S�ăr�[�t�X�e�[�L�|�p�A���v�Ƃ́A�u1956�N����58�N�ɂ����Ċ����������݂̒c�̂��B�S�ĂƖ�����Ă��邪�A���ۂɂ̓j���[���[�N�̐����X��l��َq�E�l�A��ƂȂǂ��琬�鐔�\�l�̕ϐl�̏W�c�������悤���E�E�E�v�ƃ��C�i�[�m�[�c�̒��ŋL�q����A�A�����J�����O�̋e�n���ɂƂ��Ă̏d�v�ȃA�����J���E�C�R���̂ЂƂł������Ƃ����B�{��́AROVO��30�������V�F�A�����S2�Ȃ̃X�v���b�g�ՂŁA�\��Ȃ́A���X7���قǂ̊y�Ȃ����p�ӂ��Ă��Ȃ��������̎E�l�I�ȓw�͂ɂ����30���̍�i�Ƀf�b�`�グ��ꂽ�Ƃ����V�����m�B�g�[�^��60���A���`�����l�����璮������h���������ׂĖF�_���m�Ƃ����̂��~���N���B
|
|
|
|
|

[contents]
�E �������q�̋A��
�E �W�]���X�g�����u����v
�E �u���̐��I���v�����ݏo�����A
���u�N�I�ɏ��K�͂ȑ���
�E �_���X�o���h���A
�푈����ɍ���Ă����@�ق�
|
|
 �@�X�y�C���̉F���H �@�X�y�C���̉F���H |
| �@���w�ف@4093874654�@ |
�@�e�n���̏��G�b�Z�C�W�B1999�`2001�N4���̊Ԃ�HP��G���Ɋ��c��ȃG�b�Z�C���猆������I�������́B�u���v�̓s�s���鉹�y�Ƃ̐����ƈӌ��A�Ђ��Ă͐_�o�ǓI�Ȍ���l�̊���𑨂����h�L�������g�ł���{���ɂ́A���y�A�����A�f��A���w�A�Z�b�N�X�A���_���͂Ȃǂɂ��Ẵy�_���g���[��S�J�ɂ����A�ǎ҂̌܊��ɑi��������N��ȕ��͂���������l�܂��Ă���BDCPRG�����֎���˂����������Փ��́u�_���X�o���h���A�푈����ɍ���Ă����v�ŁB2009�N���s�̕��ɔł��������B
|
|
|
|

1. Theme of Inuhime
/ �a���m��Y
2. 2004.3.17. Fine
/ �O�R���E��V���� �f���I
3. �\���T 1/2 / DCPRG
4. Song for Che �`
Reducing Agent / ONJO
5. ��s�@���ƃ����[�S�[�����h
/ Vincent Atmicus
6. ���ΓI�ߎ����I�[�l
/ ���J�_�́E�e�n��W �f���I
7. FUMO / ROVO
8. Praise Song / �씎�g���I
|
|
 �@V.A. / Boycott Rhythm Machine �@V.A. / Boycott Rhythm Machine |
| �@Vinylsoyuz�@VSAC2002�@ |
�@����50���ɂ��y�ԁg�W���Y�̖��@�g���h�B�ɂ�閲�̋����B2004�N��Ȋ������W���Y�̐V���Ȓ������A�ɍʐF�̐����ŐU��Ԃ�������R���s�B�u�\���T 1/2�v�͋e�n���ɂ��Z���t�E���~�b�N�X�B
|
|
|
|
|

[disc 1]
M-1. Playmate At Hanoi
/ DCPRG
M-2. Hey Joe �iMAHER SHALAL HASH BAZ�j
/ DCPRG�@�ق�
[disc 2]
M-2. ��l�ɂȂ��
/ ���v���q�~�e�n���E�@�ق�
|
|
 �@V.A. / �����Y�� Vol.2 �@V.A. / �����Y�� Vol.2 |
| �@P���@�C���@PCD5655�@ |
�@�X�y�[�X�V�����[TV�����s���Ă����t���[�y�[�p�[�u�_�_�_�[!�v�̃g���r���[�g�E�R���s���[�V�����E�u�b�N CD �u�����Y���v�̑�2�e�A���̖����u�����Y���v�B3���g�{72�y�[�W�E�u�b�N���b�g�d�l�BDCPRG�́A2001�N10��1���̐V�h���L�b�h���[���ł̃��C�u����2�Ȃ����^����Ă���B����ɋe�n���́A����g���b�N��������v���q�̃Z���t�J���@�[�u��l�ɂȂ�v�Ńf���G�b�g�̏��܂ł��I���Ă���B
|
|
|
|
|
|
|

�@�u�푈���O�̏����Փ��v
�@���傤��10�N�O�́u�N�C�b�N�W���p���v���i2001�NVol.38�j�̕\���ɂ͂���Ȓ����I�ȕ��������A�劲�E�e�n���E���͂��߂Ƃ������DCPRG�̖ʁX������������Ȃ���݂̓����鎋����������ɓ��������Ă����B
�@�����A���Ɠd���[�J�[�ɋΖ����Ă���OL ���V�� ��Ƃ̃A���j���C�E�|�b�v�E���j�b�g���X�p���N�n�b�s�[�i���̎��_�ő����j�ƕ������邱�ƂŎ���̌��iAB�^�B�������o�q���j�ɏ]���ł��邱�Ƃ߂����A���ʁu�ɂȃ��m���m����l�̒��ŝh�R���A������������ƕ��������v���Ƃ�~����Ƃ������_�I�ύt���ۂ����B�䂦���e�n����u�T�[�N���i�~�j�^���C���i�����j�v�Ƃ���70s�}�C���X�o�R�ɂ��ăA���r�o�����c�ɖk�̊��S�̕��`���S�Č����炷�ׂĂ��͂��܂����Ƃ���DCPRG�B����e�B�|�O���t�B�J�̎u���p�������A���t�B�W�J���Ń_���X�t���A�i��ȃ��Y�����O���[���ւƃV�t�g�����^���̂̉���I�ȋ쓮�B�����āA�u�A�����J�^�푈�^�_���X�v�B�����E�^�c������1998�`99�N�A�R�\�{�����^�������ɔ��肵���u�푈�s���v�Ƃ�����@���������p�[�\�i���ȋK�͂Ńh���C�ɕ����Ă����劲�B���̕s���́A�o���ɂ������Փ��ւƔ��]���A����I�ȃV���N���j�V�e�B�����������N�����B�u���Ȃ̕s���_�o�ǂ��������邽�߁v�Ƃ��Ȃ�����A�u���Y���E���l�T���X��W�Ԃ��邪�䂦�v�Ƃ��Ȃ�����A�T�ڂŖڂ������邱�Ƃ����͛߂߂Ȃ����������A�����J��21���I���v��ʃJ�^�`�Ŗ����J�����E�E�E�ŏ��̃t���A���o���w�A�C�A���}�E���e���x�̃����[�X���炿�傤��1�������2001�N9��11���A�j���[���[�N���E�f�ՃZ���^�[�r��2����2�@�̗��q�@���˂����ށB���̓��������e���ɂ��o�[�W�j�A�B�A�[�����g���ɂ���č����h���Ȃ́E�E�E�@�@�@�@�@�@
�@���㉹�y��t���[�E�~���[�W�b�N�ɂ�����u�J�I�X�v�ł͂Ȃ��A�_���X�E�~���[�W�b�N�ɂ�����u�J�I�X�v�Ƃ������̂����[�X�̃_���X�Փ����t���邩�ۂ��B�o���o���Ȃ��̂��u�ԓI�A�����Ď����I�ɂЂƂ̃O���[���ƂȂ�|�C���g�B�����g�̂��{�\�̕����܂܂ɂ����蓖�Ă悤�Ƃ��� or �����I�Ȍ������瑍�Ă��������uCatch 22�v�B�u�푈�̕s�𗝂Ƌ��C�v���e�[�}�ɂ����W���[�[�t�E�w���[�ɂ�鏬��������p�����^�C�g���B�����o�[�S���̃��Y�����^�C�����قȂ�O���[���̃��C���[�Q�i���ӓI�ŋ����I�H �ȃ|�����Y���j�ō\�z���ꂽ���̋Ȃ����C�u�̖`���Ɏ����Ă��邱�Ƃɂ���āADCPRG�̓_���X�E�~���[�W�b�N�̂�����\����͍�����������B���̕����I�ȏW�听���wMusical From Chaos�x�́A���X�Ȃ܂ł́uCatch 22�v 5�A���ŁB �h�Y���h�ƃY����E������u�́h�]�[���h�Ƃ̂��߂������́A���C�u�̌���ŋ����ׂ����x�Ŕ�債�i�����Ă䂭�B����A�uSpanish Key�v�̃i�C�[���ȃJ���@�[����A���テ�[�X�ɂƂ��Ă͔��Γs�s�`���̏ے��Ƃ�������قǑ������A���ꂪ�t�ɐV�N�ȁh�F�����h������u������o�u���V���X�ȃ~���[�{�[���E�T�E���h�܂ŁB�푈�ɂ����������̋Ɍ���ԁ��u�ƒ{������Ă��Ȃ��J�I�X�v ���ŗx�点�邱�Ƃ𖽑�ɂ�����A�d���}�C���X�͂��납�A�X���C�AJB�AEW&F�Ȃǂœ���^�R�x�肷��l�����Ƃ������w�����L����A�������̂���ő����DCPRG�͎������킹�Ă����B����������́A�G���ȁu�l�ł��v�����K�Ƃ���A����t���A�Œ�ԉ����ꂽ�ő���Ƃ͎����قɂ���B�u���Y�����a��v�����U���Ċ��}����A����ȃu���b�N�E�~���[�W�b�N�ʎj�ɖ��ڂɃR�l�N�g�����_���X�E�~���[�W�b�N�����u�J�I�X�v�A�Ƃł���������Ɂi�H�j
�@�u�x�点��v�u�_���X�Փ��ɑi��������v�Ƃ������ƂɎ�������ȏ�A��I�ȂЂƂ̃O���[���ɒ��n������Ȃ��̂͂����̏h���Ȃ̂�������Ȃ����A�劲�E�e�n���E�Ƃ��̓��u�����O���[���̍\���́A�Ⴆ��90�N��`00�N��ɂ����ĉh���ɂ߂��N���u�W���Y�i���邢�̓A�V�b�h�W���Y�j�I�ȃA�v���[�`�Ƃ��܂��ٌ`�B���̎�̃t�B�[���h���}�C���X�E�f�C���B�X�̈�Y�ł�������悭�𓀂��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂�����A70s�}�C���X���Z���g�����E�h�O�}�ɐ����Ċ������J�n����DCPRG�������ɑ��e���킯���Ȃ��A�ƌ������炠�܂�ɂ��Z���I���H �����A�q�b�v�z�b�v���l��DJ�J���`���[�Ƌ��ɔ��W�𐋂��Ă����N���u�W���Y�̕���ɂƂ���DCPRG�̃O���[���Ƃ����̂́A�u�Y���ŗx��v�����b�g�[�Ɍf���Ă��邾�������āA��͂�X�}�[�g�ɏ������ɂ��������R�[�h�Ńt���A���ە����Â炢���̂ł������ɈႢ�Ȃ��B�w3rd General Representation Products Chain Drastism�x�Ƃ������~�b�N�X�Ղ������삳��Ă͂��邪�A�������ɂ�����N���u�W���Y�Ɠ����n���Ō��ɂ͂��Ȃ�̖���������Ƃ������́B�ǂ̋Ȃ����e�̔Z���告�o�Ȃ���A�N���u�ɑ��ɂ��ʂ��W���Y�E���X�i�[�̉�H�����������邾���̋����Ő����������킹�Ă���Ƃ����_�ŁB
�@��F�ljp�E�ތ��DCPRG���u�O���E���h�E�[���v�f��r�������A�̂ǂ��ȑ����v�Ƃ��������i���Ă����������s�s�ɑ��H���ꕔ�D���Ƃ��A�wStructure Et Force�^�\���Ɨ́x���wMusical From Chaos 2�x��2�N�z���̍��킹�Z�ɂ͖A��H�����̂��A�ςĂ����Ȃ��t�W���b�N�o���Ɂu�A���̓��o�������ȁv�Ƃ������Đ������n���B�}�C���X���wOn The Corner�x�́A���̃��C�u�Č����̒Ⴓ�������Ԃ����Ⴏ�����͂ƁA���x�ڂ��̐���オ����݂�������ł�����B���W���[���i�������ĂȂ��������̂��Ƃ��A�ŏ����炻���ɑ��݂����t�@���N�E�~���[�W�b�N�{���̈Ӗ��A�����I�ȁA�u�t�@���N�̍����v���T�O��������劲�B�u�����p�v�u�����A�����J�v�u��]�̂Ɣ��t�v�u���@�ƓV���v�u�`�p�Ɗ��y�X�v�u�V�����p�������v�E�E�E�قȂ�6�́u�\���v���ׂĂ��ЂƂ̍����I�ȃt�@���N�͊w�ɂ���Ċт��ꔽ����������A�Ƃ����B�Ɠ����ɁA�劲���炪�������ɐ錾���Ă������U�N��2002�N�����łɒʉ߂������Ƃ�m�蓾�Ȃ���ADCPRG������Ɂu���Y�����a��v������s�\�ȂقǃL�c���n���ւƁA�O���q�Ǝl���q���������č��Ȃ��悵�Ƃ����̋��ւƁA�{�\�I�ɋA�����邩�̂��Ƃ��������Ă����̂�ϑz���Ă����������o�`�͂�����Ȃ����낤�B���Ȃ݂��w�\���Ɨ́x�̃��[�L���O�E�^�C�g���́uPRESIDENTS�i�v���W�f���c�j�v�����������ŁA�S�ȂɎ劲�I�肷����̗��A�����J�哝��10�l���W�F�[���Y�E�u���E���̖��������ꂽ2���g��\�肵�Ă����A�Ǝ劲��HP��ɋL���Ă����̂��L�����Ă���B
�@�X�p���N�n�b�s�[�����łɋx�������Ă����劲�E�e�n���E�́A�o�q���EAB�^�̌n���ǂ���ɁADCPRG�Ƃ͎�̈قȂ� �h�����ЂƂh �������͂��߂�B�w�f�M���X�^�V�I���E�A�E�W���Y�x�A�w��ẴG���U�x�X�E�e�C���[�x�Ƃ���2���̃��[�_�[�E�A���o���ɁAUA�Ƃ́wcure jazz�x�B�|�X�g�E���_���W���Y����A�L�b�`���̒�`�A�u�G�m�X�A�C���X�A�W���Y�҂�܂ł��ؗ�ɂ���Ă̂������ADCPRG�̖{���́h�R�n�h�͎劲�ɓ����I�ɓ��݂��鉽�p�^�[�����̃_���X�Փ��ւ̎��⎩������o�ꂷ��B�V�h�E�̕��꒬�ɍ�����ڂ����̂Ɠ��������Ď��R�����I�ɐ��܂ꂽ�u�����Ђ��̈ɒB�j�ɂ�鍉��v�Ɩ��t����ꂽ�y�y�E�g�������g�E�A�X�J���[���ł́A�O�����h�L���o���[���������/�����̃f�J�_���X�i�Ô��Ȓn���j��M�a���P���V�����s�Ȃ��A60�N��h�X�[�c���h�̃}�C���X�E�Z�J���h�E�N�C���e�b�g�ɃI�}�[�W����������_�u�E�Z�N�X�e�b�g�i��̂̓N�C���e�b�g�E���C�u�E�_�u�j�ł́A�����ʂ�A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y�Ƀ��A���^�C���E�_�u�̃X�������O�ȃh�L�������g���𗬂����ނ��Ƃ��^�X�N�Ƃ��ĉۂ����B�ǂ���������N�X��r�W���̃G���K���X�ł�����߂ɂ��Ȃ�����u�x��Ηx��v�ƍ���I�E�����I�Ƀ_���X�Փ�������Ă͔���A�����Ă͔���B�uT�V���c�E�Z�p���E�X�j�[�J�[�v���ł������Ԃ�DCPRG�̃��C�u�t���A�ł͂܂����ڂɂ�����Ȃ��A����ƂĒn���̂悤�ȉ��y�����L����Ƃ����Ӗ��ł͒ʒꂵ����������I�ɐ萷�肷��劲�B���ɂ��t���b�g�ɒ邱�ƂŁu���͔������Ă����w�����v�Ƃ������}���Ƀ\�t�g�^�b�`�������Ă����̂ł́H �Ǝא�����B�@�@
�@3���ڂ̃t���E�A���o���wFranz Kafka's America�x�́A�t�����c�E�J�t�J�̖����ɏI��������ҏ����u�A�����J�v���炻�̃^�C�g�������p���ꂽ���Ƃ͌����܂ł��Ȃ����A�����ɕ`���ꂽ�u�A�����J�̑�n�ނ��Ƃ̂Ȃ������M�҂ɂ��A�ϑz�̃A�����J���O���v�Ɏ劲���s���Ƃ������Ƃ�����Ȃ鑽����v���Ȃ��Ƃ��Ă悢���낤�B�u9.11�v�i�� �u�b�V���ɂ���ʔj��ۗL���ł���Ƃ̔��j�ɒ[�����C���N�푈���ڂ���Ǝ����Ɍ������C�z�������͂��߂�2007�N�A�u�푈�s���v�͂��납�u�푈�ƃA�����J�v�Ƃ����C���[�W���特�y�ւƌi�C�悭�R���o�[�g���邱�Ƃɍ���ȋ��E���Ȃ����́h�R���s���nj�Q�h�ɂ����������̖������Ɍ������Ă����Ƃ������A�u�ϑz�̃A�����J�v��ϑz���邱�Ƃɂ���ăA�����J�͂��A�����J�炵���Ȃ����ƌ����ׂ����A�Ђǂ��f�t�H�������ꂽ�A��������C���v�b�g���Ӑ}�I�ɐ��m�ȏ������{������ �h�Y���܂������h�R���[�W���Ƃ��ăA�E�g�v�b�g�����A�z�����`��ŗD�ꂽ�����f�B�����A�����J���O�����̂̃G�C���A����g�U��B���ꂪ�u�W�����O���E�N���[�Y�ɂ����Ă��̓��v�Ɩ������ꂽ���_�Ŏ劲�̖�]�͂قڒB�����ꂽ�ƌ�����̂ł́H �Ƃ������א����d�˂Ă݂�B
�@2007�N�����ɂ�����u�R�A�����J�v�Ƃ����Ӗ��ł́A�G�L�]�e�B�V�Y���������ォ��ڐ��ʼnߏ�Ɏ�荹������āA�������ŕs�����Ȃ��̍����L�̎s���`�����\���ɂ������Ȃ��U�炩����Ă��܂����ꂾ���đ傢�ɂ��邪�E�E�E�劲���J�t�J�����p���Ȃ���u�����ЂƂ̃A�����J�v�u�A�����J�̂悤�ȃA�����J�v��N�₩�ɎY�ݏo�����ϑz�͂Ƃ������̂͋ɂ߂ċ����������ƌ����邾�낤�B�u�ă\��펞��ɖ߂�̂��I�b�P�[�B�����I�ɂ͋ɒ[�ɖʔ������̂��܂��o�Ă���͂�������v�ƈȑO���ڂ��Ă����劲���K���t���̃p�p�[�n�����Ă���̂́A���Y���[���̃m�X�^���W�[�ł��^�`�̈�����₩���ł��Ȃ��A�ނ���u�㗝�푈�v���炢�����ďo�邼�Ƃ����Y�S�̏Ɍ����Ȃ����Ȃ��B�W�����E�]�[���́u�R�u���v�͂����炩�F�Ă��܂�����������Ȃ����ADCPRG�́u�A�����J�^�푈�^�_���X�v�Ƃ����O�{�̖�́A���̗��j�Ȃ��卑�̋}���߂����ĕ����ꂽ�A�Ɩϑz����̂��Ȃ��Ȃ��ǂ����Ĉ����͂Ȃ����߂ł͂������B�������A���̕a�I�Ȃ܂ł��a�肫�������Y���ƃO���[���̃R�A�ɂ́A��ꂳ�Ȃ���̍��ׂƂ������ł���ɂނɑ̂���DCPRG�N���[�̎p���z���̂悤�ɗh�炢�ł���A�Ƃ���̂����S�����A�����܂ŏ́u��O�v�̂܂܂Œ�����Ă������Ƃ̕����_���X�E�~���[�W�b�N�̍���ɂƂ��Ă͍D�s�����B
�@�hDCPRG �A�����J�E�c�A�[�h�I����A�u�w�ϑz�̃A�����J�A�ϑz�̐푈�x�Ƃ���DCPRG�̊�{�I�ȍ\���́A�����ŏ��������B�v�Ǝ劲�͓Y���ADCPRG�̗��j�A���̑傫�Ȉ�{�̗��������̎�Ő��X�������f�����B
�@�u�V�����i�����āA�܂����������ȁj�����o�[�B�ɂ���āA�R���v���[�g�ȃo���h�������ĊJ����̂ł���B�v�ƃA�i�E���X���ꂽ�̂́A2010�N�̏��Ă��������낤���B���ꂩ��3������A�h�V���~��̓���J��O�剹�y���ɂ́A�u�A�K�p���E�o���h�v�ǂ��납�u�J���o�b�N�E�o���h�v��낵���̂��悻������Ȃ��炪���ї��B�劲�H���u���m���Ȃ���A���Y���ɑ��郊�e���V�[�͍����v�Ƃ����s�A�j�X�g�̏�iSOIL&PIMP SESSIONS�^J.A.M.�j��h���}�[����Z�@�b�iCOMBOPIANO etc�j�Ɋւ��Č����A����ƂȂ��N���u�W���Y�⌻�㉹�y�`�|�X�g���b�N���ʂɎ����߂Ă�����ɂ͂��łɊ���������ꂽ���݂����A���̉A�Łu�V�����i�����āA�܂����������ȁj�����o�[�B�ɂ���āv�Ƃ����{�̃}�j�t�F�X�g�̓N�[���ɐ��s����Ă����B�s�b�J�s�J�̐V�l�Ƃ́A���̔N���_�u�E�Z�N�X�e�b�g���t�W���b�N�Ŗ{�c���̃g�������߂��c�������ids�j�ƁA�A���K�X�ib�j�A���䎬�l�iss,ts�j��3�l�B��������u�鐝��H�v�Ƃ����C���X�g�o���h�̃����o�[�ŁA�劲�̎��m�u�y���M�����y��w�v�o�g�ł����邢��Ε��S�B���邢���e�n���E�`���h�����̃Z�~�v���E�g�b�v3���B�Ƃ������A�u�V�l�̕��S�v�u���S�̐V�l�v�Ƃ������̂������ĂȂ��悤�Ȃ��̂��N�p����Ƃ����l�ވ琬�E�J�����\�b�h�͂܂��ɃG���N�g���b�N���ȍ~�̃}�C���X�̂���ɒǐ����Ă���A�Ɩ��Ȃ���������ɂ��������鎟��B�}�C�P���E�w���_�[�\�������r���E�G���@���X���̃��b�L�[�E�E�F���}�����̂�]�T�őz�N�����邱�́h���̓���ւ��h��p�ɂ́A�K�`�ƃG���^���̋��E���ł���Ȃ��������I�ɗL�떳��ɂ��Ă��܂��قǃr�b�O�ȁu�}�C���X�E���u�v���`���`���ƌ����B�ꂵ�č�����Ȃ��狹���ł������E�E�E�ƃq���[�}�j�Y���̔��e�ʼn��������߂����������̂́A���ۂ́uDCPRG���Ĉ��������i���p�C�I�j�A�ɑ�����j�̐����Ԃ�ɋ������ꂽ����v�ƁA�劲���炪����C���^�r���[�Ō���Ă����Ƃ���ƂȂ�B
�@�����Ɍ��ȑg���Ï㌤���isax�j�A�މƐS���itp�j�A���N�����������邱�ƂƂȂ��呺�F���ig�j���������z�w���u�V��DCPRG�v�ƌĂ��R���v���[�g�ȃ��C���i�b�v�B�܂����̓��́A�O���߂��A�����J���E�N���[���F�����b�`�[�E�t���[���X�iper�j�A���X���@�j�[�E�e���[�E�J�u�����isax�j�ɁA�i�呺����������܂ł́j���Ԍ���Ńc�A�[�ɑѓ����Ă������W���f�B�}����TAKUYA�ig�j���Q������Ƃ����C���M�����[�����ȃ��C���i�b�v�ŁADCPRG��O�V�[�Y���̖������ė��Ƃ��ꂽ�B���̃M�O�̖͗l�́A24bit/96kHz��WAV�t�@�C����MP3�t�@�C�����܂�DVDR�{�ʐ^�W�uBOYCOTT RHYTHM MACHINE AGAIN Live at Hibiya Yagai Ongakudo Oct.9.2010�v�i�����f�[�^�݂̂̃��m������j�Ƃ��ăp�b�P�[�W������Ă���B
�@�u�p�������Ȃ���A���Ă܂���܂����v�ƃc�B�[�g�����̂́A�������܃W�����O���������������A�O�@���̎R������~�o���ꂽ���䏯��B�u�����N�������Ă��Ȃ���v�Ǝ��}��������̊ԑ����W�����O���E�N���[�Y�Ƀ{�[�g�𑖂点��̂��e�n���E�B�u���Ȃ�A�ϑz�̐��v����݂��Ɛ��ҁA�݂��ƒE�p�������҂̍ő�������]�Ɉ�ؗ��炸�������ɂ͂����o���ċY��ł��݂���B
�@��������A�\��i�@�ł�������ЂƉ��B�劲�̃[���N��ɂ�����10�N�̊����j���w�����̃G�`�J�x�Ƃ���4�M�K�E�o�C�g�̃������[�E�X�e�B�b�N�i�~2�j�Ɉ��k���ꂽ�N�̕����ՁA����ɑO�サ���l���啝���V�Ƃ�������v�A�����Ă������̃M�O���o��2011�N9���A���悢��!!�Ɛ����r����ׂ����A���̃^�C�~���O�łȂ�!?�Ɣ����Ђ��߂�ׂ����ADCPRG�̓��[���h���C�h�E�f�r���[���ʂ����B�uTHE NEW WAVE JAZZ IS ON IMPULSE!�i�W���Y�̐V�����g�j�v���|���V�[�Ɍf���Ĕ����I�A�č��W���Y�E���[�x���̘V�܁uIMPULSE!�i�C���p���X�j�v����̃A���o���E�����[�X�����܂����B�A�[�g�E�����[�C���Q�X�g�Q������2011�N6��6���̌b������L�b�h���[�����������^�������C�u���wAlter War In Tokyo�x�B���{�l�͂��납�A�W�A�l�i�O���[�v�j�̍�i�������[�x�����烊���[�X����邱�Ǝ��̏��߂āA�Ƃ����g�s�b�N�ɖ{���Ȃ�Α�Ȃ܂łɋ����������Ƃ���Ȃ̂����A�d�v�Ȃ̂͐��������ł͂Ȃ��B���I���́u�푈�s���v�ɑ��鋹���킬���|�����Y�~�b�N�ȃO���[���ւƋ�����Ȃ���_�C���N�g�ȃ_���X�E�����B�h�[��˂��������Ă䂭�Ƃ����ADCPRG�������ȗ� 1�b����Ƃ����낻���ɂ��Ȃ����������ɋɂ߂ċ߂��R���Z�v�g���A�j����ۗL���Ɓu�O���E���h�E�[���i���S�n�j�v���i�uMAD�v�uSAD�v�̏����I�ȃ��C�~���O�ɋC�t���ʃt�������Ȃ���j���`�Ƃ��Ď������킹��A�����J�A���ɍőO���k�Ă̓���I�ȃ_���X�t���A�ŁA�T�E���h�V�X�e���ŁA�J�[�X�e���I�ŁA�x�b�h���[����WQXR Q2�ŁA�����ɂ��Ă��ς˂��A�����ɂ��ăA�W���X�g���Ă������Ƃ����U�h�₻�̐�ǂɋ����ÁX�ȂE�E�E
�@�Ƃ���̂�2010�N�܂ŋ�����Ă����A�i�ނ��Ƃ�m��Ȃ��Ӗ��ȃN���e�B�b�N�B�劲�̒��ŁA�u���o��/���m/�ϑz�Ƃ��ẴA�����J�v�Ƃ����͂Ƃ����̐̂ɏI�����Ă���̂�����A����ȍu�߂́A�ϑz��SF�ɂ��痩�邱�Ƃ̂Ȃ��A�܂������̃i���Z���X�ł���킯�ŁB�ꌩ�p���h�b�N�X�ȗl����悵�Ă���̂�������Ȃ����A���������ɂ���A�����J�I�ȃR���e�N�X�g�Ɋ�肩����Ȃ��A����Ȃ��A�ނ��댩���������Ȃ��Ƃ����p��������h�ʉ����ꂽ�푈�h�ւ̌��łȊo��͉M����B�N���E�h�̈ӎ��ɂ��m���ɕω����萶���͂��߂��ł��낤2011�N�����́h���N�h�Ƃ���A�u�}���`�v���Ń|���t�H�j�b�N�v�ȕ��a�̌`�B�w�C�g�𗽉킵�ė]�肠�郉�u�̌`�B�u�A�t�^�[�E�f�[�g�R�[�X�Ƃ��Ẵt�@���N����n�߂����v�A�܂��ɂ��̎������ܖK�ꂽ���ƂŁADCPRG�̔�������t�@���N�̘A�����A���w����O���[���̂���Ȃ�d�w�����h���Â���ꂽ�A�{���̑��݈Ӌ`�݂����Ȃ��̂������Ă������ȋC������B
�@2008�N�����肩��h�ʂ̐푈�h���N����Ɨ\�����Ă����劲�B�u�푈���O�̏����Փ��v�́u�푈����̏����Փ��v�ցB���������i�v�z�ƂȂ肻���ȃ��[�h���N���b�`���Ȃ�����A�֊��ƌ��ʁA�����Ɯ����̃��^�[���B
-

���C�u�E�A���o���wAlter War In Tokyo�x��Impulse! ���琋�ɓ����B�����ĊJ����1���N���}�����V���f�[�g�R�[�X�̂���܂łƂ��ꂩ��B�劲�E�e�n���E����ɐF�X�Ǝf���Ă܂���܂����E�E�E
-

2008�N6���ɍs��ꂽ�e�n���E���C���^�r���[�̑S7�S�łł��B�_�u�E�Z�N�X�e�b�g�A�}�C���X�A�t�@�b�V����...���̌q�����������x�l�@���Ă݂�ƁE�E�E
-

�y�y��3��ڂ������B�����ŋ߁A���[�J�z���b�N�ɂ���Ȃ锏�Ԃ����������i�H�j�e�n����ɂ��b���f���Ă��܂����E�E�E
-

�w�L���r���w�x����1�N�A�e�n���E�ƃy�y�E�g�������g�E�A�X�J���[���̍ŐV�삪���ɁB�y�y�j��ō��Ɂh�x���A���o���h�A�����Ɋ����E�E�E
-

�wLike Someone In Love�x�A�wGirl Next Door�x�ƃg���I���`�ł̌��삪�������씎�̕Б��̊�B���E�����J���e�b�g��Minami Hiroshi Go There! �Ďn���E�E�E
-

�y�i���h�ē�I �w��ɂ��肢�x��10��8�����瓌���M�����J�I �T���g������^�������I �{��̎剉�A�q�n����ƃv���f���[�T�[ �{��P�s����̑Βk�ł��E�E�E
-

�w�p�r���I���R�����x�̕y�i���h�ē��ēx�A�e�n���E���ɉ��y���˗��I���Ɏ��̈�ԃ|�b�v�Ȑt�������f�扻�E�E�E
-

�A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y�̍ō���ɂ��ėՊE�_�B�}�C���X�E�f�C���B�X�����̑����N�C���e�b�g�ɂ��1967�N���B�c�A�[�̋L�^���A3CD�{DVD�̃{�b�N�X�Z�b�g�ɂĐ��Ɍ��������[�X�E�E�E
-

�}�C���X�E�f�C���B�X�wBitches Brew�x 40���N�L�O�������K�V�[�Ղ������B�����\���C������CD�A�����\���C��DVD����lj��������S���Y����̂䂾���������E�E�E
-

�}�C���X�E�f�C���B�X��1986�N���[�i�[�ڐБ�1�e��i�wTUTU�x���A�{�҃��}�X�^�[�A����ɂ͓��N7���̃j�[�X����������lj�����2���g���ؔՂɂēo��E�E�E
-

���{�ꎚ���t���ƂȂ邱��DVD�́A�V���g�b�N�n�E�[���̖���̏����Ɏ���܂ł̃��n�[�T���ȂǏ����̗l�q�ƁA�{�Ԃ̉��t���i������^�E�E�E
|
|
|
�@�V��DCPRG�́h�a��܂������h�O���[��������ɂނɐ�������A�e�n�W���p�����l�̎������Љ�B
�@�g�b�v�o�b�^�[�́ADCPRG�́u�g�����y�b�g�̉��q�l�v�u���������j�q�v�i©�e�n���j �މƐS���B�C�㎩�q���喩���y���ɍݐЂ��Ă����Ƃ��������ׂ��o���������A�ޑ����2003�N��6�l�g�̃W�����n�W���Y�E�R���{�uurb�v�ɎQ���B2007�N�ɂ́A�}�C���X�ƕ��ьh�����Ă�܂Ȃ��e�n���̓����̐V�o���h�A�_�u�E�Z�N�X�e�b�g�ɉ������������̔O��������A�ȗ����No.1 �g�����y�b�^�[�̖���~�����܂܂ɂ��Ă���B���̊Â����痧������͑z���ł��Ȃ��قnj������R���オ��A�h���u�ŁADCPRG�t�@������A�b�p�[�M�����w�̃n�[�g�𑍂��炢�B������ɂ́A�މƂ������郏���z�[���E�J���e�b�g�A�މƐS�� 4 Piece Band��2nd�A���o���wSector b�x�������[�X���ꂽ�B�v���f���[�X�͂������e���E�e�n���B���������낵�̃|�����Y�~�b�N�E�`���[���uGL/JM�v�ADCPRG��O�ɂ��W���Y�o���h�u�A���t�H������8�v�̎O�֗T�炪�������u�A�g���v�A����ɂ����f�B�E�K�K�uPoker Face�v�̃J���@�[�ȂǁA���Ȃ�o���G�e�B�ɕx�R���|�W�V�������U��߂��Ă���B������̃|�b�v�E�q�b�g��傫�ȃ^�C�����O�Ȃ��ɃJ���@�[���邠����́A���Ƀ}�C���X�������B
 �މƐS�� 4 Piece Band
�މƐS�� 4 Piece Band
�uSector B�v
�@�������Ⴍ�ăs�`�s�`�Ƃ����C�s���B2006�N��BOREDOMS a.k.a V��REDOMS�ɉ������A���݂��R�{����������PARA��A�n粑����A�����a�v�Ƃ�COMBOPIANO�A�E���`�p���Q�ȂǕ��L�������őu�₩�ɈÖ�h���}�[�A��Z�@�b�i���� �ނ˂��݁j�B���^����n�[�h�R�A����A�t�@���N�^�O���[���E�~���[�W�b�N�ւƌ������A�����NO WAVE�ƃe�N�m��ʉ߂��Ȃ���A�������y�ƌ��㉹�y�����Â�B�u������̈ӎ���ϗe�����Ă����悤�ȃr�[�g�̑n�o�v�@���I�ɕ\�o���邱�ƂŁA���̓Ɠ��Ƃ��������Ԍ|�p�����܂�Ă���B���X�̃��R�[�f�B���O�^�c�A�[�E�T�|�[�g�Ɉ������肾���Ȃ̂��[�������A���̎Ⴓ�ɂ��ċe�n�����F���͂��납�A�r���E���Y�E�F���A�A�[�g�E�����[�C�A�����K�G�A�ז쐰�b�A�_������i!�j�Ƃ�������ؓ�ł͂����Ȃ������h�R���Ƌ�����������Ƃ����̂��X�S�C�I
 COMBOPIANO
COMBOPIANO
�uCombopiano�v
�@DCPRG��O�V�[�Y���̒��j��S���ł��낤�����ЂƂ�̐V��A�h�X�̗������u�����W���Y�v�u�f�X�W���Y�v�ŃV�[���ɕ������J���܂���SOIL&PIMP SESSIONS �i�ʓ��g���I�E�v���W�F�N�g�� J.A.M.������j�̃s�A�j�X�g�^�L�[�{�[�f�B�X�g�A��B2003�N�ɉ������o���Ȃ��܂܃t�W���b�N�ɏo������Ƃ���SOIL�̉����́A2000�`01�N�㔼���܂łɃX�v���b�g�E�V���O���w�S�ăr�t�e�L�|�p�A���x 1����������̍�i�ژ^�Ń��C�u�n�E�X��閈�M��������DCPRG�̓O��I�Ȍ����`�Ƌ��ʂ��Ă���B���̏�ƒ،��ɂ��v���Ց̐��́A70s�}�C���X��D�����R�ł���A���b�N�̓a�����V�r�ꂳ�����u�`�b�N�ƃL�[�X�v�̂��̔������C���v��������ɔ]���v���W�F�N�^�[�ɉf���o���Ȃ���E�\�B�ǂ��炪�`�b�N�H �ǂ��炪�L�[�X�H �Ƃ����̂͂��͂�ǂ��ł��悭�A���҂̉ߌ��ȃR���N�e�B�u�E�C���v�����B�[�[�V�������w������Ⰲ��O���قǂ̎h����^���邱�Ƃ��ł���ADCPRG�ɂ����Ă͖������I�b�P�[�Ȃ̂��A�����ƁB
 J.A.M.
J.A.M.
�uJust Another Mind�v
�@�����Ă��Ȃ��݁A���܂�DCPRG�̕��i�ߊ��Ƃ������錋����������̃����o�[�̂ЂƂ�A�،������B�e�n���Ƃ�DCPRG�Ƃقڎ��������āA�����ϑt�V�[�P���X�\�t�g�����Y�������ށA���d�͓I�G���N�g���E�W���Y�E���j�b�g�A�����U���B�k���o�b�n�𗧂��グ�Ă���͍̂L���m���Ă���Ƃ���B���b�v�g�b�v�E�e�N�m�̋S��numb�Ƃ̃R���{������A���g�̃\����i�ɂ�����G�t�F�N�e�B�u��@��|���E�X�C���O�̎��H�Ȃǂ��s�Ȃ�����ŁA�\���E�s�A�m��g���I�`���Ґ��R���{�ł̓A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y�E�s�A�j�X�g���̂��̖̂��͂��A�s�[������ȂǁA�e�n���ɕ��������Ȃ��u�A���r�o�����c�i���ʐ��j�v�����˔����Ă���B
 �����U���B�k���o�b�n
�����U���B�k���o�b�n
�uSweet Metallic�v
�@����������������o�[�B2000�N�����̃A���g�^�\�v���m�T�b�N�X�A�t���[�g�t���Ï㌤���ƁA�p�[�J�b�V��������V���� �i������ ����j�̂ӂ���B�Ï�́A���������������ł�����F�ljp��ONJQ�^ONJO�ɂ�2007�N�܂ŎQ�����A�[���N�㓌���̋ٔ��������̃W���Y�݂̍�����A�T�C���E�F�[�u�A�X�N���b�`�E�m�C�Y�̍i��J�X���܂݂Ȃ���P�C�I�X�ɓf���o�����B2000�N���씎�ip�j�A���J�_���ib�j�A�O�R���ids�j�Ɗ��g���������[�_�[�E�o���h�uBOZO�v�ق��A���c�z���I�[�P�X�g���A�a�J�B�Ƃ̊����Ȃǂł����̍����ŃG���K���g�ȃu���E�����Ƃ��ł���B�d���}�C���X�E�o���h�ɂ������X�e�B�[���E�O���X�}���H �\�j�[�E�t�H�[�`���[���H �͂��܂��Q�C���[�E�o�[�c�H
�@�e�n���Ɠ������̑�V���́A�w����ʂɃo�J�ł����u���_�v�����A�����q���ق�p�[�J�b�V�����E���Y���}�X�^�[�B�I���P�X�^�E�f�E���E���X�̏��ナ�[�_�[�Ƃ��Ă��m���A�E�ތ��1991�N��N.Y.�ֈڏZ���A�T���T�E�̑�䏊�V���K�[�A�e�B�g�E�j�G�x�X�̃o���h�ŃR���K��@���悤�ɂȂ�B�A�����97�N�A����11������Ȃ郊�[�_�[�E�R���{�A�T���T�E�X�C���S�T�𗧂��グ�A07�N�ɂ̓t�W���b�N�ɃT���T�E�o���h�Ƃ��Ă͏��߂Ă̏o�����ʂ����Ă���B���e���݂̂Ȃ炸���E�e�n�̃��Y�����z���������L���v���C�X�^�C���Ɣ������悭���͂̂���T�E���h�́A�G���g�D�[���̂���ɂ��S���������Ƃ��Ă��Ȃ��B�@�@�@
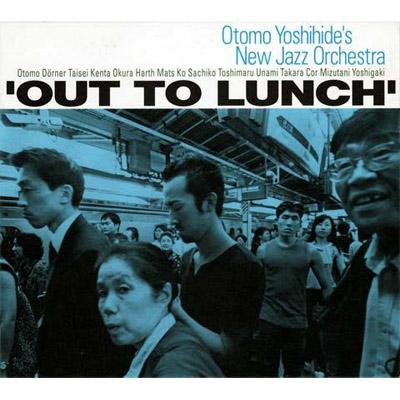 ��F�ljp ONJO
��F�ljp ONJO
�uOut To Lunch�v
 �T���T�X�C���S�T
�T���T�X�C���S�T
�uAqui Se Puede�v
�@�َ�i���Z�I�ȃ����e�B���O�|�b�g��������ɋɂ܂����Ƃ����������ȐV��DCPRG�B���̒��ł���ۈٍʂ���� �h���Ċ��h����������̂��A���N2��20���́u�����W�[�N�t�F���h�v������I�ڌ����ƂȂ����V�����M�^���X�g�A�呺�F���̑��݁B�l�����w���B���^��/�����f�B�b�N�E�w���B���^���E�M�^���X�g�́u�ő����v�Ƃ����̂����̃X�W�ł̂ӂꂱ�݁B�]���āu�U�b�p�E�o���h���X�e�B�[���E���@�C�݂����ɒe���Ă���I�v�i©�e�n���j�Ƃ������m�Ȓ��n�ꏊ��������Ƃ����Ă����̃X�J�E�g�A�Ƃ������ƂɂȂ�B���������̃��^���b�N�ȃM�^���Y�����A���w�����Ƃ����Ӗ��������܂߂āA�ƂĂ��Ȃ�DCPRG�Ƀt�B�b�g���Ă���B�����čI���B�X�s�[�h�������\�����́A�����ȍ��݂≹�̏o������݂����Ȃ��̂��n���p�Ȃ������Ă���B����JAZZ�ł̃X�e�[�W�͂����B�t���ɂȂ����B���f�i���j�̃A���o���E�W���P�b�g��������}�C�N�E�X�^�[�������Ƃ������A����ς�z���N�����Ă��܂��̂����A�u�U�b�p�E�o���h�̃��@�C�v�Ƃ����p���u���ɂ͂��Ȃ�Ȃ��B�X�^�����[�E�N���[�N�����j�[�E�z���C�g��VERTU�����b�`�[�E�R�b�c�F�����Q�����Ă��镗��Ƃ��܂��Ⴄ���E�E�E�������̌d��B
 �呺�F��
�呺�F��
�uEmotions In Motion�v
�@6��6���̌b������L�b�h���[�������B����g���[�h�}�[�N�Ƃ��Ă�������蒅�����A11�{�������̒����Ă��Ȃ����F��12���M�^�[�œo�ꂵ�A�uCatch 22�v�������}�C���X�E�f�C���B�X�wOn The Corner�x�����́uNew York Girl�v�J���@�[��DCPRG�Ƃ܂�������A�[�g�E�����[�C�B�����m�[�`���[�j���O�B�y�_���Ńs�b�`�x���h���Ȃ���A����������ł������������t�@�Y�ݍ��݁A�����Ƒ~���ނ������m�C�Y�������ƎU�炵�āA������ρB���̓��̃X�e�[�W��ڌ������m�l����̃��[���Ȃ̂����E�E�E�܂��v�_���݂͂Â炢���ƁB�����A���ƂȂ��C���[�W�ł����̂́A�u���S���Ȃ����̉�v��S��̂悤�ɂ܂Ƃ����Ȃ���A���܂��`��ȃ{�P���J�}������A�s���c�b�R�~������ꂽ��ƁA�����Q�X�g�炵���ƌ����Q�X�g�炵���A�����[�C�炵���ƌ��������[�C�炵���A���V����q�h�����j�ɂ��������������Ȍ�p�B�Ƃɂ������̐q��ł͂Ȃ����݊��ɂЂ����炷�����������ȁB
�@���Ȃ݂ɂ�����i���j�́A�}�C���X�A�e�n����w�X�X�g�x�A�A�[�g�E�����[�C����{�̃��C���Ō��Ԃ��Ƃ̂ł���M�^���X�g�A�r���[ �g�X�y�[�X�}���h �p�^�[�\�����Q�������A�A���r�V���X�E�����@�[�Y�ɂ��A�E�P�T�E�_�[�W�E�t�@���N�̍Ō�����ɂ��ĉ���B�ɂ������p�ՁI�@�@�@
 Ambitious Lovers
Ambitious Lovers
�uLust�v
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 �@�}�C���X�E�f�C���B�X �@�}�C���X�E�f�C���B�X
On The Corner |
| �@�\�j�[�~���[�W�b�N�@SICP845�@ |
�@70�N��}�C���X�̃����^���e�B�����炩�ɂ��ꂽ����ȃO���[���ƃe�I�E�}�Z���̃e�[�v�E�G�f�B�b�g���A�V���g�b�N�n�E�[���ւ̃G�j�O�}�e�B�b�N�ȐS���Ɠ��藐��Ȃ���A�s���R�ŋC�����̂悢�j�]�ށB�㔼�A�Ȗ��͈قȂ���̂̂��ׂĂ��u�u���b�N�E�T�e���v�̃��@�[�W�����Ⴂ�A���������ꂪ��ڂȂ����t����Ă���Ƃ����ɂ߂Č��㉹�y�ɋ߂����̃e�N�X�g���A�u�t�@���N��E�\�z���������́v�Ƌe�n���͎w�E�B2011�N6��6���b���LIQUIDROOM�����ł́A�u�j���[���[�N�E�K�[���v���A�[�g�E�����[�C�Ƌ��t���Ă���B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 �@���ԃ����e�B�E�p�C�\�� Vol.1 �@���ԃ����e�B�E�p�C�\�� Vol.1 |
| �@�\�j�[�s�N�`���[�Y�G���^�e�C�������g�@OPL07061�@ |
�@1969�N�ɃC�M���XBBC�ŃX�^�[�g�����u���ԃ����e�B�E�p�C�\���v�B�uDCPRG�Ɋւ���ŏ��̊�揑�v�i�w�X�y�C���̉F���H�x���j�ɂ��A�wOn The Corner�x�^���N�Ɠ���1972�N�ɕ������ꂽ�u�l�����͊C�O�J����b�v�i��3�V���[�Y ��2�b�j�̃X�P�b�`�ɑ�\�����p�C�\���Y�̍�������DCPRG�̃R���Z�v�g�Ƃ��ēV�[�I�ɍ̗p�B�u�u���b�N�W���[�N�ƍ��ƊԐ푈���e�[�}�ɂ����w���B�[�t�@���N�v�A�܂�u�����e�B�E�p�C�\���ƃ}�C���X�E�f�C���B�X�̗Z���v��ڎw�����B
|
|
|
|
|
|
|
|
 �@�e�n��� �@�e�n���
�X�X�g |
| �@�\�j�[�~���[�W�b�N�@SRCS9378�@ |
�@�X�e�B�[���E�O���X�}���iss�j�A�f�C���E���[�u�}���iss�j�A�A�C�A�[�g�E�����C���iper�j�A�o���[�E�t�B�i�e�B�ig�j�A�r���[�h�X�y�[�X�}���h�p�^�[�\���ig�j�Ƃ������}�C���X����̐痼���҂����ɁA����ᩐ��itp�j����}���A�wOn The Corner�x�����{���Ƃ���70�N��}�C���X�̍��ׂɍŐڋ߁B1980�N11���A�j���[���[�N�̃u���b�N�����ɂ������ނ̃A�g���G�Ƃ������ׂ��u�T�E���h�E�A�C�f�B�A�E�X�^�W�I�v�Ń��R�[�f�B���O���ꂽ�A�����Ő�[�E�ŐV�s�̃O���[���E�~���[�W�b�N�BDCPRG�́A���^�Ȃ́u�T�[�N���^���C���v�����S�̕��`���S�Č����邱�Ƃ�����̑��R���Z�v�g�Ɍf�����B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 �@�X�^�[�V�b�v�E�g�D���[�p�[�Y �@�X�^�[�V�b�v�E�g�D���[�p�[�Y |
| �@���� �ި��ư ��� �ެ��݁@VWDS04336�@ |
�@���o�[�g�EA�E�n�C�����C������u�F���̐�m�v�����S�f�扻�B�|�[���E�o�[�z�[�x���ē��A���o���ʂ̋����t�B���E�e�B�y�b�g�i�u�W�����V�b�N�E�p�[�N�v�j�Ǝ��g�ݒa�����������ɂ�SF�푈���ҁB�u�푈���̂��̂ł���悤�ȉ��y�v��W�Ԃ���DCPRG�B����ׂ����ɂ�����j���̕��������A�Z�b�N�X���ꎩ�̂��ے��ł��邩�̂悤�ɕ`�ʂ��邱�ƂŁA�u�r�Ԃ�Z�b�N�X�V�[���i������j�ɗ~��Ȃ��甏�芅�т��v�ƋL�q����e�n���̃C���X�p�C�A�Ƃ��Ȃ蓾���B�펞���̗}�����ꂽ���ŌJ��L������Z�b�N�X���A���Ă��������_���X���A�Ƃ������ƁB
|
|
|
|
|
|
|
|
 �@�n���َ̖��^ �@�n���َ̖��^
�R���N�^�[�Y�E�G�f�B�V����
|
| �@�ުȵ� ���ް�� ����ò���ā@GNXF1225�@ |
�@�W���[�t�E�R�����b�h�̏����u�ł̉��v������ɁA����̕�����x�g�i���푈�Ɉڂ��|�Ă����A�t�����V�X�E�t�H�[�h�E�R�b�|���ēɂ��1979�N����̐푈�f��B����DCPRG���\����|�����Y���E�`���[���uPlaymate At Hanoi�v�͂��납�A���������̃o���h�S�̂̃R���Z�v�g�́A���̉f��́u�x�g�i���̃W�����O�����n�Ƀv���C���C�g���Ԗ�ɗ���v�Ƃ����V�[���ł��̖}�����܂��Ȃ���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 �@�A���[�E�~���[�W�b�N �@�A���[�E�~���[�W�b�N |
| �@�A�~���[�Y�\�t�g�@ASBY3395�@ |
�@�S�_�[�����A�u9�11�v�Ȍ�̍�����Ⴂ����ւ̗D�����፷���������āA�u�f��v�Ɓu�����v�����āu���E�v���m�肷��B�삵���푈�f���̃����^�[�W���ɂ���10���Ԃ̑�1���u�n���ҁv�B�T���G���H��ɁA�f��ēS�_�[���i�S�_�[�����g�������Ă���j�ƁA�ނ̍u�`���ɂ������q�w���I���K�Ƃ̍��̌�����`����2���u�����i��ߊE�j�ҁv�B��2���ŏ}���Ɏ������I���K���A�A�����J���Ɏ��ꂽ����̂����炬�������3���u�V���ҁv����Ȃ�B2005�N�̌��J���ɂ́A�R�^���Ƃ̃g�[�N�V���[�̒��ŁA�S�_�[���f��̘^���S���t�����\���E�~���W�[�ւ̐[���X�|�Ԃ���I�ɂ��Ă����e�n���B2007�N�́wFranz Kafka's America�x�́A���̖��̂Ƃ���J�t�J�́u�A�����J�v����^�C�g�������p�������ŁA�u�S�_�[������w�̃[�~�ŁA�����ɐl�ގj�͐푈�̗��j���B�Ƃ������b�����鎞�ɁA�w���B�Ɉꖇ�̃��m�N���ʐ^��������E�E�E�v�Ƃ��������V�[���ɁA���z�̃g���K�[���������������B
|
|
|
|
|
|
|
|
 �@�t�����c�E�J�t�J �@�t�����c�E�J�t�J
�A�����J |
| �@�p�쏑�X�@9784042083054�@ |
�@�wFranz Kafka's America�x�̃^�C�g���R���ƂȂ����t�����c�E�J�t�J�̖����̒��ҏ����i���̏����̑����͐��O�͔��\���ꂸ�A�����̌��e��F�l�̃}�b�N�X�E�u���[�g���Ҏ[���ďo�ł��ꂽ���̂��قƂ�ǂ��Ƃ����B�u�A�����J�v�����̌���́u���H�ҁv�ƂȂ�j�B�J�t�J�A�e�n�����҂ɋ��ʂ���u�K�ꂽ���Ƃ́i�قځj�Ȃ����A�Ƃɂ����C������ŁA���Ȃ𓊉e�������Ȃ�A����ȃA�����J�́����\���ɑ��ĕ��\���v�Ƃ����j�i�̖ϑz�͂��t�@���N�ӓI�ɒ��ۉ��B�����āA�u�ϑz�̃A�����J�A�ϑz�̐푈�v�Ƃ���DCPRG�̊�{�I�ȍ\���́A�����ŏ��������B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 �@�J�[���n�C���c�E�V���g�b�N�n�E�[�� �@�J�[���n�C���c�E�V���g�b�N�n�E�[��
Gruppen |
| �@DG�@4477612 �@ |
�@�}�C���X��DCPRG����̓I�ȃC���X�s���[�V�����̌�������ɏo���Ȃ��Ƃ���ɁA���ۓI�Ȃ��̂̏ے��Ƃ��ẴV���g�b�N�n�E�[���̐��݂Ƃ������̂�����̂ł́H ����҂́w�O���b�y���x�������A�܂�����҂́w�R���^�N�e�x��w�w���R�v�^�[�E�J���e�b�g�x��������B�w���V�[�ȋq�ϐ����ʂ������ɋ��C�ɓ����������g�E�������������c���Ƃ����_�ŁA�ǂ�����ނ�Ɍ��ʓI�ɗ^�����e���܂���Q�͐r��B�e�n���̏��сu�~�X�^�[�h�[�i�c�̃V���g�b�N�n�E�[���v�ł̑N�₩�ȁh�ϑz�h���B
|
|
|
|
|
|
|
|
 �@�W�����E�]�[�� �@�W�����E�]�[��
Cobra |
| �@Hatology�@HATO580�@ |
�@�m���}���f�B�[�㗤�����V���~���C�g�������E�H�[�E�Q�[���̗v�f�������ꂽ�������t�̃V�X�e���i�A���o���wCOBRA�x��1985�`86�N�^���j�ŁA10�l�O��̉��t�҂Ɏw����^����h�v�����v�^�[�h����l���݂���B���������_�ł́A���̏����ɂ�����DCPRG�����ۂɍł��L���Ȕ�r�ƍ���i�Ƃ���Ă������A�w�X�y�C���̉F���H�x�́uDCPRG�Ɋւ����Ԗڂ̊�揑�E�E�E�v���50%�v�ł́A�u�w�R�u���x�́A�㉉���J��Ԃ����ɁA�{�������Ă����w�푈�E��ꐫ�x�͎����E�E�E�v�ƁA15�N�Ƃ������ԍ��߂邱�Ƃւ̕s���������܂߂āA������DCPRG���~�����u�펞���v�Ƃ͎��Ĕ�Ȃ邱�Ƃ��e�n�����炪�f�I���Ă���B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 �@�t�����N�E�U�b�p �@�t�����N�E�U�b�p
Man From Utopia |
| �@�r�f�I�A�[�c �~���[�W�b�N�@VACK5224�@ |
�@�q40����ɂ́u�n�G�@�n�G�@�J�J�J�@�U�b�p�b�p�v�ł��Ȃ��݂́A���C�u�ƃX�^�W�I�^�����~�b�N�X���ꂽ1982�N���\�̃A���o���B�U�b�p�y�c�ɖ��ڏ� �h�̕��W�h�Ƃ��ē��c�����X�e�B�[���E���@�C���A�e���̉̂ɃM�^�[�̃��j�]��������Ƃ�������Ɓi�I�[���@�[�_�u�H�j������Ă̂����u�댯���炯�̃L�b�`���v�Ɓu�t�F�`�V�X�g�̃}���]�N�����v�B�呺�F����i�����V��DCPRG�L�b�Y�ɂ̓o�J�E�P�K���H ���̔��ʁA�l�X�ȁh����h���d�|�����Ă���Ƃ����_�ŁA�U�b�p����ɂ͂܂����������ēK������1���BCD���ɍۂ��Č��Ճ��R�[�h����ȏ��̑啝�ȕύX�����������Ƃ��d�v�ȃU�b�p�C�Y���̂ЂƂB
|
|
|
|
|
|
Modern JazzLatest Items / Tickets Information

