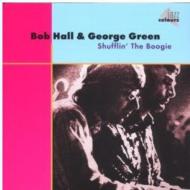�@�C�M���X�̃u�M�E�M�^���b�N�����[���E�s�A�j�X�g�A�x���E�E�H�[�^�[�Y�̍ŐV�A���o���́A���[�����O�E�X�g�[���Y�̏����s�A�j�X�g�ł������A�h�X�`���h���ƃC�A���E�X�`�����[�g�ɕ�����g���r���[�g�E�A���o���B�r���E���C�}�����悻18�N�Ԃ�́h���A��h�������������[�����O�E�X�g�[���Y�̃����o�[���͂��߁A�W���[���Y�E�z�����h�A�x���̏]�o���ł�����P.J.�n�[���F�C�炪�Q�����A�X�`���ւ̌h�ӂƈ���Ђ��Ђ��Ɠ`��肭��v���C�����Ă����B�p�����b�N�E�V�[�����\����̑�Ȃ�~���[�W�V�����B�A�����ăV�[����e����x���Ă����ʁX�̗͂��{��wBoogie 4 Stu�x�́A�u���e�B�b�V���E���b�N�̖L���Ȃ鉜�[���������������i�Ɏd�オ���Ă���B
�@
|
|
|
 �@Ben Waters �uBoogie 4 Stu�v �@Ben Waters �uBoogie 4 Stu�v |
| �@Verita Note�@VQCD10270�@2011�N4��6�������@ |
�@�I���W�i���̃u�b�N���b�g�ɉ����A���{�����^�x���E�E�H�[�^�[�Y�ŐV�C���^�r���[�^�I���W�i���̎��^�Ζ���f�ڂ����u�b�N���b�g���B
�@���O�̃X�`���������Ă�܂Ȃ������u�M�E�M�A�u���[�X�AR&B�𒆐S�ɁA���C�E�`���[���Y�A�r�b�O�E���C�V�I�A�W�~�[�E�����V�[�A�r�b�O�E�W���[�E�^�[�i�[�ȂǒʍD�݂̑I�ȂŖ����Ă����g���r���[�g�E�A���o���B�~�b�N�A�L�[�X�A���j�[�A�`���[���[�A�r���E���C�}���i�I�j�̃X�g�[���Y�����͂��߁A�X�N�B�[�Y�̈���ŃC�M���X�ł�TV�ԑg�z�X�g�Ƃ��Đl�C�̃W���[���Y�E�z�����h�A�x���̏]�o���ł�����P.J.�n�[���F�C�炪�Q���B�X�`���ւ̌h�ӂƈ���Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă���v���C�����Ă����B�������SHM-CD�Ղɂ́A�{�[�i�X�E�g���b�N2�Ȃ����^�B�A�[�g���[�N�́A�r�[�g���Y�w�T�[�W�F���g�E�y�p�[�Y�`�x�̃W���P�b�g�ł��Ȃ��݂̃T�[�E�s�[�^�[�E�u���C�N����|���Ă���B
|
|

�s���^�ȁt
01. Boogie Woogie Stomp
02. Roomin House Boogie
03. Worried Life Blues
04. Boogie For Stu
05. Make Me A Pallet
06. Midnight Blues
07. Lonely Avenue
08. Watchin The River Flow
09. Roll Em' Pete
10. Suitcase Blues
11. Bring It On Home To Me
12. Kidney Stew�i���{�Ճ{�[�i�X�E�g���b�N�j
13. Chicago Calling�i���{�Ճ{�[�i�X�E�g���b�N�j
�@�u������X�`���ɕ������i�v�Ƒ肵���x���E�E�H�[�^�[�Y�̍ŐV�A���o���wBoogie 4 Stu�x�B���␢�E���Ƀg���r���[�g�E�A���o���Ƃ������̂͐��̐��قǑ��݂��邪�A����قǂ܂łɁA���̐l�܂��͌̐l�ƂȂ������̐l�̐S�ӋC�ɐ[���h�ӂ������Ă���g���r���[�g��i�͑��ɗ�����Ȃ��A�����ɂ����������B�܂��A�C�A���E�X�`�����[�g�Ƃ����l�Ԃ������ɑ����̒��ԂɈ�����Ă������Ƃ������Ƃ��B
�@�A���o���Ɍf�ڂ���Ă����x���E�E�H�[�^�[�Y�̃C���^�r���[���܂ޔZ���ȃ��C�i�[�m�[�c�����ǂ݂���������A�{�쐧��Ɏ���o�܂₻�̃R���Z�v�g�Ȃǂ���Ɏ��悤�ɔ���킯�Ȃ̂����A�����ł̓l�^�o���ɂȂ�Ȃ����x�ɂ����wBoogie 4 Stu�x�̉���������B
�@�C�M���X�̓h�[�Z�b�g�B�o�g���x���E�E�H�[�^�[�Y�́A37�̃u�M�E�M�^���b�N�����[���E�s�A�j�X�g�B �h�m��l���m��h�Ƃ�������������������������������Ȃ��B�l���݂̃��b�N�E�t�@���ł���A���P�b�g 88�ւ̎Q���A�܂��́A�W���[���Y�E�z�����h���`���[���[�E���b�c�̃\���E�v���W�F�N�g�E�o���h�ł̃v���C�ł��̖���m��Ɏ��邩������Ȃ����A�{���C�M���X�ɂ�����m���x�Ɋr�ׂ�܂��܂����{�ł� �h�m��l���m��h ���݂Ƃ����Ƃ��낾�낤�B�������A���̎��͂͒N�����F�߂�Ƃ���ŁA�`���b�N�E�x���[�A�W�F���[�E���[�E���C�X�A���C�E�f�C���B�X�A�f���B�b�h�E�M�����A�A�V���[���[�E�o�b�V�[�Ƃ������g�b�v�E�A�[�e�B�X�g����������ȐM�����A�X�e�[�W�ɃX�^�W�I�E���R�[�f�B���O�Ɉ������肾���̖����𑗂��Ă���B���[�_�[�E�A���o�������݂܂ł�3��𐔂��A2008�N�ɂ͗����������s�Ȃ��Ă���B
�@����ȃx�������g�̃s�A�j�Y���A�v���C�X�^�C���̌��_�Ƃ��ď�ɑ������ł����̂��A�X�`�������C�A���E�X�`�����[�g�Ȃ̂ł���B�s�A�m��e�������Ƃ��������Փ��ɋ��ꂽ�̂�9�̂Ƃ��B�����v�w�̌���20���N�p�[�e�B�Ŏ��ɂ����X�E�B���M�[�ȃX�`���̃v���C�́A�����ȏ��N�̃R�R����^���c�ő������B���̓����͂������A�X�`���� �h6�l�ڂ̃X�g�[���Y�h �ƌĂ��悤�ȓ`���I�Ȑl���Ƃ������ƂȂǂ͒m��R���Ȃ��A�ɉ��ɂ܂�Ȃ��u�u�M�E�M�E�s�A�m�v�̂������悳��P�������ɋ����Ă��ꂽ �h���y�̐搶�h �Ƃ��āA�x���̓X�`���̃v���C�X�^�C�������悤���܂˂Ō������A�܂��ނ̏������Ă����s�A�j�X�g�̃r�f�I�R���N�V�����ɂ������ɂȂ��Ă������B�X�`���Ƃ̏o���������_�ɁA10��̍��ɂ́A�t�@�b�c�E�h�~�m�A�p�C���g�b�v�E�X�~�X�A�A���o�[�g�E�A�����Y�A�s�[�g�E�W�����\���A�W�~�[�E�����V�[�A�v���t�F�b�T�[�E�����O�w�A�[�Ƃ��������m�����̉��t���@�艺�����킢�A�S�����s�������B
�@�x�����v���E�v���C���[�Ƃ��Ċ������n�߂鍠�ɂ́A���łɃX�`���͂��̐��������Ă������߁A���ے��ړI�ȃv���C�̎�قǂ��邱�Ƃ͂Ȃ��������������A�u���O�̃X�`���ƃv���C���Ă����l�X�Ƌ������邱�ƂŁA�ނ̉��y���͖l�̐g�̂ɐ��݂���ł���v�ƃx���͌��B�܂��A�T���߂ʼnǖقȃX�`���̐��i�͂��̃v���C�X�^�C���ɂ����ꂽ���A�K�v�Œ���̉����ōő�̌��ʂ�����܂��Ɂh�K�E�d���l�h�I���t�́A�X�g�[���Y���͂��ߐ��X�̖����̉��䍜���x���Ă��邱�Ƃ��M���m��B�����ăe�N�j�b�N�ɒ����Ă����킯�ł͂Ȃ����A�X�`���ɂ����e���o���Ȃ������X�E�B���O���ƁA�R�N�̂���t�B�[�����O�Ƃ������̂��m���ɂ���B�X�`���̃X�^�C�����u�Ɠ��v�ƕ\������x���́A����ȗB�ꖳ��̃u�M�E�M�E�X�^�C�����p�����Ȃ���A�{���̃��b�N�����[���ƃu���[�X���������S�L�Q���Ŏ������閂�@���E�ւƉ�X��U���Ă����B
�@���X���̃A���o���́A�x�����g�ɂ��\���E�g���r���[�g�Ƃ��Ă̐������悵�Ă������������A�`���[���[�E���b�c�A�f�C���E�O���[���A�E�B���[�E�K�[�l�b�g�A�h���E�E�F���[�A�W���[���Y�E�z�����h�Ƃ��������m�̖ʁX�����X�ɎQ���������������Ƃ���ɁA�v���f���[�T�[�Ƃ����O�����E�W�����Y�A�]�o���ɂ�����P.J. �n�[���B�[�A����ɂ́A���j�[�E�E�b�h�A�~�b�N�E�W���K�[�A�L�[�X�E���`���[�Y�A�����ċ������ƂȂ���A�r���E���C�}���܂ł����{��ւ̎Q����\���o�Ă����̂ł���B�x���̖{�v���W�F�N�g�ɂ�����M�ӂ����邱�ƂȂ���A�C�A���E�X�`�����[�g�Ƃ����s�A�j�X�g�������ɑ����̓��Ǝ҂�������M������A�܂��A�ЂƂ�̐l�ԂƂ��Ĉ�����Ă�������@���ɕ����G�s�\�[�h�ƌ����邾�낤�B
�@�Ō�̎Q���I�t�@�[�����r���E���C�}���́A�����m�̂Ƃ���1992�N�ɃX�g�[���Y��E�ނ��Ă���g�Ȃ̂����A�u�X�`���̂��߂Ȃ�v�Ƃ����S�ӋC�ЂƂŁA�s��3�Ȃɂ����ăx�[�X�����t�B�S�ĕʘ^��ƂȂ���̂́A�{�u�E�f�B�����́uWatchin The River Flow�v�ɂ́A�wSteel Wheels�x���\��͖ڂɂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����� �h�P���������������h �����̃��C���i�b�v���N���W�b�g����A���̃X�g�[���Y�E�����o�[��������̍����ɕ�������t����҂͒N�ЂƂ�Ƃ��Ă��Ȃ������������B
�@�~�[�h�E���N�X����C�X�A�s�[�g��W�����\���ƕ��ԃu�M�E�M�E�s�A�m�́u3�勐���v�Ƃ��Ēm�����A���o�[�g�E�A�����Y�uBoogie Woogie Stomp�v�̓Ɖ��Ŗ����J���A��A�́������ǂ�u���[�X���Ől�C�����G�C���X�E�~���o�[���́uRoomin House Boogie�v�Ƒ����B�u�C�A���������Ƃ��C�ɓ���̂͂��v�Ƃ������_����x���ɂ���đI�є����ꂽ�J���@�[�Ȃ����S�����A�x���ƃz�����h�̘A�e�ɂ��uBoogie For Stu�v�Ƃ��������Ԃ�S�L�Q���Ńn�b�s�[�ȃI���W�i���E�g���r���[�g�Ȃ����^����Ă���B
�@�X�g�[���Y�E�t�@���ł���Ζ����Ȃ��uWatchin The River Flow�v��A�����j���[�E�o�[�o���A���Y���s�ł��f���I��I���ꂽ�r�b�O�E���C�V�I�́uWorried Life Blues�v�i�u�F�B�݂͂�Ȏ�����u���čs���Ă��܂����v�Ƃ����̎����L�[�X���S�����̃V�j�J���Ԃ�E�E�E�j���n�C���C�g�ɋ�����̂��낤���A�uRoll Em' Pete�v�̃L���̗ǂ��ɂ͓G���܂��B�X�`���̌Â�����̗F�l�ł���w�~�b�V���E�}�b�N�X�E�F�����V���K�[�߂����̋Ȃ́A�r�b�O�E�W���[�E�^�[�i�[�Ƒ��_�s�A�j�X�g�ł������s�[�g�E�W�����\���ɂ��j�������u�M�E�M�ÓT�B�W�����v�E�u���[�X���W���C�����n�E�X�E�����g�E�p�[�e�B�̔M���̒��ňꏏ�����ɂȂ��Ė����̉��������������B�V��j�������������Ŋ��т������ɁB�u�����łȂ�������I�v�ƓV���̃X�`�����v�킸�w�p�b�`���B
�@�{�҂̃��X�g�ɂ́A�X�`���̍ݐЂ��Ă������P�b�g 88�ɂ��1984�N�����g���[�E�W���Y�E�t�F�X�e�B���@���o�����̖����\���C�������uBring It On Home To Me�v�A����ɂ͓��{�Ճ{�[�i�X�E�g���b�N�Ƃ��ē��t�F�X�E���C����������uChicago Calling�v�ƁA�x�����̂��uKidney Stew�v�����^����Ă���A��������������Ȃ��B
�@�x�����͂��߂Ƃ��Ė{��i�ɎQ�������~���[�W�V�����S���̒]�炪�e�Ղɑz���ł���B�X�`���̎v���o�b�ɉԂ��炩���Ȃ���A�e���u�M�E�M�Ƀu���[�X�ɐ�ۂ�ł����́A�h6�l�ڂ̃X�g�[���Y�h���Ȃ�ėL��̂Ȍ`�e�����荞�ޗ]�n�Ȃǂ܂�łȂ��قǂɐ���オ��B�c�Ȃ����r�W�l�X��W���[�i���Y���Ƃ͂܂������W�̂Ȃ��Ƃ���Ŋ����̂������y�͑t�ł��A�����Ƀs���A�ȃ~���[�W�V�����E�V�b�v�͈�܂��B�X�`���������A�܂��X�`���Ɉ����ꂽ�l�����́A���₻�ꂼ��̗���͈Ⴆ�ǂ��̂��Ƃ��悭�S���Ȃ���݂����̂������A�����܂�������̍K���҂��Ǝv���B
�ǐL�F����3��9���ɂ́A�{���wBoogie 4 Stu�x�̔����L�O���C�����A�����h���̏�����A���o�T�h�[���E�V�A�^�[�ōs�Ȃ��A�~�b�N�A�L�[�X�AP.J.�������A���o���̎�v�Q���w�ɉ����A�~�b�N�E�e�C���[�A�~�b�N�E�n�b�N�l���A�V�F�C�L���E�X�e�B�[�����X�Ƃ������ʁX���삯�����Ƃ����B�I�n�A�b�g�z�[���ȕ��͋C�ŃV���E���i�ޒ��A�F��l���C�A���E�X�`�����[�g�Ƃ����̑�Ȃ�s�A�j�X�g�ɑz����y�����B
|
|
�s�p�[�\�i���t
�x���E�E�H�[�^�[�Y �F
�s�A�m�iM-1,2,3,4,6,7,8,9,10,12�j�^�n�����h�E�I���K�� �iM-5,7�j�^���H�[�J���iM-2,12�j/�o�b�L���O�E���H�[�J�� �iM-7�j
�~�b�N�E�W���K�[�F
���H�[�J���^�n�[���j�J�iM-8�j
�L�[�X�E���`���[�Y�F
�M�^�[�iM-2,8�j�^���H�[�J���iM-3�j
���j�[�E�E�b�h�F
�M�^�[�iM-3,8�j�^���H�[�J���iM-3�j
�`���[���[�E���b�c�F
�h�����X�iM-3,4,5,6,8,9,12�j
�r���E���C�}���F
�x�[�X�iM-2,8,9�j
�W���[���Y�E�z�����h�F
�n�����h�E�I���K���iM-3,8�j�^�s�A�m�iM-4,5,6,9�j�^���H�[�J���iM-5�j�^�M�^�[�iM-12�j
PJ�n�[���F�C�F
���H�[�J���^�o�b�L���O�E���H�[�J���^�T�b�N�X�iM-7�j
�A�f�B�E�~�����[�h�F
�h�����X�iM-2�j
�f���N�E�i�b�V���F
�T�b�N�X�iM-2)
�N���C���E�A�V�����[�F
�T�b�N�X�iM-2�j
�f�C���E�O���[���F
�E�b�h�E�x�[�X�iM-3,4,5,12)
�E�B���[�E�K�[�l�b�g�F
�T�b�N�X�iM-3,4,5,8,9,11,12,13�j
�h���E�E�F���[�F
�T�b�N�X�iM-3,4,5,8,9,12�j
�A���b�N�X�E�K�[�l�b�g�F
�o���g���E�T�b�N�X�iM-5,8,12�j
�g���E�E�H�[�^�[�Y�F
�A���g�E�T�b�N�X�iM-8�j
�f�C���E�X�E�B�t�g�F
�^���o�����iM-8�j
�w�C�~�b�V���E�}�b�N�X�E�F���F
���H�[�J���iM-9�j
�e���[�E�e�C���[�F
�M�^�[�iM-9�j
�C�A���E�X�`�����[�g�F
�s�A�m�iM-11,13�j
���W���[�E�T�b�g���F
���H�[�J���^�x�[�X�iM-11,13�j
�W�~�[�E���V���F
�M�^�[�iM-11,13�j
�N���C���E�^�b�J�[�F
�h�����X�iM-11,13�j
�I���t�E���@�X�F
�T�b�N�X�iM-11,13�j
�}�C�N�E�z�C�F
�g�����{�[���iM-11,13�j
�W�����E�s�J�[�h�F
�g�����{�[���iM-11,13�j
|
|
|
|
|

-

�u��ɖړI�������čs������l�������B���y�ɊW���鎖�ł��낤���Ȃ��낤����Ɍ��߂�ꂽ���[���ɂ̂��Ƃ莲���Ԃꂸ�ɕ�����i�߂Ă����B�l�炪�ǂ�ȂɈӌ����悤����ɋȂ��鎖�͂Ȃ�������v
-

�u�C�A���E�X�`�����[�g�́A������V���[�r�W�l�X�̉₩������͂�������Ă�����B �w����Ȏ��m�邩�I �������̓u���[�X��邾�������x���Ă���Ȋ������v
-

�u�X�`���͊ԈႢ�Ȃ��X�g�[���Y�̈����������B�ނ����Ȃ���o���h���̑����ĂȂ�������Ȃ����ȁH �ނ݂����Ȑl���K�v�������Ǝv����B�X�`�����X�g�[���Y�ɂ�����펯�������B�ނ̂������Ńo���h�͒n�ɑ������Ă���v
-

�u�`���[���[���h���}�[�Ƃ��Č}�������̂ɐs�͂��Ă��ꂽ�̂��X�`�����B���������Ӗ��ŃX�g�[���Y�̓X�`���̃o���h�������B�ނ���������l��l��I��ł��ꂽ�v
-

�u�X�`�����炵����A�������͎����ꂷ���������D�_��������Ȃ��Ȃ��ȁB�܁A���̒ʂ�Ȃ��ǂˁv
-

�u�F���ނ��ǂꂾ�������Ă��������A�ގ��g�m���Ă��Ă��ꂽ�����肤��v
-

�u�ނ̉e�������ł��������B�L�[�X�H���w���������z���ɂ��O��������Ă��x���ĂˁB���t�łǂ��\�����悤���A���ł��ނɋ����e������A�ނ̉��y������Ă�̂��v
|
|
�X�`���A���O�B��ƂȂ郊�[�_�[�E�A���o��
�@
|
|
 �@Rocket 88 �uRocket 88�v �@Rocket 88 �uRocket 88�v |
| �@Wounded Bird�@WOU9293�@2008�N11��25������ |
�@�u�u�M�E�M���a50���N�v�Ő���オ��1979�N�ɁA�v���f���[�T�[�߂��C�A���E�X�`�����[�g�ip�j�A�`���[���[�E���b�c�ids�j�A�A���N�V�X�E�R�[�i�[�ig,vo�j�A�W���b�N�E�u���[�X�ib,vo�j��ɂ���đg�t���ꂽ�v���W�F�N�g�E�o���h�����P�b�g 88�B���N11������h�C�c�E�c�A�[���s�Ȃ��A���̂Ƃ��̃n�m�[���@�[�uRotation Club�v�ɂ����郉�C�������𒆐S�ɕҏW���ꂽ�A���o�����A81�N���\�̖{��B�u�M�E�M�E�s�A�m�̎n�c�s�[�g�E�W�����X���́uRocket 88 Boogie�v�i���̌�W���b�L�[�E�u�����X�g���A�r���E�փC���[���uRocket 88�v�Ƃ��ăJ���@�[�j�ɗR������v���W�F�N�g���ǂ���A�u�M�E�M�`�o�����n�E�X�A�u���[�X�AR&B�A�W�����v�A�W���C���A�W���Y�̃N���V�b�N�����p�[�g���[�̒��S���߂Ă����B���Ȃ݂ɁA�X�`���̏����[�_�[���`�Ȃ́A���ȃO���[�v�̃��C�����[�_�[�Y�𗦂���1966�N�Ƀ����h��IBC�X�^�W�I�Ř^�����ꂽ�uStu Ball�v�Ƃ����C���X�g�E�i���o�[�B�v���f���[�X����|���Ă���r���E���C�}���ƃX�`���̋���ŁA�L�[�X�A�O�����E�W�����Y�i�G���W�j�A�j���Q�����Ă���B
|
|
�uRocket 88�v�����O��̃u�M�E�M�������^
�@
|
|
 �@Bob Hall / George Green �uShufflin' The Boogie�v �@Bob Hall / George Green �uShufflin' The Boogie�v |
| �@Jazz Colours�@8747482�@1999�N8��28������ |
�@��f�v���W�F�N�g�����̂��������ƂȂ����A�p���u���[�X�E�s�A�j�X�g�̃{�u�E�z�[���ƃW���[�W�E�O���[���ɂ��1978�N�̃u�M�E�M�E���C���E�A���o���B2�l�̂ق��ɃX�`���A�`���[���[�A�R�����E�X�~�X�炪�Q�����A���P�b�g 88�ւ̕z���قڕ~����Ă���B��������uRocket 88�v���I�[�v�j���O�ȂƂ��Ĕ�I����Ă���B
|
|
�h�������h �X�`���̑f���炵���d���̐��X
�@�������ɁA�j�b�L�[�E�z�v�L���X�Ɗr�ׂ��Ă��܂��Ε��������_�����X���邾�낤�B�������A����͓����u�M�E�M���o���Ƃ���s�A�j�X�g�Ƃ��Ă̗D�̂ł͂Ȃ��A�����܂ŘI�o�ʂɂ�����召�ł�������A�o���̉₩���ɋ�����́B����60�N�㔼����70�N�㏉���̑S�����ɂ��������[�����O�E�X�g�[���Y�̃Z�b�V�����E�s�A�j�X�g�Ƃ��Ă̍����ˎ~�߂��z�v�L���X�̖����͗]�肠����̂ŁA����͂܂��Ɂu�����E�쑺��r�v��낵���́u�Ђ܂��ƌ������v�̃R���g���X�g��z�N������B��������̃��b�N�E�t�@���ɂƂ��Ă��C�A���E�X�`�����[�g���Ƃ����̂́A�E�l�C���ł͂��邪�A�e�������Ђ�����ƘȂނ悤�ȑ��݂Ƃ��Ă����炭�͋L������Ă����̂ł͂Ȃ����낤���H �Ǝא������X�B�����A���̎����i68�N�ȍ~�j�̃X�`���͈ړ����̃X�^�W�I�E�g���b�N�����[�����O�E�X�g�[���Y�E���[�r���E���j�b�g�̊Ǘ�����щ^�]����������Ă������Ƃ�����A���C���E�s�A�j�X�g�Ƃ��ĕ\����ɗ����Ƃ͂����Ă��A���ۂ̃X�^�W�I��Ƃɂ�����X�g�[���Y�E�T�E���h�ւ̍v���Ƃ����_�ł́A�z�v�L���X�ɂ����炩�̎^�����Ă��v�����Ȃ��Ƃ���͂�������������Ȃ��B
�@�܂��A�u�M�E�M��u���[�X�A�`���b�N�E�x���[�E�X�^�C���̃��b�N�����[������ȂɈ����A���������X�^�C���ӂƂ��Ă����X�`���́A����̕ϑJ�ƂƂ��Ƀo���h�����߂�T�E���h�Ƃ������̂ɏ_��ɑΉ�����Ȃ������������������̂��낤�B�wTheir Satanic Majesties Request�x�Ŗ͍������T�C�P�Ƃ̐܂荇���A����ɂ��wLet It Bleed�x���wBeggars Banquet�x�ŃA�����J�암�̃X�����v�E�~���[�W�b�N�ɋ����Ă����ߒ��ɂ����āA�X�`���̂��قǗZ�ʂ̗����Ȃ��I�[���h�X�N�[���ȃs�A�m�E�X�^�C�������ł̓t�H���[������Ȃ������Ƃ������̂����X�o�Ă����Ƃ������Ƃ��B�������ꂽ���쎩���^�v���C���[�̑��ʂ��������킹�A�uShe's A Rainbow�v�A�uJumpin' Jack Flash�v�A�uSympathy For the Devil�v�A�uSister Morphine�v�A�uLoving Cup�v�A�uAngie�v�E�E�E�V�����I�c�ȃL�[�{�[�h�����Ȃ���A�ǂ�ȃX�^�C������p�ɒe�����Ȃ���z�v�L���X���o���h���d�p����̂͂���������O�̗��ꂾ������������Ȃ��B
�@1938�N�A�X�R�b�g�����h�ɐ��܂ꂽ�A�h�X�`���h���ƃC�A���E�A���h�����[�E���o�[�g�E�X�`�����[�g�B62�N�����A�u���C�A���E�W���[���Y�ƃo���h��g��ł����X�`���́A�o�����肾�����L�[�X�ƃ��C�����ƂȂ����p�u�ŏo�����ӋC�����B���łɃ~�b�N�ƃo���h��g��ł����L�[�X�̗U���ɂ��A4�l�͈ꏏ�ɉ��t���邱�Ƃ����ӂ��A �hRollin' Stones�h ���a�������B�f�r���[�O�A�X�g�[���Y�̕�̂Ƃ������邱�̃o���h�̒��ɂ����Ă��A�ŔN���̃X�`���͎Ⴓ�䂦�ɔ��ڂ������~�b�N�A�L�[�X�A�u���C�A�����ЂƂɂ܂Ƃ߁A����Ƃ��͎d���̒����Ȃǂ̖�ڂ������ďo�Ă����Ƃ����B�������ăX�g�[���Y�ŏ����̐��������o�[�Ƃ��čݐЂ��Ă������̂́A����}�l�[�W���[�A�A���h�����[�E�I�[���_���́u�o���h��6�l�͑�������v�u�炪�C�J���v�Ƃ���������ӌ��ɂ����ق������n����A���̌�̓��R�[�f�B���O��c�A�[�̃T�|�[�g�E�����o�[�A�܂��͎��݂̃��[�h�E�}�l�[�W���[�i���[�f�B�[�j�Ƃ��������h�����h�Ƃ��Ă̗���ŃX�g�[���Y�̊������x���Ă������Ƃ͂悭�m���Ă���Ƃ��낾�낤�B
�@�h6�l�ڂ̃X�g�[���Y�h �Ƃ́A���R�X�`�����g�{�ӂƂ���Ƃ���ł͂Ȃ��������낤���A��������فX�ƃo���h�̂��߂ɐg�����p�ɑ��ĕt����ꂽ���̌`�e�́A�z�v�L���X���W���b�N�E�j�b�`�F�͂������A�r���[�E�v���X�g���A�`���b�N�E�����F�[���Ɏ�����̃X�g�[���Y�E�s�A�m�}���ɂ͌����ĕt�����Ƃ̂Ȃ��������Ȃ�̍��ł�����A�j���A���X�I�ɂ� �h���_�ēh �̂悤�ȞB�������c���Ȃ�����A�X�`���̑��݂��̂��̂��o���h�ɂǂ�قǑ傫�Ȍ��т��c���������M���m�邱�Ƃ͂ł��邾�낤�B
�@1985�N12���ɂ��̐����������X�`�����ÂсA���N���\���ꂽ�wDirty Work�x�ɂ́A30�b�قǂ̃V�[�N���b�g�E�g���b�N�Ƃ��ăX�`���̃\���E�s�A�m�ɂ��uKey To The Highway�v�����^����A�܂�89�N�̃��b�N���E���[���E�z�[���E�I�u�E�t�F�C���̎�͎��Ń~�b�N����������t�ɂ�����͏W��Ă���B�u�ނ̂������ŃX�g�[���Y�̓u���[�X�̓��݊O�����ɂ��v�ƁB
�@�~�b�N�̂��̌��t�ɗ��t�������悤�ɁA�z�v�L���X�ɂ͂Ȃ��X�`���Ɠ��̃u���[�X�`���b�N�����[���E�t�B�[�����O�́A���������o�[���͂��ꂽ����A�قƂ�ǂ̃A���o���̗v���v���Ŏ������ꂽ�B�o���h�̃f�r���[�����A�uCarol�v�A�uAround And Around�v�A�uDown the Road Apiece�v�Ƃ������`���b�N�E�x���[�i��p�B�j�i���o�[�ȂǂŒ����������˂܂���s�A�m�E�X�^�C���͐������Ȃ�������邱�ƂȂ��A�uHonky Tonk Women�v�A�uBrown Sugar�v�A�uStar Star�v�A�uIt's Only Rock'n Roll�v�Ȃǂ̃q�b�g�E�\���O�Ƀt�B�[�`���[����Ă���B�܂��A�uLet It Bleed�v�A�uDead Flowers�v�A�uShake Your Hips�v�A�uSweet Virginia�v�A�uShort and Curlies�v�Ƃ����������Ȃ�ǃs�����Ɛh���A�[�V�[���S��A�uWhere the Boys Go�v�A�uHang Fire�v�A�uShe Was Hot�v�ɑ�\�����i�X�g�[���Y�ɂƂ��Ắj�ߑネ�b�N�����[���E�`���[���A�����āA�uBlack Limousine�v�A�uTwenty Flight Rock�iLive�j�v�̂悤��80�N��ȍ~�̃o���h�̃��[�c��A�Ȃɂ����Ă��A�X�`���̃u���[�X�`���b�N�����[���L�������Ղ�Ƃ��݂������ɔ��H�̖���Ă��Ă���B�������� �h����������h �̓o�p�Ƃ�������������A�M���x�Ƃ����_�ł͒��N���M�����[�߂��z�v�L���X�̂�����͂邩�ɏ����Ă����ƌ����A�N��ǂ����Ƃɂ��̑��݂͂ނ���u���_�I�x���v�����˂��Ō�̐�D�i���� �h�Q�Ԃ̏t�c���h ��f�i�Ƃ�����...�j�Ƃ��ďd��Ă����Ƒ�����̂��}�����R�ƌ����邾�낤�B
�@
�@���܂�h��Ɍ���邱�Ƃ̂Ȃ��C�A���E�X�`�����[�g�̏ڍׂȌo�����͂��߁A�l�ƂȂ�A�[���˂����v���C�X�^�C���̉�͂Ȃǂɂ��ẮA���̂��т̃g���r���[�g�E�A���o���wBoogie 4 Stu�x�̓o������������ɂ��āA����ɂ����i�߂��Ă������Ƃ��낤�B�܂��͂��̎肪����̈���Ƃ��āA�X�g�[���Y�ȊO�̍�i�ւ̋q���Ȃ��Љ�Ė{�e�̌��тɑウ�����Ă����������Ǝv���B
�@��\�I�ȂƂ���ł́A��͂����b�h�E�c�F�b�y�����́uRock and Roll�v�i71�N�j�ƁuBoogie With Stu�v�i75�N�j���낤�B���[�r���E���j�b�g���g�p�������R�[�f�B���O�����ƂȂ�W���C���g�����������A�X�`���̃u�M�E�A���h�E���[���̖{�̂Ƃ�������2�ȁB��҂̓^�C�g��������@�������Ƃ���A����Ƀu�M�E�M�E�x�[�X�̃X�`���]�́B1970�N���n�E�����E�E���t�Ƃ��̈���q�Ƃ������ׂ��p���u���[�X�E���b�N�̗Y���ꓰ�ɉ���wLondon Sessions�x�ł��A�uRockin' Daddy�v�A�uBuilt For Comfort�v�A�uDo The Do�v�A�uWang-Dang-Doodle�v�ȂǂŃV���A�ȃu���[�X�E�s�A�m���ƒe���Ă���X�`�����ł���B���̂ق��A�X�g���C�E�L���b�c�����Y���E�A���h�E�u���[�X�w�������߂�2nd�A���o���wGonna Ball�x�Ɏ��߂�ꂽ�uRev It Up and Go�v�i81�N�j�A�`���[���[�E���b�c�ƎQ�������U�E�u���[�X�E�o���h�́uBad Penny Blues�v�i81�N�j�A���ɂ����̃��b�L���E�u���[�Y��Y�W���[�W�E�\���O�b�h�̑S��No.1�q�b�g�uBad To The Bone�v�i82�N�j�Ƃ������y�ȂŃX�`���̃L�����ƌ���D�v���C�����ɂ��邱�Ƃ��ł���B�܂��A�wSee Me�x���wRough Mix�x�ւ̎Q���ȂǁA���j�[�E���[���Ƃ̋������v���̂ق������Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ������[���B
|


 ���[�����O�E�X�g�[���Y ���W�X�g�A
���[�����O�E�X�g�[���Y ���W�X�g�A
 �X�g�[���Y �V���O��BOX�I
�X�g�[���Y �V���O��BOX�I
 �uThe T.A.M.I. Show�v��DVD�o��
�uThe T.A.M.I. Show�v��DVD�o��
 �y���W�z �L�[�X�E���`���[�Y�̏��x�X�g
�y���W�z �L�[�X�E���`���[�Y�̏��x�X�g
 �X�g�[���Y LP�{�b�N�X�Z�b�g�I
�X�g�[���Y LP�{�b�N�X�Z�b�g�I
 �u���f�B�W�F���v �lj��f�������Ղ�I
�u���f�B�W�F���v �lj��f�������Ղ�I
 �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̐^��
�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̐^��
 �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx ���ؔ�
�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx ���ؔ�
 �y��U�z �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
�y��U�z �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��1��z ����ˁhCHABO�h��s
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��1��z ����ˁhCHABO�h��s
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��2��z �s�[�^�[�E�o���J��
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��2��z �s�[�^�[�E�o���J��
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��3��z ���c���T �i���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�ҏW���j
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��3��z ���c���T �i���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�ҏW���j
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��4��z �T�G�L����
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��4��z �T�G�L����
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��5��z ����h �i�\�E���E�t�����[�E���j�I���j
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��5��z ����h �i�\�E���E�t�����[�E���j�I���j
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� �ŏI��z�q���ʑΒk�r�z�J���` �~ ��h��
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� �ŏI��z�q���ʑΒk�r�z�J���` �~ ��h��
 ���j�[�E�E�b�h 9�N�Ԃ�V��I �v�I�������I
���j�[�E�E�b�h 9�N�Ԃ�V��I �v�I�������I
 �y���W�z �t�F�C�Z�Y�̎��W���P
�y���W�z �t�F�C�Z�Y�̎��W���P
 �u���C�A���E�Z�b�c�A�[�V��͑S�҃C���X�g�I
�u���C�A���E�Z�b�c�A�[�V��͑S�҃C���X�g�I
 ���r�[�E���o�[�g�\���V�삪�X�S�C�I
���r�[�E���o�[�g�\���V�삪�X�S�C�I
 �w�����ɉ˂��鋴�x40���N�L�O
�w�����ɉ˂��鋴�x40���N�L�O
 �O���b�O�E�I�[���}�� 14�N�Ԃ�V��
�O���b�O�E�I�[���}�� 14�N�Ԃ�V��
 �uCROSSROADS GUITAR FESTIVAL 2010�v DVD��
�uCROSSROADS GUITAR FESTIVAL 2010�v DVD��
 �wBand On The Run�x�����ؔ�
�wBand On The Run�x�����ؔ�
 �V�W�����E���m���_�b�I
�V�W�����E���m���_�b�I
 �y�C���^�r���[�z �h�N�^�[�E�W����
�y�C���^�r���[�z �h�N�^�[�E�W����
 �y�C���^�r���[�z �x���E�V�h���� �~ �W���[�W�B�E�t�F�C��
�y�C���^�r���[�z �x���E�V�h���� �~ �W���[�W�B�E�t�F�C��