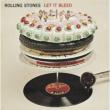2011年1月18日 (火)

2010年、『メイン・ストリートのならず者』デラックス盤を皮切りに、映像版『ストーンズ・イン・エグザイル』、70年代以降のスタジオ・アルバム・ボックス・セット第2弾、『Ladies And Gentlemen』DVD、さらには、ロニー・ウッドのニュー・アルバムに、キース・リチャーズの初ベスト盤など、ファン垂涎のプロダクツをひっきりなしに届けてくれたローリング・ストーンズ。
昨年5月からお送りしてきた HMVスペシャル・インタビュー企画「メイン・ストリートのならず者、もしくは、ローリング・ストーンズをはてしなく語る夕べ」もついに最終回。お迎えするのは、日本のレコード業界において特にローリング・ストーンズに所縁の深いお二方。元・日本ローリング・ストーンズ・ファン・クラブ会長で音楽評論家の越谷政義さん(Mike Koshitani)と、ユニバーサルミュージック合同会社相談役の石坂敬一さん。連載ラストにして2011年新春を飾るに相応しい特別対談では、60年代から音楽業界の最前線で活躍されてきたご両氏ならではの歯に衣着せぬマルチ・アングルなローリング・ストーンズ論が飛び交いました。
2011年、今年こそストーンズ本格始動の朗報が飛び込んでくることを期待しつつ・・・「ローリング・ストーンズをはてしなく語る夕べ」の最終回、たっぷりとお愉しみください。
インタビュー/構成: 小浜文晶 |
- --- 「2011年 新春特別対談」と銘打った「ローリング・ストーンズ特設ページ」のインタビュー企画 最終回では、元・日本ローリング・ストーンズ・ファン・クラブ会長で音楽評論家の越谷政義さん(Mike Koshitani)と、東芝EMI(現EMI)時代に洋楽ディレクターとしてビートルズ、ローリング・ストーンズをはじめ数々の海外アーティストを担当されていたユニバーサルミュージック合同会社相談役の石坂敬一さん、日本のレコード業界において特にローリング・ストーンズに所縁の深いお二方をお迎えして、味濃いお話を色々とお伺いしたいなと思っております。まずは、お二方の出会いについてなのですが。
-
石坂敬一(以下、石坂):ずいぶん前だよね。僕が東芝音楽工業の洋楽部にいた頃。ローリング・ストーンズがEMIに移籍してきたのが、1977年ぐらいだったかな? まぁそれ以前から越谷さんとは、ストーンズに限らず色々な音楽談義をしていたと思うんだけど・・・
-
越谷政義(以下、越谷):僕の記憶では、石坂さんと初めて会ったのは1969年。「僕もストーンズ好きなんだよね。ちなみに何の曲が好きなの?」って訊くと、石坂さんは「Empty Heart」って言ったんだよね(笑)。
-
石坂:イギリスではEPにしか入っていない曲ね。
-
越谷:(註)『Five By Five』。当時大抵の人は「(I Can't Get No)Satisfaction」とか「一人ぼっちの世界」とかさ、ちょっとコアなところでも「Tell Me」だったり、デビュー曲の「Come On」だったり。そこをいきなり「Empty Heart」が好きだなんて言うから、「この人はちょっとケアしておかないと恐いな」って(笑)。
-
石坂:でも、「Empty Heart」は本当にいい曲だよ。例えば、(註)ウィルソン・ピケットなんかがカヴァーしたら面白いなって思ってたけど、それほど知られる曲ではなかった。

写真は、ローリング・ストーンズ『Miss You』発表時の1978年に行なわれたマイク越谷氏と石坂氏の誌面対談。

(註)ローリング・ストーンズ「Five By Five」 EP・・・「If You Need Me」「Empty Heart」「2120 South Michigan Avenue」「Confessin' The Blues」「Around And Around」を収録したEP。イギリスで、デビュー・アルバム『The Rolling Stones』の発売後すぐとなる1964年8月にリリースされた。「Empty Heart」と「2120 South Michigan Avenue」の作詞・作曲クレジットには、60年代初期にミックとキースが他のメンバーとの共作の際に使用する名義「Nanker Phelge」と記載されている。 -
越谷:ちなみに、ストーンズあるいはビートルズの曲をいちばん最初に聴いたときのことって憶えています?
-
石坂:ビートルズは、(註)糸居五郎さんがディスクジョッキーをしていたニッポン放送のラジオ番組「ザ・ベスト・イン・ブリテン」で聴いた「Please Please Me」。1963年の春頃かな。毎晩11時半ぐらいから放送していたBBC制作の10分ぐらいの番組。そこで聴いたのが初めてだと思うけど・・・ストーンズはあまり憶えていないんだよなぁ(笑)。だけど、ほんとうに意識して聴いたのは、やっぱり「Carol」か「It's All Over Now」かな。いい感じだなって思ったよ。

(註)糸居五郎・・・若者向け深夜ラジオ放送の元祖「オールナイト・ニッポン」の初代パーソナリティとしても知られる元ニッポン放送のアナウンサー。その前身番組『オールナイトジョッキー』では、1963年2月にビートルズのデビュー曲「Love Me Do」を日本で最初にオンエアしている。「1曲でも多くの音楽を紹介するのが、最高のディスク・ジョッキーである」という信念に基づいた番組構成/進行で、「最初で最後の職人DJ」と言われた。命日の12月28日は「ディスクジョッキーの日」に制定されている。BBC制作の「ザ・ベスト・オブ・ブリテン」は、深夜ラジオ放送の草分け的な番組として、今も多くの音楽ファンの間で語り継がれている。70年代後半、マイク越谷氏と全国のディスコでDJ共演した。 - --- 一方で、石坂さんと出会われた1969年当時、越谷さんの最もお好きだった曲というのは?
-
越谷:今もそうだけど、ストーンズは全部。だから、「この曲」っていうのは当時も言えなかったんだよね。
- --- 日本のローリング・ストーンズ・ファン・クラブを設立したのは、そこから3、4年ほど前のことになるんですよね?
-
越谷:ストーンズのファン・クラブを作ったのが1965年で、当時僕は中学3年生。高校受験があったから、1つ年上の先輩を会長にしてね。で、ちょうど(註)「ミュージック・ライフ」の1965年8月号、たしか星加ルミ子さん(当時のミュージック・ライフ編集長)が着物姿で来日したビートルズと写っている表紙、その号の中で「ローリング・ストーンズを語ろう」っていう座談会の企画があって、そこに僕も出席したの。(註)亀渕昭信さんとか(註)朝妻一郎さんなんかもいてさ。当時の「ミュージック・ライフ」編集部の担当者が桜井ユタカさんっていう時代。でまぁ、そういった活動をしながら、翌66年から僕がファン・クラブの会長になった。だから、正式には初代会長ではないんだよね。

(註)「ミュージック・ライフ」の1965年8月号・・・当時の編集長・星加ルミ子さんが、日本のメディアとしては初めてビートルズに単独インタビューを行なった「ビートルズに会いました!」リポート24ページを掲載。取材時間は当初30分だったそうだが、この日のレコーディングが終了していたことが幸いし、急遽3時間のロング・インタビューになったという。後半は、日本のこと、着ている着物のことなど、星加さんの方がメンバーから質問攻めにあったそうだ。また、翌66年の来日時にも日本のメディア唯一のインタビューを行なっている。日本の音楽と洋楽の発展に貢献した星加ルミ子さんの半生を振り返った本『ビートルズにいちばん近い記者 星加ルミ子のミュージック・ライフ』(淡路和子・著)にもそのときの様子が詳細に綴られている。

(註)フジテレビの「リブヤング!」・・・メイン司会を愛川欽也、サブ司会をビーバー、映画情報担当を今野雄二、音楽担当をマイク越谷氏らが務めていた、1972年4月2日から1975年3月29日まで放送されたフジテレビの若者向け情報番組。歌手やバンドのライヴ演奏や、「シンガーソングライターコンテスト」のような企画も設けられ、70年代の音楽エンターテインメント番組の中でも一際異彩を放っていた。キャロルが初めてテレビ出演した番組としても知られており、また村八分も出演(当時高校生だったCharは、マイク越谷氏に連れられて番組見学をした)。彼らの発掘ライヴ音源CD 『Recorded Live '73』は、1973年2月に同番組に出演したときのライヴが収録されている。
僕は大学入学直後の1969年から、今で言うフリーのライターとして活動するようになって、テレビやラジオにも出演。70年代前半、僕がレギュラー出演していた(註)フジテレビの「リブヤング!」に「石坂さん出演してよ」なんてお願いしたりしてて。その頃から石坂さんはすごかったんだから(笑)。派手なお化粧したり、ロンドン・ブーツ履いたりして、ね? -
石坂:ようするにグラム・ロックの「宣伝塔」だよね。色んなことをやってた時代。
-
越谷:「T・レクスタシー」なんていう言葉を作ったりして。(註)ピンク・フロイドの『原子心母』や『狂気』も石坂さん。邦題だけじゃなくて、日本語のキャッチ・フレーズを確立した人なんだから。
- --- 越谷さんもストーンズの「You Can't Always Get What You Want」に「無情の世界」という邦題を付けられていますよね。
-
越谷:あと、(註)「夜をぶっとばせ!」ね。でも、石坂さんの前で『Love You Live』なんて言ったら怒られちゃうんだから(笑)。
-
石坂:そりゃそうだよ(笑)。(註)『感激! 偉大なるライヴ』じゃないとさ。外国映画が日本で評価されるきっかけとなったひとつには、日本の洋画業界の制作や宣伝マンが日本人向けの魅力的で、場合によっては文学的な格調の高い邦題を一生懸命考えて付けたから、ということがあるわけなんだよね。原題のままでいくと、勢いでいける場合もあるだろうけど、やっぱりどこか消化不良。例えば、ウィリアム・ホールデン主演の「Love Is A Many Splendored Thing」。今のいい加減なタイトル付けからすると、おそらく「ラヴ・イズ・メニー」みたいな中途半端な感じで終わってしまう。だから、あれを「慕情」と付けたのはやっぱり素晴らしい。
-
越谷:ビートルズにしたって、「抱きしめたい」だから、いいわけなんだよね。
-
石坂:あれは、(註)高嶋弘之さんだね。いいタイトルだよ。「I Should Have Known Better」にしても、直訳すると「僕はもっと早く君を知りたかった」になるんだけど、高嶋さんは「恋する二人」としているからね。あれも素晴らしいタイトル。ほとんどマッカートニーのソロとも言える『Help!』の中の「I've Just Seen A Face」は、「夢の人」。すごくロマンティック。
アラン・ドロン、マリー・ラフォレ、モーリス・ロネの「太陽がいっぱい」という映画。あの原題は「Le Plein Soleil」。だけど、「太陽がいっぱい」となった瞬間、誰もがニースの紺碧の海岸を思い浮かべることができるんだよね。 - --- 色々な風景やニュアンスがぎゅっと詰まっていますよね。
-
越谷: 「夜をぶっとばせ!」だっていいでしょ? ”ビックリ・マーク” をわざわざ付けたんだから。その時は、朝妻一郎さんや担当ディレクターなんかとみんなで考えてて、「夜をいっしょに過ごそうぜ」とか色々候補はあったんだけど、ふと僕が「夜をぶっとばせ」って口にしたら、「それ、いただき」って言われてさ。で、 ”ビックリ・マーク” を付けようよって。60年代、70年代の洋楽の邦題には面白いエピソードがいっぱいあるんだよね。
-
石坂:日本語の言葉選びや言葉遊びに興味を持って作業ができる人じゃないと、いい邦題は付けられない。単に翻訳ができるだけじゃ無理なんだよ。ローリング・ストーンズなら、ストーンズのスピリットや外観をよく理解していないと、つまり大好きじゃないとね。『Some Girls』は、やっぱり『女たち』なんだよ。ある種の“不潔さ”が入らなくちゃ。
- --- (笑)不潔、卑猥、不貞。
-
石坂:あのジャケットは、非常に大仰で、色気があって、まさしくストーンズらしい“アウトレイジアス”な出来だよね。だけど、あれを単に「サム・ガールズ」と呼んでしまうと、僕からすれば(註)クリフ・リチャードのアルバムにもそう呼べるものがあるわけだから、そこに何の差異もないじゃない? だから、逆にクリフ・リチャードに「女たち」とは付けられないわけ。ストーンズが「女たち」と呼ぶと、(註)アニタ・パレンバーグだとか、そういった悪女を芋づる式に思い浮かべることができる。
- --- 不穏でスキャンダラスな香りがプンプンします(笑)。
-
越谷:(註)マリアンヌ・フェイスフルとかさ。枚挙に暇がないわけでしょ。しかも、クリフ・リチャードは牧師さんだから、そんなタイトル付けることができない(笑)。
 女たち・・・写真左から、アニタ・パレンバーグ、マリアンヌ・フェイスフル、そして、ピーター・コリストンのコンセプト/デザインによる切り抜き特殊ジャケを採用した1978年のアルバム『女たち』のジャケットを ”本人無許可で” 飾ったラクウェル・ウェルチ、ルシール・ボール。とりわけ、ドイツ系イタリア人の女優/モデルのアニタ・パレンバーグ、”Sister Morphine”こと歌手/女優のマリアンヌ・フェイスフルの二人は、60年代のストーンズを語る上では欠かせない存在。
女たち・・・写真左から、アニタ・パレンバーグ、マリアンヌ・フェイスフル、そして、ピーター・コリストンのコンセプト/デザインによる切り抜き特殊ジャケを採用した1978年のアルバム『女たち』のジャケットを ”本人無許可で” 飾ったラクウェル・ウェルチ、ルシール・ボール。とりわけ、ドイツ系イタリア人の女優/モデルのアニタ・パレンバーグ、”Sister Morphine”こと歌手/女優のマリアンヌ・フェイスフルの二人は、60年代のストーンズを語る上では欠かせない存在。
アニタは、ブライアン・ジョーンズとの交際後、1967年からキースと付き合うようになり、退廃的で野生的なファッション・スタイルをキースに仕込んだだけでなく、当時のストーンズの音楽や悪魔的イメージの発展に大きな影響を与えたとも言われている。ドラッグ、黒魔術、奔放な性生活(ミックとの不貞も)など常にスキャンダラスな話題を振りまいた。キースとは正式な夫婦関係は結ばなかったが、69年に長男マーロン、72年に次女ダンデライオン(後にアンジェラと改名)、76年に次男タラ(生後2ヶ月余りで死亡)をもうけている。79年にキースと破局。
1964年に「As Tears Go By」でデビューしたマリアンヌは、「エンジェル・ヴォイス」と称された歌声と清楚なルックスで人気を博した。ジョン・ダンバーとの離婚後にミック・ジャガーの恋人に。1960年代後半、ドラッグ過多が原因となり、全裸で倒れているところを警察に見つかり、さらにその全裸写真が新聞に載るなどのスキャンダルに巻き込まれ、当時は「地に堕ちた天使」、「天使の顔をした娼婦」とマスコミに書き立てられた。この騒動を引き金に精神のバランスを崩したマリアンヌは、ドラッグとアルコール漬けの毎日を送るようになり、はては自殺未遂も繰り返したという。その後もドラッグ遊戯はヘヴィになり、愛想を尽かしたミックと70年に破局を迎えた。そこからおよそ10年、地獄のような低迷期を送るものの、79年に今やトレードマークとなっている「しゃがれ声」を携えて見事シーンにカムバックしている。2011年1月にフランスとドイツ、3月にイギリスでリリースされるニュー・アルバム『Horses And High Heels』には、前作に続いてキースが参加。 -
石坂:クリフ・リチャードに関して言えば、彼は、元々はポピュラー・アイドル歌手からスタートして、そこから真面目に芸能界を生き抜いてトップに上り詰めた人。音楽的にはこれといった作品を残したわけではなくて、半ばアメリカのエピゴーネンとしてロックンロールをやって、その次はカンツォーネをやってと、つまり何でもよかったんだよね。だけど、人間的には道徳を遵守して牧師になって、はてはエリザベス女王から賞までもらって。こういうヤツを、ローリング・ストーンズはハナからナメてただろうね(笑)。
-
越谷:そうだよね(笑)。
-
石坂:19世紀ビクトリア時代というのは、そういうのがウケていた。現代日本で言えば、クリフ・リチャードは、明治時代の精神を継いだ健全で素晴らしい若者みたいに称されるようなことと同じ。
- --- その健全な精神の対極に、ローリング・ストーンズが必要悪のように存在していた?
-
石坂:結果的にはそうだよね。ビートルズもそうだし。
-
越谷:ただ、60年代デビュー当初のストーンズはそこまで反体制なパフォーマンスをしていたわけじゃなかった。「ポップス・グループとしてやっていこう」っていうイメージをマネージャーの(註)アンドリュー・ルーグ・オールダムが持っていたから。キースは本名の「リチャーズ」を、クリフ・リチャードの人気にある種あやかるようなカタチで「リチャード」にしていたこともあったしね。もちろんマネージャーの意向もあって。
-
石坂:1958〜1961年の日本とイギリスの音楽界というのは、エルヴィス・プレスリーのコピーをたくさん生み出し、それが主流となってポピュラー音楽界を形成していた、という部分で共通しているんだよ。日本では、(註)平尾昌晃、ミッキー・カーチス、山下敬二郎の「ロカビリー三人男」が、1958年2月の第1回「日劇ウエスタンカーニバル」でものすごい熱狂を生んだ。エルヴィス、エディ・コクラン、ポール・アンカのコピーをやっていたんだよね。そのあとに、(註)水原弘、守屋浩、井上ひろしの「三人ひろし」、神戸から(註)内田裕也さんが出てきて、日本はエルヴィスの音楽のカヴァーをとっかかりにして、独自の歌謡ロックのようなものを生み出していった。日本の和製ポップスの第1ステージ。

(註)平尾昌晃、ミッキー・カーチス、山下敬二郎の「ロカビリー三人男」・・・平尾昌晃、ミッキー・カーチス、山下敬二郎(写真上から)の「ロカビリー三人男」は、1958年2月に開催された「第1回日劇ウエスタンカーニバル」(1958年2月から1977年8月まで日本劇場で開催されていた音楽フェスティバル)で華々しくデビュー。平尾が歌う「星は何でも知っている」、山下のポール・アンカ「ダイアナ」の日本語カヴァーがヒットし、日本中の若者たちの間に熱狂的なロカビリー・ブームを巻き起こした。2008年のクリスマスにはウエスタンカーニバル開催50周年を記念した「ウエスタンカーニバル・クリスマス同窓会」、2009年9月には「ウエスタンカーニバル in OSAKA」と銘打った各イベントに三人が再集結し、往年のロカビリー・ファンを大いに喜ばせた。また、2011年1月5日の山下の突然の訃報に平尾は「ロカビリー三人男は永遠に不滅。53年間一緒にやれてうれしかった、ありがとう」と追悼の辞を贈った。

(註)水原弘、守屋浩、井上ひろしの「三人ひろし」・・・50年代後半から60年代前半にかけて活躍した、いずれも名前が「ひろし」の歌手、水原弘、井上ひろし、かまやつひろしの3人の総称。水原弘が1959年のデビュー・シングル「黒い花びら」(第1回日本レコード大賞を受賞)のヒットで歌謡界で成功を収めると、代わって守屋浩が加わって新たな「三人ひろし」あるいは「四人ひろし」として一世を風靡した。井上ひろしは、ロカビリー歌手を経て、59年「雨は泣いている」でデビュー。同年発売の「地下鉄は今日も終電車」は若い女性の間で絶大な人気を得る。翌60年にはリバイバル曲「雨に咲く花」がヒットした。守屋浩は、58年に日劇ウエスタンカーニバルでデビュー。ロカビリー・ブームに乗って大躍進。その後60年のホリプロ設立に伴い同事務所に移籍し、歌謡曲に転向。「夜空の笛」、「僕は泣いちっち」が大ヒットする。その後も「大学かぞえうた」や「有難や節」などをヒットさせている。写真は上から、水原弘、守屋浩、井上ひろし。
同じ頃のイギリスを見てみると、ほぼ同じような流れ。クリフ・リチャード、(註)ヘレン・シャピロ、(註)ビリー・フューリー、(註)ジョン・レイトン、(註)トミー・スティール、(註)ロニー・ドネガンなんかが、ひとことで言えばプレスリーをご本尊とするエピゴーネンによって “ロック歌謡芸能界”を形成していた。だから、日本とイギリスの1958〜1961年の4年間というのは、全くと言っていいほど同じだった。
だけど、「その後」が違う。そこを大きく違えたのが、ビートルズとローリング・ストーンズの出現に尽きるということ。そして、それがカウンター・カルチャーになった。「このくだらないヤツらをみんなブッとばせ」。「オレたちはアメリカでないがしろにされている、大好きな黒人音楽をもっと研究するんだ!」って。それを「アンダーグラウンド・サブ・カルチャー」と呼んで支えていたのが、一流あるいは二流大学のイギリス人(笑)。
一方で日本は、この時期にテレビが商業主義と手を取り合って、芸能ビジネスの拡大に走っていった。ミッキー・カーチスが司会の(註)「ザ・ヒット・パレード」が導火線を担って、それが大当たり。もちろん悪いことではないけれど、イギリスはその逆だったんだよね。音楽の枢軸の転換が起こって、アーティストがそっくり入れ替わった。アンダーグラウンドがアップフロント・グラウンドに出てきたんだよ。良質なポップスを生み出し続けてはいたけど、クリフ・リチャード、ヘレン・シャピロなんかはみんな消えちゃった。ただそこに、マリアンヌ・フェイスフル、(註)ルルのような当時としてはヘヴィだった連中も出てきた。

(註)「ザ・ヒット・パレード」・・・1959年6月17日から1970年3月31日までフジテレビ系列で生放送された音楽番組。人気ロカビリー歌手だったミッキー・カーチスや長沢純の総合司会により毎週人気歌手が多数出演してステージを繰り広げる番組で、テレビが茶の間に浸透するきっかけを作ったことでも有名。また、当時デビューしたばかりのザ・ピーナッツ(写真)を司会に大抜擢したことでも話題を呼んだ。バックのレギュラー演奏は、スマイリー小原とスカイライナーズ、渡辺晋とシックス・ジョーズ。
日本で、イギリスのような音楽的転換が行なわれるのは、GSの登場から。うんと狭義に言えば、(註)ザ・ゴールデン・カップスと(註)パワーハウスの登場からだよね。 -
越谷:僕は今年、「ジャパニーズ・ロック・インタビュー集」という本を出して、その中でも書いてあることなんだけど、やっぱり1969年が日本にとっての音楽転換期だと思うんだよね。例えば、(註)エディ藩がインタビューの中でも言っていたことなんだけど、「やりたくない曲をレコーディングさせられた挙句、レコード会社からは<もっとコブシを入れて歌え>」だとか、日本のロックが花開いたと言われるGS全盛期にしてもそういうことが多かった。だから本当の意味では、裕也さんの(註)フラワー・トラヴェリン・バンドが出てきて、そこにゴールデン・カップス、パワーハウスみたいなGS勢が絡んできた時期が、日本のロックが誕生した年って言えるんじゃないかな。
-
石坂:イギリスが本当のロックに目覚めたのが1961年頃だとして、日本は越谷さんが言うように、1969年あたり。ただ、GSブームの先鞭を打った(註)スパイダースは、1964〜5年からすでに活躍していて、すごく良質だったよ。それ以前に、(註)植木等のクレイジー・キャッツなんかもある意味で日本のポップス歌謡の支えになってはいたけど、やっぱりスパイダースは全然モノが違ったよね。
-
越谷:1965年には、(註)ピーター&ゴードンをはじめとして色々な海外の大物グループが日本にやって来たんだけど、その当時中学生の僕にとっては、ピーター&ゴードンよりスパイダースの方が「ロック」していたんだよね。
-
石坂:だけど僕は、そのピーター&ゴードンの来日公演を観たとき、やっぱりホンモノだと思った。当時彼らは、「リヴァプール・サウンド」「ブリティッシュ・インヴェイジョン」って言われていたんだけど、「なんてかっこいい髪型なんだ!」って(笑)。あんな髪型なのにスーツを着ていることにもびっくりした。
-
越谷:あの当時、海外のグループはよく日本に来ていたよね。(註)ハニーカムズだとか、(註)アニマルズだとか。
-
石坂:あと、オーストラリアから “いんちきビートルズ” が来たよ(笑)。
- --- “いんちきビートルズ”(笑)。当時そういったグループは星の数ほど存在していたそうですが・・・
-
越谷:エレキ・イベントかなんかでやって来たんだけど、寺内タケシさんの自前のバカでかいアンプにびっくりしたっていう(笑)。そのとき通訳をやったのがエディ藩。
60年代のこの時期っていうのは結構おもしろかった。さっき言ったように、僕がストーンズのファン・クラブを作って運営していたのが1965年なんだけど、この年にファン・クラブの会員が激減したの。なぜかって言うと、その当時ストーンズは「(I Can't Get No)Satisfaction」をリリースした頃で、会員は、初期のストーンズ同様にブルースやリズム・アンド・ブルースが大好きなマニアックな男連中が多かったんだよね。「ビートルズはポップすぎていかん!」みたいなことを言ってる連中(笑)。だから、「(I Can't Get No)Satisfaction」が出ると、彼らはファン・クラブから離れちゃう。 - --- 曲がキャッチーすぎて。
-
越谷:そう。「Not Fade Away」や「It's All Over Now」の頃にストーンズを好きになった人たちにとっては、「The Last Time」あたりから怪しくなってくるわけ(笑)。だんだんとポップな曲が増えてきて、そこに決定的な「(I Can't Get No)Satisfaction」(笑)。初期のファン・クラブ会員の多くが辞めていったんじゃないかな。もちろん、その何十倍にも会員は増えるんだけどね。「(I Can't Get No)Satisfaction」のヒット効果で。この当時、例えば、中学校のひとクラスでビートルズ、ストーンズを聴いてたヤツなんてほんと一握り。
-
石坂:(註)ベンチャーズのほうが全然人気があったよ。
-
越谷:あとは、舟木一夫、橋幸夫、西郷輝彦の「御三家」だとかね。ビートルズはクラスで数人。ストーンズなんて学年に一人か二人。そんなレベル。で、1964年に「ミュージック・ライフ」誌が洋楽を全面的に扱うようになる。それまでは、坂本九、ダニー飯田とパラダイス・キング、中尾ミエみたいな、いわゆる日本の歌謡ポップスがメインだったからね。
- --- それが1969年ともなると、日本では本当の意味で独自のロックが誕生し始めたということもあり、ローリング・ストーンズの世間的な認知度や人気というのもうなぎ上りになっていったのでしょうか?
-
越谷:いやいや、60年代後半のストーンズって、日本ではそこまで爆発的な人気があった存在じゃなかったよ。ねぇ、石坂さん?
-
石坂:そうだね。結局、子どもにはちょっと難しい世界だったんだよ。ローリング・ストーンズのとてつもない存在感を説明すると、たしかに文化的な方面の話になっていくから。音楽的な面を言えば、60年代のストーンズはとにかくリフが強烈。あんなに素晴らしいものはない。だけど、日本にはそのルーツというか、それを受け止めるだけの十分な下地がなかった。
今はアメリカですら、その頃のストーンズのように、リフを中心にした骨太でブルージーなロックをやるミュージシャンっていうのは少なくなったけど、日本にはもっといないから。日本では相容れにくいバンドなんだよ。例えば、(註)キンクスの「You Really Got Me」は当時日本で大ヒットしたと若い人は思っているかもしれないけど、実際は全然だったからね。 -
越谷:キンクスとか(註)ゼムとか、当時まったくヒットしてなかったよ。
-
石坂:せいぜいアニマルズの「悲しき願い」と「朝日のあたる家」ぐらい。寺内タケシや尾藤イサオがカヴァーして当たった。
-
越谷:だって、あの当時いちばん人気あったのが、(註)ウォーカー・ブラザーズだもん。歴史には残らなかったけど(笑)。だから、ストーンズなんて、あまりにもマニアックな存在。
-
石坂:今 「It's All Over Now」や「Time Is On My Side」を聴いても、やっぱりあの当時には流行らないなって思うよ。
-
越谷:ストーンズの日本でのデビュー・シングルって、1964年の3月20日に発売された(註)「彼氏になりたい」なんだけど、ちょうどビートルズの「Please Please Me」や「抱きしめたい」が同じ時期にシングル・ヒットしていたけど、プレス枚数が極端に少ないんだよね。キング・レコードで何百枚しか作られていない。だから、ストーンズの日本盤シングルって世界中のマニアの間で高値で取引されている。そのぐらい人気がなかったんだよ(笑)。
ちなみにさ、同じ年の12月20日には日本で初めてアルバムも発売されてるんだよね。(註)『これがリヴァプール・サウンドの決定盤!! ザ・ローリング・ストーンズ』っていうタイトルで。これは擦り切れるまで聴いたよ。だから、僕にとっての最高のアルバムは、『Let It Bleed』でも『メイン・ストリートのならず者』でもなく、これなんだよね。

(註)ローリング・ストーンズ 「彼氏になりたい」 シングル・・・本国イギリスでのリリースから約4ヶ月後の1964年3月20日に登場した、ストーンズの日本におけるデビュー・シングル「彼氏になりたい」。当時、マネージャーのアンドリュー・オールダムがストーンズの2枚目のシングルをどうするべきか悩んでいる時に、偶然ジョンとポールに出くわし(オールダムは元々ビートルズの宣伝係をしていた)、彼らにストーンズのために曲を書いてくれと頼み、生まれた曲だ。この曲の制作の一部始終を見ていたミックとキースは、ビートルズの作曲能力に大きな感銘を受け、後にオリジナル曲を書くきっかけになった。ビル・ワイマンの回想によれば、「キースは、ビートルズの曲をやるなんて鼻高々だと喜んでいた」という。

(註)『これがリヴァプール・サウンドの決定盤!! ザ・ローリング・ストーンズ』・・・ストーンズの日本での最初のシングル・ヒット「Tell Me」に続いて、キング・レコードが「ビートルズの対抗馬」として満を持して1964年12月20日に発売した日本デビュー・アルバム。越谷さんによると、その当時はアーティストの許可なしで曲順や収録曲を各国独自の形で発売できたそうで、日本も例外なく”日本向け”の「ザ・ローリング・ストーンズ第1集」として登場。A面1曲目がシングル・ヒットしていた「Tell Me」で、UK盤の1stアルバム『The Rolling Stones』を基盤にした曲順入れ替えを施しての本邦お披露目となった。 -
石坂:ストーンズは、日本でもフランスでも世界中に熱狂的なサポーターはいるけど、みんな ”大人” なんだよ。デザイナーだったり、作家だったり、映画監督だったり。
-
越谷:(註)村上龍もストーンズ大好きだしね。「限りなく透明に近いブルー」の中にストーンズが登場したり、それこそ「コックサッカー・ブルース」なんていう作品もあるぐらいだから。

(註)村上龍もストーンズ大好きだしね・・・巷では、同じ村上でも「春樹がビートルズ派」で「龍がストーンズ派」という声を昔からよく耳にするが、どう考えても両氏共にどちらのバンドもこよなく愛しているはず。村上龍のストーンズ好き。そんな世間的なイメージを決定付けたのは、1976年のデビュー小説「限りなく透明に近いブルー」の中に登場させているストーンズのLP(「Time is On My Side」を選曲)であったり、87年の「69」の中に現われる「レディ・ジェーン」という名の女子大生であったり、また、ご本人は無意識だったそうだが、月刊「写楽」で連載していたエッセイ「コックサッカー・ブルース」というタイトルそのものであったり。さらに、1983年に宝島社から発行された「月刊宝島臨時増刊号 ストーンズ・ジェネレーション」のインタビューの中では、控えめながら余りあるストーンズ愛を吐き出している。高校時代に結成していたバンド「シーラカンス」では、よくストーンズ楽曲をコピーしていたそうだが、1968年にミック・ジャガーがパリの5月革命のデモに参加した写真を見たことでバンドの解散を決意したという。 - --- 何と言いますか・・・”おとなの玩具”として扱いやすいところもあったのでしょうか?
-
石坂:「たまにストーンズを聴かないと落ちつかねぇ」みたいなことを言わないと、カッコ悪かったんだよ(笑)。ディランもそうだけどね。「キングストン・トリオが好き」って言うよりは、「ボブ・ディランを聴いてるんだ」って言ったほうがサマになるんだよ。
- --- 1969年のそうした状況から、70年代を迎え、ストーンズは徐々に誰もが認める “ロックの王道” 的存在になっていくと思うのですが、その過程で石坂さんなりに重要視すべき点というのはありますか?
-
石坂:やっぱりストーンズには、ミュージシャンズ・ミュージシャン的なところがあった。レノンもそうだね。例えば、ミュージシャンが選ぶビートルズの最も好きな曲は「I Am the Warlus」だったりするけど、一般の感覚からはだいぶかけ離れている。あるいは、「Strawberry Fields Forever」は革命的にいいって言うけれど、「Penny Lane」のほうがまだ一般ウケはいいんじゃないかな。ビートルズは1965年の『Rubber Soul』から、ストーンズの黒人音楽の探求とはまた違った方向として、ややアバンギャルド志向とも言える自分たちだけの世界に入っていったよね。詩においても創作詩。それでも彼らが人気を博したのは、商業的なうまさがあったからね。アルバムとシングルでまったく別路線のものを作った。「All You Need Is Love」をやってる頃、アルバムでは『Revolver』、『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』でしょ。星加ルミ子さんも、『Sgt. Pepper's 〜』を聴いて何がなんだか分からなかったけど、とにかく和服を着て会いに行った感じなんじゃない?(笑)
-
越谷: (笑)いやでも実際、星加さん本人は「あのアルバムはなかなか理解できなかった」って話していたからね。
-
石坂:ローリング・ストーンズはさらに扱いにくい音楽だったんじゃないかな。僕にとって60年代のストーンズの曲と言えば、「Heart of Stone」、「Tell Me」、「Ruby Tuesday」、「Mother's Little Helper」なんかだよね。暗く翳がさして、チューダー調と言うべきか、虚飾に満ちたイギリスの世界を抉っているようで、素晴らしいよね。「As Tears Go By」なんて、マリアンヌ・フェイスフルに限らず誰が歌っても涙が出るぐらい美しい曲だよ。古い美しさがある。彼らが本気で書くとああいうことになるんだよ、やっぱり。でも、「俺たちは(註)ハウリン・ウルフが大好きだぜ」なんて意識するとおなじみの感じになっちゃう(笑)。
-
越谷:そうだよね(笑)。それと、(註)1973年の初来日公演の騒動だって、中止になってより大きく騒がれたっていう部分はあったからね。まぁ70年代に入ると、それこそ石坂さんが日本のロックを盛り上げていた時期でもあったから。60年代とは状況が多少違う。

(註)1973年の初来日公演の騒動・・・前年、ストーンズ初の日本公演(1973年1月28〜2月1日の5日間の日本武道館公演)が発表されるものの、メンバーの麻薬所持による逮捕歴や、ビートルズ来日の時のような混乱を避けるためという理由により入国許可が下りず、チケットが完売していたにも関わらず直前になって公演は中止となった。その後、1990年の初来日までストーンズのライヴは「夢のまた夢」と言われていた。ちなみに、中止となったその年には、藤本卓也の作詞・作曲で西郷輝彦が歌った「ローリング・ストーンズは来なかった」がシングル・リリースされ、また、79年の長谷川和彦・監督、沢田研二・主演の映画『太陽を盗んだ男』では、沢田扮する城戸誠が原爆を作って政府を脅迫し、「プロ野球のナイター試合を最後まで中継させろ」のほかに「ローリング・ストーンズの日本公演を実現させろ」という当時のストーンズ・ファンの心の叫びを代弁したかのような大胆な要求を行なっている。 -
石坂:それこそローリング・ストーンズには、「Born Under a Bad Sign」も「Good Sign」も両方ある。(註)1969年のオルタモントだっけ? 運命的な遭遇だろうね、ああいった事件は。あれが(註)グレイトフル・デッドのステージでの出来事だったら、あそこまで語り継がれることはないよね。デッドでもああいった騒動はありそうだけど、やっぱり三流のギャングが出てくるんだよ(笑)。
 1969年12月6日 オルタモント・スピードウェイ・・・60年代のストーンズひいてはロック史の”ダークサイド”を如実に物語る「オルタモントの悲劇」として著名な1969年12月6日のカリフォルニア州オルタモント・スピードウェイで行われたストーンズ主催によるフリー・コンサート。出演は、ヘッドライナーのストーンズほか、グレイトフル・デッド、ジェファーソン・エアプレイン、フライング・ブリトー・ブラザーズなど。群衆整理に悪名高きアウトロー・バイカー集団ヘルズ・エンジェルスを雇ったことに端を発した事件としてもおなじみで、ストーンズが「Under My Thumb」を演奏している最中、エンジェルスのメンバー、アラン・パサーロによって黒人青年のメレディス・ハンターが殺害された。パサーロはその後、正当防衛(ハンターが銃を持ちステージに向けていたため)として釈放された。この事件の一部模様は、1970年の映画『Gimme Shelter』に記録されている。
1969年12月6日 オルタモント・スピードウェイ・・・60年代のストーンズひいてはロック史の”ダークサイド”を如実に物語る「オルタモントの悲劇」として著名な1969年12月6日のカリフォルニア州オルタモント・スピードウェイで行われたストーンズ主催によるフリー・コンサート。出演は、ヘッドライナーのストーンズほか、グレイトフル・デッド、ジェファーソン・エアプレイン、フライング・ブリトー・ブラザーズなど。群衆整理に悪名高きアウトロー・バイカー集団ヘルズ・エンジェルスを雇ったことに端を発した事件としてもおなじみで、ストーンズが「Under My Thumb」を演奏している最中、エンジェルスのメンバー、アラン・パサーロによって黒人青年のメレディス・ハンターが殺害された。パサーロはその後、正当防衛(ハンターが銃を持ちステージに向けていたため)として釈放された。この事件の一部模様は、1970年の映画『Gimme Shelter』に記録されている。 -
越谷:その半年前にはウッドストックがあったけど、そこで殺人事件までは起こらなかったわけだから、やっぱり運命的というか。
-
石坂:言い方は悪いかもしれないけど、ギャングにしても超一流が鼻息荒く出てきたわけだ。さらに、それを取材する新聞記者も一流ならライターも一流、そこで完全に舞台は揃ったよね。
- --- ある意味、客席も舞台となって。
-
石坂:あくまで想像の範囲だけど、ローリング・ストーンズらしいと言ったら、らしいよ。
「レジェンド・ロッカーズ vol.2 夢のライヴ&バトル」 ライヴ・イベントのおしらせ
ジャパニーズ・ロック・インタビュー集 発売記念
[レジェンド・ロッカーズ vol.2 夢のライブ&バトル]
ROCK AND A HARD PLACE!
日本のロック・ヒストリーを築き上げた20人のロッカーズの語りおろし「ジャパニーズ・ロック・インタビュー集」発売を記念してのスペシャル・イベント!インタビュー集登場ミュージシャンを中心に≪レジェンド・ロッカーズ 夢のライヴ&バトル≫開催第2弾!!山本恭司が率いるBOWWOW!2011年ファーストLIVE!! そしてこの日限りのスペシャル・グループ、加納秀人(外道)・山本恭司(BOWWOW)・鮫島秀樹・つのだ☆ひろ・厚見玲衣(元VOWWOW)から成るザ・レジェンド・ロッカーズ! この2グループがロックなステージをROCK JOINT GBでくりひろげるのだ。 スーパー・ギタリスト秀人&恭司+鮫島&つのだ+玲衣による夢のスーパー・セッションが実現する。そして、出演者たちのトーク・ライヴも!そして特別ゲストは?! 60〜70年代ロック・ファンからギター小僧まで、このスペシャルなライヴは見逃せない。

 吉祥寺 ROCK JOINT GB
吉祥寺 ROCK JOINT GB2011年1月29日(土)
18:00開場/18:45開演
出演:BOWWOW/ザ・レジェンド・ロッカーズ [Vo&G:加納秀人(外道)/ Vo&G:山本恭司 / B:鮫島秀樹 / Ds:つのだひろ / Key:厚見玲衣]/スペシャル・ゲスト有り!!!
前売:5,000円+1D
当日:5,500円+1D
GB店頭販売有り / HP予約承り中
【問】 ROCK JOINT GB 0422-23-3091
「メイン・ストリートのならず者、もしくは、ローリング・ストーンズをはてしなく語る夕べ」
|
その他の関連記事はこちら
 【特集】 キース・リチャーズの初ベスト
【特集】 キース・リチャーズの初ベスト
 ストーンズ LPボックスセット!
ストーンズ LPボックスセット!
 「レディジェン」 追加映像たっぷり!
「レディジェン」 追加映像たっぷり!
 『メインストリートのならず者』の真実
『メインストリートのならず者』の真実
 『メインストリートのならず者』 豪華盤
『メインストリートのならず者』 豪華盤
 【解剖】 『メインストリートのならず者』
【解剖】 『メインストリートのならず者』
 ロニー・ウッド 9年ぶり新作! Wオリ特も!
ロニー・ウッド 9年ぶり新作! Wオリ特も!
|
Rolling Stones |
|
Rolling Stones |
|
Rolling Stones |
|
Rolling Stones |
|
Rolling Stones |
|
【スーパー・デラックス・エディション】 Rolling Stones |
|
Rolling Stones |
|
〜「メイン・ストリートのならず者」の真実 Rolling Stones |
|
From The 70s To 00s Vol.1 Rolling Stones |
|
In The Sixties Rolling Stones |
|
【スーパー・デラックス・エディション】 Rolling Stones |
|
【デラックス・エディション】 Rolling Stones |
|
【デジタル・リマスター版】 Rolling Stones |
|
【デラックス・エディション】 Rolling Stones |
|
コレクターズ・ボックス Rolling Stones |
 その他のローリング・ストーンズの商品はこちら
その他のローリング・ストーンズの商品はこちら

-
越谷政義 (こしたに まさよし)
1966〜69年に日本ローリング・ストーンズ・ファン・クラブ会長を務めた音楽評論家/DJ/MC。現在は、ミュージック・ペン・クラブ・ジャパン事務局長、ローリング・ストーンズ・ファン・クラブ顧問、エルヴィス・プレスリー・ファン・クラブ顧問。ストーンズ、エルヴィス・プレスリーをはじめ、ロック、ブルース、ソウルなどのアルバム・ライナーノーツ、雑誌/新聞への執筆、ラジオDJ、イベントMC/プロデュースを手掛ける。
著書に「STONES COMPLETE」(双葉社)、「ローリング・ストーンズ大百科」(ソニー・マガジン)、「ワークス・オブ・エルヴィス」(共同通信社)、「ストーンズそこが知りたい」(音楽之友社)他、監修&主著「キース・リチャーズ・ファイル」(シンコー・ミュージック)、「ジャパニーズ・ロック・インタビュー集 時代を築いた20人の言葉」(TOブックス)がある。
石坂敬一 (いしざか けいいち)
慶應義塾大学経済部卒業後、1968年に東芝音楽工業 (現EMIミュージック・ジャパン)に入社。洋楽ディレクターとして、ビートルズ、ローリング・ストーンズ、ピンク・フロイド、レノン&ヨーコ、Tレックス、エルトン・ジョン、ジェフ・ベックなどを担当。その後、同社邦楽本部において、BOOWY、松任谷由実、長渕剛、矢沢永吉を担当。91年に同社常務取締役に就任。94年、ポリグラム株式会社に入社、代表取締役社長就任(現 ユニバーサル ミュージック合同会社)。99年にユニバーサル ミュージック株式会社入社、代表取締役社長就任(現 ユニバーサル ミュージック合同会社)。2009年1月、ユニバーサル ミュージック合同会社 最高経営責任者兼会長に就任。11月に同社会長 就任。2011年から同社相談役に就任。ほか、社団法人日本レコード協会理事 (1999年4月 〜)、社団法人日本レコード協会副会長 (2000年 4月 〜)、社団法人日本レコード協会会長 (2006年 7月 1日 〜)を務めている。著書に「BEATLESの辞典」(ごま書房)、訳書に「ザ・ローリング・ストーンズ物語」(日音楽譜出版)など。
- 関連サイト(外部サイト)
-
本文中に登場する主要人物について |
 |
Wilson Pickett (ウィルソン・ピケット) サザン・ソウル、アトランティック・ソウルの代表的シンガー。幼い頃からゴスペルを歌い、50年代末にゴスペル歌手としてデビュー。のちにソウルに転向し、ファルコンズのメンバーとなる。1964年にアトランティック・レコードに移籍し、「In The Midnight Hour」、「Land of 1000 Dances(ダンス天国)」といった現在でもR&Bの古典として知られるヒット曲を放った。 |
 |
亀渕昭信 (かめぶち・あきのぶ) 「オールナイトニッポン」では、1969年10月〜1972年6月および、1972年7月〜1973年6月にかけてパーソナリティを担当。同番組の「ビバカメショー」(72年7月〜73年9月)で人気DJとして一時代を築いたディスクジョッキー、音楽評論家。99年〜05年にかけてはニッポン放送の代表取締役社長を務めた。 |
 |
朝妻一郎 (あさづま・いちろう) 現フジパシフィック音楽出版代表取締役会長。ポニーキャニオン取締役、音楽出版社協会顧問(前会長)、日本音楽著作権協会(JASRAC)理事も務める音楽評論家、音楽プロデューサー。1966年に入社したパシフィック音楽出版(PMP)のディレクター時代には、フォーク・クルセダーズやジャックスのレコード制作を手掛ける。以来、大瀧詠一、山下達郎、サザンオールスターズ、オフコース等に関わる。一方で、1970年代までは音楽評論も続けていた。85年にPMPはフジテレビジョン(現フジ・メディア・ホールディングス)の子会社・フジ音楽出版と合併、フジパシフィック音楽出版と改称されるとともに社長に就任。その後もおニャン子クラブ、Winkなどに関わる。2008年には、自身の半生を振り返った著書『ヒットこそすべて 〜オール・アバウト・ミュージック・ビジネス〜』(白夜書房)を発刊している。 |
 |
高嶋弘之 (たかしま・ひろゆき) 高嶋音楽事務所代表。「ビートルズの日本での仕掛人」として有名な楽ディレクター、プロデューサー。1959年に東京芝浦電気に入社、レコード事業部に配属されディレクターとしてのキャリアをスタートさせる。翌60年にレコード事業部が分社化され東芝音楽工業(現・EMIミュージック・ジャパン)となったことに伴い同社に移籍。以後主に洋楽担当のディレクターとして活動。英EMI傘下のパーロフォンからデビューしたビートルズについても本国からのデビュー当初からその存在を知っていたため、ビートルズの日本における仕掛人として国内で様々なプロモーション活動を仕掛けた。その結果ビートルズは日本においても大ヒットを連発し、高嶋も一躍その名を知られるようになる。その後邦楽部門に移り、フォーク・クルセダーズや黛ジュン、ジローズなどのディレクターを手がけた後、1970年にキャニオンレコード(現・ポニーキャニオン)の設立に参加し、同社取締役制作部長に就任した。兄は俳優の高島忠夫。義姉は女優の寿美花代。バイオリン奏者の高嶋ちさ子は娘。 |
 |
Cliff Richard (クリフ・リチャード) バックバンドのシャドウズと共に、ビートルズ時代到来前の1950年代末から60年代初めにかけてイギリスのポップ・ミュージック・シーンを席巻したシンガー。1958年の夏に発売されたデビュー曲「Move It」は同年8月のブリティッシュ・チャートで3位を記録。ここからクリフ・リチャード栄光の50年が始まったと言われている。クリスチャンに改宗後、その音楽はポップスからロック寄りになる。アメリカにおいてはイギリスほどの成功を収めることはなかったが、イギリスでは映画やテレビにおいても成功し、いくつかの国でも同様の成功を収めた。 |
 |
Andrew Loog Oldham (アンドリュー・ルーグ・オールダム) 1960年代にローリング・ストーンズのマネージャーをしていたことで最もよく知られる音楽プロデューサー。ビートルズのマネージャー、ブライアン・エプスタインの下で彼らの宣伝係を担当後、ストーンズと関わるようになる。 オールダムはストーンズのためにマネージャー、レコード・プロデューサー、パブリシテイ担当の3つの役割を果たし、その宣伝の才能でストーンズを国際的な評判へ導いた。ストーンズを不良スタイルで売り出したのも、キース・リチャーズの「s」を外して「リチャード」にしたのも、ピアニストのイアン・スチュワートを正式メンバーから外したのも彼の提案であった。1965年にイミディエイト・レコードを設立、クリス・ファーロウ、スモール・フェイセズ、ロッド・スチュワート、P.P. アーノルドらのレコードをリリース。67年後半、ストーンズに解雇される。 |
 |
内田裕也 (うちだ・ゆうや) 兵庫県西宮市出身。1959年に日劇ウエスタンカーニバルにて本格的なデビューを果たす。以降、グループ・サウンズの内田裕也とフラワーズのヴォーカリスト、フラワー・トラベリン・バンドのプロデュース活動などを経て、1970年代後半からは俳優としても活躍し、映画出演や監督なども手掛ける。また、映画『コミック雑誌なんかいらない!』や『エロティックな関係』などでは脚本も担当した。1971年4月に当時発足したばかりのワーナー・パイオニア(現・ワーナーミュージック・ジャパン)のアトランティック・レーベルから、フラワー・トラヴェリン・バンドとして2ndアルバムとなる『SATORI』を発売。その後、72年2月に3rdアルバム「Made in Japan』、73年2月には72年年9月16日の横須賀文化会館でのライブ音源にスタジオ録音の新曲を加えた4thアルバム『Make Up』を発売。しかし、翌73年4月の京都円山公園でのコンサートを最後にフラワー・トラベリン・バンドは活動を休止する。同年、初のソロ・アルバム『ロックンロール放送局(Y.U.Y.A 1815KC ROCK'N ROLL BROADCASTING STATION)』を発表。10月には悠木千帆(現・樹木希林)と結婚。12月には年越しロックイベント「フラッシュ・コンサート」(NEW YEAR'S WORLD ROCK FESTIVALの前身)を開催。以来毎年行なわれ、2011年には38回を数える。74年8月に「ワンステップ・フェスティバル」、75年8月に「第1回ワールドロック・フェスティバル」の主催、ジェフ・ベックやニューヨーク・ドールズなどの来日に尽力するなど、70年代中盤からは日本国外のアーティストの招聘に労力を注いだ。 |
 |
Helen Shapiro (ヘレン・シャピロ) クリフ・リチャードのプロデューサー、ノリス・パーマーに見出されて、1961年に「Don't Treat Me Like a Child(子供じゃないの)」が英チャート3位、続くバラードの「You Don't Know(悲しき片想い)」と「Walking Back to Happiness(夢見る恋)」が1位に輝きポップスターの座についたイギリスのシンガー。日本では、弘田三枝子らによるカヴァーから人気に火が点き、64年には初の来日を果たしている。ブルース、ジャズ・スタンダードからガールポップまでを幅広く歌いこなす実力派。 |
 |
Billy Fury (ビリー・フューリー) 英リヴァプール生まれのポップ・シンガー、ソングライター。1960年から65年にかけて英国でトップ10ヒットを記録し、一時代を築いた。55年に自身のバンドを結成して活動を開始。58年には自身の曲でタレント・コンテストに優勝。デッカ・レコードと契約し翌59年にデビューし、初シングル「Maybe Tomorrow」が英国で18位を記録。60年代前半はクリフ・リチャードに迫る活躍で大成功を収めるものの、ビートルズの登場以降は徐々に勢いが衰え、66年にデッカ・レコードを去ってからはヒットに恵まれることもなかった。しかし、81年にポリドール・レコードと契約して復帰。翌82年には英国で16年ぶりに2曲がチャートインを記録している。 |
 |
John Leyton (ジョン・レイトン) 60年代前半、イギリスで最も人気があったシンガー、俳優のひとり。1961年に「Johnny Remember Me(霧の中のジョニー)」が全英1位となり、一躍スターの座を築いた。この曲は克美しげるのカヴァーなどで日本でも大ヒットした。また、大瀧詠一作曲の太田裕美「さらばシベリア鉄道」の元歌としても有名である。その後も「霧シリーズ」の続編「霧の中のロンリー・シティ」をはじめ、「Wild Wind」(全英2位)、「Son This Is She」(15位)などのヒットを記録。俳優としても「大脱走」、「ジェリコ作戦」など多くの映画、テレビに出演した。 |
 |
Lonnie Donegan (ロニー・ドネガン) 50年代に英国で大流行したスキッフル・ギターの第一人者。フォーク、ブルース、ジャズ、カントリーを見事に融合させ1950年代の音楽の礎を築き上げ、1958年から62年まで英チャートのトップ30に34曲を送り込むという偉大な記録を残した。中でも55年に発表した「Rock Island Line」は半年間に300万枚のセールスを記録し、ジョン・レノンはこの曲に熱心に耳を傾け、やがてはギターで演奏するようになったという。ほか、クリフ・リチャード、エリック・クラプトン、マーク・ノップラー、ロリー・ギャラガーらに多大な影響を与えた。イギリスの新しい音楽=ギターを中心にしたポピュラー・ミュージックのベースを創り出したと言える。 |
 |
Lulu (ルル) 60年代のイギリスで当時最年少のシンガーとしてデビューしたルル。1964年、16歳のときにデビュー・シングル「Shout」がヒット。67年には「To Sir With Love (いつも心に太陽を))」が全米チャート1位を記録し、スターの仲間入りを果たした。その後はテレビ番組などでも活躍。69年には、尊敬するレイ・チャールズの故郷アメリカ南部にあるマッスル・ショールズ・スタジオにてレコーディングを行ない、『New Routes』を発表している。2002年には、エルトン・ジョン、ポール・マッカートニー、クリフ・リチャード、ボビー・ウーマック、ウェストライフ、サマンサ・マンバら、彼女をリスペクトする数々のミュージシャンとコラボレイトしたアルバム『Together』が話題となった。 |
 |
The Golden Cups (ザ・ゴールデン・カップス) 1966年12月、神奈川県横浜市でデイヴ平尾を中心に結成されたグループ・サウンズ。結成当初のメンバーは、リード・ヴォーカルのデイヴ以下、リード・ギター、ヴォーカルのエディ藩、ベース、ギターのルイズルイス加部、リズムギター、ベース、ヴォーカルのケネス伊東、ドラムス、ヴォーカルのマモル・マヌー。その後は、後にゴダイゴのリーダーとして両バンドを兼務するミッキー吉野(キーボード)、ザ・カーナビーツのアイ高野(ドラムス)、柳ジョージ(ベース、ヴォーカル)などが途中時期に在籍した。1967年、シングル「いとしのジザベル」でレコード・デビュー。同シングルは18万枚のヒットを記録。68年の3rdシングル「長い髪の少女」はオリコン14位、35万枚のセールスを記録し、一躍人気グループの仲間入りを果たした。69年4月にエディ藩とケネス伊東が「エディ藩グループ」結成のために脱退している。 |
 |
Powerhouse (パワーハウス) 横浜出身の陳信輝(g,b,ds,p)、竹村栄司(vo)、柳ジョージ(b,vo)、野木信一(ds)によって日本初の本格的ブルース・ロック・バンドとして登場したパワーハウス。1969年に発表された唯一のアルバム『ブルースの新星〜パワー・ハウス登場』は、ビートルズ、ジミ・ヘンドリックス、クリーム、ウィリー・ディクソン、ヤードバーズなど全曲著名ナンバーのカヴァーで構成されているものの、ビートルズの2曲におけるブルージーなアレンジ、全体に漂うインプロも交えたヘヴィネスは、当時他のバンドとは一線を画していた。グループ解散後、陳はフードブレイン、スピード・グルー&シンキへ、柳はストロベリー・パス、ゴールデン・カップスなどを経て、柳ジョージ&レイニー・ウッドを結成。竹村はパワー・ハウス・ブルース・バンドを経て、ベイサイド・ストリート・バンドを結成している。 |
 |
Flower Travellin' Band (フラワー・トラヴェリン・バンド) 元4.9.1(フォー・ナイン・エース)のジョー山中(ヴォーカル)、元ビーバーズの石間秀樹(ギター)、元タックスマンの上月ジュン(ベース)、元フラワーズの和田ジョージ(ドラムス)の4人によって結成され、1970年10月、内田裕也のプロデュースによる1stアルバム『Anywhere』でデビュー。同年開催された大阪万博のライブ・ステージで競演したカナダのロックバンド、ライトハウスに誘われ、12月カナダ トロントへ出国。71年にはアメリカのアトランティック・レコードと契約し、アルバム「SATORI』をアメリカ、カナダで発表。東洋的旋律を持つ日本のオリジナル・ロックが、初めて世界のロック・カルチャーに名乗りを上げた歴史的瞬間となった。シングル「SATORI part2」はカナダ・チャートの8位を記録した。72年のアルバム『Made In Japan』、73年の『Make Up』の発表、京都円山公園音楽堂でのコンサート後に活動を停止。ちなみに、同年中止となったローリング・ストーンズの武道館公演では、フラワー・トラヴェリン・バンドがオープニング・アクトを務める予定だった。2008年に活動を再開し、「フジ・ロック・フェスティバル08」への参加、アルバム『We are here』を発表している。 |
 |
The Spiders (スパイダース) 1961年に、田邊昭知(現・田辺エージェンシー社長)が結成し、ジャッキー吉川とブルーコメッツとともにGSの礎を築いたザ・スパイダース。65年にシングル「フリフリ」でデビュー。リーダーでドラムスの田邊以下メンバーは、加藤充(ベース)、かまやつひろし(リズムギター、ボーカル)、大野克夫(オルガン、ピアノ、スチール・ギター)、井上孝之(現:井上堯之)(リードギター、ボーカル)、堺正章(ボーカル、タンバリン、フルート)、井上順(ボーカル、タンバリン、パーカッション)、前田富雄(ドラムス)。当時の音楽の先端であったマージー・ビートやブリティッシュ・ビートに強く影響を受けたサウンドで、「ノー・ノー・ボーイ」、「ヘイ・ボーイ」、「サマー・ガール」はヒットこそ記録しなかったものの若者の間で熱狂を生み、その後「夕陽が泣いている」、「なんとなくなんとなく」、「あの時君は若かった」の大ヒットにより一躍スターダムにのし上がった。また、来日した外国アーティストの前座やバック演奏をこなすことも多く、バックでは64年のピーター&ゴードン、前座では65年1月と9月のベンチャーズ、6月のアニマルズ、8月のザ・サーファリーズ、ザ・ハニカムズ、66年のザ・ビーチ・ボーイズで務めている。1970年に解散。 |
 |
クレイジー・キャッツ 元々は「キューバン・キャッツ」の名で活動を開始し、進駐軍のキャンプ回りをしていた際、演奏中に洗面器で頭を叩くギャグがウケて、"You, crazy."と言われたことから「クレイジー・キャッツ」に改名したとされている、60年代に一世を風靡したコミックバンド。1955年の結成当初のメンバーは、ハナ肇、犬塚弘、萩原哲晶、橋本光雄、柴田昌彦、南晴子、筑波礼子。56年2月に谷啓、3月に石橋エータローが加入。3〜6月の間に、「ハナ肇とクレイジー・キャッツ」へと改称した。57年3月に植木等、9月に安田伸が加入。この頃からテレビ番組などに進出し、「おとなの漫画」(フジテレビ)、「シャボン玉ホリデー」(日本テレビ)などへの出演をきっかけに人気が爆発。映画でもクレージーの出演作は東宝のドル箱シリーズとなり(東宝クレージー映画)、挿入歌として発表されたシングル「スーダラ節」、「ハイそれまでョ」、「ドント節」なども軒並み大ヒットを記録した。 |
 |
Peter & Gordon (ピーター&ゴードン) ロンドンにあるウェストミンスター・スクールで出会ったピーター・アッシャーとゴードン・ウォーラーによって結成され、1964年に、「レノン/マッカートニー作品」である「A World Without Love(愛なき世界)」が全米1位のヒットとなり、一躍有名になったブリティッシュ・インベイション時代のデュオ。エヴァリー・ブラザーズ風のコーラスを取り入れ、本国イギリスだけでなくアメリカでも多大な人気を得た。65年に初来日コンサートを行なっている。67年に発表した「Lady Godiva」と「Sunday for Tea」以降ヒットから遠ざかり、68年に解散している。その後、ピーターは海を渡ってアメリカでプロデューサーとして成功し、リンダ・ロンシュタット、ジェームス・テイラー、シェールなど70年代に多数のヒットを世に送り出している。2005年には、37年ぶりの再結成を果たしている。 |
 |
Honeycombs (ハニーカムズ) チャーミングな女性ドラマー、ハニー・ラントリーを擁したハニーカムズは、「Have I the Right?」、「I Can't Stop」、「That's The Way」のヒットなどで知られる5人組。エコーを駆使した音作りで知られるプロデューサーのジョー・ミーク、作詞・作曲チームにハワード&ブレイクリーという強力なバックアップ陣営の下、1964年にシングル「Have I The Right?」でデビュー。イギリスで1位、アメリカでもトップ5に入る大ヒットを記録し、世界的な人気グループとなった。65年には、イギリスのグループとしてはピーター&ゴードンに次いで2組目となる来日を果たし、そのときに「Love In Tokyo」という曲を録音している。 |
 |
The Animals (アニマルズ) エリック・バードン(ヴォーカル)、アラン・プライス(オルガン、ピアノ)、さらには、チャス・チャンドラーはジミ・ヘンドリックスを見出したことでも知られるチャス・チャンドラー(ベース)らによって結成され、1960年代半ばにビートルズなどと共に世界的に人気を博したブリティッシュ・インベイジョンの代表格バンド。アメリカのブルースに根ざした作風が特徴で、ジョン・リー・フッカーの「Boom Boom」などをカヴァーしている。対照的にシングル曲にはヒットを意識して、ブリル・ビルディング系の作曲家の作品が多く取り上げられている。「The House Of The Rising Sun(朝日のあたる家)」が最大のヒット曲として知られ、これはアメリカの伝統的なフォーク・ソングを、ブルース的な解釈でカバーしたもの。日本でも「Don't Let Me Be Misunderstood(悲しき願い)」が尾藤イサオにより日本語カバーされるなど人気を博した。66年に解散した後、本拠地をサンフランシスコへ移し「エリック・バードン&ジ・アニマルズ」として再始動。グレイトフル・デッド、ジェファーソン・エアプレインらとシスコ・サウンドの一翼を担った。 |
 |
Ventures (ベンチャーズ) ドン・ウィルソンとボブ・ボーグルによって1959年に結成された、日本に於いてはビートルズと並び、日本の音楽業界に影響を与えたバンドとされているインストゥルメンタル・バンド。60年の全米メジャー・デビュー曲「Walk, Don't Run(急がば廻れ)」で、地元シアトルのラジオ局がニュース番組のテーマ曲として起用した事から火が点き、瞬く間にビルボード誌のヒットチャート第2位を記録した。初来日は62年だが、実際に日本で人気が出たのは2回目の来日となる65年のアストロノウツらとのパッケージ・ツアーから。シグネイチャー・モデルのモズライト・ギターで真空管アンプのもつダイナミックなサウンドを奏で、たちまち日本の若者たちをとりこにし日本に大エレキ・ブームを巻き起こした。いわゆる 「テケテケ」と呼ばれるクロマティック・ラン奏法のサウンドと共に、「Diamond Head」、「Pipeline」、「Slaughter On Tenth Avenue (10番街の殺人)」、「Walk, Don't Run」、「Caravan」など数々のヒット曲を生み出した。彼らが本国米国で一番人気があったのは60年代だが、一方日本では長く人気を保ち、来日回数は今年の1月で61回目。2010年4月に日本政府から叙勲受章(旭日小授章)を授与。 |
 |
Them (ゼム) ヴァン・モリソンが在籍したことで知られる、北アイルランドの工業都市ベルファストで結成されたゼム。1964年にデビュー。初期のレコーディングにはスタジオ・ミュージシャンとしてジミー・ペイジも参加していた。同年末にシングル「Baby Please Don't Go」のB面「Gloria」がヒットして名を上げる。「ストーンズのミック・ジャガーとアニマルズのエリック・バードンを足して2で割ったような」と称されるソウルフルな歌声を特徴とするヴァン・モリソンのヴォーカルを最大の武器としたリズム・アンド・ブルース・バンド。66年にモリソンが脱退した後もアルバムを発表し、70年代初頭まで活動を続けた。79年にモリソン抜きで一時的に再結成している。 |
 |
Walker Brothers (ウォーカー・ブラザーズ) スコット・ウォーカー、ゲイリー・リーズ(後のゲイリー・ウォーカー)、ジョン・ウォーカーと共にアメリカで結成されたグループ。イギリスに渡った後にフィリップス・レコードと契約し、1965年にシングル「Pretty Girls Everywhere」でデビュー。2ndシングル「Love Her」は全英チャート20位、3rdシングル「涙でさようなら」は全英チャート1位のヒットを記録した。以降も「太陽はもう輝かない」、「孤独の太陽」、「ダンス天国」等のヒットを放ち、メンバーのルックスも手伝って、イギリスのみならずヨーロッパ、オセアニア諸国、日本などで一時はビートルズに匹敵する高い人気を得た。 |
 |
Howlin' Wolf (ハウリン・ウルフ) マディ・ウォーターズと並びストーンズに最も大きな影響を与えた、米ミシシッピ州ウェストポイント生まれの黒人ブルース・シンガー。本名チェスター・アーサー・バーネット。1952年からシカゴに拠点を移し、以後ウルフが亡くなるまで相棒として活躍したギタリスト、ヒューバート・サムリンがセッションに参加するようになる。59年に初のLP『Moanin' In The Moonlight』を発表。その後チェスから発表された主なLPには、『Howlin' Wolf』、『Real Folk Blues』、『More Real Folk Blues』、『Change My Way』(編集盤)などがある。ウルフの個性と存在感はストーンズ、クリームら60年代に活躍したイギリスのロック・ミュージシャンたちに大きな影響を与えた。ストーンズの「Little Red Rooster」、クリームの「Spoonful」、ドアーズの「Back Door Man」、ジェフ・ベック・グループの「I Ain't Superstitious」などカヴァーにも枚挙に暇がない。71年にローリング・ストーンズ・レコードからリリースされた『London Howlin' Wolf Sessions』には、ウルフに憧れる英国ロッカーが大挙参加。エリック・クラプトン、スティーヴ・ウィンウッド、リンゴ・スター、クラウス・フォアマン、ストーンズのビル・ワイマンとチャーリー・ワッツ、ストーンズのサポート・ピアニストだったイアン・スチュワートらが参加した。 |
 |
Grateful Dead (グレイトフル・デッド) 60年代のヒッピー文化、サイケデリック文化の申し子的アーティストであるグレイトフル・デッドは、1965年にジェリー・ガルシアを中心にサンフランシスコで結成された。ロック、フォーク、ジャズ、ブルーグラス、カントリー、ブルース、サイケデリック・ロックなど様々な要素を内包し、さらには、ライブの長時間に渡る即興演奏を信条としていたこともあり、現在においてジャムバンド系グループの元祖としても称えられている。「デッドヘッズ」と呼ばれる熱狂的な追っかけファンが多く、ヒット・チャートとはほとんど無縁の存在ながら、毎年のようにスタジアム・ツアーを行ない、常にアメリカ国内のコンサートの年間収益では一、二を争う存在だった。メンバーの脱退や死亡によるメンバー・チェンジを頻繁に繰り返しながらも精力的なライブ活動を続け、日本では知名度が高くないが、本国ではアメリカを代表する伝説的バンドとして認識されている。 |