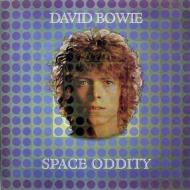2010年5月20日 (木)

ローリング・ストーンズ『メイン・ストリートのならず者』デラックス・エディションの発売を記念しておくる、HMVスペシャル・インタビュー企画。題して「メイン・ストリートのならず者、もしくは、ローリング・ストーンズをはてしなく語る夕べ」。
第3回目のゲストは、「レコード・コレクターズ」編集長の寺田正典さん。編集長である以前に筋金入りのストーンズ・マニアでもある寺田さんは、ときに冷静、ときに熱っぽい独自のストーンズ論がレココレ誌上でも人気。今回の『メイン・ストリートのならず者』デラックス・エディション国内盤においても、ボーナス・ディスク向けのライナー/曲解説の執筆をご担当されているということで、すでに”ならず者”モードは全開。
スタジオ録音における”二層構造”説、グリマー・ツインズのパワー・バランス、奇才ビル・プラマーの貢献、ストーンズ・チルドレン〜孫世代のアティテュード、「彼に会いたい」再評価・・・湯水のごとく湧き出てくる寺田さんのストーンズへの愛情、叱咤激励、教育的指導諸々は、「レコード・コレクターズ」最新号とこちらのインタビューで、ご確認どうぞ!
インタビュー/構成: 小浜文晶
- --- 本日は宜しくお願いいたします。今回、寺田さんは、『メイン・ストリートのならず者』デラックス・エディション国内盤のボーナス・ディスク向けのライナー/曲解説をご担当されているそうですが、まずは、そのボーナス・ディスク収録の未発表楽曲についてはどのようなご感想をお持ちになりましたか?
ちょっとびっくりしました。その理由は2つあって。昔からのファンにとっては“アンダーグラウンド”でおなじみだった曲が一部収録されていたということと、今のミックの声が聴こえてきたという、この2点ですね。
- --- その中でも「Plundered My Soul」は、アメリカの「レコード・ストア・デイ」イベント用の限定7インチ・シングルとしてリリースされているようですね。
この曲にも最近のミックの声が入っていて驚いたという印象が強いですね。
今回の『メイン・ストリートのならず者』のリニューアル・プロジェクトに関しては、(註)「ROLLING STONE」誌とイギリスの(註)「UNCUT」誌でミックとキースがすでにインタビューを受けていて・・・まぁ新曲に関しては真相にあまり触れていない感じもありましたが(笑)。

(註)「Rolling Stone」、「Uncut」のローリング・ストーンズ特集・・・『メイン・ストリートのならず者』を特集した米版「ROLLING STONE」誌1104号。表紙は、ノーマン・シーフが撮影したミック・ジャガーとキース・リチャーズのポートレイト、2バージョン。記事内容はまったく一緒だが、当時のネルコートでの制作秘話に関するミックとキースそれぞれのインタビューがかなり興味深い。また、英「UNCUT」2010年4月号においても特集が組まれ、こちらの表紙はキース・リチャーズ。付録のフリーCD「Rip This Joint」には、イアン・ハンター、ダン・ベアードなど『メイン・ストリートのならず者』録音当時のストーンズの音に影響を受けた16曲を収録している。両誌ともに現在入手は困難だそう。
その「UNCUT」によると、「”Exile Period”、つまり”Exileの時期”というのを明確に決めた」とミックが語っています。今回の未発表サイドにも収録されている「Loving Cup」(別ヴァージョン)が、まずは69年6月にロンドンのオリンピック・スタジオで録られていて、そこから最後72年3月までL.A.はハリウッドのサンセット・サウンド・スタジオで作業が行われているわけなんですね。その合間に(註)スターグローヴスというミックのイギリスの別荘で録音したものがあったり、南フランスのキースのネルコート邸の地下室で録られたものなんかがある。ようするに、69年の6月から72年の3月までに録音されたマテリアルを一区切りとしてディスク2にまとめようと決めたんですね。ただし、その時期のマテリアルはあくまでベースとしながら、さらに追加でレコーディングを行ったということです。
その中で一体どのぐらい追加レコーディングをするのかな? というところでは、思った以上に大胆にやっているな、と(笑)。 と同時に「Loving Cup」なんかはおそらく69年当時の歌入れのテイクをそのまま採用していると思うので、追加でレコーディングされた今のミックの声と並んで出てくると、ミックの歌い方や声質がこんなにも大きく変わっているものなのかということをあらためて感じましたね。

(註)ミック・ジャガーのスターグローヴス邸・・・イギリスはニューバリーにあるミック・ジャガー所有の別荘で、1970年に5万5000ポンドで購入したという。その広大な敷地と部屋面積からしばしばローリング・ストーンズ・モービルを持ち込んだレコーディングが行われ、『Sticky Fingers』、『メイン・ストリートのならず者』に収録された一部楽曲の初期テイクやデモ、さらに『It's Only Rock'n Roll』などがこのスターグローヴスで録られている。また、レッド・ツェッペリン『Physical Graffiti』所収の「Black Country Woman」が同邸宅内庭園で、5thアルバム『聖なる館』がスターグローヴス敷地内に乗りつけたモービルで録音されている。98年にはロッド・スチュワートが250万ポンドで購入したものの、一度も生活拠点を置くことなく数ヵ月後に売りに出している。
- --- ミックの歌い方の変遷については、寺田さんは以前から「レコード・コレクターズ」誌上をはじめ様々なところでかなり興味深い考察をされていますよね。
ミックは、ソロ・アルバムを出すようになってから歌い方に新しいクセが出てきたなということを何となくは意識していて、以前ミックに電話インタビューをした時に「ソロの時とストーンズの時とで歌い方を変えていたりするのですか?」と訊いてみたんですが、「そんなことはないよ」と(笑)。
- --- (笑)ご本人がきっぱりと・・・
だから今考えてみると、ソロとローリング・ストーンズとの間で歌い方を変えていたんじゃなくて、ミックの歌い方そのものが変わってきているんだなと実感しましたね。ソロを契機にしてそうなった部分もあるかもしれませんが。
そういう意味でも、基本的には“お蔵出し”ディスクではあるんですが、単純なお蔵出しというわけではなく、結局今のローリング・ストーンズとして、あえて言えば今のミック・ジャガーとして世の中に出したい音ということで作り込んできたんじゃないかなと思うんですよ。クレジットを見てみるとエンジニアは全曲、(註)ボブ・クリアマウンテンになっていますし。以前に僕らが“アンダーグラウンド”で聴いていた仮ミックスの段階にあった曲にしても、イチからミックスをし直しているから、知ったような曲でも実はミックスが全く違っているというのもあるんですね。だから、かなり丁寧で細かい作業をやってきているんだなということを感じました。

(註)ボブ・クリアマウンテン・・・70年代から現在に至るまでに第一線で活躍する名ミックス・エンジニア。ストーンズ作品は、『刺青の男』、『Still Life』、『Stripped』、『Live Licks』のミキシングを担当しており、最近では、映画『Shine A Light』を手掛けていることでも有名。80年代からニューヨークのパワー・ステーション・スタジオを拠点に、ロキシー・ミュージック『Avalon』、ブルース・スプリングスティーン『Born In The U.S.A』、ブライアン・アダムス『Reckless』、ホール&オーツ『Big Bam Boom』、ボン・ジョヴィ『These Days』などのミックスを手掛け、ドラムに重きを置いたシャープでソリッドなロック・サウンドのスタンダードを作り上げた。 - --- では、当初の情報どおり今回のリニューアル・プロジェクトに関してはほとんどミック主導で行われていたというのは間違いなさそうなんですね。当時の『メイン・ストリートのならず者』はキースが中心になって制作されていたらしいのですが、40年近くの時を経て今回なぜまたミックが積極的に動いているのか? というのが素朴な疑問でもあるのですが。
実は最近色々なところで話しているんですが、“ミック主導”対“キース主導”というバランスの中の“キースが中心になってやっていたであろう”ということが、かなりミック寄りに転んだりしてまして・・・
- --- 180度覆っているものもあるんですか?
いちばん多い例としては、ギターの関係で。キースによるギターだと思っていた何割かは実はミックだったとか。
- --- 「レココレ」誌上に寄稿されていた「Brown Sugar」の件にしてもそうですよね。
そうなんですよ。あのリフを作ったのも実はミックではないかと。もちろんキースが弾き直しているんで、キースらしさというのが最終的に表れてはいるんですけど。だから、ミックとキースが5割ずつでやっているとこれまで言われていた関係は、実はバランス的にもミックのディレクションが最終的には大きいのかなと、最近思い始めてるのがひとつあって。
それからもうひとつ。先ほどの「UNCUT」での“両者の意見にズレがある”インタビューでも語られていることなんですが(笑)、どうやら南フランスでのレコーディングはキースの中では「かなりうまくいった」という解釈。ところがミックはあまりその出来に満足していなかった。で、ストーンズは60年代から主要なレコーディングはほとんどアメリカで、特にハリウッドで行っていましたから、この時も同じように71年の暮れあたりからL.A.にテープを持っていくんですね。まぁドラッグ問題で南フランスにいれなくなったということもあったんですが、その時の考え方としてキースは「もうちょっとなんとかすればアルバムは完成するぞ」、逆にミックは「相当L.A.でいじらないとダメだな」って思っていたようなんですよね(笑)。
実際、ミックは結婚したばかりで、しかも奥さんのビアンカが、後に「Fool To Cry」で歌うこととなる娘のジェイドを妊娠していたこともあって、彼女が住むパリに飛んでいってしまうことが多かった。そうした部分でも、基本的なレコーディングはキース主導で行われていた可能性はかなり高いんですよ。けれども最後のL.A.での作業は2人がっちりというか、どちらかといえばミックが「もっと色々詰めようよ」と言っていじったんじゃないかなと思うんですね。- --- ミックは新婚気分も一息ついて、遅まきながら本腰を入れ出したのが最終ミックスの段階、という捉え方は自然ではありますよね。
『メイン・ストリートのならず者』をストーンズのアルバムとして最終的にどんな装いで出すのが適してるかということに関しては、やっぱりミックのディレクションが当時もかなり入っていたのかなって思っていますし、その延長としての今回の未発表プロジェクトだとも思うんですよね。歌詞もなければ当然歌も入っていない未完成のアウトテイクに対して、もちろん72年当時のL.A.においてもあれこれと知恵を搾り出し完成にこぎ着けようとする作業はやっていたとは思いますし、それを2009年から2010年にかけてもやっていると。さらに言えば、これは僕の完全な予測なのですが・・・歌入れも含めて2009年〜2010年のレコーディングだけじゃないかもしれない。
- --- 72年から現在に至る途中で、折りにふれしばしば手直しや追加が行われていた可能性も・・・?
あるということです。それを裏付けるポイントとして、81年に『刺青の男』というアルバムがありましたよね。70年代のアウトテイクをかなり使っていると言われていて、有名なところでは「Tops」という曲。あれはまだミック・テイラーが在籍していた『山羊の頭のスープ』の頃のジャマイカ・セッションが使われているし、「Waiting On A Friend」もそうだと言われている。「Slave」や「Worried About You」なんかにしても『Black And Blue』のセッションだと言われている。その頃の未完成だったテイクに歌を加えたりミックスをし直しているんですね。その時もボブ・クリアマウンテンだったんですけど、最新のミックスを施して出したら、それがいちばんウケたという(笑)。
『メイン・ストリートのならず者』にしても、結局はさっき言った「Loving Cup」のように69年から取り組んでいる曲を収録しているわけなんですよ。69年には『Let It Bleed』、さらに71年には『Sticky Fingers』とその間2枚アルバムを出していて、それぞれがオリンピック・スタジオ、ミックのスターグローヴスで録られたものがかなり使われている。ようするに、ミックが“Exileの時期”とインタビューで言っているものは、『Let It Bleed』や『Sticky Fingers』のアウトテイクも含めて72年にまとめ直したものが『メインストリートのならず者』だったということになるわけですよね。
だから、そうしたアウトテイクを基にしたリ・レコーディング・スタイルというのはずっと続いていて、この未発表ボーナス・トラックというのは、『メイン・ストリートのならず者』のアウトテイクスであると同時に、ローリング・ストーンズというバンドがスタジオ録音をどのように考えて、どういうやり方でレコードを作ってきたのか、ということを教えてくれるものでもあるんです。- --- それだけ深いものであると。
キースの「Happy」にしても、(註)ポール・バックマスターの名前がストリングスでクレジットされているのがちょっと不思議なんですよね。ストリングスなんか全く聴こえないし、ポール・バックマスターといえば『Sticky Fingers』の「Sway」や「Moonlight Mile」でのストリングスですからね。それを考えると、「Happy」は『Sticky Fingers』を制作しているときのアウトテイクで、当初はストリングスが入っていたけど、そこにホーンを被せて消してしまったのかな?・・・とか。
さらに推測すれば・・・94年の『Voodoo Lounge』ぐらいのアウトテイクも入っているんじゃないかなと(笑)。というのは、ストーンズの歴史の中では『Voodoo Lounge』の時にしかクレジットが残っていないストリングス・アレンジャーのデイヴィッド・キャンベル氏、ベックのお父さんなんだそうですけど、その人の名前も今回クレジットされているんですね。この追加レコーディングのためにまた呼んだのかな?それとも『Voodoo Lounge』の時期の・・・という気はするわけですよ(笑)。

(註)ポール・バックマスター・・・イギリス出身のチェロ奏者/作曲家/ストリングス・アレンジャー。古くはエルトン・ジョン、デヴィッド・ボウイ、ブラッド・スウェット&ティアーズ、レナード・コーエン、ニルソン作品のストリングス〜ホーン・アレンジを手掛けたことで有名。また、バックマスター独特の空間を生かしたリズムのとり方は、『Bitches Brew』、『On The Corner』といったいわゆるエレクトリック期のマイルス・ディヴィスにも多大な影響を与えた。
(註) ポール・バックマスターがストリングス・アレンジを手掛けた主なアルバム
やっぱりそう考えると、ベーシック・トラックの録音と、歌入れを含めたオーヴァー・ダビングや編集作業というのを全く“1対1”の関係にしてレコードを作っているわけではないという結論に至ってしまうんですよね。勢いで色々とレコーディングはするんだけれど、さらにその時代に見合ったアイデアで編集し直す、整理し直すという作業をいつもやってきていて、その中には“寝かせて”きたものも時々使っているのかなと。
『刺青の男』ほど激しく過去のアウトテイクを使っているものはないにしろ、ストーンズっていうのは実はそういうバンドなんだなと。わりと一発録音で何も手を加えず、「それがロックンロールだぜ」っていう感じで捉えられがちですけど(笑)、その作業が丁寧かどうかは別として、こうした二層構造、つまり“ダブル・レイヤー方式”(笑)でレコーディングが進んでいる不思議なバンドなんだなとあらためて思いました。- --- そこで例えば「よし、もうちょっと寝かせておこう」という決定権みたいなものは、やはり最終的にはミックにある感じなのでしょうか?
ミックじゃないかなとは思うんですけど・・・ただ72年の『メイン・ストリートのならず者』のL.A.でのレコーディングで当時の色を足すという中で、やっぱり大きかったのは、日本で言うところの「L.A.スワンプ」と呼ばれていた70年代前半に流行ったアメリカ南部志向の音にしたいと考えたことだと思うんですよ。そこで、そういう音にするために、ヴェネッタ・フィールズ、クライディ・キングといったゴスペル系バックグラウンドを強く持った女性ヴォーカリストを参加させたというのがひとつ大きいのと、もうひとつはDr.ジョンを呼んでいることなんですが、そのDr. ジョンに「ちょっと手伝ってくれよ」と連絡を入れたのが実はキースじゃないかと言われていて・・・
- --- ミックではなく? Dr.ジョンのアルバムにミックは参加もしていましたし、てっきりミックのコネクションで参加したのかと思っていました。
ロンドンで録音された(註)『The Sun, Moon And Herbs』というアルバムですよね。その流れで全部つながりそうなものなんですけど、意外なところにキースの名前が出てきたりして・・・だから、キース、キースと思っているとミックだし、ミック、ミックと思えば時々キースかなということもあって、この2人の関係っていうのは実はまだまだ理解できてないなと思わされる部分があります(笑)。
- --- Dr.ジョンの参加にキースが一枚噛んでいたという新説に対して、逆にグラム・パーソンズと頻繁に連絡を取り合っていたのが実はミックだったという可能性は?(笑)
それはないと思うんですが(笑)、グラム・パーソンズに関しては、彼が具体的にどこまでこのアルバムに参加していたのかはっきり判っていないんですよね。色々説はあるんですが、グラムの自伝には「<Sweet Virginia>を録音するときには、ただ横に座っていただけ」と書かれていたり。
- --- ネルコートでの写真は残っていますよね。
ドミニク・ターレ氏が撮った写真の何枚かには写っているので、ネルコートにいたことはたしかです。だから、わざわざフランスにまで行って録音に参加しないかな? とは思うんですが(笑)。キースとは仲が良かったけど、ミックは少し距離を置きたがっていた・・・とか。
- --- ネルコートで撮られた、(註)ミック、キース、グラムの3人がテーブルを囲んで談笑している写真では、ミックがやや神妙な面持ちというか、キースとグラムの仲睦まじい関係に少し嫉妬の表情を浮かべているような気もするんですが(笑)・・・
ひょっとしたらL.A.の最終作業で、「これ、グラムの声?」(ミック)、「そうだぜ」(キース)、「じゃ消そう」(ミック)、みたいなことがあったかもしれない(笑)。
ただ、わりとミック中心だと思った方が考えやすい気はしていますけどね。キースはどちらかというとその時のノリを大事にして進もうとして、それをミックが「待て待て」と嗜める(笑)。時代時代の中で常に輝いているものにしたいという強いこだわりを持っているのはミックの方なんじゃないかなと、つい思ってしまうんですが・・・むしろレコーディングにおけるミックとキースの役割分担の謎というのは、僕の中で深まる一方(笑)。
今回の再発では1曲ごとに詳細なパーソナルが記載されていて、その中でかえって疑問が深まったものとして「Stop Breaking Down」があったんですよ。「なぜブルース・ナンバーの<Stop Breaking Down>では、ミック・ジャガーとミック・テイラーのギターが中心になるのか?」 と。
新しく記載されているパーソナルでは、ギターが3本入っているということになってるんですが、メインはどうも2人のミックみたいなんですよね。ただミック・ジャガーのリズム・ギターのピッキングがあまりにも絶妙すぎて、当初、僕はミック・ジャガーじゃないと思っていたんです。ところが、それがミック・ジャガーによるギターだというのを証明したのが、『A Bigger Bang』に入っていた「Back Of My Hands」だったんですね。あれはオリジナル曲ですが、ロバート・ジョンソン・スタイルをとったブルースなんですよね。「Stop Breaking Down」はシャッフルではなく、あえて8ビートにしているんですが、「Back Of My Hands」と同じようなスタイルで演奏されている。だから、ミック・ジャガーのフィンガー・ピッキングで弾くと、「Back Of My Hands」や「Stop Breaking Down」みたいになるんだなということが判ったんです。キースがピックで弾いている感じとはたしかに違う。
あと、これについてもあまり触れられないんですけど、「Stop Breaking Down」でのミック・テイラーのスライドもものすごい。僕はスライド・ギターにそこまで詳しいわけではないんですが、スライド・ダウンして開放弦の音を鳴らして、それを巧みに入れつつ次のフレーズにリズミカルにつなげていくっていう技がすごいんですよ。その技を応用した「All Down The Line」の72年のライヴもかなりすごい。ちなみにこの曲の要素はそのまま(註)エアロスミスの「Draw The Line」に流れ込んでいますけどね。あと、「Soul Survivor」は曲として突出しているわけではないんですが、当時のスワンプな雰囲気を持つスライド・ギターの響かせ方という点においては、ものすごく影響力は大きいと思うんですよ。
- --- ミック・テイラーは、『Sticky Fingers』の録音時よりさらにバンドになじんだというか、主張も含めて自分のプレイスタイルを強く出せるようになってきたということでしょうか?
「Ventilator Blues」で作曲クレジットをもらえているぐらいですから、そうなんでしょうね。この曲に限っていえば、リフとかフレーズとか骨格となるほとんどを作っているんだと思います。
あと、このアルバムで大きいのはやっぱりホーン隊ですかね。『Sticky Fingers』でも入っているけど、『メイン・ストリートのならず者』では、南フランスで一緒に合宿もしているし、その直前にはツアーも回っている。さらにはキースとボビー・キーズは生まれた日が同じで、“ソウル・ブラザー”のような関係(笑)。だから、ボビー・キーズもジム・プライスもすでに「デラニー&ボニーのホーン隊」というよりは、「ローリング・ストーンズのホーン隊」という風になっているんですよね。
ジム・プライスという人は、71年に(註)『Kids Nowadays Ain't Got No Shame』というソロ・アルバムを出しているんですけど、そのアルバムは、ジミー・ミラーのプロデュースで、ローリング・ストーンズ・モービルを使ってミックのスターグローヴスで録音されているんですよ。ということは、『Sticky Fingers』や『メイン・ストリートのならず者』の一部楽曲と全く同じ頃。アルバムのジャケット裏にはそのときのスターグローヴス邸の様子も載っているんです。それぐらいファミリーとしての関係ができあがっていたんですね。

(註)ジム・プライス「Kids Nowadays Ain't Got No Shame」(CD廃盤)・・・ストーンズ以前にはビートルズ、B.B.キング、デラニー&ボニーやジョー・コッカーのマッド・ドッグス&イングリッシュメンといったスワンプ・サークルへのセッション参加で、泥くさいテキサス・ハイノートを轟かせていたジム・プライスの71年1stソロ・アルバム。プロデュースは、この時期のストーンズ諸作と同じくジミー・ミラー。さらに、ボビー・キーズ(sax)、ニッキー・ホプキンス(p)、クラウス・ブーアマン(b)、ジム・ケルトナー(ds)といったストーンズ、あるいはジョージ・ハリスン、ジョン・レノンのソロ作品でもおなじみのアーシーなメンツが集合。ミックのスターグローヴス邸にローリング・ストーンズ・モービルを持ち込んでの録音で、プライス自身は各種ホーン、キーボード、ヴォーカルとマルチぶりを発揮。『Sticky Fingers』や『メイン・ストリートのならず者』からスピンオフして世に出た最高の副産物ともいえるだろう。2002年にユニバーサルからCD化されたが現在は廃盤。 - --- こうしたファミリーやクルーの形成というのは、レオン・ラッセルのシェルター・ピープルなどに影響されてそこに倣っていた部分も大きかったのでしょうか?
シェルターにしても、レオン・ラッセルがロンドン・レコーディングをあえてやっていること自体は、業界的な話題にしたいっていうのもあったんでしょうけど、イギリス勢(スワンプ)の空気も吸いたいっていうのが大きかったんじゃないでしょうか。アメリカ勢主導だとは思いますけど、当時のスワンプ作品はけっこう英米の合作が多かったようなので。その人脈が最後に集結するのが、ジョージ・ハリスンの『Concert For Bangladesh』だったりするんですけどね。そうした当時のストーンズ・ファミリーの中核を担っていたスワンプ・ファミリーの人たちも調べれば調べるほど、おもしろいつながりが浮き上がってきますよね。
そうしたストーンズ・ファミリーも、74年の『It's Only Rock'n Roll』のレコーディング途中で崩壊してしまうんですけどね。みんなヤクだらけになって(笑)。アンディ・ジョンズが連中についていけなくなって抜け、アンディと同じ歳で仲の良かったミック・テイラーも不安を覚えたときに、ちょうどジャック・ブルースからセッションの誘いがあって、そっちにばかり顔を出しているうちに結局脱退することになると。ジミー・ミラーもヤクにハマってほとんどスタジオに来なくなりやがてクビになる。さらにローリング・ストーンズ・レコード初代社長のマーシャル・チェスもこの前後に辞めているんですよ。だから、70年前後あたりからのストーンズの黄金期というのは意外と短くて、しかも本当にいいものが録音されていた時期っていうのは、ミックがインタビューで言っていた“Exileの時期”、つまり69年から72年なのかもしれないということですよね。
ローリング・ストーンズ その他の記事はこちら
 【スペシャル・インタビュー企画 第1回】 仲井戸 ”CHABO” 麗市
【スペシャル・インタビュー企画 第1回】 仲井戸 ”CHABO” 麗市
 【スペシャル・インタビュー企画 第2回】 ピーター・バラカン
【スペシャル・インタビュー企画 第2回】 ピーター・バラカン
 【スペシャル・インタビュー企画 第4回】 サエキけんぞう
【スペシャル・インタビュー企画 第4回】 サエキけんぞう
 【スペシャル・インタビュー企画 第5回】 中川敬 (ソウル・フラワー・ユニオン)
【スペシャル・インタビュー企画 第5回】 中川敬 (ソウル・フラワー・ユニオン)
 【スペシャル・インタビュー企画 最終回】 〈特別対談〉越谷政義 × 石坂敬一
【スペシャル・インタビュー企画 最終回】 〈特別対談〉越谷政義 × 石坂敬一
 『メインストリートのならず者』の真実
『メインストリートのならず者』の真実
 HMVオリ特決定! 『メインストリートのならず者』
HMVオリ特決定! 『メインストリートのならず者』
 【解剖】 『メインストリートのならず者』
【解剖】 『メインストリートのならず者』
 SHM-CD/紙ジャケ・ボックス第2弾
SHM-CD/紙ジャケ・ボックス第2弾
 ストーンズ 真夏のネブワーズ祭 1976
ストーンズ 真夏のネブワーズ祭 1976
|
Exile On Main Street スーパー・デラックス・エディション |
その他のバージョン
 国内盤
¥3,800
国内盤
¥3,800デラックス・エディション(デジパック) 2010年05月19日
 国内盤
¥2,200 2010年05月19日
国内盤
¥2,200 2010年05月19日
 国内盤
¥2,800
国内盤
¥2,800限定盤 SHM-CD (紙ジャケ) 2010年06月30日

-
寺田正典 (てらだ まさのり)
1962年長崎生まれの福岡育ち。早稲田大学卒業。1985年ミュージック・マガジン社に入社。93年から「レコード・コレクターズ」編集長に着任。監修及び編集に携わったローリング・ストーンズ関連の書籍としては、『レコード・コレクターズ増刊 ローリング・ストーンズ』(1990年発刊)、『レコード・コレクターズ増刊 STONED! The Ultimate Guide To The Rolling Stones』(1998年発刊)、『レコード・コレクターズ増刊 The Rolling Stones CD Guide』(2003年発刊)などがある。
「レコード・コレクターズ」
ミュージック・マガジン社から刊行されている、ひと味違う音楽ファン、レコード・ファンのための月刊誌。1960〜70年代の米英のロックを中心に、ポピュラー音楽を幅広く扱う。詳しいディスコグラフィー付きで取り上げたアーティストの音源をすべて聞くためのガイドとなる特集が好評。
インタビュー中に登場する主要人物について |
 |
Andy Johns (アンディ・ジョンズ) ロンドンのオリンピック・スタジオを拠点に仕事をしていたイギリスの名エンジニア/プロデューサー、グリン・ジョンズを兄に持つアンディ・ジョンズ。60年代末から70年代初頭にかけては兄の関わる作品で共同エンジニアを務め、レッド・ツェッペリン、ブラインド・フェイスのアルバムに携わり、また、70年代初期のフリーの作品をプロデュースしていることでも知られている。ストーンズ作品では、『Sticky Fingers』から『It's Only Rock'n'Roll』までの4作品でエンジニアを務め、70年代黄金期のストーンズ・サウンドの確立に貢献している。70年代末にアメリカに移り、テレヴィジョン、ジョニ・ミッチェル、ロン・ウッドの作品に参加。80年代以降はヴァン・ヘイレンなどハード・ロックの名プロデューサーとして名を馳せている。 |
 | Bill Plummer (ビル・プラマー) 米西海岸出身で元々ジャズ畑を中心に活動をしていたマルチで異色なベース・プレイヤー/シタール奏者、ビル・プラマーは、「The Basses International Project」というプロジェクトで共に活動していた、ジョン・レノン、エリック・クラプトン、ライ・クーダー作品への参加でおなじみの名セッション・ドラマーのジム・ケルトナーを介してストーンズのプロデューサー、ジミー・ミラーと知り合い、そこで『Exile On Main Street』の数曲でアップライト・ベースを弾くよう依頼されたという。 |
 |
Bobby Keys (ボビー・キーズ) 60年代末、レオン・ラセルを中心とする米南部スワンプ・ロック・サークルで活動していたボビー・キーズは、ジミー・ミラーを介してストーンズと出会うことになる、テキサス出身のサックス奏者。10代でバディ・ホリーのバック・バンドでの演奏を経験し、その後も様々なバンドでの演奏を経たのちにレオンの紹介でディレイニー&ボニーのツアー・バンドに参加。この大編成バンドには、エリック・クラプトンやデイヴ・メイソンらも参加していた。『Let It Bleed』所収の「Live With Me」を皮切りに、『Sticky Fingers』の「Brown Sugar」など数々のストーンズ楽曲でブルース・フィーリング溢れるサックス・ソロを披露し、1970年以降はツアーのレギュラー・メンバーに着任している。ボビーに「キースのような人間に一生で5人会えればラッキーだよな」と言わしめたそのキースとは同じ生年月日(1943年12月18日)ということもあり、ソロやニュー・バーバリアンズなどストーンズ以外の活動でも度々共演しながら、現在もソウルメイトのような理想的な信頼関係を保ち続けている。 |
 |
Clydie King (クライディ・キング) テキサス州ダラス出身のR&B/ソウル・シンガー、クライディ・キングは、60年代にはレイ・チャールズのコーラスを担当していた3人組レイレッツの一員として活動していた。ソロとしてもSpecialty、KENTといった名門にシングルをコンスタントに吹き込んでいたが、彼女の知名度を飛躍的に伸ばしたのは、やはり様々なセッションへのコーラス参加だろう。ジョー・コッカー『Mad Dogs And Englishmen』のツアー一行として、ヴェネッタ・フィールズ、シャーリー・マシューズらと結成したブラックベリーズは、そのまま『Exile On Main Street』のLA録音の現場になだれ込むかたちとなった。 |
 |
Dr. John (ドクター・ジョン) おなじみニューオリンズ・スワンプの生き字引、Dr. ジョンことマック・レベナック。ニューオリンズ・ミュージックとスワンプ・ロックの素晴らしい交叉盤『Gumbo』をすぐ近くのサウンド・シティ・スタジオでレコーディングしていた時期でもあり、そちらのレコーディング・メンバーであったタミ・リン、シャーリー・グッドマンを引き連れ、ハリウッド・スタジオでの「Let It Loose」のコーラス録音に参加したというのがおおよその経緯。また、1970年に録音されたDr. ジョンのアルバム『The Sun、Moon & Herbs』には、ミック・ジャガーが6曲もバック・コーラスで参加している。 |
 |
Gram Parsons (グラム・パーソンズ) インターナショナル・サブマリン・バンド、バーズ(『ロデオの恋人』時代)、フライング・ブリートー・ブラザーズを渡り歩き、カントリー、またはカントリー・ロックを追求し続けた男、グラム・パーソンズ。『Let It Bleed』の制作にとりかかった頃から、キースとグラムとの親交は始まったと言われている。「Love In Vain」、「Country Honk」、「Wild Horses」、「Dead Flowers」、「Moonlight Mile」など、グラムがストーンズ・サウンドに与えた影響というものは計り知れない。もちろん『Exile On Main Street』のレコーディングにおいても、仏ネルコートにグラムは訪れていて、「Sweet Virginia」、「Torn & Frayed」といった楽曲でその親睦が窺える。グラムは、1973年、2枚目のソロ・アルバム『Grievous Angel』を完成させた直後にアルコールとドラッグの過剰摂取により26歳という若さでこの世を去ったが、その後もストーンズは、「Far Away Eyes」、「Indian Girl」、「The Worst」といった曲にカントリー・フレイヴァを吹き込むことによって、その友情を永遠のものとしている。 |
 |
Jimmy Miller (ジミー・ミラー) 1968年、春の訪れとともに「ブルース」、「米国南部」というルーツ・ミュージックへの指針をしっかりと捉えたストーンズは、アイランド・レコーズ創設者クリス・ブラックウェルの肝煎りとしてスペンサー・デイヴィス・グループやトラフィックなどを手掛け注目を集めていた新進気鋭のジミー・ミラーをプロデューサーに抜擢。ちょうどその頃完成したばかりだったトラフィックの2ndアルバム『Traffic』のサウンドをミックがいたく気に入ってスカウトしたそう。ブルースを機軸とした手堅くアーシーなサウンド作りの中にも実験的な試みを次々と取り入れた『Beggars Banquet』でそれは吉と出て、以降『Goat's Head Soup』までにおいてジミー・ミラーはストーンズから全幅の信頼を得て、揺るぎない黄金期のサウンドを作り上げている。 |
 |
Jim Price (ジム・プライス) ボビー・キーズと同じくL.A.スワンプ・サークル諸作品やビートルズ作品などに参加していたテキサス出身のセッション系トランペット奏者ジム・プライス。ボビ・キーズの紹介によりストーンズ作品へ参加となったその初登場曲は、『Sticky Fingers』所収となる「Bitch」で1970年のオリンピック・スタジオにて。Stax系ジャンプ・ナンバーをストーンズ流に昇華したこの曲では、ジムとボビーによるパンチの効いたホーン・セクションが明らかにドライヴ感を与えている。この後1973年のウインター・ツアーまでバンドに同行し、70年代ストーンズの黄金期を支えた。 |
 |
Kathi McDonald キャシー・マクドナルド ジャニス・ジョプリン亡き後のビッグ・ブラザー&ホールディング・カンパニーの2代目ヴォーカリストとして、さらには、ジョー・コッカー『Mad Dogs And Englishmen』やレオン・ラッセル率いるシェルター・ピープルへの参加など、地味ながらもブルース・ロック、スワンプ・ロックの最重要作品にこれでもかと名を連ねているブルース・ロック女裏番長シンガー、キャシー・マクドナルド。1974年のソロ1stアルバム『Insane Asylum』(邦題:精神病棟!)には、スライ・ストーン、ロニー・モントローズ、ニルス・ロフグレンといった大物たちが参加。彼女の歌声がいかに魅力的かを間接的に証明している。ストーンズとは『Exile On Main Street』の「All Down The Line」での共演となり、疾走感のあるキャッチーなフックを華やかにバックアップ。 |
 |
Leon Russell (レオン・ラッセル) グリン・ジョンズの紹介でストーンズと出会うこととなるレオン・ラッセルは、まずは『Let It Bleed』の「Live With Me」にピアノで参加し持ち前のLA流スワンプ・サウンドの一片を名刺代わりに差し出す。しかし、レオンのストーンズへの最大の貢献は、その広い人脈を生かし米南部のミュージシャンズ・サークルを彼らストーンズと共有したという点にある。自身のシェルター・ピープル、デラニー&ボニー&フレンズ、ジョー・コッカーのマッド・ドッグス&イングリッシュメンといった共同体が誇る腕利きの人海を、当時南部ルーツ・サウンドに飢えていたストーンズの助力のために惜しげもなく送り込み、ブルース、ソウル、カントリー、ゴスペルの持つ泥くさく豊かなニュアンスを分かち合ったその功績は称えられてしかるべき。また、1969年初のソロ・アルバム『Leon Russell』の録音には、ビル・ワイマン、チャーリー・ワッツが参加している。 |
 |
Robert Frank (ロバート・フランク) 大方のロック・ファンにとっては『Exile On Main Street』のジャケット・アートワーク、そして、ドキュメンタリー・フィルム『Cocksucker Blues』という、ストーンズ史上屈指のいかがわしい芸術性を匂い立たせる2大プロダクツを手掛けた人物としてよく知られるロバート・フランク。1924年、スイスのチューリッヒで生まれ育ったフランクは、47年に移民としてニューヨークに出てきた後、50年代半ばには全米を放浪しながら、実にフィルム767本を使用しながら市民の現実の生活を写真に収め続け、58年5月に「Les Americains(アメリカ人)」という写真集として刊行されている。アレン・ギンズバーグやジャック・ケルアックといったビート詩人らと共鳴し合うことで「視覚的詩人」とも呼ばれていたフランク。「Les Americains(アメリカ人)」にも掲載されていた写真をコラージュしたアートワークは、ストーンズの楽曲イメージを肥大化させる一種の魔法や麻薬めいたパワーに満ちている気がしてならない。 |
 |
Venetta Fields (ヴェネッタ・フィールズ) ニューヨークはバッファロー出身のR&B/ソウル/ゴスペル・シンガー、ヴェネッタ・フィールズは、アイク&ティナ・ターナーのバック・コーラス・グループ、アイケッツに在籍していたことでも知られている。アイケッツがレビューを離れた後は、据え置きメンバーでミレッツとしての活動に移行。その後はクライディ・キング、シャーリー・マシューズらとのブラックベリーズとして様々なミュージシャンのバック・コーラスに参加。中でもピンク・フロイド『Dark Side Of The Moon』のツアー、そして、『Exile On Main Street』といったロック畑でのビッグネームとの仕事が特に目を引く。 |