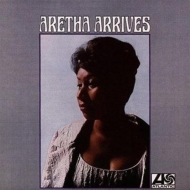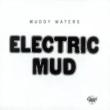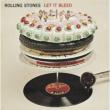【新春特別対談】 越谷政義 × 石坂敬一 〈2〉
Monday, January 17th 2011

-
石坂:ローリング・ストーンズのことは越谷さんに訊けば何でも判ると思うんだけど、僕はまたちょっと違う角度。ビートルズは、もし仮にビートルズが世に出なかったとしても、彼らに匹敵するような存在は何かしら出現していた可能性は高い。ローリング・ストーンズは、「売れる売れない」に限った成功の質や量はひとまず置いといて、やっぱりビートルズに匹敵するほどの重要性を持っている。それは何かと言うと、「白人が黒人を認めた」。また、それ以上に「頼った」ということ。こういう例は、分野別でも存在しないよ。政治においてもね。(註)マーティン・ルーサー・キング Jr. があそこまで大きな勢力となった背景には、遠回しにローリング・ストーンズの影響力があるんじゃないかな。(註)マルコムXにしてもそう。
ローリング・ストーンズのようなスタイル、つまり「白人が黒人を頼った」というスタイルのバンドは、その当時他にいなかった。後に、アニマルズ、(註)プリティ・シングス、(註)マンフレッド・マンなんかも追随したけど、次元が違い過ぎた。アメリカで白人が(註)チャック・ベリーをやっても、ビーチ・ボーイズになっちゃうんだよ(笑)。 -
越谷:チャック・ベリーがビーチ・ボーイズの「サーフィンUSA」に怒ってね。「あれはオレのパクリだ」って(笑)。
-
石坂:それにしても音が軽すぎるよね。カール・ウィルソンのリード・ギターがキンキンしている(笑)。ただし、1964年に実際にビーチ・ボーイズを観たけど、それなりの存在感はあった。だから、ストーンズのようにあそこまで黒人を意識してリスペクトしたカタチで登場してきたのは、ほんとうに稀だった。でも、ストーンズ本人たちはあくまで無意識だったと思うけど。
-
越谷:1965年に、さっき話しにも出た「(I Can't Get No)Satisfaction」がヒットするんだけど、その翌年に(註)オーティス・レディングがカヴァーする。しかもシングル・ヒットして、R&Bチャートの上位にランクインされるんだよね。
-
石坂:あれはオーティスからのメッセージなんだよ。「アフロ・アメリカンも君たちのことが好きだよ」っていう。
- --- さらにその翌年には、(註)アレサ・フランクリンもカヴァーしていますし。
-
越谷:(註)マディ・ウォーターズが『Electric Mud』っていうアルバムで「Let's Spend The Night Together」をやったりだとか。ブルースやリズム・アンド・ブルースの人たちが積極的にストーンズの曲を取り上げている。それは、石坂さんがおっしゃった「ブラックは君たちの味方だよ」っていうことなんだよね。
-
石坂:だから、「(I Can't Get No)Satisfaction」で人気が出なかったら、文化的にはもっと語られる存在になったはずなんだよ(笑)。人気が出すぎたから、ある種アイドル的な立ち位置になった。
-
越谷:それは、“石坂説”だよね(笑)。
-
石坂:ローリング・ストーンズと人気の面以外でほぼ同じようなことをしていたのは、プリティ・シングス。どちらも甲乙付けがたいラフなよさがあってね。だけど、ストーンズはポジ、方やプリティ・シングスはネガで終わった。
なぜイギリスからそういったグループが出てきたかというと、やっぱりアメリカのバンド連中とは出自が違うから。イギリスはほぼ中産階級出身。美術の専門学校だとかも含めて教育をしっかり受けている。アメリカではごく一部。 - --- あくまでインテリジェンスがあった上での創作活動。
-
石坂:そう。インテリジェンスな個性を持った人たち。美術にせよ何にせよ。だから、白人の世界にとっても新鮮で破壊型のバンドだったんだと思う、ローリング・ストーンズは。しかも、それまでのアメリカが基準値としていた音楽に対しての否定的なメッセージが込められている。だって、その頃(註)マディ・ウォーターズはChessのスタジオの窓拭きをやっていたんだから。
-
越谷:そうなんだよね。で、当時ストーンズがChessスタジオをレコーディングで訪れたら、マディはペンキ塗りをしていて(笑)。驚きながらも感激した彼らは「先生のレコードをいつも参考にさせてもらってます!」って最敬礼(笑)。僕は、その話をキースから直接訊いたことがあるけど、びっくりだよね。
-
石坂:あと、ローリング・ストーンズは、ヨーロッパの悪徳の流れ、つまりギリシャ・ローマの腐敗した華麗なる貴族文化、この官能的なデカダンスに触れていた。これはビートルズにはなかったこと。ただ本人たちはいたって無自覚。ミック・ジャガーに直接訊いたら「もちろん意識していたよ」って答えるかもしれないけど(笑)。
これは、(註)フェリーニが描く『サティリコン』の世界と同じ。黒人とはまったく関係ないところで、ローリング・ストーンズは、知ってか知らずかそういう世界にも立ち入っていた。まさに、カリギュラ、ヘリオガバルスといった伝説のローマ帝王による悪徳の退廃なんだよ。金持ちになっても、ビートルズはそうならない。それは、ひとことで言えば、教養がないから。

(註)フェデリコ・フェリーニ監督「サティリコン」・・・1969年製作・公開のイタリア・フランス合作映画『サティリコン』は、ペトロニウスの著した紀元1世紀ころの文学「サテュリコン」を、「映像の魔術師」の異名を持つイタリアの映画監督/脚本家フェデリコ・フェリーニが映画化した作品。『甘い生活』、『フェリーニのローマ』とともに「フェリーニのローマ三部作」と言われている。愛する少年奴隷ジトーネを恋敵に奪われたマーティン・ポッター扮する主人公エンコルピオが貴族トリマルキオの饗宴に参加し、その後様々な出来事に見舞われながらローマの快楽と退廃を経験する物語。日本では70年9月に劇場公開されている。 - --- 笑。
-
石坂:まぁ、ストーンズ自身に教養があるっていうよりは、誰か別の人間の手によって作為的にそうなっている場合が多いのかもしれない。ベルギーの画家(註)ギー・ぺーラートの「Rock Dreams」なんて見てると、ローリング・ストーンズの描かれ方はデカダンスばっかり。

(註)ギー・ぺーラートの「Rock Dreams」・・・独特のセンスで構成されたポップなアートで現在でもカルト的人気を誇るベルギー人コミック・アーティスト/イラストレーター、ギー・ぺーラート。1964年に初作となる『ジョデルの冒険』の企画とともにパリに活動の場を移す。66年『ジョデルの冒険』をエリック・ロスフェルド社から出版。68年第2作となる『プラウダ』を出版。その後はコミック製作から離れ、『Taxi Driver』や『Paris,Texas』といった映画ポスターや舞台芸術プレタポルテや家具のデザインなど多岐に渡って精力的な活動を続ける。音楽アーティストの作品に関わったものとしては、ローリング・ストーンズの『It's Only Rock'n Roll』やデヴィッド・ボウイの『Diamond Dogs』のアルバム・ジャケット、数多くのロック・スターたちを描いた人気イラスト集『Rock Dreams』(1973年出版)などが有名。
例えば、『It's Only Rock'n Roll』でいうところの「Luxuary」だよね。あれはブラックの影響というよりは、ローリング・ストーンズの古代ギリシャ・ローマに対する憧れ。僕にはそう思える。 -
越谷:「Luxuary」なんかの音楽的な部分で言えば、レゲエが流行ればそのエキスをちょっと入れてみたり、ディスコが流行ればその要素を「Miss You」で取り入れる。その嗅覚が鋭くて、なおかつ着手が早いっていうその典型的な曲。いかにそのときの旬な要素を散りばめながらやっていくかというのは、今も続いていること。
-
石坂:『It's Only Rock'n Roll』のジャケット画はギー・ぺーラートによるものだけど、ほぼ金と銀で描かれていて、カリギュラの世界さながら。皇帝カリギュラ、ネロなんかが出てきてもぴったりだよ。イギリス人でも、その他のヨーロッパ人でも、成功者はキリスト教の神秘の世界にどこかで触れたいところがある。それから、ギリシャ・ローマ時代への愛着、そして肉体主義。ちなみに、その対極にあるのは宮本武蔵の精神主義なんだけど。(註)ロンドンのトラファルガー広場に行ったら、将軍ウェリントン以外は、裸ばっかりだ(笑)。肉体を誇示しているわけ。だけど、おちんちんは小さい。時の皇帝がもし大きいのをぶら下げていたら、「オレをバカにしたな、このヤロウ!」ってなるからね(笑)。
キリスト教とギリシャ・ローマ時代への賛美、そして肉体への憧憬。ここまでローリング・ストーンズが勉強しているわけではないと思うけど、それをやっているんだよ。

(註)ロンドンのトラファルガー広場・・・ロンドンのウェストミンスターにある、1805年のトラファルガーの海戦を記念して造られた広場。中央に噴水のある広いスペースがあり、ネルソン提督の記念碑(ネルソン記念柱)は噴水の隣に、巨大な4頭のライオンのブロンズ像に囲まれて建っている。広場の北側はナショナル・ギャラリー、東側にはセントマーティンズ教会がある。 -
越谷:自然にね。例えば、ミック・ジャガーが60過ぎても腹を露わにしたり、最後は上半身全部脱いでみたりっていうパフォーマンスはまさにそれで。あと、ミックはツアーの前にクラシックのバレエの先生に付いて、3ヶ月間みっちりバレエを習って体作りをする。もちろん緻密に計算されている部分もあるけど、そういうことを自然にやっている人なんだよね。
- --- ただ、ローリング・ストーンズの世界というのは、キリストやギリシャ・ローマ時代への賛美や肉体主義に、黒人音楽への敬意を混ぜ合わせて生成された単純なものでもないですよね?
-
石坂:グレコローマンは金持ちの文化の象徴なわけだから、初期のモチベーションは間違いなく黒人へのリスペクト。それは今もそうだとは思うけど。多くの健全な人たちが眉をしかめるような退廃的、反道徳的なローリング・ストーンズの人生は、西洋の成功者のみが抱くキリスト教、グレコローマン特有の腐敗。美しい腐敗だよ。西洋にはあるんだよ、憧れの腐敗が。日本にも平安時代にはあった。
ローリング・ストーンズで残念なのは、アメリカに較べて日本では文化論的な視点で語られることがあまりにも少ないというところ。越谷さんをはじめとして音楽的に詳しいひとは何人かいて、それはそれで必要なんだけど、音楽的に詳しくなくても、言わばレーゾンデートル的視点で語れる評論家が非常に少ないんだよね。「ローリング・ストーンズはすごいんだ! ピカソなんて問題じゃないんだ!」って声を大にして言える人がやっぱり必要なわけ。まぁ僕がそう言っているひとりでもあるんだけれど。 -
越谷:というのも、ストーンズに限らずだけど、音楽の聴き方っていうのは多様なわけだよね。「何年に何がヒットして、どれそれがオリジナル」っていうデータを軸にして評論したようなこと、これはこれで大切なことだとは思う。ただ、1986年に(註)「ローリング・ストーンズ大百科」っていう本を僕は出したんだけど、それ以降はかなりマニアックな研究に偏っていた部分もあって(笑)、少し良くない傾向かなと。
もちろんそういうことも必要なんだけど、その一方では、石坂さんがおっしゃっていた存在理由を語る部分、それからもうひとつ、もっと若い世代にストーンズの音楽のかっこよさを、第三者からストレートに伝える部分が必要なんじゃないかなって思っているわけ。南米では、ストーンズのコンサートに来る若いコたちが増えているらしいんだよね。日本で、ストーンズのコンサートに10代、20代のコたちが観に来ている光景なんてほとんど目にしたことがない。だから、ストーンズの聴き方が、マニアだけが重箱の隅を突くようなものに一本化されちゃったのかなって、僕らも反省はしているんだけど・・・その分、今はストーンズ・メルマガを配信するときにできるだけキャッチーな話題を判りやすいカタチで盛り込もうとしているんだよね。

(註)ローリング・ストーンズ大百科・・・1986年にCBS・ソニー出版から発刊されたマイク越谷氏著によるローリング・ストーンズ完全ディスコグラフィー。ストーンズの全作品、ソロ・ワークをレコーディング・データ、ベスト・ランク等とともに完全解説。貴重な写真も満載。2002年には双葉社から加筆・訂正を加えたリニューアル版も出ており、そちらでは当時のミック・ジャガーの最新シングルまでを網羅している。
キースが言ってるよね。「オレにとってはモーツァルトもロックンロールだぜ」って。あるいは、「たかがロックンロール、だけど、好きだからやってるんだ、ただそれだけだぜ」って。そういう部分が最近は抜け落ちちゃって・・・まぁストーンズ自身もいけないんだけどね(笑)。年齢的なことやビジネスの関係なんかで色々あるんだろうけど、ニュー・アルバムのインターバルが年々長くなっているのはいかがなものかなと。『A Bigger Bang』からもう5年以上が経過しているわけだからね。
そういう意味で、ストーンズは今現在も活動しているグループなんだから、ビートルズやエルヴィスを聴くのとはやっぱりワケが違う。ストーンズについて語っている人たちの中には、意外と最近のアルバムをちゃんと聴いていなかったり、ツアーを観ていなかったりする人も結構いる。ある種机上の学問にとどまっちゃっているんだよね。 -
石坂:例えば、(註)ヴェルヴェット・アンダーグラウンドにはシングル・ヒットがない。だけど、アメリカの大衆文化史には確実に刻まれている存在。なぜか? その存在自体がすごいからなんだよ。そこには様々な人脈があって、絵描きから、技術家、資本家、女優に至るまで。ルー・リード云々っていうよりは、ニューヨークのヒップ・カルチャーの源泉でもある(註)アレン・ギンズバーグなんかのビートの流れを汲んでいてね。こういう部分には、いくら大きいヒットを出してもかなわないんだよね。加えて、ニコの夭逝も彩りを添えている。(註)アンディ・ウォーホールがなぜあんなに求心力があるかと言うと、「屈折したアメリカ文化の象徴」だったからなんだよね。そういった文化的な衝撃を与える存在というのは、たまにいるけど、ローリング・ストーンズはまさしくそうなんじゃないかな。だけど、だんだん普通の人になっていくから(笑)、そこが難しいところ。そういう意味でも、ローリング・ストーンズは、70年代半ばぐらいまでしか興味がない。
- --- 先ほどお話に出た『It's Only Rock'n Roll』あたりまででしょうか?
-
石坂:あるいは、当時自分が制作を担当していた『女たち』まででもいいかな。だけど、60年代の方が全然いい。チェルシーを感じさせるね。それ以前にあった、例えば(註)ジョン・レイトンの「霧の中のジョニー」なんてたまらなく好きだけど、聴いた後に、別に(註)克美しげるでもいいやって気になる(笑)。

(註)「霧の中のジョニー」・・・1961年にイギリスの俳優ジョン・レイトンが歌手デビュー曲として放った哀愁の全英No.1 ヒット。原題は「Johnny Remember Me」。このヒットを契機に、ビート・グループ登場前夜の全英チャートに次々とヒットを送り込んだ。日本では翌62年に、テレビアニメ『エイトマン』の主題歌でよく知られる克美しげるがデビュー・シングルでこの曲を取り上げ、独特の日本語訳が話題を呼び、40万枚のヒットを記録した。
ようするに曲がいいだけ。アーティストは無味乾燥。「霧の中のジョニー」のプロデューサーは、ノリー・パラマーっていう人物で知り合いなんだけど、単なる普通のおじさんだよ。そういうつまらなさがある。クリフ・リチャードも会って話してみると、いたって普通。ブライアン・フェリーにしてもそう。ローリング・ストーンズは・・・会わなきゃいいんだ。 - --- 会わなきゃいい?
-
石坂:こっちがモデリングして、決め込んでね。絵画で言うと、(註)ギュスターヴ・モローとか。僕の世界でローリング・ストーンズを表現すれば、どんどん妖しい存在になっていくことは確か。
- --- ある時期までのストーンズは、石坂さんにとって、「デカダンス」、「ミスティック」の絶対的な象徴だったんですね。それゆえに会うことは避けたいと。
-
石坂:本当にデカダンスを体現できたのはローリング・ストーンズだけだからね。しかも、彼ら自身、無自覚なままやっている。彼らのボキャブラリーはたかが知れているから、「ラリってる」とか「アンフェタミンがどうした」とか「パクられるぜ」とか(笑)、そんな用語しか出てこないけど、やってることはフェリーニの『サティリコン』とほとんど同じなんだよ。
60年代には、造語あるいは、従来ある言葉に別の意味を持たせる発明語が多かった。(註)「フリーク(Freak)」、「キンキー(Kinky)」、「ウィアード(Weird)」、「キャンプ(Camp)」・・・だいたいローリング・ストーンズを形容するときに使われたんだよ。ビートルズじゃなかったな。唯一ジョン・レノンが「オンリー・ローリング・ストーン」って呼ばれていたぐらい。型破りで、非道徳的で、非倫理的で、何をするか判らないって。
(註)「フリーク(Freak)」、「キンキー(Kinky)」、「ウィアード(Weird)」、「キャンプ(Camp)」・・・いずれも若者を中心に使われた俗語。「フリーク」は、「心酔者」「変人」「変態」が転じて「すごく魅力的なヤツ」。「キンキー」も同様に「(性的に)変態」という意味が、褒め言葉としての「アブないヤツ」を形容する場合に使われる。「ウィアード」も「すげぇ、クールでかっこいい!」などの意。「キャンプ」は、フランス語の俗語「se camper」(誇張された ファッションでポーズをとること)から派生した語で、多くは同性愛者を指しながら「けばけばしい」「仰々しい」「気取った」という意味で使われる。
レノンは、ヨーコから芸術用語を教えてもらったところはあるよね。(註)アルチュール・ランボーすら知らなかったぐらいだから。1968年ぐらいのインタビューで、ヨーコは「レノンがビートルズにならなかったら、彼は何をしていたと思いますか?」という問いに、「ピルグリムのような格好をしてリヴァプールの街を徘徊しながら、詩を詠み上げていることでしょう。誰も聞いていないのに。つまり、リヴァプールのアルチュール・ランボーになっていたんじゃないでしょうか」と答えていた。つまり、ヨーコはレノンの寓話を作ってあげたんだよね。それで、レノンも「ランボーっていう人がいるのかぁ」って(笑)。
- --- むしろストーンズやジョン・レノンの在り様が、そうしたキワどい造語を生み出したとも言えそうですね。
-
石坂:ローリング・ストーンズをどう見るかは千差万別だろうけど、僕にとっては、60年代初頭のイギリスというのがキー・ファクターになっているんだよ。(註)ハンター・デイヴィスの本なんかを読むと「1960年頃のリヴァプールでは、ほとんどの若者は絶望的な人生しか送れない。コメディアンになるか、喧嘩に明け暮れるか、あるいはフットボールをやるか」って書いてある。低調だったんだよ。そこに銀幕から怒り狂って出てきたのが、(註)トニー・リチャードソン、(註)カレル・ライス。フランスのヌーベルバーク、(註)ゴダールなんかと呼応してるんだよね。イギリスでは、特に労働者階級の若者が発言するようになった。そういう時期に出てきたのがビートルズとローリング・ストーンズだった。だから飢えているんだよな。
しかも、ロンドン、リバプール、マンチェスター界隈のシーンは狭いから、ジャズのセッションや、(註)アレクシス・コーナー、(註)シリル・デイヴィスなんかのバックに参加したりって、電話一本で駆けつけて何でもやっちゃう。そして、民族的伝統音楽もないから。それゆえに、ピンク・フロイド、キング・クリムゾン、T・レックスみたいなアメリカから見ると理解に苦しむ混合音楽が生まれるんだよね。
ローリング・ストーンズにしたって、あそこまでピュアにブルースやリズム・アンド・ブルースを追求しているバンドは、アメリカからは出ない。だってアフロ・アメリカンがいるんだもの。敵うわけがない。馬力が違いすぎる。そういう意味で、イギリス人が黒人音楽をやるっていうこと自体おもしろいんだよ。存在証明にもなるわけだ。逆に言えば、イギリスに出自があるからローリング・ストーンズは黒人音楽を徹底的に追求したんだろうしね。 -
越谷:1964年にミックが(註)ジェームス・ブラウンと共演したとき、JBのライヴをステージ袖で食い入るように観ていたんだから。
ミックは、中学生の頃には米軍基地でアルバイトをしていて、そこでブルースを色々と教えてもらっていたらしいんだよね。小遣いを全部つぎ込んで、通信販売で南ミシガン通りのChessレコードにオーダーして、ブルースやリズム・アンド・ブルースのレコードなんかを熱心に取り寄せていた。これはミック本人や弟の(註)クリス・ジャガーから訊いた話なんだけど。それだけ黒人音楽にのめり込んでいたんだよね。

(註)ジェームス・ブラウンと共演・・・1964年、共演したローリング・ストーンズ(トリです)を圧倒し、ミックとキースをたちまちトリコにした伝説の「T.A.M.I.(Teenage Awards Music International) Show」におけるJBのパフォーマンスは、後日キースに「あの時、JBの後に出るなんて間違いだった」と言わしめるほど圧巻のものだった。さらに、「このときオレのパフォーマンスを観たミックは、その後ステージで高速ダンスをするようになったんだ」と生前にJBは語っている。出演は、JB、ストーンズほか、シュプリームス、マーヴィン・ゲイ、チャック・ベリー、スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ、ビーチ・ボーイズ。本フィルムは、コンサート映画の走りとして今なお高い人気を博している。日本では66年に「ビート・パレード」というタイトルで劇場公開された。 -
石坂:例えば「ロック貴族」「ロック・アリストクラット」なんていう呼び方は、たしかに当時ローリング・ストーンズだけに使われていた。そういう描かれ方なんだよ。エルヴィスはそう呼ばれていなかったよ。昔からイギリス貴族には、少なからず不謹慎なイメージがあった。エドワード8世なんかに代表されるけど。そういった古くからの王侯貴族のイメージに託されて描かれると、やっぱりストーンズはぴったり。ステージで真っ裸になって歌って踊る、そのキリスト教的裸崇拝とグレコローマンの退廃した貴族文化。まさに魔王のようなイメージだよ。ジェームス・ブラウンもハーレムの帝王だけど、それとはちょっと勝手が違う。
ローリング・ストーンズは、ヒット・ソングが少ないのにこんなに評価が高い。そんなロック・バンド、この先二度と現れないだろうな。デジタル時代にはまず出てこないよ。 -
越谷:実際、ストーンズのレコードで日本でいちばん売れたのって『Steel Wheels』だからね。(註)あの初来日の大フィーバーで、初めてストーンズのCDを買った人だっていっぱいいるんだからさ。


(註)初来日の大フィーバー・・・幻となった日本武道館公演から実に17年の時を経て実現したストーンズの初来日公演。1989年に「Steel Wheels Tour」のUS興行を終えたストーンズ一行が90年のツアー再開の最初の地に選んだのが、ここ日本。従ってセットリストはUSツアーとほぼ同じものだった。場所は、一足お先の88年にミック・ジャガーの初来日ソロ・コンサートが行なわれた東京ドーム(2月14・16・17・19〜21・23・24・26・27日の計10公演)。発表は1月6日の全国朝刊数紙において。ちなみに、チケット発売前日の90年1月12日には、翌日からの発売に関する問い合わせだけで都内のNTT電話回線がパンクという非常事態が起こった。また、さらなる混乱を避けるために発売日は、1月13日と14日の2日間に分けられ、購入枚数も4枚までと制限されたが、発売両日共にNTTの電話回線は終日パンクという、過去に例のない争奪戦が繰り広げられた。さらには、チケットぴあをテナントに擁する各百貨店にも徹夜組を含む長蛇の列ができ、10公演およそ50万人分のチケットは即日秒殺と相成った。スポンサーは「ポカリスエット」でおなじみの大塚製薬。 -
石坂:「ビートルズほど売れない」なんて言われているけど、それはローリング・ストーンズの楽曲そのものが最高だからなんだよ。あれだけ黒人音楽に重きを置いて崇敬して、それでいてビルボードの1位に7〜8曲送り込んでいるんだから、それもまた大したもんだよ。最後のビルボード1位曲ってたしか「Miss You」だったと思うけど、やっぱりすごい。
だけどもうちょっと、グレゴリオ聖歌的というか、「Ruby Tuesday」みたいな曲が増えてもいいんじゃないかなって思うな、個人的には。イギリスの悲しみを抉るようなさ。イギリス人じゃないのに一緒に悲しめるようなね。しかも品のいい王侯貴族の失恋みたいな感じ。 -
越谷:「Dandelion」とかね。
-
石坂:そう。ああいう感じの曲をもっとやってほしい。ライヴばっかりやってると曲作る時間がほとんどないんじゃないかな?
-
越谷:そういう部分で「ストーンズは金儲けに走っている」だなんてよく言われるけど、本人たちは腐るほど持っているわけだから、結局は周りのコンサート・スタッフの稼ぎも重要視しているってことでもあるんだよね。ツアーには200人ぐらいのスタッフが常に帯同していて、みんなストーンズのコンサート収益でメシ食ってるわけだから。バック・ステージでゴミを拾う係なんかもいて、ちゃんと全公演一緒に回っているからね(笑)。それから、キースの友達の奥さんなんかも、「キースの束の間の話し相手」っていう役どころで常にツアーに付いて回っている(笑)。彼らがいて初めて現在のローリング・ストーンズのコンサートが成り立つ。だから、みんなミック・ジャガーのことを「社長」って呼んでいるんだよね(笑)。
石坂さんがストーンズのコンサートを初めて観たのはいつでした? 1978年に内田裕也さんと一緒だった時? -
石坂:そうだね。(註)内田裕也さんが「平凡パンチ」の掲載原稿用としてミック・ジャガーにインタビューするっていうときに同行して。あれは面白かった。L.A.のウエスト・ウッドのホテルかどこかにミックは泊まっていて、会場のニューヨークに向かう出発当日ぐらいにやっと会ってくれたんだよ。

(註)内田裕也さんが「平凡パンチ」の企画でミック・ジャガーにインタビュー・・・永遠のロックン・ローラー、内田裕也がミック・ジャガーに独占インタビューするという1978年の「平凡パンチ」誌上企画。7月にL.A.のアナハイム・スタジアムで行われたローリング・ストーンズのコンサートに赴き、ミックと接触。そのときの様子を「その夜の3時にホテルでミックに会えた。きれいな男だった。オレは日本のrockerだと自己紹介した。オレは質問するというより会話がしたかった。同じジェネレーションのロックンローラーとして」と綴っている。また、取材現場に同席した石坂敬一さんは「日本に対するミックの連綿たる興味みたいなものを問わず語りに喋っていた」と振り返っている。ちなみに内田裕也とミックは、4年後の82年に英ウェンブリー公演のバックステージで再会を果たしている。実は両者は78年以前から交流があり、73年初来日公演の中止に際しても、グァム島でのコンサート・プランを立ち上げて、サテライト便で日本からもツアーを組んで観客を送り込むということを企て、ミック本人からも了承を得ていたという。 - --- 実際、ミックを目の当たりにしたときの印象というのは?
-
石坂:たしかイッセイミヤケの服を着てて・・・綺麗なオカマみたいだったな(笑)。
-
越谷:その当時ミックはそんな感じだね。僕が初めてストーンズのライヴを観たのは1973年。ハワイに来て、その後日本に来るはずだったんだけど、その来日が土壇場で中止になってね。そのとき、(註)湯川れい子さんに「ハワイ公演のチケットが20枚あるから、ツアーを組みなさい」って言われたんだけど、みんな忙しくて行けないんだよね。石坂さんにも電話したけど、結局今じゃ考えられない定員割れの11人しか集まらなかった(笑)。業界人ばっかりと行ったけどさ。前から5列目ぐらいのド真ん中の席!
- --- 1973年のローリング・ストーンズ、訊くのも野暮ですが、いかがでしたか?
-
越谷:そりゃ、最高だよ(笑)。あまり大声じゃ言えないけど、カセット・レコーダーを持って行ってさ。そこで隠密に録った音源をニッポン放送のラジオ番組で流せた、そういう時代だったからね(笑)。ちなみに、前座が(註)ZZトップ。
70年代のストーンズに対しては、僕は純粋にファンとして観ていたかったところが大きかった。色々なレコードのライナーを書いたり、(註)スリー・ディグリーズや(註)アイク&ティナ・ターナーのライヴの司会をやったりって、そういう中でもやっぱりストーンズだけは別格だったよね。 - --- 実際、ストーンズにお仕事として接触されるのは、そこからかなり後になるわけですよね?
-
越谷:うん。1987年にまずミック・テイラー、翌88年にはミック・ジャガーとロニー・ウッドがそれぞれソロ・ツアーで初来日する。そのあたりから仕事として彼らの活動に関わっていこうかなって思ったんだよね。僕も40歳になるかならないかっていうときで、色々と考えるところはあったから(笑)。そして、ストーンズ本隊初来日の90年に、初めて彼らにインタビューをしたんだよ。もちろん、それ以前にバック・ステージでメンバーみんなと話しをしたり、それなりに交流は持っていたんだけどね。
- --- バック・ステージでラフな状態で会うストーンズと、インタビューなどビジネスを介して会うストーンズとでは、かなりその表情に差があるのでしょうか? メンバー個々にもよるとは思いますが。
-
越谷:ミック・ジャガーに関して言えば、例えばインタビューのときでも、聞き手がどれだけオレたちのことを知っているかをしっかり見極めている。逆にプロフェッショナルに徹して、日本のキー局のジングル・コメントみたいなことをやるのもお手のもの。僕がインタビューしたときでも、日本でシングル・カットされる曲をしっかり自分でメモったりして、それをセット・リストに組み込んでみたりとかね。とにかくプロフェッショナル。
キースは、すごくマイペースな人だね。いつも同じ。一度仲良くなると、一生友達みたいな。で、ひとつ質問したことに対して、15分ぐらい熱心に答えてくれる。そういうタイプ。キース曰く「ミックがロックで、俺がロールだ」。ザ・グリマー・トゥインズとはよく言ったもので、それぞれに突出した個性があるよね。
 1992年、キースのN.Y.のレコーディング・スタジオにて。 Photo by Mikio Ariga
1992年、キースのN.Y.のレコーディング・スタジオにて。 Photo by Mikio Ariga -
石坂:やっぱり、ローリング・ストーンズに似たバンドっていうのは、今全然いないんだよ。同時代にはいくつかあったけど。逆に、ビートルズみたいなバンドは、ストーンズに較べて生まれやすい。ただ、質がまったく違うから、あそこまで大きな存在にはなり得ない。
-
越谷:石坂さん、ミック・ジャガーにインタビューしてみたいって最近は思わないの?
-
石坂:思わない。僕は憧れには会いたくない。インタビュアーの立場なんかで会うとさ、現実的な言葉で、現実的なレベルで話さざるを得ないでしょ? そうすると決まって「気さくないい人だった」ってなるから。ミック・ジャガーが気さくじゃ困るんだよ(笑)。
昔、ピンク・フロイドの(註)デヴィッド・ギルモアにインタビューしたヤツが、「会う前まではドキドキしてたけど、会ったらすごく気さくな方だった」なんて言ってたけど、それ言ったらみんな気さくになっちゃうんだよ。 -
越谷:ミック・ジャガーはサービス精神みたいなものが旺盛だからね。僕もいちばん最初は、バック・ステージで一緒に写真撮ってサインもらって、言わばいちファンとして会ったわけだから、やっぱりそれはそれで興奮した。その後は、インタビュアーっていう、あくまで仕事としての立場で頻繁に会うようになるわけだから、そういったファンとしての感情は自制していくしかなかった。もちろん毎回会えるのは嬉しかったけどね。
- --- まだまだお話に尽きない感じなのですが、そろそろお時間のほうが迫ってきておりまして・・・最後に、お二方がこれからのローリング・ストーンズに期待されていることというのはありますか?
-
越谷:ニュー・アルバムをリリースして、またツアーに出てほしい、それだけだよ。それこそがストーンズなんだからさ。
-
石坂:僕の中では、70年代までだから・・・今のストーンズにはあまり興味がないかな(笑)。
-
越谷:それもアリだよね(笑)。ただ、例えば「メイン・ストリートのならず者」のデラックス・エディションが出たタイミングで、「ならず者」を完全再現したステージをやる可能性も!? なんて言う噂もあったけど、別にそんなものは観たくねえよ! っていうさ(笑)。やっぱり何だかんだ言っても、新曲を聴きたいわけなんだよね。その新曲をフィーチャーした形のライヴで「Tumbling Dice」を味わう方がどんなに最高か・・・ストーンズのころがり続ける姿をしっかり追い続けていくだけ、僕はネッ。
|
「レジェンド・ロッカーズ vol.2 夢のライヴ&バトル」 ライヴ・イベントのおしらせ
ジャパニーズ・ロック・インタビュー集 発売記念
[レジェンド・ロッカーズ vol.2 夢のライブ&バトル]
ROCK AND A HARD PLACE!
日本のロック・ヒストリーを築き上げた20人のロッカーズの語りおろし「ジャパニーズ・ロック・インタビュー集」発売を記念してのスペシャル・イベント!インタビュー集登場ミュージシャンを中心に≪レジェンド・ロッカーズ 夢のライヴ&バトル≫開催第2弾!!山本恭司が率いるBOWWOW!2011年ファーストLIVE!! そしてこの日限りのスペシャル・グループ、加納秀人(外道)・山本恭司(BOWWOW)・鮫島秀樹・つのだ☆ひろ・厚見玲衣(元VOWWOW)から成るザ・レジェンド・ロッカーズ! この2グループがロックなステージをROCK JOINT GBでくりひろげるのだ。 スーパー・ギタリスト秀人&恭司+鮫島&つのだ+玲衣による夢のスーパー・セッションが実現する。そして、出演者たちのトーク・ライヴも!そして特別ゲストは?! 60〜70年代ロック・ファンからギター小僧まで、このスペシャルなライヴは見逃せない。

 吉祥寺 ROCK JOINT GB
吉祥寺 ROCK JOINT GB2011年1月29日(土)
18:00開場/18:45開演
出演:BOWWOW/ザ・レジェンド・ロッカーズ [Vo&G:加納秀人(外道)/ Vo&G:山本恭司 / B:鮫島秀樹 / Ds:つのだひろ / Key:厚見玲衣]/スペシャル・ゲスト有り!!!
前売:5,000円+1D
当日:5,500円+1D
GB店頭販売有り / HP予約承り中
【問】 ROCK JOINT GB 0422-23-3091
「メイン・ストリートのならず者、もしくは、ローリング・ストーンズをはてしなく語る夕べ」
|
その他の関連記事はこちら
 【特集】 キース・リチャーズの初ベスト
【特集】 キース・リチャーズの初ベスト
 ストーンズ LPボックスセット!
ストーンズ LPボックスセット!
 「レディジェン」 追加映像たっぷり!
「レディジェン」 追加映像たっぷり!
 『メインストリートのならず者』の真実
『メインストリートのならず者』の真実
 『メインストリートのならず者』 豪華盤
『メインストリートのならず者』 豪華盤
 【解剖】 『メインストリートのならず者』
【解剖】 『メインストリートのならず者』
 ロニー・ウッド 9年ぶり新作! Wオリ特も!
ロニー・ウッド 9年ぶり新作! Wオリ特も!
|
Rolling Stones |
|
Rolling Stones |
|
Rolling Stones |
|
Rolling Stones |
|
Rolling Stones |
|
【スーパー・デラックス・エディション】 Rolling Stones |
|
Rolling Stones |
|
〜「メイン・ストリートのならず者」の真実 Rolling Stones |
|
From The 70s To 00s Vol.1 Rolling Stones |
|
In The Sixties Rolling Stones |
|
【スーパー・デラックス・エディション】 Rolling Stones |
|
【デラックス・エディション】 Rolling Stones |
|
【デジタル・リマスター版】 Rolling Stones |
|
【デラックス・エディション】 Rolling Stones |
|
コレクターズ・ボックス Rolling Stones |
 その他のローリング・ストーンズの商品はこちら
その他のローリング・ストーンズの商品はこちら

-
越谷政義 (こしたに まさよし)
1966〜69年に日本ローリング・ストーンズ・ファン・クラブ会長を務めた音楽評論家/DJ/MC。現在は、ミュージック・ペン・クラブ・ジャパン事務局長、ローリング・ストーンズ・ファン・クラブ顧問、エルヴィス・プレスリー・ファン・クラブ顧問。ストーンズ、エルヴィス・プレスリーをはじめ、ロック、ブルース、ソウルなどのアルバム・ライナーノーツ、雑誌/新聞への執筆、ラジオDJ、イベントMC/プロデュースを手掛ける。
著書に「STONES COMPLETE」(双葉社)、「ローリング・ストーンズ大百科」(ソニー・マガジン)、「ワークス・オブ・エルヴィス」(共同通信社)、「ストーンズそこが知りたい」(音楽之友社)他、監修&主著「キース・リチャーズ・ファイル」(シンコー・ミュージック)、「ジャパニーズ・ロック・インタビュー集 時代を築いた20人の言葉」(TOブックス)がある。
石坂敬一 (いしざか けいいち)
慶應義塾大学経済部卒業後、1968年に東芝音楽工業 (現EMIミュージック・ジャパン)に入社。洋楽ディレクターとして、ビートルズ、ローリング・ストーンズ、ピンク・フロイド、レノン&ヨーコ、Tレックス、エルトン・ジョン、ジェフ・ベックなどを担当。その後、同社邦楽本部において、BOOWY、松任谷由実、長渕剛、矢沢永吉を担当。91年に同社常務取締役に就任。94年、ポリグラム株式会社に入社、代表取締役社長就任(現 ユニバーサル ミュージック合同会社)。99年にユニバーサル ミュージック株式会社入社、代表取締役社長就任(現 ユニバーサル ミュージック合同会社)。2009年1月、ユニバーサル ミュージック合同会社 最高経営責任者兼会長に就任。11月に同社会長 就任。2011年から同社相談役に就任。ほか、社団法人日本レコード協会理事 (1999年4月 〜)、社団法人日本レコード協会副会長 (2000年 4月 〜)、社団法人日本レコード協会会長 (2006年 7月 1日 〜)を務めている。著書に「BEATLESの辞典」(ごま書房)、訳書に「ザ・ローリング・ストーンズ物語」(日音楽譜出版)など。
- 関連サイト(外部サイト)
-
本文中に登場する主要人物について |
 |
Martin Luther King, Jr. (マーティン・ルーサー・キング Jr.) アメリカ合衆国のプロテスタント・バプテスト派の牧師。「キング牧師」の名で知られ、アフリカ系アメリカ人公民権運動の指導者として活動した。1963年8月28日に行われたワシントン大行進においてリンカーン記念堂の前で「I Have a Dream(私には夢がある)」で知られる有名なスピーチを行なった。キングを先頭に行われたこれらの地道かつ積極的な運動の結果、アメリカ国内の世論も盛り上がりを見せ、ついに64年7月2日に公民権法(Civil Rights Act)が制定された。これにより、建国以来200年近くの間アメリカで施行されてきた法の上における人種差別が終わりを告げることになった。同年にノーベル平和賞を受賞。アメリカの人種差別(特にアフリカ系アメリカ人に対する差別)の歴史を語る上で重要な人物の一人。ちなみに、スティーヴィー・ワンダーの『Hotter Than July』に収録された「Happy Birthday」は、「キングの誕生日を祝日にしよう」という運動に捧げた曲である。 |
 |
Malcolm X (マルコムX) 「ネーション・オブ・イスラム教団」のスポークスマン、「ムスリム・モスク・インク」および「アフリカ系アメリカ人統一機構(Organization of Afro-American Unity)」の創立者でもある黒人公民権運動活動家。非暴力的で融和的な指導者だったキング牧師らとは対照的に、マルコムが唱えたのは完全な人種分離であり、公民権運動を指導するキングを「白人に迎合するアンクル=トム」だと激しく非難。キングが白人社会に自らを合わせようとしたのに対し、マルコムは「黒は美しい」と叫び、黒人民族主義を訴えた。65年に凶弾に倒れる。 |
 |
The Pretty Things (プリティ・シングス) ギタリストのディック・テイラーがストーンズのオリジナル・ベーシストだったということはよく知られているだろう。60年代に勃興したブリティッシュ・インヴェイジョン時代のバンドとして、おそらくもっとも不当に低評価されている彼らは、40年近くにわたりカルト・ヒーローであり続けている。ボ・ディドリー、チャック・ベリー、ジミー・リードなどのブルース・カヴァーに加え、彼らのサイケデリック/ガレージ・ロック然としたオリジナル・スタイルは常に革新的で多様的だったのは間違いない事実。1963年の結成以来現在も不動のラインナップで活動を続けている。 |
 |
Manfred Mann (マンフレッド・マン) マンフレッド・マンことマンフレッド・ルボウィッツ、マイク・ハグ、マイク・ヴィッカーズ、デイヴ・リッチモンドがマン・ハグ・ブルース・ブラザーズを結成し、そこにポール・ジョーンズがオーディションで加入。1963年、彼らはバンド名をマンフレッド・マンに改名した。64年、リッチモンド脱退に伴い、トム・マッギネスが加入し、1stアルバム『The Five Faces Of Manfred Mann』を発表。シングル「Do Wah Diddy Diddy Do Wah Diddy Diddy」が全世界で大ヒットした。65年頃までは、マン、ハグのジャズ志向、ジョーンズのブルース、R&B志向が相まって、アレンジ、演奏共に当時のビート・グループの中では群を抜いていた。60年代後期は、ポップな面が強くなり、サイケデリック・ロックの要素も加わることになった。 |
 |
Chuck Berry (チャック・ベリー) エルヴィス・プレスリー、リトル・リチャード、ジェリー・リー・ルイス、バディ・ホリーなどと並び、ロックンロールの創始者の一人と言われている。特徴的なギター・リフを使ったその音楽のスタイルは、後のロック・ミュージシャン達に多大な影響を与えた。マディ・ウォーターズの口利きによって1955年、チェス・レコードと契約。シングル「Maybellene」(全米5位)でデビューした。独特のギター奏法とギターを弾きながら腰を曲げて歩く「ダックウォーク」が話題となった。56年にはシングル「Roll Over Beethoven」などがヒット。57年、最初のアルバム『After School Session』を発表。シングル「School Days」、「Rock and Roll Music」がヒット。58年には2枚目のアルバム『One Dozen Berrys』を発表し、シングル「Sweet Little Sixteen」、「Johnny B. Goode」、「Sweet Little Rock and Roller」、ストーンズがデビュー・シングルでカヴァーした「Carol」などがヒットした。81年には初の来日コンサートを行っている。86年にロックの殿堂入りを果たし、また同年、キース・リチャーズがオールスターのバンド・メンバーを集め、ベリーの故郷セントルイスで「生誕60周年記念コンサート」を開催。このときの様子は映画「ヘイル! ヘイル! ロックンロール」として翌年公開された。 |
 |
Otis Redding (オーティス・レディング) 言わずと知れた「ソウルの巨人」。60年代初頭、ジョニー・ジェンキンズのパイントッパーズで音楽キャリアをスターと。その後、ソロ・シンガーとして1962年に「These Arms of Mine」を発表。この曲のヒットによって64年スタックス傘下のヴォルトからアルバム『Pain in My Heart』を発表し、アメリカ国内でアトランティック・レコードのもとで全国流通を果たす。同年、ブッカー・T&ザ・MG'sのスティーヴ・クロッパーとの「Mr. Pitiful」は、R&Bシングル・チャートで最高位41位のヒットに。また、ジェリー・バトラーとの「I've Been Loving You Too Long」でR&Bのシングル・チャートで2位を記録。彼のキャリアの中で最も高い評価を得る作品となった。その後も「Try a Little Tenderness」、「I Can't Turn You Loose」、ストーンズのカヴァー「(I Can't Get No) Satisfaction」、アレサ・フランクリンに提供した曲のセルフ・カヴァー「Respect」などのヒットを立て続けに発表。67年のモンタレー・ポップ・フェスティバル出演は、音楽に人種の壁はないことを示し、大喝采を浴びた。1967年12月10日、公演地であるウィスコンシン州マディソンに向かう移動途中、自家用飛行機の墜落事故によって、26歳の若さでこの世を去っている。 |
 |
Muddy Waters (マディ・ウォーターズ) 戦後シカゴ・ブルースの形成に大きな足跡を残したことから、「シカゴ・ブルースの父」と称される、ブルース・シンガー、ギタリスト。本名マッキンリー・モーガンフィールド。1950年初頭からリロイ・フォスター、リトル・ウォルター、53年からオーティス・スパン、翌54年からウィリー・ディクスンがレコーディングに加わるようになり、マディのバンド・スタイルが固まる。同年、「I'm Your Hoochie Coochie Man」、「I Just Want To Make Love To You」など代表曲となる曲がチェス・スタジオでレコーディングされた。豊富で深淵な声、豪快なボトルネック・ギターで、ロック界においても、ストーンズ、エリック・クラプトン、ロリー・ギャラガー、ポール・ロジャース、 ザ・バンドなど、彼から影響を受けたミュージシャンは多く、その影響力は計り知れない。チェスの前身アリストクラット・レーベルに48年に吹き込まれた「I Can't Be Satisfied」は、マディにとって初の全米R&Bナンバー1ヒットを記録。後のストーンズの大ヒット・ナンバー「(I Can't Get No)Satisfaction」にはこの曲の影響が色濃く見られ、実際に彼らのバンド名もマディの50年のナンバー「Rollin' Stone」に由来している。 |
 |
Velvet Underground (ヴェルヴェット・アンダーグラウンド) 活動中はヒットに恵まれなかったが、それまでに類を見ない極めて前衛的なサウンド、性におけるタブーや薬物など人間の暗部を深く鋭く見つめる詩世界は、デヴィッド・ボウイやセックス・ピストルズなどに多大な影響を与え、ロックの芸術性の向上に大きな役割を果たした、ルー・リードとジョン・ケイルを中心に1965年にニューヨークで結成されたグループ。グリニッジ・ヴィレッジのカフェ・ビザールでヴェルヴェッツのステージを観て気に入ったアンディ・ウォーホルは、バンドのプロデュースを申し出、ファクトリーに出入りしていたニコをヴォーカルとして加入させる。67年に、ウォーホルによるバナナのジャケットで有名なデビュー・アルバム『Velvet Underground and Nico』が発表される。このアルバムは商業的には成功することはなかったが、後に再評価され、今日では歴史的な名盤とされている。 |
 |
Allen Ginsberg (アレン・ギンズバーグ) ジャック・ケルアック、ウィリアム・バロウズとともに50年代のアメリカで巻き起こった文学的ムーブメント「ビートニク」の巨匠として知られ、ヒッピー・ムーブメントの前身である「ビート・ジェネレーション」の発起人でもあるアメリカの詩人。盟友ボブ・ディランの映像中にも時折出演していた。権威的な社会と物質主義の圧迫、世界各地での放浪、セックス、麻薬による幻視体験、溺愛していた母親の死を通して「Howl(吠える)」 (1956年)、「Kaddish」 (1961年)などの代表作にを生み出した。彼が開拓した自由な思想に、インテリ層を中心とした多くの若者が賛同。60年代には、ヒッピー・ムーヴメントへと派生した。ギンズバーグ自身も詩の朗読でロック・フェスティバルに参加するなど、ベトナム反戦運動においても重要な先導役を果たした。 |
 |
Andy Warhol (アンディ・ウォーホール) 1962年、ウォーホルが34歳。写真をベースにするシルクスクリーンという手法を使い、「反復と量産」を意識したコカ・コーラ、キャンベル・スープ、プレスリー、モンローなど、20世紀のアメリカの資本主義が生み出した工業製品や有名人のポートレートをモチーフにした作品は、彼のスタジオ“ファクトリー”で工場の流れ作業を意識してアートとして量産された。ウォーホールの仕事はアート作品制作だけにとどまらず、「チェルシー・ガールズ」など数多くの映画製作やナイトクラブのショー、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのプロデュース、69年にはインタビューで誌面すべてを構成する雑誌「インタビュー」”の創刊など、多方面に亘った。ウォーホルは、彼のアート作品とともに意識的に自分自身がメディアとなり、数多くのスキャンダラスな話題を提供しながらマスコミ、ファッション界、ニューヨークの社交界でも注目を浴びる存在となっていった。70年代には社交界からの注文で、トルーマン・カポーティー、ミック・ジャガー、マイケル・ジャクソン、キャロライン王女など幅広い分野の有名人のポートレイト制作を行なっている。 |
 |
Tony Richardson (トニー・リチャードソン) イギリスの演出家・映画監督。1956年にオズボーンの戯曲「怒りをこめてふり返れ」を演出し、文化現象として「怒れる若者たち」の口火を切った。1958年に同作の映画化で監督デビュー。独特のリアリズムで庶民ドラマを新鮮に描いた。代表作に「長距離ランナーの孤独」、「トム=ジョーンズの華麗な冒険」など。 |
 |
Karel Reisz (カレル・ライス) チェコスロバキア出身、イギリスの映画監督。1960年、アラン・シリトーの小説を原作とした『土曜の夜と日曜の朝』で長編映画をはじめて手掛ける。先に製作したドキュメンタリー映画の手法を多く用い、その評価は英国アカデミー賞最優秀イギリス映画賞の受賞といったかたちで表れた。さらに、リンゼイ・アンダーソン監督映画『孤独の報酬』に製作として参加。コメディ映画『モーガン』、イサドラ・ダンカンの伝記映画『裸足のイサドラ』、そのほか『熱い賭け』、『ドッグ・ソルジャー』でメガホンをとる。 |
 |
Jean-Luc Godard (ジャン=リュック・ゴダール) ソルボンヌ大学時代、カルチェ・ラタンのシネマクラブに通いはじめ、シネマテークの常連となり、フランソワ・トリュフォーやエリック・ロメールらと知り合う。1952年から「カイエ・デュ・シネマ」誌に映画評を書くようになり、59年に初の長編「勝手にしやがれ」を手掛ける。この作品が評判となり、“ヌーヴェル・ヴァーグ”の代表として世界的に有名になる。65年にジャン=ポール・ベルモンド主演の「気狂いピエロ」、68年にはストーンズのスタジオ・レコーディングを追ったドキュメンタリーと、社会運動にかかわるドキュメンタリーめいたフィクション部分が交差する「ワン・プラス・ワン」(アメリカ等では「Sympathy for the Devil」のタイトルで公開)を製作。68年にカンヌ映画祭を中止に追い込んだり、71年にオートバイの事故に遭いつつ、一時テレビの世界に活躍の場を移すが、80年より映画に復帰。「カルメンという名の女」、「ゴダールのマリア」、「右側に気をつけろ」、「ゴダールの決別」など問題作・異色作を輩出した。 |
 |
Alexis Korner (アレクシス・コーナー) 多くのミュージシャンを育てた功績から「ブリティッシュ・ブルースの父」と呼ばれるギタリスト、ヴォーカリスト。1940年にロンドンに移り、40年代後半にギターやピアノを始め、50年代中期には本格的にブルースを演奏するようになる。61年、ブルース・インコーポレイテッドを結成。初期の主要メンバーの一人は、後にコロシアムで活動するサクソフォーン奏者ディック・ヘクトール・スミス。また、多くの若手ミュージシャンが入れ替わり参加したが、その中にはジャック・ブルースやチャーリー・ワッツなどもいた。ブライアン・ジョーンズもコーナーのライブに参加したことがあるが、その時にミック・ジャガーやキース・リチャーズに見初められ、ローリング・ストーンズ結成のきっかけとなった。 |
 |
Cyril Davies (シリル・デイヴィス) 英バッキンガムシャー出身のブルース・シンガー、ハーモニカ、バンジョー、12弦ギター奏者。自身のバンド、ヒズ・リズム・アンド・ブルース・オールスターズ(ニッキー・ホプキンスも参加)を率いての活動のほかに、アレクシス・コーナーとブルース・インコーポレイテッドを結成したことでも知られている。 |
 |
Chris Jagger (クリス・ジャガー) 英ケント州ダートフォードの生まれ。いわずと知れたミック・ジャガーの5歳下の弟。60〜70年代にかけて、インドや中近東、ギリシャあたりを放浪したり、役者としてイスラエルでミュージカル『ヘアー』の主役を演じる。その後、ファッション・デザイナーとして、エリック・クラプトン、ジョン・レノン、ジミ・ヘンドリックスの為に仕事をしたり、また照明技術者としてロンドンのレインボウ・シアターで働いていた過去もある。ミュージシャンとしては、73年に1stアルバム『You Know The Name But Not The Face』、74年『The Adventures of Valentine Vox』という2枚のソロ作を発表するが、その後しばらく表舞台からは遠ざかる。その後、ストーンズのアルバム『Dirty Work』、『Steel Wheels』などでスタッフの一員として関わっている。裏方稼業が続く中、90年代に入り再び自身のアルバム制作を開始、94年『Chris Jagger's Atcha』で復帰。95年に『Rock The Zydeco』、2000年には『Channel Fever』を発表。2006年には兄のミックやデヴィッド・ギルモアも参加した名盤『Act of Faith』をリリースしている。 |
 |
湯川れい子 1960年、ジャズ専門誌「スウィング・ジャーナル」へ投稿。その才能が認められ同年、ジャズ評論家としてデビュー。ラジオのDJ、ポップス評論、解説を手掛けるほか、講演会、テレビでの審査員、コメンテーターとしても活躍中。多数のレギュラー頁を持ち、作詞のヒットメーカーでもある。既成の概念にとらわれない自由でおおらかな彼女の人間性といつまでも若々しいセンスが光っている作風が好評。また、真の優しさと夢を持ちつづけ、ディズニー映画日本語吹き替え版日本語詞も手掛けている。 |
 |
ZZ Top (ZZトップ) 1969年に米テキサス州で結成された3人組ロック・バンド。バンド結成当初は、ブルースに根ざしたサウンドで、黒人のブルースマン達と一緒にツアーで回ることもあった。70年にアルバム・デビュー。72年発表の3枚目のアルバム『Tres Hombres』がプラチナ・ディスクに輝く。それまでの精力的なライヴ活動と、ストーンズ、ディープ・パープル、ジャニス・ジョプリンといった数々の大物バンドの前座経験がセールスに繋がったとされている。同時に全米にも名が知られるようになり、コンサートの規模や観客動員数で次々と記録を樹立。トラック数台分に及ぶ膨大なステージ・セットを携え全米を回り、ステージに本物の蛇を持ち込むなど、ライブ・パフォーマンスも大きな話題を呼んだ。結成から40年以上経った今もメンバー・チェンジは一度もない。 |
 |
Three Degrees (スリー・ディグリーズ) 70年代に一世を風靡したフィリー・ソウルを代表する女性ヴォーカル・トリオ。1973年にギャンブル&ハフが主宰するフィラデルフィア・インターナショナル・レコーズと契約。同レーベル初の女性グループとして「Dirty Ol'Man(荒野のならず者)」で登場。コーラスを担当した「ソウル・トレインのテーマ(TSOP)」で注目を集めた。74年には「When Will I See You Again(天使のささやき)」が全米ポップ・チャート2位を記録。華やかなフィリー・サウンドに乗るセクシーで可憐な歌声は米国のみならず世界各国で人気を呼び、日本の東京音楽祭でも金賞を受賞した。その後、「にがい涙」、「ミッドナイト・トレイン」といった日本制作のナンバーも披露。70年代後半にはアリオラに移籍してジョルジオ・モロダーと組み、以降も黄金期のメンバーであるヴァレリー・ホリデイを中心に精力的な活動を続けている。 |
 |
Ike & Tina Turner (アイク&ティナ・ターナー) 1940年代後半から、自己のバンド=キングズ・オヴ・リズムを結成し活動するようになったアイク・ターナーことアイズィアー・ラスター・ターナー・ジュニア。50年代半ば、自らのファンであったというアンナ・メイ・ブロック (後の芸名ティナ・ターナー)をバンドで歌わせることになった。2人は60年に結婚し、アイク&ティナ・ターナー・レヴュー名義で活動するようになり、「Proud Mary」や「Ooh Poo Pah Doo」など、60年代から70年代にかけて数々のヒットを飛ばす人気デュオとして頭角を現していった。66年から69年の間には、ローリング・ストーンズのアメリカ公演の前座も務めており、その模様は2009年にリリースされた『Get Yer Ya-Ya's Out』の完全盤にも収録されている。特に、ティナ・ターナーの全身全霊のパフォーマンスは、当時のミック・ジャガーはもとより、現在においてもビヨンセなどの劇場型R&Bシンガーらに明白に受け継がれている。 |
 |
David Gilmour
(デヴィッド・ギルモア) 1968年にイギリスのプログレッシブ・ロック・バンド、ピンク・フロイドに正式メンバーとして加入。フロイド・サウンドを支えるギタープレイやヴォーカルで活躍する。派手なプレイは少ないものの、緻密な音作りによって叙情的で美しい独特のサウンドを生み出し、高い評価を得ている。ブルージーかつ浮遊感のあるギルモアのバッキングは、フロイド・サウンドの代名詞ともいえる存在である。また、「Comfortably Numb」、「Time」、「Money」などでのギター・ソロはロックの歴史に残るプレイとして名高い。 |