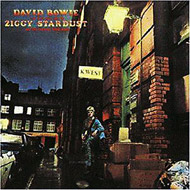Tuesday, June 1st 2010

�@���[�����O�E�X�g�[���Y�w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�f���b�N�X�E�G�f�B�V�����̔������L�O���Ă�����AHMV�X�y�V�����E�C���^�r���[���B�肵���u���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁA�������́A���[�����O�E�X�g�[���Y���͂Ă��Ȃ����[�ׁv�B
�@��4��ڂ̃Q�X�g�́A���Ă�80�N�㓌���j���[�E�F�[�u�E�V�[���̊���Ƃ��āA���݂͔����ƃ��[���A�ɂ܂݂ꂽ�t�����`�E�~���[�W�b�N�E�����^�[�A�܂��́A�쎌�ƁA�v���f���[�T�[�A�G�b�Z�C�X�g�Ƃ��Ĕ��ʘZ�]�̂����������Ă����T�G�L��������B���͂��Ȃ�̃X�g�[���Y�E�t���[�N�A�Ƃ����̂͐��ԓI�ɂ��܂�m���Ă��Ȃ��Ƃ��납������܂��A���w���̍����瑊���ȃ��b�N�E�}�j�A�Ƃ��Ēn���ߏ��łȂ炵�A���⒆�w���̂Ƃ��ɂ� �h�T�U�����b�N�n�̃o�[�h�ɓ���Z���Ă����Ƃ����G�s�\�[�h��u���A�T�G�L����̃��b�N�A�Ђ��Ă̓��[�����O�E�X�g�[���Y�ւ̕��X�Ȃ�ʈ���⎷�O�𐄂��͂����Ƃ������̂ł��傤�B
�@�N��搂����Ƃ̂Ȃ������w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�ւ̊�]�Ǝ��]�ƁA���̋��J�B�X�g�[���Y�i���b�N�j�͑��p�I�Ɏړx�A�ʓx���͂����Ă����A���߂ă}���`�ȃX�g�[���Y�i�}���`�ȃ��b�N�j�ł��蓾��A���F�̔����̂��H �ӂƂ���Ȃ��Ƃ����������Ă�������A����̃C���^�r���[��ށB�X�m�b�u�ȃj���[�E�X�^���_�[�h�u���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�S�Ă͈����邪�䂦�̂��̂��ˁA�Ȃ̂ł��B
�C���^�r���[�^�\���F ���l����
�@
- ---�@�{���͋X�������肢�������܂��B�܂��͖����\�{�[�i�X�E�f�B�X�N�̂����z���炨�f�����܂��B�S�̂�ʂ��Ă������ł������H
�@1�Ȗڂ́uPass The Wine�iSophia Loren�j�v�ɐs���܂��ˁB���̋Ȃ�1���ڂ̍��݂őS�ăI�[�P�[�Ƃ�����ۂ������܂����B�����悤�ȗ�Ō����A�uHonky Tonk Women�v�̃C���g��1���ځB�܂��A����͖{���ɃS�[�W���X�Ș^���ŁA���A���^�C���ɑ_���ɑ_���č��ꂽ���̂ł����ǁB����̓{�c�Ȃ̃f���E�e�[�v�����t�@�C���������̂ł���Ƃ͌����A�uPass The Wine�v�ɑS�Ă��������Ă���Ǝv�킹��A�������@�̂悤�Ȃ��̂������ɂ͊܂܂�Ă���ƁB
�@�ł͂Ȃ��A�J�b�e�B���O1���ł����܂Ő�����������̂��H �Ƃ������Ƃ��A�܂�����́w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx���j���[�A���E�v���W�F�N�g�̑S�̂̓���������ɂȂ��Ă����Ȃ����ȂƎv���܂����B- ---�@�����\�S11�Ȃ�ʂ��Ē����ƁA�ŏI�I�ɍ���̃v���W�F�N�g�̑S�̓I�ȃR���Z�v�g�Ƃ����̂��͂����肵�Ă���Ƃ����������ł��傤���H
�@�����ł��ˁB�C���X�g�́uTitle 5�v�A���邢�́u�_�C�X�����낪���v�̃I���^�l�C�g�E�e�C�N�����Ȃ��ۓI�ŁA�l�͖{�҂���������̃{�[�i�X�E�f�B�X�N�̕���100�{�D���ł��ˁi�j�B
- ---�@100�{�ł����I�H�i�j
�@�����A�l�́w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̓t�F�C���@���b�g�E�A���o���ł͂Ȃ���ł��B�f�����܂����B
- ---�@������������ł��ˁB���Ȃ݂Ƀt�F�C���@���b�g�Ƃ����܂��ƁH
�@�ЂƂO�́wSticky Fingers�x�̕����D���ł����A��������wLet It Bleed�x�̕����D���B����ɁA�wLet It Bleed�x�Ɠ������炢�wBeggars Banquet�x���D���Ƃ����n�D�Ȃ�ł���ˁB
- ---�@�N��ǂ����Ƃɏ������n�D����O��Ă����Ƃ����B
�@�悤����ɁA���[�����O�E�X�g�[���Y�̏����Ȃ���сA���̗��j����鉮�䍜�ɂȂ����̂́A���ǂ́g�t�@���N�h�ł���Ƃ����l���������邩��Ȃ�ł��ˁB�uJumpin' Jack Flash�v�Ńt�@���N��A���āA���ꂪ���l���y�I�ȂЂƂ̗v�f�Ƃ��āwBeggars Banquet�x�S�̂ɐF�Z���U��߂��A���̗��ꂪ���S�Ɋm�����ꂽ�̂��uHonky Tonk Women�v�B���ꂩ��A�V�����Ӗ��̃W�����v�E�i���o�[�Ƃ������ƂŁA�t�@���N�̉��߂��������Ɗ��ݍӂ��đS���V��̃X�g�[���Y�E�t�@���N�ݏo�����̂��uBrown Sugar�v�B
�@�������班�����オ����ŁA�Ⴆ���i���j�A�C�Y���[�E�u���U�[�Y���i���j�X���C���U�E�t�@�~���[�E�X�g�[���Ȃ̃t�@���N�̉e�����ė��������̂��uFingerprint File�v�ŁA�����\���ɂ��āuHot Stuff�v���͂��߂Ƃ���wBlack And Blue�x�Ɏ���ƁB����ɂ��ꂪ�A�uMiss You�v�ɂȂ�A�uStart Me Up�v�ɂȂ�Ƃ������ƂȂ�ł���ˁB60�N��}�[�W�[�E�r�[�g�ȍ~�A�܂�A�o�u���K���ȗv�f���܂q�b�g�E�V���O����`�ȍ~�́A�S�č��l���y�A���Ƀt�@���N�̊��o�����䍜�Ƃ����y�Ȃ��X�g�[���Y�̃q�b�g�ȂɂȂ����B�����ƌ����A�X�g�[���Y�̉��y���̍������Ȃ����ƁB
�i���j �X�g�[���Y�����������ł��낤�A�C�Y���[�A�X���C�̑�\�A���o��
�@���̓X�g�[���Y�͂���������Ƃ��Ȃ�����A�q�b�g���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����g���̒��ł́A�F�X�ȃg���C���������Ă���Ƃ������Ƃł������ł��B�Ⴆ�uSex Drive�v�̂悤�ɁA�V���O���E�q�b�g��_�������ǁA���ǂ̓{�[�i�X�E�g���b�N�݂����ɂȂ��Ă��܂����Ȃ�������B- ---�@�uSex Drive�v�͂�������ƃV���O���E�q�b�g��_���č��ꂽ�Ȃ�������ł����H
�@�ԈႢ�Ȃ��_���č�����Ǝv���܂��B�����A��肭�����Ȃ����������Ȃ�ł���B�F��Ȏ���ŁB���Ƃ́uUndercover Of The Night�v�������ł��ˁB�i���j�X���C�����r�[�Ȃ̗͂���āA���Ȃ�_���Ă��܂��B�wDirty Work�x��������ł��ˁB�uHarlem Shuffle�v�͈ꉞ�q�b�g�͂�����ł����A��͂�t�@���ɂƂ��Ă͕s���̎c��T�E���h�����ŁE�E�E�������A����̓X�g�[���Y�̂����ł͂Ȃ�����̂����Ȃ�ł��B�i���j�X�e�B�[���E�����[�z���C�g�̃v���f���[�X�ŃQ�[�g�E�G�R�[���g��ꂽ�肵�āA���̎���̒��ł͍őP��s�����Ă����ł���ˁB�������A�őP��s�������ɂ�������炸�A���Ǐ�肭�������̂́wTattoo You�x�́uStart Me Up�v�̂݁B������A�ǂ�ȂɊ撣���ăq�b�g��_���Ă���肭�����Ȃ��Ƃ��͂����Ȃ����A�����Ƃ��͂����A�Ƃ������Ȃ�ł���ˁB

�i���j�X�e�B�[���E�����[�z���C�g�E�E�E80�N��Ƀs�[�^�[�E�K�u���G���w�V�x�AXTC�wBlack Sea�x�A�|�[�O�X�w�����V�g�x�AU2�wWar�x�Ȃǂ���|�����g�b�v�E�v���f���[�T�[�ƂȂ����X�e�B�[���E�����[�z���C�g�B�u�Q�[�g�E�G�R�[�v�ƌĂ��X�l�A�̉����G�t�F�N�g�����ő�����������قȃh�����E�T�E���h�́A80�N�ネ�b�N�̏ے��Ƃ��Ȃ����B�X�g�[���Y��i�ɂ́wDirty Work�x�œo�p����A�uHold Back�v�Ȃǂł��̒�]����u�Q�[�g�E�G�R�[�v�T�E���h�����Ƃ��ł���B���Ȃ݂ɃL�[�X���̂����Q�G�E�`���[���uToo Rude�v�̃G�R�[�����Ɋւ��Ă͍����t�@������^�ۗ��_����E�E�E�B�v�l�̓V���K�[�ł�����J�[�X�e�B�E�}�b�R�[���B
�@���̏�肭�����������łȂ���ƁA�uJumpin' Jack Flash�v�ȍ~�́A�S�ăt�@���N�E�i���o�[�Ƃ������ƂɂȂ��Ă����ł���ˁB
�@�ŁA���̘b���Ȃ��������ł���̂��Ƃ����ƁA�܂ɂӂ�Ėl�͌��������Ă��邱�ƂȂ�ł����A�܂��ɂ��̉�������ɍ���̃{�[�i�X�E�g���b�N�������āA���N�l�������Ă������̓������A1�Ȗڂ́uPass The Wine�v�A����ɂ���1���ڂ̃J�b�e�B���O�����ŕ\������Ɏ����Ă����ł���B���̍ŏ��̉��������u�ԂɁA�����͌��܂����悤�Ȃ��̂ŁA�����ŁA���N�X�g�[���Y�ɑ��ĕ����Ă�����肪�ؖ������Ƃ������ʂɂȂ��Ă����ł��ˁB���́uPass The Wine�v�̖����Ƃ��ẮB������A�~�b�N�̐�������܂ł��Ȃ��Ƃ����i�j�B- ---�@�������܂��ƁA���́uPass The Wine�v�Ɓw���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�{�҂Ƃ̒��ړI�ȊW���͔����Ȃ�Ƃ����܂����A�ނ���A���̋Ȃ����ނقǂɁw�Ȃ炸�ҁx�̃A�E�g�e�C�N�łȂ��̂ł́H �Ƃ�����ۂɂ��Ȃ��Ă����ł���ˁB
�@��������Ȃ�ł��B�܂�A�Ȃ�2010�N�ɂ��ꂪ�o��̂��H �Ƃ������B�����āA�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�Ƃ����͉̂��������̂��H �Ƃ������ƂɂȂ��Ă���킯�Ȃ�ł��ˁB
�@�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�͒��������܂�������ǁA��͂�l�̒��ł̈�ۂ͕ς��Ȃ������B���}�X�^�[���Ă��B��N�����[�X���ꂽ�r�[�g���Y�̃��}�X�^�[�̒��ɂ́A��ۂ��ς�����Ȃ�A���o��������������܂����B�wRevolver�x��������������ł����A������i���j�uTaxman�v�ɂ��Ƃ��낪�傫��������ł��B���̋Ȃł̓x�[�X���ٗl�ȕ����������A�������i���j�n�[�r�[�E�n���R�b�N�E�O���[�v�ɂ�����|�[���E�W���N�\���̂悤�ȃx�[�X���|�[���E�}�b�J�[�g�j�[���e���Ă����B21���I�^�̃t�@���N�E�T�E���h�����łɂ���Ă����Ƃ������������炩�ɂȂ�A�wRevolver�x�̕]���͓h��ւ���ꂽ�ƁB�����ɂ���͂�g�t�@���N�h���o�Ă���̂ł����AR&B�̂悤�ȉ��y�Ƃ����̂́A���ɑ@�ׂȋZ�p����сA����ɔ����^���Z�p���K�v�Ƃ����Ƃ������ƂȂ�ł���B�����ƃ}�X�L���O����Ă����wRevolver�x�̔閧����N�̃��}�X�^�����O�Ŗ��炩�ɂ��ꂽ�B
�@���ꂪ�����āA����̃X�g�[���Y�Ȃ�ł��B�uPass The Wine�v�̂��̃��Y���́A���C�Ȃ������Ă���ƁA�u�X�g�[���Y���đ��ς�炸���Ȃ��v���Ē�������̂�������Ȃ���ł����A�t�Ɍ����A����͍�����Ȃ��Ƃł��Ȃ������Ƃ��������ł������ł��ˁB���ۂ̃}�X�^�[�E�e�[�v���Ă݂Ȃ��ƒf���ł��Ȃ������͂���܂����A�����Ȃ��Ƃ����݂̔g�`����ƃ_�r���O�ɂ�����ނ�̋Z�p�������ŁA���̋Ȃ͂܂��Ɂg���h�o��������ł���B
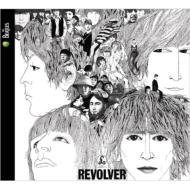
�i���j�r�[�g���Y�́uTaxman�v�E�E�E1966�N�ɔ��\���ꂽ�r�[�g���Y�̒ʎZ7���ڂ̃A���o���wRevolver�x�̃I�[�v�j���O������W���[�W�E�n���X�����쎌�E��Ȃ���|�����ȁB�T�G�L���H���u�|�[���E�W���N�\���̂悤�ȁv�Ƃ����|�[���ɂ��萔�̑����t�@���N�E�x�[�X�́A���}�X�^�[�ՂŐ��m�F���B�܂����[�h�E�M�^�[���|�[�����S�����A���ς��ŃG�X�j�b�N�ȃt���[�Y�荞��ł���B�̎��́A�����̍��z�Ȑŋ���x�T�w���璥�����Ă����J���}�����������Ă�����́B

�i���j�|�[���E�W���N�\���E�E�E1973�N�Ƀn�[�r�[�E�n���R�b�N������w�b�h�n���^�[�Y�̃x�[�V�X�g�Ƃ��ē��c�ȍ~�A���悻10�N�ɂ킽��G���N�g���b�N�E�n���R�b�N�̃{�g�����A���̑����ꖡ�s���x�[�X�E�v���C�Ŏx���Ă���B���C�u�Ղ́w�^���x��w�j���[�|�[�g�̒Ǒz�x�ł̃t�@���N�E�x�[�X�͈����B70�N��̓t�F���_�[�E�e���L���X�^�[�E�x�[�X�����p�B���݂�ESP�А��̃I���W�i���E���f�����g�p���B���{�l�����Ƃ̌������@�ɁA85�N������{�ɍݏZ���Ă���B
�@�����ЂƂ́A���R�ɂ��قړ������Ƀ����[�X����邱�ƂƂȂ����i���j���⒉�́wHORO2010�x�B���́wHORO2010�x�̒��łȂ���Ă��邱�ƂƁA���Ȃ莗�Ă����ł���ˁB���̃{�[�i�X�E�g���b�N�W�́A�ǂ��܂Ŏ���������Ă��邩�肩�ł͂���܂��A���E���H�[�J������Ă���A���邢�̓��E�M�^�[��������F��Ȃ��Ƃ��Ȃ���Ă���B�X�g�[���Y�� �g������肽���������Ɓh�ƁA�g���ł���悤�ɂȂ������Ɓh�Ƃ��������Ă����ł���ˁB���邢�́A�ނ炪���������ł������ǁA����ł͔��蕨�ɂȂ�Ȃ��������ƁB�܂�A�����̌��ʂƂ��ẮA�X�g�[���Y�I�t�@���N�E�T�E���h�Ƃ����̂́A���̎���Ȃ������܂����蕨�ɂł��Ȃ������Ƃ������ƂȂ�ł���B�Ƃ��낪�A�{���͔ނ�͂��������ꓬ���Ď������Ă����B����̓|�[���E�}�b�J�[�g�j�[�́uTaxman�v�ɂ����鏊�Ƃ��A���N�F������ĂȂ��������ƂƂ��Ȃ莗�Ă����ł��ˁB�����ł́A�uBrown Sugar�v�̂悤�ȃt�@���N�E�T�E���h�Ȃ��X�g�[���Y������Ă݂��͂������A���܂������������Ȃ������Ƃ����ꂢ�����B �uPass The Wine�v�Ȃǂ̑���ɁuRip This Joint�v��uLet It Loose�v�݂����ȋȂłƂ肠�������߂��������A�Ƃ�����ۂ��w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�ɂ͎����Ă��܂���ł��B

�i���j���⒉�́wHORO2010�x�E�E�E�W���p�j�[�Y�E�\�E���^R&B�̌��_�Ƃ��Ă��m����1975�N�̖��Ձw�ق��낤�x�B����16ch�̃}���`�E�g���b�N���������ꂽ���Ƃ��@�ɁA�V���ɏ��⒉�����H�[�J����V�^�������j���[�E�G�f�B�V���������́wHORO2010�x�B�����̃��R�[�f�B���O�E�����o�[�́A�ז쐰�b�A�ї��v�A��ؖA���C�J�����A��쌰�q�A�g�c���ގq�A�R���B�Y�A��і��q�A��쐽�Ƃ������B�X����ʁX�B35�N�O�ɔR���オ�����Ⴋ���{�̃\�E���̏�M�ɁA���܂̏��⒉���̂ʼn�����B�O��̂Ȃ����j���[�A���E�A���o���Ƃ��āA����܂łɂȂ������������V�������Ղ��a�������B - ---�@�i�j�����������Ă����Ƃ������Ƃł����H
�@���̍��̃X�g�[���Y�̋Z�p�ƁA�q�b�g�Ȃݏo���Ȃ�����Ȃ�Ȃ������̒��ł́A�uRocks Off�v��uRip This Joint�v�̂悤�Ȃ��ƃX�g���[�g�Ȏd�オ��̋Ȃ���邱�ƂőË��_�邵���Ȃ������Ǝv���܂��B���̖`��2�Ȃ̗��ꂩ�炵�āA�������g���}���l���I�h�Ƃ������i�j�B�{�r�[�E�L�[�Y�̃T�b�N�X������Ƃ���ȂA�ǂ��l���Ă����m�������肷���邵�B�Ⴆ�A�����W�����v�E�i���o�[�ł��A�uBrown Sugar�v�̏ꍇ�́A�T�b�N�X�E�\��������܂łɂȂ���������u�ˑR�̍U���ɃA�^�}�Ԃ���т܂����v�݂����ȓ˂������������������ł����A����Ɋr�ׂ�ƁuRocks Off�v�́A�ǂ����Ă��g�u���ɂ����Ă�h�������ۂ߂Ȃ���ł���ˁB
�@��͂�l���������������̂́A�uBrown Sugar�v�̑��҂������B�uBrown Sugar�v�̑��҂ƌĂׂ�悤�ȉ���I�ȃ��Y���\���ł���Ȃ���A�W�����v�E�i���o�[�Ƃ��Ă̋Ȃ̗ǂ������˔����Ă���Ƃ������̂�����������ł��B
�@�uBrown Sugar�v�̃��Y���\���Ɋւ��ẮA�������낢�b������܂��āB������i���j�����a�F����f�����uBrown Sugar�v�̂��b�Ȃ�ł����B2007�N�ɁA�i���j�z�J���`����̃v���f���[�X�ŁwRespect The Stones 2�x�Ƃ����g���r���[�g��A���o���𐧍삷��ۂɁA�l���R�[�f�B�l�[�g���Ƃ��ĐF�X�Ɠ����Ă�����ł��ˁB�����ŁA�i���j�T�f�B�X�e�B�b�N�E�~�J�E�o���h�ɂ��J���@�[�Ȃ����^���悤�ƍl���Ă��āA��������������I�[�P�[���o�Ă�����ł��B�\�Z���ł̂�肭����F�X�ƍl���Ă���āA�u�킩�����A����������v�ƁB�u���́A���^�C���}�V�[���ɂ��˂������̃��Y���́A��Brown Sugar�����Q�l�ɂ��č���Ă��邩��A��Brown Sugar�����A���̋Ȃ̃��Y���ɂ��̂܂��v���Č�����ł���B�܂�A�o���h���W�߂ăC�`����^�艺�낷�̂ł͂Ȃ��A�u�^�C���}�V�[���ɂ��˂����v�̃}���`���g���āuBrown Sugar�v��^��������Ă������ƂȂ�ł���ˁB

�i���j�����a�F / �T�f�B�X�e�B�b�N�E�~�J�E�o���h�E�E�E���́u�g�m�o���v�Ƃ��đ����̃t�@���A���y���Ԃ������爤����A���h���ꂽ�H��̖��~���[�W�V�����^�v���f���[�T�[�A�����a�F�B60�N��㔼�Ƀt�H�[�N�E�O���[�v�̃t�H�[�N�E�N���Z�_�[�Y�Ńf�r���[�B���̌�70�N�㏉������́A�\�������ƕ��s���ă��b�N�E�o���h�A�T�f�B�X�e�B�b�N�E�~�J�E�o���h�������~�J�ivo�j�A�p�c�Ђ�i�̂����Ђ�Fds�j��ƌ������A�������`�ig�j�A�����K�G�ids�j������ib�j�������o�[�ɉ����Ȃ���A75�N�ɉ��U����܂ő����̖��Ȃ��c�����B73�N�Ƀf�r���[�E�A���o���w�T�f�B�X�e�B�b�N�E�~�J�E�o���h�x�\������A���������͂قƂ�ǔ���Ȃ������Ƃ����B�قǂȂ����āA�܂��̓����h���Ől�C�ɉ����u�t�A���v�Ƃ����`�œ��{�ł������]�������悤�ɂȂ����G�s�\�[�h�͗L���ŁA�����ɉ����a�F�̓����̉p�ă��b�N�Ȃǂɑ��鍂���x�⏸�̃Z���X���D��Ă���������Ă���B�~�J�E�o���h�́A89�N�ɋ˓������A2006�N�ɖؑ��J�G�������ꂼ��{�[�J���Ɍ}���A��x�Č������͂����Ă���B

�i���j�z�J���`�E�E�EMike M. Koshitani���Ɖz�J���`���́A1966�`69�N�܂œ��{�̃��[�����O�E�X�g�[���Y�E�t�@���E�N���u��߂Ă������Ƃł������ȉ��y�]�_�Ɓ^DJ�^MC�B�X�g�[���Y�A�G�����B�X�E�v���X���[���͂��߁A���b�N�A�u���[�X�A�\�E���Ȃǂ̃A���o���E���C�i�[�m�[�c�A�G���E�V���ւ̎��M�A���W�IDJ�A�C�x���gMC�^�v���f���[�X�Ȃǂ���|���Ă���B��Ȓ����ɂ́uSTONES COMPLETE�v�i�o�t�Ёj�A�u���[�����O�E�X�g�[���Y��S�ȁv�i�\�j�[�E�}�K�W���j�A�u���[�N�X�E�I�u�E�G�����B�X�v�i�����ʐM�Ёj�A�u�X�g�[���Y�������m�肽���v�i���y�V�F�Ёj�A�ďC�^�咘�Ɂu�W���p�j�[�Y�E���b�N�E�C���^�r���[�W �`�����z����20�l�̌��t�v�iTO�u�b�N�X�j�A�u�L�[�X�E���`���[�Y�E�t�@�C���v�i�V���R�[�E�~���[�W�b�N�j�Ȃǂ�����B���݂��A�~���[�W�b�N�E�y���E�N���u�E�W���p�������ǒ��A���[�����O�E�X�g�[���Y�E�t�@���E�N���u�ږ�A�G�����B�X�E�v���X���[�E�t�@���E�N���u�ږ�Ƃ��đ�����ŕ��L�������𑱂��Ă���B
- ---�@�����Ă݂�A�Ƃ����C���ق�̏������܂����E�E�E��͂�ӊO�Ƃ������A���̂��b���f���܂ł͂���2�Ȃ��Ȃ��锭�z�͑S������܂���ł����B
�@�ɂ킩�ɂ͂悭�����ł��Ȃ��Ƃ���������ł����A�������낢�b�ł���ˁB�ŁA���̕����ł��肢�͂�����ł����A���ǁA���ߐ�̊W�ȂǂŎ����͂��܂���ł����B
�@�����ЂƂA��������̂��b�ɂȂ��ł����A�ȑO�u���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�v����́u�T�f�B�X�e�B�b�N��~�J�E�o���h�̃T�E���h�̔閧�������v�Ƃ������W�̒��ŁA�l����������ɃC���^�r���[���s���Ă����ł��ˁB����ɁA�u�~�J�E�o���h���Q�l�ɂ������y�v�Ƃ����悤�ȃe�[�}�Ō��e���������Ƃɂ��Ȃ��āB�����wNarkissos�x�Ƃ����A���o�����o������ŁA�����ɖl��������Ă����Ƃ������Ƃ�����A���[���ʼn�������ƒ��ڂ��Ƃ�����Ă����̂ŁA��ɖl���u���������̂͂ǂ��ł��傤���H�v�Ə����g�Ђ˂����h�I�ՂŃ��X�g�𑗂�����ł���B����������A���ł��Y����Ȃ���ł����A�ƂĂ��Ȃ��{��̃��[������������Ԃ��Ă��܂��āi�j�B���[�h�ɕM���̂Łu�T�G�L����ց@�N�̂����������Ⴂ�͋����Ȃ��B�܂�Ŕ����ĂȂ��v�݂����Ȃ��Ƃ�������Ă��āA����ɉ�������u�Q�l�ɂ������y�v�Ƃ��ĕԂ��Ă������̂��A�i���j�f���B�b�h�E�{�E�C�́wZiggy Stardust�x��A�i���j���b�g�E�U�E�t�[�v���́w���ׂĂ̎Ⴋ��Y�ǂ��x��A�i���j�t�F�C�Z�Y�́w�n�̎��ɔO���x���͂��߂Ƃ���A���̂�����������O��10����������ł���B���Q�G�ɂ��Ă��i���j�W�~�[�E�N���t�́wThe Harder They Come�x�ŁA������Ƃ��Ă�STUDIO ONE��i�̓˂����Ƃ�����Ă�����Ȃ����H �Ǝv���Ă����̂ł����A�����ł͂Ȃ��āE�E�E�p�ӂ������̂͑S���p���i�j�B
�i���j �{�����ɓo�ꂷ��A���o��
�@���̒��ʼn�������́wSticky Fingers�x�������Ă��āA�u��Brown Sugar���Ƃ����Ȃ��O�����E���b�N�ݏo�����ɂȂ��Ă����Ȃ����v�Ƃ������Ƃ�����������Ă�����ł���B����ȑO�ɁA�uBrown Sugar�v�ɑ������܂ŏd�v���������������Ă���l�͂��Ȃ��������A�l���g���ӊO���Ɗ����Ă����̂ł����A�u���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�v�ҏW���̎��c���T����̓s���Ƃ����炵����ł��B�l����ŋC���t�������ƂȂ�ł����A���̋Ȃ̃h���~���O�̗����̎����Ƃ������̂ɂ͉���I�ȗv�f�������āA����܂ŃX�g�[���Y�����H���Ă����o�b�N�E�r�[�g�������������������Ƃ������ƂȂ�ł��ˁB�A�b�v�E�r�[�g�ł���Ȃ���A�o�b�N�E�r�[�g�������Ă���B������R�s�[�����ɓ���āA�����̍��Z���R�s�[�E�o���h�Ȃ��A�P���� �g�O�̂߂�h�ȃR�s�[�͑����Ă��A�����Ƀo�b�N�E�r�[�g�����������R�s�[�����Ă���o���h�͂܂��Ȃ�������ł���ˁB��������Rocks Off��̂悤�Ȓ����I�ȃR�s�[�ɂȂ��Ă���ꍇ���قƂ�ǁB���Ƀh���}�[�����̕ӂ̊��o��������Ɨ������Ă��Ȃ��ƁA�uBrown Sugar�v�̃��Y���̎��j���A���X�͏o���Ȃ���ł��傤�B
�@������A�u�^�C���}�V�[���ɂ��˂����v���uBrown Sugar�v���Q�l�ɂ��Ă���Ƃ������Ƃ�S�������ł��Ȃ��̂ɂ́A�����ɔ閧������킯�ŁA�{���ɖڂ���̂��b�Ȃ�ł��B��������Ɓi�����j�K�G�����1970�N�㏉���ŁA���Y���I�ȉ��y���ɂ����āuBrown Sugar�v�𐳂����Q�l�ɂ��Ă����I ���͗͂����ɉ߂��܂��B���ۈ꒮����ƑS���Ⴄ���E�ł�����ˁB
�@�����������Ƃ������āA70�N�ネ�b�N�E�V�[���ɂ�����uBrown Sugar�v�̏d�v���Ƃ��̌㗲������O�����E���b�N�Ƃ̊W���A����ɂ́A�T�f�B�X�e�B�b�N�E�~�J�E�o���h���uBrown Sugar�v�̃��Y���\���������ɍו��܂Ŕc�����A���������̃T�E���h�ɐ��������Ƃ��Ă������A�Ƃ������ƑS�Ă��Ȃ�������ł��ˁB- ---�@�uBrown Sugar�v�̃��Y���\���Ȃǂɂ����������Ă��܂��ƁA���̌�ɑ������̂ɊȒP�ɂ͖������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂���������肻���ł��ˁB
�@���������܂����A���N�����Ă��āuStart Me Up�v�ȍ~�q�b�g�Ȃ����܂�Ȃ����Ƃ������Ă��܂����B������A�uSex Drive�v���Ă����܂��������ł��Ȃ��i�j�B���̌�́wVoodoo Lounge�x�ł́A�X�g�[���Y���ۂ�����₷��������͂�����Ƃ������ƂŁA�uLove Is Strong�v�Ȃ��Ë��_�ɂȂ��āA����������������o���̂̓v���f���[�T�[���i���j�h���E�E�H�Y�A�Ƃ������ƂɂȂ�B�wSteel Wheels�x�ɂ͎c�O�Ȃ��炻�������Ȃ͂���܂���ł����B�uMixed Emotions�v���M���M���Ë��_�Ƃ��Ďd�オ���Ă��邮�炢�B�wBridges To Babylon�x����U��ł����B�uRough Justice�v���Ƃ��A�wA Bigger Bang�x�͂��ƃC�C�������Ă��܂������A����ς�q�b�g�Ȃ͐��܂�Ă��܂���ˁB

�i���j�h���E�E�H�Y�E�E�E�{���h�i���h�E�t�F�C�O�\���B80�N��ɂ́A���Ƃ��̃f���B�b�h�E�E�F�C�X�ƌ��������f�g���C�g�̃t�@���L�[�E�o���h�A�E�H�Y�E�m�b�g�E�E�H�Y�Ŏa�V�ŃJ���t���ȃ_���X�E�T�E���h�ݏo���ꐢ���r�����B���̃J���t���Ԃ�́A�E�F�C���E�N���[�}�[�iMC5�j�A�����E�g�[���A���i�[�h�E�R�[�G���A�~�b�`�E���C�_�[�A�I�W�[�E�I�Y�{�[���A�n�[�r�[�E�n���R�b�N�A�}�[���E�n�K�[�h�A�V�[���EE ��Ƃ̋������ɂ������B�u12�C���`�E���~�b�N�X�v�̐���ɐϋɓI�������_���X�E�p�C�I�j�A�I�ȑ��ʂ̈���ŁA�v���f���[�X��ł́A����̃J���[���d�邩�Ȃ�E�l�C���Ȗ����ɓO����B�{�j�[�E���C�b�g�wNick of Time�x�ɂ���A�{�u�E�f�B�����wUnder The Red Sky�x�ɂ���A�X�g�[���Y�wVoodoo Lounge�x�ɂ���A��������̃R���Z�v�g���\���������Ȃ���V���v���ŗ��ɂ��Ȃ������@�_�ŃT�|�[�g���A�S�̂��I���܂Ƃߏグ�Ă���B
�@���Ȃ݂ɁuJumpin' Jack Flash�v�̑O�́A�u�iI Can't Get No�jSatisfaction�v�Ȃ�ł��ˁB�uSatisfaction�v�i1965�N�j�����Ɍ����Ă���̂́A�i���j�}�[�T���U�E���@���f���X�uDancing In The Street�v�i1964�N�j���Q�l�ɍ��ꂽ�B����ɂ��̌��i���j�X�e�B�[���B�[�E�����_�[�uUptight�v�i1965�N�j�́A���̕ԗ�ō��ꂽ�ƌ����Ă��܂��B����ȃ��[�^�E���Ƃ́A�h�������ǂ�h�̂��Ƃ肪����B������ɂ���A�ǂ��l���Ă����[�^�E�����X�g�[���Y�̕����g�����̏d�����Y���h ���Ƃ������ƁB

�i���j�}�[�T���U�E���@���f���X�uDancing In The Street�v�E�E�E1962�N�Ƀ}�[�T�E���[���X�𒆐S�Ɍ������ꂽ�}�[�T���U�E���@���f���X�ɂ��ł����[�^�E���炵�����S�ʂɏo��1964�N�̃q�b�g�ȁuDancing In The Street�v�́A����܂ō��l�w�����̃}�[�P�b�g�Ƃ���Ă���R&B�����X�ɔ��l�哱�̃|�b�v�E�`���[�g�ւƑ��荞�܂ꂽ�A����Ȏ���̉ߓn����@���ɏے����Ă���B�܂��A���̋Ȃ̃v�����[�V�����E�t�B�����́A�f�g���C�g�̎����ԍH��Ń��P���ꂽ���̂ŁA�������ւ����h���[�^�[�E�V�e�B�h�̉�������`�����邱�Ƃ��ł���B85�N�ɃA�t���J�Q��~�σ`�����e�B�E�R���T�[�g�u���C���E�G�C�h�v�Ŏ��������~�b�N�E�W���K�[���f���B�b�h�E�{�E�C�ɂ�鋤���J���@�[���X�g�[���Y�E�t�@���ɂ͂��Ȃ��݂ȂƂ���ŁA���̑��ɂ��L���N�X�A�}�}�X���p�p�X�A���[���E�j�[���A�O���C�g�t���E�f�b�h�A���@���E�w�C�����炪�G��ȃJ���@�[���c���Ă���B�ق��A�uHeat Wave�v�A�uNowhere To Run�v�A�uJimmy Mack�v�Ȃǂ����[�^�E���E�N���V�b�N�X�I
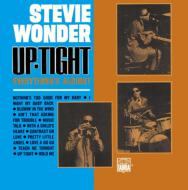
�i���j�X�e�B�[���B�[�E�����_�[�uUptight�iEverything's Alright�j�v�E�E�E�x�j�[�E�x���W���~���ids�j�ƃW�F�C���X�E�W�F�}�[�\���ib�j�ɂ��A�^�}�ł��Ŗ������郊�Y�����A���ς������傤�ǏI��������̃��g���E�X�e�B�[���B�[�E�����_�[�̂����܂����Ȃ����m�h�ɐ�����B66�N�̃q�b�g�ȁuUptight�v�ƁA�X�g�[���Y�u�iI Can't Get No�jSatisfaction�v�Ƃ̋ߐe��������邱�Ƃ͂����B����Ӗ��ōJ�̋c�_�ɃP���𒅂����̂́A�w�Ȃ炸�ҁx���s��72�N7���j���[���[�N�A�}�W�\���E�X�N�G�A�E�K�[�f�������B�O���߂��X�e�B�[���B�[�E�����_�[�E���r���[�Ƃ̋������������A�uUptight�v����́uSatisfaction�v�Ƃ����A�h����2�Ȃ͓������F�̂����h�Ƃ������Ƃ��Âɗ��҂����F�������h���[���I�B���̖͗l�͂�������t�B�����uCocksucker Blues�v�ɂ����߂��Ă���B - ---�@�����ł��ˁB�����܂ŋɒ[�Ƀ��Y���͒��˂Ă��Ȃ��悤�ȋC�͂��܂��B
�@�X�g�[���Y�̕����w���B�ɒ��������ł��ˁB�܂�A���b�N���w���B�ɂȂ��Ă�����Ń|�C���g�ƂȂ��Ă���ȂȂ�ł��B���l�̃��b�N�͍��l���y�قǐꖡ��d�݂Ƃ������̂������Ă��Ȃ��̂�����܂ŕ��ʂ�������ł����A�uSatisfaction�v�͍��l���������ȂƂȂ�킯�Ȃ�ł��B�uR&B�����l�̕����D��Ă��ăG�����v�Ƃ����}���������Ă���̂ł͂Ȃ��A���l�̑�����ɃX�g�[���Y��r�[�g���Y����e�����Ă�����ł��B�Ƃ͌����Ă��A�uYesterday�v���狭���e�����Ă����킯�ł͂Ȃ��A��͂�uSatisfaction�v�ɋ����āu���l���ĂƂ��ǂ��R�����ȁE�E�E�v�Ɗ����Ă����Ǝv����ł���ˁB�r�[�g���Y�ɂ��Ă��u�������߂����v�Ƃ��uShe Loves You�v�ɂ͈�ڒu���Ă����Ǝv����ł��B�����炱���A�r�[�g���Y�y�Ȃ̍��l�ɂ��J���@�[�������킯�ł�����B�uSatisfaction�v�Ɋւ��ẮA�i���j�I�[�e�B�X�E���f�B���O�̕ԓ�������܂����A���l�ɂƂ��Ă͓��ɋ������ꂽ�Ȃ�������Ȃ����ȂƎv����ł���B

�i���j�I�[�e�B�X�E���f�B���O�̕ԓ��E�E�E�~�b�N�E�W���K�[���������ɂ����\�E���̑勐�l�A�I�[�e�B�X�E���f�B���O��1966�N���\��3rd�A���o���wOtis Blue�x�i2���g�S40�Ȃ̃R���v���[�g�Ղ������[�X����Ă���j�Ɏ��^���ꂽ�uSatisfaction�v�B�uI've Been Loving You Too Long�v�ւ̕ԓ����ۂ��肩�ł͂Ȃ����A�u����ȉ̂����́�Satisfaction���́A���܂łɂȂ������E�E�E�v�Ɩ{�Ƃ����R�Ƃ����������ŁA�wLive In Europe�x�A�wIn Person At The Whisky A Go Go�x�A�wLive In Paris And London�x�Ƃ������e�탉�C���Ղł��������Ƃ��ł���B�ق��A�A���T�E�t�����N�����A�X���[�L�[�E���r���\�����U�E�~���N���Y�A�T�����f�C���A�����[�E�E�F���Y��ɂ��J���@�[����Ă���A�\�E�����l�����ɂ��Ƃ̂ق�������I�Ɉ����ꑱ���Ă��闝�R���������m�肽���E�E�E
�@���������Ӗ��ł��A���́uPass The Wine�v�̓q�b�g�������Ȃ���������܂��A���N�̋Q�������Ă���郊�Y���\���������Ă����ł��B�����A�����Ȃł���ΐ�ɓ��������[�X����Ă���킯�ł�����A�c�O�Ȃ���{�c�ɂȂ����Ƃ������Ƃ́A�����f�B�I�ɕW���ȉ��������Ƃ������ƂȂ̂�������܂���B�������Ȃ���A���Y���\���Ƃ����_�ɂ����č���̃{�[�i�X��f�B�X�N�́A�wDirty Work�x�Ȍ�ł��l�̋��������Ă����A���o���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ���ł���B- ---�@�T�G�L����ɂƂ��ẮA���̃{�[�i�X�E�f�B�X�N���肫�́w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��ˁH
�@�Ђǂ�������������A�{�҂��I�}�P�ł��ˁi�j�B�{�[�i�X�����C���ŁB�D��S�����Ă����Ƃ����Ӗ��ł́A�ԈႢ�Ȃ��X�g�[���Y�j��n�܂��Ĉȗ��̃A���o���ɂȂ��ł���B����������20�N�ԁA�X�^�W�I�^���ł͖{���ɖ�������Ă��Ȃ������̂ŁE�E�E����20�N�Ԃɂ����Ă��ԈႢ�Ȃ��i���o�[�E�����̃A���o���ł��B
- ---�@���̃{�[�i�X�E�f�B�X�N�����ɏo�Ă��Ȃ���Ζ{�҂́E�E�E
�@�l�ɂƂ��āA�c�O�Ȃ���i���ɓ�R�ł��i�j�B������A���̒��ɂ͂����������悤�ȃP�[�X���ǂ̂��炢����̂��H �Ǝv���Ă��܂��܂���ˁB�S���ʂ����Ȃ�������]�Ƃ������̂������āA���ꂪ�ʂ������Ƃ��ɁA���̒����ĉ���ł��Ђ�����Ԃ�낤�Ȃ��āB������l����Ƌ��낵���Ȃ��Ă��܂��܂����ǂˁB
- ---�@�X�g�[���Y�A�r�[�g���Y�ȊO�ŁA����̂悤�ȑ̌��������A���o���Ȃǂ͂���܂������H
�@�A���o���ł͂Ȃ���ł����A���̊Ԃ��i���j�W�F�C���X�E�e�C���[�ƃL�������E�L���O�̌����ɂ́A��������Ȉ�ۂ������܂����B�S�Ă̗��j��h��ւ��āA���̐l���������������Ƃ����C��������ł��ˁB�F�������S�Ƀ��Z�b�g���ꂽ�Ƃł������܂����A�������70�N�㓖������D���ł͂���܂������A�o�b�N�̃U�E�Z�N�V�����̉��t���܂߂Ă����܂Ől�����������鉹�y�ł��������Ƃ������Ƃ���������ł��B
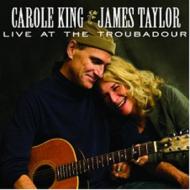
�i���j�W�F�C���X�E�e�C���[�ƃL�������E�L���O�E�E�E70�N��̕ăV���K�[�E�\���O���C�^�[�E�u�[���̉Εt�����ɂ��āA�G�o�[�O���[���ȉ́i�Ɖ��t�j�ō��������̐l�X�𖣗����鎊���̃����f�B�E���C�J�[�A�W�F�C���X�E�e�C���[�ƃL�������E�L���O�B�ނ�t������߂�����L.A.�̓`���̃��C�u�n�E�X�u�g���o�h�[���v��50���N�L�O���C�u�ł̍ďW���������i�ʐ^CD�j�����������ɁA2010�N�Ɂu�g���o�h�[���E�����j�I���v�c�A�[���J�n�B4���ɂ͓��{�����ٌ��������������B�_�j�[�E�R�[�`�}�[�ig�j�A�����E�J�X�P���ib�j�A���[�E�X�J���[�ids�j�狌�m�̃U�E�Z�N�V�������o�b�N�ɁA���R�̂Ȃ���G�l���M�b�V���ȃX�e�[�W���I�����B - ---�@���Ȃ݂ɁA����72�A3�N������̃X�g�[���Y�̃��C���ɂ͂ǂ���������ۂ��������ł����H
�@�����������ς�Ȃ������Ƃ������Ƃ�����̂ŁA���̎����̃��C���ɂ����́g���z�h������Ă���Ƃ���͂���܂��ˁB����ȑO�́wGet Yer Ya-Ya's Out�x�ɂ����Ċ��S�ɏ���Ă��Ȃ������Ƃ��낪����A���ꂪ73�N�ɍŐ������}����B���������Ӗ��ł��A���܂�Ȃ����̂͂���܂���ˁB
�@�ł��A���̍��̃��C��DVD���ςĂ���ƁA�~�b�N�̑̂̓����Ȃ͈��|�I�Ɍ��݂̕���������ł���B���̃j���A���X��������ɑ��� �g�C���̎����h�́A2000�N��̕����Ђ���Ƃ����炢���̂�������Ȃ����E�E�E�������Ⴓ�͂Ȃ��ł����ǂˁB- ---�@�g���h���ӎ������_���X�E�p�t�H�[�}���X�ɁA�܂��������Ȃ�������ƁB
�@���`��A�������Ȃ��Ƃ������A��͂莞��I�ɂ��A�܂����ꂩ��̕�������������ł��ˁB���X�����ƕ\���B������A73�N�̃��C�������łȂ��A�wGet Yer Ya-Ya's Out�x�ɂ���A�wLove You Live�x�ɂ���A�wStill Life�x�ɂ���A�S�̓I�ɂǂ���꒷��Z���ȁH �Ƃ����C�����āB�ӊO���i���j�wA Biggest Bang�x�ɓ����Ă������I�ł̃��C�����D���������肷���ł���B

�i���j�u���W���A���I�E�f�E�W���l�C���̃R�p�J�o�[�i�E�r�[�`�ɉ�����t���[�E�R���T�[�g�E�E�E�uBigger Bang World Tour�v�̈�Ƃ��āA2006�N2��18����A�u���W���̓��I�E�f�E�W���l�C���̃R�p�J�o�[�i�E�r�[�`�ɂčs��ꂽ�X�g�[���Y�̃t���[�R���T�[�g�ɂ�150���l���钮�O���W�܂����B�T���o�̍��u���W���̊X���グ�Ă̂��Ղ葛���ɁA�X�g�[���Y�����p�ӂ����R���T�[�g�E�Z�b�g������Ńh�h��B22���~57���̃��C���E�X�e�[�W��55���̃T�u�E�X�e�[�W�A�����16�{�̃^���[��8�̃r�f�I�E�X�N���[���Ƃ��Ȃ��|����Ȃ��́B�����̉��ݒu�A�����o�[�̃I�t�V���b�g�A���C���̖͗l���h�L�������g���ɒǂ����f���́ADVD�wThe Biggest Bang�x�ɏڍׂɎ��߂��Ă���B
�@���ƁA73�N�����̃��C���Ń~�b�N�E�e�C���[���ʂ����Ă�����������|�I�ɑ傫���B���͂��������ŁA�~�b�N�E�e�C���[�Ƃ̓X�g�[���Y�ɂƂ��ĉ��������̂��H �ƁB���S�Ȑ����ł����A���C���ł��ꂾ�������Ă���l���A�X�^�W�I�ł̓L�[�X�̎d��ő�ςȖڂɍ����Ă���Ɓi�j�B���̃o�����X�������������B�~�b�N�E�e�C���[�́A�X�g�[���Y�̃A���o�����A�����W�����g�ł��邾���̒n�ʂ��Ȃ���A�����炭�A�����o�[�ɗn������Ń��[�h������Ȃ��B���C�u�ł͏d��Ă�̂ɂˁB�����Ȃ��Ƃ��uTime Waits For No One�v�̂悤�Ƀ~�b�N�E�e�C���[�̃L�����N�^�[����������Ă���Ȃ��Ă����̂́A�ނ��낳���̂ڂ��āA�wLet It Bleed�x�ɂ����Ȃ����ȂƁB�wLet It Bleed�x�̕����~�b�N�E�e�C���[���ۂ����o�Ă���B�wLet It Bleed�x�́A�~�b�N�E�e�C���[�ɑ���g�T�[�r�X�E�A���o���h�Ȃ�Ȃ����Ǝv����ł��B�u�X�g�[���Y�ɓ���A���ꂾ���������Ƃ�������炳���v���āi�j�B�ł��X�g�[���Y�̑̎��Ƃ����̂́A�����ł����A���������Ōカ���ƒn���������ł���i�j�B�����ԓk�퐧�x�Œb���グ���āA20�N�ڂ��炢�ł���Ɛ��������o�[�ɂȂ����Ă����o���h����Ȃ��ł����H �܂��A�����E�E�b�h�̂��Ƃł����B ���Ƃ�����A�~�b�N�E�e�C���[�͑����Ђǂ��ڂɍ����Ă����Ȃ����Ƃ����J���Ă��܂���ł���ˁB
�@�Ƃ��낪�A�����E�E�b�h�̓L�[�X�ƌZ��̂悤�ɃT�E���h����邱�Ƃ��ł���B�i���j�wNow Look�x���i���j�j���[�E�o�[�o���A���Y�̃��C�����Ȃǂ��Δ���Ƃ���A�L�[�X�Ƃ̗ގ����͖��炩�B�����A���ꂾ�����Ă��������߂ɁA���̂�������J�����邱�ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v�����ł��ˁB�~�b�N�E�e�C���[�ɑ���g�T�[�r�X��A���o���h���wLet It Bleed�x���Ƃ�����A�����E�E�b�h�ɑ��� �g�T�[�r�X��A���o���h�́w�������x���Ǝv����ł��ˁB���̃A���o���ɂ����Ẵ����E�E�b�h�̌��̏o���́A���Ȃ�ˏo���Ă���C�����܂��B�u���̐V����ō������v�Ƃ����̂��o���h���A�s�[�����Ă����ɁA�u���[�����O�E�X�g�[���Y�ɂ���A�������������Ƃ�������v�Ƃ����̂������E�E�b�h�ɖ���킹�Ă����Ă���悤�ȃA���o���Ȃ�Ȃ����ȂƎv���܂��i�j�B
�@�������A����ȍ~�͐V�������Ƃ������Ƃ́g�C����h�ł���A�g�őO���h�ł����邩��A��������Ɓu�����ڂ��������Ă����悤�v�Ƃ����悤�ȐS�����������Ă��Ă��܂��āB
- ---�@�\���Ă���ꍇ����Ȃ��Ƃ������A�ނ���u���܂ł����q����d�����Ă�Ȃ�v���炢�̋l�ߕ��͂���Ă������ł��ˁi�j�B
�@�Ƃɂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ɓi�j�B����ŁA������E�b�h�͂ǂ�ǂ�h������ɂȂ��Ă������A���[�����O�E�X�g�[���Y���̂̃|�e���V���������������P������Ȃ��Ȃ��Ă����E�E�E�Ƃ��������Ȃ̂ł͂Ə���ɑz�����Ă��܂��B
�@�b��߂��ƁA�~�b�N�E�e�C���[�̖����̐����Ƃ����̂����ڂ����A���P������Ȃ��Ȃ��Ă����āA�ŏI�I�ɂ́A�T���^�i�݂����ȁwTime Waits For No One�v�̂悤�ȋȂŁu�͂��A����Ȃ�v�ƁB���̃A���o���i�wIt's Only Rock'n Roll�x�j�ɂ��Ă����ǂ́A�����E�E�b�h���t�B�[�`���[�����uIt's Only Rock'n Roll�v�����C���ȂɂȂ��Ă��܂�����A�g�O�����́h�őh��������Ƃ��� �g�X�e�b�v�E�A���o���h�ł���ˁB�����炱�����̃A���o���͂�����ƌ��C������B�w�R�r�̓��̃X�[�v�x�Ȃ͖{���ɍ��ׂƂ��āA�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�Ƃ͑S���Ⴄ�ǖʂ������Ă���킯�ł�����B
�@�ɒ[�Ȍ�����������A�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�Ɓw�R�r�̓��̃X�[�v�x�́A�~�b�N�E�e�C���[���͂��߂Ƃ���A�T�E���h��������Ă��Ȃ��A���o���ƌ������Ȃ����ȂƎv���Ă��܂��B�Ƃ��낪�A2009�`10�N�Ƃ��Ȃ�܂��ƁA�~�b�N�E�e�C���[�͂Ƃ����̐̂Ɏ��߂Ă��邵�A�n�[�h�E�f�B�X�N�Ŏ��R�ɐ������ł��邵�A�����ւ������R�ɂł���ƂȂ�ƁA��肽������̂��Ƃ��ł���B������āA�u��������ׂ��v�Ƃ����M�O�Ɍ������Ĉ꒼���ɁA�~�b�N�ƃL�[�X���G�f�B�b�g���Ă�������Ȃ����Ǝv����ł���B�܂��A�`���[���[�͂��������l�ł�����u�D���Ȃ悤�ɂ���Ă���v�Ƃ�������Ȃ��ł��傤���ǁB�ł��`���[���[���A���̌��ʂ́A�����������I �Ǝv���Ă�͂��B �@- ---�@�h������V���������ւ�����A�����������͂Ȃ������ł���ˁB
�@��Ԃ��Ⴄ�Ƃǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����Ȃ��ł���ˁB�h�������������Ԃ��x�z����y��Ȃ̂ŁB���̕��A�x�[�X���������肻�̂܂܍����ւ��Ă��܂��A��ۂ͂����ԈႢ�܂����ǂˁB
- ---�@�x�[�X���_�����E�W���[���Y�ɑւ�邾���ł����܂ŕς�邩�Ƃ����B
�@��͂�S���Ⴄ���̂ɂȂ�܂���ˁB�����܂Ő����ł����A���ɃL�[�X������Ȋ����̃x�[�X�������Ǝv���Ă��A�e���Ȃ���Ȃ��ł��傤���ˁB�r���E���C�}�����e���Ă���Ƃ����O������S�ɖ������Ęb���Ă��܂����ǁE�E�E�i�j
- ---�@����̃X�g�[���Y�⏬�⒉����wHORO2010�x�̂悤�ȃ��j���[�A���E�A���o����肪�A���ꂩ��ЂƂ̃X�^���_�[�h�ɂȂ�\���͂��肻���ł����H
�@�K�v��������A�Ƃ��������ł��傤���ǁB�Ⴆ�X���C�́wFresh�x�ȍ~�̍�i���A����������č�蒼���āA�����Ƃ������̂ɂ���Ƃ��B����͂��Ȃ苻������܂���ˁB�u��蒼���Ăق����A���o���v���x�X�g10�`���ŕ�W����̂�������Ȃ��ł����ˁi�j�B
- ---�@����͂��Ȃ肨�����낻���ł��ˁi�j�B
�@�l�����v��������Ƃ���ł́A�i���j�W�����E���m���wMind Games�x�A�i���j�X���C�wHeard Ya Missed Me, Well I'm Back�x�A�i���j�W���j�E�~�b�`�F���w�đ��̗U���x�B���ꂩ��A�i���j�T���^�i�wWelcome�x�B�T���^�i�̂��̃A���o���Ɋւ��ẮA���\�����̗��������͂������悩������ł����A���������o�[�ł���ɂ�������炸�A���̂悳���A���o���̃T�E���h�ɂ͌���Ă��Ȃ��Ǝv���Ă��܂�������B����ŁA�i���j�{�Y�E�X�L���b�O�X�́wSilk Degrees�x���i���j�C�[�O���X�́wHotel California�x�Ȃ́A��ɍ�蒼���K�v���Ȃ��A���o�����Ǝv���܂����B
���[�����O�E�X�g�[���Y ���̑��̋L���͂�����
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��1��z ����� �hCHABO�h ��s
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��1��z ����� �hCHABO�h ��s
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��2��z �s�[�^�[�E�o���J��
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��2��z �s�[�^�[�E�o���J��
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��3��z ���c���T�i���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�ҏW���j
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��3��z ���c���T�i���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�ҏW���j
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��5��z ����h �i�\�E���E�t�����[�E���j�I���j
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��5��z ����h �i�\�E���E�t�����[�E���j�I���j
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� �ŏI��z �q���ʑΒk�r�z�J���` �~ ��h��
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� �ŏI��z �q���ʑΒk�r�z�J���` �~ ��h��
 �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̐^��
�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̐^��
 HMV�I��������I �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
HMV�I��������I �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
 �y��U�z �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
�y��U�z �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
 SHM-CD�^���W���P�E�{�b�N�X��2�e
SHM-CD�^���W���P�E�{�b�N�X��2�e
 �X�g�[���Y �^�Ẵl�u���[�Y�� 1976
�X�g�[���Y �^�Ẵl�u���[�Y�� 1976
�T�G�L���� ���C�����g�[�N�C�x���g�E�X�P�W���[��
�T�G�L������Club Je t'aime ���C�u
�u�̐S�ɏW���IReal French Night! 2�v
���F�a�J ������
�����F2010�N6��24���i�j�J��18:00�@�J��19:00
�����F�i�\��j2500�~�^�i�����j3000�~
�o���F����J�J�^��
�T�G�L������Club Je t'aime ��NANASE�ip�j�A�،b�悵�ig�j��
�ules cocottes�v(���E�R�R�b�g) ��YUCA�ifrom �����L�����o�j�[)�ivo,dance�j�A
MIHO�ifrom hi-posi�j�ivo,dance�j�A�Q�C���[�����ip�j��
�c�m���O�Y�i�A�R�[�f�B�I���j
���R�V�}�o���ifrom Pecombo�j�������y�q�A�������G�ivo�j�A�������F�ig�j��
�����H�[�J���O���[�v�u�y�R���{�v���琶�܂ꂽ�����y�q�E�������G�̎o�����j�b�g�B
�t�����`�E�{�T�m�o���珺�a�̗w�܂ŁE�E�E���R�V�}�Ȃ���{�[�_���X�ȑI�Ȃ��ɏ�ȃn�[���j�[�ł��� �����܂���
DJ�@KOKI
���⍇���^���\��F03-3407-3564
���[���ł̂��\��Finquiry@aoiheya.com
pearlnet@nifty.com
�T�G�L�����̃R�A�g�[�N�@vol.79
�u�Ǔ��F�����a�F����낤�v
���F�V�h���t�g�v���X����
�����F2010�N7��23���i���j18��30���J��@19��30���J��
�����F�i�O���j2000�~�^�i�����j2300�~�@���Ƀh�����N���
�o���F�y���ʃQ�X�g�z���� ��i�T�f�B�X�e�B�b�N�E�~�J�E�o���h�j
�y�Q�X�g�z����^��
�y�i��z�T�G�L����
���⍇���F03-3205-6864
���t�g�v���X����
���O����6/5�i�y�j��胍�[�\���`�P�b�g�A�C�[�v���X�Ŕ���
�yL�R�[�h�F37893�z
|
Exile On Main Street �X�[�p�[�E�f���b�N�X�E�G�f�B�V���� |
���̑��̃o�[�W����
 ������
��3,800
������
��3,800�f���b�N�X�E�G�f�B�V�����i�f�W�p�b�N�j 2010�N05��19��
 ������
��2,200 2010�N05��19��
������
��2,200 2010�N05��19��
 ������
��2,800
������
��2,800����� SHM-CD �i���W���P�j 2010�N06��30��
-
-

-

- �T�G�L�������N���u�E�W���e�[��
�p�������� - 2009�N���\
-
-
-

-

- �T�G�L����
�X�V���̒j - 2003�N���\
-
-
-

-

- �p�[���Z��
�����̓p�[�� - 1986�N���\
-
-
-

-

- �p�[���Z��
�p�[���g���� - 1987�N���\
-
-

-

- �p�[���Z��
�S�A�F�A��̃p�[���Z��{�� - 1987�^89�N���\
-
-

-

- �p�[���Z��
Blue Kingdom - 1988�N���\
-
-
-

-

- �p�[���Z��
Toyvox - 1989�N���\
-
-
-

-

- �p�[���Z��
�Z�{�ؓ� - 1990�N���\
-
-
-

-

- �p�[���Z��
�S�[���f�����x�X�g - 2004�N���\
-
-
-

-

- �n�������Y
�n�������Y�̋ߑ�̑� - 1980�N���\
-
-
-

-

- �n�������Y
�n�������Y��20���I - 1981�N���\
-
-
-

-

- ���N�z�[�������Y
���N�z�[�������Y16 - 1988�N���\
-
-
-

-

- Parador�@�n���C�̋x��
�i�T�G�L���� �I�ȁj - 2004�N���\
-
-
-

-

- Ananda
Ananda
�i�T�G�L���� �v���f���[�X�j - 2003�N���\
-

-
�T�G�L���� �i������ �����j
�@1958�N��t���o�g�B1980�N�A�n�������Y�̃��H�[�J���X�g�Ƃ��āw�n�������Y�̋ߑ�̑��x�Ńf�r���[��A83�N�ɌE�c���j�A�����M�Y��ƃp�[���Z��������B86�N�w�����̓p�[���x�ŃA���o���E�f�r���[�B90�N�ɌE�c���j�́u�����v�i���E�ށj�Ŏ�����̊�����~��]�V�Ȃ��������A2003�N�ɌE�c�̕��A�Ŋ������ĊJ�B�A���o���w�F�����s�x�ƃX�^�W�I�E���C�uDVD�w�^��ƃ��m�N���x�i�h�����ɁAROVO�A�f�[�g�R�[�X�E�y���^�S���E���C�����E�K�[�f���ł��Ȃ��݂̖F�_���m�A�x�[�X�ɂ́A�{�ԗ��V�ƃj���[�n�[�h�A�~�Øa���O���[�v�Œm���闧�ԑוF���}����4�l�Ґ��o���h�j�������[�X���Ă���B�\���Ƃ��ẮA2003�N�Ƀt�����X�ŃA���o���w�X�V���̒j�x�������[�X���A�t�����X�E�c�A�[���s�����B�܂��A��c����u�|�����C�hGIRL�v�A���[�����C�_�[�Y�u9���̊C�̓N���Q�̊C�v�A����G���uRock Your Fire�v�A���[�j���O���B�u���̎�v�ȂǑ����̃A�[�e�B�X�g�ɍ쎌���s���Ȃ���A�e���r�A���W�I�o���A����ɂ́A�G�b�Z�C�X�g�A�v���f���[�T�[�Ƃ��Ă����L���������B2009�N�ɂ́A�����v���f���[�X����|�����A�L�o�n�K�[���Y�E�|�b�v�E�R���s�wTOgether SONGS Neo girls 2010�x�����g��Pearlnet�@Records���烊���[�X���Ă���B
- �֘A�T�C�g�i�O���T�C�g�j
- �֘A���W�iHMV�T�C�g���j