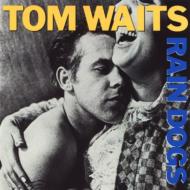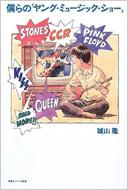「レコード・コレクターズ」編集長・寺田正典 インタビュー 3
Friday, May 7th 2010

- --- 2010年はツアーも新作発表もないというアナウンスがされた中で、「Plundered My Soul」などが準新曲として世に出てきたことはファンとして喜ばしいのですが、来年以降、純粋な新作のリリースやツアーを開始するにあたり、現在のストーンズの状況に関してはどうご覧になられていますか? 個人的にはリハビリ明けのロニーが少し心配な部分でもあるのですが・・・
う〜ん、そうですねぇ・・・ロニーが抜けてミック・テイラーが入るなんていう単純なパターンにはならないと思いますが(笑)、ミック・テイラーも体調的にちょっとキビしそうな感じもするし・・・体型的にも体が大きくなりすぎて、ミック・ジャガーの美学からして「ステージには立たせたくない」っていうのがあるんじゃないかなと(笑)。ただ、ゲストで時々迎えるなんてことはありそうですよね。例えば、ミック・テイラーを迎えてロイヤル・アルバート・ホールでスペシャル・ギグを行うとか。そういったことぐらいはしそうだなと思います。
- --- 先ほどお話にも出ていた『メイン・ストリートのならず者』再現ライヴに多少近いものを観れる可能性もありそうですよね。例えば、ライヴ中間部のこじんまりとしたアコースティック・セットで「Sweet Virginia」や「Sweet Black Angel」などを挟んで”ならず者メドレー“のようなことをやったりだとか。
当時と演奏スタイルが変わってしまっているからガッカリする面もあるかなとは思いますが(笑)、まぁ考えられますよね。たしか2003年の「Licks Tour」の日本公演のときに、ステージ上の巨大モニターに『メイン・ストリートのならず者』のジャケットとトラックリストを映し出して、ファン・サービス的な演出も含めてその中から「Loving Cup」を選んで演奏したりして。その程度か、そこに色が付いた程度のことはすると思いますが・・・やるからにはちゃんと歌ってほしいんですけどね(笑)。
- --- 「Loving Cup」にしても、当時のキーで歌い切るのは相当難しそうですね(笑)。
ミックは声も歌い方も当時と変わっているんですけど、それ以上に変わっているのがキースで。キースは、78年のツアーの途中で“声変わり”というのがあって。それ以降も声はさらに潰れてきて、今は完全にトム・ウェイツになってますから(笑)。「Loving Cup」や「Sweet Black Angel」で僕が好きだったのは、キースのハーモニーなんですけど、さすがにそれはもう無理でしょうね。(註)バーナード・ファウラーあたりが歌うしかない。でも、「Loving Cup」ではそれすらちゃんとやっていなかったんですよ(笑)。もはやキースじゃなくてもいいから、ハーモニーだけは付けてほしい(笑)。
- --- 『メイン・ストリートのならず者』からは、いまだライヴで演奏されていない楽曲をまずは聴いてみたいですよね。「彼に会いたい(原題:I Just Want To See His Face)」なんてどう再現されるのか妄想しただけでもう・・・
そうなんですよね。というのも、今回僕はこの「彼に会いたい」をとても重視していまして。以前「レコード・コレクターズ」で(註)トム・ウェイツの特集を組んだときに資料を色々整理していて、トム・ウェイツの自伝を読み直したりしていると、彼はこの曲にすごく影響を受けていたっていうんですね。しかも、(註)『Swordfishtrombones』以降サウンドがガラッと変わるときに、Dr.ジョンの初期のヴードゥー色の濃い楽曲と「彼に会いたい」に特に影響を受けたと、自分のフェイヴァリット・カヴァー・アルバムを作るとしたら、タイトルは「I Just Want To See His Face」にしたいって言ってるぐらいで。
- --- そうだったんですね。さすが判っていらっしゃるというか。
「彼に会いたい」は、元々ストーンズがDr.ジョンに影響を受けて作った曲なんじゃないかと僕は思っていたので、Dr.ジョンの影響がストーンズを経由してトム・ウェイツに及んでいることが見えてきて、なるほどな、と思いました。
ちなみに、ジャム・バンドの(註)フィッシュが昨年『メイン・ストリートのならず者』を丸々カヴァーするというライヴをやっていたんですが、その音源を聴いてみると、「彼に会いたい」をけっこうな長尺でやっていて「あぁ、判ってるな」と。「Turd On The Run」もかっこよかったですけどね。
オンマウスで大きな画像 (註)フィッシュの「メイン・ストリートのならず者」カヴァー・ライヴセット・・・言わずと知れたアメリカのジャム・バンド、フィッシュが昨年のハロウィン週に開催した「Festival 8」という3日間のイベントの中日で、「Exile On Main Street」を丸ごと演奏(曲順もそのまま)するというセットを敢行し、ストーンズ・ファンのド肝を抜いた。このセットの中で、特に再現が難しいと言われていた(本家も1度もライヴ演奏はなし)「彼に会いたい」を、ゴスペル色濃厚のバックアップ・シンガー(おそらくDAPTONEレコーズのシャロン・ジョーンズ)を交えた10分近い長尺ジャム・アレンジでキメてくれた。ちなみに彼らのオフィシャル・ホームページでは、その全18曲のライヴ音源をフリーダウンロードしていたが現在は終了している。 - --- ゴスペル色の強い黒人女性コーラスを加えて、かなり“判ってる”カヴァーでしたよね。
ドキュメンタリーDVDの『Stones In Exile』には、この曲の女性コーラスによる当時のオーヴァーダビング・シーンが入っていて、これがまたすごくかっこいい。おそらく『メイン・ストリートのならず者』の中で当時一般的に判りにくいと思われていた曲って、ちょっとカントリーっぽいB面(当時のLP)あたりか、変わったリズムの「Ventilator Blues」か、あるいはこの「彼に会いたい」かだったような気がするんですよ。だけど、この曲の本当のかっこよさっていうのは、その『Stones In Exile』での映像を見て初めて鮮明に伝わってくるんじゃないかなと思います。このゴスペル感といい、ヴードゥー感といい、今最も再評価をしたい曲なんですよ。
- --- たしかに「彼に会いたい」は、僕も個人的にもっと評価が高くてもいいと思っている曲で、『メイン・ストリートのならず者』というアルバムが持つ猥雑で妖しいかっこよさがこの曲に集約されているとまで感じています。
この曲に関しては、(註)ビル・プラマーの貢献というのも大きいんですよ。L.A.で色々と最終作業をする中で、ビル・プラマーのベースを足していますよね。この人はすごいおもしろい人だなと前から思っていまして、(註)ヘンリー・マンシーニの『The Party』というラーガ・ロックっぽいサントラがあるんですけど、その中でシタールを弾いているのが実はビル・プラマー。本来はシタール奏者なんですが、兼任してアップライト・ベースも弾くという変り種。彼のソロ・アルバムの邦題が(註)『ビル・プラマーの不思議な宇宙世界』(笑)。Impulseから出ているんですが、これの帯付LPがあったら是非買いたいなと思っているぐらいで、めちゃめちゃそそられるでしょ?(笑) 他では、ボブ・シールなんかと一緒にやっていたりしてすごい変わった活動歴がある人なんですよ。ベーシストとしての仕事は、普通のスタジオ・ミュージシャン的なこともかなりやっていて、トム・ウェイツの(註)『Closing Time』にも参加しているんです。
『メイン・ストリートのならず者』では、「Rip This Joint」や「Turd On The Run」などで切れのいいアップライト・ベースが聴けるんですが、「彼に会いたい」でもすごい味のある音を出しているんですよね。「これベース?」みたいな音が全編に入っていて、それが何ともいえないグルーヴを作り上げている。だから、L.A.での最終仕上げでいちばん変な作業だったのが、「彼に会いたい」でのビル・プラマーのベースかなと(笑)。それまで謎に包まれていたこともありますが、ついついビル・プラマーを過大評価してしまうひとつとしては、この曲があるからなんですよね。
(註) ビル・プラマー リーダー&参加の主なアルバム
さらに、「彼に会いたい」とは別にストーンズがトム・ウェイツに影響を与えたもうひとつのラインがあって、それが、『メイン・ストリートのならず者』のジャケット・アートワークをディレクションしている写真家/ムーヴィ・カメラマンのロバート・フランク。そのロバート・フランクに最も影響を受けた人というのが、(註)ジム・ジャームッシュなんですね。ジャームッシュがモノクロの世界でアメリカを捉えるあの感覚。で、彼と組んで映画を作るのがトム・ウェイツ。つまり、トム・ウェイツとジャームッシュが組んで作る映画の世界の大元には、実は『メイン・ストリートのならず者』があったんだなと。ジャームッシュがこのアルバムに対して特別な意識を持っていたかどうかは判りませんが、ラインとしてはこの2つがトム・ウェイツに流れ込んでいて、ロバート・フランクという人物を挟むことによってその全てのつながりが見えてきたんです。
ところが、そのトム・ウェイツに今や逆に影響を受けて、キースはあんな声になってしまったという(笑)。キースの歌うバラード・ナンバーの世界にしても然りで。

(註)ジム・ジャームッシュ・・・80年の処女作『パーマネント・バケーション』で注目され、84年の第2作『ストレンジャー・ザン・パラダイス』が、その独特のユーモアと新鮮な演出で絶賛され、カンヌ国際映画祭カメラ・ドールを受賞。「ニューヨーク・インディーズ派」の若手映画監督として注目を浴びた。キャリア初期には、ラウンジ・リザーズのジョン・ルーリー、トム・ウェイツ、ジョー・ストラマーなど自身が愛好するミュージシャンたちを俳優としてキャスティングすることが多かった。また、2003年の「コーヒー&シガレッツ」にはイギー・ポップを起用している。2005年には、カンヌ国際映画祭で『ブロークン・フラワーズ』(エチオピア・ジャズの開祖ムラトゥ・アスタトゥケ音源を多数使用!)が審査員特別グランプリを受賞。2009年の最新作「リミッツ・オブ・コントロール」では、エクスペリメンタルなサイケ〜アートロックを展開する日本のバンド、ボリスの楽曲を使用している。 - --- 話が前後してしまうのですが、寺田さんが初めて『メイン・ストリートのならず者』本編を聴いたときの印象というのは?
よかったですよ。ただ聴いたのが発売当時ではないんです。そもそもストーンズを聴くようになったのが77年ぐらい、(註)NHKの「ヤング・ミュージック・ショー」で初めて観てからなので。そこからちょこちょこと聴き出して、しかもキャッチーな曲がなさそうという理由で、『メイン・ストリートのならず者』はかなり後回しになっていたんです。「Tumbling Dice」や「Happy」は知っていましたけど。当初は『Beggars Banquet』にしても僕にとってはちょっと難しそうな気がしたアルバムだったので、それ以上に難しそうだなと思って買うのを躊躇っていたんですよね。
それでも結局は、躊躇っていたにもかかわらず、1曲目(「Rocks Off」)からバッチリでした(笑)。リアルタイムで聴いたわけではないんですが、70年代っぽい時代の泥くささとストーンズっぽいグルーヴがいちばん完成されたカタチになっているなと思ったんですよ。いちばん最初は、「ヤング・ミュージック・ショー」で「Star Star」を観て気に入って、『山羊の頭のスープ』を買ったんですが、なんだかドロッとしたアルバムで・・・投げ捨てようとしたぐらい(笑)。そういう具合に1発で気に入るものもなかった中で、『メイン・ストリートのならず者』はもう1発で。最初から大好きでしたね。
しかも、好きな要素がどんどん増えていくという。当時はLPでしたから、CD時代だったらもしかして飛ばしていたかもなという曲が、どんどん減っていく。それで、今回あらためて評価を与えたい曲その2が、「Casino Boogie」。- --- これも歌詞の並べ方がおもしろい曲ですよね。
この曲の歌詞に関しては、「UNCUT」のインタビューでもミック・ジャガーが「(註)ウィリアム・バロウズのカットアップの手法を用いた」って。そんなこと全然知らなくて、ビックリ。

(註)ウィリアム・シュワード・バロウズ・・・1914年セントルイス生まれ。1950年代のビート・ジェネレーションの作家の一人で、60年代にJ・G・バラードらによって「ニューウェーブSFの輝く星」として称えられた。ハーヴァード大学卒業後のニューヨーク時代には、ビート世代の詩人アレン・ギンズバーグや、作家ジャック・ケルアックらと知り合い親交を深めた。52年にデビュー作『ジャンキー』を発表。59年、ギンズバーグらの熱心なすすめと手助けにより、書き溜めていた断片をもとにした小説『裸のランチ』を発表。猥褻かつグロテスクな内容で発禁処分を受けたことがかえって話題となり、実験小説の雄として一躍バロウズの名を世に広め、同時に、タイプした紙をバラバラに刻んでランダムにつなげた「カットアップ」という手法をも広く知らしめることになった。主な著書には「裸のランチ」、「シティーズ・オブ・ザ・レッド・ナイト」、「ゴースト」などがある。97年没。 - --- バロウズだったんですね。
たしかに変な詞だなとは思っていたけど、当時そこまで深くは考えていませんから。多分ネイティヴの人には相当変な歌に聴こえていたんでしょうね。さらに言えば、『Stones In Exile』DVDの中には、テーブルの上に(註)「Skydiver, insider...」だとか「Pause for business」だとか書かれた紙が置いてあって、それを並べ替えているシーンがあるんですよ。
(註)「Skydiver, insider...」 「Pause for business」・・・「スカイダイバー 事情通 縄跳び 曲芸師...」 「仕事のための小休止 わかって欲しい...」と、「Casino Boogie」の風変わりな歌詞は、ミック曰く「ウィリアム・バロウズのカットアップの手法」を引用したものだという。頭で考えて作り込んだストーリーをあてがうのではなく、シャッフルしたカードをランダムに並べるような言葉遊びから、奇妙なストーリーを偶発させる。ややもすると『メイン・ストリートのならず者』においてもっともドラッギーでリズミカルな遊戯と言えるのかもしれない。71年にバロウズは「裸のランチ」をミック・ジャガー主演のミュージカルにしたいということをこぼしていたらしい・・・ - --- そんなシーンが存在するんですか!?
そのシーンはどうも「Cocksucker Blues」(未公開のドキュメンタリー・フィルム)のアウトテイクのようなんですよね。「Cocksucker Blues」自体はL.A.以降の姿しか追っていないので、必然的に「Casino Boogie」の歌詞はL.A.で作られたということになるんですが・・・まぁ単なる演出なのかもしれませんけど(笑)、ただそのシーンがあるということで、この曲の歌詞のひとつひとつの言葉の強さみたいなものがより感じられて、こんなかっこいい曲だったのか、と(笑)。
- --- そうしたお話を訊いていますと、『メイン・ストリートのならず者』のボックス・セットと『Stones In Exile』DVDは、 あらためて “ニコイチ”で持っておくべきなんだなと思いますね。
本当そうですよね。ボックス・セットのDVDには「Ladies And Gentlemen」と「Cocksucker Blues」のダイジェストが丁寧な編集で入っているので、もちろんそれにも目を通しつつ、より深くこの時期のストーンズを知りたい人は『Stones In Exile』も観ることをおすすめします。そのDVDで使われている音源をよく聴いていると、ソノシート・ヴァージョンとは異なる「Exile On Main Street Blues」だとか貴重なものもあって、「Casino Boogie」のくだりのような驚くべきシーンもいっぱい入っているんですよ。
もっとも「Cocksucker Blues」もダイジェストではありますが、ようやくオフィシャル化ということで貴重ではあります。その中にはスティーヴィー・ワンダーと共演している「(I Can't Get No)Satisfaction」のライヴ・シーンなども入っていますし、さらに「Ladies And Gentlemen」に至っては画も音もかなりクリアになっていて、見逃せない内容になっています。
そうしたドキュメント映像を含めて、今回新しい発見が非常に多かったですね。『メイン・ストリートのならず者』というアルバムを再評価するだけじゃなくて、ローリング・ストーンズというバンドのレコーディング方法を含めたバンドとしての在り方をあらためて考えさせられることになりましたね。
|
ローリング・ストーンズ その他の記事はこちら
 【スペシャル・インタビュー企画 第1回】 仲井戸 ”CHABO” 麗市
【スペシャル・インタビュー企画 第1回】 仲井戸 ”CHABO” 麗市
 【スペシャル・インタビュー企画 第2回】 ピーター・バラカン
【スペシャル・インタビュー企画 第2回】 ピーター・バラカン
 【スペシャル・インタビュー企画 第4回】 サエキけんぞう
【スペシャル・インタビュー企画 第4回】 サエキけんぞう
 【スペシャル・インタビュー企画 第5回】 中川敬 (ソウル・フラワー・ユニオン)
【スペシャル・インタビュー企画 第5回】 中川敬 (ソウル・フラワー・ユニオン)
 【スペシャル・インタビュー企画 最終回】 〈特別対談〉越谷政義 × 石坂敬一
【スペシャル・インタビュー企画 最終回】 〈特別対談〉越谷政義 × 石坂敬一
 『メインストリートのならず者』の真実
『メインストリートのならず者』の真実
 HMVオリ特決定! 『メインストリートのならず者』
HMVオリ特決定! 『メインストリートのならず者』
 【解剖】 『メインストリートのならず者』
【解剖】 『メインストリートのならず者』
 SHM-CD/紙ジャケ・ボックス第2弾
SHM-CD/紙ジャケ・ボックス第2弾
 ストーンズ 真夏のネブワーズ祭 1976
ストーンズ 真夏のネブワーズ祭 1976
|
Exile On Main Street スーパー・デラックス・エディション |
その他のバージョン
 国内盤
¥3,800
国内盤
¥3,800デラックス・エディション(デジパック) 2010年05月19日
 国内盤
¥2,200 2010年05月19日
国内盤
¥2,200 2010年05月19日
 国内盤
¥2,800
国内盤
¥2,800限定盤 SHM-CD (紙ジャケ) 2010年06月30日

-
寺田正典 (てらだ まさのり)
1962年長崎生まれの福岡育ち。早稲田大学卒業。1985年ミュージック・マガジン社に入社。93年から「レコード・コレクターズ」編集長に着任。監修及び編集に携わったローリング・ストーンズ関連の書籍としては、『レコード・コレクターズ増刊 ローリング・ストーンズ』(1990年発刊)、『レコード・コレクターズ増刊 STONED! The Ultimate Guide To The Rolling Stones』(1998年発刊)、『レコード・コレクターズ増刊 The Rolling Stones CD Guide』(2003年発刊)などがある。
「レコード・コレクターズ」
ミュージック・マガジン社から刊行されている、ひと味違う音楽ファン、レコード・ファンのための月刊誌。1960〜70年代の米英のロックを中心に、ポピュラー音楽を幅広く扱う。詳しいディスコグラフィー付きで取り上げたアーティストの音源をすべて聞くためのガイドとなる特集が好評。
インタビュー中に登場する主要人物について |
 |
Andy Johns (アンディ・ジョンズ) ロンドンのオリンピック・スタジオを拠点に仕事をしていたイギリスの名エンジニア/プロデューサー、グリン・ジョンズを兄に持つアンディ・ジョンズ。60年代末から70年代初頭にかけては兄の関わる作品で共同エンジニアを務め、レッド・ツェッペリン、ブラインド・フェイスのアルバムに携わり、また、70年代初期のフリーの作品をプロデュースしていることでも知られている。ストーンズ作品では、『Sticky Fingers』から『It's Only Rock'n'Roll』までの4作品でエンジニアを務め、70年代黄金期のストーンズ・サウンドの確立に貢献している。70年代末にアメリカに移り、テレヴィジョン、ジョニ・ミッチェル、ロン・ウッドの作品に参加。80年代以降はヴァン・ヘイレンなどハード・ロックの名プロデューサーとして名を馳せている。 |
 | Bill Plummer (ビル・プラマー) 米西海岸出身で元々ジャズ畑を中心に活動をしていたマルチで異色なベース・プレイヤー/シタール奏者、ビル・プラマーは、「The Basses International Project」というプロジェクトで共に活動していた、ジョン・レノン、エリック・クラプトン、ライ・クーダー作品への参加でおなじみの名セッション・ドラマーのジム・ケルトナーを介してストーンズのプロデューサー、ジミー・ミラーと知り合い、そこで『Exile On Main Street』の数曲でアップライト・ベースを弾くよう依頼されたという。 |
 |
Bobby Keys (ボビー・キーズ) 60年代末、レオン・ラセルを中心とする米南部スワンプ・ロック・サークルで活動していたボビー・キーズは、ジミー・ミラーを介してストーンズと出会うことになる、テキサス出身のサックス奏者。10代でバディ・ホリーのバック・バンドでの演奏を経験し、その後も様々なバンドでの演奏を経たのちにレオンの紹介でディレイニー&ボニーのツアー・バンドに参加。この大編成バンドには、エリック・クラプトンやデイヴ・メイソンらも参加していたということもあり、彼らからストーンズ作品参加へのアドバイスなどもされていたのだろう。『Let It Bleed』所収の「Live With Me」を皮切りに、『Sticky Fingers』の「Brown Sugar」など数々のストーンズ楽曲でブルース・フィーリング溢れるサックス・ソロを披露し、1970年以降はツアーのレギュラー・メンバーに着任(1975〜78年はゲスト扱い)している。ボビーに「キースのような人間に一生で5人会えればラッキーだよな」と言わしめたそのキースとは同じ生年月日(1943年12月18日)ということもあり、ソロやニュー・バーバリアンズなどストーンズ以外の活動でも度々共演しながら、現在もソウルメイトのような理想的な信頼関係を保ち続けている。 |
 |
Clydie King (クライディ・キング) テキサス州ダラス出身のR&B/ソウル・シンガー、クライディ・キングは、60年代にはレイ・チャールズのコーラスを担当していた3人組レイレッツの一員として活動していた。ソロとしてもSpecialty、KENTといった名門にシングルをコンスタントに吹き込んでいたが、彼女の知名度を飛躍的に伸ばしたのは、やはり様々なセッションへのコーラス参加だろう。ジョー・コッカー『Mad Dogs And Englishmen』のツアー一行として、ヴェネッタ・フィールズ、シャーリー・マシューズらと結成したブラックベリーズは、そのまま『Exile On Main Street』のLA録音の現場になだれ込むかたちとなった。そのほか、ハンブル・パイ、ボブ・ディラン、スティーリー・ダンなどの名アルバムの中に彼女のクレジットを見かけるはずだ。 |
 |
Dr. John (ドクター・ジョン) おなじみニューオリンズ・スワンプの生き字引、Dr. ジョンことマック・レベナック。ニューオリンズ・ミュージックとスワンプ・ロックの素晴らしい交叉盤『Gumbo』をすぐ近くのサウンド・シティ・スタジオでレコーディングしていた時期でもあり、そちらのレコーディング・メンバーであったタミ・リン、シャーリー・グッドマンを引き連れ、ハリウッド・スタジオでの「Let It Loose」のコーラス録音に参加したというのがおおよその経緯。また、1970年に録音されたDr. ジョンのアルバム『The Sun、Moon & Herbs』には、ミック・ジャガーが6曲もバック・コーラスで参加しており、そのお礼に、といったところも多分に含んでいるのだろう。 |
 |
Gram Parsons (グラム・パーソンズ) インターナショナル・サブマリン・バンド、バーズ(『ロデオの恋人』時代)、フライング・ブリートー・ブラザーズを渡り歩き、カントリー、またはカントリー・ロックを追求し続けた男、グラム・パーソンズ。『Let It Bleed』の制作にとりかかった頃から、キースとグラムとの親交は始まったと言われている。「Love In Vain」、「Country Honk」、「Wild Horses」、「Dead Flowers」、また、キースとグラムが南カリフォルニアの公園にUFOを見に行った時にアイデアが浮かんだとも言われている「Moonlight Mile」など、グラムがストーンズ・サウンドに与えた影響というものは計り知れない。もちろん『Exile On Main Street』のレコーディングにおいても、仏ネルコート、最終ミックスが行われたLAハリウッド・スタジオにグラムは訪れていて、「Sweet Virginia」、「Torn & Frayed」といった楽曲でその親睦がのぞかれる。グラムは、1973年、2枚目のソロ・アルバム『Grievous Angel』を完成させた直後にアルコールとドラッグの過剰摂取により26歳という若さでこの世を去ったが、その後もストーンズは、「Far Away Eyes」、「Indian Girl」、「The Worst」、「Sweethearts Together」といった曲にカントリー・フレイヴァを吹き込むことによって、その友情を永遠のものとしている。 |
 |
Jimmy Miller (ジミー・ミラー) 1968年、春の訪れとともに「ブルース」、「米国南部」というルーツ・ミュージックへの指針をしっかりと捉えたストーンズは、アイランド・レコーズ創設者クリス・ブラックウェルの肝煎りとしてスペンサー・デイヴィス・グループやトラフィックなどを手掛け注目を集めていた新進気鋭のジミー・ミラーをプロデューサーに抜擢。ちょうどその頃完成したばかりだったトラフィックの2ndアルバム『Traffic』のサウンドをミックがいたく気に入ってスカウトしたそう。ブルースを機軸とした手堅くアーシーなサウンド作りの中にも実験的な試みを次々と取り入れた『Beggars Banquet』でそれは吉と出て、以降『Goat's Head Soup』までにおいてジミー・ミラーはストーンズから全幅の信頼を得て、揺るぎない黄金期のサウンドを作り上げている。 |
 |
Jim Price (ジム・プライス) ボビー・キーズと同じくLAスワンプ・サークル諸作品やビートルズ作品などに参加していたテキサス出身のセッション系トランペット奏者ジム・プライス。ボビ・キーズの紹介によりストーンズ作品へ参加となったその初登場曲は、『Sticky Fingers』所収となる「Bitch」で1970年のオリンピック・スタジオにて。Stax系ジャンプ・ナンバーをストーンズ流に昇華したこの曲では、ジムとボビーによるパンチの効いたホーン・セクションが明らかにドライヴ感を与えている。この後1973年のウインター・ツアーまでバンドに同行し、70年代ストーンズの黄金期を支えた。 |
 |
Kathi McDonald キャシー・マクドナルド ジャニス・ジョプリン亡き後のビッグ・ブラザー&ホールディング・カンパニーの2代目ヴォーカリストとして、さらには、ジョー・コッカー『Mad Dogs And Englishmen』やレオン・ラッセル率いるシェルター・ピープルへの参加など、地味ながらもブルース・ロック、スワンプ・ロックの最重要作品にこれでもかと名を連ねているブルース・ロック女裏番長シンガー、キャシー・マクドナルド。白人でありながらディープなソウル/ブルース歌唱で魅せるという点でジャニスやボニー・ブラムレットらとしばしば比較されるキャシーだが、ミュージシャンズ・サークルにおける彼女の評価というものは2人を遥かに凌ぐ高いものがあった。1974年のソロ1stアルバム『Insane Asylum』(邦題:精神病棟!)には、スライ・ストーン、ニール・ショーン、ロニー・モントローズ、ニルス・ロフグレン・・・といった大物たちが参加。彼女の歌声がいかに魅力的かを間接的に証明している。ストーンズとは『Exile On Main Street』の「All Down The Line」での共演となり、疾走感のあるキャッチーなフックを華やかにバックアップ。 |
 |
Leon Russell (レオン・ラッセル) グリン・ジョンズの紹介でストーンズと出会うこととなるレオン・ラッセルは、まずは『Let It Bleed』の「Live With Me」にピアノで参加し持ち前のLA流スワンプ・サウンドの一片を名刺代わりに差し出す。しかし、レオンのストーンズへの最大の貢献は、その広い人脈を生かし米南部のミュージシャンズ・サークルを彼らストーンズと共有したという点にある。自身のシェルター・ピープル、デラニー&ボニー&フレンズ、ジョー・コッカーのマッド・ドッグス&イングリッシュメンといった共同体が誇る腕利きの人海を、当時南部ルーツ・サウンドに飢えていたストーンズの助力のために惜しげもなく送り込み、ブルース、ソウル、カントリー、ゴスペルの持つ泥くさく豊かなニュアンスを分かち合ったその功績は称えられてしかるべき。また、1969年初のソロ・アルバム『Leon Russell』の録音には、ビル・ワイマン、チャーリー・ワッツが参加している。 |
 |
Robert Frank (ロバート・フランク) 大方のロック・ファンにとっては『Exile On Main Street』のジャケット・アートワーク、そして、ドキュメンタリー・フィルム『Cocksucker Blues』という、ストーンズ史上屈指のいかがわしい芸術性を匂い立たせる2大プロダクツを手掛けた人物としてよく知られるロバート・フランク。1924年、スイスのチューリッヒで生まれ育ったフランクは、47年に移民としてニューヨークに出てきた後、50年代半ばには全米を放浪しながら、実にフィルム767本を使用しながら市民の現実の生活を写真に収め続けた。撮影イメージ約27、000点、ワークプリント約1000枚の中から83作品が写真集にまとめられ、58年5月に「Les Americains(アメリカ人)」として刊行されている。アレン・ギンズバーグやジャック・ケルアックといったビート詩人らと共鳴し合うことで「視覚的詩人」とも呼ばれていたフランク。「Les Americains(アメリカ人)」にも掲載されていた写真をコラージュしたアートワークは、ストーンズの楽曲イメージを肥大化させる一種の魔法や麻薬めいたパワーに満ちている気がしてならない。 |
 |
Venetta Fields (ヴェネッタ・フィールズ) ニューヨークはバッファロー出身のR&B/ソウル/ゴスペル・シンガー、ヴェネッタ・フィールズは、アイク&ティナ・ターナーのバック・コーラス・グループ、アイケッツに在籍していたことでも知られている。アイケッツがレビューを離れた後は、据え置きメンバーでミレッツとしての活動に移行。その後はクライディ・キング、シャーリー・マシューズらとのブラックベリーズとして様々なミュージシャンのバック・コーラスに参加。中でもピンク・フロイド『Dark Side Of The Moon』のツアー、そして、『Exile On Main Street』といったロック畑でのビッグネームとの仕事が特に目を引く。 |