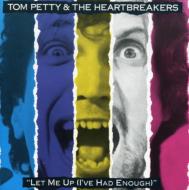�u���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�v�ҏW���E���c���T �C���^�r���[ 2
Friday, May 7th 2010

- ---�@���̃^�C�~���O�Łw���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̃f���b�N�X�Ղ������[�X����ɂ������ẮA�o���h���������̓��R�[�h��Б��ɉ������ʂȈӐ}�ł��������̂ł��傤���H
�@�����[�X�����߂�܂ł̑�܂��ȗ���Ƃ��ẮA�f���b�N�X�E�G�f�B�V�����E�V���[�Y��ɂ��Ă���Universal�̕�����A�܂��̓o���h���ɖ����\�e�C�N�̒lj������肢���������ŁA����ɂ́A����ɍ��킹�āw���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx��S�ȉ��t���郉�C���̃I�t�@�[�������炵����ł���B�f��ꂽ�����ł����A�u�ł��܂���v�Ɓi�j�B�����o�[�������Ƃ͈���Ă���Ƃ������Ƃ������ł����A�`���[���[�E���b�c�H���u�X�^�W�I�ł����o���Ȃ��m���ƃ��C���ł����o���Ȃ��m�����͂�����ʂ�Ă��邩��v�Ƃ������Ƃ炵����ł���B�܂��A�`���[���[�͓����̃A���o���������Œ��������Ƃ����^�C�v�ł͂Ȃ�����悭�����Ă��Ȃ���ł��傤���ǁi�j�B�~�b�N�ɂ��Ă����C����MC�Ŏ��^�A���o�����ԈႦ���肵�Ă��܂�����i�j�A�ߋ��̍�i�ȂɊւ��Ă̓t�@���قǎv������͂Ȃ��̂�������܂��ǁB���邢�́A�������������g�_�u���E���C���[�����h�̂悤�ȍ��������Ă��邩��Y��Ă��܂��̂����m��܂��ǂˁB���������I�t�@�[���o�������炢�����獡��̃f���b�N�X�ՂɊւ��ẮAUniversal�T�C�h�����Ȃ���C�������Ǝv���܂��B
�@�X�g�[���Y�Ƃ��Ă͂�����āA�u�o���������́v �u�o�������Ȃ����́v�A�u�����Ă�����́v �u�����Ă��Ȃ����́v��U�蕪�����B����ł��A�A�E�g�e�C�N�Ƃ����Ă������i������������̂����Ȃ葽�������B�������AUniversal���܂߂āg�A���_�[�O���E���h�h�ł��łɏo����Ă�����̂�������Ă����̂͏\���ӎ��͂��Ă����݂����Ȃ�ł��ˁB�����Ȃ�Ƃ������K�ՂƂ��ďo�������ƂȂ�Ə������Â炢�Ƃ����l���������āA�V���Ɏ�������邱�ƂɂȂ����݂����Ȃ�ł���B- ---�@�����܂ō�荞���̂��o���Ă���Ƃ������Ƃ́A�������邢�͂���܂łɁA�~�b�N�A�L�[�X�ɂƂ��Ă����c�������Ƃ����ɑ����āA�u�����́E�E�E�v�ƍ���̂悤�ȋ@����f���Ă����Ƃ��l����ꂻ���Ȃ̂ł����B
�@�����E�E�E�Ȃ�ł����A���̂��ɂ͗L���ňӖ��̂�����̂����Ȃ������Ƃ����̂͂����ł����ǂˁB
- ---�@�ȑO�ɏo����Ă����d�v�ȃ\�[�X�̒��ŊO��Ă�����̂�����ƁH
�@�Ⴆ�ΐ����ɏo����Ă������̂̒��ł́A�uAll Down The Line�v���uHappy�v�̃V���O����B�ʂɎ��߂��Ă������ɂ��i���j���m�����E�~�b�N�X�ŁA������̕����u�X�����v���ۂ��Ă����������v�Ƃ��������t�@���̒��ł͑���������ł����A���܂�CD�����炳��Ă��Ȃ��B
- ---�@�L���V�[�E�}�N�h�i���h�̃R�[���X���S�ʂɏo�Ă���~�b�N�X�ł��ˁB
�@������f���b�N�X�E�G�f�B�V�����̓��{�ՂɃ{�[�i�X�E�g���b�N�Ƃ��āuAll Down The Line�v�̕ʃe�C�N���lj������Ƃ������Ƃ����܂����Ƃ��ɂ́A���̃��m�����E�~�b�N�X�������̗L���ȃA�R�[�X�e�B�b�N�E���@�[�W����������̂��ȂƎv���Ă�����ł����A�S���ʂ̃e�C�N���̗p����Ă����ł��ˁB

�i���j�uAll Down The Line�v���m�����E�~�b�N�X�E�E�E72�N7���ɃA�����J�ł̑�2�e�V���O���Ƃ��ăJ�b�g���ꂽ�uHappy�v�B���̏����v���X��B�ʂ́A�A���o���E���@�[�W�����Ƃ͈قȂ郂�m�����E�~�b�N�X�́uAll Down The Line�v�����߂��Ă���A�s�A�m�ƃL���V�[��}�N�h�i���h�ɂ��R�[���X�����O�ʂɏo����Ă����B�t�@������CD����ؖ]�����X�g�[���Y�̃��A�E�g���b�N�̒��ł���\�I�ȉ����̂ЂƂł�����B
�@���邢�́A�X�g�[���Y���Ƃ��Ă͏o�������Ȃ����̂������̂����m��܂��A�i���j���I���E���b�Z����DCC����S�[���hCD�Ƃ��čĔ����ꂽ1st�A���o���̃{�[�i�X�E�g���b�N�̒��ɂ́A�uShine A Light�v�i�u�iCan't Seem To�jGet A Line On You�v�j�����I���E���b�Z���̍�ȃN���W�b�g�œ����Ă��āA�o�b�N���X�g�[���Y�ł͂Ȃ����ǃ~�b�N���̂��Ă���Ƃ������̂������āB�w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�Ɏ��^���ꂽ�Ƃ��ɂ́A��������X�g�[���Y�̃N���W�b�g�ɂȂ��Ă��邵�A���Ȃ�s�v�c�ł͂�������ł����A���̓�ɂ��Ă��S���G����Ă��炸�𖾂��ꂸ���܂��B

�i���j���I���E���b�Z�� 24KARAT GOLD DISC �uLeon Russell�v�E�E�E�uShine A Light�v�̌��ȂƂ������́A���̃��n�[�T���E�e�C�N�Ƃ������鉹���u�iCan't Seem To�jGet A Line On You�v���{�[�i�X�E�g���b�N�Ƃ��Ď��^����DCC�́wLeon Russell�x24KARAT GOLD DISC�BL.A.�X�����v���ɉ����A�r���E���C�}���A�`���[���[�E���b�c�A�G���b�N�E�N���v�g���A�W���[�W�E�n���X������Q�����A69�N9���̃����h���E�I�����s�b�N�E�X�^�W�I�ōs��ꂽ���̃A���o���̃Z�b�V�����E�\�[�X���o���ƂȂ��Ă���A�̎��̓X�g�[���Y�ŁuShine A Light�v�ƈقȂ���̂́A�~�b�N�E�W���K�[���̂��A�����S�E�X�^�[���h������@���Ƃ������Ȃ苻���[���p�[�\�l���ƂȂ��Ă���B
�@�����ЂƂ́A����72�N��2�����炢�Ɂu�j���[�E�~���[�W�J���E�G�N�X�v���X�v�Ƃ����C�M���X�̉��y�V���ɕt���Ă����i���j�v�����[�V�����p�̃\�m�V�[�g�B�~�b�N���s�A�m��e���Ȃ���uExile On Main Street Blues�v�Ƃ����u���[�X���̂��A���ԂɎ��^�����Ȗ������݁A�Ȗ����o�Ă���Ƃ��̋Ȃ�������Ƃ����A���ƃm�x���e�B���̋������̂ł͂����ł����ǁA����Ɋւ��Ă������̓o�b�N�̃s�A�m���X�e�B�[���B�[�E�����_�[�ɒe�����悤�Ǝv�������Ƃ��A�L�������E�L���O�ɓd�b�Ő��܂Ŋ|�������̂̎q��ĂɖZ�����f���A���ǃ~�b�N���e�������Ƃ��i�j�A��������݂����Ȃ�ł���B�������v�����p�\�m�V�[�g�̂��߂ɂ����܂ł�邩�A�Ǝv���܂������ǂˁi�j�B�@�����������������c�O�Ȃ������Ȃ�������ł���B

�i���j�uExile On Main Street Blues�v�\�m�V�[�g�E�E�E�w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�A���o��������2�T�Ԍ�ɍT����72�N4���̍ŏI�T�A�C�M���X�̉��y�V���u�j���[�E�~���[�W�J���E�G�N�X�v���X�v�ɂ́A�s�A�m�̔��t���o�b�N�Ƀ~�b�N���A���o���Ɏ��^�Ȗ���g�ݍ��킹�ĉ̂��������I�ȃI���W�i���E�u���[�X�uExile On Main Street Blues�v���t�^�Ƃ��ĕt����ꂽ�B���̋Ȃ̍��ԂɁA�uAll Down The Line�v�A�uTumbling Dice�v�A�uShine A Light�v�A�uHappy�v��5�Ȃ��_�C�W�F�X�g�ŕ��^����Ă���B
�@�ł��܂��A���̕ӂ̉��Ɋւ��ẮA7���ɏo��wStones In Exile�x�Ƃ����A�����J�A�C�M���X�ł�TV���f�����h�L�������^���[DVD�̒��ł��炿�璮�����ł���B����DVD���ςĂ���ƁA�����\�{�[�i�X�E�f�B�X�N�Ƃ͂܂��قȂ�A�E�g�e�C�N��ʃ~�b�N�X���������������邵�A�g�[�N�o�b�N�Ȃł̓X�^�W�I�̃Z�b�V�����E�e�[�v�����̂܂g���Ă����ł��B������A�{���ɃA�E�g�e�C�N�����ō�낤�Ƃ��Ă����Ƃ��J�^�`�ɂ͂Ȃ�����Ȃ����Ȃ��Ďv����ł����ǂˁB�ł��F��ȈӖ��ł����͂������Ȃ�������ł��傤�B�܂肻�ꂪ�ނ�̃X�^�C�����ȂƁB- ---�@�Ⴆ�uSo Divine�v�Ȃǂ� �h�A���_�[�O���E���h�h�ł͊��S�ȃC���X�g�ŁA�uAladdin Story�v�Ƃ������肪�ނ����ʓI�ł�����ˁB
�@�uSo Divine�v�Ƃ����^�C�g�����̒��������Ƃ��Ȃ��������B�A���r�b�N�Ƃ��������m�I�Ȃ��̃����f�B���o�������_�Ń��[�L���O�E�^�C�g���Ƃ��ăo���h���t�������A���o�����ۂɋƎ҂��t�������E�E�E����Ō�ɁuSo Divine�v�Ƃ����^�C�g�����t����ꂽ���Ă��Ƃ͓��R�̎����ォ��t�����Ă���ƁB����Łh�Ώہh������悤�ɁuAladdin Story�v�Ə����Ă���Ǝv���܂��B
- ---�@���̋ȂɌ��炸�A�h�A���_�[�O���E���h�h���ʂɂ��e�ȃ^�C�g���t��������Ă��܂���ˁB
�@�ӎ��͂��Ă��܂���ˁB�ӎ����Ă��Ȃ���uSo Divine�v�����ł悩�����킯�ł�����B����Ƃ������낢�̂��A���ɂ��̋ȂŎv�������ƂȂ�ł����A�w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̂Ƃ��̕��͋C�ƈႢ�܂���ˁH�i�j �{�҂͂���������ƃA�[�V�[�Ńu���[�W�[�ȓ��ꊴ�����邩��A����ȃT�C�P�ȁA�ނ���w�T�^�j�b�N�E�}�W�F�X�e�B�[�Y�x�̂Ƃ��̃A�E�g�e�C�N�ƌ����Ă��M���Ă��܂������ȋȂ�����͕̂s���R���ȂƂ��v������ł����A�悭�悭�l���Ă݂�Ƃ��̋Ȃ̃A�C�f�A�Ƃ����̂́h�����z���h�����āA���̂܂��́w�R�r�̓��̃X�[�v�x�̃W���}�C�J�E���R�[�f�B���O�ւƗ���Ă�������Ȃ����ȂƁB�ŁA���̃A�C�f�A�̔��W�`�������炭�u���ׂĂ͉��y�iCan You Hear The Music�j�v�Ƃ����ȂɂȂ�����Ȃ����ȂƂ����z�����ł�����ł���B�����Ȃ��Ă���ƍ��x�́wLet It Bleed�x��wSticky Fingers�x�̃A�E�g�e�C�N�Łw���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx���ł����悤�ɁA�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx���������ɂ��ڂ�o�����̂������āA����͂��̌�̃A���o���ɂȂ����Ă���Ƃ����B
- ---�@�u�_�u���E���C���[�����v�ł���A�u�L�����[�E�I�[�o�[�����v�ł�����܂��ˁi�j�B
�@�����Ȃ�ł��B�w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�ɗ���Ă���A�E�g�e�C�N�������������Ă���̂ł͂Ȃ��āA�������痬��o�����̂��������Ă���B���̂��Ƃ���A���́w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx��L.A.��71�N�̕�ꂩ��72�N�ɂ����āA�ꉞ�~�b�N�𒆐S�ɓ����̎��㐫�Ȃǂ��l�������^�Ȃ�������x�i���Ă����Ȃ����Ǝv����ł���B����ł�2���g�ɂ͂Ȃ��Ă��܂����ǁB�����͋Ȃ��G�������Ĕ���ɂ����A�L���b�`�[�ȋȂ��Ȃ����Ă��������L�c�������Ă����悤�ł����A����ł������ƍi���Ă��āA�{���͂����ƃA�C�f�A���c���ł�����Ȃ����ȂƁB�c��݂����Ă����Ɏ��܂肫��Ȃ��A�C�f�A�����́w�R�r�̓��̃X�[�v�x�Ɏ����z���ꂽ��A�t�@���N���ۂ��j���A���X���l�I�Ɋ������uPass The Wine�v�Ȃ́wBlack And Blue�x�ɂ܂łȂ�������Ƃ��B�܂�X�����v�ƌĂ��A�����J�암�ƈꕔ�C�M���X���ɂ�鉹�y�̈�僀�[�������g���N������70�N��O���ɁA�X�g�[���Y�͂��łɂ��̎��Ɍ��������̂���肩���Ă�����Ȃ����ȁA�ƂȂ�킯�Ȃ�ł��ˁB
�@������A�uPlundered My Soul�v�Ȃ��͂��߂Ƃ��āA�ӊO�Ɓw���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx���ۂ��Ȃ��ȂƂ����������łɋ������Ă���Ǝv����ł���B����ɂ�2�Ӗ��������āA���̉��Ƃ��č�蒼���Ă���Ƃ����ʂ�1�ƁA�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̃R���Z�v�g�I�ɂ������ʂ�̃A�E�g�e�C�N�ƂȂ��Ă�����̂������Ă��邩��ł͂Ȃ����Ɩl�͎v���܂����B
�@���̃o���h����Ȃ菬�Ȃ����Ă��邱�Ƃ��Ƃ͎v���܂����A�����������ɍl����l����قǁA���R�[�f�B���O�E�o���h�Ƃ��ẴX�g�[���Y�Ƃ����̂́A���R�[�f�B���O�̓��R�[�f�B���O�A�����i�͊����i�Ƃ�������I�蕪���A���̎��㐫�����s���낵�F�t�����č�i���o���Ă����o���h�ȂȂƎv���Ă��܂���ł���B- ---�@����Ɍ����A�A�E�g�e�C�N�̊Ǘ��\�͂Ƃ����܂����g�Q�������h�ɂ������Ă����̂ł͂Ȃ����ƁE�E�E
�@�g�Q�������h����肾���Ă��Ƃ͂��邩�Ǝv���܂��B�S���̋Ȃ��������ƊǗ����Ă����Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����A�ꕔ �g�����z���h�Ń��E���[�N�����悤�Ȃ��̂Ɋւ��ẮA�~�b�N�Ȃ�L�[�X�Ȃ�̓��̕Ћ��A���Ǝ�̓͂��͈͂ɂ������肵�āA�Ƃ��ǂ�����Ɏ��L���Ƃ��E�E�E�ނ���w�h�̒j�x�̈Ȍ�A�������������Ƃ��������Ȃ��Ă����̂�������܂��ǂˁB���̃A���o�������܂��������Ƃ������Ƃ������āB
�@����ɁA���́w�h�̒j�x���E�P�����Ƃɂ���āA�X�g�[���Y���g���g70�N��̎��������h�Ƃ������̂��ĕ]�����n�߂Ă��銴���������ł���B70�N��̎��������̂ǂ��������������t�@���ɃE�P�Ă����̂��H ���邢�͍����E�P�邩�H�@�ƍl���o���B
�@�����炭80�N�ギ�炢���������Ǝv����ł����A���́w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx���u�ނ�̍ō����삾�v�Ƌ}�Ɍ�����悤�ɂȂ�����ł���B�����͌������]���������̂ɁB�l�̋L���ł́A80�N��㔼�ɃA�����J���E�C���f�B�[�Y�̒��ŁA�Ⴆ���i���j�f���E�t�G�S�X���i���j�u���b�N�E�N���E�Y�̂悤�Ȃ�����ƃS�X�y���A�X�����v���ۂ����t���������T�E���h�̃o���h���o�Ă�����Ƃ��A�i���j�g���E�y�e�B�̃o���h�������������悤�ȃT�E���h��ڎw���n�߂���Ƃ��A���������������Ɂu�����C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁ��݂����ȁE�E�E�v�Ƃ������Ƃ����̂��������ɂ����悤�ȋC�������ł���B����ȑO�ɂ��G�A���X�~�X�݂����ȃo���h�͂�����ł����ǁA�����܂Ńn�[�h���b�N�F�������Ȃ��Ƃ���� �u�X�g�[���Y���ۂ��v���Č�����o���h�̃T�E���h�ɑ��āA�K���ƌ����Ă����قLj��������ɏo����Ă����̂��w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�Ȃ�ł���ˁB�uAll Down The Line�v�̂悤�ȃp���[�E�R�[�h�ȏ�̃R�[�h�������������郊�t�ɁA�S�X�y�����ۂ��R�[���X��X���C�h�E�M�^�[�Ȃ�����Ă��肷��8�r�[�g�̃��b�N�����[���ɑ��ẮA��̂��������Ă����悤�ȋC�����܂��B
�i���j �����ɓo�ꂷ��80�`90�N��� �h�Ȃ炸�ҁh�I�A���o���{�� �s�C�O�ҁt
�@�ŁA���̑O�ォ��X�g�[���Y�{�l������������ӎ�����悤�ɂȂ��āA�wVoodoo Lounge�x�ł͂��ꂪ���Ȃ��̓I�Ɍ���Ă����Ȃ����ȂƁB�uYou Got Me Rocking�v�����Ƃ��ɁA�u�X�g�[���Y���X�g�[���Y�̐^��������}�Y�C��v���Ėl�͎v������ł����ǁi�j�B�X�g�[���Y���g��70�N��̃X�g�[���Y���A�������悭�����č\�z�i�j�B- ---�@���������A�ނ���Ȃ������i�j�B
�@�i�j�uYou Got Me Rocking�v�ɂ́A�w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�ɁuBrown Sugar�v�̗v�f�Ȃ������Ă��܂�����B�}���J�X�̐U������܂߂Ă�����70�N��I�B
- ---�@�����b�ɏo���u���b�N�E�N���E�Y�Ȃ́g�Ȃ炸�҂��ۂ��h�Ƃ����̂́A�i���j�wSouthern Harmony & Musical Companion�x������ɂƂ��������Ȃ̂ł��傤���H �ނ���1st�A���o�����i���j�wShake Your Money Maker�x����H
�@1st�����肩�炷�łɂ������������͂��������Ǝv���܂����A�ǂ��炩�Ƃ����u�u�t�F�C�Z�Y�I�v�Ȋ������E�E�E�ł����̃A���o�����o��89�N�����ƁA�i���j�K���Y�E�A���h�E���[�[�Y�Ȃ̕��������ƃX�g�[���Y���ۂ���ł���ˁB�����n�[�h�E���b�N���ł����ǁB���{�Łu�o�b�h�{�[�C�Y�E���b�N�v������オ�����Ƃ��ł��ˁB���̕ӂ�̍�i�ɑ��ẮA�u�X�g�[���Y�I�Ȃ��́v�Ɓu�t�F�C�Z�Y�I�Ȃ��́v�ƁuT�E���b�N�X�I�Ȃ��́v���炢�܂ł��悭������܂��ɂȂ��Č����Ƃ��������ł���B�uT�E���b�N�X�I�v�Ƃ����̂́A�uGet It On�v�݂����ȗ������g�������Y���E�M�^�[�ŁA������L�[�X�����ƁuIt�fs Only Rock�fn Roll�v�ɂȂ�Ƃ����i�j�B
�i���j �u���b�N�E�N���E�Y�́h�Ȃ炸�ҁh�I�A���o��
- ---�@�g�X�g�[���Y���g��70�N���A�h�Ƃ����A���c����̃u���O�ł́A�i���jSuperfly�́wBox Emotions�x�ƃX�g�[���Y�Ƃ̊W�ɂ��Ă̂��Ȃ苻���[�����y������Ă��܂����ˁB
�@Superfly�̏ꍇ�������낢�̂́A�u90�N��X�g�[���Y�̒��ɂ�����g70�N��X�g�[���Y�ĕ]���h�v�ȍ~�̉�����������Ƃ����Ƃ���Ȃ�ł���B���A���^�C���ł͂Ȃ��������������������āA�i���j�X�g���[�g�E�X���C�_�[�Y���i���j�������A�ŋ߂ł��i���j�є�̃}���[�Y�̂���Ă���X�g�[���Y�I�ȗv�f�Ƃ͈Ⴄ�B�������A�A�e�B�e���[�h�����ŁA�i�D�������B�����ɃT�E���h�����B���̒��ŁA�u90�N��ȍ~�̃X�g�[���Y���g�ɂ�� �g70�N��X�g�[���Y�ĕ]���h�v�̗���ɂ���70�N��X�g�[���Y�E�T�E���h��ǂ��Ă���悤�Ɏv���Ă���̂ŁA���o�������ԈႤ��ł���ˁB���̓��������ǁA���͋C�͑S�R�Ⴄ�B���܂��ɁuAlright!!�v�Ƃ����Ȃɂ́A�~�b�N�̃\���̗v�f�������Ă���Ƃ����i�j�B���j�[�E�N�����B�b�c���D���Ȃ�ł��傤���ǁA���̗��҂������Ŋy�Ȃ�����Ă���Ƃ������Ƃ��ӎ�������ŁA���j�[�E�N�����B�b�c�̗v�f�����߂āA����ɑS�̓I�ɁuJumpin' Jack Flash�v�̃X�p�C�X���U��߂Ă���ƁB
- ---�@�g�X�g�[���Y�E�`���h�����h�Ƃ������́A ���͂�g������h�̐V�����X�g�[���Y�̑������ł���ˁB
�@90�N��ȍ~�ɗm�y���n�߂Ă�����ǁA���̑O��J-POP����D�����������オ�������肷�邩��A�h���J���̏�ɃX�g�[���Y������Ă���݂����ȂƂ���������ł���ˁi�j�B������A����܂ł̂�����X�g�[���Y�E�t�H�����[�ƌĂ�Ă����o���h�Ƃ̓A�e�B�e���[�h���قȂ��āA�ł����͂�����������X�g�[���Y�����Ă����B���ꂪ�������낢��ł���ˁB
�@����Ɋ����邱�ƂƂ��āA���g�����炳�܁h�ɂ��Ƃ������Ƃ́A�Ђ���Ƃ����DJ�ȍ~�̊��o�Ȃ̂�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB�X�g�[���Y�Ɠ����ゾ�Ɓg�܂�܁h��邱�Ƃɒ�R�͂��邯�ǁA���̌�̐���̌h�ӂ̕\�����Ƃ��ẮA�u���X�y�N�g�͑f���Ɂv�Ƃ������Ƃ�������܂����ˁB
�i���j �X�g�[���Y�E�`���h�����`������̃A���o���{�� �s���{�ҁt
- ---�@����w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�������\�e�C�N�ƂƂ��ɍēx���̒��I�ɐ���オ��ƁA�܂��g������h�ɂ��V�������߂��F�X�Ɛ��܂��\�������肻���ł��ˁB
�@ Superfly������́w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�ɔ������ĉe������Ƃ���A�����炭�����\�e�C�N�̕����炶��Ȃ��ł��傤���B�X�g�[���Y���g����荡���ۂ��Z���X��70�N��𑨂������Ă���Ƃ��������ŁB����ɁA����܂ň�ʓI�Ɂw���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�Ől�C������ȂƂ����̂́A����ς�uTumbling Dice�v�A�uRocks Off�v�A�uAll Down The Line�v�������肵����ł����ǁA���ꂩ��́uLoving Cup�v�A�uVentilator Blues�v�A�u�ނɉ�����v�݂����ȋȂ����̃o���h�Ȃɉe����^�����肷��Ƃ������낢�ł���ˁB
- ---�@�g�X�g�[���Y�E�`���h�����h�̖���Ƃ�������K���Y�ł́A�i���j�wUse Your Illusion 1 & 2�x�́g�������ϊ��h�́A���� �g�Ȃ炸�҂��ۂ��h��������̂ł����B�܂Ƃ܂肪�Ȃ��悤�Ɍ����āA���̓A���o����ʂ��Ẵe���V�����͈�т��Ă���Ƃ����_�Ȃǂɂ��������ߐe���������܂��B
�@�K���Y�A�u���b�N�E�N���E�Y�A���邢���i���j�N���C�A�E�{�[�C�Y�Ƃ������悤�ȃo���h���F�X�Əo�Ă����Ƃ������Ƃ��w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�A���邢�́w�Ȃ炸�ҁx�𒆐S�Ƃ���70�N��O���̃X�g�[���Y�̍ĕ]���̂��������ɂȂ����̂�������Ȃ��ł��ˁB90�N��ȍ~�̓X�g�[���Y���g�����̂��Ƃ��\���Ɉӎ�����B�Ђ���Ƃ����炻�̒���70�N�㓖���̘^�����Ԃ����Ƃ������Ă����\��������܂���ˁB
- ---�@�Ȃ�قǁB���̉����ō���́w���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̃��j���[�A���ɂ܂łȂ����Ă��Ă���Ƃ����t�V�����肻���ł��ˁB
�@������A�X�g�[���Y���ăA���o�����o���x�Ɂu���x���������C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁ����A���Ă����I�v���ď�������ł���B�u���x�����v���Ă����̂�������Ɣ߂����Ƃ���ł����ǁi�j�B��܂�J�Z�b�g�e�[�v�Ȃ̐�`�ƈꏏ�ł���B�u�O���@�[�W�������i��10���A�b�v�I�v�݂����ȁi�j�B
- ---�@���Д�10���A�b�v�݂����ȁi�j�B
�@�i�j �u�g���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁE�x�h���Д�10���A�b�v�I�v�݂����Ȃ��Ƃ͏�Ɍ����Ă������ǁA���ۂ��炭�����Ă��邤���ɈႢ���ڗ����Ă���B����ȑO�ɁA�݂�Ȃ������������҂������Ē����Ă�����Ă������Ƃł���ˁB�قƂ�ǂ̃t�@���ɂƂ��Ă͂��̂��炢�p�[�t�F�N�g�ȃA���o�������A�X�g�[���Y���g�ɂ����ꂪ�e�����Ă���B�����������Ƃ������āAUniversal�Ƃ��Ắw���C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�ʂɍĔ��������Ȃ�������ł��傤�ˁB
- ---�@�^�C�~���O���v�炢�����R�[�h��Ђ������܂Łg�Q�����āh�����Ӑ}�Ƃ������v�f���A���̕ӂɂ�������ł��ˁB
�@2008�N�Ƀ��[�����O�E�X�g�[���Y�E���R�[�h��Polydor���[�x���ƍČ_����������_�ŁA�܂����[�x��������u�����C���E�X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁ����f���b�N�X�E�G�f�B�V�����ŏo�������̂ł����A�N���i2009�N�j�����[�X�̕����ł����܂����H�v�Ƃ����Őf���������Ǝv����ł���B���ꂪ2010�N�ɃY�����݂͂��܂������ǁA���傤�ǐV�^�A���o�����c�A�[���Ȃ����������Ƃ������Ƃ������āA���W�����Đ���Ɏ��g�߂���Ȃ����ȂƎv���܂����ǂˁB
���[�����O�E�X�g�[���Y ���̑��̋L���͂�����
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��1��z ����� �hCHABO�h ��s
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��1��z ����� �hCHABO�h ��s
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��2��z �s�[�^�[�E�o���J��
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��2��z �s�[�^�[�E�o���J��
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��4��z �T�G�L����
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��4��z �T�G�L����
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��5��z ����h �i�\�E���E�t�����[�E���j�I���j
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� ��5��z ����h �i�\�E���E�t�����[�E���j�I���j
 �y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� �ŏI��z �q���ʑΒk�r�z�J���` �~ ��h��
�y�X�y�V�����E�C���^�r���[��� �ŏI��z �q���ʑΒk�r�z�J���` �~ ��h��
 �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̐^��
�w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx�̐^��
 HMV�I��������I �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
HMV�I��������I �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
 �y��U�z �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
�y��U�z �w���C���X�g���[�g�̂Ȃ炸�ҁx
 SHM-CD�^���W���P�E�{�b�N�X��2�e
SHM-CD�^���W���P�E�{�b�N�X��2�e
 �X�g�[���Y �^�Ẵl�u���[�Y�� 1976
�X�g�[���Y �^�Ẵl�u���[�Y�� 1976
|
Exile On Main Street �X�[�p�[�E�f���b�N�X�E�G�f�B�V���� |
���̑��̃o�[�W����
 ������
��3,800
������
��3,800�f���b�N�X�E�G�f�B�V�����i�f�W�p�b�N�j 2010�N05��19��
 ������
��2,200 2010�N05��19��
������
��2,200 2010�N05��19��
 ������
��2,800
������
��2,800����� SHM-CD �i���W���P�j 2010�N06��30��

-
���c���T �i�Ă炾 �܂��̂�j
�@1962�N���萶�܂�̕����炿�B����c��w���ƁB1985�N�~���[�W�b�N�E�}�K�W���Ђɓ��ЁB93�N����u���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�v�ҏW���ɒ��C�B�ďC�y�ѕҏW�Ɍg��������[�����O�E�X�g�[���Y�֘A�̏��ЂƂ��ẮA�w���R�[�h�E�R���N�^�[�Y���� ���[�����O�E�X�g�[���Y�x�i1990�N�����j�A�w���R�[�h�E�R���N�^�[�Y���� STONED�I The Ultimate Guide To The Rolling Stones�x�i1998�N�����j�A�w���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�����@The Rolling Stones CD Guide�x�i2003�N�����j�Ȃǂ�����B
�u���R�[�h�E�R���N�^�[�Y�v
�@�~���[�W�b�N�E�}�K�W���Ђ��犧�s����Ă���A�ЂƖ��Ⴄ���y�t�@���A���R�[�h�E�t�@���̂��߂̌������B1960�`70�N��̕ĉp�̃��b�N�𒆐S�ɁA�|�s�����[���y�L�������B�ڂ����f�B�X�R�O���t�B�[�t���Ŏ��グ���A�[�e�B�X�g�̉��������ׂĕ������߂̃K�C�h�ƂȂ���W���D�]�B
- �֘A�T�C�g�i�O���T�C�g�j
- �֘A���W�iHMV�T�C�g���j
�C���^�r���[���ɓo�ꂷ���v�l���ɂ��� |
 |
Andy Johns �i�A���f�B�E�W�����Y�j �����h���̃I�����s�b�N�E�X�^�W�I�����_�Ɏd�������Ă����C�M���X�̖��G���W�j�A�^�v���f���[�T�[�A�O�����E�W�����Y���Z�Ɏ��A���f�B�E�W�����Y�B60�N�㖖����70�N�㏉���ɂ����Ă͌Z�̊ւ���i�ŋ����G���W�j�A�߁A���b�h�E�c�F�b�y�����A�u���C���h�E�t�F�C�X�̃A���o���Ɍg���A�܂��A70�N�㏉�����t���[�̍�i���v���f���[�X���Ă��邱�Ƃł��m���Ă���B�X�g�[���Y��i�ł́A�wSticky Fingers�x�����wIt's Only Rock'n'Roll�x�܂ł�4��i�ŃG���W�j�A�߁A70�N�㉩�����̃X�g�[���Y�E�T�E���h�̊m���ɍv�����Ă���B70�N�㖖�ɃA�����J�Ɉڂ�A�e�����B�W�����A�W���j�E�~�b�`�F���A�����E�E�b�h�̍�i�ɎQ���B80�N��ȍ~�����@���E�w�C�����Ȃǃn�[�h�E���b�N�̖��v���f���[�T�[�Ƃ��Ė���y���Ă���B |
 | Bill Plummer �i�r���E�v���}�[�j �Đ��C�ݏo�g�Ō��X�W���Y���𒆐S�Ɋ��������Ă����}���`�ňِF�ȃx�[�X�E�v���C���[�^�V�^�[���t�ҁA�r���E�v���}�[�́A�uThe Basses International Project�v�Ƃ����v���W�F�N�g�ŋ��Ɋ������Ă����A�W�����E���m���A�G���b�N�E�N���v�g���A���C�E�N�[�_�[��i�ւ̎Q���ł��Ȃ��݂̖��Z�b�V�����E�h���}�[���W���E�P���g�i�[����ăX�g�[���Y�̃v���f���[�T�[�A�W�~�[�E�~���[�ƒm�荇���A�����ŁwExile On Main Street�x�̐��ȂŃA�b�v���C�g�E�x�[�X��e���悤�˗����ꂽ�Ƃ����B |
 |
Bobby Keys �i�{�r�[�E�L�[�Y�j 60�N�㖖�A���I���E���Z���𒆐S�Ƃ���ē암�X�����v�E���b�N�E�T�[�N���Ŋ������Ă����{�r�[�E�L�[�Y�́A�W�~�[�E�~���[����ăX�g�[���Y�Əo����ƂɂȂ�A�e�L�T�X�o�g�̃T�b�N�X�t�ҁB10����o�f�B�E�z���[�̃o�b�N�E�o���h�ł̉��t���o�����A���̌���l�X�ȃo���h�ł̉��t���o���̂��Ƀ��I���̏Љ���f�B���C�j�[���{�j�[�̃c�A�[�E�o���h�ɎQ���B���̑�Ґ��o���h�ɂ́A�G���b�N�E�N���v�g�����f�C���E���C�\������Q�����Ă����Ƃ������Ƃ�����A�ނ炩��X�g�[���Y��i�Q���ւ̃A�h�o�C�X�Ȃǂ�����Ă����̂��낤�B�wLet It Bleed�x�������uLive With Me�v����ɁA�wSticky Fingers�x���uBrown Sugar�v�Ȃǐ��X�̃X�g�[���Y�y�ȂŃu���[�X�E�t�B�[�����O����T�b�N�X�E�\�����I���A1970�N�ȍ~�̓c�A�[�̃��M�����[�E�����o�[�ɒ��C�i1975�`78�N�̓Q�X�g�����j���Ă���B�{�r�[�Ɂu�L�[�X�̂悤�Ȑl�ԂɈꐶ��5�l�����b�L�[����ȁv�ƌ��킵�߂����̃L�[�X�Ƃ͓������N�����i1943�N12��18���j�Ƃ������Ƃ�����A�\�����j���[�E�o�[�o���A���Y�ȂǃX�g�[���Y�ȊO�̊����ł��x�X�������Ȃ���A���݂��\�E�����C�g�̂悤�ȗ��z�I�ȐM���W��ۂ������Ă���B |
 |
Clydie King �i�N���C�f�B�E�L���O�j �e�L�T�X�B�_���X�o�g��R&B�^�\�E���E�V���K�[�A�N���C�f�B�E�L���O�́A60�N��ɂ����C�E�`���[���Y�̃R�[���X��S�����Ă���3�l�g���C���b�c�̈���Ƃ��Ċ������Ă����B�\���Ƃ��Ă�Specialty�AKENT�Ƃ���������ɃV���O�����R���X�^���g�ɐ�������ł������A�ޏ��̒m���x�����I�ɐL�����̂́A��͂�l�X�ȃZ�b�V�����ւ̃R�[���X�Q�����낤�B�W���[�E�R�b�J�[�wMad Dogs And Englishmen�x�̃c�A�[��s�Ƃ��āA���F�l�b�^�E�t�B�[���Y�A�V���[���[�E�}�V���[�Y��ƌ��������u���b�N�x���[�Y�́A���̂܂܁wExile On Main Street�x��LA�^���̌���ɂȂ��ꍞ�ނ������ƂȂ����B���̂ق��A�n���u���E�p�C�A�{�u�E�f�B�����A�X�e�B�[���[�E�_���Ȃǂ̖��A���o���̒��ɔޏ��̃N���W�b�g����������͂����B |
 |
Dr. John �i�h�N�^�[�E�W�����j ���Ȃ��݃j���[�I�����Y�E�X�����v�̐��������ADr. �W�������ƃ}�b�N�E���x�i�b�N�B�j���[�I�����Y�E�~���[�W�b�N�ƃX�����v�E���b�N�̑f���炵���������wGumbo�x�������߂��̃T�E���h�E�V�e�B�E�X�^�W�I�Ń��R�[�f�B���O���Ă��������ł�����A������̃��R�[�f�B���O�E�����o�[�ł������^�~�E�����A�V���[���[�E�O�b�h�}���������A��A�n���E�b�h�E�X�^�W�I�ł��uLet It Loose�v�̃R�[���X�^���ɎQ�������Ƃ����̂������悻�̌o�܁B�܂��A1970�N�ɘ^�����ꂽDr. �W�����̃A���o���wThe Sun�AMoon & Herbs�x�ɂ́A�~�b�N�E�W���K�[��6�Ȃ��o�b�N�E�R�[���X�ŎQ�����Ă���A���̂���ɁA�Ƃ������Ƃ���������Ɋ܂�ł���̂��낤�B |
 |
Gram Parsons �i�O�����E�p�[�\���Y�j �C���^�[�i�V���i���E�T�u�}�����E�o���h�A�o�[�Y�i�w���f�I�̗��l�x����j�A�t���C���O�E�u���[�g�[�E�u���U�[�Y��n������A�J���g���[�A�܂��̓J���g���[�E���b�N��Nj����������j�A�O�����E�p�[�\���Y�B�wLet It Bleed�x�̐���ɂƂ肩������������A�L�[�X�ƃO�����Ƃ̐e���͎n�܂����ƌ����Ă���B�uLove In Vain�v�A�uCountry Honk�v�A�uWild Horses�v�A�uDead Flowers�v�A�܂��A�L�[�X�ƃO��������J���t�H���j�A�̌�����UFO�����ɍs�������ɃA�C�f�A�������Ƃ������Ă����uMoonlight Mile�v�ȂǁA�O�������X�g�[���Y�E�T�E���h�ɗ^�����e���Ƃ������̂͌v��m��Ȃ��B��������wExile On Main Street�x�̃��R�[�f�B���O�ɂ����Ă��A���l���R�[�g�A�ŏI�~�b�N�X���s��ꂽLA�n���E�b�h�E�X�^�W�I�ɃO�����͖K��Ă��āA�uSweet Virginia�v�A�uTorn & Frayed�v�Ƃ������y�Ȃł��̐e�r���̂������B�O�����́A1973�N�A2���ڂ̃\���E�A���o���wGrievous Angel�x����������������ɃA���R�[���ƃh���b�O�̉ߏ�ێ�ɂ��26�Ƃ����Ⴓ�ł��̐������������A���̌���X�g�[���Y�́A�uFar Away Eyes�v�A�uIndian Girl�v�A�uThe Worst�v�A�uSweethearts Together�v�Ƃ������ȂɃJ���g���[�E�t���C���@�𐁂����ނ��Ƃɂ���āA���̗F����i���̂��̂Ƃ��Ă���B |
 |
Jimmy Miller �i�W�~�[�E�~���[�j 1968�N�A�t�̖K��ƂƂ��Ɂu�u���[�X�v�A�u�č��암�v�Ƃ������[�c�E�~���[�W�b�N�ւ̎w�j����������Ƒ������X�g�[���Y�́A�A�C�����h�E���R�[�Y�n�ݎ҃N���X�E�u���b�N�E�F���̊̐���Ƃ����X�y���T�[�E�f�C���B�X�E�O���[�v���g���t�B�b�N�Ȃǂ���|�����ڂ��W�߂Ă����V�i�C�s�̃W�~�[�E�~���[���v���f���[�T�[�ɔ��F�B���傤�ǂ��̍������������肾�����g���t�B�b�N��2nd�A���o���wTraffic�x�̃T�E���h���~�b�N���������C�ɓ����ăX�J�E�g���������B�u���[�X���@���Ƃ����茘���A�[�V�[�ȃT�E���h���̒��ɂ������I�Ȏ��݂����X�Ǝ����ꂽ�wBeggars Banquet�x�ł���͋g�Əo�āA�ȍ~�wGoat's Head Soup�x�܂łɂ����ăW�~�[�E�~���[�̓X�g�[���Y����S���̐M���āA�h�邬�Ȃ��������̃T�E���h�����グ�Ă���B |
 |
Jim Price �i�W���E�v���C�X�j �{�r�[�E�L�[�Y�Ɠ�����LA�X�����v�E�T�[�N������i���r�[�g���Y��i�ȂǂɎQ�����Ă����e�L�T�X�o�g�̃Z�b�V�����n�g�����y�b�g�t���W���E�v���C�X�B�{�r�E�L�[�Y�̏Љ�ɂ��X�g�[���Y��i�֎Q���ƂȂ������̏��o��Ȃ́A�wSticky Fingers�x�����ƂȂ��uBitch�v��1970�N�̃I�����s�b�N�E�X�^�W�I�ɂāBStax�n�W�����v�E�i���o�[���X�g�[���Y���ɏ��������̋Ȃł́A�W���ƃ{�r�[�ɂ��p���`�̌������z�[���E�Z�N�V���������炩�Ƀh���C������^���Ă���B���̌�1973�N�̃E�C���^�[�E�c�A�[�܂Ńo���h�ɓ��s���A70�N��X�g�[���Y�̉��������x�����B |
 |
Kathi McDonald �L���V�[�E�}�N�h�i���h �W���j�X�E�W���v�����S������r�b�O�E�u���U�[���z�[���f�B���O�E�J���p�j�[��2��ڃ��H�[�J���X�g�Ƃ��āA����ɂ́A�W���[�E�R�b�J�[�wMad Dogs And Englishmen�x�����I���E���b�Z��������V�F���^�[�E�s�[�v���ւ̎Q���ȂǁA�n���Ȃ�����u���[�X�E���b�N�A�X�����v�E���b�N�̍ŏd�v��i�ɂ���ł����Ɩ���A�˂Ă���u���[�X�E���b�N�����Ԓ��V���K�[�A�L���V�[�E�}�N�h�i���h�B���l�ł���Ȃ���f�B�[�v�ȃ\�E���^�u���[�X�̏��Ŗ�����Ƃ����_�ŃW���j�X���{�j�[�E�u�������b�g��Ƃ����Δ�r�����L���V�[�����A�~���[�W�V�����Y�E�T�[�N���ɂ�����ޏ��̕]���Ƃ������̂�2�l��y���ɗ����������̂��������B1974�N�̃\��1st�A���o���wInsane Asylum�x�i�M��F���_�a���I�j�ɂ́A�X���C�E�X�g�[���A�j�[���E�V���[���A���j�[�E�����g���[�Y�A�j���X�E���t�O�����E�E�E�Ƃ������啨�������Q���B�ޏ��̉̐��������ɖ��͓I�����ԐړI�ɏؖ����Ă���B�X�g�[���Y�Ƃ��wExile On Main Street�x���uAll Down The Line�v�ł̋����ƂȂ�A�������̂���L���b�`�[�ȃt�b�N���₩�Ƀo�b�N�A�b�v�B |
 |
Leon Russell �i���I���E���b�Z���j �O�����E�W�����Y�̏Љ�ŃX�g�[���Y�Əo����ƂƂȂ����I���E���b�Z���́A�܂����wLet It Bleed�x���uLive With Me�v�Ƀs�A�m�ŎQ���������O��LA���X�����v�E�T�E���h�̈�Ђ𖼎h����ɍ����o���B�������A���I���̃X�g�[���Y�ւ̍ő�̍v���́A���̍L���l�������ē암�̃~���[�W�V�����Y�E�T�[�N����ނ�X�g�[���Y�Ƌ��L�����Ƃ����_�ɂ���B���g�̃V�F���^�[�E�s�[�v���A�f���j�[���{�j�[���t�����Y�A�W���[�E�R�b�J�[�̃}�b�h�E�h�b�O�X���C���O���b�V�������Ƃ����������̂��ւ�r�����̐l�C���A�����암���[�c�E�T�E���h�ɋQ���Ă����X�g�[���Y�̏��͂̂��߂ɐɂ������Ȃ����荞�݁A�u���[�X�A�\�E���A�J���g���[�A�S�X�y���̎��D�������L���ȃj���A���X�������������̌��т͏̂����Ă�����ׂ��B�܂��A1969�N���̃\���E�A���o���wLeon Russell�x�̘^���ɂ́A�r���E���C�}���A�`���[���[�E���b�c���Q�����Ă���B |
 |
Robert Frank �i���o�[�g�E�t�����N�j ����̃��b�N�E�t�@���ɂƂ��Ă��wExile On Main Street�x�̃W���P�b�g�E�A�[�g���[�N�A�����āA�h�L�������^���[�E�t�B�����wCocksucker Blues�x�Ƃ����A�X�g�[���Y�j����w�̂������킵���|�p���������������2��v���_�N�c����|�����l���Ƃ��Ă悭�m���郍�o�[�g�E�t�����N�B1924�N�A�X�C�X�̃`���[���b�q�Ő��܂������t�����N�́A47�N�Ɉږ��Ƃ��ăj���[���[�N�ɏo�Ă�����A50�N�㔼�ɂ͑S�Ă���Q���Ȃ���A���Ƀt�B����767�{���g�p���Ȃ���s���̌����̐������ʐ^�Ɏ��ߑ������B�B�e�C���[�W��27�A000�_�A���[�N�v�����g��1000���̒�����83��i���ʐ^�W�ɂ܂Ƃ߂��A58�N5���ɁuLes Americains�i�A�����J�l�j�v�Ƃ��Ċ��s����Ă���B�A�����E�M���Y�o�[�O���W���b�N�E�P���A�b�N�Ƃ������r�[�g���l��Ƌ����������ƂŁu���o�I���l�v�Ƃ��Ă�Ă����t�����N�B�uLes Americains�i�A�����J�l�j�v�ɂ��f�ڂ���Ă����ʐ^���R���[�W�������A�[�g���[�N�́A�X�g�[���Y�̊y�ȃC���[�W���剻��������̖��@�▃��߂����p���[�ɖ����Ă���C�����ĂȂ�Ȃ��B |
 |
Venetta Fields �i���F�l�b�^�E�t�B�[���Y�j �j���[���[�N�̓o�b�t�@���[�o�g��R&B�^�\�E���^�S�X�y���E�V���K�[�A���F�l�b�^�E�t�B�[���Y�́A�A�C�N���e�B�i�E�^�[�i�[�̃o�b�N�E�R�[���X�E�O���[�v�A�A�C�P�b�c�ɍݐЂ��Ă������Ƃł��m���Ă���B�A�C�P�b�c�����r���[�𗣂ꂽ��́A�����u�������o�[�Ń~���b�c�Ƃ��Ă̊����Ɉڍs�B���̌���N���C�f�B�E�L���O�A�V���[���[�E�}�V���[�Y��Ƃ̃u���b�N�x���[�Y�Ƃ��ėl�X�ȃ~���[�W�V�����̃o�b�N�E�R�[���X�ɎQ���B���ł��s���N�E�t���C�h�wDark Side Of The Moon�x�̃c�A�[�A�����āA�wExile On Main Street�x�Ƃ��������b�N���ł̃r�b�O�l�[���Ƃ̎d�������ɖڂ������B |