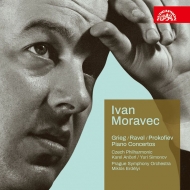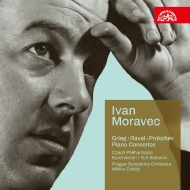「海」で始まるCD漂流
2021年03月01日 (月) 09:00 - HMV&BOOKS online - Classical
連載 許光俊の言いたい放題 第286回

ここのところ、なんだか暑苦しい文章ばかりここでは掲載したかもしれない。暑苦しい文章を書くのは嫌いではないのだが、今回はざっと、このところ聴いて感心したCDについて述べよう。全部暑苦しく書いていると身が持たないので。
ここではブルックナーの交響曲のピアノ連弾版なども紹介したことがあるが、珍しくピアニスト3人で弾くドビュッシーの「海」が出た。これがおもしろかった。いや、実にすばらしいものである。この版の詳細は宣伝やライナーノートに譲るとして要点を。
この曲、たいそう有名で、好きな人は細かいところまで覚えてしまっているかもしれないが、そう簡単、単純な音楽ではない。3人で弾くと、必要な音はすべて入っているという感じがする。そして、オーケストラ版をピアノ版にしたというより、ピアノ音楽として魅力的なのが驚きだ。オーケストラだと個々の楽器の音色がいろいろ複雑に組み合わされ、重なるわけだが、あれを取ってしまったときにどうなるか。それが想像以上におもしろいのである。東洋風に聞こえたり、「展覧会の絵」のようだったり、ジャズみたいだったり。もしかしたら、オーケストラ版以上に作品の斬新さ、異常なまでの精緻さが理解できるのではないか。少なくとも私は、オーケストラ版以上に、こんな作品が書けてしまう作曲者の突き抜けた天分に圧倒された。
また、えも言われぬゴージャス感もいい。何だろうこのゴージャス感は。連弾よりピアニストがひとり多いというだけではない不思議なゴージャス感。おそらく、作品と演奏の両方からこの印象が生まれる。ラヴェルの「夜のガスパール」にも共通するような。というか、これ、「夜のガスパール」にあちこちでそっくり。ポゴレリチが弾くときみたいな、ゴージャスだけど暗黒的な感じがたいへんする。
で、最後の楽章の高揚感は「トリスタン」さながらにエロティック。いや、もっと恥ずかしい感じがする。たいへん肉体的な、ですね。ここで言葉にするのは控えます。
とにかく、聴いて大いに楽しく、かつ示唆的な録音だ。
ここで室内楽を取り上げたことはほとんどない。クラシック音楽の究極、そして世界的に見て最大の特徴のひとつは、大編成がひとりの音楽家のように演奏するオーケストラと、たったひとりですべてを作り上げるピアノあるいはオルガン独奏に集約されると思っていることもある。それに、「弦楽四重奏は4人の賢者の対話」などと言われているが、なあに、賢者じゃない演奏家もたくさんいるじゃん、と思ってしまうのである。

さて、それはともかく、予想外に気に入って繰り返し聴きたくなったのは、モディリアーニ弦楽四重奏団とザビーネ・マイヤーほかによるシューベルトの八重奏曲だ。とにかく全体のバランスがすばらしい。誰ひとり悪目立ちしたりしない。冒頭からして、現代らしい精密、緻密さ。もっとわかりやすくチャーミングなウィーン風が好きな愛好家も多いだろうが、私はそれは苦手。ひとりだとひどく暗く吹いたりするマイヤーも、ここでは暗くなり過ぎない適度な存在感。

シューベルトはこの曲を書きながら、交響曲やオペラを頭の中でイメージしていたことがよくわかる。別に力ずくでガーガー弾いているわけではない。おのずとそいういうイメージが表現されるのがよいのだ。

ところで、この曲については、イザベル・ファウストらのCDもある。これは異常なまでに緻密な演奏だ。とにかくファウストの演奏が細かくて、なんだかルーペで拡大した風景が延々と続く感じ。ほかの演奏家もそれに付き合っていて、結果的にはヴァイオリン協奏曲みたいだ。この演奏もすごいことはすごいのだが、全体としてこういう曲だった、というイメージがつかみにくいのだ。
細かな響きの配慮がリゲティとかああいう現代音楽みたい。大編成オーケストラで微妙な響きをいっぱい出すような印象。きわめてユニークである。いっそ怪演の部類に含めたほうがよいのかもしれない。特にフィナーレの序奏部分のやり過ぎ感たっぷりな不気味さは耳に残る。
それにしてもこのCDでのファウストは異常なまでに冴えている。おまけで入っている5つのメヌエットが、全然おまけではない。死神の踊りのようなのだ。

チェコの名ピアニスト、イヴァン・モラヴェツ・・・記憶から飛んでいました。この人の協奏曲を集めたCDがいい。きわめて透明な音。しかも、それが単にお行儀よく並べられているのではなく、多彩な表情を得て跳躍するのだ。グリーグの協奏曲では、強弱、緩急が実にロマンティック。このグリーグ、1984年の演奏だが、プラハ交響楽団にもロマンティックな味が濃く残っていて、いささか驚く。
ラヴェルの伴奏はなんとあのシモノフだ。うーん、なんだかストラヴィンスキーみたい。原色がナマでぶつかり合う感じ。1974年ということだが、音質がよい。というか、不審なほど明快。ピアノは、やはりロマンティックでエモーショナル。ショパンにつながるようなラヴェル。

ええ? グルダの交響曲?? あのクラシックの正統に反逆したグルダがよりによって交響曲を書いていた? しかし、おそらく、あえて交響曲を書くことで異を唱えていたのかもしれない。そう思わせるのは、この曲がジャズのように開始され、以後もどこか流行音楽的な軽さを維持するからだ。一瞬クラシック音楽的な瞬間が訪れても、相対化されてしまう。どんな音楽もみな同じ、そういう書き方がされている。そういえば、昔大きなレコード屋に行くと、あっちこっちから別な音楽が聞こえてきたものだ。ああいう音環境。
そして、以前ここでジャズ版のブルックナー交響曲第5番を取り上げたことがあるが、このグルダ作品を聴くと、意外なほどに両者に共通するものを感じるのだ。
さらに意外なことには、オーケストラがジャズっぽいノリに案外すなおに反応できている。いかにも他流試合という不器用さがない。恐るべきシュトゥットガルト放送響。
全体として演奏家全体がとにかく熱っぽい。グルダって、こういう曲を書いたり演奏して、ひんしゅくを買っていたのではなかったけ? 少なくとも私は、若い時にそのような記事を読んでいた。だけど、どうやら違うらしい。これを喜んでいる人は想像以上に多かったのではないか。ああ、これ、チェリビダッケも同じ楽団に出演していた時代だよね、と思うとよけい感慨が深い。
中ではゆっくりした第2楽章が比較的クラシックぽい。少なくともそのように始まるのだが・・・すぐに変わる。バーンスタインみたいな、ものすごく素朴な人懐っこさ。クラシックとジャズがなめらかに切り替わってしまうような不思議さ。
第3楽章はヴィヴァルディかアルビノーニみたいにセンチメンタルに始まる。昔はやったバロック調かあと思う。その静けさから、いきなりジャズバンドの爆発。心臓に悪い。グルダ流の「驚愕」交響曲なのだろう。そこからあとは、もうまるで完全に頭がいかれた異常興奮状態。それにしても、演奏家たちをソノ気にさせたというのはまぎれもない事実。ライヴでもないスタジオ収録らしいが、そのときスタジオは尋常ならざる空間に化けたのだろう。
そうか、しかしもう50年も前のことなのか。20世紀も遠ざかってしまったなあとしみじみ感じた。
 評論家エッセイ情報
評論家エッセイ情報
 青柳いづみこ
青柳いづみこ
 マイヤー
マイヤー
 モディリアーニ四重奏団
モディリアーニ四重奏団
 ファウスト
ファウスト
 グルダ
グルダ

ここのところ、なんだか暑苦しい文章ばかりここでは掲載したかもしれない。暑苦しい文章を書くのは嫌いではないのだが、今回はざっと、このところ聴いて感心したCDについて述べよう。全部暑苦しく書いていると身が持たないので。
ここではブルックナーの交響曲のピアノ連弾版なども紹介したことがあるが、珍しくピアニスト3人で弾くドビュッシーの「海」が出た。これがおもしろかった。いや、実にすばらしいものである。この版の詳細は宣伝やライナーノートに譲るとして要点を。
この曲、たいそう有名で、好きな人は細かいところまで覚えてしまっているかもしれないが、そう簡単、単純な音楽ではない。3人で弾くと、必要な音はすべて入っているという感じがする。そして、オーケストラ版をピアノ版にしたというより、ピアノ音楽として魅力的なのが驚きだ。オーケストラだと個々の楽器の音色がいろいろ複雑に組み合わされ、重なるわけだが、あれを取ってしまったときにどうなるか。それが想像以上におもしろいのである。東洋風に聞こえたり、「展覧会の絵」のようだったり、ジャズみたいだったり。もしかしたら、オーケストラ版以上に作品の斬新さ、異常なまでの精緻さが理解できるのではないか。少なくとも私は、オーケストラ版以上に、こんな作品が書けてしまう作曲者の突き抜けた天分に圧倒された。
また、えも言われぬゴージャス感もいい。何だろうこのゴージャス感は。連弾よりピアニストがひとり多いというだけではない不思議なゴージャス感。おそらく、作品と演奏の両方からこの印象が生まれる。ラヴェルの「夜のガスパール」にも共通するような。というか、これ、「夜のガスパール」にあちこちでそっくり。ポゴレリチが弾くときみたいな、ゴージャスだけど暗黒的な感じがたいへんする。
で、最後の楽章の高揚感は「トリスタン」さながらにエロティック。いや、もっと恥ずかしい感じがする。たいへん肉体的な、ですね。ここで言葉にするのは控えます。
とにかく、聴いて大いに楽しく、かつ示唆的な録音だ。
ここで室内楽を取り上げたことはほとんどない。クラシック音楽の究極、そして世界的に見て最大の特徴のひとつは、大編成がひとりの音楽家のように演奏するオーケストラと、たったひとりですべてを作り上げるピアノあるいはオルガン独奏に集約されると思っていることもある。それに、「弦楽四重奏は4人の賢者の対話」などと言われているが、なあに、賢者じゃない演奏家もたくさんいるじゃん、と思ってしまうのである。

さて、それはともかく、予想外に気に入って繰り返し聴きたくなったのは、モディリアーニ弦楽四重奏団とザビーネ・マイヤーほかによるシューベルトの八重奏曲だ。とにかく全体のバランスがすばらしい。誰ひとり悪目立ちしたりしない。冒頭からして、現代らしい精密、緻密さ。もっとわかりやすくチャーミングなウィーン風が好きな愛好家も多いだろうが、私はそれは苦手。ひとりだとひどく暗く吹いたりするマイヤーも、ここでは暗くなり過ぎない適度な存在感。

シューベルトはこの曲を書きながら、交響曲やオペラを頭の中でイメージしていたことがよくわかる。別に力ずくでガーガー弾いているわけではない。おのずとそいういうイメージが表現されるのがよいのだ。

ところで、この曲については、イザベル・ファウストらのCDもある。これは異常なまでに緻密な演奏だ。とにかくファウストの演奏が細かくて、なんだかルーペで拡大した風景が延々と続く感じ。ほかの演奏家もそれに付き合っていて、結果的にはヴァイオリン協奏曲みたいだ。この演奏もすごいことはすごいのだが、全体としてこういう曲だった、というイメージがつかみにくいのだ。
細かな響きの配慮がリゲティとかああいう現代音楽みたい。大編成オーケストラで微妙な響きをいっぱい出すような印象。きわめてユニークである。いっそ怪演の部類に含めたほうがよいのかもしれない。特にフィナーレの序奏部分のやり過ぎ感たっぷりな不気味さは耳に残る。
それにしてもこのCDでのファウストは異常なまでに冴えている。おまけで入っている5つのメヌエットが、全然おまけではない。死神の踊りのようなのだ。

チェコの名ピアニスト、イヴァン・モラヴェツ・・・記憶から飛んでいました。この人の協奏曲を集めたCDがいい。きわめて透明な音。しかも、それが単にお行儀よく並べられているのではなく、多彩な表情を得て跳躍するのだ。グリーグの協奏曲では、強弱、緩急が実にロマンティック。このグリーグ、1984年の演奏だが、プラハ交響楽団にもロマンティックな味が濃く残っていて、いささか驚く。
ラヴェルの伴奏はなんとあのシモノフだ。うーん、なんだかストラヴィンスキーみたい。原色がナマでぶつかり合う感じ。1974年ということだが、音質がよい。というか、不審なほど明快。ピアノは、やはりロマンティックでエモーショナル。ショパンにつながるようなラヴェル。

ええ? グルダの交響曲?? あのクラシックの正統に反逆したグルダがよりによって交響曲を書いていた? しかし、おそらく、あえて交響曲を書くことで異を唱えていたのかもしれない。そう思わせるのは、この曲がジャズのように開始され、以後もどこか流行音楽的な軽さを維持するからだ。一瞬クラシック音楽的な瞬間が訪れても、相対化されてしまう。どんな音楽もみな同じ、そういう書き方がされている。そういえば、昔大きなレコード屋に行くと、あっちこっちから別な音楽が聞こえてきたものだ。ああいう音環境。
そして、以前ここでジャズ版のブルックナー交響曲第5番を取り上げたことがあるが、このグルダ作品を聴くと、意外なほどに両者に共通するものを感じるのだ。
さらに意外なことには、オーケストラがジャズっぽいノリに案外すなおに反応できている。いかにも他流試合という不器用さがない。恐るべきシュトゥットガルト放送響。
全体として演奏家全体がとにかく熱っぽい。グルダって、こういう曲を書いたり演奏して、ひんしゅくを買っていたのではなかったけ? 少なくとも私は、若い時にそのような記事を読んでいた。だけど、どうやら違うらしい。これを喜んでいる人は想像以上に多かったのではないか。ああ、これ、チェリビダッケも同じ楽団に出演していた時代だよね、と思うとよけい感慨が深い。
中ではゆっくりした第2楽章が比較的クラシックぽい。少なくともそのように始まるのだが・・・すぐに変わる。バーンスタインみたいな、ものすごく素朴な人懐っこさ。クラシックとジャズがなめらかに切り替わってしまうような不思議さ。
第3楽章はヴィヴァルディかアルビノーニみたいにセンチメンタルに始まる。昔はやったバロック調かあと思う。その静けさから、いきなりジャズバンドの爆発。心臓に悪い。グルダ流の「驚愕」交響曲なのだろう。そこからあとは、もうまるで完全に頭がいかれた異常興奮状態。それにしても、演奏家たちをソノ気にさせたというのはまぎれもない事実。ライヴでもないスタジオ収録らしいが、そのときスタジオは尋常ならざる空間に化けたのだろう。
そうか、しかしもう50年も前のことなのか。20世紀も遠ざかってしまったなあとしみじみ感じた。
(きょみつとし 音楽評論家、慶応大学教授)
Showing 1 - 8 of 8 items
表示順:
※表示のポイント倍率は、ブロンズ・ゴールド・プラチナステージの場合です。