�y���W�z �X���[�E�u���C���h�E�}�C�X
Wednesday, July 10th 2013
 �@70�N��A���{�̃W���Y���M���������A�u�X���[�E�u���C���h�E�}�C�X�v�Ƃ������[�x�����������BTBM�̈��̂Œm���u�y�����W���Y�v�u�X�C���O����W���Y�v�u�n���I�ȃW���Y�v�u���I�ȃW���Y�v���l�{���ɁA���C���X�g���[���n�̃��_���E�W���Y����r�b�O�E�o���h�A���H�[�J���A�t���[�E�W���Y�A�t���[�W�����܂ŁA���L���J�e�S���[��ԗ��B���c���A�R�{���A��،M�A����p�l�A���{�}���ȂǁA����܂ł��܂背�R�[�f�B���O�̋@��Ɍb�܂�Ȃ��������C���E�V�[���̎��͎҂�����ϋɓI�ɋN�p���A���{�̃W���Y�E�ɐV���𐁂����B���̌��т͔ނ�̌��݂Ɏ���܂ł̊���Ԃ������Ζ��炩�ł���B��150��̍�i�������[�X����Ă��邪�A�ʍ�̗ނ͂ЂƂ��Ȃ��B���ٓI�ȃ��x���̍�����TBM�̑傫�ȓ����ɂ��Ė��͂ł���B �@����܂łɈꕔCD�����ꂽ���̂����邪�A���������݂͂��ׂĔp�Տ�ԁB���Îs��ł̓g���f���Ȃ����i�Ŏ�����Ȃ���Ă�����̂�����B���̂��сATHINK! RECORDS�����I�����^�C�g����S7���ɂ킽�蕜���B���E�̃W���Y�j�ɂ��c��M�d�ȉ������Ăѐ��ɖ₤!! �@���G���W�j�A�̗_�ꍂ���_���F�F���肪�����K�b�c�̂��鉹���́A�u���ɂ̃W���Y�E�T�E���h�v�ƌĂ�u�W���Y�E�I�[�f�B�I�v�Ƃ����T�O���m�������B����͂��̖��͂�]���Ƃ���Ȃ����`������ׁA�S�^�C�g�������W���P�b�g�d�l��Blu-spec CD™�Ń����[�X�I ����ɓ����̃I���W�i���u�b�N���b�g������!!
|
�ߋ��̊֘A�L������
 �y�Βk�z ����[ �~ ��ˍL�q (2011�N3��)�@
�y�Βk�z ����[ �~ ��ˍL�q (2011�N3��)�@�uWax Poetics Japan�v�ďC�R���s��2�e�́A�a�W���Y�̕�ɃL���O���R�[�h�Ƃ�������X�N������g�� �hJP JAZZ�h �X�y�V�����B���̔������L�O���� ����[����A��ˍL�q����ɂ��Βk�ł��B
 ���k�L����ɐu�� �u�a�W���Y�v (2009�N9��)�@
���k�L����ɐu�� �u�a�W���Y�v (2009�N9��)�@���E���̘a�W���Y�E�f�B�X�N�E�K�C�h�w�a�W���Y�E�f�B�X�N�E�K�C�h Japanese Jazz 1950s-1980s�x���s���L�O���A�{���̒��҂ɂ��āu�a�W���Y�E�u�[���̎d�|���l�v ���k�L����ɂ��b���f���܂����B
 �y�C���^�r���[�z �n�Ӓ�v �V��wOutra Vez: �ӂ����сx�@
�y�C���^�r���[�z �n�Ӓ�v �V��wOutra Vez: �ӂ����сx�@80���}������v����ɁA1988�N�ȗ��ƂȂ�u���W���^���V��wOtra Vez: �ӂ����сx�ɂ��Ă�A�u���W�����y�Ƃ̏o��ȂǁA���������܂����B
 �y�C���^�r���[�z �e�n��� (2012�N7��)�@
�y�C���^�r���[�z �e�n��� (2012�N7��)�@�E�F���J���E�o�b�N�A�v�[����I ECM���^���̃g���I��w�T�����C�Y�x�����[�X��ɍs�Ȃ�ꂽ�A����6���̓��{�M���h���A�h�����ɐk����B�v�[���Ƌe�n��͂���́u���݁v�����f�����Ă��܂����B


 �@TBM�n�ݎ҂̈�l�͓��䕐�ŁA�ނ���i�v���f���[�X���s�����B���̃��[�x���̃��b�N�E�F���n�ݎ҂ŁA�W���Y�]�_�ƂƂ��Ă������Ȗ��䐳��́A���[�x���\�z���������ɏ����𑗂������Ƃ�����BTBM�ݗ��O���1970�N�O��A����̓r�N�^�[�Łw���{�̃W���Y�E�V���[�Y�x�̊ďC�߂����A���̍��ɔނ��ڂ����������G���W�j�A�̐_���F�F���Љ���B�C�O�ɂ��Љ�ł���A�I���W�i���e�B��������{�l�W���Y�̃����[�X��ڎw���w���{�̃W���Y�E�V���[�Y�x�̐��_�́A��������TBM�֎p���ꂽ�̂ł���B�����ɐ���ׂ��f�U�C�i�[�Ƃ��ĉ����A�W���P�b�g���烉�C�i�[�E�m�[�g�A�т܂ōS�����f�U�C����������TBM�́A�������߃u���[�m�[�g�̃A���t���b�h�E���C�I���A���f�B�E���@���E�Q���_�[�A���[�h�E�}�C���X���t�����V�X�E�E���t�̐��̓��{�łƂł��`�e�ł��邾�낤�B
�@TBM�n�ݎ҂̈�l�͓��䕐�ŁA�ނ���i�v���f���[�X���s�����B���̃��[�x���̃��b�N�E�F���n�ݎ҂ŁA�W���Y�]�_�ƂƂ��Ă������Ȗ��䐳��́A���[�x���\�z���������ɏ����𑗂������Ƃ�����BTBM�ݗ��O���1970�N�O��A����̓r�N�^�[�Łw���{�̃W���Y�E�V���[�Y�x�̊ďC�߂����A���̍��ɔނ��ڂ����������G���W�j�A�̐_���F�F���Љ���B�C�O�ɂ��Љ�ł���A�I���W�i���e�B��������{�l�W���Y�̃����[�X��ڎw���w���{�̃W���Y�E�V���[�Y�x�̐��_�́A��������TBM�֎p���ꂽ�̂ł���B�����ɐ���ׂ��f�U�C�i�[�Ƃ��ĉ����A�W���P�b�g���烉�C�i�[�E�m�[�g�A�т܂ōS�����f�U�C����������TBM�́A�������߃u���[�m�[�g�̃A���t���b�h�E���C�I���A���f�B�E���@���E�Q���_�[�A���[�h�E�}�C���X���t�����V�X�E�E���t�̐��̓��{�łƂł��`�e�ł��邾�낤�B

![TBM���� [��2��]](https://img.hmv.co.jp/News/images/free4/digital3/JZ22/0-00000000TBM2_332_415.jpg) �@���䎠�t�Ƃ̃_�u���E�g�����{�[���̐��Ńj�b�|���E�W���Y�̖閾�����ĂԁB�u�g�����{�[���̕����v�����������������w���[�j���O�E�t���C�g�x�A�n�[�r�[�E�n���R�b�N�A�����E�J�[�^�[�琔���������g���R�ɂ������x�[�X�t�ҁA���E�́uMr. GON�v���Ɛ����F�̏����[�_�[���w�j�����������鎞�x�A�X�����A�n�Ӎ��Ô��A���{�}����T�C�h�̗V���肪�ʂ�Y�����،M��TBM4����w�I�����E�[�^���x�A�����̓A�C�h�����̐l�C���ւ����y��p�j�̂��ꂼ���_�ɂ��ĕ��Ґk���̃X�g���[�g�E�A�w�b�h�����w�g�L�x�A���[�x����ɁE���䕐���������ɂ����Ⴋ�V�˃s�A�j�X�g�A�R�{���ɂ��u���[�W�[�ȃg���I���`�w�K�[���E�g�[�N�x�A���̎R�{�g���I���o�b�N�ɃX�E�B���O���܂���70s�j���W���Y�E���H�[�J���̓s��h���C�����E�X�g���[�g�E�t���b�V���ՁA�X�R�_���w�X�}�C���x�B[��2��]�ł́A�ߔN��CD�����ɑ҂���Ă����l�C�Ղ͂������A�{���g���A�̃��m�ƃ��@���G�[�V�����L����6�^�C�g�����B
�@���䎠�t�Ƃ̃_�u���E�g�����{�[���̐��Ńj�b�|���E�W���Y�̖閾�����ĂԁB�u�g�����{�[���̕����v�����������������w���[�j���O�E�t���C�g�x�A�n�[�r�[�E�n���R�b�N�A�����E�J�[�^�[�琔���������g���R�ɂ������x�[�X�t�ҁA���E�́uMr. GON�v���Ɛ����F�̏����[�_�[���w�j�����������鎞�x�A�X�����A�n�Ӎ��Ô��A���{�}����T�C�h�̗V���肪�ʂ�Y�����،M��TBM4����w�I�����E�[�^���x�A�����̓A�C�h�����̐l�C���ւ����y��p�j�̂��ꂼ���_�ɂ��ĕ��Ґk���̃X�g���[�g�E�A�w�b�h�����w�g�L�x�A���[�x����ɁE���䕐���������ɂ����Ⴋ�V�˃s�A�j�X�g�A�R�{���ɂ��u���[�W�[�ȃg���I���`�w�K�[���E�g�[�N�x�A���̎R�{�g���I���o�b�N�ɃX�E�B���O���܂���70s�j���W���Y�E���H�[�J���̓s��h���C�����E�X�g���[�g�E�t���b�V���ՁA�X�R�_���w�X�}�C���x�B[��2��]�ł́A�ߔN��CD�����ɑ҂���Ă����l�C�Ղ͂������A�{���g���A�̃��m�ƃ��@���G�[�V�����L����6�^�C�g�����B

 �@�����ɂ����Ă͒������u�_�u���E�g�����{�[���E�N�C���e�b�g�v�Ґ��Ő������܂ꂽ�A���ł͋����q���ق�{���g���勐���Ƃ��ČN�Ղ���A�������ƌ��䎠�t�ɂ��o�����[�_�[��B�X�E�B���O�E�W���Y�S�����ɂ͒����t���قǂ̉Ԍ`�y�킾�����g�����{�[�����AJJ�W�����\���A�J�C�E�E�B���f�B���O�A�J�[�e�B�X�E�t���[�̖ىߑR��A���_���W���Y�ȍ~�̃V�[���ł͂��܂�X�|�b�g���C�g�������炸�A���s���Ȃ鑶�݂Ƃ���������Ă������A�����ł͂���ȕ̂�ɂ�����������]���B�R�Ƃ����ԓx�ŕ����悤�ȁA���2�l�̔M���\��L���ȃv���C�Ƀg�L���L�����ڂ���B1973�N�̂��Ƃ��B
�@�����ɂ����Ă͒������u�_�u���E�g�����{�[���E�N�C���e�b�g�v�Ґ��Ő������܂ꂽ�A���ł͋����q���ق�{���g���勐���Ƃ��ČN�Ղ���A�������ƌ��䎠�t�ɂ��o�����[�_�[��B�X�E�B���O�E�W���Y�S�����ɂ͒����t���قǂ̉Ԍ`�y�킾�����g�����{�[�����AJJ�W�����\���A�J�C�E�E�B���f�B���O�A�J�[�e�B�X�E�t���[�̖ىߑR��A���_���W���Y�ȍ~�̃V�[���ł͂��܂�X�|�b�g���C�g�������炸�A���s���Ȃ鑶�݂Ƃ���������Ă������A�����ł͂���ȕ̂�ɂ�����������]���B�R�Ƃ����ԓx�ŕ����悤�ȁA���2�l�̔M���\��L���ȃv���C�Ƀg�L���L�����ڂ���B1973�N�̂��Ƃ��B ������ �i�ӂ��ނ� �Ђ낵�j
������ �i�ӂ��ނ� �Ђ낵�j �@��r�I�Ⴂ�W���Y�E�t�@���ɂƂ��ẮA�uSamba De Negrito�v�̃q�g�ł��Ȃ��݂ƌ����Ă��悢�̂��낤���B�n�[�r�[�E�n���R�b�N�ip,el-p�j�A�u���[�m�E�J�[�ids�j�A�����ƕv�ib�j�炪�T�C�h�Q������77�N�j���[���[�N�^����w�����E�`���[�Y�f�C�E�C���E�j���[���[�N�x�́A�x�[�V�X�g �����F�̃C���^�[�i�V���i���Ȋ�����������Ō������Ȃ��A�܂����������̃W���Y�E�t�@���`�N���u�W���YDJ�����ɓM�������ꖇ�Ƃ��Ēm���Ă���B�u�W���Y�E�l�N�X�g�E�X�^���_�[�h�v�A�u�u���U�E�u���W���C���v�Ƃ������ߔN�̃f�B�X�N�K�C�h�{�̎w����ʂɂ��Ƃ�����傫���̂��낤���A�����艽������̃o�����ʼn̐S�E�u���[�X�t�B�[�����O��ꂽ�ቹ�ɐG��Ă݂�A���̍�i�̎��ł��t�B�W�J���Ń}�W�J���ȃO���[���̐^���Ƃ������̂ɔ��肫�邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
�@��r�I�Ⴂ�W���Y�E�t�@���ɂƂ��ẮA�uSamba De Negrito�v�̃q�g�ł��Ȃ��݂ƌ����Ă��悢�̂��낤���B�n�[�r�[�E�n���R�b�N�ip,el-p�j�A�u���[�m�E�J�[�ids�j�A�����ƕv�ib�j�炪�T�C�h�Q������77�N�j���[���[�N�^����w�����E�`���[�Y�f�C�E�C���E�j���[���[�N�x�́A�x�[�V�X�g �����F�̃C���^�[�i�V���i���Ȋ�����������Ō������Ȃ��A�܂����������̃W���Y�E�t�@���`�N���u�W���YDJ�����ɓM�������ꖇ�Ƃ��Ēm���Ă���B�u�W���Y�E�l�N�X�g�E�X�^���_�[�h�v�A�u�u���U�E�u���W���C���v�Ƃ������ߔN�̃f�B�X�N�K�C�h�{�̎w����ʂɂ��Ƃ�����傫���̂��낤���A�����艽������̃o�����ʼn̐S�E�u���[�X�t�B�[�����O��ꂽ�ቹ�ɐG��Ă݂�A���̍�i�̎��ł��t�B�W�J���Ń}�W�J���ȃO���[���̐^���Ƃ������̂ɔ��肫�邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
 �����F �i�݂��͂� �������j
�����F �i�݂��͂� �������j �@��ɂ��q�ׂ��w�u���[�E�A�b�v�x�A�w�u���[�E�V�e�B�x�Ńj�b�|���E�W���Y�E�V�[���̍őO���ɖ��o����،M��TBM�ł�4���ڂ̃��[�_�[��́A�u�W���Y���b�N�v�ƕ������̂��邱�Ƃ������݂��A���S�~���[�^���g�n�́g�I�}�X�Y�E�O���[���h���G���B�����ł̓x�[�X�����łȂ��A�G���s���ǂ��ǂ�����Ƃ����̂�����A���͂₻�̎p�͈�c�̑��叫�Ƃ��ă^�N�g�������}�C���X�A�t�F���E�N�e�B�AJB�̃}�i�[�ɂ������B����1975�N�A�n���̃g�[�^���e�B�ɏd����u�����A��̉��y�I�������ЂƂ̒��_�������ƌ����Ă��悢�A���o�����낤�B
�@��ɂ��q�ׂ��w�u���[�E�A�b�v�x�A�w�u���[�E�V�e�B�x�Ńj�b�|���E�W���Y�E�V�[���̍őO���ɖ��o����،M��TBM�ł�4���ڂ̃��[�_�[��́A�u�W���Y���b�N�v�ƕ������̂��邱�Ƃ������݂��A���S�~���[�^���g�n�́g�I�}�X�Y�E�O���[���h���G���B�����ł̓x�[�X�����łȂ��A�G���s���ǂ��ǂ�����Ƃ����̂�����A���͂₻�̎p�͈�c�̑��叫�Ƃ��ă^�N�g�������}�C���X�A�t�F���E�N�e�B�AJB�̃}�i�[�ɂ������B����1975�N�A�n���̃g�[�^���e�B�ɏd����u�����A��̉��y�I�������ЂƂ̒��_�������ƌ����Ă��悢�A���o�����낤�B
 ��،M �i������ �������j
��،M �i������ �������j �@��،M�O���[�v�A�{�ԗ��V�ƃj���[�n�[�h�A����ᩐ��O���[�v�ł̊����A����ɂ͓�x�ɂ킽�鎩�ȃR���{�̉������o�āA1975�N�A���������Đ������܂ꂽ�ꖇ��̃��M�����[�E�J���e�b�g�𗦂����f�r���[�E�A���o���B�X�����A��F�`�Y�ƕ��ԁA�����̎��A���g�O�l�O�̂ЂƂ�ł��������y��̃C�P�C�P�Ԃ�𑨂����{��́A1�Ȃ������đS�ă����E�e�C�N�Ř^������A����TBM���R�[�f�B���O�j��ŒZ���v���Ԃ̐V�L�^��ł����Ă��Ƃ����B
�@��،M�O���[�v�A�{�ԗ��V�ƃj���[�n�[�h�A����ᩐ��O���[�v�ł̊����A����ɂ͓�x�ɂ킽�鎩�ȃR���{�̉������o�āA1975�N�A���������Đ������܂ꂽ�ꖇ��̃��M�����[�E�J���e�b�g�𗦂����f�r���[�E�A���o���B�X�����A��F�`�Y�ƕ��ԁA�����̎��A���g�O�l�O�̂ЂƂ�ł��������y��̃C�P�C�P�Ԃ�𑨂����{��́A1�Ȃ������đS�ă����E�e�C�N�Ř^������A����TBM���R�[�f�B���O�j��ŒZ���v���Ԃ̐V�L�^��ł����Ă��Ƃ����B
 �y��p�j �i�Ƃ� �Ђłӂ݁j
�y��p�j �i�Ƃ� �Ђłӂ݁j �@��ꂫ�����̂��₳������ݍ��ށB�u�lj��v�̃s�A�m�͂܂�ŁA�ꂪ�킪�q�Ɍ�����A�Ƃ��Ղ�Ƃ������̕��i�̂悤���B�^���̑f���炵�����������A�R�{���̙z�Ƃ����n�C�g�[���ɗ܂����ڂ��B�l�ɂƂ��ẮA�l���R�o�[�u���E�X�g���C�T���h�̉̏��]�X�𗽉킵���A�I���W�i���e�B�ɖ������ō��̎q��S�Ȃ̂ł���B
�@��ꂫ�����̂��₳������ݍ��ށB�u�lj��v�̃s�A�m�͂܂�ŁA�ꂪ�킪�q�Ɍ�����A�Ƃ��Ղ�Ƃ������̕��i�̂悤���B�^���̑f���炵�����������A�R�{���̙z�Ƃ����n�C�g�[���ɗ܂����ڂ��B�l�ɂƂ��ẮA�l���R�o�[�u���E�X�g���C�T���h�̉̏��]�X�𗽉킵���A�I���W�i���e�B�ɖ������ō��̎q��S�Ȃ̂ł���B
 �R�{�� �i��܂��� �悵�j
�R�{�� �i��܂��� �悵�j �@����ȂɃX�e�L�Ȓj���W���Y�E�V���K�[�����̐��ɂ����̂�����Ǝv�킸�V�����A����قǂ܂łɔ��������̂���X�R�_��̐��B�n�X�L�[�Ȃ�ǂ�����҂蒆���I�ȃg�[���ŁA�����X�L���b�g�Ƀt�F�C�N�ɁA���̕�����ڂȂ��a���ł䂭�B���オ�~���Ă���̂����Ȃ��̂��A�ꕔ�Œj���W���Y�E���H�[�J���X�͊��Ƃ������Ă�������A�͂����ĐX�R�̉̐��͎s��ɂǂ̂悤�ɋ����̂��B�����̂ł���B
�@����ȂɃX�e�L�Ȓj���W���Y�E�V���K�[�����̐��ɂ����̂�����Ǝv�킸�V�����A����قǂ܂łɔ��������̂���X�R�_��̐��B�n�X�L�[�Ȃ�ǂ�����҂蒆���I�ȃg�[���ŁA�����X�L���b�g�Ƀt�F�C�N�ɁA���̕�����ڂȂ��a���ł䂭�B���オ�~���Ă���̂����Ȃ��̂��A�ꕔ�Œj���W���Y�E���H�[�J���X�͊��Ƃ������Ă�������A�͂����ĐX�R�̉̐��͎s��ɂǂ̂悤�ɋ����̂��B�����̂ł���B
 �X�R�_�� �i������ �������j
�X�R�_�� �i������ �������j


![TBM����[��1��]](https://img.hmv.co.jp/News/images/free4/digital3/JZ22/0-00000000TBM11_332_415.jpg) �@�X���[�E�u���C���h�E�}�C�X��1����i�Ƃ��Ă��̗��j�ɎW�R�ƋP�������N�C���e�b�g���w�~�l�x�ATRIO�Ձw�X�g���C�g�E�A�w�b�h�x���C�V���[�Ȃǂň�C�ɎႢ�W���Y�E���X�i�[����̃v���b�v�X�邱�ƂƂȂ����A���F�v�̏����[�_�[���w�f�r���[�x�A�������s�A����p�l�𒆐S�ɁA�Ⴋ���̕x�~��F�A�e�n��́A����ᩐ��A�R���m���Ō������ꂽ�u�V���I���y�������v���A1963�N6��26����������̃V�����\���i���E��b���Ŗ閈�s�Ȃ��Ă����Z�b�V�����̋L�^�w��b���Z�b�V�����x�A�����h���ŋ��������A�V�b�h�E�W���Y�E���[�������g�ȍ~�A�C�O�̃W���Y�E�R���N�^�[�ADJ��ɂ����Q�̐l�C���������ƕv�́h�a�W���Y�h���������w���j�R�[���x�ATBM�̊Ŕv���[���[�Ƃ������閼�x�[�V�X�g�A��،M������f�r���[�Ձw�u���[�E�A�b�v�x�ɑ����Đ������A��������{���w�u���[�E�V�e�B�x�A���������N�C���e�b�g���悹���𒎂��}�����u�b�^�鍡�c���̒ɉ��A�[�o���E�t�@���N���w�O���[���E�L���^�s���[�x�A���̖��Ձw�C�̗U���x����O��A�O�ؕq�傪��E�ҋȉƁ^�T�b�N�X�t�҂Ƃ��Ă��̋S�˂Ԃ���������������B��Ɠ������j�I���w�k���g�ȁx�B�L�O���ׂ�[��1��]�́ATBM���[�x�����\�����i�𒆐S��7�^�C�g���I
�@�X���[�E�u���C���h�E�}�C�X��1����i�Ƃ��Ă��̗��j�ɎW�R�ƋP�������N�C���e�b�g���w�~�l�x�ATRIO�Ձw�X�g���C�g�E�A�w�b�h�x���C�V���[�Ȃǂň�C�ɎႢ�W���Y�E���X�i�[����̃v���b�v�X�邱�ƂƂȂ����A���F�v�̏����[�_�[���w�f�r���[�x�A�������s�A����p�l�𒆐S�ɁA�Ⴋ���̕x�~��F�A�e�n��́A����ᩐ��A�R���m���Ō������ꂽ�u�V���I���y�������v���A1963�N6��26����������̃V�����\���i���E��b���Ŗ閈�s�Ȃ��Ă����Z�b�V�����̋L�^�w��b���Z�b�V�����x�A�����h���ŋ��������A�V�b�h�E�W���Y�E���[�������g�ȍ~�A�C�O�̃W���Y�E�R���N�^�[�ADJ��ɂ����Q�̐l�C���������ƕv�́h�a�W���Y�h���������w���j�R�[���x�ATBM�̊Ŕv���[���[�Ƃ������閼�x�[�V�X�g�A��،M������f�r���[�Ձw�u���[�E�A�b�v�x�ɑ����Đ������A��������{���w�u���[�E�V�e�B�x�A���������N�C���e�b�g���悹���𒎂��}�����u�b�^�鍡�c���̒ɉ��A�[�o���E�t�@���N���w�O���[���E�L���^�s���[�x�A���̖��Ձw�C�̗U���x����O��A�O�ؕq�傪��E�ҋȉƁ^�T�b�N�X�t�҂Ƃ��Ă��̋S�˂Ԃ���������������B��Ɠ������j�I���w�k���g�ȁx�B�L�O���ׂ�[��1��]�́ATBM���[�x�����\�����i�𒆐S��7�^�C�g���I
 �@�L�O���ׂ��X���[�E�u���C���h�E�}�C�X�iTBM�j��1����i�B���������̂͏o�������̐S�A�i�C�悭�B�u�Ȃ߂�ꂿ�Ⴂ���˂��v���Ă���ŁA�I�[�v�j���O�������̃A���g���u���u���ƗY���т��グ��B�����̑O���[�_�[��ɂ����߂�ꂽ�u���[�j���O��^�C�h�v�̍ĉ��B�������̂ڂ�A���������A���悢�搶�����������n�߂饥�����ȏ�Ȃ������������J������Ȃ����B���䏮����������Ƃ����g�����{�[���E�\���ʼn���B��j���ɂ߂邱�ƂȂ��A���㊰�̃h�������A���҃v�b�V���B���J�F�̃x�[�X���u���u�����Ȃ�B�����A�s��G�j�̃G���s��Ⰲ��O��o���B�������R�[�h�ɐj�𗎂Ƃ��A�₨�炱�̔M����̂����ς��ɎƂ߂��ҒN�����A����䂭�ӎ��̒��A�u���ɂ��̍��ɂ��z���}�����̃W���Y�E���[�x���������������I�v�ƁA�S�̒��ŃK�b�c�|�[�Y���ւ����Ȃ������͂����B
�@�L�O���ׂ��X���[�E�u���C���h�E�}�C�X�iTBM�j��1����i�B���������̂͏o�������̐S�A�i�C�悭�B�u�Ȃ߂�ꂿ�Ⴂ���˂��v���Ă���ŁA�I�[�v�j���O�������̃A���g���u���u���ƗY���т��グ��B�����̑O���[�_�[��ɂ����߂�ꂽ�u���[�j���O��^�C�h�v�̍ĉ��B�������̂ڂ�A���������A���悢�搶�����������n�߂饥�����ȏ�Ȃ������������J������Ȃ����B���䏮����������Ƃ����g�����{�[���E�\���ʼn���B��j���ɂ߂邱�ƂȂ��A���㊰�̃h�������A���҃v�b�V���B���J�F�̃x�[�X���u���u�����Ȃ�B�����A�s��G�j�̃G���s��Ⰲ��O��o���B�������R�[�h�ɐj�𗎂Ƃ��A�₨�炱�̔M����̂����ς��ɎƂ߂��ҒN�����A����䂭�ӎ��̒��A�u���ɂ��̍��ɂ��z���}�����̃W���Y�E���[�x���������������I�v�ƁA�S�̒��ŃK�b�c�|�[�Y���ւ����Ȃ������͂����B ����� �i�݂� ���������j
����� �i�݂� ���������j �@�u�R���g���[���A�W���[�E�w���_�[�\����̑���痂����h�X�����u���E�Łv�ƕ]����邱�Ƃ̑����e�i�[�E�T�b�N�X�t�ҁE�A���F�v�B�g�h�X�����h�Ƃ����`�e�͂Ƃ������A���̉��ɂ܂��Y�b�V���Ƃ����d�ʊ������邱�Ƃ́A���̏����[�_�[��A�܂��̓T�C�h�����Ƃ��ĎQ�����g����h���x���̍D�����c���Ă���W���[�W��ˁw�V�[�E�u���[�Y�x�A�����ҁw�T�E���h�E�I�u�E�T�E���h���~�e�b�h�x�A���{���u�w�o�r���j�A�E�E�C���h�x�A����ᩐ��w�x�������E�W���Y�E�t�F�X�e�B�o���e71�x�Ƃ���������i���Ă���������Ζ��炩���낤�B
�@�u�R���g���[���A�W���[�E�w���_�[�\����̑���痂����h�X�����u���E�Łv�ƕ]����邱�Ƃ̑����e�i�[�E�T�b�N�X�t�ҁE�A���F�v�B�g�h�X�����h�Ƃ����`�e�͂Ƃ������A���̉��ɂ܂��Y�b�V���Ƃ����d�ʊ������邱�Ƃ́A���̏����[�_�[��A�܂��̓T�C�h�����Ƃ��ĎQ�����g����h���x���̍D�����c���Ă���W���[�W��ˁw�V�[�E�u���[�Y�x�A�����ҁw�T�E���h�E�I�u�E�T�E���h���~�e�b�h�x�A���{���u�w�o�r���j�A�E�E�C���h�x�A����ᩐ��w�x�������E�W���Y�E�t�F�X�e�B�o���e71�x�Ƃ���������i���Ă���������Ζ��炩���낤�B
 �A���F�v �i�����܂� �������j
�A���F�v �i�����܂� �������j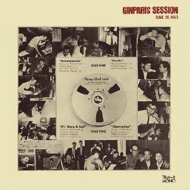 �@������ЂƂ̃g�L�����I�t�Q������B��S����Ⴂ�N���G�C�^�[�����������������Ȃ��疢�����B�Ȃ낤�A�Ȃ낤�A�����Ȃ낤�A�����͞w�ɂȂ낤�A�̐��_�ł���B�����1963�N6��26���̓�������̃V�����\���i���u��b���v�B�������s�A����p�l�A�x�~��F�A�e�n��́A����ᩐ��A�R���m���𒆐S�ɁA�����܂������ɋ߂������Ⴋ�W���Y�����ɂ����50�N�㖖�Ɍ������ꂽ�u�V���I���y�������v�́A������Ӗ��ɂ����� �g�����˔j�h���邽�߂̃��{�ł��莛�q���ł��������B
�@������ЂƂ̃g�L�����I�t�Q������B��S����Ⴂ�N���G�C�^�[�����������������Ȃ��疢�����B�Ȃ낤�A�Ȃ낤�A�����Ȃ낤�A�����͞w�ɂȂ낤�A�̐��_�ł���B�����1963�N6��26���̓�������̃V�����\���i���u��b���v�B�������s�A����p�l�A�x�~��F�A�e�n��́A����ᩐ��A�R���m���𒆐S�ɁA�����܂������ɋ߂������Ⴋ�W���Y�����ɂ����50�N�㖖�Ɍ������ꂽ�u�V���I���y�������v�́A������Ӗ��ɂ����� �g�����˔j�h���邽�߂̃��{�ł��莛�q���ł��������B
 �������s �i������Ȃ� �܂��䂫�j
�������s �i������Ȃ� �܂��䂫�j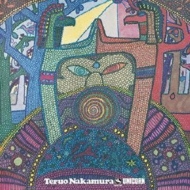 �@�[���N��ȍ~�A�p���f�~�b�N�I�Ɋ����N�������Ƃ���関�\�L�́u�a�W���Y�E���[�������g�v�B�����A����ȑO���獑���݂̂Ȃ炸�C�O�̃W���Y�E�R���N�^�[����������₦�����ڂ���Ă������{�̃W���Y�E���R�[�h�Ƃ����̂�����B80�N�����̃����h���ŋ��������A�V�b�h�E�W���Y�E���[�������g�Ɍĉ����ē��ɍ����l�C���ւ����̂��A�R�{�M�R�̎ڔ��I���G���^������Ձw��E�x�ł���A����ᩐ��́w�X�l�C�N�E�q�b�v�x�ł���A�����Ē����ƕv�̏����[�_�[��ƂȂ�A���́w���j�R�[���x�ł���B
�@�[���N��ȍ~�A�p���f�~�b�N�I�Ɋ����N�������Ƃ���関�\�L�́u�a�W���Y�E���[�������g�v�B�����A����ȑO���獑���݂̂Ȃ炸�C�O�̃W���Y�E�R���N�^�[����������₦�����ڂ���Ă������{�̃W���Y�E���R�[�h�Ƃ����̂�����B80�N�����̃����h���ŋ��������A�V�b�h�E�W���Y�E���[�������g�Ɍĉ����ē��ɍ����l�C���ւ����̂��A�R�{�M�R�̎ڔ��I���G���^������Ձw��E�x�ł���A����ᩐ��́w�X�l�C�N�E�q�b�v�x�ł���A�����Ē����ƕv�̏����[�_�[��ƂȂ�A���́w���j�R�[���x�ł���B �����ƕv �i�Ȃ��ނ� �Ă邨�j
�����ƕv �i�Ȃ��ނ� �Ă邨�j �@�A�[�g�E�u���C�L�[�y�c�ł̉��t���o�āA�j���[���[�N����A��������،M���A1973�N�ɃW���[�W��ˁids�j�A����M�F�ip,el-p�j�A�����F�ib�j�Ƃ̃J���e�b�g�i�ꕔ�g���I�j�Ő��������[�_�[�E�f�r���[��w�u���[�E�A�b�v�x���A�u�V�˃x�[�V�X�g/�R���|�[�U�[����!�v�Ƃ��̖�������S���ɒm�炵�߂���̂ƂȂ����̂͗L���Șb�B30�N��ɂ͑��҂܂ō���Ă���A�܂��Ɏ������ɔF�߂���{�W���Y�̋�������i���B
�@�A�[�g�E�u���C�L�[�y�c�ł̉��t���o�āA�j���[���[�N����A��������،M���A1973�N�ɃW���[�W��ˁids�j�A����M�F�ip,el-p�j�A�����F�ib�j�Ƃ̃J���e�b�g�i�ꕔ�g���I�j�Ő��������[�_�[�E�f�r���[��w�u���[�E�A�b�v�x���A�u�V�˃x�[�V�X�g/�R���|�[�U�[����!�v�Ƃ��̖�������S���ɒm�炵�߂���̂ƂȂ����̂͗L���Șb�B30�N��ɂ͑��҂܂ō���Ă���A�܂��Ɏ������ɔF�߂���{�W���Y�̋�������i���B
 �@����͂����A�̂������獡�c�����̃A�[�o���E�t�@���N���y��\��ȂɑS�Ă��W��Ă��銴�����낤���B1975�N�Ƃ�������̋�C�����������ł����Ƌz�������̋Ȃ̉��̂���ɂ́A�u�a���w�b�h�n���^�[�Y�v�u���{�Ń����[�E�����O�Y�E�t���[�G���v�ƌĂ�ō����x���Ȃ��قǂ̂��̂�����B���[�_���ȁu�X�g���[�g�E�t���b�V���v�ɂ��Ă������B
�@����͂����A�̂������獡�c�����̃A�[�o���E�t�@���N���y��\��ȂɑS�Ă��W��Ă��銴�����낤���B1975�N�Ƃ�������̋�C�����������ł����Ƌz�������̋Ȃ̉��̂���ɂ́A�u�a���w�b�h�n���^�[�Y�v�u���{�Ń����[�E�����O�Y�E�t���[�G���v�ƌĂ�ō����x���Ȃ��قǂ̂��̂�����B���[�_���ȁu�X�g���[�g�E�t���b�V���v�ɂ��Ă������B
 ���c�� �i���܂� �܂���j
���c�� �i���܂� �܂���j �@������|�̈ꌾ�ɐs����B�Y�b�R�P�唚�Ƃ����j���A���X�ł͂Ȃ��A���́A���܂�ɂ��_�C�i�~�b�N�ŁA���H�L�ȋ�C������������r�b�O�o���h�E�T�E���h�ɁA�ЂƂ���ǂ�ł��ĉx�ɓ���A�Ƃ������o���B�����{�̃r�b�O�o���h�E�W���Y�̖��ƁA�����B��Ɠ������j�I����1977�N�X���[�E�u���C���h�E�}�C�X�ł�3��ڂɁA��E�ҋȉƁ^�T�b�N�X�t�҂Ƃ��ăN���W�b�g����Ă���̂��A�����B�������̎O�ؕq��B���́A�ƌ����Ă��s���Ɨ��Ȃ������O�ɂ͏��X�������K�v���낤���B�u�݂��E�тv�B���̖��O���炵�Ă��łɂ�炩�������ȃ��[�h���Y���Ă��邪�A�W���Y�݂̂Ȃ炸���a�`�����̉��y�E�A���ɉf�批�y�A���䉹�y�̐��E�ɂ����Ă͑�ςȏ@���Œm���Ă��邨�l�Ȃ̂��B1988�N�ɂ́A�u�ނ�o�J�����v�̋L�O���ׂ���1��ڂ̉��y����|���A���̖��������̊ԂɍL���Z���������A����u�ނ�o�J���y�̐l�v�ƌĂ�ł��T�˃o�`�͓�����Ȃ����낤���B�Ƃ������A6�N�Ԃ̕č����ҏC�s���I���A�������O�ɂƂ���TBM�Ƃ������[�x���́A�Ȃ̃|�e���V�������ő���Ɉ����o�����߂ɁA����ȏ�Ȃ��ӂ��킵�����[�x���������ɈႢ�Ȃ��B�@�@
�@������|�̈ꌾ�ɐs����B�Y�b�R�P�唚�Ƃ����j���A���X�ł͂Ȃ��A���́A���܂�ɂ��_�C�i�~�b�N�ŁA���H�L�ȋ�C������������r�b�O�o���h�E�T�E���h�ɁA�ЂƂ���ǂ�ł��ĉx�ɓ���A�Ƃ������o���B�����{�̃r�b�O�o���h�E�W���Y�̖��ƁA�����B��Ɠ������j�I����1977�N�X���[�E�u���C���h�E�}�C�X�ł�3��ڂɁA��E�ҋȉƁ^�T�b�N�X�t�҂Ƃ��ăN���W�b�g����Ă���̂��A�����B�������̎O�ؕq��B���́A�ƌ����Ă��s���Ɨ��Ȃ������O�ɂ͏��X�������K�v���낤���B�u�݂��E�тv�B���̖��O���炵�Ă��łɂ�炩�������ȃ��[�h���Y���Ă��邪�A�W���Y�݂̂Ȃ炸���a�`�����̉��y�E�A���ɉf�批�y�A���䉹�y�̐��E�ɂ����Ă͑�ςȏ@���Œm���Ă��邨�l�Ȃ̂��B1988�N�ɂ́A�u�ނ�o�J�����v�̋L�O���ׂ���1��ڂ̉��y����|���A���̖��������̊ԂɍL���Z���������A����u�ނ�o�J���y�̐l�v�ƌĂ�ł��T�˃o�`�͓�����Ȃ����낤���B�Ƃ������A6�N�Ԃ̕č����ҏC�s���I���A�������O�ɂƂ���TBM�Ƃ������[�x���́A�Ȃ̃|�e���V�������ő���Ɉ����o�����߂ɁA����ȏ�Ȃ��ӂ��킵�����[�x���������ɈႢ�Ȃ��B�@�@
 �O�ؕq�� �i�݂� �тj
�O�ؕq�� �i�݂� �тj