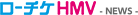【追悼特集】 デヴィッド・ボウイ『★』と現代ジャズ・シーンの精鋭たち
Friday, January 29th 2016

1947 - 2016
 David Bowie 『★』
David Bowie 『★』
ニュー・アルバム『★』は、デヴィッド・ボウイ69歳の誕生日(2016年1月8日)に発売された。ボウイと”70年代のボウイを創った男”とも言える盟友トニー・ヴィスコンティがプロデュースを手掛け、ダニー・マッキャスリン(Saxophone, Flute, Woodwind)、マーク・ジュリアナ(Drums, Percussion)、ジェイソン・リンドナー(Piano, Wurlitzer Organ, Keyboards)ら“新世代のジャズ・シーン”を牽引するアーティストや、2011年に活動を終了したLCDサウンドシステムの中心人物、ジェームス・マーフィーがパーカッションで参加している。
デヴィッド・ボウイ『★』に参加した現代ジャズ・シーンの精鋭たち
デヴィッド・ボウイ最後の置き土産となった『★(ブラックスター)』。その参加アーティストをめぐって、ジャズ界隈がちょっとした騒ぎになっていることはすでにご存知の方も多いのではないでしょうか。「JAZZ THE NEW CHAPTER」監修でおなじみの柳樂光隆さんを筆頭に、多くのジャズ系評論家、ライター、ミュージシャン諸氏が、ほぼリリース前より本作について言及するというおもしろい現象が起きているのです。
つまりある視点に立てば、このアルバム・プロダクションにおけるテーゼなり基準となり得ているものは、ずばり「ボウイの現代ジャズメンの本格的な起用」であり、ボウイのみならずロックサイドが急進的に必要としている”新しいサウンド”の在り処の一例を「現代ジャズの柔軟性」「ポスト・ジャズの強度」として導き出すことができるのではないか・・・とそんな数々の考察・見解が、”押し黙る”主役作家を傍目に『★』を騒然と取り巻いている今日この頃。
 もちろんこれは、現代ラージ・アンサンブル最高のビッグバンド・リーダー/作編曲家マリア・シュナイダーのオーケストラを起用した前年の「Sue(or In A Season Of Crime)」からの流れを汲めば、至ってナチュラルな着地点と見ることもできるでしょう。またかつて、マリア・シュナイダーのお師匠さんでもあるギル・エヴァンスのオケで「Absolute Beginners」(自身が主演を務めたミュージカル映画)をフェイクジャズ気味に歌っていたことを踏まえると、ティーンの頃から胸を焦がし続けてきたジャズへの接近を四半世紀ぶりに成就できたボウイのカタルシスも少なからず推知できるのではないでしょうか。ちなみに、2006年頃のマリア・シュナイダー・オーケストラのコンサート、その客席には、ボウイやデヴィッド・バーンらの姿があったということ。
もちろんこれは、現代ラージ・アンサンブル最高のビッグバンド・リーダー/作編曲家マリア・シュナイダーのオーケストラを起用した前年の「Sue(or In A Season Of Crime)」からの流れを汲めば、至ってナチュラルな着地点と見ることもできるでしょう。またかつて、マリア・シュナイダーのお師匠さんでもあるギル・エヴァンスのオケで「Absolute Beginners」(自身が主演を務めたミュージカル映画)をフェイクジャズ気味に歌っていたことを踏まえると、ティーンの頃から胸を焦がし続けてきたジャズへの接近を四半世紀ぶりに成就できたボウイのカタルシスも少なからず推知できるのではないでしょうか。ちなみに、2006年頃のマリア・シュナイダー・オーケストラのコンサート、その客席には、ボウイやデヴィッド・バーンらの姿があったということ。今回のアルバムにおいても、『Alladin Sane』以来ボウイの狂気と儚さを支え一時代を築いた古参の盟友でもあるジャズ・ピアニスト、マイク・ガーソンの参加は勿論なく、ボウイ、あるいはプロデューサーのトニー・ビスコンティが選んだのは、ここ数年さらにギアを上げて進化・拡張化する現代ジャズ・シーンの精鋭たち。彼らはいずれも「ジャズのイディオムの中でジャズを超えることができる」、しかし一方で往年のジャズ通の目には半ばアクロバティックなトリックアート作家程度にしか映らない恐れもある、大胆不敵でしたたかなアプローチで”ジャズにハッパをかける”ゼネラリストばかりなのです。
マリア・シュナイダー (Maria Schneider)
 1960年米ミネソタ州ウィンドム出身。ミネソタ大学で音楽理論と作曲法を習得後、NYに進出。ギル・エヴァンスとボブ・ブルックマイヤーにアレンジを学び、1992年に自己オーケストラを結成。同年9月に自主制作による第1作『Evanescence』を発表。「マジカルで雄大で心臓が止まるほど美しいサウンド」と形容される、アンサンブル・ミュージックの最先端を行くマリア・シュナイダー・オーケストラ。現代性に富むサウンドをジャズ・オーケストラで巧みに描き出す手法は各メディアで高く評価されており、『Concert in the Garden』(2004)、『Sky Blue』(2007)などで多数のグラミー賞受賞歴を誇る。最新アルバムは2015年発表の『Thompson Fields』。
1960年米ミネソタ州ウィンドム出身。ミネソタ大学で音楽理論と作曲法を習得後、NYに進出。ギル・エヴァンスとボブ・ブルックマイヤーにアレンジを学び、1992年に自己オーケストラを結成。同年9月に自主制作による第1作『Evanescence』を発表。「マジカルで雄大で心臓が止まるほど美しいサウンド」と形容される、アンサンブル・ミュージックの最先端を行くマリア・シュナイダー・オーケストラ。現代性に富むサウンドをジャズ・オーケストラで巧みに描き出す手法は各メディアで高く評価されており、『Concert in the Garden』(2004)、『Sky Blue』(2007)などで多数のグラミー賞受賞歴を誇る。最新アルバムは2015年発表の『Thompson Fields』。
 『Concert In The Garden』 (2004)
『Concert In The Garden』 (2004) スペインや中南米音楽の要素を積極的に採り入れたリズムやハーモニー、木管楽器を多用した柔らかく美しい音色など、それまでの一般的なビッグバンドの概念からはかけ離れているオーケストレーションだが、そこに全く不自然さを感じさせないのはやはり彼女のコンポーザー/アレンジャーとしての見事な腕が光っているだと言えよう。こちらは2012年リリースの新装ジャケ再発盤。
 『Thompson Fields』 (2015)
『Thompson Fields』 (2015) ギル・エヴァンス直伝のオーケストレーションをさらに独自発展させて、ジャズのイディオムとコンテンポラリーな感覚を見事に融合させた魔法のようなサウンドの数々。ダニー・マッキャスリン(ts)、ラーゲ・ルンド(g)、クラレンス・ペン(ds)、ジェイ・アンダーソン(b)、フランク・キンブロウ(p)らおなじみの精鋭を従えて、21世紀最高のビッグバンド・アンサンブルが世界を揺らす。
アルバムの取っ掛かりとなった「Sue」には、前述通りマリア・シュナイダー・オーケストラによる現代的なビッグバンド・サウンドが組み込まれていますが、ここでは核となるレギュラー人員を少々入れ替えることで、ボウイとビスコンティが追い求めた「21世紀のジャズの鳴り」(本人たちがそう言ったかどうかは?)というオファーに首尾よく対応。そう、そのサウンド・デザインを決定的なものとするために必要だったのが、マーク・ジュリアナのドラムであり、ベン・モンダーのギターであったということ。
イレギュラー的にオーケストラに参加した二人(モンダーは出戻り)。果たしてこれがボウイ直々のラブコールだったのかは不明ですが、いずれにせよ「ジャズのイディオムの中でジャズを超えることができる」という点ではどちらも申し分のない実績を残し、化学反応の中でさらなる飛躍や逸脱を予感させるポテンシャルの持ち主であることは、少なくとも現代ジャズ・チェッカーズの間では有名。このたびそれが、ボウイ作品への参加によって白日の下にさらされた、そう言い切ってしまっても乱暴ではないでしょう。
マーク・ジュリアナは、その類稀なるスキルと持ち味のミニマル・グルーヴを駆使しながら、エレクトロ、ビートミュージック、ベースミュージック、EDM、ドラムンベース、インディロック・・・あらゆるリズムのコンテンポラリー要素を複合的にジャズのいちエッセンスとして取り込むことができるドラマー。ミシェル・ンデゲオチェロが絡んだビートミュージック集、ブラッド・メルドーとの電化メリアナ・プロジェクトなど、どちらかと言えば非ジャズ傾向が強い作風が目立つものの、昨年は純正カルテットで吹き込んだ『Family First』という、ジャズにしっかりと軸足を置いた素晴らしいアルバムも発表しているのです。
イレギュラー的にオーケストラに参加した二人(モンダーは出戻り)。果たしてこれがボウイ直々のラブコールだったのかは不明ですが、いずれにせよ「ジャズのイディオムの中でジャズを超えることができる」という点ではどちらも申し分のない実績を残し、化学反応の中でさらなる飛躍や逸脱を予感させるポテンシャルの持ち主であることは、少なくとも現代ジャズ・チェッカーズの間では有名。このたびそれが、ボウイ作品への参加によって白日の下にさらされた、そう言い切ってしまっても乱暴ではないでしょう。
マーク・ジュリアナは、その類稀なるスキルと持ち味のミニマル・グルーヴを駆使しながら、エレクトロ、ビートミュージック、ベースミュージック、EDM、ドラムンベース、インディロック・・・あらゆるリズムのコンテンポラリー要素を複合的にジャズのいちエッセンスとして取り込むことができるドラマー。ミシェル・ンデゲオチェロが絡んだビートミュージック集、ブラッド・メルドーとの電化メリアナ・プロジェクトなど、どちらかと言えば非ジャズ傾向が強い作風が目立つものの、昨年は純正カルテットで吹き込んだ『Family First』という、ジャズにしっかりと軸足を置いた素晴らしいアルバムも発表しているのです。
マーク・ジュリアナ (Mark Guiliana)
 Modern Drummer誌に「ドラミングのエキサイティングなニュースタイルの最前線に立っている」と評された、米ニュージャージー出身のマーク・ジュリアナ。ユニークで妥協を許さないドラムスタイルは、リーダーとして、また名サイドマンとして、アメリカ国内にとどまらず、世界的に高い評価を獲得。2004年に“実験的ガレージ・ジャズ”トリオ、HEERNTを結成。サイドマンとしては、ジュリアナは長らくアヴィシャイ・コーエンとともに活動。2003年から2008年までのツアー、6枚のスタジオ・アルバムで脇を固めている。ほか、ミシェル・ンデゲオチェロ、ウェイン・クランツ、ティグラン・ハマシアン、マティスヤフ、ボビー・マクファーレンなど多彩なジャンルのアーティストと活動。2013年、ブラッド・メルドーとのエレクトロ・プロジェクト「メリアナ」でアルバムを発表後、自身のBeat Music Productionsから初のリーダー作『My Life Starts Now』とミシェル・ンデゲオチェロとの共同プロデュースによる『Beat Music』をリリース。2015年には、盟友シャイ・マエストロ、クリス・モリッシーらとのジャズ・カルテット名義で『Family First』をリリースしている。
Modern Drummer誌に「ドラミングのエキサイティングなニュースタイルの最前線に立っている」と評された、米ニュージャージー出身のマーク・ジュリアナ。ユニークで妥協を許さないドラムスタイルは、リーダーとして、また名サイドマンとして、アメリカ国内にとどまらず、世界的に高い評価を獲得。2004年に“実験的ガレージ・ジャズ”トリオ、HEERNTを結成。サイドマンとしては、ジュリアナは長らくアヴィシャイ・コーエンとともに活動。2003年から2008年までのツアー、6枚のスタジオ・アルバムで脇を固めている。ほか、ミシェル・ンデゲオチェロ、ウェイン・クランツ、ティグラン・ハマシアン、マティスヤフ、ボビー・マクファーレンなど多彩なジャンルのアーティストと活動。2013年、ブラッド・メルドーとのエレクトロ・プロジェクト「メリアナ」でアルバムを発表後、自身のBeat Music Productionsから初のリーダー作『My Life Starts Now』とミシェル・ンデゲオチェロとの共同プロデュースによる『Beat Music』をリリース。2015年には、盟友シャイ・マエストロ、クリス・モリッシーらとのジャズ・カルテット名義で『Family First』をリリースしている。
 『Family First』 (2015)
『Family First』 (2015) マーク・ジュリアナ最新作は、活動の別軸となるアコースティック・ジャズの普遍的な魅力を今一度見つめ直したかのような内容に。アヴィシャイ・コーエン・バンド時代の盟友シャイ・マエストロ(p)、鉄壁のリズム隊復活となったクリス・モリッシー(b)ら旧知の面々との”純ジャズ”カルテット編成にて、これまでのジュリアナ作品にはなかった美しくも原初的な音のつばぜり合いが横溢した。
 『My Life Starts Now』 (2014)
『My Life Starts Now』 (2014) 同時リリースのビート・ミュージック集と対になるNY録音の2014年初リーダー作。DUB TRIOなどで活動をするステュー・ブルックス(b)、ユキ・ヒラノ(key)、マイケル・セバーソン(g)とのカルテット+@に、グレッチェン・パーラト、ミシェル・ンデゲオチェロらがゲスト参加。「My Name Is Not Important」、「Move Over Old Guy」などで聴ける本領とも言える精巧な人力ドラムンベース&テクノビートが圧巻。
 Brad Mehldau / Mark Guiliana
Brad Mehldau / Mark Guiliana『Mehliana: Taming The Dragon』 (2014)
ブラッド・メルドーとのエレクトロ・デュオ・プロジェクト「メリアナ」のフルアルバム。プロデュースはグレッグ・コラー。ボーダレスな音楽的実験を繰り返しながら自らの音楽性を進化させているメルドーとジュリアナ。本作においても、ジャズや現代音楽といった範疇を超えた真の意味でのプログレッシヴ・ミュージックを展開。
 Sam Crowe Group
Sam Crowe Group『Towards The Centre Of Everything』 (2013)
マシュー・ハーバート・バンドでの活躍、さらにネイティヴ・ダンサーという新グループでの活動も注目を集める、英国ジャズが次なるフェーズに入ったことを伝えるロンドンのピアニスト、サム・クロウ。甘美でメランコリックな旋律が壮大なスペースに放たれる本作においては、やはりマーク・ジュリアナ、アラン・ハンプトンというNYリズム隊によって創出されたギャラクティック・グルーヴが肝になっている。
昨年末にECMから最新リーダー作『Amorphase』(録音は2010、12年)も届けられたNYのギタリスト、ベン・モンダーは、多くの先鋭的な巨匠ジャズ・ミュージシャンからも引っ張りだこのファーストコーラー。ビル・フリーゼルやジョン・アバクロンビー直系の透明感と浮遊感をキープしながら、ときにノイジーでメタリックな音をかきむしり、また十八番の高速アルペジオをトランシーに繰り出して芸術的な空間を創出。「Sue」では、決して出しゃばらないながらも、変幻自在のサウンド、フレージングで圧倒的な存在感を放っています。
ベン・モンダー (Ben Monder)
 1962年米ニューヨーク・ウェストチェスター出身。80年代初頭よりプロ活動を開始。以来30年以上に亘り、マーク・ジョンソン・グループ、テオ・ブレックマン・デュオ、ポール・モチアン・エレクトリク・ビ・バップバンド、そしてマリア・シュナイダー・オーケストラといった様々なグループ、プロジェクト、ビッグバンド・オーケストラに参加しながら、自身のカルテットやトリオを率いてSunnysideやECMなどからリーダー・アルバムを発表している。トレードマークの高速アルペジオを駆使しながら、ジム・ホール、ビル・フリーゼル、ジョン・アバクロンビー系統の繊細で浮遊感のあるプレイ、ときにディストーションを効かせた激しいインプロビゼーション・ノイズで、スペースの創出、サウンドの陰陽を巧みに形作る。2015年には、生前のポール・モチアンとのデュオ・マテリアルに、アンドリュー・シリルとのレコーディング・プロダクションを加えることで完成を見た『Amorphae』を発表している。
1962年米ニューヨーク・ウェストチェスター出身。80年代初頭よりプロ活動を開始。以来30年以上に亘り、マーク・ジョンソン・グループ、テオ・ブレックマン・デュオ、ポール・モチアン・エレクトリク・ビ・バップバンド、そしてマリア・シュナイダー・オーケストラといった様々なグループ、プロジェクト、ビッグバンド・オーケストラに参加しながら、自身のカルテットやトリオを率いてSunnysideやECMなどからリーダー・アルバムを発表している。トレードマークの高速アルペジオを駆使しながら、ジム・ホール、ビル・フリーゼル、ジョン・アバクロンビー系統の繊細で浮遊感のあるプレイ、ときにディストーションを効かせた激しいインプロビゼーション・ノイズで、スペースの創出、サウンドの陰陽を巧みに形作る。2015年には、生前のポール・モチアンとのデュオ・マテリアルに、アンドリュー・シリルとのレコーディング・プロダクションを加えることで完成を見た『Amorphae』を発表している。
 『Amorphae』 (2015)
『Amorphae』 (2015) 2004年のポール・モチアン・バンド『Garden of Eden』で初のECM録音を経験したモンダー。2010年にそのモチアンとのデュオをECMで録音するも、モチアンが2011年に他界してしまったため制作作業が途絶えてしまったものの、2012年からアンドリュー・シリル(ds)、ピート・レンデ(synth)と共にプロジェクトを再開。ソロ、モチアンとのデュオ、そしてシリルとのデュオ、シリルとレンデとのトリオという各編成で構成されている。
 『Hydra』 (2013)
『Hydra』 (2013) 長年の盟友である鬼才ヴォーカリスト、テオ・ブレックマンをフィーチャーし、またこちらも旧知のスクリ・スヴェリソン(b)、テッド・プア(ds)も参加したSunnyside3作目。浮遊系のコードやヴォイシング、スペイシーな音色とロック的なフレーズの交錯、そしてミステリアスで緩急自在のアルペジオ。パット・メセニー・グループ的なストーリー性を感じさせるタイトル曲をはじめ、幽玄で広大な音空間を描き上げる。
さらに付け加えたいジャズメンが2人ばかり。ピアニスト/キーボーディストのジェイソン・リンドナーと、マリア・シュナイダー・オーケストラ不動のソロイストにして、2016年現在において最も飛躍的に「ジャズのイディオムの中でジャズを超える」ことができるサックス奏者ダニー・マッキャスリン。
リンドナーの現時点での代表作と言えばやはり、こちらもミシェル・ンデゲオチェロがプロデュース&参加した『Now VS Now』になるでしょうか。マーク・ジュリアナらとのトリオをベースにして、アヴィシャイ・コーエン(tp)、カート・ローゼンウィンケル(g)ら”分かってる”ゲスト陣が入り乱れながら、エレクトロ、ヒップホップ、ときにポエトリー・リーディングなど多様なアプローチでジャズ街道、またはジャズの畦道(バイパス)を鮮やかに走り抜けていきます。
リンドナーの現時点での代表作と言えばやはり、こちらもミシェル・ンデゲオチェロがプロデュース&参加した『Now VS Now』になるでしょうか。マーク・ジュリアナらとのトリオをベースにして、アヴィシャイ・コーエン(tp)、カート・ローゼンウィンケル(g)ら”分かってる”ゲスト陣が入り乱れながら、エレクトロ、ヒップホップ、ときにポエトリー・リーディングなど多様なアプローチでジャズ街道、またはジャズの畦道(バイパス)を鮮やかに走り抜けていきます。
ジェイソン・リンドナー (Jason Lindner)
 現在、マーク・ジュリアナ(ds)、パナジオティス・アンドレオウ(b)とのリーダー・エレクトロジャズ・トリオ「NOW VS NOW」の活動をメインに行なっているNYのマルチ鍵盤奏者ジェイソン・リンドナー。90年代後半〜00年代にかけて自己グループを率いて出演していた、グリニッチヴィレッジにあるNYジャズファン御用達の人気ジャズクラブ、スモールズでのライヴ活動が方々で話題に。その後、若手ジャズメンの登竜門レーベルFresh Sound New Talentやアナット・コーエン主宰Anzicから秀作を連発。サイド参加も多数。ジャズのみならず、ネオソウル、レゲエ、インディロックなど様々な音楽スタイルを吸収昇華した独創性あふれるプレイスタイル〜サウンドで、ミシェル・ンデゲオチェロ、マリア・シュナイダー、オメル・アヴィタルらをも魅了した。
現在、マーク・ジュリアナ(ds)、パナジオティス・アンドレオウ(b)とのリーダー・エレクトロジャズ・トリオ「NOW VS NOW」の活動をメインに行なっているNYのマルチ鍵盤奏者ジェイソン・リンドナー。90年代後半〜00年代にかけて自己グループを率いて出演していた、グリニッチヴィレッジにあるNYジャズファン御用達の人気ジャズクラブ、スモールズでのライヴ活動が方々で話題に。その後、若手ジャズメンの登竜門レーベルFresh Sound New Talentやアナット・コーエン主宰Anzicから秀作を連発。サイド参加も多数。ジャズのみならず、ネオソウル、レゲエ、インディロックなど様々な音楽スタイルを吸収昇華した独創性あふれるプレイスタイル〜サウンドで、ミシェル・ンデゲオチェロ、マリア・シュナイダー、オメル・アヴィタルらをも魅了した。
 『Now VS Now』 (2009)
『Now VS Now』 (2009) そのサウンドを「ガレージ・ジャズ」とジェイソン自ら称したジャズ〜ファンク〜ロックなサウンド。多岐に渡るリズムと多彩な鍵盤ワークによる圧倒的なトリオプレイに加え、様々なゲストの参加により、多国籍な味付けが加えられ、まさに本領発揮とも言うべきエッジの効いたコンテンポラリー・ジャズを創造。プロデュースはミシェル・ンデゲオチェロ、ミックスはボブ・パワー。ゲストには、そのンデゲオチェロほか、カート・ローゼンウィンケル、アヴィシャイ・コーエン(tp)、クラウディア・アクーニャらが参加。
 Anat Cohen
Anat Cohen『Luminosa』 (2015)
NYの女流クラリネット奏者アナット・コーエンの2015年新作にサイド参加。ミルトン・ナシメントの声に魅了されて以来傾倒しているという心よりのブラジル集で、ショーター×ミルトン「Lilia」、エドゥ・ロボ&シコ・ブアルキ「Beatriz」、バーデン・パウエルに捧げたオリジナルなどブラジル音楽への深い理解がそこかしこに。フライング・ロータス「Putty Boy Strut」のアコースティック再構築などユニークな試みも。
そして、マッキャスリンが昨年リリースした『Fast Future』はさらに刺激的。リズムを重点的に研磨しビート化したサウンド、主役のトレードマークの奔放で力強いブロウもさることながら、エイフェックス・ツイン「54 Cymru Beats」、アンチコンのバス「No Eye」を好きだから当然のように採り上げました的態度からしてもはやネクストレベル。
マッキャスリンのプロジェクトのレギュラーメンバーの顔ぶれをのぞいて見ると、ジュリアナ、リンドナー、そしてベーシストのティム・ルフェーヴル、つまり『★』に参加したカルテットが勢揃い。裏を返せば『★』は、このセッション(+1)によるロック詣に他ならず、とはいえ二次的な流用にとどまることなくボウイ支配のダークで物語趣味の強いサウンドや世界観の大枠を生きたセッションの中で見事に拵えきっていると、そんな捉え方も必然・・・というか、むしろそう捉えるしか他に道はないでしょう。
ダニー・マッキャスリン (Donny McCaslin)
 1966年米カリフォルニア州サンタ・クルーズ出身のテナーサックス奏者。高校卒業後にバークリー音楽院に進学。ゲイリー・バートン、ジョージ・ガゾーンらに師事する。1991年NYに移住後は、エディ・ゴメスのバンドに参加、またゴメスの紹介でマイケル・ブレッカーの後任としてステップス・アヘッドに加入。ほか、ギル・エヴァンス・オーケストラ、マリア・シュナイダー・ジャズ・オーケストラ、ミンガス・ビックバンド、ダニーロ・ペレス・カルテットなどで活動。中でもとりわけ、ポストプロダクションやサンプラー、シーケンスなどを駆使し新しいジャズのフィギュアを模索するNYのアルト奏者デヴィッド・ビニーとの共演や共同作業はマッキャスリンの作曲法に大きな影響を与えることとなった。モンダーのギターにも溜飲を下げる2009年の『Declaration』では、中南米音楽とジャズのマリアージュが、ビニーとデイヴ・ダグラスがプロデュースし、ジュリアナ、リンドナー、ルフェーヴルの最強カルテットが出揃った2012年の『Casting For Gravity』では、ボーズ・オブ・カナダの「Alpha and Omega」カヴァーに象徴されるジャズとエレクトロの有機的な融合が成されている。
1966年米カリフォルニア州サンタ・クルーズ出身のテナーサックス奏者。高校卒業後にバークリー音楽院に進学。ゲイリー・バートン、ジョージ・ガゾーンらに師事する。1991年NYに移住後は、エディ・ゴメスのバンドに参加、またゴメスの紹介でマイケル・ブレッカーの後任としてステップス・アヘッドに加入。ほか、ギル・エヴァンス・オーケストラ、マリア・シュナイダー・ジャズ・オーケストラ、ミンガス・ビックバンド、ダニーロ・ペレス・カルテットなどで活動。中でもとりわけ、ポストプロダクションやサンプラー、シーケンスなどを駆使し新しいジャズのフィギュアを模索するNYのアルト奏者デヴィッド・ビニーとの共演や共同作業はマッキャスリンの作曲法に大きな影響を与えることとなった。モンダーのギターにも溜飲を下げる2009年の『Declaration』では、中南米音楽とジャズのマリアージュが、ビニーとデイヴ・ダグラスがプロデュースし、ジュリアナ、リンドナー、ルフェーヴルの最強カルテットが出揃った2012年の『Casting For Gravity』では、ボーズ・オブ・カナダの「Alpha and Omega」カヴァーに象徴されるジャズとエレクトロの有機的な融合が成されている。
 『Fast Future』 (2015)
『Fast Future』 (2015) ”ヘッズごころ”を持ち合わせるジャズ・リスナーから絶大な支持を集めた前作『Casting For Gravity』同様、ジェイソン・リンドナー(p)、ティム・ ルフェーヴル(b)、マーク・ジュリアナ(ds)の鉄壁のカルテット+@で贈るネクストジャズの本丸フィギュア。エイフェックス・ツイン「54 Cymru Beats」、アンチコンのバス「No Eye」の仰天ジャズ解釈など、様々なエレメンツを様々な角度から果敢にクロスしながら再びジャズとエレクトロのインターゲートを試みた真のコンテンポラリー・ミュージック。
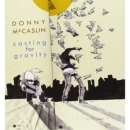 『Casting For Gravity』 (2012)
『Casting For Gravity』 (2012) デヴィッド・ビニーとデイヴ・ダグラスによるプロデュース、ジュリアナ、リンドナー、ルフェーヴルの最強布陣でおくる、マッキャスリンのエレクトロ×ジャズ融合志向が初めて全開となった2012年のアルバム。ボーズ・オブ・カナダの「Alpha and Omega」カヴァーやパット・メセニー・グループ的な「Praia Grande」など、ソリッドでメカニカルなバックトラックとマッキャスリンの多彩なアプローチのブロウとが有機的に絡み合って成立する、新しい時代のジャズのアイデンティティ。
 Enrico Pieranunzi『Proximity』 (2015)
Enrico Pieranunzi『Proximity』 (2015) 近年、スコット・コリー(b)、アントニオ・サンチェス(ds)とのニュートリオで、またフェデリコ・カサグランデとのデュオ作品などで攻め続ける欧州ジャズピアノの王将エンリコ・ピエラヌンツィ。CAM JAZZ新作は、ダニー・マッキャスリン、ラルフ・アレッシ(tp,cor,flh)、マット・ペンマン(b)という現代NYシーンの主役たちを擁する驚愕のドラムレス”アメリカン・カルテット”で挑んだ意欲作。
 Florian Weber
Florian Weber『Criss Cross: Exploring The Music Of Monk & Bill Evans』 (2016)
こちらもマッキャスリンのサイド参加作。ドイツEnjaの看板ピアニスト、フローリアン・ウェバーの最新リーダーアルバム。マッキャスリンに、先鋭的なリーダー作で知られる俊英ドラマー、ダン・ワイスとのサックス・トリオで吹き込んだセロニアス・モンク&ビル・エヴァンス集。
情報筋によれば、ボウイはこの後にもう1枚アルバムを作る予定があったのだとか。それが、『★』を踏襲するような、「ジャズ」というワードを持ち出して語り得るものかどうか定かではありませんが、花めくジャズメンとのコラボレーションによる「Sue」という傑曲を起点にして、湧き出るアイデアと制作意欲にまみれ勇み立つボウイの幻影、これは永遠のものとしてファンの脳裏に刻み込まれていくことでしょう。
関連記事
 JAZZ THE NEW CHAPTER 柳樂光隆が選んだ2015年の10枚。
JAZZ THE NEW CHAPTER 柳樂光隆が選んだ2015年の10枚。
ローチケHMVジャズ年間ランキング2015 【特別編】。こちらでは、「JAZZ THE NEW CHAPTER」監修でおなじみジャズ評論家の柳樂光隆さんに、2015年の私的ベスト10枚を選んでいただきました。