Monday, November 5th 2012
 60年代Decca/Abkco期とThe Rolling Stones Records設立の70年代以降の楽曲をカバー。デビューから現在までの全キャリアから厳選された50〜80曲を収録したローリング・ストーンズの新ベスト・アルバム『GRRR! Rolling Stones Greatest Hits』が登場!! 10月スタートのフジテレビ系月9ドラマ『PRICELESS』(主演:木村拓哉)の主題歌に決定した「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」をはじめとする数々のシングル・ヒットはもちろん、アルバムに収録された名曲、人気曲、重要なステージ・レパートリーも網羅。さらに約7年ぶりとなる新曲2曲の収録も決定! 今年8月、パリのスタジオに4人が集まってレコーディングされたもので、タイトルは「ドゥーム・アンド・グルーム」と「ワン・ラスト・ショット」。 ベストに先がけて、ストーンズ最初期の姿を捉えたドキュメンタリー・フィルム『チャーリー・イズ・マイ・ダーリン』も公式パッケージ化。さらに同時期には、「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」の冒頭歌詞をタイトルに冠したマーティン・スコセッシ制作・総指揮によるドキュメンタリー映画『クロスファイアー・ハリケーン』も公開予定。転石党の長く辛い冬は終わった。おたのしみはこれからだ!
[5CD+7"EP] *国内盤はSHM-CD仕様で5SHM-CD+7"EP |
 |
2012年10月18日「クロスファイヤー・ハリケーン」 ロンドン・ワールド・プレミアにて 撮影:有賀幹夫
|
 英国での10枚目のシングル。3作目の全英・全米ナンバーワン・ヒット。ブライアン・ジョーンズが様々な楽器を使い始めた頃の楽曲で、このオリエンタルなムード漂う楽曲には、ビートルズでもお馴染みのインド楽器シタールで彩りを添えている。
英国での10枚目のシングル。3作目の全英・全米ナンバーワン・ヒット。ブライアン・ジョーンズが様々な楽器を使い始めた頃の楽曲で、このオリエンタルなムード漂う楽曲には、ビートルズでもお馴染みのインド楽器シタールで彩りを添えている。
 from 『Aftermath』 (US)
from 『Aftermath』 (US)1965年発表。米国での4枚目となるアルバム。イアン・スチュアートをはじめ、ジャック・ニッチェらが参加し、初の全米1位を記録した。「ラスト・タイム」、「サティスファクション」などを収録している。
光陰矢の如し感は意外と後を引く
 from
fromFeelies 『Crazy Rhythms』 (1980)
ウィーザーやチャットモンチーのジャケット・アートワークに引用されたことで若衆にもいくらか”見覚えのある”USインディの雄フィーリーズ、その1stアルバムから。ポストパンク的でありギターポップ的であり、性急にしてユルふわなキメラ性がカレッジ・シーンを中心に大うけ。ここでは、ビートルズの「Everybody's Got Something To Hide」に気を取られがちになるが、「黒くぬれ!」の光陰矢の如し感は意外と後を引く。刹那の甘酸っぱさがスッと身体を通り抜けた。グレン・マーサーのギターとアントン・フィアの太鼓との隙間に、唯一黒くぬり潰されていない部分がありそうだが。
「しゃれたカフェなど行きたくねえ」
 from
fromRCサクセション 『カバーズ』 (1988)
「しゃれたカフェなど行きたくねえ」という素晴らしいパンチライン。カラフルな衣装を纏った清志郎のドぎついモノクロニズムと喧嘩ごしのニヒリズムに溜飲を下げる。「ブっ飛んでいたい!」と丁重に恫喝する冨士夫ちゃんもひょうきんなら、「イモなドラマは観たくもねえ」と生真面目に唄う三浦友和もファニー。ユラメクちあきまゆみを含むトリニティが、キヨシに不気味にハッパをかけた。
 シングル「夜をぶっ飛ばせ」のB面曲ながら、米国では歌詞が問題視されたA面に変わって1位を獲得。ストーンズのポップ期を代表するメロディアスなバラード。流麗なフルートはブライアンによるもの。
シングル「夜をぶっ飛ばせ」のB面曲ながら、米国では歌詞が問題視されたA面に変わって1位を獲得。ストーンズのポップ期を代表するメロディアスなバラード。流麗なフルートはブライアンによるもの。
from 『Flowers』
 1967年発表。当時のアメリカのフラワー・ムーヴメントにヒントを得て企画したと言われる米国編集アルバム。発表当時、英国での未発表は3曲ながら、米国におけるそれは、「ルビー・チューズデイ」、「夜をぶっとばせ」など実に7曲を数えた。
1967年発表。当時のアメリカのフラワー・ムーヴメントにヒントを得て企画したと言われる米国編集アルバム。発表当時、英国での未発表は3曲ながら、米国におけるそれは、「ルビー・チューズデイ」、「夜をぶっとばせ」など実に7曲を数えた。
 1967年発表。当時のアメリカのフラワー・ムーヴメントにヒントを得て企画したと言われる米国編集アルバム。発表当時、英国での未発表は3曲ながら、米国におけるそれは、「ルビー・チューズデイ」、「夜をぶっとばせ」など実に7曲を数えた。
1967年発表。当時のアメリカのフラワー・ムーヴメントにヒントを得て企画したと言われる米国編集アルバム。発表当時、英国での未発表は3曲ながら、米国におけるそれは、「ルビー・チューズデイ」、「夜をぶっとばせ」など実に7曲を数えた。
清志郎が唄えばストーンズもへったくれもない
 from
from 忌野清志郎 & レザー・シャープ
『Happy Heads』
(1987)
もういっぱつ清志郎。イアン・デューリーのバックバンド、ブロックヘッズのメンバーを中心に構成されたレザー・シャープとの初のソロ・アルバム・ツアー(@中野サンプラザ)実況録音盤から。パブロック・シーンの名士たちが下支えするサウンドは、その名のとおりシャープでキレキレ。「ルビー・チューズデイ」は珍しく原曲英詞のままだが、清志郎が唄えばもはやストーンズもへったくれもない。翳りあるチューダー調が国分寺のロックな火曜日に溶けてゆく。
 英国での12枚目のシングル。米国では歌詞が検閲にひっかかり、「エド・サリバン・ショー」に出演した際には“The Night”を“Sometime”に変えて歌ったことでも有名。
英国での12枚目のシングル。米国では歌詞が検閲にひっかかり、「エド・サリバン・ショー」に出演した際には“The Night”を“Sometime”に変えて歌ったことでも有名。
from 『Flowers』
 1967年発表。当時のアメリカのフラワー・ムーヴメントにヒントを得て企画したと言われる米国編集アルバム。発表当時、英国での未発表は3曲ながら、米国におけるそれは、「ルビー・チューズデイ」、「夜をぶっとばせ」など実に7曲を数えた。
1967年発表。当時のアメリカのフラワー・ムーヴメントにヒントを得て企画したと言われる米国編集アルバム。発表当時、英国での未発表は3曲ながら、米国におけるそれは、「ルビー・チューズデイ」、「夜をぶっとばせ」など実に7曲を数えた。
 1967年発表。当時のアメリカのフラワー・ムーヴメントにヒントを得て企画したと言われる米国編集アルバム。発表当時、英国での未発表は3曲ながら、米国におけるそれは、「ルビー・チューズデイ」、「夜をぶっとばせ」など実に7曲を数えた。
1967年発表。当時のアメリカのフラワー・ムーヴメントにヒントを得て企画したと言われる米国編集アルバム。発表当時、英国での未発表は3曲ながら、米国におけるそれは、「ルビー・チューズデイ」、「夜をぶっとばせ」など実に7曲を数えた。
我々にはオックスの恍惚版がある
 from
from オックス 『ヴィンテージ・コレクション』
(2005)
GS全盛期に彗星の如く現れ、たちまちタイガース、テンプターズに次ぐ人気グループになったオックス。楽器を壊す過激なステージや、オルガンの赤松愛の失神パフォーマンスで有名になったが、音楽性自体は極めて高く、ストーンズ、ビートルズほか、ザ・フー、スライなどライヴのカヴァー・レパートリーにも好事家を唸らせるものがあった。「夜をぶっとばせ」では、”君がいなけりゃ世界は暗い”調の湿り気ある日本語詞とカタカナ英語が違和感たっぷりに絡み合い、思わずもんどり打つこと必至。がしかし、こういう初期衝動に任せた洋楽カヴァーこそが今の日本には必要だ。アフロ・アメリカンにはマディ・ウォーターズの粘泥版がある。ならば我々にはオックスの恍惚版がある。
 英国ではアルバム『アフターマス』のオープニングを飾ったフォーク・ロック。米国ではアルバムには収録されず、8枚目のシングルとしてリリースされ8位を記録した。シタールはブライアン・ジョーンズ。
英国ではアルバム『アフターマス』のオープニングを飾ったフォーク・ロック。米国ではアルバムには収録されず、8枚目のシングルとしてリリースされ8位を記録した。シタールはブライアン・ジョーンズ。
小品ながら宴もたけなわのハイライト
 from
from Tesla 『Five Man Accoustic Jam』
(1990)
「GNRペイシェンス症候群」が蔓延した80年代末のハードロック・シーン。つまり、のちのMTVアンプラグドよろしくのアコースティック・スタイルで一席ぶつのが大流行したということ。エアロ、シンデレラ、ブラック・クロウズらのようなルーツ愛好型のブルース・ベースHRバンドに分類されるテスラも例に漏れずこの流れにライド。結果は百点満点のアコースティック・ライヴ・アルバムが誕生した。ファイブ・マン・エレクトリカル・バンド、グレイトフル・デッド、CCR、ビートルズ・ナンバーに交じって披露される「マザーズ・リトル・ヘルパー」は、小品ながら宴もたけなわのハイライトとなっている。
 英国ではアルバム『アフターマス』、米国では『フラワーズ』に収録されたポップな作品。マリンバはブライアン。同年にシングル・リリースされたクリス・ファーロウによるカヴァー・ヴァージョンが全英1位を記録した。
英国ではアルバム『アフターマス』、米国では『フラワーズ』に収録されたポップな作品。マリンバはブライアン。同年にシングル・リリースされたクリス・ファーロウによるカヴァー・ヴァージョンが全英1位を記録した。
王侯貴族のエゴと知性と悲しみを想起
 from
from Manic Street Preachers
『Lipstick Traces』
(2003)
そもそもは、仰々しいストリングスが入るクリス・ファーロウのカヴァー版からイギリスで火が付いた「アウト・オブ・タイム」。ゆえにそのストリングスの導入具合が出来の良し悪しを分かつ。ラモーンズのヴァージョンも木琴導入の本家に準拠していて悪くはないが、やはりここはレペゼン大英帝国、王侯貴族のエゴと知性と悲しみを想起させるマニックスのヴァージョンに軍配。ストリングスが生命線になっていることをよくぞここまで心得たもの。天晴れだ。シングルB面曲やレアリティに加え、彼らの節操ない趣向を伺わせるカヴァー曲などからなる裏ベスト盤から。
 シングル「この世界に愛を」のB面に収録されたカラフルなポップ・ナンバーで、米国ではA面を上回るヒットとなった。キースは1972年に生まれた自分の娘に「ダンデライオン」と名付けている(後に改名)。
シングル「この世界に愛を」のB面に収録されたカラフルなポップ・ナンバーで、米国ではA面を上回るヒットとなった。キースは1972年に生まれた自分の娘に「ダンデライオン」と名付けている(後に改名)。
from 『Through The Past Darkly (Big Hits Vol.2)』
 1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
 1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
ちょっぴりダルなメロウ歌唱で
 from
from Miranda Lee Richards
『Herethereafter』
(2002)
ゼロ年代を代表するフォーキー&メロウ歌姫ミランダ・リー・リチャーズのデビュー・アルバムから。シスコ出身ならではの”フラワー感”が、60年代半ば〜後半のストーンズにあったサイケなポップ・フィーリングと見事にマッチ。『サタニック・マジェスティーズ』へのブリッジ役を務めるこの曲の妙味を、装飾を含む緻密な音のレイヤーやミランダのちょっぴりダルなメロウ歌唱で再現している。
 アルバム『サタニック・マジェスティーズ』に収録されたサイケデリック・ポップの名曲で、ニッキー・ホプキンスが奏でるピアノが美しい。ストリングスのアレンジは、ジョン・ポール・ジョーンズ。
アルバム『サタニック・マジェスティーズ』に収録されたサイケデリック・ポップの名曲で、ニッキー・ホプキンスが奏でるピアノが美しい。ストリングスのアレンジは、ジョン・ポール・ジョーンズ。
from 『Their Satanic Majesties Request』
 1967年発表。ストーンズ自身が初めてプロデュースした第1弾。ビートルズの『サージェント・ペッパーズ〜』やサイケデリック・サウンドの影響を受けており、当時賛否両論を巻き起こした。
1967年発表。ストーンズ自身が初めてプロデュースした第1弾。ビートルズの『サージェント・ペッパーズ〜』やサイケデリック・サウンドの影響を受けており、当時賛否両論を巻き起こした。
 1967年発表。ストーンズ自身が初めてプロデュースした第1弾。ビートルズの『サージェント・ペッパーズ〜』やサイケデリック・サウンドの影響を受けており、当時賛否両論を巻き起こした。
1967年発表。ストーンズ自身が初めてプロデュースした第1弾。ビートルズの『サージェント・ペッパーズ〜』やサイケデリック・サウンドの影響を受けており、当時賛否両論を巻き起こした。
最高級の安心感が詰まっている
 from
from コトリンゴ 『Picnic album 2』
(2011)
本来であれば、GSサイケの最高峰ビーバーズのヴァージョンをチョイスしたかったのだが、ふと耳にしたコトリンゴ版があまりにも愛くるしくて (フレッシュな顔ぶれにもしたかったし)、こちらを採用。CM、映画音楽作曲家としても活躍するだけあって、楽曲のポイントをおさえるのが非常に上手い。原曲のイメージを損なうことなく薄めの味付けで料理された「シーズ・ア・レインボウ」には、 いくらあっても邪魔にならない最高級の安心感が詰まっている。

 寺田正典さんの場合
寺田正典さんの場合
ストーンズ・ナンバーのカヴァーには、全米32位まで上昇した(5)のような例外を除くと商業的に成功したものは少ない。だが、敢えてPV版の方でカヴァーした(3)や、1973年1月22日ハワイ公演(1stショウ)での演奏のコピーを試みた(6)、未発表曲(後に『メイン・ストリートのならず者』豪華版で発表)を勝手にカヴァーしてしまった(9)のような「マニアの異常な愛情」型に出会えるのが痛快! 元または現メンバーが加わる豪華過ぎるカヴァーも結構あって、(8)はミック・テイラーのスライド名演入り。愛情より友情の(4)はシングルB面だったこちらの方で選出。歌い出し部分に加えられたアド9thコードに心奪われる(2)、「サンバのつもり」アレンジのこの曲をルベーン・ブラデスの歌入りの強力なラテン・アレンジで聴かせる(7)などは、原曲が潜在的に持っていた可能性を引き出した例。ヘヴィなカントリー・ロックの(1)は、オーティス・レディング版「サティスファクション」以来のハマり方でカッコ良過ぎ。(10)はメドレーだが今聴いても笑ってしまうほど似てる箇所多数! このシングル・ヴァージョンと、オランダ版12インチ、米版12インチで少しずつ編集が違うので聴いてみて!!
寺田正典(レコード・コレクターズ 元編集長)
寺田さんのストーンズ・カヴァー ベスト 10
- (1) Dead Flowers / Steve Earle
- (2) Wild Horses / Summerhill
- (3) Jumpin' Jack Flash / Flamin' Groovies
- (4) Under My Thumb / The Who
- (5) Tumbling Dice / Linda Rondstadt
- (6) It's All Over Now / スクリュー・バンカーズ
- (7) Sympathy For The Devil / Horacio El Negro Hernandez & Bobby Ameen
- (8) Love In Vain / Stephen Dale Petit
- (9) So Divine (Alladin Story) / Death In Vegas
- (10) The Greatest Rock'N Roll Band In The World / Stars On 45
 英国での14枚目のシングル。全英1位。押しも押されもせぬストーンズの代表曲で、キースのギター・リフを軸とするラフでルーズな曲調は、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”の礎となった。
英国での14枚目のシングル。全英1位。押しも押されもせぬストーンズの代表曲で、キースのギター・リフを軸とするラフでルーズな曲調は、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”の礎となった。
from 『Through The Past Darkly (Big Hits Vol.2)』
 1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
 1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
本家に肉迫しそうな”クロスファイヤー・ハリケーン”ぶり
 from
fromJohnny Winter 『Live』 (1971)
「JJF」カヴァーと言えばコレっきゃないだろという超本命曲。ストーンズとジョニーの交流録については、「I'm Yours and I'm Hers(I'm Yours She's Mine)」、「Silver Train」、「Stray Cat Blues」などを題材に諸々講釈たれたいところだが自粛しておくとして。2011年奇跡の初来日〜翌年の再来日公演では、ブルースロックおやじたちもきっと涎を垂らしながら待ち構えていた必殺の「JJF」・・・その夢は叶わなかったものの、アレサ・フランクリンやレオン・ラッセルのヴァージョンにはない、本家に肉迫しそうな”クロスファイヤー・ハリケーン”ぶりはジョニーの永遠の代名詞のひとつとして語り継がれていくことだろう。それこそが、カヴァーするという行為の中で自然発芽したオリジナリティに他ならない。
ボヤ騒ぎのようなグルーヴを産出してしまった埼玉ストーンズ
 from
fromテンプターズ 『オン・ステージ』 (1969)
テンプターズの荒ぶる魂と転石愛とが絨毯爆撃のようなガレージ・サウンドに乗ってヤンチャに横溢した銘演。理屈じゃない熱くほとばしる何かが「JJF」を別次元のモノへと昇華。「超絶技巧」という口説き文句が相場のこのギョーカイにおいて、あってはならないボヤ騒ぎのようなグルーヴを産出してしまった埼玉ストーンズ。銘演と怪気炎を上げたものの、やはり今でも賛否あるらしい・・・ただし間違いなくひとつ言えるのは、この感じにしっくりきた者とそうでない者とでは、その後の人生の歩みを大きく違えるということ。
 英国での15枚目にして、Decca/London時代のラスト・シングル。後にキースのトレードマークとなる5弦オープンGチューニングのリフを使った代表曲で、4作目の全英・全米No.1。
英国での15枚目にして、Decca/London時代のラスト・シングル。後にキースのトレードマークとなる5弦オープンGチューニングのリフを使った代表曲で、4作目の全英・全米No.1。
from 『Through The Past Darkly (Big Hits Vol.2)』
 1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
 1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
1969年発表。ストーンズを代表するシングル曲(アルバム未収録)を収めるデッカ期ベスト・アルバム第2弾。直前にグループを脱退した後、不慮の死を遂げたブライアン・ジョーンズに捧げられた。
決して俳優業の片手間で唄っているのではないという証
 from
from松田優作 『ハーデスト・ナイト・ライブ』 (1981)
苦みばしった形相で「酒場でぇ見つけたおんなぁ♪」と唄う優作にキュン。自前の男くさい日本語詞は、アニキと慕う原田芳雄同様、決して俳優業の片手間でブルースを唄っているのではないということの証。ハマの”自称”番長各位はシリコ玉を抜き取られた気分だ。バックは、竹田和夫(g)をはじめとしたクリエイションの面々とエディ藩(g)。もう二度と会うことのない、されど夢の中で何度でも愛し合うことができる、忘れじの女たち。ちなみに、小林克也率いるナンバーワン・バンドの「港の女」も、80年代の極東が誇る風俗の鑑的ナイス・カヴァー。優作版と双璧を成すため再CD化希望!
バンド・オブ・ジプシーズがもしカヴァーしていたらこんな感じに
 from
fromPrince 『The Undertaker』 [VHS/LD] (1995)
たしかこの映像盤は過去一度もDVD化がされていないと記憶する、殿下の1993年ペイズリ御苑でのリハーサル・セッション集。のちにイレギュラーな形で音源のみリリースされたかどうか定かではないが、記録としてはまずまず貴重な部類に入ると思われる。ジャンジャンバリバリ弾きまくる重戦車のようなヴァージョンで、バンド・オブ・ジプシーズがもしカヴァーしていたらこんな感じになっていたのかも知れない・・・世界で一、二を争う”過小評価ギタリスト”が自宅で燃え上がる。
[こちらの商品は現在お取り扱いしておりません]
 ストーンズが本格ロック・バンドとしての地位を固めた傑作アルバム『ベガーズ・バンケット』のオープニング曲。呪術的なパーカッション、クールなベースライン、ユニークなコーラス、鋭角なギターソロなど、妖しい魅力に溢れる絶品ナンバー。
ストーンズが本格ロック・バンドとしての地位を固めた傑作アルバム『ベガーズ・バンケット』のオープニング曲。呪術的なパーカッション、クールなベースライン、ユニークなコーラス、鋭角なギターソロなど、妖しい魅力に溢れる絶品ナンバー。
from 『Beggars Banquet』
 1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
 1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
桃井かおりが唄ってもサマになることが判明
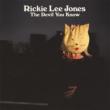 from
from Rickie Lee Jones 『Devil You Know』
(2012)
「悪魔を憐れむ歌」は、「サティスファクション」、「ギミー・シェルター」などと並んで今も昔も割り合いカヴァー頻度が多く、しっかり録音作品として残されている一曲と言えるだろうか。BS&T、ブライアン・フェリー、ガンズ、U2、ライバッハのヴァージョンは今や殿堂入り。そこに続く形で、アメリカン・クラーヴェ一派のオラシオ・ヘルナンデス、米ジャムバンドのワイドスプレッド・パニック、仏のマグレブ集団オルケストル・ナショナル・ ドゥ・バルベス、さらに日本からは布袋寅泰、クオシモードのヴァージョンが次々と産声を上げている。いずれもエクスタシー到達の甲乙付けがたいパフォーマンスだが、2012年にリリースされたリッキー・リーによる枯山水のようなヴァージョンが目から鱗。ベン・ハーパーをブレインに従えた永遠のアンニュイ女史、そのブルージーな観音姿を拝む。またこの結果、桃井かおりが唄ってもサマになるということが判明した。
 アコースティック楽器をメインにしながらも破壊的なサウンドが際立つ強烈なナンバーで、米国ではアルバム『べガーズ・バンケット』に約4ヶ月先行してシングル・リリース(別ヴァージョン)。英国では暴動を触発するとして見送られた。
アコースティック楽器をメインにしながらも破壊的なサウンドが際立つ強烈なナンバーで、米国ではアルバム『べガーズ・バンケット』に約4ヶ月先行してシングル・リリース(別ヴァージョン)。英国では暴動を触発するとして見送られた。
from 『Beggars Banquet』
 1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
 1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
妖美なサイケデリック感覚に闘争心も一旦マヒ
 from
from Lake Trout 『Not Them You』
(2005)
納得のいかない世の中、こちらも折りに触れよく採り上げられる一曲。原曲の持つデモ抗議・階級闘争コンセプトに因って、ブルーカラーを焚き付ける一揆〜フーリガン型の爆暴アレンジに落ち着く場合が多いのだが、ジャムバンド〜ポストロック系に属するレイク・トラウトのヴァージョンは少々ユニーク。所謂シューゲイザー的に加工された妖美なサイケデリック感覚に闘争心も一旦マヒする。何かが噛み合わない、どうもしっくりこない中にこそドラマがあるのだろう。全共闘世代とゆとり世代とが食卓を囲んだようなこの音風景には、奇妙にして日常よくある”ズレ”や”ギャップ”の趣深さが挿し込まれている。ロッド・スチュワート版以来の良質カヴァーと断言できよう。
 アルバム『ベガーズ・バンケット』のラストを飾る重厚なバラードで、冒頭のリード・ヴォーカルはキース・リチャーズ。後半の女性コーラスも絡む盛り上がりはゴスペルの雰囲気も漂わせる。
アルバム『ベガーズ・バンケット』のラストを飾る重厚なバラードで、冒頭のリード・ヴォーカルはキース・リチャーズ。後半の女性コーラスも絡む盛り上がりはゴスペルの雰囲気も漂わせる。
from 『Beggars Banquet』
 1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
 1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
1968年発表。ポップ〜サイケデリック期を経て、後にロックの代名詞ともなる“ストーンズ・サウンド”がここに完成。代表曲「悪魔を憐れむ歌」「ストリート・ファイティング・マン」他、米南部のルーツに根差したアーシーで粘っこい感性が全編を貫く。
しぶといコブシ回しに酒もすすむ
 from
from Bettye Lavette
『Interpretations: The British Rock Songbook』
(2010)
汗にまみれたストーンズ流の労働歌をベティ・ラヴェットがさらに塩辛く絶唱。北原ミレイ「石狩挽歌」とつなげて聴けばグーを握る手にもおのずと力がみなぎる。ロッド・スチュワートの”亜米利加たそがれ”の向こうを露骨に張ったかのような、出来すぎた”英吉利慕情”。ベテランのしぶといコブシ回しに酒もすすむ。「地の塩」は、「貧しくとも懸命に働くオレたちに乾杯」というリリックからレゲエ界隈でも人気が高く、現場のソウル・セグメントではニューオリンズR&Bダンディ、ジョニー・アダムスのヴァージョンが今も昔もファウンデーション。70年代には、ケイブルズ、ダンディ・リヴィングストン、最近ではリッチー・スティーヴンスなどにもカヴァーされている。
 アルバム『レット・イット・ブリード』収録曲で、キース・リチャーズが初めて単独でリード・ヴォーカルを取ったカントリー・ブルース。1969年6月に脱退、直後にこの世を去るブライアン・ジョーンズ最後の参加曲のひとつ。
アルバム『レット・イット・ブリード』収録曲で、キース・リチャーズが初めて単独でリード・ヴォーカルを取ったカントリー・ブルース。1969年6月に脱退、直後にこの世を去るブライアン・ジョーンズ最後の参加曲のひとつ。
from 『Let It Bleed』
 1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
 1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
夫君デレクも絶妙なスライド・アシスト
 from
from Susan Tedeschi 『Hope And Desire』
(2005年)
ご存じデレク・トラックスの姉さん女房、ハスキー&スモーキーなブルース語りで枯淡の境地を今日も往くスーザン・テデスキ。オーティス・レディング、キャンディ・ステイトン、ボブ・ディランらの隠れた名曲が並ぶ、そんなスーザンの審美眼も光るカヴァー・アルバムから。注目のストーンズ・カヴァーは、驚きのと言うべきか、腑に落ちたと言うべきか、キースの魂がデルタ辺りをあてどなく彷徨うカントリー・ブルース「ユー・ガット・ザ・シルヴァー」。夫君デレクも絶妙なスライド・アシストにて、おしどりエレジーにきっちり入眼。
 デッカ/ロンドン時代の最後を飾った『レット・イット・ブリード』のオープニング曲。イントロのギターとコーラス、そしてミックとメリー・クレイトンによるヴォーカルの絡みがデカダンな緊張感を生み出している。
デッカ/ロンドン時代の最後を飾った『レット・イット・ブリード』のオープニング曲。イントロのギターとコーラス、そしてミックとメリー・クレイトンによるヴォーカルの絡みがデカダンな緊張感を生み出している。
from 『Let It Bleed』
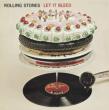 1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
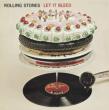 1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
両チャンネルから耳をつんざくエディ・ヘイゼルのギター
 from
fromRuth Copeland 『I Am What I Am』 (1971)
ざっくり言えば、Pファンク版ギミー・シェルター。Pコミュニティでは珍しいイギリスの白人女性シンガー、ルース・コープランドが、モデル級のすらっとした容姿からは想像も付かないほどヒステリックな激情をスピットさせる。マザーシップ前夜ゴリゴリ期の絶頂にあったファンカデリックが、伴奏というよりは扇動役のようなバッキングでおてんば娘の暴走に拍車を掛ける。中でも両チャンネルから耳をつんざくエディ・ヘイゼルのギターがすさまじく、跳ねまくるファンキーなカッティングと、デトロイト・マナーの轟音で饒舌に弾き倒すソロには、キース、ミック・テイラー当時の本家G組も相当怯んだに違いない。本作にはゴスペルデリカルな「プレイ・ウィズ・ファイヤー」カヴァーも収録。
かつてない大陸的なダンス衝動を生む
 from
fromAngelique Kidjo 『Djin Djin』 (2007)
メリー・クレイトン版が早や殿堂入りを果たしたのち、女史アクトによるギミー・シェルターは中々そのワールドレコードを更新できずにいたのだが、2007年に西アフリカ・ベナン出身のシンガー・ソングライター、アンジェリーク・キジョーの手によってそれは鮮やかに塗り替えられた。アフリカ音楽に、ファンク、ソウル、ブラジル、カリビアンなど様々な音楽を融合させながら昇華した、プリミティヴ・ポップと称されるグローバル様式のアレンジが、かつてない大陸的なダンス衝動を生む。ホーンセクションにはアンティバラス、さらにゲスト・シンガーとしてジョス・ストーンをフィーチャーと、甚だ抜かりのない一曲で踊ろう。
 アルバム『レット・イット・ブリード』に収録された長尺のブルース曲。ステージではインプロヴィゼーションを加えたスケールの大きな演奏が展開され、特に70年代前半から中盤にかけてハイライトとして人気を博した。
アルバム『レット・イット・ブリード』に収録された長尺のブルース曲。ステージではインプロヴィゼーションを加えたスケールの大きな演奏が展開され、特に70年代前半から中盤にかけてハイライトとして人気を博した。
from 『Let It Bleed』
 1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作のひとつに数えられる一枚。
1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作のひとつに数えられる一枚。
 1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作のひとつに数えられる一枚。
1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作のひとつに数えられる一枚。
重厚感たっぷりトリップ感少々の
 from
from V.A.
『In Search Of Space』
(1997)
60〜70年代のガレージ、アシッド、サイケ、プログレ系アクトのエクスペリメンタル・チューンから、Dr.ジョン、サンタナ、ジミヘン、ジョニー・ウィンター、アリス・クーパーらの隠れた小宇宙的名曲までを取り揃えた3枚組コンピレーション。ここに、英国ハードサイケの首領ミック・ファーレン率いるカルト・バンド、ピンク・フェアリーズが、重厚感たっぷりトリップ感少々のとっぽい「ミッドナイト・ランブラー」にて参戦。楽曲の性質上さほど頻繁に採り上げられることのない曲だが、こうして世に出回っているものの中には聴き応えのあるヴァージョンも少なくない。先頃来日公演を果たした伝説のパブロック・バンド、ダックス・デラックスのカヴァー(ライヴ音源)も是非CD化してほしいもの。
 「ホンキー・トンク・ウィメン」のB面としてリリースの後、アルバム『レット・イット・ブリード』に収録された、ロンドン・バッハ合唱団のコーラスとアル・クーパーのフレンチ・ホルンに導かれる壮大な1曲。渾然一体となった後半の盛り上がりは圧巻。
「ホンキー・トンク・ウィメン」のB面としてリリースの後、アルバム『レット・イット・ブリード』に収録された、ロンドン・バッハ合唱団のコーラスとアル・クーパーのフレンチ・ホルンに導かれる壮大な1曲。渾然一体となった後半の盛り上がりは圧巻。
from 『Let It Bleed』
 1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
 1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
1969年発表。ブライアン・ジョーンズ脱退、ミック・テイラー参加という過渡期にありながらも、ストーンズがそのクリエイティヴィティの頂点を見せつけた、60年代デッカ期の最後を飾るスタジオ作にして、最高傑作の一つに数えられる1枚。
ダンサンブルなディスコ大会へと突入
 from
from Aretha Franklin
『Love All The Hurt Away』
(1981)
アレサの転石カヴァーでは、「サティスファクション」、「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」に次ぐ”三番手”として巷ではおなじみかもしれないが、脇固めのメンツ及び絶妙なアレンジを踏まえて聴くと興奮度はさらに高まる、実に奥深い大人のための一席。スティーヴ・ルカサー(g)、ジェフ・ポーカロ(ds)、デヴィッド・ペイチ(p)、グレッグ・フィリンゲインズ(key)といったTOTO組に、マーカス・ミラー(b)、デヴィッド・ウィリアムズ(g)らブラコン・シーンを牽引する若獅子たち、80年代の女王をバックアップするにはこれ以上ない布陣で臨んだ「無情の世界」。本家版に負けじとブ厚いゴスペル・コーラスでムードを高めるイントロからすわ一転、期待を裏切ることなくタイトでダンサンブルなディスコ大会へと突入する。ブラック・ミュージック・サイドからの転石リスペクトは、やはりこのぐらいバネが効いていた方が快哉だ。





 「チャーリー・イズ・マイ・ダーリン」が公式パッケージ化!
「チャーリー・イズ・マイ・ダーリン」が公式パッケージ化!
 英国での7枚目のシングル。キース・リチャーズによるファズを駆使したギター・リフがあまりにも有名なストーンズを代表する1曲で、全英はもちろん、全米でも初の1位を記録。1997-98ツアーでオープニングに採用。
英国での7枚目のシングル。キース・リチャーズによるファズを駆使したギター・リフがあまりにも有名なストーンズを代表する1曲で、全英はもちろん、全米でも初の1位を記録。1997-98ツアーでオープニングに採用。

 from
from from
from 6枚目にして、英国では初めてシングルA面に採用された「ジャガー/リチャード」のオリジナル作。全英1位。流れるような単音のギター・リフはブライアン・ジョーンズによるもの。
6枚目にして、英国では初めてシングルA面に採用された「ジャガー/リチャード」のオリジナル作。全英1位。流れるような単音のギター・リフはブライアン・ジョーンズによるもの。

 from
from  米国では6枚目のシングルとして発表、英国では遅れてアルバム『アウト・オブ・アワ・ヘッズ』に収録された、ジャガー/リチャーズ最初期の傑作と名高いソウルフルなバラード。
米国では6枚目のシングルとして発表、英国では遅れてアルバム『アウト・オブ・アワ・ヘッズ』に収録された、ジャガー/リチャーズ最初期の傑作と名高いソウルフルなバラード。
 from
from  元々はマリアンヌ・フェイスフルのデビュー曲として提供された上品なフォーク・ナンバー。米国では10枚目のシングルとしてリリースされ6位を記録。英国では「19回目の神経衰弱」のB面に収録された。
元々はマリアンヌ・フェイスフルのデビュー曲として提供された上品なフォーク・ナンバー。米国では10枚目のシングルとしてリリースされ6位を記録。英国では「19回目の神経衰弱」のB面に収録された。

 from
from  英国での8枚目のシングルにして、連続の全英・全米1位を記録したストーンズ初期の代表曲の1つ。R&Bの名曲「ルイ・ルイ」のコード進行を利用しながら、よりアグレッシヴなリズムで聴かせる。
英国での8枚目のシングルにして、連続の全英・全米1位を記録したストーンズ初期の代表曲の1つ。R&Bの名曲「ルイ・ルイ」のコード進行を利用しながら、よりアグレッシヴなリズムで聴かせる。
 from
from  英国での9枚目のシングルとしてリリースされたストレートなロックンロール・ナンバ−。ブライアンが奏でるギター・リフは、ボ・ディドリー「ディドリー・ダディ」へのオマージュ。
英国での9枚目のシングルとしてリリースされたストレートなロックンロール・ナンバ−。ブライアンが奏でるギター・リフは、ボ・ディドリー「ディドリー・ダディ」へのオマージュ。

 from
from  アルバム『アフターマス』収録曲。ブライアン・ジョーンズによるマリンバと、ビル・ワイマンによるファズを通したベースが雰囲気を作る人気曲で、1981-82年ツアーではオープニングに抜擢された。
アルバム『アフターマス』収録曲。ブライアン・ジョーンズによるマリンバと、ビル・ワイマンによるファズを通したベースが雰囲気を作る人気曲で、1981-82年ツアーではオープニングに抜擢された。

 from
from 