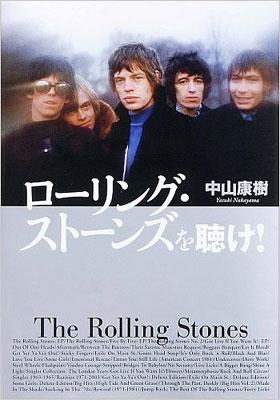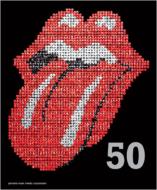「ローリング・ストーンズを聴け!」 中山康樹さんに訊く [前編]
2012年7月14日 (土)

『マイルスを聴け!』など唯我独尊の帝王論でもおなじみ、中山康樹さんの最新著書は、結成50周年を迎えたローリング・ストーンズ、その祝砲とも言うべき満を持しての初論評。
半世紀到達のメモリアル・イヤー、待てど暮らせど”本隊動かず”の憂き状況ながら、先頃リリースされたマディ・ウォーターズとの ”フーチークーチー蔵出し映像” 御宝箱や、大手飲料メーカー主導によるド派手な”バーコラボ”など、本国に負けないストーンズ愛でお祭りムードを扇動する我が国ニッポン。そこに続けとばかりに登場する本著「ローリング・ストーンズを聴け!」は、かつてない視点と饒舌さによって記された新しいテキストブックになることは間違いないでしょう。2年ぶりのHMV ONLINEご登場となる中山康樹さんに、”新説”たっぷりのローリング・ストーンズ論、伺ってまいりました。
インタビュー/文・構成:小浜文晶
おそらくブルースから最初に飛び出したのは
ブライアン・ジョーンズだったんじゃないかって思うんですよ。
-- 本日は宜しくお願いします。7月20日に発売される「ローリング・ストーンズを聴け!」は、中山さんにとって初のローリング・ストーンズ論評になるのですが、今回執筆にあたる動機としては、「60年代の作品が世界的な統一規格としてカタログ化されていない」ことに対する歯痒さというか、ある種の問題提起がやっぱり一番大きかったところですか?
勿論、それもひとつの要素ですよね。つまり、アメリカ盤が“定番”と呼ばれて久しくなったことに対して、周りが何も言いなさすぎるんじゃないかなと(笑)。音楽雑誌にしても評論家にしても。ただし、そこに物申せばすぐに正常な形に戻るという話ではなくて、やっぱりそれを言い続けないことには...
-- ABKCO(アブコ)が動いてくれないと。
そうなんですよ。だからその部分で、最初のボタンが掛け違いなくしっかり入っていないと、次の時代を重ねていっても、何かを語ったり説明しようとするときに全部がチグハグになってしまうんですよね。そこにストーンズが、特に日本で “広がらない”原因があるのかなと。

-- 例えば、同じファースト・アルバムでも、イギリス盤とアメリカ盤とでは収録内容、特にアタマの曲順が決定的に違うわけですし。「ルート66」と「ノット・フェイド・アウェイ」、どちらを最初に聴くかでその印象はかなり異なってきますからね。
仮にそういうケースが他のバンドであったとしても、ストーンズほどのバンドにそうしたズレや混乱があるのはちょっとありえないと言うか。キャピトル盤を土台にしたビートルズのカタログが今だに“定番”として平然と出回っているようなものですから(笑)。そういう意味では、イギリス盤、アメリカ盤両方出るっていうのがひょっとしたら理想なのかもしれませんけど。で、ストーンズの場合、一時的にそういう状況になったりもするんですけど、でも結局は、オリジナルであるイギリス盤が隅っこに追いやられてしまう。
特にストーンズは歴史が長い、しかも現役だから、片付けていかなきゃいけない問題が多々あって、その原点がそこだと思うんですよ。だから、いつまでたっても彼らは、「ブルースバンド」、「オルタモントの悲劇」、「夜をぶっとばせコノヤロー!」みたいな一面でしか語られていないわけで(笑)。それはやっぱり、先ほど言った土台が揺らいでいるというか、むしろ全然出来ていないからだと思うんですよ。
それこそ近い将来、イギリス盤が普通に手に入るようになって、アメリカ盤の方が二次的なものになっていかないと、ストーンズの“広がり”という点においては、そこが相当なネックになってくると思うんですよ。書き手もそうだし、読み手や聴き手もそうなんですけど、アメリカ盤だけ並べて見てると、何と言うか...本当にワケが分からない(笑)。だから、イギリス盤を足蹴にして、アメリカ盤が完全にスタンダードになっていることを考えると、よくここまで色々な人が語ってこれたなと不思議に思えてきて(笑)。本にも書きましたけど、ビートルズ以上にファン想いで、シングルと収録曲をダブらせないようにしていたにも関わらず、あるアルバムではいきなり「サティスファクション」が入っていたりと...ビートルズのアメリカ盤以上に“イビツ”なんですよ(笑)。
ビートルズのアメリカ盤っていうのは、曲を抜いたり足したりと、割と単純な入れ替えではあったんですけど、ストーンズの場合はもうちょっと複雑というか。
-- 意味不明というか。
(笑)そこが全てをおかしくしている原因なのかなと。

 1964年5月30日発売。こちらは、シングルヒットを記録した「ノット・フェイド・アウェイ」が冒頭に据えられたアメリカ盤。ジャケットには、彼らが何者かであることを知る、所謂プロモーション文句としてのタイトル『England's Newest Hit Makers』、そしてグループ名がデカデカと記され、オリジナル盤の”プレーン”な仕様とは大きくムードを違える。
1964年5月30日発売。こちらは、シングルヒットを記録した「ノット・フェイド・アウェイ」が冒頭に据えられたアメリカ盤。ジャケットには、彼らが何者かであることを知る、所謂プロモーション文句としてのタイトル『England's Newest Hit Makers』、そしてグループ名がデカデカと記され、オリジナル盤の”プレーン”な仕様とは大きくムードを違える。

-- 当時のマネージャー、アンドリュー・ルーグ・オールダムの過多なプロモーション・コンセプトも原因のひとつになっているような気はしますね。結果的にディスコグラフィとしては整理しづらいものになっていますから。
当時としてはあまりにもしっかり組み立てすぎたのかもしれませんよね。
-- ちなみに、中山さんご自身が初めて買われた“ファースト・アルバム”は何盤だったんですか?
キングの日本盤ですね。所謂ロンドン・レーベルの。だから、イギリス盤とはまた異なる曲順。その次に買ったのがアメリカ盤で、イギリス盤は一番最後。真逆なんですよね。CD化されて、その順番が入れ替わるのかなと期待していたんですけど、またアメリカ盤から発売されたりして(笑)。
土台作りという意味合いにおいても、60年代のストーンズが語られる上で一番大切な初期のカタログがそういう具合ですから、いきなり『ベガーズ・バンケット』から語り始めなきゃいけないような状況でもあるんですね(笑)。だから、『ベガーズ・バンケット』より以前は“別のグループ”というか(笑)、そういう感覚ですよね。僕らの世代はブライアン・ジョーンズの時代を結果的にでも一番聴いていたから、ごく初期の作品に馴染みのあった人たちにとっては、やっぱり『ベガーズ・バンケット』から話を始めるっていうことにはかなり違和感があるんですよ。
 ビートルズの初代マネージャー、ブライアン・エプスタインの下で宣伝係を担当し、その後自らがスカウトしたストーンズのマネージャーに就任。レコード・プロデューサー、パブリシテイを担当。ビートルズとは正反対の「不良っぽさ」を売りにし、それが見事的中した”仕掛屋”ぶりはよく知られるところ。プロモーション戦略以外にも、オリジナル・メンバーのイアン・スチュワートを「ルックスがバンドにフィットしていない」という理由でクビにしたり、ミック・ジャガーにリーダーとしての実権を握るよう示唆したりと、ほぼ全権に亘って強固なイニシアチヴを握っていた。1966年頃にマネージメントをアラン・クラインに譲り渡すことを決意。1965年にはすでにイミディエイト・レコードを設立し、スモール・フェイセズのマネージメントを行なっていた。
ビートルズの初代マネージャー、ブライアン・エプスタインの下で宣伝係を担当し、その後自らがスカウトしたストーンズのマネージャーに就任。レコード・プロデューサー、パブリシテイを担当。ビートルズとは正反対の「不良っぽさ」を売りにし、それが見事的中した”仕掛屋”ぶりはよく知られるところ。プロモーション戦略以外にも、オリジナル・メンバーのイアン・スチュワートを「ルックスがバンドにフィットしていない」という理由でクビにしたり、ミック・ジャガーにリーダーとしての実権を握るよう示唆したりと、ほぼ全権に亘って強固なイニシアチヴを握っていた。1966年頃にマネージメントをアラン・クラインに譲り渡すことを決意。1965年にはすでにイミディエイト・レコードを設立し、スモール・フェイセズのマネージメントを行なっていた。

-- 逆に僕らの世代(=R35)では、『ベガーズ・バンケット』あたりから聴き込む人が圧倒的に多かったんですけどね。
そうでしょうね、きっと。でも僕の感覚からすると『ベガーズ・バンケット』以降は、ビートルズで言うところの「赤盤」や「青盤」みたいな感じ(笑)。とはいえ、そういう違和や疑問が書きたいことの中心ではなかったんですけど、でも、まずそれを書かないことには、この本に関してはどうしても組み立てができなかったんですね。
-- それこそ、冒頭はじめ、「EP」がしっかりディスコグラフィに組み込まれていますよね。
ビートルズではそういうことができなかったんですよ。その必要がないというか。ストーンズだけの着眼点ですよね。チェス・セッションを集めたもの(『ファイヴ・バイ・ファイヴ』)だとか、当時は相当新しかった。でも、その新しさが少なくとも日本には伝わっていなかったので、初期はいつまでも「ビートルズの二番煎じ」的な扱い。すごく損をしているバンドだと思うんですよね。「EP」に関して言うと、当時オリジナル盤を目にすることなんてまずなかった。CDになったのですら比較的最近ですから。
-- ABKCO制作のシングル・ボックスで。
あれも簡易的なジャケットですけどね。だから、今回はちょっと生真面目すぎるぐらいにきっちりとイギリスにおける発売手順みたいなものを踏みたかったんですよ。そういう本は、僕が知る限りあまりなかったので。

中山氏も「ストーンズのアルバム史はこの4曲入りEPから始まる」と語る、1964年1月発売のイギリス・デビューEP。「バイバイ・ジョニー」、「マネー」、「ユー・ベター・ムーヴ・オン」、「ポイズン・アイヴィ」と収録曲は全てリズム・アンド・ブルース/ロックンロールのカヴァーとなっており、当時の彼らが黒人音楽にいかに深く傾倒していたかが分かる。英チャートではNo.1を獲得したが、「バイバイ・ジョニー」、「マネー」、「ポイズン・アイヴィ」の3曲は、1972年の米国ロンドンレコードによる編集盤『モア・ホット・ロックス』に収録されるまで、アメリカでは長らく未発表となっていた。
「ファイヴ・バイ・ファイヴ」 EP
シングル「イッツ・オール・オーヴァー・ナウ」と同じく、1964年6月10,11日に行なわれたシカゴのチェス・レコーディング音源を纏めた2枚目のEP(1964年8月発売)。「イフ・ユー・ニード・ミー」、「エンプティ・ハート」、「南ミシガン通り2120」、「コンフェッシン・ザ・ブルース」、「アラウンド・アンド・アラウンド」の5曲を収録。いずれもアメリカ盤セカンド・アルバム『12×5』に収録されているため、音源としての「英米ギャップ」は発生していない。ちなみに、「アラウンド・アンド・アラウンド」には、マディ・ウォーターズのギターソロがフィーチャーされているロング・ヴァージョンというものも存在する。
「ガット・ライヴ・イフ・ユー・ウォント・イット!」 EP
-- 今回ユニバーサルの「SHM-CD再発」企画にしても、50周年アニーヴァーサリーとはいえ、イギリス盤ファースト・アルバム、セカンド・アルバムなどの再登場はなかったわけですから...
結局、アメリカ盤主体なんですよね。音楽雑誌の場合は、レコード会社との広告云々の関係なんかでそうなるのは仕方ないんでしょうけど、少なくとも記録や記事として同等に扱って欲しいなっていうのはあるので。
-- なので、この本は“ガチ”ですよね。日本のストーンズ・ファンにはすごく重宝されるのではないかなと思います。
データも困ったんですよ。信憑性という部分で、ビートルズほど確立されたものがないので。イギリスでの発売日ですら、三つか四つの説があったりして。色々なサイトを見たりしても、極端な話全部違うぐらい。
-- そういった場合は、どの辺りで折り合いを付けたんですか?
「THE ULTIMATE GUIDE TO THE ROLLING STONES」というデータベース・サイトがあって、そこはその他の要素から見ても最も信頼性が高かったので、基本的にはそのデータに合わせるようにしました。だから、その他の資料とは異なる部分もあるんですよ。1969年のマッスル・ショールズでのレコーディングにしても、そのサイトによれば、レコーディングしていないことになっている。つまり、レコーディング自体してはいるけど、公式盤にはそのテイクが採用されていないという見解なんですよ。その部分なんかは、こちらで調べ直して書き加えましたけど。
ストーンズ研究では今だにマーク・ルイソンみたいな人がいないから、データが整理されずに散らかったままなんだと思いますよ。

 ビートルズ研究の第一人者。その結成から解散までの記録を徹底的な取材と事実検証に基づいてまとめたクロニクル書「ザ・ビートルズ全記録 (1957‐1964)」、「ザ・ビートルズ 全記録 Vol.2(1965‐1970)」は、「最も信頼のおけるビートルズ・ヒストリー」として現在もビートルズ・ファンから圧倒的な支持を受けている。ほか、「ザ・ビートルズ レコーディング・セッションズ完全版」などがある。
ビートルズ研究の第一人者。その結成から解散までの記録を徹底的な取材と事実検証に基づいてまとめたクロニクル書「ザ・ビートルズ全記録 (1957‐1964)」、「ザ・ビートルズ 全記録 Vol.2(1965‐1970)」は、「最も信頼のおけるビートルズ・ヒストリー」として現在もビートルズ・ファンから圧倒的な支持を受けている。ほか、「ザ・ビートルズ レコーディング・セッションズ完全版」などがある。
-- 初期のカタログに関しては、この本を読んだ上で、やっぱり手元にイギリス盤を置いておきたいところですよね。
まぁ、そうですよね。だからいつまでもイギリス盤がなおざりにされていることが非常に不可解で。結局ビートルズみたいに、日本でも発売元が一社じゃないことのデメリットがあったとしか言いようがないんですよ。
-- 一方で、『アフターマス』、『ビトゥイーン・ザ・バトンズ』は、まるでアラン〜ジョディ・クレインの気まぐれが作用したかのようにイギリス盤であったり。
不思議ですよね(笑)。ミックやキースにしても原盤をABKCOから“買い戻す”という気はないみたいなんですよ。そこがやっぱり現役のバンドなんだっていうところでもあって。とりあえず目先の新作やツアーなんかに着手している限りは、「過去は別にどうでもいい」っていう感じなのかもしれませんよね。
-- オリジナル・イギリス盤以外で、初期のストーンズ秘蔵音源で「これが陽の目を見たらテンションが上がる」というものは、中山さんの中で何かありますか?
RCAスタジオのセッション音源ですかね。何度かそこでやっていますから。最初のセッション、あるいは「サティスファクション」が生まれるぐらいの時期のセッション。いずれにせよ、ブライアン・ジョーンズのいる時代。それにジャック・ニッチェが参加していたら、もう最高ですね。

僕の見立てだと、やっぱりブライアンは死ぬまでストーンズの中心なんですよね。そのことが上手くこの本で表現できたかどうか心配ではあるんですけど(笑)、結局それがこの本を書く大きな動機にもなっているんですよ。
ブライアン・ジョーンズって、ブルースが好きすぎて、結果ストーンズから追われた「悲劇の主人公」として一般的に語られていますよね? それもたしかに事実なんですけど、でも例えば『サタニック・マジェスティーズ』までの過程だったりを順を追って聴いてみると、必ずしもブルースだけではなくて、もっとワイドに多種多様な音楽を貪っていたことを感じさせるんですよね。ブライアン自身にしても、ある種天才だったゆえに、自分の中にどういう音楽的素養があるのかという見極めが出来ていなかったんだと思うんですよ、結成当初は。若かったし。そのときは確かにブルースに狂ってはいたものの、コピーの段階はあっという間に卒業する。その後はセッションやレコーディングを重ねていく度に、「自分はブルース以外にこんな才能があったんだ」ということを確認していったんじゃないかなと。聴き手としては、そのことを色々な楽器を演奏するっていうことでしか知ることができなかったんですけど。そういう部分でストーンズを引っ張っていたところが多々あって、おそらくブルースから最初に飛び出したのはブライアンだったんじゃないかって思うんですよ。
-- あぁ、なるほど。
むしろ、ミックやキース、あるいはイアン・スチュワートの方が、ブルースやブギウギなんかにずっと固執していて(笑)、ブライアンは結構トンデたんじゃないかなと。だから結局、ストーンズの外に共感してくれる人を求めたときに、ジョージ・ハリスンが出てきたんじゃないかなと思うんですね。今回の本では、そうした見立てに沿って「60年代の章」を書いたんですよ。
-- ブライアンの再評価、というよりは評価の見直しですね。
定説とはズレるんですけど、僕はそう思っていて。そうなると、ますますイギリス盤じゃないと見えてこないんですよ。さらに言えば、ブライアンのそうした豊かな才能を取り込んだ上で、ミックやキースが新しいストーンズとしてのオリジナル曲を書くことができた。だから、「ブライアンを排除して」だとか、一口にそういうワケでもなさそうなんですよね。
-- 本の中では、“円満退社”のような書かれ方がされています。
ストーンズの物語は、ビートルズ同様に上手くできている部分があって、結果ブライアンも“上手く”死ぬわけなんですけど...。実際、ブライアンは自分のバンドをやろうとしていたし、可能性はまだまだあったということは、『サタニック・マジェスティーズ』あたりの作品が雄弁に物語っていますからね。
-- この時期は自ら現地まで赴き、ジャジューカやグナワの演奏を録音・編集していますもんね。
そうなんですよ。ジョージが、ビートルズ解散と同時に才能をいち早く開花させた、そういう形がブライアンにも待っていたような気がするんですよね。だから、すごく惜しまれる死だと思います。
余談ですが、僕は、一時期「3人のブライアン」について考えていて。ブライアン・ウィルソン、ブライアン・エプスタイン、そしてブライアン・ジョーンズ。ブライアン・ウィルソンに関しては、生き延びてしまった不幸を感じさせますが(笑)、逝去したブライアン・エプスタイン、ブライアン・ジョーンズ、とりわけブライアン・ジョーンズの死というものは、その後の音楽的展開などを想像してみると、やっぱり惜しまずにいられないんですよ。ブライアン・エプスタインの死にまとわりついている類の”悲しみ”が意外と少ないんです。

-- ジョージもそうですし、ジミヘンなんかとの交流の成果もきちんとした形で見たかったです。
ジョージ・ハリスンの場合は、結果的に彼の方がブライアンにシンパシーを感じていたんですよね。第一に、誕生日が三日違い。これがどうやらジョージにとっては親近感という部分で大きかったようで。それから、自分もブライアンもグループ内で“三番目”の存在だったこと。しかも、並みのグループの三番目ではなく、大天才が二人いる中での三番目という気持ちは自分とブライアンにしか分かるはずがない、と思っていたみたいです。
-- あとは、本職以外にも色々な楽器に興味を示す部分だったり。
シタールにしてもそうですよね。ジョージは当時「ノルウェーの森」を吹き込んでいて、でもそれはまだ世に出ていなかった。その間にブライアンがジョージの自宅に遊びに行って、シタールがあるのを見付けたんですね。ブライアンはその場ですぐに弾けるようになって、その直後に「黒くぬれ!」が出来た。もう完璧にマスターしているんですよね。だけど、ジョージはたどたどしいんですよ(笑)。そこが「ノルウェーの森」の良さでもあるんですけど。要するに、方やインド、方やモロッコと、民族音楽や楽器を含む外の文化に目を向けていたところであったり、どこか一ヶ所に留まらない広がり方という部分でかなり共通するところがあったんですよね。
ブライアンが音楽を担当した『ディグリー・オブ・マーダー』のサントラにしても、まだ聴いてはいないんですけど、おそらくジョージの『不思議の壁』や『電子音楽の世界』なんかに近い感じがあると思うんですよ。


-- そうですね。たしかにブライアンが現在も存命だったら、ノイズやドローン、あるいはアンビエント系の音楽なんかに着手しているような気もします。
シンセサイザーが登場したときも、ブライアンはかなり強い興味を示していましたから。そういうことを積み重ねて見ていくと、全然ブルース一辺倒じゃないんですよ(笑)。そういう意味では、62、3年当時のブライアンにとってはブルースが新しい音楽だったんじゃないですかね。
『アフターマス』や『ビトゥイーン・ザ・バトンズ』なんかは、ミックとキースのオリジナリティが爆発した時代の作品とも言われていて、勿論その通りだとは思うんですけど、でも全体のサウンドを引っ張っていたり、あるいは全体の色彩を決定していたっていうのは、やっぱりブライアンだったと思うんですよ。その頂点がまさしく『サタニック・マジェスティーズ』になるわけで、これが果たして成功したのか失敗したのかとなると...そこは謎のまま(笑)。とはいえ、評価を完全に分かつところにこのアルバムの面白さがあるんですけどね。
-- 『アフターマス』、『ビトゥイーン・ザ・バトンズ』、『サタニック・マジェスティーズ』には、作品を追うごとに霧や靄が濃厚にかかっていく感じがあって、然るにこれらを「ブライアン三部作」と言っても過言ではないみたいな。
そうですね。定説であるごく初期のブルース/リズム・アンド・ブルース時代の作品ではなくて、この三作品にこそブライアンらしさというものが色濃く滲み出ているんじゃないかなと思うんですよ。
だから、僕らが思っている以上に60年代のブライアンというのは影響力があって。ドノヴァンにしてもジミ・ヘンドリックスにしてもザ・フーにしても、アイドル視していたのはジョン・レノンやポール・マッカートニーではなく、ブライアンだったんですよ。アメリカのバーズなんかにしてもそうですけどね。女性服を着る発想だったり、ああいった髪型のカツラを着けてみたりだとか、ファッション的な部分でもブライアンの影響というのは大きかったようですから。ロックスター、トリックスターのアイコンとしての条件を全て持っていた人なんですよね。
-- ジャック・ニッチェとブライアンのシナジーも当時は大きかったようですね。
そこは、RCAスタジオ・セッションなどが世に出れば、さらにいくつか垣間見ることができるようになると思うんですけどね。僕が持っているブートでは、「サティスファクション」にしろ「黒くぬれ!」にしろ、セッションではなく、単純なバックトラック、所謂カラオケでしかないんですよ。だから、「ワン・プラス・ワン」みたいに、もう少し長大なセッションの模様が見れれば面白いなとは思うんですけど。
 ストーンズ「黄金のRCAスタジオ時代」を語る上で欠かすことのできない名伯楽。元々はフィル・スペクターの右腕的存在のアレンジャーだったが、むしろフィルのヒット曲はニッチェなくしては生まれることがなかったのでは、と囁かれているほどそのアレンジ力には定評がある。クラシックやジャズ・オーケストラの理論を用いた独特な音の使い方で、それまでのポップスにおけるアレンジの常識を覆した。ストーンズとは友人であったアンドリュー・ルーグ・オールダムを介して知り合い、RCAスタジオの録音に立ち会った。またライ・クーダーを紹介し『レット・イット・ブリード』に参加させたのもニッチェで、その流れから、ミック主演映画『パフォーマンス 青春の罠』のサントラを、初めての映画音楽仕事として手掛けることとなる(ライも参加)。ほか、バッファロー・スプリングフィールド、ニール・ヤング作品への参加、また「エクソシスト」、「愛と青春の旅だち」、「スタンド・バイ・ミー」など数々の有名サントラの制作も行なっている。
ストーンズ「黄金のRCAスタジオ時代」を語る上で欠かすことのできない名伯楽。元々はフィル・スペクターの右腕的存在のアレンジャーだったが、むしろフィルのヒット曲はニッチェなくしては生まれることがなかったのでは、と囁かれているほどそのアレンジ力には定評がある。クラシックやジャズ・オーケストラの理論を用いた独特な音の使い方で、それまでのポップスにおけるアレンジの常識を覆した。ストーンズとは友人であったアンドリュー・ルーグ・オールダムを介して知り合い、RCAスタジオの録音に立ち会った。またライ・クーダーを紹介し『レット・イット・ブリード』に参加させたのもニッチェで、その流れから、ミック主演映画『パフォーマンス 青春の罠』のサントラを、初めての映画音楽仕事として手掛けることとなる(ライも参加)。ほか、バッファロー・スプリングフィールド、ニール・ヤング作品への参加、また「エクソシスト」、「愛と青春の旅だち」、「スタンド・バイ・ミー」など数々の有名サントラの制作も行なっている。
-- このセッションの様子は、音源なりフィルムなりで残っているものなのでしょうか?
あると思うんですけどねぇ...大体無いと言われていた物がポッと出てくるのが最近の流れですから(笑)。
 中山康樹 『ローリング・ストーンズを聴け!』
中山康樹 『ローリング・ストーンズを聴け!』
今年結成50周年を迎えるローリング・ストーンズ。『聴け!』シリーズがベストセラーの音楽評論家・中山康樹が、彼らの代表作50枚を最新データをもとに独自の視点で論じ尽くす初の「ローリング・ストーンズ評論」。1960年代前半から現在まで、ローリング・ストーンズがリリースしてきた主要アルバム50枚についてオリジナル・ジャケット写真とともにすべて解説。カバー写真は、60年代から伝説的ミュージシャンをとり続けてきた、ジェレド・マンコヴィッツ。
contents
イントロダクション
第1章 イギリス・オリジナル・アルバム
第2章 編集アルバム
第3章 ベスト・アルバム
コラム 1 イギリス盤を追放したアメリカ盤
コラム 2 続々リリースされる公式ブートレグ
あとがき
(なかやま やすき)
[関連リンク]
関連記事はこちら
-
【オリ特】ストーンズ 結成50周年公式写真集!
貴重な写真とメンバー自身によるコメントで構成されバンドの50年を総括した、Rolling Stones唯一の公式写真集が世界同時発売!【先着購入特典】オリジナル絵柄ポストカード付き!
-
ストーンズバー CMタイアップ曲!
ストーンズ結成50周年! サントリーから発売される”ストーンズバー”のCMタイアップ曲「ロックス・オフ」が急遽シングル・リリース!
-
【特集】 源泉かけ流しブルースの湯で
ストーンズ自身の1981年シーズン・ハイライト! 同年11月シカゴ、マディ・ウォーターズとストーンズの師弟共演ギグ公式映像、遂に到着!
-
【特集】 1978年のストーンズ
『女たち』発表直後の78年北米ツアーを捉えたストーンズの歴史的ライヴ映像、ついに発売! ハンサムボーイズよ何処へ!?
-
「マイルス ラスト・イヤーズ」 中山康樹さんに訊く
奇跡のカムバックを果たした帝王が往くさらなる荒野。中山康樹さんをお迎えしておくる「マイルス 華麗なるラスト・イヤーズ」についてのお話。お愉しみください。
-
「エレクトリック・マイルス」 中山康樹さんに訊く
壮大なスケールと密度の「帝王・超電化絵巻」。その謎を解き明かす。最新著書『エレクトリック・マイルス 1972-1975』を発刊されたマイルス研究の第一人者、中山康樹さんにお話を伺いました。
ブロンズ・ゴールド・プラチナステージの場合です。
%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

中山康樹 その他の著書 [ロック編]
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

中山康樹 その他の著書 [ジャズ編]
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
-
-
-
品切れ
-
-
-
品切れ
-
%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

その他いろいろ
-
 限定盤
限定盤 Rocks Off
The Rolling Stones
価格(税込) : ¥1,572
会員価格(税込) : ¥1,447
まとめ買い価格(税込) : ¥1,337発売日:2012年06月20日
-
 販売終了
販売終了
-
-
-
品切れ
-
-
 限定盤
限定盤 Live At The Checkerboard Lounge Chicago 1981 (+lp)
Muddy Waters / Rolling Stones
価格(税込) : ¥14,143
まとめ買い価格(税込) : ¥11,739発売日:2012年07月04日
-
 販売終了
販売終了
-
-
 限定盤
限定盤 Live At The Checkerboard Lounge Chicago 1981
Muddy Waters / Rolling Stones
価格(税込) : ¥5,217
まとめ買い価格(税込) : ¥4,330発売日:2012年07月04日
-
 限定盤
限定盤 Some Girls Live In Texas '78
The Rolling Stones
価格(税込) : ¥14,143
まとめ買い価格(税込) : ¥12,022発売日:2012年09月12日
-
 販売終了
販売終了
-
-
 限定盤
限定盤 Some Girls Live In Texas '78
The Rolling Stones
価格(税込) : ¥18,647
まとめ買い価格(税込) : ¥15,851発売日:2012年06月13日
-
 販売終了
販売終了
-
-
-
 販売終了
販売終了
-
%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

%%header%%![]()
%%message%%

|
|
このアイコンの商品は、 洋楽3点で最大30%オフ 対象商品です |