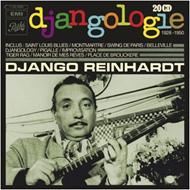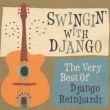ストーケロ・ローゼンバーグ インタビュー
2011年2月1日 (火)

去る2010年に各地で催された、マヌーシュ・スウィング(ジプシー・スウィング)を世界に広めたギタリスト、ジャンゴ・ラインハルトの生誕100周年を祝したイベント。
中でも日本国内最大級の規模となる渋谷クラブクアトロで行なわれたジャンゴ祭には、現代マヌーシュ・スウィングの最高峰ギタリスト、ストーケロ・ローゼンバーグ率いるトリオをはじめ、日本からは渡辺香津美、吾妻光良、モアリズム、ハッチハッチェルバンド、ザッハトルテ、そしてもちろん、日本ジャンゴラインハルト研究会という錚々たる顔ぶれが集結し、マヌーシュ・スウィングという、1930年代にフランスで生まれた”もうひとつのジャズ”の愉しさや妙味を伝えてくれた。
世界中に数多く存在するジャンゴの遺志を継ぐ現代ギタリストの中においても、人気・実力ともに群を抜く存在と言えばやはりこの人、ストーケロ・ローゼンバーグ。「ジャンゴの再来」と謳われたデビューから20年余経った今も、様々な要素を取り入れながら独自のマヌーシュ・スタイルを追求し続けている真のヴァーチュオーゾ。ジャンゴ生誕100周年を記念した最新アルバム『Djangologist』を引っさげ、その滑らかで切れ味鋭いギターで日本のファンを魅了したストーケロ・ローゼンバーグにお話を伺いました。
インタビュー/構成: 小浜文晶 |
- --- 昨年の11月に渋谷クラブクアトロで行なわれたライヴ、とても愉しませていただきました。意外に、と言ったら失礼にあたるかもしれませんが、かなり若いオーディエンスが多かったので・・・正直少しびっくりしました。
-
ストーケロ・ローゼンバーグ(以下、ストーケロ):僕もびっくりした(笑)。でも、若い人たちがこういった音楽に興味を持ってくれているっていうのはすごくうれしいことだよ。僕らのやっている音楽は、(註)ジャンゴ・ラインハルトを取り上げていることもあって、ジャズの中ではどちらかと言うとモダンではなくて、古いスタイルに属するものだからね。
- --- しかも、女性の割合が心なしか多かったような・・・ジャンゴにしてもストーケロさんにしても、フレーズ、音の響きに何とも言えない色気が漂っていて、なおかつ指使いも滑らかときたら、それも納得できます(笑)。
-
ストーケロ:ホントに? 今までそんなこと一度も言われたことないな(笑)。昔、友人に「お前の書く曲って女向きだな。ジプシー・ミュージシャンが書いた曲に聴こえないよ」って冗談で言われたことはあるけど(笑)。
- --- (笑)ストーケロさんの地元オランダでも、ライヴ会場にはわりと若いお客さんが多いのですか?
-
ストーケロ:毎年、僕らはホール規模のライヴ会場を回るツアーをやっているんだけど、そこでは多少、年配のお客さんが多いかな。それはごく自然なことかもしれないけど。ただ、僕らはジャンゴの音楽をやるミュージシャンの中では若手にあたる。そこが若い人たちにとって親近感が沸くところなのかもね。しかも、僕らは純然たるジャンゴの曲やスタイルをただなぞっているだけじゃなく、色々と新しい要素を取り入れながらやっているから、そういうところに興味を持ってもらえてるのかなって。ジャズ・フェスティヴァルなんかに出るとやっぱり若い人たちの方が多いよ。
- --- 「新しい要素を取り入れながら」と言えば、アルバム『Djangologist』に収録されている「Gipsy Groovin'」などはまさにそういったタイプの典型的な曲かなと。ちなみに、この曲でベースを弾いているのは、(註)ビレリ・ラグレーンさんなんですね。
-
ストーケロ:そう、ビレリにお願いしたんだ。こういう曲を入れることによって、伝統的なジプシー音楽にモダンな要素をミックスできるんだっていうことを判りやすく伝えられたんじゃないかな。
- --- 今後はこうしたタイプの楽曲の割合も増えてくる?
-
ストーケロ:いや、そうでもないと思うよ。でもまぁ、ジャンゴの音楽を色んな要素とミックスしてみるっていうことに関しては、昔からそれなりにオープンにやってきたつもりだから、気が向いたらという感じかな。強いて言うなら、「Gipsy Groovin'」タイプの曲を、こうしたジャンゴの名を語ったアルバムに入れてしまう、そのこと自体がすごく“ジャンゴ的”というかさ(笑)。実は、直前まで収録しようかどうか迷った部分もあったんだけど・・・でも、常に失敗を恐れずに新しいことにどんどんチャレンジしていく、ジャンゴはまさにそういう人だったし、そこに僕らは惚れ込んできた。だから、あえて「Gipsy Groovin'」をアルバムに入れようって決めたんだ。
- --- 垣根のようなものを設けずに作り込んでいく姿勢というのは、『Djangologist』のボーナスDVDに収められていた、(註)エイドリアン・ヴァンデンバーグとのセッション・シーンなどにも顕れているように感じましたよ。 「お、ヴァンデンバーグだ!」って(笑)。
-
ストーケロ:(笑)同郷人だしね。エイドリアンもジャンゴの大ファンなんだよ。僕も彼からそのことを聞いたとき最初は「意外だな」って思ったんだけど、話しているうちに「この人、相当好きなんだな・・・」って(笑)。それで、「君らのスタジオを見学したいんだけど、いいかな?」って彼から言ってきた。それがあのシーンなんだ。
-
ローゼンバーグ・トリオのマネージャーでフランス人のアイヴァン氏(以下、アイヴァン):いやでもさ、日本の取材メディアとか、あるいはリスナーの人たちってすごく視点が広いよね。音楽だけじゃなくてカルチャーとして幅広くジャンゴに興味を持っているんだなって感じるよ。スタジオにエイドリアンが遊びに来ているとか、ベースにビレリ・ラグレーンが参加しているとか、そういう指摘をしてくれるのって日本だけかもしれない。それって、実はすごいうれしいことなんだ。
というのも、これまで他の国でも色々と取材をやってきたんだけど、そこではいわゆる「ジャズ的な視点」のみで捉えられた話が多かったから、「ローゼンバーグの新譜である」「ジャンゴの音楽をやっている」、結局この二点だけにテーマが絞られちゃってさ。
僕は実際このアルバムのプロデューサーのひとりでもあるから、そこでやってきたことが初めて正しい反応を得たんじゃないかって、日本にやって来てまずそう思ったぐらいだよ(笑)。 - --- ケニー・ドーハムの「Blue Bossa」、ジミー・ウェッブの「Sunny」、スティーヴィー・ワンダーの「I Wish」などをレパートリーに取り入れたりと、そういう部分での幅広さもやはりジャンゴの表現した世界に共通するものがあるなと感じました。
-
ストーケロ:今自分がやっているような音楽に対するこだわりはもちろんあるんだけど、それと同時に、ジャンゴ・フリークのミュージシャンがふつう取り上げないような曲をどんどん取り上げていきたいなって。スティーヴィー・ワンダーの「I Wish」なんかはまさにそうだよね。だって、同じ音楽だしさ。共通言語になるんだよ。自分たちの基盤となっている音楽に、結局どういうものを取り入れても成り立つんだって感じているよ。
まさにジャンゴもそういう人だったよね。彼が活動していた1930〜50年代のジャズの歴史を見てみると、例えば40年代にビ・バップの台頭があった。そうなるとジャンゴはすぐに自分のスタイルにビ・バップの要素を取り入れた、それぐらい実験精神に溢れた人だったんだ。 - --- 今回タイトルには、衒いなくストレートに『Djangologisit』と冠しているだけに、これまでの作品よりいっそう思い入れが強いものが出来上がったと言えるのではないでしょうか?
-
ストーケロ:うん、間違いなく僕らにとって特別な作品になった。タイトルに限って言えば、もちろん「ジャンゴ・ラインハルト生誕100年」を祝福するという意味合いもあるけど、内容に関しては、せっかくの機会なんだから、「Nuages」や「Minor Swing」みたいな誰もが知っているようなレパートリーを取り上げるのだけはやめようって。今回はあえて他のジプシー・スウィング系のギタリストが取り上げないような曲を選んでいるんだ。
- --- ストーケロさんは、10歳でギターを始められたそうですが、それ以前には他の楽器を嗜んでいたこともあったのですか?
-
ストーケロ:何もやっていなかったよ。ホントにギターだけ。
- --- では、初めて聴いたレコードもジャンゴ・ラインハルトだったとか?
-
ストーケロ:たしかに、ギターを弾くようになってから初めて聴いたレコードはジャンゴだったよ。でも、ジャンゴは僕らのコミュニティでは大昔から有名だったから、ギターを始める以前からその名前だけは知っていたんだ。
- --- 初めてジャンゴの音楽を聴いたとき、どういう印象を受けました?
-
ストーケロ:オランダのジプシー・コミュニティでギターを始めるって言ったら、ジャンゴから入るのが当たり前なところがあるんだよね。だから、僕にとってもジャンゴを聴くということは、すごく自然なことだった。最初からまったく違和感なく入れたよ。
- --- 「ジャンゴを音楽の入り口とする」というようなコミュニティの伝統というのは、オランダで今現在も残っているのですか?
-
ストーケロ:さすがに今はちょっと変わってきているかもね。僕、あるいは僕の父親や祖父あたりの世代までは、ジャンゴを聴いて音楽を始めるというのが当たり前だったんだ。だけど、今のフランス、オランダなんかの若いジプシー系のギタリストたちは、必ずしも全員がジャンゴから入っているわけじゃなさそうだね。むしろ、僕らも含めた新しい世代のジプシー・スウィングを聴いて音楽を始めたっていう人が多いみたい。
でもあえて、そういう人たちには苦言を呈するようにしているんだ(笑)。「ここを入り口にしてちゃダメだよ。もっとさかのぼったところに源があるんだから、そこから入るべきだ」って。 - --- ただ、クアトロのライヴ会場にいたような若いオーディエンスたちが、ストーケロさんの音楽を入り口にしてジャンゴにまでさかのぼっていくという流れは、音楽の聴き方としてはすごく自然だと思いますし、それはそれでアリかなと。
-
ストーケロ:たしかにアリだね。実際、オランダで「君たちの音楽に出会えてよかったよ」って言ってくれる人の中にも、ジャンゴのことなんてまるで知らなかった人だっているから。僕らの音楽に触れたことをきっかけにして、色々とサーチしながらジャンゴにまでたどり着くっていうことなんだもんね。
- --- ちなみに、ジャンゴ以外で影響を受けたミュージシャンというのはいらっしゃるのですか? 例えば、ギタリスト以外のプレーヤーなどで。
-
ストーケロ:インスパイアを大きく受けたという点では、バイオリン奏者の(註)ステファン・グラッペリかな。(註)ベン・ウェブスターのテナー・サックスの音も好きだよ。
-
アイヴァン:(註)オスカー・ピーターソンもたしか好きだったよな?
-
ストーケロ:あぁ、いいねぇ(笑)。最高だよ。オスカーは、どんなに速いフレーズを弾いても、ひとつひとつの音が力強くクリアに聴こえるんだ。素晴らしいピアニストだよね。
- --- クアトロのライヴのアンコールでは、(註)渡辺香津美さんと「Caravan」を演奏されていましたが、ジャンゴ・スタイルを取り入れている日本のミュージシャン、あるいは熱狂的な「ジャンゴ研究家」についてはどのようにお感じになりました?
-
ストーケロ:地球の反対側でこんなにもジャンゴの音楽が盛り上がっているのかって、驚きでもあったし、感激でもあったし。ジャンゴの音楽がヨーロッパ限定のものではなく、本当に世界中に飛び火していったということの証明にもなるわけだから、もし本人が生きていたらきっと大喜びしていただろうね。
-
アイヴァン:「日本ジャンゴ・ラインハルト研究会」の存在すら知らなかったから、僕はとにかく驚いたね! そもそもフランスにはジャンゴの愛好家サークルみたいなものがないからさ。2人だけでコソコソやっているのはあるけど(笑)。
ここ10年ぐらい特に感じるのは、世界各地でジャンゴの音楽の何度目かの再評価が進んでいるっていうこと。フランスでもそうなんだけど、昔は「ジャンゴの音楽=年寄りが好む古い音楽」って相場が決まっていたからさ。でも今じゃ、若い人たちが中心になってジャンゴの音楽に新しい価値観を付け始めているんだよね。 - --- ストーケロさんがギターを手にし始めた頃(1978年頃)が、ジャンゴ再評価の最初の波がやってきた時代だったという話も耳にしたことがあるのですが・・・
-
ストーケロ:でも実際には、もっと後、1989年ぐらいだったんじゃないかな。僕らが『Seresta』っていうアルバムを出した頃。そのアルバムがテレビやラジオで大きく取り上げられて、そこで初めてひとつの盛り上がりにつながった。僕らに続いて、オランダでは似たようなことをやるグループがたくさんその時期に出てきて、いわゆる大きなムーヴメントになったんだよね。その後一旦は落ち着いたんだけど、またこの10年ぐらいで徐々に盛り返してきて今に至る感じはあるかな。
- --- この10年の傾向みたいなものとしては、そうした「ジプシー・スウィング」などに、カントリー、ブルーグラス、ラグタイム、ジャグバンドなどの様々なルーツ音楽の要素が渾然一体となって、”アコースティック・ダンス・ミュージック”としてのひとつの新しいサークルが形作られてきているんじゃないかなと個人的に感じています。
-
ストーケロ:アイリッシュ・ミュージックなんかもそこに入るかもね。オランダでも一時期盛り上がったけど。
-
アイヴァン:ひとつには、アコースティック楽器の魅力の再発見っていうのがあるんじゃないかな。電子楽器で作られた音楽がほとんどっていう時代だからこそのね。アコースティック・ギターなんかが持っているナチュラルな音の響きに、またみんなが惹かれはじめているんだと思うよ。
- --- たしかに、楽器においての “バック・トゥ・ルーツ” “オーガニック”指向は日本でもありましたからね。
-
ストーケロ:15年前ぐらいに、エリック・クラプトンが「Unplugged」で一世を風靡した感じにも似ているのかもね。
-
アイヴァン:つまりは、全体的にシンプルなところに向かおうとする流れだよね。「Unplugged」は特別新しいことをやっていたわけじゃないのに、それが革新的なものとして取り上げられた。「元々あったところに立ち返ろうよ」っていうコンセプトをもって電源を引っこ抜いた点に関しては、いわゆる「アコースティック・スウィング」のような音楽が盛り上がる傾向と共通する部分はかなりあるよ。どちらの根底にも必ず伝統音楽の流れみたいなものがあるしね。それともうひとつは、「エコ」みたいなことが盛んに求められている今の世の中の動きにも少なからず関係しているんじゃないのかなって。
- --- それでは最後に、ベタなのですが最も難しい質問を(笑)。お二方にとってのジャンゴ・ラインハルト、その最大の魅力というのは?
-
ストーケロ:やっぱり、あの音だよね。ギターの響かせ方ひとつとっても前例のないものだったし、ジャズの世界でジャンゴのような演奏をする人っていうのは他にいなかった。唯一無二の存在。
さらにその独自性もさることながら、1930年代と言えば、ジャズそのものがまだ黎明期にあった時代で、「ジャズ=アメリカ」っていう認識もほとんどだった。その中で、新しいスタイルの音楽をヨーロッパ発として送り出した、それはやっぱりすごいことだよ。口で言うほど簡単なことじゃない。だから、「本当に新しいものを生み出した開拓者」ということで、特にアメリカ人はジャンゴのことをすごくリスペクトしているんだよね。 -
アイヴァン:僕はジプシーでもないし、ミュージシャンでもないから、いちファンの視点から言わせてもらうと、ジャンゴってすごく興味深い人生を送った人でもあるなって。かいつまんだ説明になっちゃうけど、貧しいキャラバンで生まれ育って、そこから世界的な人気を博して最もお金を稼げるジャズ・ミュージシャンに成り上がっていく、そういう人生なんだよね。しかも、フランスに限らずヨーロッパ全土で活躍した。ストーケロも言っていたけど、1930年代当時のヨーロッパで「本物のジャズを演奏していた人」としてアメリカに認められた数少ないミュージシャンのひとり。その頃からすでにアメリカの黒人ミュージシャンたちとコンボを組んで演奏して、怯むことなくまったく対等に渡り合っていたんだ。あとさ、普通だったら死んでもおかしくないようなアクシデントに遭いながらも、しぶとく生き残って(笑)、そこからさらに演奏力や表現力に磨きがかかっている。そんな人なかなかいないよ(笑)。
ジャンゴはかなり気まぐれな性格で、パリの有名ホールで演奏するっていうときに、「釣りをしたい」って出かけたまま開演時間を過ぎても戻ってこなかったり(笑)。そういう愛すべき子どもっぽさを持っていた。でも、すごくロマンチックな人でもあって。とにかく、演奏、楽曲、性格、生涯・・・全部ひっくるめて杓子定規じゃ計りきれないものがあるんだ。今話したのはごく一部。ジャンゴの魅力についてはホントに語り尽くせないよ(笑)。 -
ストーケロ:いやいや、大いに語ったねぇ(笑)。
 |
ストーケロ・ローゼンバーグ@渋谷クラブクアトロ
|
 |
ローゼンバーグ・トリオ@渋谷クラブクアトロ
|
 |
ローゼンバーグ・トリオと渡辺香津美(中央)@渋谷クラブクアトロ
|
|
- Djangologists
- ジプシー音楽の伝統を今に伝承する現代マヌーシュ・スウィングの最高峰ギタリスト、ストーケロ・ローゼンバーグを中心としたトリオが贈る「ジャンゴ・ラインハルト生誕100周年記念盤」。究極のジャンゴ・ラインハルト・トリビュート・アルバムとなる本作には、こちらもジャンゴの遺志を継ぐ天才ギタリスト、ビレリ・ラグレーンとの夢の共演曲も4曲収録。こちらの国内盤には、配信のみで販売されたミニ・アルバム『Free As The wind』(全6曲)を収録。また、初回限定となるボーナスDVDには、本作のレコーディング・セッションの様子を収録。
|
Rosenberg Trio 2010年08月22日発売 |
-

-

- Roots
Rosenberg Trio - 2007年発売
-

-

- Live in Samois
Rosenberg Trio - 2003年発売
-
-

-

- Suenos Gitanos
Rosenberg Trio - 2001年発売
-
-
-

-

- Noches Calientes
Rosenberg Trio - 1998年発売
-
-
-
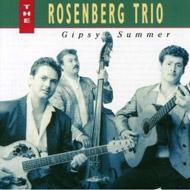
-

- Gipsy Summer
Rosenberg Trio - 1996年発売
-
-
-
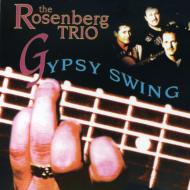
-

- Gipsy Swing
Rosenberg Trio - 1995年発売
-
-
-

-

- Best of
Rosenberg Trio - 2002年発売
-

-
Stochelo Rosenberg Trio
(ストーケロ・ローゼンバーグ・トリオ)
Stochelo Rosenberg (Lead Guitar)
Mozes Rosenberg (Rhyhm & Lead Guitar)
Sani Van Mullem (Double Bass)
現在のマヌーシュ・スウィング(ジプシー・スウィング)の最高峰ギタリスト、ストーケロ・ローゼンバーグが中心となったトリオ。滑らかで切れ味鋭い速弾きギターが魅力。ストーケロは1968年にオランダ南部ヘルモントで代々音楽を受継ぐ名門ジプシー一家に生まれる。10歳からギターを始め、父親と叔父から手ほどきを受けジャンゴ・ラインハルトの曲を繰り返し聞き練習する。12歳で従兄弟のノニー・ローゼンバーグ、ヌーチェ・ローゼンバーグらと出演したオランダのTV番組のコンテストで優勝。
1989年にローゼンバーグ・トリオ『Seresta』でレコード・デビュー。以降、トリオ編成での活動を中心にマヌーシュ・スウィングを代表するギタリストとして着々とキャリアを積む。その傍らソロ活動も行っており、フランス人ギタリスト、ロマーヌ(3枚のアルバムを発表)とも共演、最近ではオーケストラとも共演している。
2010年、ストーケロと並ぶマヌーシュの大物ギタリスト、ビレリ・ラグレーンをゲストに迎え、「ジャンゴ・ラインハルト生誕100周年」を記念して作った入魂の新作アルバム『Djangologist』を完成させた。
-
-

-

- Djangology(10CD)
Django Reinhardt - 2005年発売
-
-

-

- Djangology
Django Reinhardt - 2011年2月1日発売

-
Django Reinhardt
(ジャンゴ・ラインハルト)

フランスが生んだ最も偉大なジャズミュージシャンと言えば、異口同音にジャンゴ・ラインハルトの名前が挙がるに違いない。ギタリストとしての貢献に止まらず、作曲家として数え切れない名曲、しかも、パリのエスプリ溢れる作品を残している。ジャンゴの紡ぎだすメロディには、幼少のころの思い出や、火事になって不自由になってしまった指に対する悲しみ、そして、その不自由な指で彼だけにしか出来ない奏法を生み出すまでの血の滲むような努力が礎となっている。ジャンゴ・ラインハルトこそは、ジプシー・スイングのコンセプトをジャズと総合し、鑑賞音楽として認識されるに相応しいレベルに引き上げた稀有な存在だった。
1920〜30年代、アメリカのチャーリー・クリスチャンと同時代に現われた”Jean Baptiste Reinhardt”ことジャンゴ・ラインハルトは1910年1月23日、ベルギーに生まれている。母、ローレンス“ネグロス”ラインハルトはダンサー、父、ジャン−ユージン・ワイスはヴァイオリンをはじめ様々な楽器を演奏する人だった。初めに演奏したのはバンジョーで、他にはヴァイオリンを手にし、ハンガリアン・ジプシーのメロディなどを演奏していた。様々な民族の音楽が絡まり合うヨーロッパ独特の混交を表現するジャンゴは、ジプシー・キャラバンの中で多くの仲間たちとセッションを重ね、次第に一目置かれる存在となっていた。
この時期、1928年ジャンゴの住んでいたキャラヴァンが火事となり、指を火傷したジャンゴは一年半をリハビリと、新しい奏法を編みだすのに費やす。この頃、1931年、初期のジャンゴを見出し、積極的に応援したジャン・コクトーはジャンゴにとって文化的なバックグラウンドとしても重要な存在だった。
そして、このころジャンゴにとって永遠の盟友となるステファン・グラッペリとの出会いがある。グラッペリは、パリのキャバレーのヴァイオリニストであり、無声映画のピアニストとして演奏活動をしていた。 また、兄ジョセフとのコートダジュールでの仕事の時、彼等の音楽を気に入った、絵描きであり、写真家のエミール・サヴトリーの家で「ジャズ」に出合ったジャンゴは、これ以降ジプシー・ミュージックとジャズの融合を試みることになる。
1932年、パリに戻ったジャンゴは、彼の人生の中でも特別の新しいページを歩みだすことになる。このころ、後にグループを組むことになるアルゼンチンのミュージシャン、ギターのオスカー・アルマンとも出会っている。そして、人気歌手ジャン・サブロンの伴奏者としてパリの有名クラブに出入りするようになり、絵画の“ゴヤ”になぞらえられたジャンゴは、1934年から「ホット・クラブ」での「席」を確保するようになり、様々なセッションを残している。1935年にはルイ・アームストロング、ベニー・カータ−、ビル・コールマン等、スイング時代の大御所と共演している。1934年から1935年にかけて遂にジャンゴは自己名義の録音を開始している。
このころからパリを訪れるアメリカのミュ−ジシャンたちが最も共演したがるのはジャンゴになっていったという。コールマン・ホーキンス、ベニー・カーターを含めて多くのミュージシャンが来仏した。 当時、ジャンゴはユベール・ロスタンをフィーチャーしたベニー・グッドマン・スタイルのバンドでも並行して演奏している。
1940年代に入り、ロスタンの代わりに様々なミュージシャンが行き来するが、基本的には「ヌーボー・クインテット・オブ・ホット・クラブ・デ・フランス」を旗印に活動を続け、1944年にはグレン・ミラー楽団のバンドメンバーとも録音をしている。戦争が終わった1945年12月、ビッグバンドでのコンサートを開いたジャンゴは、彼のキャリアの中でもひとつのピークを得ている。
1946年、GIたちがパリを去り、スイング時代は終わりを告げた。クラブは閉鎖、BBC放送の依頼で「元のクインテット」を再結成、これにはグラッペリも参加している。その後、ジャンゴはデューク・エリントンとのアメリカ・ツアーを契約、1947年2月にはパリに戻り、再びビッグバンドで出演、さらに、11月にはクインテットを再結成するが、1948年、「ニューオリンズ・リヴァイバル」が起こり、ジャンゴは音楽的に苦境に立たされる。
時はビバップの時代を迎えていた。ディジー・ガレスピーが大成功を収めるのもこの時期だった。一方のジャンゴはモーリス・メニエ、ユベール・ロスタンなどを入れ替えてクラリネット・クインテットを結成するが、時代はすでに彼のスタイルを「オールド・ハット」と決め付け始めていた。
1950年代に入るとジャンゴは時代から取り残されるようになり、「次代」を担うユベール・フォル、モーリス・ヴァンデール、ピエール・ミシェロ、、マーシャル・ソラールら数少ない音楽的な信奉者とのセッションを行なって過ごしていた。
1953年5月16日、ジャンゴはフランス・ジャズ史上最高のジャズ・ミュージシャンとして、そしてマヌーシェを出自とする最高の音楽家としての実績を残して神に召されて行った。
本文中に登場する主な人物について |
 |
Bireli Lagrene (ビレリ・ラグレーン) 1966年フランスのバラン県アルザスに生まれる。フランスの伝統的なマヌーシュでジプシーの家族と地域社会で育った。バイオリニストの父や音楽好きの兄の影響で4歳の時にギターを弾き始めた。8歳の時に早くもジャンゴ・ラインハルトのレパートリーをマスターし、「ジャンゴの再来」と言われ、12歳の時にストラスブールにおけるジプシー音楽祭を受賞。その後ドイツをツアーで回り、1980年、『Routes To Django』でデビューを果たした。弱冠13歳。以後、アメリカに渡り有名ジャズ・ジャイアント達と共演。現在はジプシー・プロジェクトなどでも活動している。ギターのみならずフレットレス・ベースにおいてもその超絶テクを堪能できる。 |
 |
Adrian Vandenberg (エイドリアン・ヴァンデンバーグ) 1982年に自らのファミリー・ネームを冠し結成したヴァンデンバーグや、86年に加入したホワイトスネイクなどで活躍したオランダ人ギタリスト。80年代型ハードロックの王道とも言えるメロディアスでストレートなギター・サウンドで人気を博し、ブラッド・ギルス、フィル・コリン、ジョン・サイクスらと共に“四天王”と呼ばれた。ギター・テクだけでなく、コンポージング、アレンジ、プロデュースのすべてをひとりでこなすマルチなクリエイターぶりを発揮した。98年以降は画家としても活動している。 |
 |
Stephane Grappelli (ステファン・グラッペリ) 1908年フランス、パリ生まれ。1934年にジャンゴ・ラインハルトの“フランス・ホット・クラブ五重奏団”にヴァイオリニストとして加入し、一躍注目を浴びる。エレガントでしなやかにスイングする演奏は世界中のファンに受け入れられ、その後のジャズ・ヴァイオリンのお手本となった。盟友ジャンゴとのコンビで名演を多数残し、97年に死去するまでジャズ・ヴァイオリンの第一人者として活躍した。 |
 |
Ben Webster (ベン・ウェブスター) 1909年米国カンザス・シティ生まれ。1930年代から長年にわたって人気を博したテナー・サックス奏者。32年にニューヨークに上京し、ベニー・モーテン楽団やフレッチャー・ヘンダーソン楽団などのバンドを経験。39年にデューク・エリントン楽団に参加。”地を這うような”独特のトーンが持ち味で、特にバラードにおいて多く名演を残した。64年に渡欧。以後活動の拠点をヨーロッパに移し活躍した。73年9月20日オランダにて死去。 |
 |
Oscar Peterson (オスカー・ピーターソン) 1925年カナダのモントリオール生まれ。45年から地元カナダでリーダー作品を残し、49年に興行師のノーマン・グランツに才能を見出され米国デビュー。グランツによる慈善興行「J.A.T.P.(Jazz At The Philharmonic)」などのオールスター・セッションに起用される一方、レイ・ブラウン、バーニー・ケッセル、エド・シグペンらと多くの名作を発表した。90年代に脳梗塞で倒れるも見事な復帰を果たし、その健在ぶりを強くアピールした。2007年12月23日、腎不全のためカナダ・トロントの自宅で死去。享年82。 |
 |
渡辺香津美 (わたなべ・かづみ) 1953年東京渋谷生まれ。弱冠17才でデビュー作『インフィニット』をリリースし、天才ギタリストの出現と騒がれる。今田勝、渡辺貞夫、鈴木勲など国内のトップ・グループに在籍し、79年には坂本龍一、矢野顕子、村上秀一等と伝説の「キリンバンド」を結成。同年秋には「イエロー・マジック・オーケストラ」のワールドツアーに参加し、「Kazumi」の名は一躍世界的なものとなった。80年代には大ヒット・アルバム『トチカ』を皮切りに、『Mobo』、『Spice Of Life』といったフュージョン史に残る伝説的作品を次々とレコーディング。自己のグループで全米〜アジア・ツアーも行ない、トップ・ギタリストとしての地位を確立する。90年代からはアコースティック・プロジェクトに力を入れはじめ、ジャズ、クラシックの境界線を乗り越えて世界中で活躍している。 |